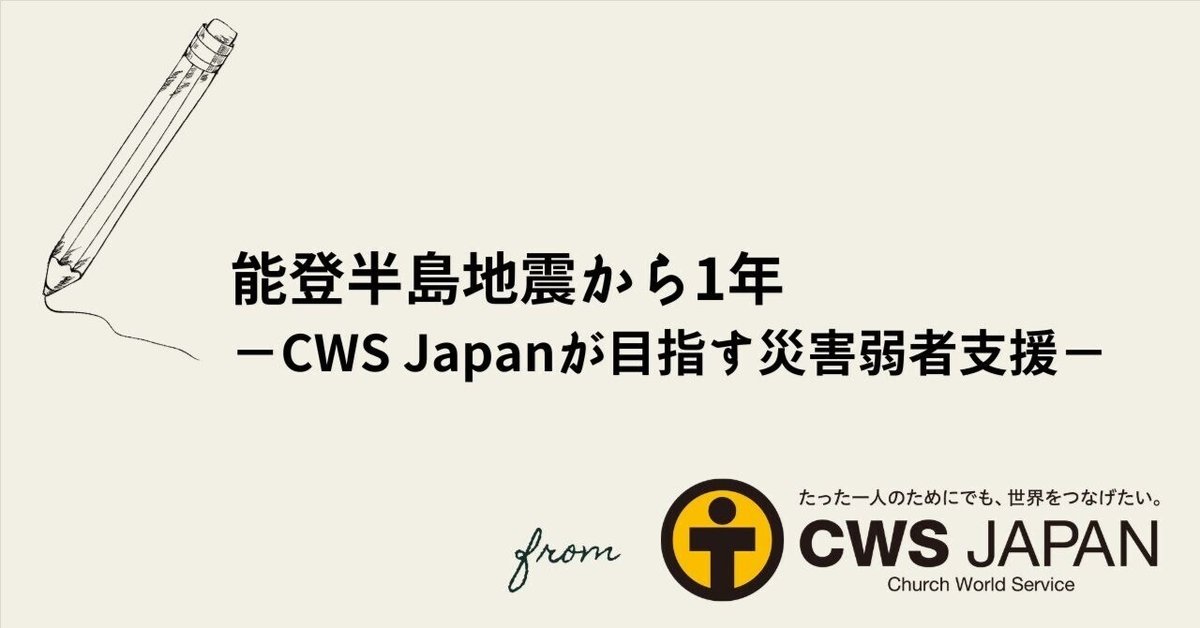
能登半島地震から1年|CWS Japanが目指す災害弱者支援
ディレクターの牧です👩今年は大規模災害が起きないことを祈りつつお正月を過ごしました🙏🎍 能登半島地震発生から1年に合わせ、年明けから新聞を開けば、連日のように、災害関連記事が続いています📰 CWS Japanの能登半島での支援活動を振り返りつつ、CWS Japanが目指す災害弱者支援についてお伝えします。
1年前の元日
1年前の元日、能登半島で発生した大規模災害によって、何とも重苦しい年明けを迎えたのが、昨日のことのように思えます。発災直後、関係団体である日本基督教団事務局から輪島教会が被災したという知らせが入りました。当時、奥能登の全インフラが壊滅状態🛣️🚫 宿泊施設もなく、他団体も金沢から半日かけて被災現場に通うような状況でした。多くの被災者が県内外に開設された広域避難所に移る中、輪島教会の牧師は、隣接する、被害を受けて壁に穴が開いたままの自宅で愛猫と一緒に在宅避難を続けていました。

苦戦した能登支援
当初から、能登支援をするなら、この被災教会が立つ輪島市と決めていました。わたしは発災から18日後に先ずは金沢に向かい、現地パートナーと考えていた団体の代表を訪ねました。しかしながら、その団体は、その後金沢市内に開設された広域避難所にてお弁当配布の支援を始めることになったことから、わたしたちはなかなか輪島で活動が始められずにいました。そんな時、「輪島に炊き出しに行きます!👩🍳」と、隣県福井市の教会から連絡を受け、3月に入って、ようやく輪島での支援が始動しました。

男性被災者はどこに?
その後、わたしたちは輪島の小学校・避難所・仮設住宅の集会所を借り、福井市から通いで移動食堂やカフェを開く活動を続けてきました。そんな中で気づきがありました。炊き出しで食事を提供する時にちらほらと見えた男性被災者の姿が、交流目的のカフェ活動に移行してみると、全く見られなくなったのです。まるで、仮設住宅には男性が居住していないのかと思えるほど、毎回、集会所のカフェに集まる参加者は高齢の女性たちばかりが続いています。
最近、全国的に子ども食堂やカフェなど居場所活動が増加傾向にありますが、わたしの知る限り、圧倒的にボランティアも利用者も女性中心です。男性は一体どこにいるのでしょうか。

災害関連死と福祉的支援
一方で、能登半島地震では、避難生活の疲労やストレスなどで体調を崩して亡くなる「災害関連死」として276人(2025年1月6日時点)が認定されました。この数字は建物倒壊などで亡くなる直接死者数よりも多く、また2016年の熊本地震を上回りました。
政府は、このような長期化する避難生活によって、体調悪化が原因による災害関連死のリスクを低減する取組を本格化させようと、配慮が必要な被災者や在宅避難する高齢者などへの生活面の支援強化を目指し、災害救助法の救助項目に福祉的サービスを追加する改正案を国会に提出することを決めました。
CWS Japanのチャレンジ
この動きは、CWS Japanが目指す災害弱者支援に合致するものと考えています。わたしたちが日ごろから行っている潜在的災害弱者の特定や生活相談とフォローアップ、伴走支援、福祉職関係者とのネットワーキングは、有事にも適用でき、その実績を日々積みながら、チーム内には社会福祉士有資格者がおり、専門的知見をも蓄えています。
2024年4月、孤独・孤立対策推進法が施行されました。孤独死現状レポート(一般社団法人日本少額短期保険協会2024年12月発表)によれば、孤独死の男女比率は男性83.5%に対して女性が16.5%と圧倒的に男性が多い結果が出ています。
この問題は都市部のみならず、被災地でも見られる現象であると考え、早速、現在、新宿区大久保で運営しているコミュニティカフェ☕の活動でも取り組みを始めたいと考えています。
ただ、災害支援の問題は、災害が「いつ・どこで」起きるか予測がつかないことです。そこで必要なのは、ネットワーク力であり、そして最も被災地に近いところにわたしたちの仲間がいて欲しい。それをわたしたちの強みにしていくことがCWS Japanの目指すところです。
(文:ディレクター 牧 由希子)
