
【担当者必見】CVC モニタリングの実務 ~CVCは如何にモニタリングを行うべきなのか~
※記事の最後に無料相談コーナーを設けています
悲劇はいつも突然に
「CVCの状況はどうなってるんだ!?」

CVCを始める際には設立目的やシナジーに関する議論は当然行われますが、投資後の話が行われることはあまりないでしょう。
それも当然、CVCを始める時にはスタートアップ市場のことも投資後の世界のことも分からないところから、走りながら考える、的にスタートすることが多いからです。
運用を開始し、初期(1年~2年)は投資とシナジーのために事業部とやり取りすることで精一杯。投資件数が数件程度のうちは経営に対する報告もまとめやすいですし、何より投資してすぐはスタートアップの事業状況も協業状況も変わりません。
既に一定期間運用を経過したCVCの方々はこの時点で分かる分かる、となっているかもしれませんが、投資件数が増えてきたある日経営からモニタリングのオーダーが降りてきます。
モニタリングとは?その必要性って?
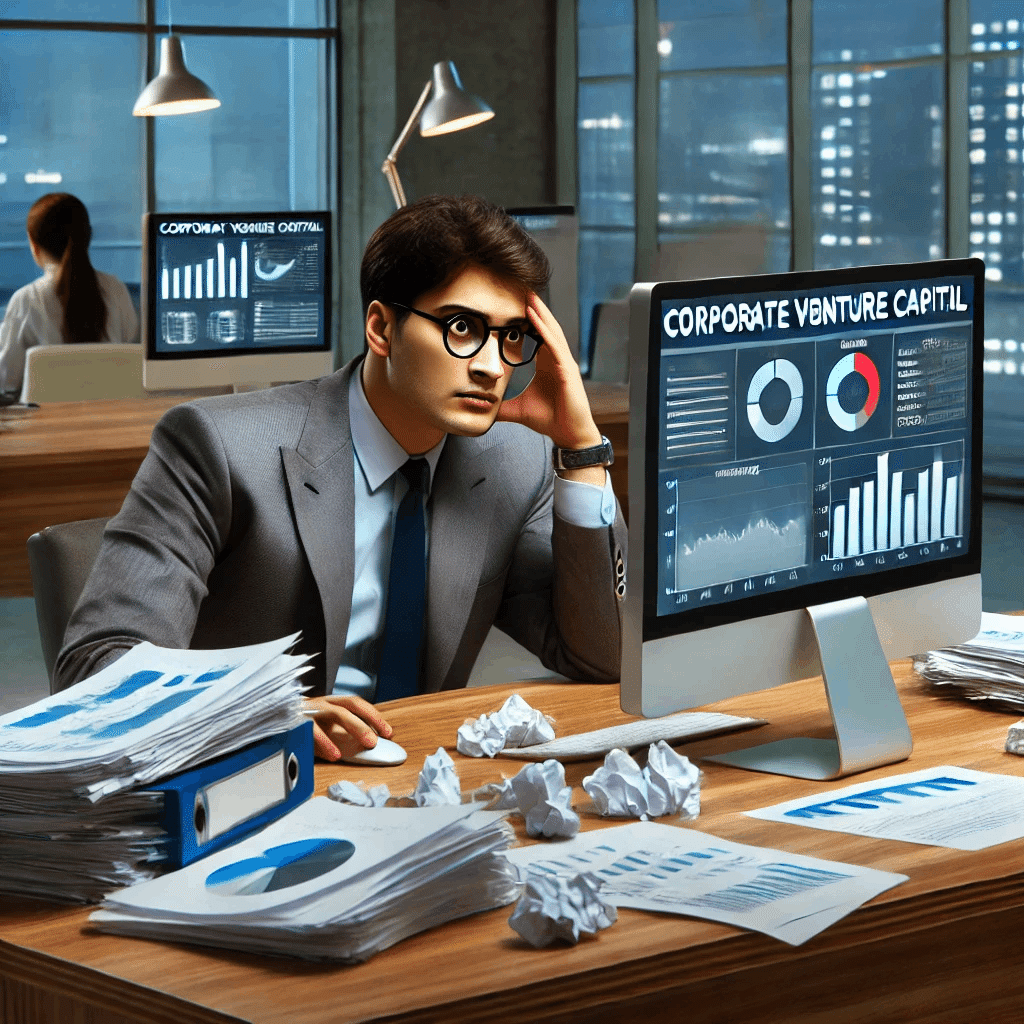
CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)活動におけるモニタリングとは、企業が出資したスタートアップやベンチャー企業のパフォーマンス、リスク、戦略の進捗を定期的に評価し、投資目標の達成状況やリターンを確認するプロセスです。
では、なぜモニタリングが必要なのかという点について考えてみましょう。
1.管理・アピールのため
CVCは経営層からの理解と継続的な支援が不可欠です。そのためにはCVC部隊が適切に運用しているということを示していくことが重要です。
突然投資した企業が倒産し、「聞いていなかったぞ!」なんてことになったら大変(それが正しい経営スタイルかという話は別)ですし、決裁した投資案件の協業が進んでいるのか知りたいですよね。
2.すべての投資を成功に導くため
現場にとっても定期的なモニタリングは重要です。案件が増えてくると投資担当者も網羅的に状況理解ができなくなってきますし、注力している案件以外はどうしても優先度が下がり放っておく状態になりがちです。ゴール設定をした協業、シナジーの創出に向けては有益と言えるでしょう。
何をモニタリングすべきか?

大きく分けると、
ポートフォリオ全体の状況
個別投資先の状況
協業創出の状況
の3点です。
”ポートフォリオ全体の状況”ですが、これは「投資がどのくらい進んでいるのか」「全体的にうまくいっているのか」を見通すものです。
具体的には投資件数・領域だとか、事業が伸びている投資先の割合、協業が進んでいる投資先の割合が挙げられます。
”個別投資先の状況”は事業上重要なKPIの推移や定性的な課題、
”協業創出の状況”は事業部と取り組んでいる案件内容や状況ですね。

現場で起こる問題点
上で整理した内容だと一見簡単そうに見えるんですが、実際はめちゃくちゃ面倒なのが実態です。どんな面倒ごと、問題が起こるか挙げてみます。
投資先が適切に情報開示をしてくれない
情報がスケジュール通りに集まらない
何が重要なKPIかよくわからない
事業部とのコミュニケーションが円滑にできない
何を協業、と言っていいのかわからない
上手くいっていないから経営からの目が心配(で資料作りが難航)
等々、です。
気付けばモニタリングだけでかなりの時間を使ってしまい、本来やるべき投資先探索や協業推進に割く時間がなくなる、なんていうのもあるあるだと思います。
投資件数は増えるが、その分CVC担当者が増えていくこともありませんので、どんどんモニタリングの比重は高くなりますし、当然上手くいかない投資先も出てきますので、そういったところへの対応負荷も増えていきます。
経験者だからこその提言

これまでの内容で、モニタリングで苦労したんだなということはお分かりいただけたかと思いますが、そんな経験をした私だからこそこれからモニタリングを始める皆様にこんな風にやったらいいですよ、とアドバイスさせてください。
CVC立ち上げ時に経営層の期待値を正しく設定する
モニタリングフォーマットを早期に固める
投資目的を振り返りやすくしておく
事業部とのコミュニケーションコストを下げる
投資先状況に応じて対応リソースを切り分ける
順に説明していきます。

①CVC立ち上げ時に経営層の期待値を正しく設定する
CVCにおいてはモニタリングに限らずこれが一番重要です。
スタートアップへの理解がないのが当たり前ですので、「倒産する、資金が尽きそう」こんな状況に過度に反応されがちですし、スタートアップが事業会社の思う通りに動いてくれないなんていう状況も理解されません。
立ち上げの時点で「スタートアップとはこんなものである」「協業ができる可能性とはこんなものである」というインプットがとても重要ですし、立ち上げ時に難しい場合には活動の中で学んだことを報告していってください。
それがない限りは実態に合わない指示が下りて来続けることになります。スタートアップは子会社ではありませんので、事業会社の言う通りに動くことはありませんし、自社のルールで市場は動いてくれません。
最も重要なのは「協業」をどう定義するか、という点ですが、これはモニタリング以前の問題ですので別の回で説明したいと思います。
②モニタリングフォーマットを早期に固める
多くの場合、パワーポイントやエクセルに表を作って管理、みたいなことが多いと思いますが、確実に何重にも管理することになりますし、ミスが起こります。
初めのうちは必要性を感じづらいかもしれませんが、継続的に一貫した管理を行うことや、件数が増えてからフォーマットを改める場合の労力を考えると、初期から適切なフォーマットで管理、報告していくことで経営からも信頼を受けやすくなりますし、攻めの活動にリソースを割けるようになります。
➂投資目的を振り返りやすくしておく
スタートアップ投資は5年以上に渡ることが多く、CVCは担当者もほぼ確実に変わっていきます。決裁者も変わりますので、そもそもなんでこれ投資したんだっけ?ということになりがちです。
投資目的が忘れられると、本来そんな目的のために投資した訳じゃないのに、みたいな内容で指摘を受けることにも繋がります。
何年経っても投資目的を簡単に振り返られるようにすることで、協業推進のための活動指針も立てやすくなります。
④事業部とのコミュニケーションコストを下げる
運営体制によりますが、事業部とのコミュニケーションが上手くいかないというのもCVCに多くある悩みです。
これもモニタリング以前にどのように事業部とのコミュニケーションを設計するかという問題であり、CVCの各担当者のコミュニケーション能力によるところでもありますが、継続的かつ正しい状況把握、経営から余分な指摘を受けないような管理を行うことで相乗的に達成され得るものだと思います。
⑤投資先状況に応じて対応リソースを切り分ける
事業会社、CVCがスタートアップにできることは限られています。
倒産しそうだ、となっている会社に対してできることはほぼありませんし、協業仮説が全て検証し終えた会社に無理な提案をし続けても逆効果です。
適切に状況管理を行い、時間軸を把握し、注力すべきプロジェクトの優先順位付けが重要ですし、既に上手くいきようのない投資先は淡々と管理を行うような切り分けが必要になります。
おわりに
モニタリングについて簡単にまとめましたが、各社方針やCVCの状況によって対応は各社各様だと思います。
そんなもんだよね、と安心材料にしていただけるだけでもいいですし、現在はCVCアドバイザリーも行っておりますので、お気軽に無料相談を申込いただければと思います。
また、CVCに特化したモニタリングツールの開発にも取り組んでおります。初期ユーザーとしてのご興味がある方がいらっしゃいましたらそちらも是非よろしくお願いします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Yz0sYvDNF0_f0talf5zKm5nq1CJ9w4J1xj7YZQ_estst0Q/viewform
↑CVCアドバイザリーは上記のフォームからお問い合わせください!
