
理解や気付きの春学期!!
皆さん、お久しぶりです!
法政大学坂本ゼミに所属する3年の中村です。
2回目となる今回は、3年生になりゼミの活動に対してより主体的に関わるようになった春学期を振り返り、「何にを気付いたのか」や「これからはどうすべきか」等についてのまとめをしていきたいと思います!
ESD支援に向けての動き
突然ですが、皆さんは「ESD」って知ってますか?
簡単に言うと、「SDGsを実現するための力を育てる教育」といった意味があります!
私たちは、このESDを実践的な活動を通して身に付けようとする取り組みの支援を行おうとしています。これから本格的に動き出すプロジェクトなのですが、今回は現時点での流れを紹介していきたいと思います!
6月9日 ジェイアーン国際協働学習シンポジウム
このシンポジウムでは、「『持続可能な社会の創り手』を育てる学び」というテーマに基づき、講演・パネルディスカッションを通して、ESDについての理解を深める場でした。
実際に私たちが支援を行う真岡北陵高校の先生も参加されており、その高校がどのようなESD活動を行っているのかが分かり、自分達がサポートしていくためには、どの点に注意すべきかを考えるきっかけを得られました。
7月19日 生徒との初顔合わせ(自分はオンライン)
自分はオンラインではありましたが、真岡北陵高校の生徒たちと初めての顔合わせを行いました!更にこの日は、真岡市役所に生徒達が出向き、現状課題を把握する講演会にも参加させて頂けるという、とても有意義な回となりました!

主な課題として挙げられていたのは人口減少と少子高齢化の2つです。特に若者の流出を問題視しており、この部分の改善が最も効果的と感じました。
現在取り組まれている活動として、「いちご王国栃木の首都 もおか」という日本トップレベルを誇る苺の生産量を謳ったキャッチコピーの作成や、複合交流拠点施設「monaca」が来年オープンすること等が紹介されていましたが、現実的な問題解決のためには地域に暮らす一人一人の意識を向上させていく一番重要だということも分かりました。
10~20代の方の流出が多い真岡市にとって、地元の生徒がESDに取り組むことはとても有効的です。改めてサポートするにあたっての責任の重大さを理解しましたが、自分達が支援することでこれからの取り組みをより発展的なものへと導き、課題解決に少しでも近づけるように、臆せず務めていきたいと思いました!
デジタルストーリーテリング(DST)の制作
今回で3回目となるDST制作でしたが、実は別の授業で作成した作品をリメイクしたものを今回提出しました。理由としては、自分のこれまでの軌跡を明確にまとめることができた作品だったからです。プライバシーの観点で個々では全てをお見せすることは出来ないのですが、今回のリメイク兼ブラッシュアップによって自分の思いをより明確に具体化でき、深み付け加えることもできたのではないかなと思っています!

また、制作過程の中で気付いたことがあります。それは、自分が「過剰適応」だということを知ったことです。
過剰適応とは、自分がどんな行動をするかを決める際に、他者や環境(組織)の価値観を優先させ、それが客観的に見て「度が過ぎる・過剰」なほどであったとしても、本人はそのことを自覚なく受け入れている状態のことを指します。この「自覚なく」という点はまさに自分にも該当しており、過去の経験を振り返りそれを映像化させたことで、当時は当たり前の様に行動していたその行為が実は「少し過度」であったと今になって分かったのです。他にも、キャリアデザイン学部の他の授業では自分の過剰適応度合いを診断できる回があり、その際自分は29点中23点と高い診断結果で、今も尚過剰適応をしている場面があることも分かりました・・・。
過剰適応について
そもそもの自分の様な過剰適応の人はどれくらいいるのでしょうか?
調べてみると、約3千人の調査対象者の内およそ17%の人が該当するといった結果(ただし同様の調査を何度もしないと明確な数字は分からない)が出る程でその数は決して少なくありませんでした!しかし海外に目を向けると、過剰適応という言葉はあまり知られている訳ではなく、「過剰適応」をテーマとする研究は殆ど見られませんでした。すなわち、過剰適応は日本人だけに見受けられる特有の精神状況なのです。
では何故日本人特有のものなのでしょうか?
日本人の性質上「和をもって尊しとなす」と言うように、何事をやるにも協調を大事にする傾向があり、周囲に合わせながら自分の役割も全うしなければならないと色んな場面で思いがちだからです。その結果、時には自分のことよりも他人や組織を優先しようと考える形が一般化し、過剰適応に陥りやすい流れを生んでいるんだそうです。
(メチャクチャ自分に当てはまってます・・・)
若年層の対人関係としては、親子関係、友人関係、上下関係、恋愛関係等が主に挙げられます。特に親子関係に関しては、過剰適応ととても繋がりが深いトピックです。親はよく子どもに対して「よい子」に育って欲しいと願うものですが(ここで言う「よい子」とは、親の言うことをよく聞き、親の望む通りに行動することを指す)、この期待が子どもに悪影響を及ぼす可能性があるのです。
親の期待が強く且つ表に出している場合、子どもはその期待に沿うように常に周囲に憚りながら自由な感情を抑えるようになります。その様は、まさに過剰適応と直結していると言え、どんな子どもでもそのような状態になってしまうとは決して限らないが、過剰適応となってしまう人の一つの要因としては十分過ぎる家庭環境でなのです。
また、友人関係やクラスメイト等といった学校内でのコミュニティの環境においても、過剰適応に係わる点は多いです。中でもいじめの問題に関しては、過剰適応と関連性が非常に高いです。
いじめというものは基本的に理不尽な動機によって始まることが多く、何が地雷かは分からないという特徴があります。時には仲の良い友達でさえ、自分にとって「敵」になることもあるのがいじめの恐ろしい部分です。そういった不安定な環境下に身を置き続け、いじめられないように毎日あらゆる決断を迫られながら子どもたちは学生生活をさも当たり前かの如く過ごしている状況は、一種の狂気じみたものと言っても過言ではないでしょうか。
ひたすら周囲の友だちから嫌われないように、自己主張や対立を避けて周囲に同調し、当たり障りのない人間関係を維持しようとする子どもたちの心掛けは、過剰適応を助長していると考えられるのです。
自分の場合
私の場合は、上記の親子関係や学校内でのコミュニティ環境に非常に苦しめられてきました。親子関係については、子どもの頃から父親が完璧主義だったため、何かとハードルの高いことを要求されることが多く、親の望んだ以上のことが出来ない場合は、激しく怒鳴られ「お前は出来ない奴だ」烙印を押される感じでした・・・。
決して打破出来ない環境の中、自分が行える唯一の措置は認められるように振る舞うことでした。なので、小学校高学年の時に受けたいじめの話も落胆されたくないため、親には一切話しませんでした。
きっとこの頃から、過剰適応ぎみであったのではないかと今は思っています・・・。
いじめが解決した後も、あの時に受けた衝撃はそう簡単に忘れられるものではありませんでした。中学校ではそれなりに親しくできる友人は少なくはありませんでしたが、素のままの自分が出せるかと言われればそういう訳ではなく、何から何まで気を許せる関係ではなかった気がします。何気ない会話でも自分は常にその内容に集中し、「これを話せば場を乱さずについていける」や「これを言うとA君が不機嫌に思うかもしれない」等、一言一句に気を配ってました・・・。
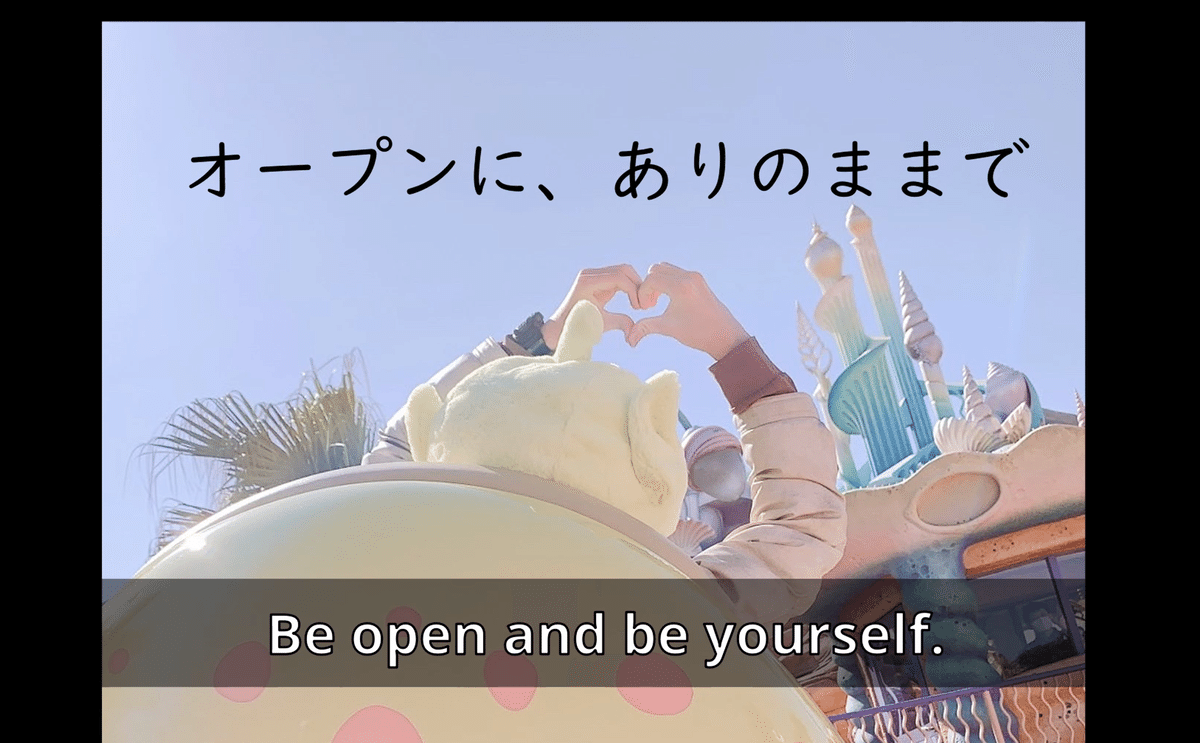
他人事ではないからこそ、知ることが大切!
今まで書いてきた内容は特殊なケースばかりという訳ではなく、経験している人も少なくないはずだと思っています。しかし、過剰適応になる人とならない人とが分かれているのには、偶然にも辛い環境が続いてしまうことや、本人の元々の性格等によって明暗が分かれるという可能性もありえます。
大事なのは、過剰適応に「なる・ならない」ではなく、過剰適応についてもっと知ることではないです!
認知度が上がることで人との接し方や、周りからのサポート等が良い方向に変化する可能性があり、実際の当事者は改めて自分を認識することで、見落としていた大事なものを再発見する機会にもなります。
受け入れ、次に繋げようと行動することが過剰適応との一番の関わり方なのです!
おわり
春学期の内容をまとめてみると、「中々に濃い学生生活を遅れているのでは」と感じていますが、秋学期からはより密度の高い活動が続いていきます!
色々と不安なことはありますが、自分らしさを大切にし、健康に気を付けながら突っ走って行きたいです!!
拙い文章でしたが、ご一読下さってありがとうございました!
