
パヴリコフスキと行く! ソ連崩壊直後の世界を旅するドキュメンタリー①
10/19公開の「グレース」がとても良かった。ソ連崩壊後の荒廃したコーカサス地方を、寄る辺ない父娘が旅をするロードムービーで、送電線を辿ってたどり着く先には、超大国になり損ねた世界の果てが横たわっている。監督はイリヤ・ポボロツキーで、これまでドキュメンタリーを撮ってきてこれが長編劇映画デビューだという。
で、なにかソ連遺産をめぐる旅ものなかったかな、と例によって無理やり思いついたのが今回紹介する劇映画を撮る前のパブリコフスキが撮った1990年から1994年までのソ連崩壊を挟んだ激動期を映したドキュメンタリー。まさに崩壊したばっかりのソ連とその周辺を、キャラ強めの被写体のポルトレを通して映し出し、1時間弱の尺では物足りないほど面白い。ちなみにどれも未ソフト化、劇場未公開だがYouTubeで英語字幕付きでみられる。
監督したのはパヴェウ・パヴリコフスキで、ポーランド生まれイギリス育ちの映画監督。今世紀に入ってから「イーダ」「COLD WAR あの歌、2つの心」のモノクロ2作を発表して絶賛を浴び、最も新作が楽しみな監督のひとりである。その監督が劇映画を撮る前に4本のドキュメンタリーを撮っている。BBC製作でこの時期この場所この人でしかありえない、一回限りのすごい撮れ高となっており、混迷を極めた時代に良くも悪くも目立った傑物たちにかなり近い距離まで近づくことに成功している。この距離感が絶妙であまりに惨めすぎてもはや笑わずにはいられない強烈なシーンを畳み掛けてくる(とくに『エロフェーエフ』『ドストエフスキー』)。被写体の強烈なパーソナリティと稀有な時代が合わさった偶然は、その後の歴史を思うとゾッとする笑えない不謹慎な喜劇でもある(とくに『セルビア』『ジリノフスキー』)。テレビ製作ゆえどれも45-60分の時間の中にテンポよく構成されており、これどこまでドキュメンタリーなのだろうか、と疑ってしまう撮れ高は、実は監督の関心とも密接に関わっており、1998年の商業映画デビュー作『ストリンガー』ではそのあたりにテーマを絞って自身のキャリアを振り返るような作品を撮っている。まず1回目のこの記事では最初の2本を取り上げる。ついで後半ではドキュ2本と長編劇映画を取り上げる予定。
ちなみにパヴリコフスキの新作は、報道によればホアキン・フェニックスとルーニー・マーラ主演のようだが、製作が難航しているようだ。まあ、いつまでも待ちますよ。
記事書きながら思い出した余談をひとつ。「コールドウォー」公開時無職真っ盛りだったのをいいことに平日昼間(サービスディ)渋谷HTにガラガラの回を選んで観に行った。映画の中で主役の歌姫ヨアンナ・クーリクが「Сердце」というロシア語の歌を歌うのにはびっくりした。というのも、彼女がモスクワの劇場で見た映画で覚えた、というその歌を、私も同じ映画で歌詞を覚えてよく歌っていたからだ。これは『陽気な連中весёлых ребят』という戦前のミュージカルコメディで、歌う場面だけYouTubeに上がっていたのを見つけて、ロシア語の勉強のつもりで歌詞を覚えていたのだった。ロシア語で歌える歌など数えるほどしかないだけに、何か縁のようなものを感じてしまったのだった。
もう少しあとの話になるが、『陽気な連中』ものちシネマヴェーラの良企画ソ連映画特集で日本語字幕付きで見ることができた(ドタバタのコメディだった)。また全然赴き違う旅もの『インポート・エクスポート』(こっちはユーロスペース)では、エンディングでСердцеを聞くことできる。映画のトーンも曲の使われ方もまったく違うがどちらも傑作なのでついでにおすすめしておく。
で、「Сердце」と映画の内容に感動しながら客席を出て売店でパンフを買おうと列に並ぶと、前に並んでいた老人の顔にどこか見覚えが。同伴者と会話する声で確信したが、これが細野晴臣なのだった
From Moscow to Pietushki with Benny Yerofeyev 「一緒に座りたまえ。 足元に真理はないよ」
伝説の地下出版小説『Moscow-Petushki』。ロシアの酒呑みならば知らぬもののない書物のタイトルでで、書いたのはヴェネディクト・エロフェーエフ。カメラはソ連崩壊後ようやくおおやけの人となったアングラ作家をモスクワはフロツカヤ通りにあるアパートの一室に訪ねる。そこには昼から飲んでる氏がいて、長年の飲酒が祟って患った喉がんの手術跡を覆う痛々しいガーゼの上からマイクを喉に当ててボコーダー声でインタビューに応じてくれる。メタリックなウニャムニャ声にも面喰らうが、グラス片手に喋る内容がはじめから終いまでなんとも破滅的なのだ。
『酔いどれ列車』Москва — Петушкиは1969年に密かに発表された。地下出版サミズダートで流通し、1973年にイスラエルで、次いで1977年にパリで少部数が印刷された。ペレストロイカ期にあたる1988年にはロシアでも公式に出版された。

原作『酔いどれ列車』は一人の男がモスクワからペトゥシキまで列車に揺られるあいだ酒を浴びるように飲みながらあてもなくくだを巻く呑み鉄のひとり語り。物語詩らしいので散文の翻訳で読んでも原文のリズムはよくわからない(映画では著者の朗読が聞けるシーンがあり、しっかり韻を踏んでいて聴衆もそこに反応してる)。ひとりで徐々に酔っていくところから思考の呂律がおかしくなりはじめ、特製カクテルのレシピ大公開するあたりでエンジンがかかり、シェラザード形式で仲間がめいめいにネタを披露しあうと不思議なドライブ感が。ただしヤマオチイミなしの三拍子揃ったぐだくだぐでんぐでん話で、どこから読んでもいいし、どこで読み終わっても何も残さない。決して終点にたどりつかない、酔っ払いの戯言にシラフでどこまで付き合えるか、酔ったスフィンクスが言う通り「そもそもペドゥシキに行ける者なんぞ、誰一人いないのさ、ハハハ!…」
聖書、文学、政治プロパガンダを徹底的におちょくったその文体は、エロフェーエフの人となりに直に繋がっている。
ヴェネディクト・エロフェーエフВенеди́кт Васи́льевич Ерофе́ев(1938-1990)は北極圏コラ半島南西の都市カンダラクシャに生まれた。父親は駅長だったが1946年ソ連政府を批判したかどで収容所送りとなり、「人民の敵」の妻となった母親は四人の子供を養えずエロフェーエフは孤児院で暮らすことを余儀なくされる。優秀な成績でモスクワ大学に入学するも、学校の雰囲気に馴染めず軍事訓練に参加しなかったことでわずか1年半で退学してしまう。その後は様々な職を転々とし(石工、火夫、図書館員etc)、鉄道の架線技師としてソ連中を移動する生活を10年にわたって続ける。酒と読書に明け暮れるなか、『酔いどれ列車』は執筆された。ちなみにエロフェーエフは5歳から書きはじめ、17歳のときに書いた『精神異常者の手記』Записки психопатаが2000年に入ってから発見され出版もされているようだ。『酔いどれ列車』も素人目には一見ただの呑べえの乱文に見えるが、実は深い教養に裏づけられているのだという。ロシアでの出版が叶った2年後の1990年にエロフェーエフは咽頭癌で亡くなった。映画は彼の最晩年を捉えている。日本での翻訳は1996年『酔いどれ列車、モスクワ発ペトゥシキ行』(国書刊行会)が出ている。作品の詳しい分析は訳者安岡治子氏による巻末解説を参照のこと。
映画の構成は原作の舞台となった駅の佇まいを映し、原書から抜粋が英訳で朗読され、作中登場人物のモデルになった人物がカメラの前でエロフェーエフについて語る。皆厳しい時代を生き、貧しく、だからこそ呑みまくった。画面を通して伝わってくる破滅的な飲酒ライフから、絶望を突き抜けた明るさと人懐こさに肩を寄せ合った作家の過ごした時代を想像させる。エロフェーエフは言う『俺はまわりにいた仲間のために書いたんだ』
エロフェーエフと『酔いどれ列車』の愛好家は後を絶たない。それもそのはず、ロシアには酒好きが五万といる。ソ連時代とはすなわち酒節制の歴史でもあり、最盛期には2000万人ものアルコール中毒者を抱えていた。劇中酩酊した酔っ払いたちが牢屋に引きずられていくのが確認できるが、酔いを醒ますためだけの独房があるほど、街のあちこちで酔いつぶれるひとがあふれていた。
没後10年記念でモスクワに記念碑が建てられたようだ。銅像の台座には碑銘が刻まれている。「二日酔いにあらざるものを信用するな」

Dostoevsky's Travel 「私の名前はドストエフスキーです」
ドストエフスキーといえばソローキン以前のロシア文学界最重要人物で、ロシア語を学んだ端くれとしては読んでないとは口が裂けても言えない文学界の大審問官みたいな凄すぎてもうよくわからない存在です。ことあるごとに”現代によみがえるドストエフスキー”などと引き合いに出されるとおり、ドストエフスキーは現代に生きているのだ。これは比喩ではない。『ドストエフスキーの旅』は生きて動いているドストエフスキーに密着した世にも珍しいドキュメンタリーである。ただしあのフョードル・ミハイロヴィチ・ドストエフスキーではなくて、そのひ孫ドミトリー・ドストエフスキーなのだが。
ドストエフスキーには四人の子供がいた。うち二人は早世したが、残されたひとりリュボーフィは欧州に渡り父親ドストエフスキーについてエッセイを残した。残るひとりは父親と同じフョードルという名前を持ち、作家になろうとしたが成功せず父親の残した作品の整理収蔵を成した。このフョードルにはこれまたフョードルという息子がいて、彼が1945年に成した息子が今回の主人公となるドミトリーである。

パヴリコフスキはサンクトペテルブルクのドストエフスキー博物館を訪ねた際(私も昔行った)作家の子孫が生きていることを知り、ドミトリーに接触した。1000ポンドの出演料を払う代わりに、1862年にご先祖が旅したように欧州を横断する様子を撮影させてほしいと頼んだ。ドミトリーは高校卒業後ダイアモンド加工、タクシー運転者、電気技師、ツアーガイドなど20もの仕事を転々としており、お世辞にも成功しているとは言い難かった。
ドミトリーはご先祖を意識してかひげを生やして威厳を装ってはいるが、物腰低く、ベンツに憧れる小市民的な性格である。かの大作家の面影をうっすら感じさせながら、とぼけた佇まいがどこか気のおけない存在である。
最初の訪問地はドイツ。ソ連崩壊後資本主義社会に参入した旧ソ連人は、ドイツに行ってまず真っ先にメルセデス・ベンツを求めたという。ドミトリーもご多分に漏れず車を物色しにかかるのだが、懐さみしくなかなか手が出ない。人懐こいディーラー(いいキャラ!)を前に、ドミトリーは斜め上の相場を知らされる。よし、と目的も定まりベンツを買う金を貯めるべく、資金調達のためもって回った口上を繰り返して金策旅行が幕を開ける。
「私の名前はドミトリー。『カラマーゾフの兄弟』と同じ名前です。イワン、アリョーシャ、ドミトリー。ね?」
上目遣いにペコペコ頭を下げながら、ドストエフスキーと名前のついたサークル、サロン、観劇に出没しては子孫を名乗って出演料をもらい、ご先祖の肖像を描いた素朴なドローイングを手売りして細々と小銭を稼ぐ。行く先々で文学愛好家たちのイベントに顔を出し、'真の預言者'、'ロシアを理解する鍵'とさえ言われる偉大な先祖の末裔として、新生ロシアのゆくえを問われてはしどろもどろに適当なことを答えては観衆を眠気に叩き込む。
ドミトリーのドサ周りを追いかけるとドストエフスキーという存在を通して西側世界の人間がロシアをどう見ているのかを垣間見ることができる。とはいえ映画の演出はやや意地悪な撮り方で、言葉に不自由するドミトリーが失態を繰り返すのを無様に見えるように撮ったり、あたかもドミトリーが名前以外に何の取り柄もないかのように単純化し突き放して映している。どことなく胡散臭い風貌も手伝って、こいつ悪名高い「偽ドミトリー」じゃね?と誰もが疑わないではいられない(失礼)。
いつまでたってもベンツにありつけず手をこまねいていると、カジノで遊んでる金持ちの御仁から「お前は自分の名前の価値をわかってないな。おれならそんなちまちま小銭稼ぎなんてしないでバーデン・バーデンに行くね」とアドバイスを受け、言われるがままかの地を訪ねて歓迎を受ける。言わずとしれた『賭博者』の舞台になったカジノ保養地にドストエフスキーがやってくる!バーデン!バーデン!
歴史的な再訪(?)がタブロイド紙に写真付きで見出しを飾ると、これで要領を得たのかドミトリーはご先祖の名を盾に一躍タレント気取りで社交界の仲間入りを目論む。『白痴』に出てくる貴族の子孫を訪ねて君主制を語り、トルストイの子孫が主催する『戦争と平和』ボールパーティで社交ダンスを踊り、21世紀のボヤール(бояре中世の地主)再興を予言して周囲を唖然とさせる。手当たり次第かやけっぱちか、あてのない放浪は続き、あとに残るはタブロイドの飛ばし記事だけ。念願のベンツを手に入れられたかどうかは見てのお楽しみ。
ちなみにドミトリーは2004年に来日しドストエフスキーイベントで講演もしていたようだ。そして今年9月に風邪をこじらせて79歳で亡くなった。
映画を見ればわかるとおり、ドミトリーはご先祖よりはるかに親しみやすい。文豪の難解な作品に手が出ないのなら、まずはこっちのドストエフスキーから見始めてみるのも悪くないだろう。
訃報記事→https://www.themoscowtimes.com/2024/09/05/dostoevskys-only-great-grandson-dmitry-dies-at-79-a86274
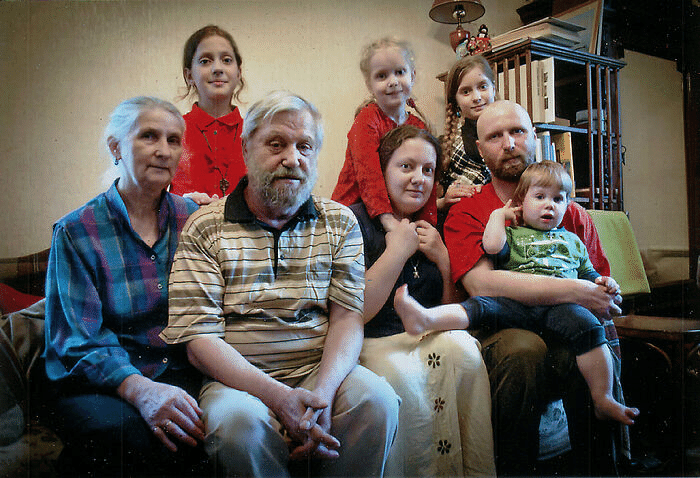
いいなと思ったら応援しよう!

