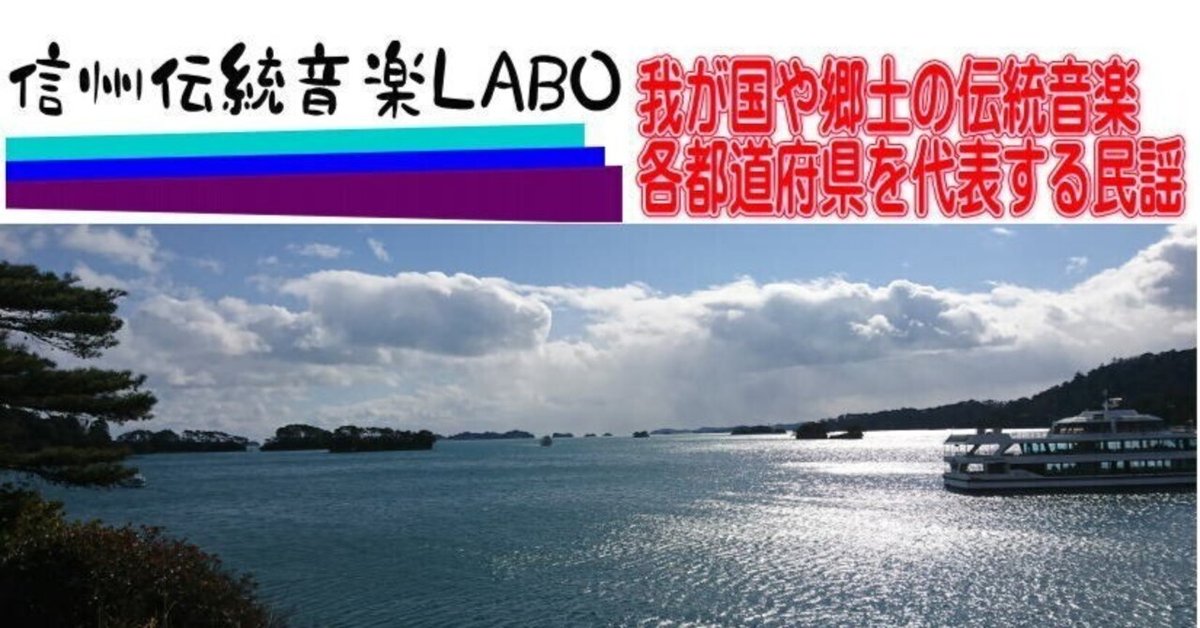
富山県の民謡~越中おわら節
「風の盆」…何とひびきのいいことばでしょうか。毎年、9月1、2、3日の3日間、《越中おわら節》が歌い踊られるのは、富山県富山市八尾。この時期は二百十日で、「おわら風の盆」という固有名詞として、もう全国に知られたものになっています。趣のある八尾の町で踊られる様子は、何ともいい雰囲気です。

また「前夜祭」として、8月20日から30日までの11日間、町内の11の支部により、日ごとに踊られているのだそうです。
■曲の背景
おわら節の成立
「おわら」とはどういう意味でしょうか。その語源について、地元では「大笑い」が「おわら」となったという説、豊作を願い、稲の藁が成長するようにという祈りをこめた「大藁」が「おわら」になったという説、小原村の娘が歌い始めたという「小原村」説などがあります。
民謡研究の竹内勉氏によれば、
〽︎あいや可愛いや 何時来てみても
たすき投げやる オワラ暇がない
といった歌詞が九州の酒盛り唄である《ハイヤ節》の変化した《アイヤ節》の歌詞であることから、日本海沿岸から伝播してきた唄ではないかと説明されています。
確かに、全国的にみても第3句目と第4句目に「オワラ」とか「オハラ」というリフレインが挿入される「おはら節」「小原節」「おわら節」といった楽曲があるので、各地に流行した歌が八尾に伝播したものと考えられるように思います。
おわらと胡弓
《越中おわら節》といえば胡弓のイメージがあります。むせぶような哀愁に満ちた音色の胡弓は、もはや欠かせない楽器です。《越中おわら節》に胡弓が取り入れられたのは、明治以降のことです。石川・輪島出身の塗師で、浄瑠璃の修行をして八尾に移り住んだ松本勘玄(明治10年(1877)~昭和24年(1949))が、八尾に来ていた越後瞽女の佐藤千代の弾く胡弓に触れ、研究を重ね《おわら節》に取り入れ、現在の形にしたものといいます。
胡弓というと中国の二胡をイメージしがちで、混同されがちです。日本の楽器の割に、実際に目に触れることが少ないこともあって、同じものをさしてるように思われがちですが、二胡と胡弓は全く違う楽器です。形は三味線をそのまま小さくしたようなフォルムで、弦が3本(4弦の胡弓も存在)、弓で擦奏します。バイオリンの弓などとは違い、指で調節しながら毛を張って弾きます。また、弓の位置を動かすのではなく、楽器本体を動かすのも特徴です。
洗練されていくおわら節
《おわら節》と「風の盆」はセットで考えられていますが、もともと「風の盆」は、いわゆる盂蘭盆の8月よりも遅く、台風シーズンとなる二百十日、9月1~3日に行われるようになったもので、秋の風除けの行事であるといいます。かつては、人々が思い思いの鳴り物などではやしながら、歌い踊り、流して歩くようなもので、いろいろな歌が歌われた中に《小原節》があったようです。
しかし、このままでは廃れてしまうかもしれないとの危機感をもったのが八尾町・東町の医師、川崎順二(明治31年(1898)~昭和46年(1971))でした。

それまで猥雑な歌詞で歌われていたものから、より洗練されたものにし、郷土芸能として広められるよう、日本画家で歌人の小杉放庵(明治14年(1881)~昭和39年(1964))に、新しい歌詞を依頼したことから始まり、八尾に文人たちを招聘し、歌詞を整えていきます。
踊りについては、日本舞踊の家元、初代若柳吉蔵(明治12年(1879~昭和19年(1944))が大正年間に関わった旧踊り、豊年踊りがありました。その後、東京三越で行われる富山物産展に合わせて、昭和4年(1929)に川崎順二が日本舞踊の初代若柳吉三郎(明治24年(1891)~昭和15年(1940))に新しい踊りの振付を依頼しました。
また、地元には優れた唄い手が存在しましたが、中でも江尻豊治(明治23年(1890)~昭和33年(1958))は、浄瑠璃で鍛えた歌唱力と美声によって、より洗練さが加わりました。特に、上の句と下の句をそれぞれ一息で歌い切るという名人芸的唱法まで生まれました。
こうした努力もあり、《越中おわら節》は土地の香りを保ちつつも、洗練された日本民謡の名曲の1つになっていきました。
おわら節の保存・伝承
八尾ではおわら節研究会が組織され、やがて昭和4年(1929)には、越中八尾民謡おわら保存会が発足、昭和26年(1951)には越中富山県民謡おわら保存会、平成21年(2009)には富山県民謡越中八尾おわら保存会と改称し、今日に至ります。
現在、八尾では東町 西町 今町 上新町 鏡町 下新町 諏訪町 西新町 東新町 天満町 福島の11町内を支部として、保存会が構成されています。なお、川崎順二は初代の会長です。
一方、保存会とは別に越中八尾おわら道場(旧越中おわら保存研修道場)という団体が《越中おわら節》の研修と伝承・普及を目的として、昭和60年(1985)に設立(平成元年(1989)に現行の通り改称)されました。民謡研究の竹内勉氏を特別顧問として、講習会の運営、技能審査会で資格認定を行ってきました。風の盆の当日に、浄土真宗の古刹・門名寺の境内で踊られているとのことです。
■音楽的な要素
曲の分類
踊り唄
演奏スタイル
歌
唄バヤシ
三味線(本調子)
胡弓(三下り)
太鼓
拍子
2拍子
音組織/音域
民謡音階/1オクターブと4度(五文字冠り、字余りでは5度)

曲の構造/特徴
①詞型は7775調の甚句形式です。下の句第3句目のあとに「オワラ」というリフレインが入ります。
②各唄では、ハヤシの
・唄われよ わしゃはやす
を聞いて、唄に入ります。上の句のあとには、
・キタサノサドッコイサノサ
が入り、下の句に移ります。
この他に、唄の前後に長バヤシが入ります。なお、
・浮いたか瓢箪 軽そに流れる
行き先ゃ知らねど あの身になりたや
で演舞を終わるようになっているようです。
③基本的な歌い方は、戦後から今日にいたるまで歌われているものです。7775調の基本的な歌い方を「素唄」とか「平唄」といいます。また、素唄の詞型に5文字を加えて歌う五文字冠り、7775調よりも多い文字数の歌詞を詞の配分や旋律を変化させて長く歌う字余りがあります。
④江尻豊治のような名人の歌唱が広まる以前は、奔放に歌われていたようですが、今日でも天満町に天満町おわらとか川窪(コクボ)おわら等と呼ばれる独自の節回しが残されています。現行の《おわら節》のような長く一息で歌うようなスタイルではなく、途中でブレスを入れながら歌われます。
⑤素唄(平唄)には、歌い出しの長さから三拍子 五拍子 七拍子 の3通りの歌い方があります。
三拍子は、もっとも素朴な歌い方で、歌い出しのアウフタクト後の強拍から伸ばして3拍目に次の文字に移るスタイルです。現在ではあまり歌われないようです。
五拍子は、歌い出しのアウフタクト後の強拍から伸ばして5拍目に次の文字に移るスタイルです。
七拍子は、現在もっともよく歌われているもので、戦後から歌われているといいます。歌い出しのアウフタクト後の強拍から7拍伸ばして次の文字に移るスタイルです。
比較すると下記のようになります。

ここで言われている「拍子」とは、西洋音楽的な意味ではなく、拍と考えると分かりやすいと思います(《越中おわら節》の採譜では拍子は2/4拍子で採りました)。
■評価例
[知識・技能]
①歌と三味線・胡弓・太鼓の伴奏パートとの音の重なり方の特徴について、独特なテクスチュアの構成を聴き取り、風の盆で繰り広げられる音空間の雰囲気につながっていることと関わらせて理解している。気付いている。
[思考・判断・表現]
①歌パートと三味線・胡弓パートの音の重なり方を知覚し、それらの働きが生み出す複雑な音の重なり方や哀愁を感受しながら、曲全体を味わって聴いている。
[主体的に学習に取り組む態度]
歌パートと三味線・胡弓・太鼓の伴奏パート部分の音の重なり方に関心をもち、音楽活動を楽しみながら主体的・協働的に民謡の特徴を探る鑑賞の学習に取り組もうとしている。
下記には、《越中おわら節》の「素唄七拍子」「素唄五拍子」「素唄三拍子」「五文字冠り」「字余り」(8種類)「天満町おわら」の各採譜を掲載しました。
ここから先は
¥ 600
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
