
連載小説|恋するシカク 第8話『彼女からの電話』
作:元樹伸
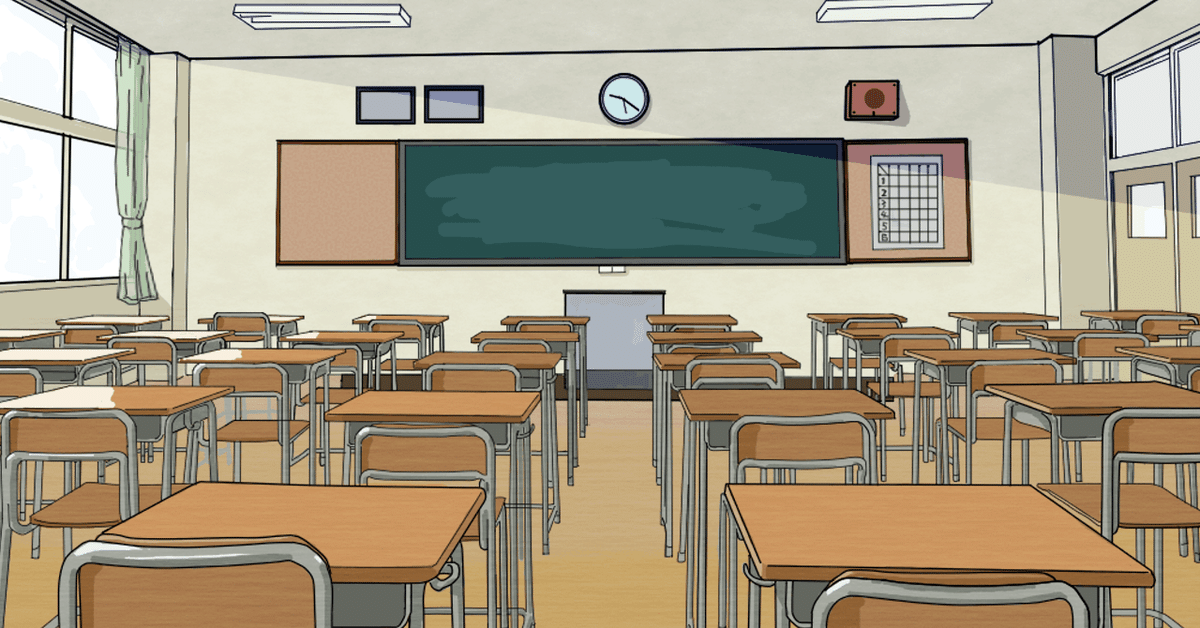

本作の第1話はこちらです
↓↓↓↓↓↓
第8話 彼女からの電話
文化祭で上映する予定の映画はホラー作品で、殺人鬼に追われる主人公とヒロインの姿を描く予定だ。安西さんが出てくれるなら沢山の出番が欲しいと思った。だからヒロインは最後まで生き残り、主人公は彼女をかばって命を落とすストーリーにするのだ。
一度はホラーを止めて恋愛映画も考えたけど、安西さんに勘ぐられて嫌がられたらそれまでだ。この段階まで漕ぎ着けた以上、計画は慎重に進めたかった。

脚本の執筆が始まり、美術室に寄ることが少なくなった。放課後はドリンクバーと山盛りポテトでファミレスに居座り、日が暮れるまで黙々と脚本を書いた。
絵を描くのとは違って、適度な環境音がある中で作業した方が筆も進んだ。それに安西さんがヒロインだと思うと書く勢いも増して、いつもの難聴からくる耳鳴りが全然気にならなかった。
僕の右耳は中学二年の時に突然聞こえなくなった。病院の耳鼻科で検査を受けて突発性難聴だと診断された。医者はストレスが原因かもしれないと告げた。当時は学校でいじめられていたから、それが原因かもしれなかった。
診断されてから一ヶ月間は治療のために学校を休んだ。おかげで次第に聴力は回復したけれど、煩わしい耳鳴りだけはいつまでも続いた。
ザザッ、ザザッ。
周波数の合わないラジオのような音につき纏われて、治療中もストレスが溜まった。だけどそれも数週間が経つと慣れてきて、僕は次第に普段の生活へと戻っていった。
コーラのお代わりをしようとグラスを手に席を立ちかけた時、携帯電話が鳴った。画面を確認すると安西さんからだった。
普段はメールだけのやり取りなのに、電話をくれるなんて、今日は一体どうしたんだろう。僕は幾ばくかの期待感を胸に秘めて、緊張したまま通話ボタンを押した。
「林原くん、今大丈夫?」
スピーカーのむこうで、安西さんが奴の名前を呼んだ。
「あの、河野だけど……」
「ごめんなさい! 間違えました!」
電話はすぐに切れて僕は愕然とした。
第一に間違えた相手が林原だった。第二に安西さんは林原を「先輩」ではなく「くん」付けで呼んでいた。そして第三に、やっぱりあの二人は付き合ってるみたいだった。
ザザザッ。
喧噪と共に終わりなき蝉騒のような耳鳴りが戻ってきた。完全に集中力が途切れ、僕はのろのろとお店を後にした。

文化祭で行われる美術部の展示会は、部員が新作の絵を発表する場となる。僕はいつも描いているから焦ったりはしないけど、作品と一緒に貼り出す作者の自己紹介文は今年も用意する必要があった。それも美術部にはこだわりがあり、画用紙に手描きの文字を書いて作成するルールになっていた。
「河野くん、やってるねぇ」
美術室で紹介文の内容を考えていると林原がやって来て、僕の手元にある画用紙を覗き込んで言った。
「文化祭に出す絵、林原はどうするつもりなんだ?」
三年になって林原が絵を描く姿を見た記憶がないので、一応聞いてみた。
「別に去年描いたやつでもいいんだろ?」
「まあね」
鉛筆で下書きを続けながら適当に答えた。やる気のない奴には何を言っても無駄だからだ。
「で、頼みがあるんだけどさ。その自己紹介文、オレのもやってくんないかな?」
「何で僕が林原の自己紹介を書かなきゃいけないんだよ」
不躾にもほどがあったので苛立ちを憶えて聞いた。
「だって字が上手いだろ? それにクラスの準備が忙しくてさ。マジでやべぇんだよ」
「こっちだって映画忙しいし」
断る理由を口にしたけど、本当はただ嫌だからだった。
「それなら奈子に聞いたよ。でもあいつ、演技なんかできんの?」
林原は安西さんを下の名前で呼び捨てた。彼女のことなら何でも知っているような口ぶりで、「オレたち付き合ってます」オーラが全身から漂っていた。
それから林原は「まあ頼むよ」と続けたので、「安西さんなら大丈夫だから」と僕は即座に答えた。
「奈子のことじゃなくて俺の自己紹介文の話なんだけど」
「だから忙しいって言ってんだろ!」
林原に突っ込まれて恥ずかしくなり、僕は大きな声を出してごまかした。
「なら下書きだけでもいいよ。オレって字が汚いからさ。マジで頼むって!」
林原の提案はどこまでも勝手だけど、このまま問答を続けるより引き受けた方が奪われる時間が少ない気がして、僕は仕方なく承諾した。
「助かる! じゃあこれが内容な」
渡されたメモ用紙には、手書きの文章が記されていた。でもそこには一言も「女好き」とは書かれていなかった。
つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
