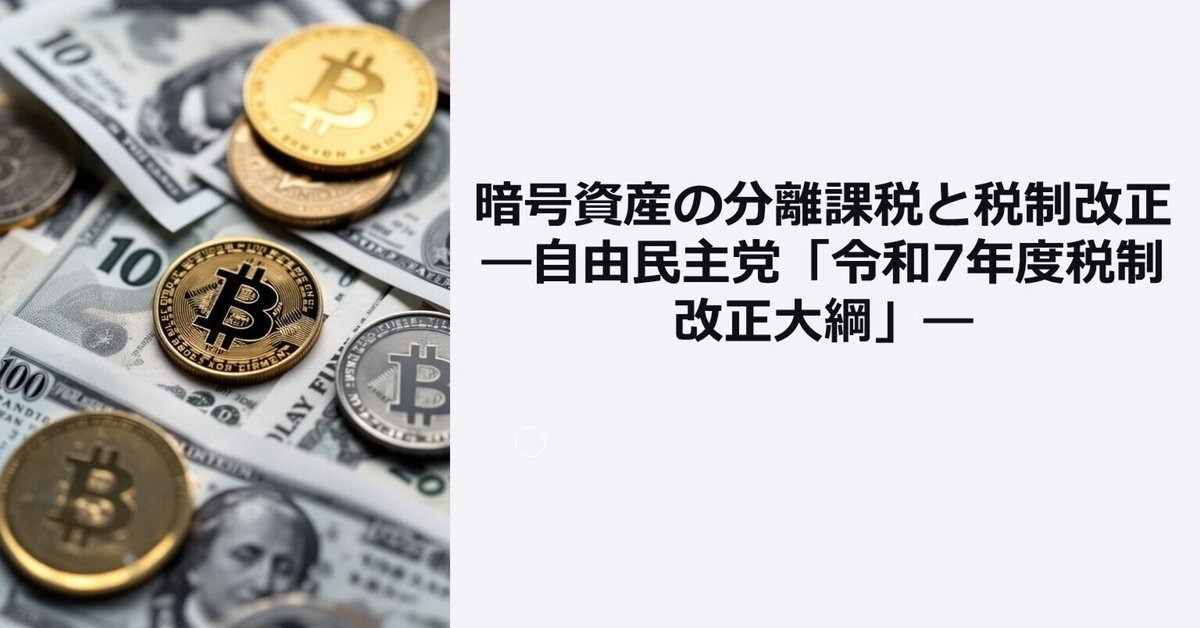
暗号資産の分離課税と税制改正:自由民主党「令和7年度税制改正大綱」
令和6年12月20日に自由民主党「令和7年度税制改正大綱」が承認されました。
暗号資産の分離課税については明記されていません。
ただ、あくまで「第三 検討事項」の項目にすぎませんが、以下のような記述が入りました。よって、今後、金融商品取引法で規律されるようになる場合は又は規律される一定の暗号資産については、分離課税の適用となる可能性があるでしょう。ただし、取引業者等による取引内容の税務当局への報告義務の整備等をすることが前提とされていますので、適正申告のための環境整備も実施されるようです。
「暗号資産取引に係る課税については、一定の暗号資産を広く国民の資産形成に資する金融商品として業法の中で位置づけ、上場株式等をはじめとした課税の特例が設けられている他の金融商品と同等の投資家保護のための説明義務や適合性等の規制などの必要な法整備をするとともに、取引業者等による取引内容の税務当局への報告義務の整備等をすることを前提に、その見直しを検討する。」
もっとも、自民党は早くから、暗号資産取引による損益を申告分離課税の対象にすることを検討すべきと提言していましたので、上記の記述は形式的には自民党のこれまでの考え方を繰り返したものにすぎません。他方で、税制改正大綱にこのような記述が入ったのは初めてですので、今後は一層、「分離課税導入の検討」が進むでしょう(導入することが決まったわけではありません)。
まず、自由民主党デジタル社会推進本部web3PT「web3関連税制に関する緊急提言」(2022.11.10)は、暗号資産取引による損益を申告分離課税の対象にすることを検討すべきであると明記していました。
このような記述は、自由民主党デジタル社会推進本部web3PT「web3ホワイトペーパー―誰もがデジタル資産を利活用する時代―」(2023.4)においても、次のとおり、引き継がれています。
「個人が保有する暗号資産に対する課税については、①暗号資産の取引により生じた損益について20%の税率による申告分離課税の対象とすること、②暗号資産にかかる損失の所得金額からの繰越控除(翌年以降3年間)を認めること、③暗号資産デリバティブ取引についても、同様に申告分離課税の対象にすることが検討されるべきである。
〔中略〕
上記の検討にあたっては、諸外国における個人の暗号資産取引に関する課税上の取扱いとの比較検討を行う必要がある。また、上記の取扱いによって納税者の税務申告や国家の税収にどのような影響を与えるかについても検討する必要がある。」
これに対して当局側は、次のとおりかなり渋い回答を繰り返していました。
令和4年3月16日参議院財政金融委員会・住澤整財務省主税局長の答弁
「まず、ファンジブルトークンのこの一種であります暗号資産の取引に係る所得につきましては、外国通貨の為替差益と同様に、原則として雑所得に区分されて総合課税の対象となるというのが現在の扱いでございます。
上場株式等の譲渡益等につきましては、税制の中立性ですとか簡素性、それから執行の適正な確保といった観点から、あるいはその貯蓄から投資への政策的要請でありますとか一般投資家が投資しやすい税制を構築するといった観点から20%の分離課税が採用されているわけでございます。
一方、この暗号資産の取引による所得に20%の分離課税を採用することにつきましては、給与所得や事業所得などのほかの所得とのバランスについて御理解が得られるかといったようなことですとか、株式のようにこの家計が暗号資産を購入することについて国として政策的にどういうふうに考えていくのかといった辺りについて、所管省庁等において考えていただいた上での検討が必要であるというふうに考えております。」
令和元年11月5日の参議院財政金融委員会 矢野康治主税局長の答弁
「上場株式等の譲渡益ですとか、あるいはFXを含む先物取引につきましては、20%の分離課税ということになっておりますけれども、このうち、例えば上場株式等の譲渡益等につきましては、貯蓄から資産形成へという考え方のもとで、家計における株式投資を後押しする意義がございまして、所得再分配機能を一定程度犠牲にしてもなおこうした意義が重要との判断によって、分離課税が採用されているところでございます。
暗号資産の取引による所得につきまして、20%の分離課税を同じく採用するということにつきましては、同じ1億円であっても、給与や事業で稼いだお金は最大55%の税率が適用される一方で、暗号資産の取引で稼いだ方は20%の税率でよいとすることについての国民的理解が得られるかどうかですとか、あるいは、株式のように、家計が暗号資産を購入することを国として推奨することが妥当かどうかなど、さまざまな課題があると考えております。」
「もちろん委員御指摘のように、投資家の方によっては、同じように投機目的で取り組んでおられるという方もおられなくはないかと存じますけれども、一方で、本源的な通貨あるいは株価があって、それのデリバティブズとしての先物であるとかFX等と位置づけがやはり違うということも事実だと思います。そういったことから、同列に扱うということはいかがなものかという考え方も強いというふうに認識しております。」
分離課税自体は、所得税法本法ではなく政策的な立法等を行う際に使われる租税特別措置法で定められています。租税法の原理原則から外れる面を有するため、一般論として分離課税の採用のハードルは高いです。例えば、次のような観点から検討する必要があります。
①国益追及・国民の理解
・暗号資産への投資による国益・国民の利益を具体化できるか
・投資資産なのか、他に実需があるのか、国として保護すべき取引か
・国民の理解は得られるか
ただし、これまでの租税政策のすべてが国民の支持や理解を得てきたか、得られてきたかという点は議論の余地があります。「国民の理解」という語は、人によっては使い勝手のよいマジックワードに聞こえるでしょう。
②投資家保護・市場基盤の整備
・安全な投資資産として市場基盤の整備
・金商法への組込み、取引所等に対する規制を厳格化
③適正課税の環境整備
・KYCルール等が整備されている国内取引所における取引の促進が適正課税に接続(比較、DeFiや相対取引)
・CARF(非居住者に係る暗号資産等取引情報の自動的交換のための報告制度)、特定事業者等への報告の求め、支払調書・年間取引報告書(直接的・悉皆的な所得捕捉)、適正記帳・損益計算・データ保全に係る仕組みの整備やの実効性の確保
④中立性
・金融商品間の課税の中立性
・有価証券、FXのほか、国外組成暗号資産ETF、国内暗号資産ETF(今後)との整合性
⑤その他
・イノベーション促進、企業の稼ぐ力とこれを後押しするために個人所得税を優遇
・地方創生の支援
いずれにしても実際に暗号通貨の損益に対して分離課税を導入しようとすると、解決すべき様々な問題や考えられる種々の制度設計がありうるため、議論の取りまとめは難航しそうです。
解決すべき様々な問題や考えられる種々の制度設計の例:
・無数にある暗号資産を一律に分離課税の対象とすべきか
・ビットコインだけを分離課税の対象とすべきか、そのことに合理的な理由はあるか。ユーティリティトークンも対象とすべきか。発行者や管理者が存在する、存在するといえるような暗号資産は分離課税対象外とすべきか
・詐欺的コインやIEOしてプロジェクトを進めていないような暗号資産を排除するか
・既存の金商法規制と同レベルの規制を導入すべきか金商法の規制に入った場合に、交換所やweb3事業者は規制遵守コストがどの程度上がるか。
・分離課税について、金商法規制とセットではない導入ルートはないのか。
・マネロンや課税・徴収の観点からリスクの高い外国の取引所、DEX、プライベートウォレット、ブロックチェーンゲームにおける取引も分離課税の対象とすべきか
・暗号資産ETFのみを分離課税の対象とすべきか、現物やデリバティブも対象とすべきか(例えば、金のように現物とETFで取り扱いを分けるべきか)
・各取引所で取引や損益計算が完結するもののみを分離課税の対象とすべきか。暗号資産の取得経路及び取得価額が明らかなもの(国内取引所で購入し、一度も外に移転していないもの)のみを分離課税の対象とすべきか、現時点で外国の取引所やプライベートウォレット等で管理しているものも対象とすべきか。
・流動性供給、ラップ・アンラップ、レンディングなど、暗号資産の「譲渡」、課税イベントであるか否かが不明確な取引、国税庁がいまだ取り扱いを示さない取引についても分離課税の対象とすべきか
・購入・保有目的によって分離課税の対象・対象外を分けるか
・レンディング、ステーキング、マイニングの報酬はどうすべきか
・損失の繰越し控除を認めるべきか、どの種類の所得と損益通算を認めるべきか
