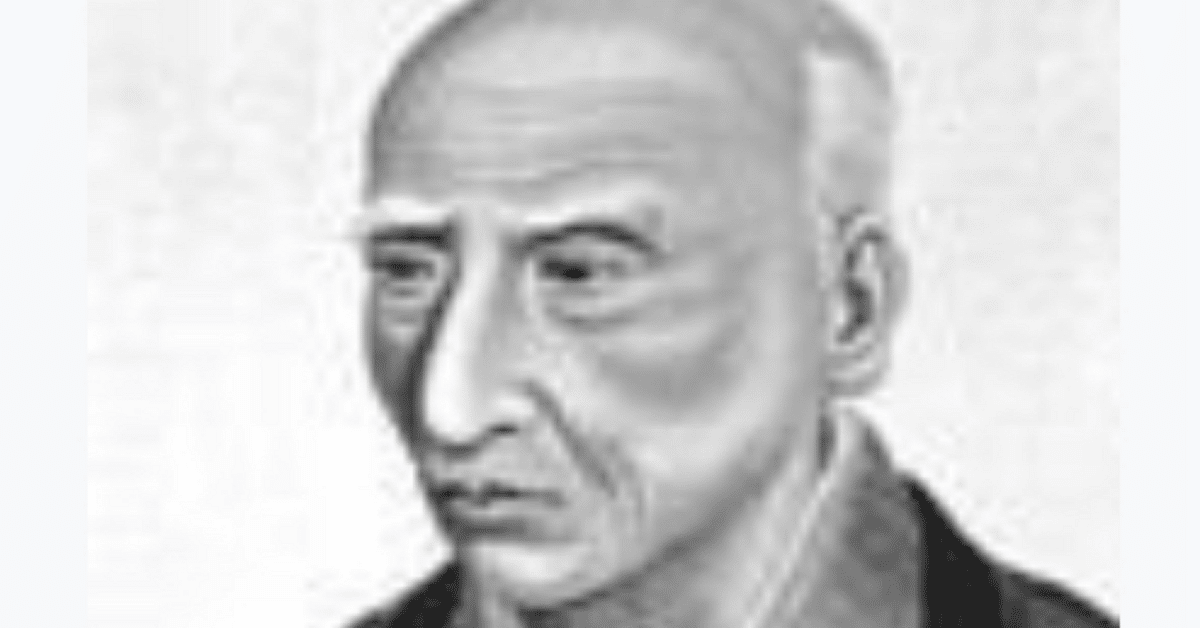
東京は今年で201歳
日本の首都は?と聞かれれば、ほとんどの方が東京と答えられるくらい東京という名前は万人にとって当たり前の地名だ。
しかし歴史の教科書を読むと東京という名前が出てくるのは明治になってから。
ではその前はなんと呼ばれていたか。
江戸だったり、国でいえば武蔵だったり。
となると、いつどのようにして東京が生まれたのか?
もちろん地名なので、自動的に自然的に変わったわけでは当然なく、名付け親がいる。
江戸を東京、大坂(大阪)を西京というように二都制を提唱したのは
佐藤信淵(さとうのぶひろ)という経済学者。
彼が東京の名付け親だ。
徹底した日本至上主義で、世界征服についても書かれているので、
あまり公にできない書物らしい。
言ってみれば、日本原理主義みたいなものか。
混同秘策、あるいは宇内混同秘策と呼ばれた本は1823年に出された本で、ここで初めて東京という名前が出てくる。
つまり去年2023年は東京が東京になってから200歳になった年だった。
去年、こんなニュースは一度もなかったかな。
この佐藤信淵という学者が東京という名前をつけたことで
今自分は【交差点東京】というnoteを書くことができている。
地名の由来は調べてみると意外な発見があって面白い。
これからも暇を見つけては地名の由来を調べてみよう。
