
【コンサル物語】19世紀末のシカゴを描いた文学
1890年代、シカゴの人口は100万人を超え、ニューヨークに次ぐ第二の都市に成長していました。そのスピードは驚異的で、成長が留まる様子はありません。その様子を当時の文学作品から見てみたいと思います。
1890年代のシカゴを舞台にした作品に、アメリカ人作家セオドア・ドライサーの『シスター・キャリー』があります。1900年に出版された小説です。アメリカ中西部の田舎からシカゴに出てきた18歳のキャリーが、都会の華やかな魅力に取りつかれながら、シカゴ、ニューヨークで舞台女優として成功していくなかで、大都会の光と影を描いた物語。日本語訳は岩波文庫から上下巻で出版され、上巻はシカゴ、下巻はニューヨークが作品の舞台になっています。
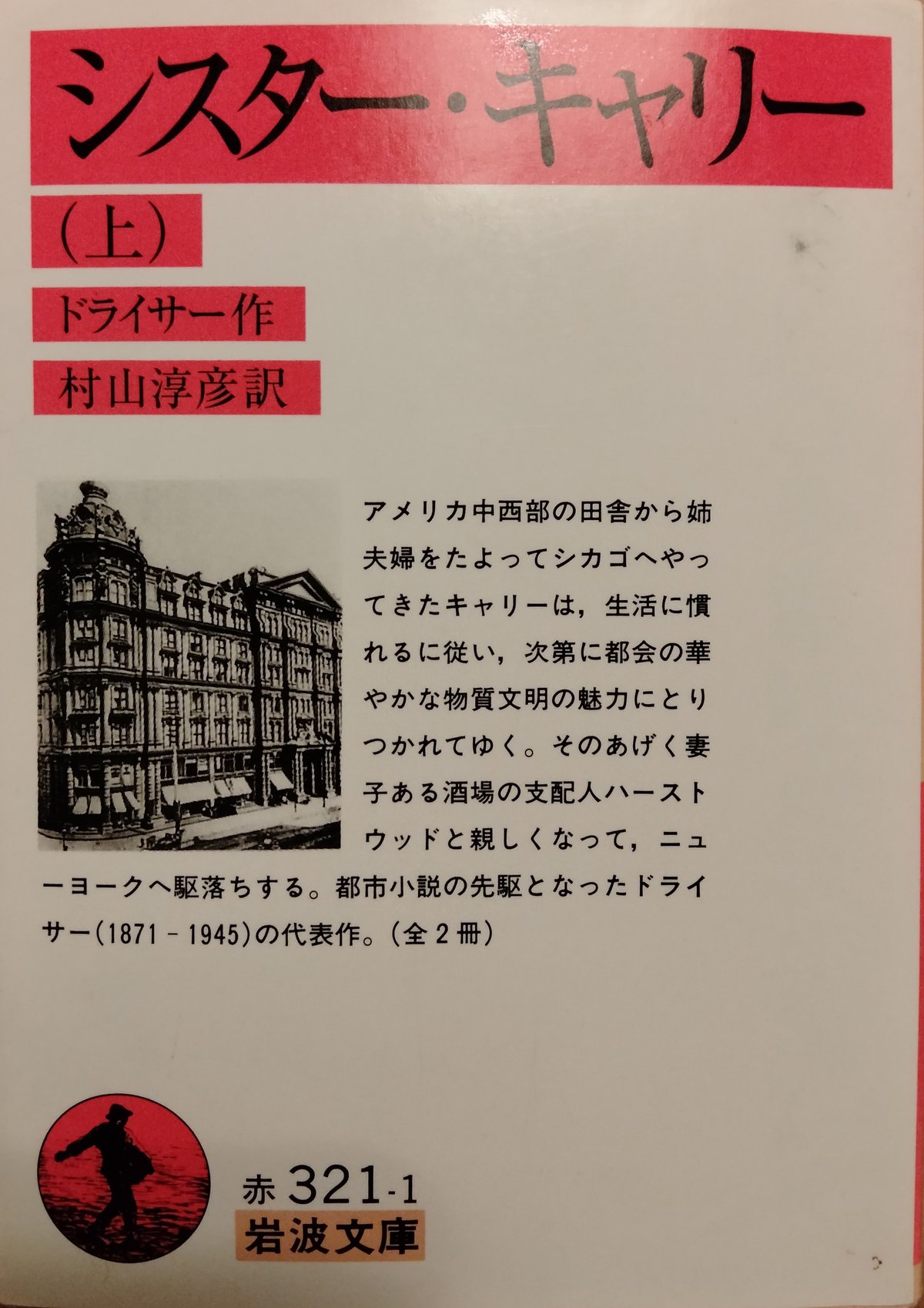
シカゴでの初日、キャリーが職探しのため街に出て行く場面では、当時のシカゴの様子が分かりやすく描かれ、大変参考になります。
仕事を探して歩きまわるキャリーのあとについていく前に、彼女の未来が広がるはずである舞台を見ておきたい。一八八九年のシカゴは、前代未聞の成長を遂げている真っ最中で、若い娘たちさえもこのように胸躍る旅に出てやってくるのは、無理もないと思えるような都市だった。稼ぎにありつける可能性にあふれていて、まだまだ発展中だという噂は遠くにまで広がっており、そのために、あらゆるところから希望にみちた人びとや希望を失った人びとを引きつける巨大な磁石になっていた
(中略)
人口五十万を超える都市であり、百万都市にふさわしい野望と派手さと活力を発散していた。その街路と建物が占めている面積は、すでに七十五平方マイルの広さに及んでいた。急増する人口を吸収していくのは、既存の商業界よりも むしろ、よそから新たにやってくる人びとをあてにして拡大していく産業界だった。建設の槌音がいたるところで響き、新しい建造物が建てられつつあった。大企業が進出してきた。この地域の将来性に早くから目をつけていたあちこちの巨大な鉄道会社は、輸送中継基地や貨物配送場にする目的で、すでに広大な土地を入手していた。路面鉄道は、 人口急増を見込んで遠くの田園地帯にまで延びていた。市は道路や下水道を何マイルも敷設し、場合によっては、孤立した家屋がたった一軒きたるべき人口稠密地の先駆者といった風情で立っているだけの地域にまで及んでいた。吹きさらしの風や雨 に打たれるままになっている地域もあり、それでもそこは夜になると、長く列をなしたガス灯の風に吹かれてちらちら揺れる光がいつまでも点っていた。板敷きの狭い歩道が、遠い距離を隔てて点在する住宅や店舗をつなぐように延びて、それがしまいに途切れるところの先には、大草原が広がっていた。
1889年のシカゴは前代未聞の成長を遂げ、あらゆるところから人々を引きつけ、百万都市にふさわしい派手さと活力を持っていました。シカゴのダイナミズムは、その成長の余地がまだまだ続いていたというところでしょう。街の中心部には既にいくつもの建物が建設されていますが、中心部から何マイルも離れた田園地帯でさえ、将来の拡張を見込み、路面電車、道路、下水道、ガス灯といったインフラが整備されていたことが分かります。そして、更に先には大草原が広がり、無限の成長を期待できる都市が描かれています。
百万都市になってなお発展途上だというシカゴのダイナミズムは、主人公キャリーが列車でシカゴに到着する場面でも描かれていました。徐々に近づいてくるシカゴの街並みが手に取るように伝わります。
列車はシカゴに近づいていた。いたるところに無数の看板が見えてきた。そのそばをかすめるようにして列車は走る。野原に並び立つ電柱に張り渡された電線が、大股で歩く人のように上下しながら、さえぎるものもなく広がる平坦な大平原の景色を横切り、大都会に向かっている。遠くには、郊外の町らしいものが見え、何本かの煙突が空高くそびえ立っている。だだっぴろい野原の真ん中で、堀も植木もない敷地にぽつんと立っている二階建て木造家屋が、頻繁に見えてきた。もうじき大挙して押し寄せてくる住宅群の前哨をつとめる一軒家だ。
シカゴの周辺はまだ、大平原であり、だだっ広い野原であったわけですが、そのエリアまで電線が敷かれ、人口増に備えていたことが分かります。
さて、シカゴでコンサルティングが生まれるきっかけの一つに、当地での会計の発達が挙げられます。19世紀後半に急速に発展したシカゴでは、企業が最新機器や簿記に精通した人材を求め始め、ちょうど1890年代にはシカゴは会計の中心地となっていきます。
『シスター・キャリー』でも当時の様子が描かれています。主人公キャリーがシカゴで仕事を探していく描写のなかで、タイプライターや簿記のスキルが求められていたことがわかります。(主人公キャリーは、いくつもある会社の中から、これはという所に職を求めて飛び込んでいきます)
「ご用は何でしょう、お嬢さん」こう訊きながら、興味を示してキャリーをじろじろ見まわす。
「お仕事がいただけないかどうか、教えていただきたいのです」
「たとえばどんな」
何か特別決まったものでなくていいんです」キャリーはたじろいだ。
「これまで衣料品問屋の業界で働いた経験はありますか」
「いいえ、ございません」
「速記かタイプライターはできますか」
「いいえ、できません」
「そう、それではここには口はありませんね。うちは経験者しか雇いませんから」キャリーはドアのほうへあとずさりした。
「ご用は」
「何かお仕事をいただけませんか」
「さあて、じつはわたくしには何とも」男の言い方はやさしかった。
「どんな仕事をお望みですかーあなた、タイピストではないでしょうね」
「はあ、ちがいます」
「そうですか、ここでは帳簿係とタイピストしか雇いません。あちらの脇から上の階にあがって、訊いてみたらいいでしょう。(後略)」
このように、シカゴでは会計人材を集めることが急務であったわけですが、一方で会計の専門家を育成することも喫緊の課題とされていました。現場の会計業務を担っている簿記係だけでは、新しい技術、法律、複雑な取引や組織体系に十分対応できませんでした。
そこでシカゴのあるイリノイ州では、会計の専門性向上を目指した活動として、1897年、後に州の公認会計士協会の母体となる専門団体が設立され、1903年には、公認会計士制度を定める州法が作られました。
ちょうどこの頃、スコットランドやイングランドの大手会計事務所も徐々にシカゴに支店を設立し始めました。1890年にロンドンからニューヨークに進出したプライス・ウォーターハウス(後のPWC)は、2年後にシカゴに支店を設立し、アーサー・ヤング(後のEY)は1906年に設立しています。
(参考資料)
『ENCYCLOPEDIA of CHICAGO』(Accounting (chicagohistory.org))
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
