
高品質なクレジットとは?
COP29初日に正式に承認された、第6条第4項に基づく方法論や吸収除去活動の要件についての基準。驚きを持って受け取られましたよね。
これにより明らかになたのは、パリ協定6条4項メカニズム(PACM : Parisi Agreement Crediting Mechanism)における、方法論の作り方ですが、早くもそのルールに従って作られた、炭素除去によるクレジット創生の方法論も公開されています。
先のnoteでは、その方法論に記載された「Definitions」により「高品質な炭素除去クレジット(Removal Credit)はどのような要件を備えておかなければならないのか」が判明したため、既存のボラクレの方法論がどのように変わるのかについて、自分なりの見解をお届けしました。

6条4項メカニズムに基づくGHGsの吸収・除去(removals)を含む活動の要件の基準(右)
今回は、「方法論の作り方」から「高品質なクレジットはどうあるべきか」を読み取っていきたいと思います。
この規格の構成はこんな感じ。
1.INTRODUCTION
2.ENTRY INTO FORCE
3.NORMATIVE REFERENCES
4.METHODOLOGY PRINCIPLES
5.ADDITINALITY DEMONSTRATION
6.LEAKAGE
7.NON-PERMANENCE AND REMOVALS
なので、4〜7を読み進めていけばOK
ちなみに、前回は「5.追加性の実証」を参照し、ICVCMのCCPsと比較したものです。
さて、この規格は6.4条メカニズム の規則、様式、手順(RMPs)の附属VB(方法論)で言及される要求事項の適用に関する規格の作成を、パリ協定の締約国会議(CMA)から要請されたものなので、全て附属VBに適合的なものとなっています。
その、RMPsはこちら。
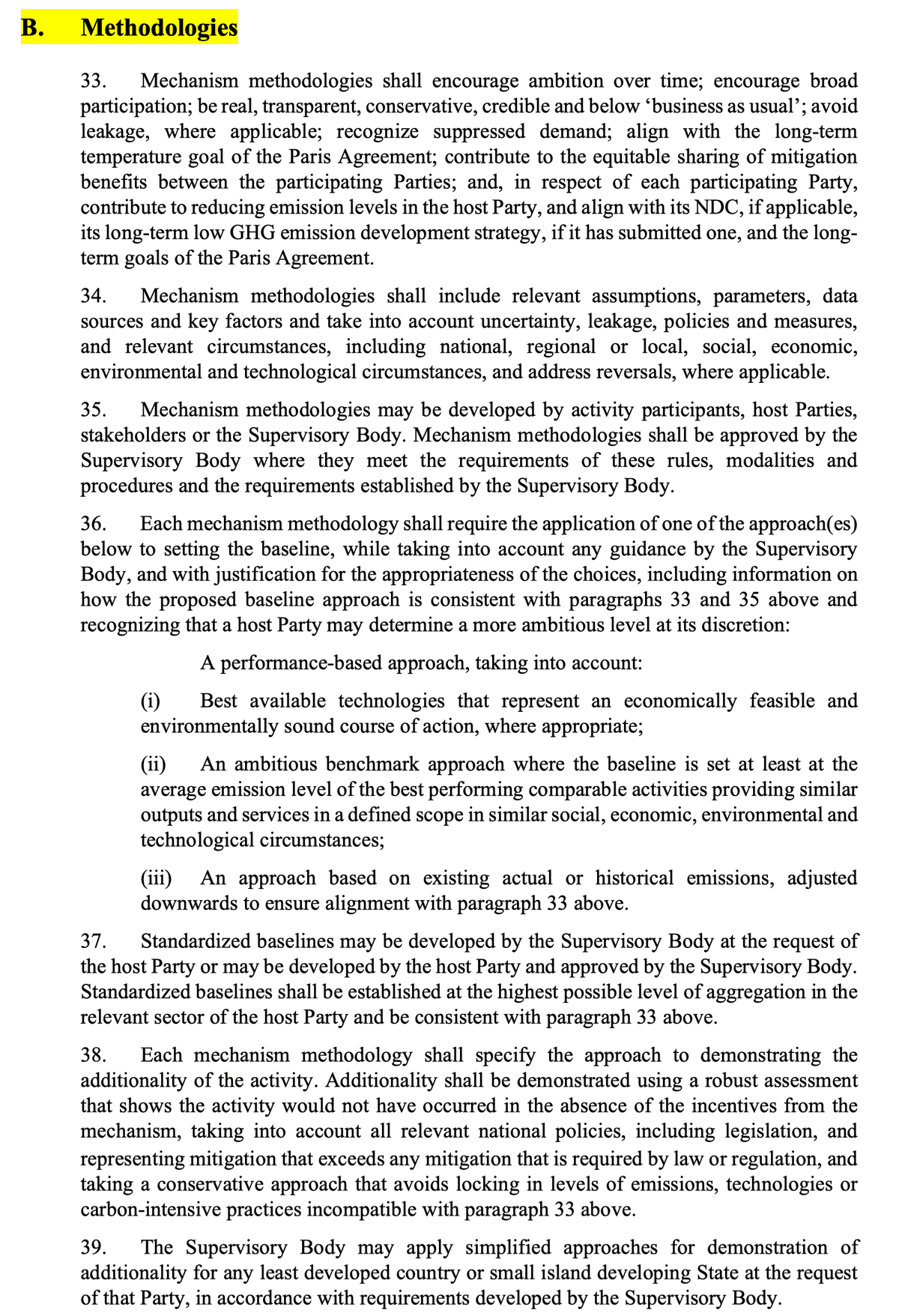
これを実施ルールに落とし込んだのが、「6条4項メカニズム方法論の開発・評価基準」と言うわけです。施行令と施行規則のような関係でしょうか。その上位のパリ協定は、法律ですね。
皆さんは方法論を作る側で無く、それに基づいたプロジェクトを実施し、クレジットを創生する側ですから、詳しく知っておく必要はありません。(方法論に基づけば満足するような修正を、スキームオーナーが行いますから)
ざっくりまとめると、こんな感じ。

目新しいものは無く、今まで一般的に考えられていた定義と同じではありますが、大御所が発表したこと、デファクトで無くデジュールになったことに意味があります。
前回の「追加性」と同様、スキームオーナーは既存の方法論を適合させてくるでしょうから、これからクレジットを創生する場合、どのような準備・対応をしておけばよいのかを、予測して動くことが肝要です。
詳しく知っておく必要はないと言いましたが、何が書かれているかを、もう少し具体的に紹介しておきますね。

恐らく、今後はネットゼロへ向けて、各国がNDC達成に本腰を入れてくること、ウォッシュに対する批判がさらに高まることを考慮すると、「4.ホスト国の政策や長期目標との整合性」及び「6.持続可能な開発への貢献」に対して最大限の配慮が求められるかと思います。
ということで、「高品質なクレジットはどうあるべきか」について考えてきましたが、いかがだったでしょうか。
前回の追加性と併せて、各ボラクレの方法論やICVCMのCCPsの改訂が行われ、内容が明らかになってくると思います。
2025年も、引き続き、クレジット界隈の情報を継続的にウォッチし、タイムリーにお届けしたいと思います。よろしくお願いします。

いいなと思ったら応援しよう!

