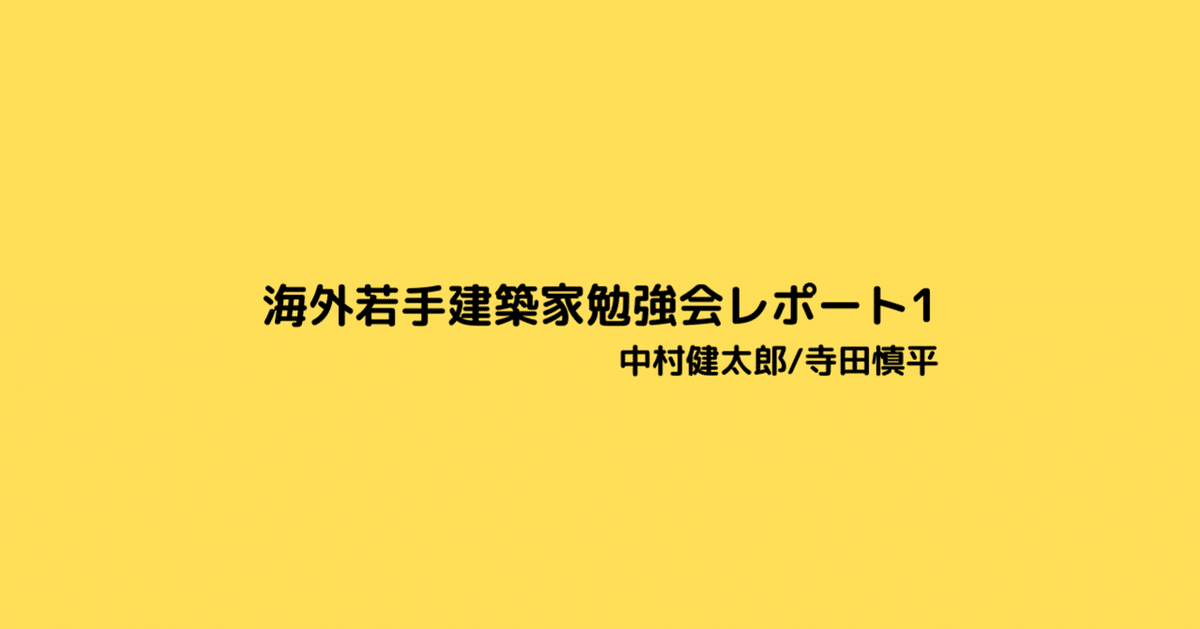
海外若手建築家勉強会レポート1
筆者:中村健太郎
メニカンではときおり、案のエスキスや相互の作品批評のかたちで、ちょっとした勉強会が立ち上がることがあります。活動アーカイブの意味もこめて、先日行った「海外若手建築家勉強会(仮)」の様子をレポートしようと思います。
それぞれが注目している海外建築家の紹介を通じて、いまの建築界の動向についての見立てを共有しよう──という目論見のこの勉強会は、僕と寺田さん(メニカン)のやりとりから企画され、GROUPを主宰する大村高広さんにお声掛けすることで形になりました。勉強会は少人数の参加者とともにzoomで行いました。
初回の担当は寺田さんです。5組の海外建築家をセレクトしてくれました。いずれも、作品の「イメージ」の扱い方に特徴のある面々です。TREES studio(NY, US), David Klemmer (Zurich, CH), Faye Toogood(London, UK), Charlotte Taylor (London, UK), Six N. Five (Barcelona, Spain)。 彼らのように建築のイメージを発表しつづける戦略は、ここ数年でとみに増加しているように思えます。以下、寺田さんのメモとともに5組の建築家を紹介します。
TREES STUDIO(NY, US)
TREES STUDIOはNYの建築事務所(らしい)。「らしい」というのも実作らしいものは見当たらないし、インターネット上でも確かな情報がみつからない。よって彼のプロジェクトの全貌を掴むことは非常に困難だが、instagramの投稿を見ていると、gifになってドアが動くある種の冗談のような図面、パースペクティブが効いた室内をトレースしたような平面図、vaporwaveの世界観にも近しいざっくりとしたレンダリング、図面の添景をそのまま三次元化したような模型などなど、新しい建築表現が満載で、非常に魅力的である。
他にもOlgiatiからの影響がありそうだったり、zineの製作なんかも手がけていたり、いくつかの視点から掘り下げられそうな建築家である。 (寺田)
David Klemmer(Zurich, CH)
David Klemmerはもともとデジタル・フォトグラファー、いわゆるレンダラーとしてキャリアを始めているようで、Olgiatiのコンペのイメージや、その他スイスやイギリスの建築家の建築イメージを手がけている。その後自身のスタジオを持ち、設計もしているようだが、実作はまだないかもしれない。
レンダリングのテイストはフォトリアリスティックでもあり、建築模型のように抽象的でもあり、リアルとヴァーチャルのあいだを狙っているような感じがある。(寺田)
Faye Toogood(London, UK)
Faye Toogoodはロンドンのデザイナー。家具やインテリアのプロジェクトを手がけながら、姉妹のEricaとともにクロージングラインも展開している。
模型をそのまま拡大したような家具、レンダリングからそのまま飛び出してきたかのようなインテリア。さまざまな分野を横断するという行為は、リアルとヴァーチャルの境界も、曖昧にしているのかもしれない。(寺田)
Charlotte Taylor (London, UK)
Charlotte Taylorはロンドンの3Dデザイナー。興味深いのは、自身が手がけたレンダリングの添景として使われている特徴的な家具を、自宅にも製作し、その写真をインスタグラムで展開しているところ。(寺田)
Six N. Five (Barcelona, Spain)
フォトリアリスティックにレンダリングができるようになってから、一度手作り感のあるイメージが流行し、その後、リアルとヴァーチャルのあいだのような、レンダリングでしか実現できない質感をイメージに求める時代になりつつあるような気がする。
Six N. Five はRicardo Boffilとのコラボレーションから知った。こうしてレンダリングとして、建築を実現するのもまた、1つのアンビルドの在り方なのだと感じている。(寺田)
ディスカッションでは、こうした積極的な「イメージ」提案の戦略についての議論が交わされました。スイスの建築家ヴァレリオ・オルジアティのドローイングによる建築表現や、ドイツの現代美術家作家トーマス・デマンドによる写真をメディウムとする制作手法の影響について。またレンダリングの高度化・高速化が可能にしたデジタル技術によるコラージュの質感に関する意見交換から、果てアメリカ東海岸で不動産に投資マネーを呼び込むためのイメージづくりまで。話題は多岐に及びました。
議論をふりかえると、近年の「建築のイメージ」にまつわる議論は、暫定的に次のようにまとめられそうです。
1. 現代のアンビルドな「建築のイメージ」は、過去の”アンビルド作家たち”の試みと、どこが違うのか。
2. 現代の「建築のイメージ」は、どのような技術や環境に支えられているのか。
3. 現代の「建築のイメージ」は、現代社会のどのような需要を喚起しているのか。
個人的には、「建築のイメージ」にまつわる議論は、まだまだ深められそうだと感じています。引き続き勉強会を通して議論を深めていければ、またどこかで成果をまとめて発表できると良いと思っています。
最後に、ETHでも教鞭をとるスイスの建築家デュオMade Inが、京都工芸繊維大学で行ったワークショップの記録映像のなかで述べた発言を引用しておきます。
「昨今ではイラストレーション(図解)に重きを置いた表現ばかり制作されていますが、想像力を制限してしまうので悲しいことだと思います。ミース・ファン・デル・ローエは、フリードリッヒ街のオフィスビルプロジェクトで街を粘土模型で制作し、ビルをガラス模型で表現しました。これはイラストレーション(図解)からはかけ離れています。私たちはイメージを解読しなければなりません。」
いいなと思ったら応援しよう!

