
デザイン会社が全社横断で取り組む「知識創造とデザインの民主化」
こんにちは。株式会社コンセントの嶋田です。
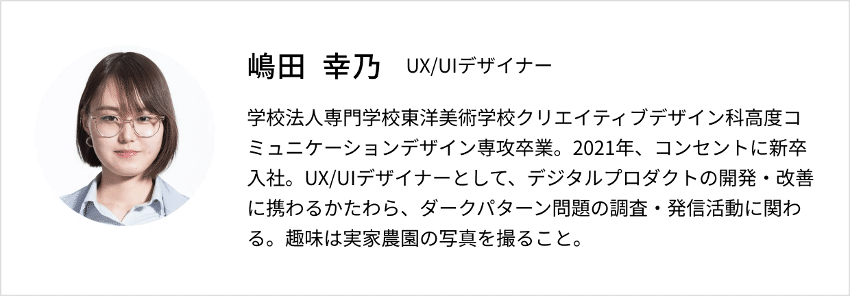
2024年10月13日(日)、日本最大級のデザインカンファレンス「Designship 2024」スポンサーセッション(オープンステージ)に登壇させていただきました。この記事ではスポンサーセッションでお話しした内容の一部をご紹介します。

私自身、2日間にわたって行われたさまざまなセッションや参加者の方々とのやりとりからは、多くの学びや気づきを得ることができました。私の発表も、誰かの学びや気づきのきっかけになれればうれしいです。
「知識創造とデザインの民主化」とは

そもそもタイトルにある「知識創造とデザインの民主化」 とは何か。それはコンセントの「デザイン知識を生産する組織でありたい」という思いから生まれた取り組みです。

多くの企業・組織の支援をさせていただいているコンセントには、その関わりの中から得たさまざまなナレッジの蓄積があります。
「ナレッジは、ただもっているだけでは勿体無い」
「それらを活かして開発したデザイン技術や知識を社会のためにひらきたい」
「ひいては、誰もがデザインできる社会の実現につなげていきたい」
と私たちは考えています。「知識創造とデザインの民主化」はそうした思いのもと、それぞれ30名程度が在籍する複数の部署を横断して全社で取り組む活動です。


「知識創造とデザインの民主化」の中にも、複数のテーマがあります。メンバーは思い思いの研究テーマを立てて活動しています。
ダークパターン問題に対する活動
私が携わる「ダークパターン問題」の調査・発信活動も、そのひとつです。
ダークパターンとは、アプリやウェブサービスなどのUIにおいて、消費者を騙したり操ったりするなどして、企業などにとって都合の良い行動を取るようにしむける手法です。ダークパターンによる消費者被害は深刻で、近年はメディアでも多く取り上げられるようになってきました。

「ダークパターン問題」の調査・発信活動に取り組みはじめたのは、弊社代表の長谷川敦士がダークパターンの研究を行っていたことがきっかけです。

つくり手の責任としてダークパターンを理解すること、そしてダークパターンの被害を防ぐための活動を行っていくべきだと考え、継続的に調査・発信活動をするテーマとしました。
コンセントにダークパターン問題の調査・発信活動のためのチームが立ち上がったのが2022年。私は2023年から、この活動に参加しています。
ダークパターンをテーマに取り組むチームでは、活動の目的を「ダークパターンによる被害を減らすこと」としています。そのためにはまず、つくり手、企業、消費者、すべての人たちへの「ダークパターンに対する認知向上」が必要であると考え、活動をしてきました。

主な活動としては、ダークパターンに関する正しい情報を発信するために、国内外の最新の動向調査を日常的に行ったり、

ECサイトやアプリでの購入経験者を対象に、ダークパターンへの意識調査を行い、その結果をまとめた『ダークパターンレポート2023』を発行。ダークパターンを知ってもらう機会をつくったり、
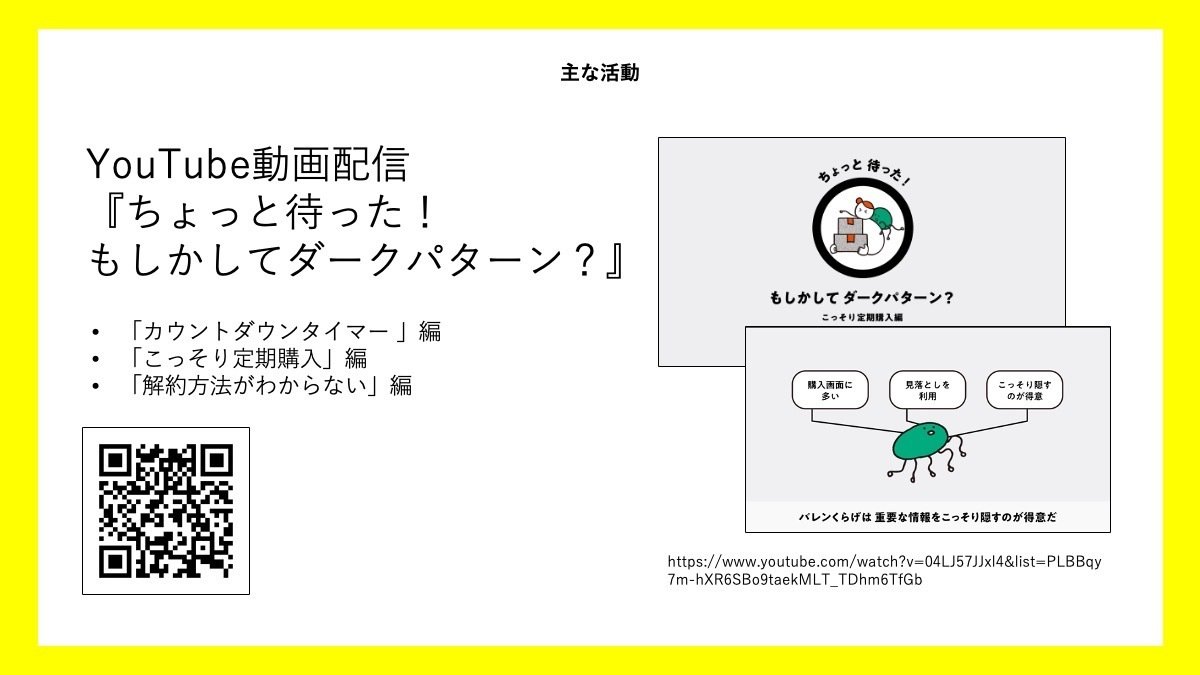
コンセントの公式YouTubeチャンネルで、ダークパターンの解説動画シリーズを発信したり、

もちろん社内に対しても、世の中にさまざまな制作物を公開していくデザイン会社の責任としてダークパターンへの理解を深める機会をつくったりと、さまざまな活動を行ってきました。
このような取り組みは、ダークパターン問題に関するメディアでの連載や報道等への監修協力などにも活動を広げていくことにつながっていきました。当初の目標としていた「ダークパターンの認知向上」に寄与できた部分ではないかと思います。

社内の知見を深め、社会に発信できる理由

このように社内の知見を深め、社会に発信できるのは「知識創造とデザインの民主化」が全社横断の取り組みだからこそです。
会社公式・公認の取り組みであるため、活動時間が確保しやすかったり、成果が出るまでに時間がかかるテーマもある中で、短期的な成果を問わない評価の仕組みがあったりすることで、メンバーは無理のない範囲で安心して取り組むことができています。

また私自身が活動を前向きに続けられているのは、「知識創造とデザインの民主化」という取り組み自体が、日々のお仕事を楽しむ視点を与えてくれるものだからです。

自分ひとりでは出会えない物事に触れる機会や、ひとつのことを深く考える時間が、ついつい目先の物事に気を取られて狭まりがちな視野や凝り固まってしまう思考をほぐしてくれることで、フレッシュな気持ち・視点で仕事に臨むことができています。

まとめると、自身の関心や探究心を活かし、楽しみながらも、社会に貢献できる取り組みが「知識創造とデザインの民主化」であると私は思います。
楽しいと思う気持ちは、また次の楽しいを呼び寄せてくれます。コンセントはこれからも「知識創造とデザインの民主化」の取り組みを、楽しく、そして長く続けていきます。
「知識創造とデザインの民主化」以外にも、コンセントでは全社横断で行っている取り組みがいくつかあります。こうした取り組みにご興味をおもちの方は、ぜひ「イニシアチブ組織」の記事も合わせてご覧ください。
コンセントのダークパターン対策への取り組み
以上が、Designshipでの発表でした。
ここからはセッション内では詳しくお伝えしきれなかったダークパターン問題にまつわるコンセントの直近の活動をご紹介します。

Designship直前には、第2弾となるダークパターンの調査レポート『ダークパターンレポート2024』を発表しました。一般消費者を対象にした第1弾とは異なり、ダークパターン対策に取り組む企業に所属するビジネスパーソンを対象としたインタビュー調査レポートです。企業はどうすれば「ダークパターンの無自覚な使用」を防げるのか、その論点を考察しました。
また9月末には一般社団法人ダークパターン対策協会の理事の一人に代表の長谷川が就任、コンセントも設立時社員、賛同企業として参画しています。
数年前まで日本ではその存在さえあまり知られていなかったダークパターン。いち早くダークパターン研究に取り組み、社会に問題提起してきたコンセントの活動が、少しずつ波及している実感があります。
Designshipでも、「ダークパターンに関心がある」「社内でダークパターンの対策をしていきたい」と話す方が多くいらっしゃいました。これからも、 ダークパターン問題のさらなる顕在化や認知・理解度の向上に、そしてダークパターンによる被害を減らすことに、貢献していけたらと考えています。
