
『ワンダリング・メモリア』 この映画は二人で撮られていない
『ワンダリング・メモリア』(2024年/金内健樹)
【あらすじ】
昔住んでいた団地にふたりで行く。
一先ず、この愛おしいホラー映画がたった二人で撮られたという事実について語らなくてはならない。エンドクレジットを埋め尽くす金内健樹と倉里晴の名前は、そういったアティテュードの表明に他ならない。二人だけの人物で物語られる物語を、二人だけで撮る。二人で表象した世界に、他の何者も介入させない。事ここにおいて、二人という数字には過剰なロマンティークもなければ、閉塞的なおそれもない。単にそれがアンセムとして、結果的に作品の強度を補強していることは明確である。
わたしも、俳優と二人で映画を撮影したことは何度かある(日本ホラー映画大賞に応募した拙作にも、そういった箇所がある)。個人的には、コミュニケーションの効率と速度、あらゆる利便性に重きを置いた際に、二人でサクサク撮ることが楽だと感じることがしばしばある(自主映画で最も多い理由は人件費削減だが)。同時に、人員が必要であったと認識する場面ももちろんある。そこをどう乗り越えるかは、俳優と自分との信頼関係に他ならない。そう、信頼し合っていなければ、二人で映画を作るという行為はかなり難儀だ。
『ワンダリング・メモリア』の金内健樹と倉里晴は、恐らく、わたしたちが想定している以上に信頼し合っているはずだ。金内健樹が判断したカメラの配置場所は、漏れなくどれも的確である。構図も含めて、あらゆるショットが驚くほどうまい(なぜかシャッタースピードの調整だけされていなかったが、それも意図的とも思える異様さ、空間の歪みみたいなものを演出できていて良い)。金内の潜在的な映画を撮るという運動神経の良さと、倉里晴が備えるあどけなさ、イノセントな雰囲気を醸す演技が、絶妙な手触りを形成している。金内もまた、過剰に倉里晴の魅力に欲求することなく、倉里ちゃんは倉里ちゃん自身が最高なんだよ、とでも言いたげかのように、他では見たことがない彼女の演出に成功している。そこに信頼が読み取れる。倉里晴自身、金内を信頼していなければ、姉妹編とも呼べる『スーパームーンフェイズ・ウィッシュ』に出演することもなかっただろう(日本ホラー映画大賞入選を祈願したおまじないとしての短編作品。音楽がクソかっこいい)。
作品を鑑賞しながら、確かにこの二人ならば、一本のホラー映画を二人だけで撮ることも可能だろうという確信があり、感心と感銘を受けた。
二人だけで映画を撮るという行為は、時として、ファインダーを覗くことなくカメラを回すことを意味する。二人が画面に映っている時間、そこでカメラのファインダーを覗く者は当然存在しない。恐らく、構図を確認した末に金内健樹が録画ボタンを押して、そのまま芝居の定位置についているはずだ。もしくは、ギミックやその操作が必要な場合、操作を金内が行い、録画ボタンを押すのは倉里晴かもしれない。
『ワンダリング・メモリア』の撮影現場には二人しかいないということを前提に、この映画には、二人のことを撮影する「第三の撮影者」が存在している時間が発生している。
二人で撮られた映画、という事実が明確になればなるほどに、ではこの瞬間、この映像を記録したのは一体誰なのかという、ざわめきにも似た不安が感じられる。もちろん、その撮影手法は前述の通りである。
しかし、そうであっても、だ。そうであっても、この二人をファインダー越しに覗く「誰か」の眼差しが感じられる。
「第三の撮影者」は、静かに二人のことを見つめ続けながら、宙吊りの状態のまま着地することなく、この作品を漂っている。それをたとえば「幽霊」と呼んでしまうことにためらいはない。最終的に、クライマックスで幽霊譚らしい結末を迎える本作は、恐怖シーン一点突破型に思われがちかもしれないが、この映画が表象するおそろしさとは、むしろクライマックスまでの時間にこそ刻印されている。
何もおそろしいものは映ってはいない。けれども、時折わたしたちは、二人を見つめる「背中」を感じる。「視線」を感じる。
唐突にスピッツの『ロビンソン』から引用するが「誰もさわれない/ふたりだけの国」が確かにそこに映し出されているにも関わらず、絶対にこれは「ふたりだけの国」ではないと確信しながら鑑賞してしまう居心地の悪さがある。
そういった「第三の存在」がふたりに触れようとするその瞬間まで、「きみたちは決して二人きりではない」と宣告される魔の時間が引き伸ばされる。恐怖そのものと対峙することよりも、その予感、不安、気配に対して着眼された、極めてミニマルかつ真摯な恐怖論が、ここにはある。
本作は、ひとりであること/二人きりであることを強調することによって、逆説的に「第三の存在」の印象が濃厚になってくる。
記録されることもクレジットされることもない「第三の存在」は、しかし確かにこの映画に「存在」していると信じて疑わない。
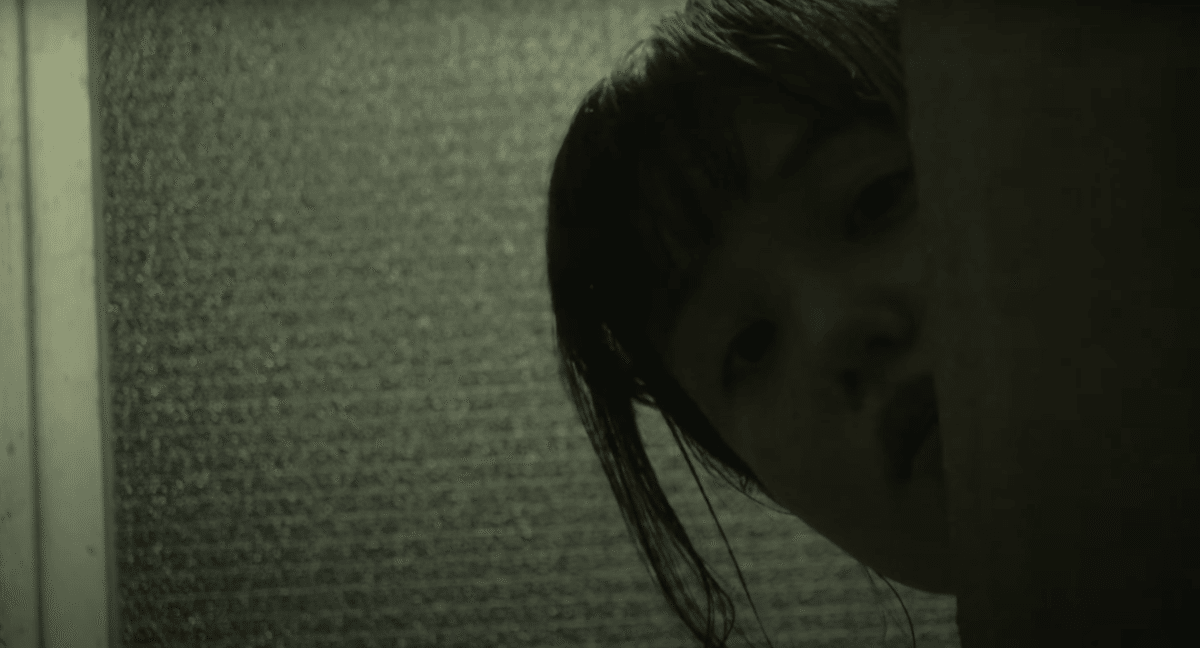
劇中においてハルカは、はっきりとは明言できないほどに不明瞭な「気配」を感じ続けている。冒頭でかつての住まいだった団地を彼女は見つめるが、それは彼女がそう感じているだけであって、本質的には団地から彼女が見つめられている(そのように撮っている)。彼女が偶然団地の前を通ったのではなく、場所の磁力に引き寄せられて彼女が到着したと考える方が、違和感がない。こうして、最初から"魔"はハルカを見つめ続けているし、ハルカもそのことに無意識的に気付いている(ような演技を倉里晴はしていたと思う)。
魔と接触した者が、その場所の記憶を他者に伝聞することによって、「ひとり」から「ふたり」へと世界を拡張していく作法もまた、怪談的なマナーを遵守していると感じる。
二人だけで歩く夏の夜道の美しさを、金内健樹は理解した上で撮っているものの、ここではやはりロマンスやノスタルジー以前に、深淵へと導かれていく感覚が強く演出されている。何気ない形で、後戻りできない状態にまで接近していく感覚、それを当事者たちは「気づくこともできない」。そして観客もまた、二人と同じ目線で場所の魔を垣間見ていくわけだが、(ホラーというジャンルであることを度外視にしても)ハッピーなことが起こるはずがない、という空気が正しく演出されているため、その魔から視線を逸らすことができない。
夏の夜の、ほんの少しだけ涼しい時間。ひとりだと怖いけど、二人なら怖くないと思える時間。金内健樹が撮る夏の夜には、夏のリリカルな刹那性すら呼び起こす美しさが真空パックされている。本当にこの人は夏が好きなんだなと感じられる。
同時に、そう思いたいだけだろと、首元に刃物を突きつけられるような残酷さが、夏の夜にはある。そう思いたいだけで、夏の夜だって暑苦しいし、汗も止まらない。握った恋人の手は手汗で濡れている。夏の夜空は明るいね、という幻想が届かない、決して光が届かない闇は、どんな季節の夜にも存在している。団地の懐かしさよりも、湿った空気とカビ臭さ、虫の死骸のむごたらしさを感じながら奥へと進む。誰のために点灯しているのか分からない電灯だけが、その場所を照らし続けている。時計の針が止まった場所を訪れるということは、それだけの覚悟が必要なことである。
夏の夜は美しい/夏の夜は恐ろしい
この世界のままならさや不可解さ、そして美しさを信じている人だけが、こういう映画を撮れるのだと証明しているようだ。
静かに二人を見つめ続ける「第三の存在」、それはメタ的な視点で指摘してしまえば、すなわち「カメラ」という存在そのものの擬似幽霊性を表すことができる。
けれども、よりメタに捉えれば、二人を見つめていて、二人からは見つめられない幽霊のような存在というのは、まさしく「観客」そのものである。
わたしたちは、「第三の存在」を感じながら、自分達が二人にとっての背後霊と化していることを失念してしまっている。あるいは、二人を見つめるあなたの背中、を背後から見つめる「誰か」もまた、存在しているのかもしれない。「見る/見られる」の関係性の延長線上にあるのは、そういった恐怖と不安でしかない。誰かを見ているあなたもまた、誰かに見られている。それは今、この文章を読んでいるこの時、あなたが今いる場所で、誰かがあなたを見つめているかもしれない。絶対にそんなことはない、と、あなたは言い切れるだろうか。自分が夏の夜の住人であると表明できる人こそ、いつ闇に向かって歩んでいるのか気づくこともできないだろう。闇はどこにでも、すぐ隣にもある。恋人と些細な会話をしている時間でさえも、恋人と手を握っている時間でさえも、決して安全ではない。世界とは、そうやってできている。
ここからは私的な感想となるが、本作は金内健樹がホラー映画を撮った、ということよりも、金内健樹が女優を撮った、という意味において大変興味深い。
金内健樹は"女優"に対して、(たとえば私のように)恐怖にも似たフェティッシュを備えていないだろう。極めて楽天的な眼差しをもってして、演出を施し、カメラを向けているのが理解できる。きれいに撮りたいとか、こわく撮りたいとか、女優に対してそのような自意識を抑制できている。被写体への恐怖も憎悪もなく、素材として、その魅力を自在に撮れているのである。映画作家の知性とは、そういうものでなくてはならない。
だから、金内健樹が撮った倉里晴の自然なまでの「素材そのものとしての魅力」は、間違いなく本作の強固な要素のひとつとなっている。
ノスタルジー的、あるいはオタク的な理想としてのヒロイン(キャラクターとしてカリカチュアされた女性)を表象しても、作法としては健全であっただろう。なんなら、その方が、あまりにも不釣り合いなカップルのバランスも取れていたかもしれない(日本ホラー映画大賞において、審査員長の清水崇は「『ワンダリング・メモリア』の男役が無理」と述べていたが、これはもはや金内健樹を知る者としては賛辞である)。
しかし、のほほんとした雰囲気の女性と、挙動がおかしな男性、そのアンバランスなバランス性もまた、この映画の特異な良さなのだと感じる。

最後に、わたしが個人的に最も好きだったシーンについて書き留めておく。
団地からの帰路の途中、深夜で人の気配がないスーパーマーケットへ二人が入る。買い物を済ませて、二人は退店する。別に何も起こらない。もしくは、こんなシーンがなくても成立するかもしれない。しかし、このシーンは定点ワンショットで、40秒もある。
必要なものだけを隙なく敷き詰めた作品よりも、わたしは「不必要な/無駄な時間を愛おしく思える」作品の方が好きだ。なにも該当シーンを無駄だといいたいわけではない。映画には、ああいった何の変哲もない、意味もない、そういう時間をこそ記録して表現する豊かさがゆるされている。
あのショットをゲリラ的に二人で撮ったのかというメタ的な視点なんか放棄して、素直にあの瞬間の虜になったことを表明したい。あの瞬間に、最も夏の夜の時間を感じられた。それはデヴィッド・ロバート・ミッチェル作品に流れているような、アメリカ郊外の時間の流れのような、ゆったりとした、「だれもさわれない/ふたりだけの国」としか言いようのない時間である。
あの瞬間の二人を見つめているのが、たとえ「第三の存在」だとしても、ちょっとあの瞬間だけは、あの二人にあこがれていたと思う。
追伸:サイゼリヤで金内健樹さんとダベっていた時に「感想書いてくれよ!」と懇願され、ええーとか言いつつ、書いておきたかったので書きました。そんな金内健樹さんは、拙作『絶縁』では音楽として楽曲製作していただいております。お見知り置きを。
いいなと思ったら応援しよう!

