
色名の由来も覚えられる「和の伝統色カルタ」
紅花の花弁から採取した植物染料。
くれない色ともいう。
「呉」の「藍」が変化したもので、呉国(中国)伝来の色。
紅色はどれでしょう?
「はい!」「はーい、とったー!」
歓声と共に笑顔が広がります。

和の伝統色カルタ
紅色、萌黄色、鴇色、鶯色、藤色、鼠色など、
たくさんの色名がありますが、これらの色名にはどのような由来があるのでしょうか?
色名の由来が読み札になっているので、
楽しみにながら学べる教材がこちらの「和の伝統色カラーカード」です。
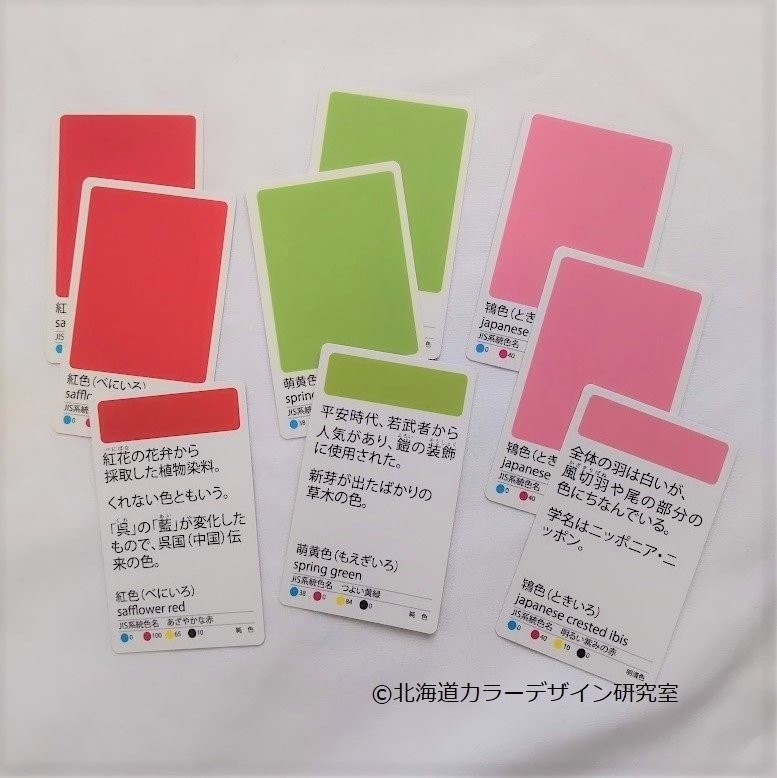
ゲーム性を高めるために、取り札が2枚あります。
2~3名の少人数から7~8名までのグループでも楽しめる事ができます。場合によっては1人で2枚取りする方も。
色の神経衰弱ゲーム
さらにこの取り札が2枚になっていることで、別のゲームも楽しめます。
「色合わせゲーム(色の神経衰弱ゲーム)」です。
トランプの神経衰弱ゲームと同じ要領で、同じ色を合わせていきます。
私がこれまで行ってきたワークショップや体験型セミナーでの声を聞くと、
みなさん「トランプのマークよりも色を覚えるのは難しい」と言います。
鴇色と珊瑚色など似たような色があり、
記憶力が試されるゲームでいつも盛り上がります!

収納されている色名は、
紅色、黄丹色、蒲公英色、萌黄色、常盤色、青緑、青、瑠璃色、江戸紫、牡丹色、珊瑚色、藤色、鴇色、青磁色、団十郎茶、朽葉色、鶯色、鉄色、藍色、茄子紺、鼠色。以上21色。
以上の色名の中にも、すでに知らない色名があるのでは?
色彩学の勉強、色彩センス向上、記憶力向上が期待され、
アナログのグループワークによるコミュニケーションにも役立ちます。
教材開発の経緯
私がこの教材を作ったのは今から15年くらい前です。
北海道内の社会福祉協議会様に講演やセミナーで呼ばれることが多く、
「ボランティア活動をする際のワークがしたい」
「地域のコミュニケーションを向上させたい」
「色で幅広い人が楽しめる内容にしてほしい」などの依頼があり、
【和の伝統色カラーカード】を作りました。
最初は手作りで、厚紙に折り紙を貼り付けて色合わせゲームとして試作。
見た目は少々雑でしたが、実際にワークを行ってみると、
これがもう!大盛り上がりでした!!
ということで、しっかり作ろう!と思い、
色合わせゲームだけでなく、色名の由来を読み札にしたカルタもできるようにしました。
せっかくなので、情報をさらに盛り込んで
CMYK値とJIS系統色名、色彩学の現況が出来るように工夫しました。

この教材によって、色彩を楽しみ、コミュニケーションが生まれ、
笑顔が連鎖していくので、「スマイル色サプリ(R)」と名付けました。
おかげ様でたくさんの方に喜んでもらっています。
ありがとうございます。
北海道カラーデザイン研究室
