
【歴史夜話#7】ミセス一豊の小袖
山内一豊と言えば、キュリー夫人の旦那と並んで有名な、奥さんの付き人ですね。
「内助の功」は今や死語ですが、一豊夫人は様々な機転で夫を助け、目立った武功がない夫を大名にまで押し上げました。
そういった視点ではなく、女性の活動に制限があった時代に、才知のある女性はどうやって自分を表現したのか? その点から、ミセス一豊の服飾デザインなどを見てみたいと思います。

へそくりの金額
やはり山内家を語るにあたって、「馬」の話は避けて通れない。
一豊夫人の名は、「千代」説と「まつ」説がある。一豊と結婚したのは、14、5歳のときで、一豊がロリコンだったわけではなく、戦国時代の標準だった。
夫である一豊は、千代(「功名が辻」ではこの名を採用)と結婚した頃の朝倉氏との戦いで、顔に矢が刺さる重症を負いながらも敵将を討ち取った。
結婚前後で張り切っていたのだろう。これが唯一と言っていい武勇伝。
有名な馬の話は、結婚から7、8年経った天正9年の信長主催の馬揃えでのこと。信長が京都を制圧し、軍事パレードでその力を誇示したセレモニーに向けて、夫のために高額な名馬を購入した。
昭和の頃は自家用車がステータスだったが、戦国時代は馬。
千代が購入のためにへそくりをはたいたのは、関東・東北の在来馬で栗毛だった。
「鏡筥(かがみばこ)」の底に隠してあった10両を使ったので、馬は「鏡栗毛」と呼ばれた。
この当時の10両は、だいたい150万~200万円くらい。持参金だったとも言われる。
200万円台で買える車だと、トヨタの「ヤリス」とかホンダの「フィット」だから高級車というより大衆車。
けど生産性の低い戦国時代だと、ベンツとかロールス・ロイスを、旦那のためにポン、と買ってあげたイメージなのかな。

ご神体となった枡(ます)
結婚時代の清貧エピソードとして、千代は枡を裏返してまな板代わりに使っていた。
そのため、枡の底には無数の傷があったと言われる。
この枡は高知の藤並神社で、鏡とともにご神体として治められていたが、昭和20年の空襲で焼けてしまった。
結婚当初の苦労話としては、藤吉郎と呼ばれていた秀吉がねね(高台院)と恋愛結婚した当時と似ている。
このふたりの場合は、藤吉郎の身分が低かったので反対に合い、それを押し切ったので、藁と薄縁を敷いて行った質素な結婚式だったという。
こうした類似性からか、千代(見性院)は淀殿よりも正妻であるねねの方に、シンパシーを感じていたようだ。
これがのちに、一豊が大化けする伏線となる。

「未読」の重み
一豊と千代の仲は睦まじく、天正8年(1580年)には、ひとり娘の与祢(よね)が生まれた。
しかし思わぬ不幸に、ふたりは見舞われる。
天正13年(1586年)には、一豊は長浜城主として2万石を領していた。
その年1月に、天正大地震が一帯を襲う。幸い一豊も千代も罹災は免れたが、娘の与祢をこの地震で喪ってしまう。
子どもを喪った悲しみに暮れる千代は、与祢姫の供養のための妙心寺参りの門前で、男の捨て子を拾ってわが子として育てた。
この子「拾(ひろい)」は、山内家の家督を継ぐことはなく、のちに妙心寺で修行して湘南宗化と号した。
慶長5年(1600年)に、関ヶ原の戦いの前哨戦である会津征伐に従軍していた一豊に、千代から3通の手紙が届く。
一通は千代からの手紙。もう一通は未開封の大阪城からの書状。この二通は文箱に納められていた。
そして最後の一通は、使者の傘の緒に織り込んだ千代からの密書。
文箱の中の千代からの手紙には、一豊に対して「ねねが推していた」家康への忠誠を貫くよう書かれていた。さらに大阪城からの未読メールは、石田三成からの味方するよう督促した書状。
笠の緒に織り込んだ密書には、千代から一豊への指示がしたためられていた。
一豊は軍事的な能力も乏しく、吏僚としての巧妙な身過ぎもできなかったが、見栄を張らずに妻の言うことに耳を傾ける、という究極の才能があったのだ。
千代の指示に従い、一豊は大阪からの手紙を「未読」の状態で家康に差し出した。
この演出で、家康に対する一豊の印象は爆上がりする。そして戦後の論功行賞で土佐一国を賜るのだ。
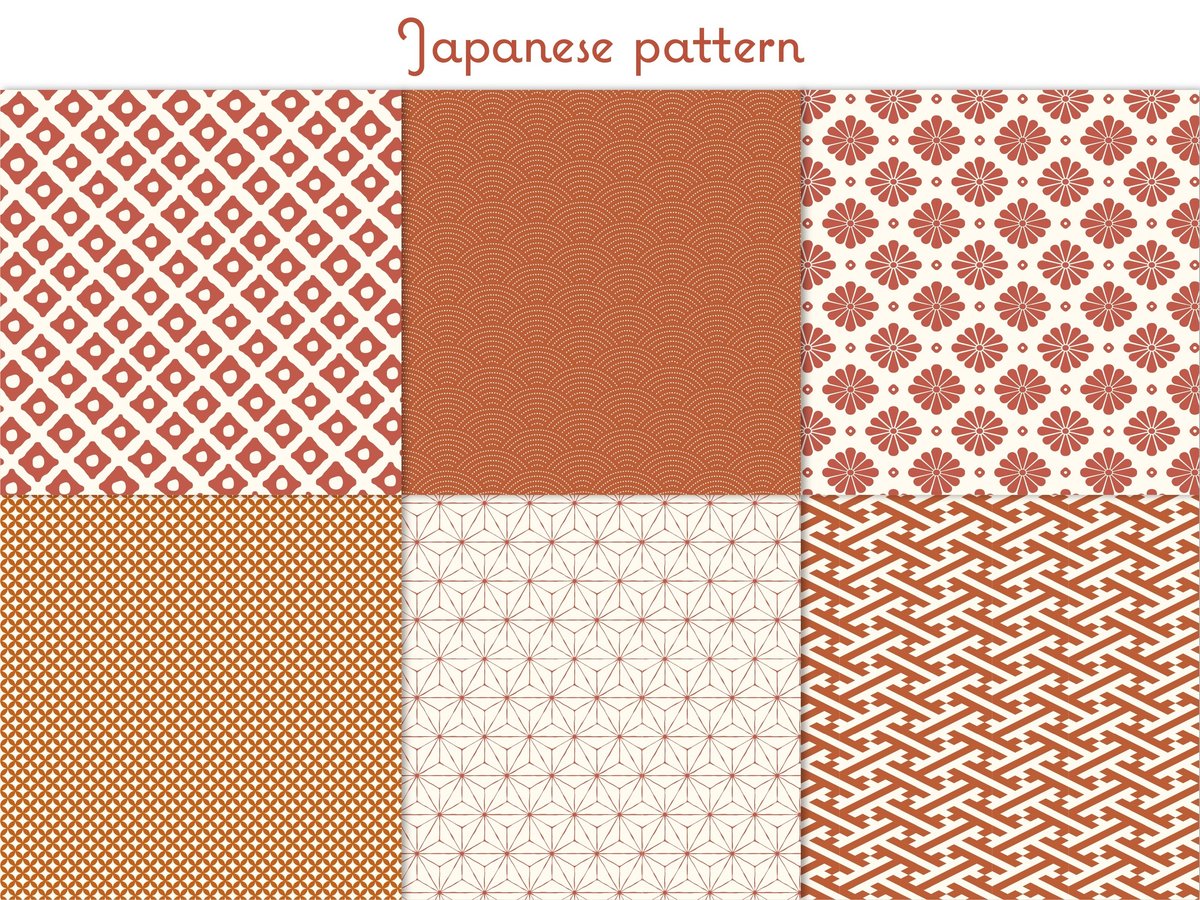
パッチワークの小袖
小袖とは、袖口を狭くして袖下を丸く仕立てるのが特徴的な和服。
長浜時代に、千代は唐織りの端切れを買い集めて、パッチワークの小袖を仕立て、北政所(秀吉正室ねね)に献上したりしている。
秀吉はこの『作品』をいたく気に入り、聚楽第に展示して時の後陽成天皇にも披見した。
このエピソードは『稿本見性院記』にのみ記述があり、どの程度事実を反映しているかわからない。
しかしこれが実は、出家後に『見性院』と院号を称した、千代の本質ではなかったか、と思う。
アーティスティックな才能に恵まれながら、中世のしきたりや習俗でその才を表現する場が限られていた女性。
今ならファッションデザイナーとして、その才能を思う存分発揮できただろう。あるいはマンガ家、脚本家、小説家などの分野で活躍していたかもしれない。
はち切れんばかりの才の片鱗が、歴史の断片のすき間から、輝いているように感じるのだ。
夫の一豊が亡くなった(慶長10年(1605年))あと、千代(見性院)は後事を一豊の弟とその子に託して土佐を去ります。
そして京都の妙心寺近くに移り、あの拾(湘南宗化)との再会を果たすのです。
晩年は、古今和歌集や徒然草などを読んで過ごしたそうです。やはり文学の才もあったのでしょうね。
最後は、湘南宗化に看取られてその生涯を終えたとのこと。
女性がその才能を発揮する機会は、現代ほどはなかったでしょう。しかしそんな状況でも、才能の光が垣間見える生涯ではなかったか、と思います。
