
【初心者も】使役動詞のhaveがキーポイント
こちらの記事は、「英語をきちんと話せる様にしたい」「英語脳を作りたい」と日々悩んでいる方に向けた記事になっております。
手っ取り早く結論を知りたい方は、「まとめ」まで飛んでみてください。
動詞を制しろ

英語を話す上で、動詞をどう使いこなすかが非常に重要です。しかし、「動詞の「意味」を覚えるだけ」は時間の無駄になりかねません。
本当に必要なことは、動詞それぞれの「イメージ」を掴むこと。今回はそんな中でも”have”を使って
具体的にイメージ化とはどういったものなのか。
動詞の意味だけを覚えることがなぜダメなのか。
以上のことを理解していただきます。
また、「使役動詞」なんて難しい単語を使っておりますが、こちらの記事は「英語初級者」から「上級者」の方まで幅広く楽しんでいただける記事になっております。
動詞のイメージ化とは?
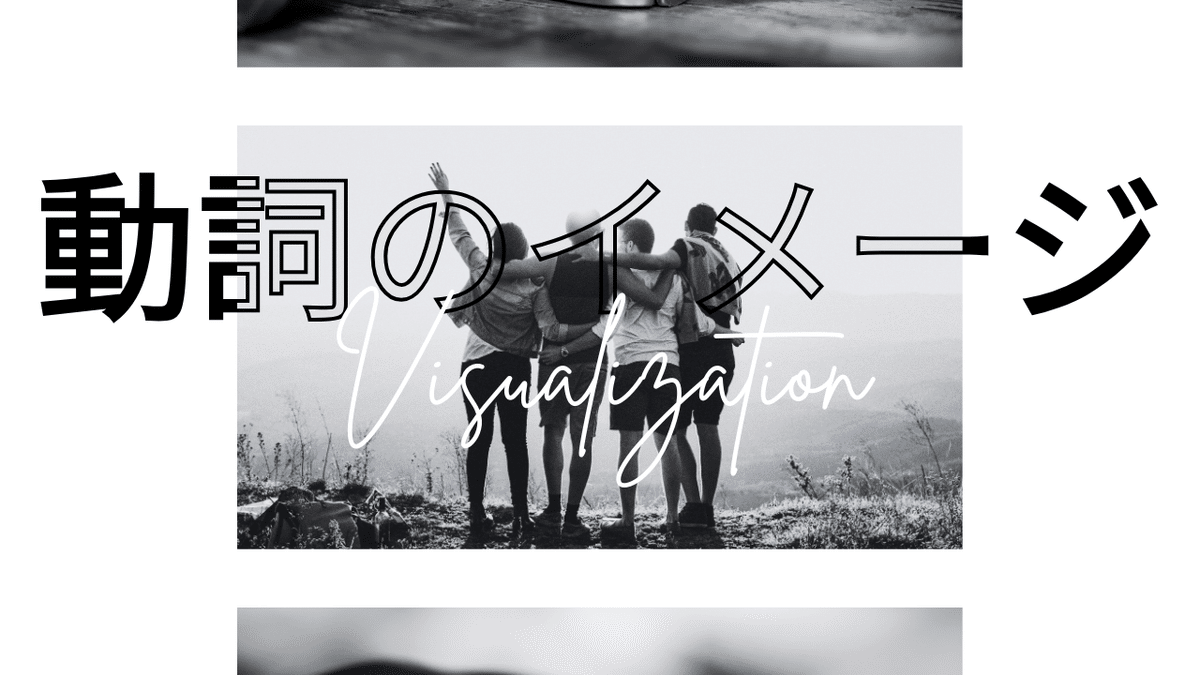
例えば「have」と聞くと、「持っている」という意味が頭に浮かぶ方がほとんどだと思います。ただ、もちろん意味だけにフォーカスするとそれだけではありません。
“I have a brother.”
「私には兄がいます」
“I have to study English.”
「私は英語を勉強しないといけない」
“I had my son study.”
「私は息子に勉強させた」
同じ「have」なのにも関わらず、日本語の意味が変わってきますね。この他にも無数に意味が出てくるでしょう。
それをいちいち覚えていく様では途方もない時間が溶けていくわけです。
だから「意味に囚われてはいけない」と僕は言うんです。
でも、「have のイメージ」はたった1つ。「抱える」です。

このイメージさえ出来ればこれから先どんな” have ”が出てきても対応できるということです、
だから「イメージを持つ意識を持とう」と僕は言うんです。
中でもこのイメージからかけ離れている様な
「使役動詞 have」
(“I had my son study.”「私は息子に勉強させた」)
を理解することができたら、あなたは英語脳を手に入れたといっても過言ではないでしょう。
それぞれ順番に解説していきます。
使役動詞の「have」は?
have のイメージは何度も言うように「抱える」です。

“抱えるもの”によって意味が変わるということです。
I had my son study.
このイメージ訳は
「私は勉強する自分の息子を抱えた」

つまり、今回”I”が抱えたものは、「勉強する息子」なんです。
この状況を自然な日本語で説明をすると、
「私は自分の息子に勉強させた」
という風になるのです。
たったそれだけ。
他の使役動詞も少しだけ
せっかく使役動詞の話が出ているので、他のもみてみましょう。
数は少ないです。”have””make”let””get”この4つだけ。
make

I made my son study.
「私は自分の息子に勉強させた」
あれ?”have”の時と同じ訳になりましたね。違いは何でしょうか?
make のイメージをみてみましょう。
make のイメージは「パン生地の様にこねくって形作る」こんなところでしょうか?

パン生地をこねている人が「クロワッサンを作りたい」と考えているのであれば、このパン生地は「クロワッサン」になるしかないでしょう。もし仮にパン生地が「メロンパン」になりたかったとしても。
では今回「コネくるもの」はなんでしょうか?「息子」です。
こねくられる息子は自分の意見が通るでしょうか?いいえ。パン生地と同じです。言われるがままなんです。
その結果、状況としてはこんな感じでしょう。

それに対して have はもう少し柔らかいイメージになります。なので「促した」とか「お願いした」的なニュアンスが含まれるのです。
let

I let my son study.
「私は自分の息子に勉強させた」
また同じ訳になってしまいます。もうお分かりですね。 let のイメージをみてみましょう。
let のイメージは「やりたい様にさせる」です。

勉強したがっているのなら、そうさせる。
何も止めずに自由にさせているのが let のイメージですね。

get

I got my son study.
「私は自分の息子に勉強をさせた」
やっぱりこのイメージになります。が、 get のイメージはより分かりやすいかと思います。
あるアニメのキャラクターで
「○○モンゲットだぜ!!」
といっているのがいるのですが、みなさんご存知でしょうか?

あのアニメ/ゲームの主人公である彼が、最初の町であるマサラタウンから一歩も出ずにだらけて○○モンをゲットしていたらどうでしょうか?
面白さなんてこれっぽちもないですね。
getのイメージはそれまでの経緯も含まれているのです。
要は、「何かお願いをする」イメージですね。

以上が使役動詞のそれぞれのイメージです。
“have to”は何を持っている?
「have to」と「must」はどちらも「〜しなければならない」という意味ですが、ニュアンスが異なります。
must: 義務や強い命令(話し手の主観)。
例:You must finish your homework.
(宿題を終わらせなければならない=絶対的な義務)
have to: 状況による必要性(外的な要因)。
例:I have to go to work early tomorrow.
(明日は早く仕事に行かなければならない=状況に基づく必要性)
こんなことを言われても、英語が全くわからない側からしてみると、
「で?だから?」
で終わりますよね?分かります。僕も学生時代、「だから嫌いなんだよなぁ」なんて思っておりました。
でもこうは考えたことはありませんか?
「なんで have だったんだろう?」
答えは簡単です。この場合、『義務』を”持っている”んです。
I have to study English.
「私は英語を勉強しなければならない。」
と習いました。ただこれはもともと、
「私は英語を勉強するという義務を持っている。」
というイメージだったのです。
この考え方だと、”must”との違いも明白になるはずです。
must との違いは?

“I must study English.”
“I have to study English.”
どちらも「私は英語を勉強しなければならない。」と習いました。
しかしこれが否定文になると話が変わってくるのです。
“I must not study English.”
「私は英語を勉強してはならない」
“I don’t have to study English.”
「私は英語を勉強しなくても良い」
意味が全く違ってきます。なぜか?簡単です。
”don’t have to ”は
「する義務を持っていない」から
mustについてはまた後日”助動詞”と一緒にお話ししますね。
「います」は have ?
「みなさん。「です/ます/います」は英語で言うとbe動詞にあたります。」
と僕たちは習います。
ただ、
「私には、家族/友人/恋人etc… がいます」になるとこれも話が変わります。
“I have a brother.”
「私には兄がいます。」
ここの have はどんなイメージでしょうか?
もうお分かりですよね?
家族も友人も恋人も英語では「持つ」物なんです。
be動詞に関しては、これもまた別でお話しいたします…
「意味」とは何?
ここまでくると、結局意味ってなんなんだ。となってしまうのですが、
結局便利なんです。
例えば、この状況を言葉で表現しようとすればどうなりますか?

女の子のことを話そうとすれば、
「この女の子にはボーイフレンドがいる」
という表現になるじゃないですか。
意味というのは、結局聞き手が理解しやすいように、表現した結果なまでなんです。
「ここで出てくる have は「持つ」ここの have は「いる」…」と無数に出てくるのは当たり前なんです。
そうするしかないんだから。
「意味に振り回される時代」はもう終わり。
「イメージで解決する時代」の到来です。

まとめ
イメージを掴むことで英語が話せる様になる。
今回、なぜ使役動詞の have を全面に出したのかと言うと、こいつが一番日本人にとってややこしいからです。
そしてこの使役動詞の have をはじめとする have のイメージを掴み使いこなすことができれば、大抵のイメージも同じように掴むことができるのです。
何度も言いますが、 have が一番様々な訳に化けるのです。
今回持って帰って欲しいポイントは、
haveのイメージは「抱える」
動詞のイメージ化ができれば英語は案外シンプル
「意味」にフォーカスするんじゃなくて、「イメージ」を掴むことにフォーカスを
以上の3点です。
次回予告
次回は、助動詞について書きます!
「助動詞はあくまで「話している人の考え」にすぎない」
これがNext Domy’s Hintです。
また、Clumsylingoは「習慣化」をテーマにコツコツ発信しています。
Youtube/本ブログ/Instagramもありますので、ぜひチェックしてみてください!
ではでは。
