
デザイン×エンジニアリング|「二刀流」で変革を起こすエンジニアの姿とは

中塚 貴大 (なかつか たかひろ)
Cloudbase株式会社 / Software Engineer
京都大学在学中から、モバイルアプリを中心としたスタートアップ企業、Biome株式会社とAruga株式会社にエンジニアとして従事。Biome株式会社では、iOSアプリ開発チームの2人目のメンバーとしてプロジェクトマネージャー(PjM)を、Aruga株式会社ではCTOを務める。Cloudbaseには、6ヶ月間の業務委託を経て2024年2月にジョイン。
簡単に自己紹介をお願いします。
アプリケーションチームでソフトウェアエンジニアをしており、フロントエンドからバックエンドまで幅広く担当しています。大学時代から前職までにデザインツールのFigmaを頻繁に使っていた経験があり、そこで得たデザイナーの視点を活かして、Cloudbaseではデザイナーとエンジニアの橋渡し役をしながら、フロントエンドの実装をしています。
これまでの経歴を教えてください。
2018年に株式会社Biomeにジョインし、プロジェクトマネージャー(PjM)を担当していました。Biomeのプロダクトの1つである「Biome」は、植物・動物・昆虫などの写真を撮影すると、機械学習を用いてそれらの名前を表示され、登録や投稿ができるSNSアプリです。このアプリのβ版は、Biome創業者のエンジニア2人がAndroid版として完成させたのですが、資金調達後のiOS版の開発から私も深く事業に携わり始めました。実はこの時、現Cloudbase 代表の岩佐や、エンジニアの岩井も開発に参加していたんです。私はPjMとして、タスクを分解して適切な割り振りを行いながら、自分自身もエンジニアとして開発やデザインの調整に関わっていました。
その後、スポーツチーム向けに、選手一人一人を育成するマネジメントツールを提供しているAruga株式会社へ移り、Flutter(Googleからリリースされているモバイルアプリ用のフレームワーク)を用いたモバイルアプリの開発を担当しました。その他、自分自身でもiOSアプリの開発・リリースをした経験があります。
技術スタックの壁は、実は存在しなかった
Cloudbaseを知った経緯を教えてください。
代表の岩佐とは大学の同期で仲が良かったので、彼が起業しようと試行錯誤している時からずっと知っています。なので事業を何度もピボットさせていた時代や、Cloudbaseの前身である株式会社Levettyを設立した時、経営陣が加わった時期など、会社が辿ったこれまでの大まかな流れは把握しています。
Cloudbaseの初期からジョインしなかったのは、当時私は株式会社Arugaに入社したばかりで、そちらに全力を注ぐと決めていたからです。また、それまでの私はiOSアプリの開発経験を積んでいたため、Cloudbaseが扱うWeb系の技術スタックに不安を感じていたことも理由の1つではあります。
Cloudbaseへのジョインを決めたきっかけを教えてください。
Cloudbaseが毎月開催するMeetUpイベントに参加し、エンジニアメンバーから詳しく話を聞いたことで、自分にとっての技術的な壁は、実は低いのではないかと気づいたことがきっかけです。
当時の私は、Web開発の基本となるHTMLやCSSが得意ではなく、Webフロントエンドを扱うことは難しいと考えていたのですが、MeetUpの際にCloudbaseではChakra UIというUIコンポーネントライブラリを使用していることを聞きました。Chakra UIは、それまで私が使ってきたFlutterでのUIコンポーネントとほとんど同じ感覚で実装できます。ソフトウェアやプログラム、Webサービスをつなぐインターフェース(Application Programming Interface:API)の実装など、役に立てることがありそうだと感じ、まずは業務委託として関わることにしました。
そこから6ヶ月の業務委託期間の中で、言語に対する苦手意識は問題でなかったと気づくとともに、もっとCloudbaseのプロダクトを磨きたいという思いが強くなりました。「技術スタックの壁」という、ジョインを阻む理由がなくなったことが最終的な決め手でしたね。
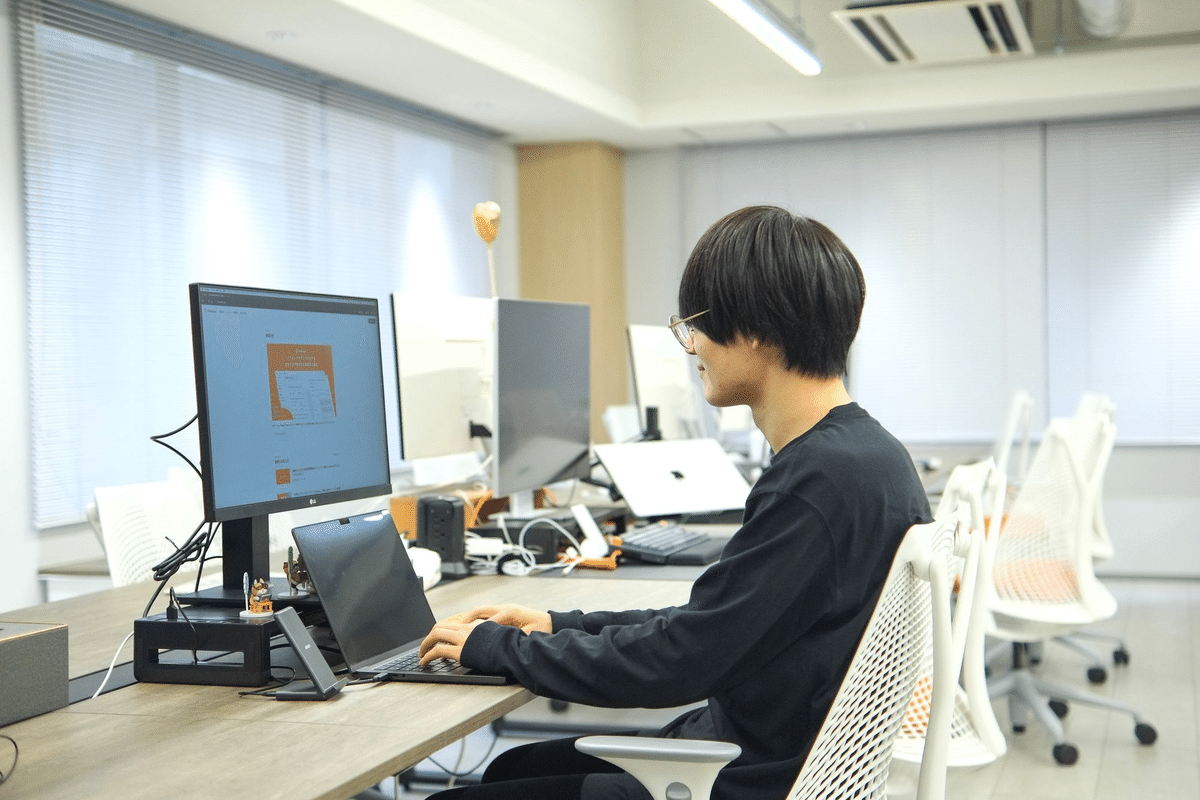
デザインにはどのように興味を持ったのですか?
学生時代に参加したサマーインターンでのプロダクト開発がきっかけです。私は岩佐と同じチームで、彼が機能実装を担当していました。エンジニアとして自分があまり役に立てていない気がして最初は落ち込んでいましたが、私はデザインの面からアプローチすることでチームの力になろうと決意しました。ユーザーの視点を理解しようとヒアリングを重ねてデザインに取り入れた結果、審査員の方から「機能だけでなく、UIも優れていて使いやすい」と評価をいただき、見事優勝することができました。この経験を通じて、デザインの大切さや面白さに目覚め、自分が貢献できる新しい分野を確立するに至りました。
「With」な取り組みは「Unlock」につながる
現在Cloudbaseで行っていることを教えてください。
Cloudbaseのアプリケーションチームでは、段階ごとではなく機能ごとに役割を分担しています。
基本的な流れは以下の通りです。
まずはデザイナーと連携して仕様を決め、そこからシステムを設計して実装します。その後、リリース前に社員同士で行う試用の中でバグや改善点を洗い出し、修正したものを最終的にリリースします。
またお客様からいただくフィードバックにはその機能の担当者が改善から運用まで一気通貫で担当します。一般的には多くの担当者が携わる開発プロセスですが、Cloudbaseではエンジニアとデザイナーが仕様を決め、以後の実装まではエンジニア担当者が1人で担います。結果として、各担当者がオーナーシップを発揮しながら迅速に開発を進めることができる点が特徴と言えます。
尊敬しているメンバーを教えてください。
エンジニアの岩井です。彼は大学の同級生で、学生時代には一緒にアプリを作り、前職のArugaでも同僚として働いていました。どこに行っても活躍できる抜きん出たスキルを持っていて、彼の書くコードは社内で「ryunosukeスペシャル」と呼ばれるほどです。彼の活躍を身近で見られることは、私にとって大きな刺激となっています。
また、エンジニアの荊尾(かたらお)の圧倒的な知識量には、毎度驚かされています。特にフロントエンドの知識がずば抜けています。
さらに素晴らしいのは、その豊富な知識を惜しみなくメンバーに共有してくれることです。私がCloudbaseへジョインしたばかりの頃、会社の事業やセキュリティ、パブリッククラウドに関する学習に時間を要し、フロントエンドに関する最新の動向を追う余裕がありませんでした。しかし、荊尾は毎週のミーティングやコードレビューの際に、役立つ情報をシェアしてくれており、現在に至るまでとても助かっています。
バリューに対する印象を教えてください。
端的で2つしかないので覚えやすくて好きです。それぞれたった一単語ですが、メンバーの意識が一致しており、普段から活用しているので形骸化していません。
事例として、アプリケーションチームでのバリューを発揮した取り組みを紹介させてください。特定の目的を達成するためのコードには複数の書き方があり、毎回自由に選んでいるとエラーやバグが発生しやすくなることが以前から問題視されていました。この課題を未然に防ぐため、メンバーが開発効率や生産性を向上させる施策をテキストにまとめてくれました。その結果、以前は様々だったコードの書き方が統一され、開発生産性が向上し、人為的なミスも格段に減少しました。これはエンジニアにとって非常にありがたい「With」な取り組みであり、より「Unlock」な成果を出すことにつながっていると思います。

入社後のキャッチアップに関して、コメントをお願いします。
Cloudbaseに入ったエンジニアの中で、私は入社時に最も知識が少なかったメンバーの1人だと思います。Web開発の経験が少なく、Cloudbaseで使用している言語もあまり使ったことがありませんでした。それでも今は大きな問題なく業務を行っています。
これは日頃からの周りのメンバーのサポートや、入社時のオンボーディングコンテンツが非常に充実していたことで会社やドメインについてわかりやすく学べたおかげです。また、Cloudbaseにはドキュメント文化が根付いているため、過去の実装については仕様設計書を確認することですぐに理解することができる点も理由の1つと考えます。もしも実装者の頭の中だけで考えていてドキュメントが残されていなかったら、設計の意図などが分からず困っていたと思います。
このような環境のおかげで、クラウドセキュリティやWeb開発の経験が少なかった私も安心してキャッチアップすることができました。
デザイナーの視点を持つエンジニアだからこそできること
これからどのようなことに取り組んでいきたいですか?
プロダクトデザインの統一化を進めたいです。現在は画面ごとに小さなデザインの揺れがあり、ユーザーの認知負荷につながる可能性があると考えています。プロダクトの強みであるUIの使いやすさを維持・強化するために、デザインを統制させることが重要です。効率よく実装に反映し、早期に実現させることで、ユーザーにより良い体験を提供できるプロダクトになっていくと考えます。

どのような方にCloudbaseへ来ていただきたいですか?
「With」と「Unlock」という2つのバリューに共感し、カルチャーフィットする方に来ていただきたいです。特に「With」の精神が大切だと思います。
エンジニアの観点から言うと、コードの書き方や実装に正解がないことも多いので、自分の意見を押し付けずに柔軟に考えられることが重要だと感じています。Cloudbaseのエンジニアは、ただ黙々と実装するだけでなく、他の部署とも積極的にコミュニケーションを取る必要があるため、チームワークを大切にし、協力的な姿勢を持っている方を歓迎したいです。
最後に、候補者の方へ一言お願いします。
クラウドセキュリティなどの専門知識をキャッチアップすることは確かに大変ですが、その分成長できる環境が整っています。メンバーから技術力を吸収し、パブリッククラウドについて詳しくなれる絶好の機会です。興味を持ってくださった方は、ぜひ下記のリンクからお気軽にお問い合わせください。カジュアルにお話しましょう!
