
アートのルールについて
おひさしぶりです。田中です🦄
突然ですがアートには「文脈」という概念がある事を知っていますか?
『アートにはルールが無い、何をやっても良い』と思われがちですがアートにもスポーツと同じくルール・不文律があります。
めちゃくちゃで斬新なアイディアを出しても着地点を誤れば盛大にコケます。めちゃくちゃに見える作品にも実はしっかりと導線があるのです。
試しに文脈をキャラクターで考えてみましょう
例えばゆるキャラで『せんとくん』というキャラクターがいますね。

この『せんとくん』はめちゃくちゃ現代アート的です。
このキャラクターはキモかわキャラクターとして世間から評価を得ていたキャラクターだと思います。賛否両論ありながらも世間に受け入れられた印象があります。
しかし
そもそもキャラクターという概念が世間一般では無い時代に出てきたらどうでしょう。
世の人々はおそらく困惑して受け入れられない可能性が高いです。
日本のキャラクターの元祖はおそらく『ドラえもん』『ハローキティ』だろう。
この2キャラが社会で人気を博してキャラクターという存在を受け入れる土壌ができます。
キャラクター=国民的である
という固定観念に対するカウンターの様に今度は都道府県ごとの公認「ゆるキャラ」が登場します。
ここで「別に都道府県ごとにキャラクターがいても良いんだ!」という新たな価値観を投ずることができます。これがまず最初の文脈。
さらにそこへ非公認キャラとして「ふなっしー」が登場します。「別にゆるキャラって非公認でも出していいんだ!」というカウンターになります。
ここで満を持して『せんとくん』が出てきます。
キャラクター=kawaii
だった所にキモかわという価値観をぶち込みます。キモかわという言葉自体はそれ以前からありましたがキャラクターはキモくても良いという考えは新しいです。
こうして『せんとくん』は世間から受け入れられる土壌と導線、刷り込みがあって着地できた。
これが『文脈』です。
これがアートにも存在しています。
まずポップアートの旗手、ロイ・リキテンシュタインという作家がいます。


リキテンシュタインはたくさんのコミックを買い漁りそこから気に入った漫画のコマをコピーして描き写すことで有名ですが今回はそれとは違う切り口で触れていきます。
リキテンシュタインはコピーのつぎのステージとしてリミキサー(オマージュ)を行います。
ピカソ、マティス、ダリ、ゴッホなどの過去の名画を自分のタッチで書き直すようになります。



こうした既存の絵を描き直すスタイルは現代のアーティストにも遺伝子が受け継がれています。
MADSAKI
挑発的、風刺的なフレーズ、歴史上の名画を題材にしたシリーズを製作している。
近年は私小説的でプライベートな絵画シリーズも展開。
日本とアメリカにまたがる複雑なアイデンティティから生まれるテーマを、大胆なスプレーワークを通じて表現する。

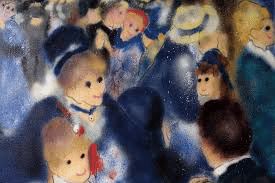
ダニエル・アーシャム
ニューヨークを拠点に、ファインアート、建築、パフォーマンス、映画など幅広い分野で活躍しているアーティスト。アーシャムの象徴的な作品は、20世紀後半の様々な瞬間へのノスタルジアが持つ可塑性とパワーを表現しながら、過去、現在、未来を融合させています。


既存のモチーフ×自分のタッチ
これらの現代のアーティストの手法はリキテンシュタインのやり方なのではないかなと私は考えています。
ここまでくると何をオマージュするか、何を描いたかというより作家のタッチ(作風、筆のストローク)自体が主題になっているように思えます。
上記のリキテンシュタインもデュシャンやジャスパーの文脈もあると思いますが今回は省きます。
今回は文脈について説明してみました。いかがだったでしょうか?
またつぎの記事でお会いしましょう。ではまた
