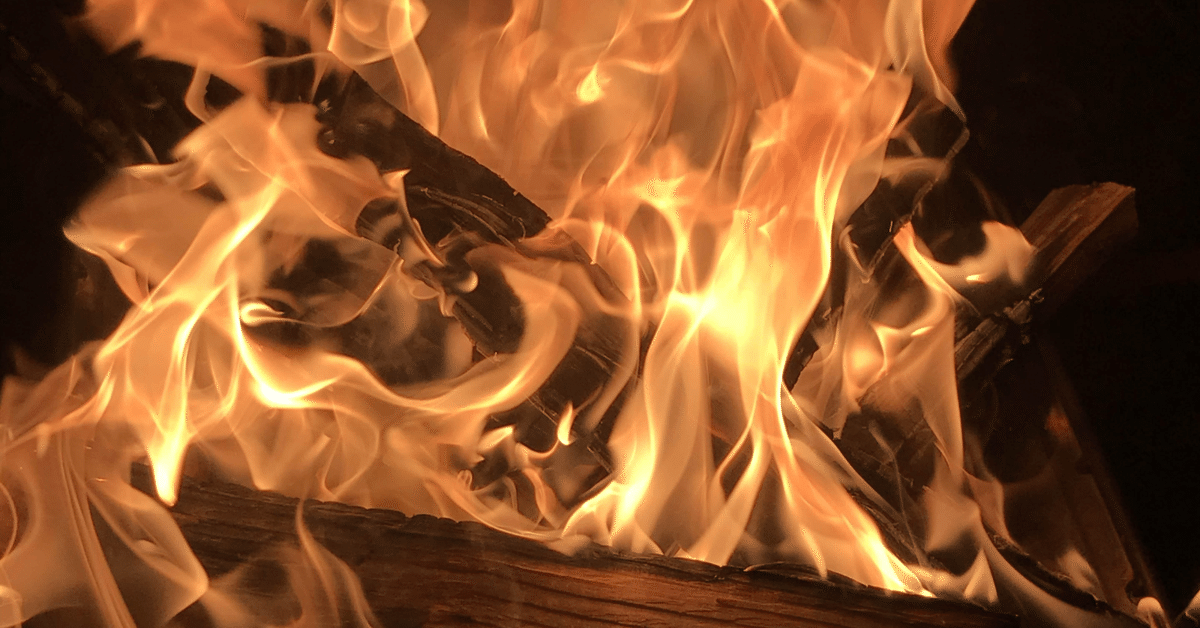
著作権譲渡契約の注意点と雛形【完全解説】
1. はじめに
著作権は、音楽、美術、文学、プログラム、映像など、私たちの身の回りのあらゆる創作活動に関わっています。これらの創作物(著作物)を利用したいとき、利用者は著作権者(原作者や出版社、レコード会社など)から使用許諾(ライセンス)を得ることが原則です。しかし、ビジネスの場面などでは、著作権そのものを譲り受ける=「著作権譲渡契約」を結ぶケースも存在します。
著作権は、比較的複雑な権利構造をもっています。特に「著作者人格権は譲渡できない」という原則や、著作権法で保護される権利範囲(複製権や翻案権など)をどこまで譲渡するか、といった点を明確にしておかないと、契約後にトラブルが生じる可能性があります。
本記事では、初めて著作権譲渡契約を検討される方に向けて、基本的な考え方や注意点をなるべく分かりやすく解説します。さらに、記事の後半では、著作権譲渡契約書の雛形も掲載しますので、ぜひ参考にしてみてください。
2. 著作権の仕組みと特徴
2-1. 著作権とは
著作権とは、法律で定められた創作者の権利で、創作者の思想や感情を表現した創作物(著作物)を保護するために与えられます。たとえば、文章、絵画、音楽、映像、プログラムなどが典型的な著作物です。著作権者は、その著作物を複製したり、翻案・翻訳などの形で二次的に利用したり、公に送信したりする際に排他的な権利を持つことになります。
2-2. 著作人格権と著作権(財産権)
著作権には大きく分けて「著作人格権」と「財産権的権利」の二つがあります。
著作人格権
公表権、氏名表示権、同一性保持権などを含む権利で、著作者の人格的利益を保護するためのもの。
一身専属権とされ、原則として譲渡できません。
ただし、契約上「不行使特約(著作者人格権を行使しないという合意)」を結ぶことは可能です。
著作権(財産権)
複製権、上映権、公衆送信権、翻案権など、著作物を財産的に利用する権利。
こちらは譲渡・相続やライセンスが可能な部分です。
3. 著作権譲渡とライセンスの違い
3-1. ライセンス(使用許諾)
ライセンス契約は、著作物を利用する際に、一定の範囲内で利用を認める契約形態です。著作権者が自ら権利を保有し続けながら、利用者に対し複製や翻案、配信といった行為を限定的に許可するというイメージです。
メリット:著作権者から見れば、今後も権利を保有し続けて複数の相手にライセンスを与えられるため、継続的な収益が期待できる。
デメリット:ライセンスを与える相手の数や範囲をコントロールする必要があり、著作物の管理が煩雑になる場合がある。
3-2. 著作権譲渡
著作権譲渡契約は、特定の著作物の財産的権利を、著作者から譲受人へ移転するものです。譲渡を受けた側は、著作物を独占的に利用したり、さらに第三者へライセンスを与えたりすることが可能になります。一方で著作権者は、譲渡後にその著作物を勝手に利用できなくなる(あるいは厳しく制限される)点に注意が必要です。
メリット:譲受人から見れば、著作物を自由に活用できるほか、後々の管理や収益化もスムーズに行いやすい。
デメリット:譲渡側は権利を失うため、二次利用などで収益を得る機会を手放すことになる。
4. 著作人格権の不行使特約とは
日本の著作権法では、著作人格権は一身専属的で譲渡できないとされています。しかし、実際のビジネスの場面では、著作物に修正や改変を加えたい場合などに、著作者本人から「著作人格権を行使しない」と約束してもらわないと、後日トラブルが生じるおそれがあります。
そこで、著作権譲渡契約においては、「著作者は著作人格権を行使しないものとする」旨の合意を交わすことが一般的です。これを「不行使特約」と呼び、実質的には「著作者人格権を主張しない・問題にしない」という取り決めです。もっとも、法律上は譲渡できない権利なので、「譲渡」ではなく「行使しないことの合意」という形を取る点に留意が必要です。
5. 著作権譲渡契約で押さえるべき主なポイント
著作権譲渡契約を締結するにあたり、以下の点を明確にしておく必要があります。
5-1. 譲渡の対象範囲を明確化する
対象作品の特定
どの著作物を譲渡の対象とするのかを、タイトルや作者名などを用いて正確に示す必要があります。
譲渡する権利の範囲
著作権法で保護されるいくつかの権利(複製権、翻案権、公衆送信権など)のうち、どれを譲渡するのか。
翻案権(続編やリメイクを作る権利)や二次的使用(映画化やゲーム化など)も含めるかどうか。
著作権法27条および28条が定める「翻訳・翻案などの二次的著作物に関する権利」まで含めるかどうか。
5-2. 契約時に存在しなかった権利の扱い
技術の進歩によって、新しい利用形態が生まれることがあります。
例えば、将来的にVRやAR、メタバースなどでの利用形態が開発された場合、その新しい形態も含めて譲渡の対象とするのか。
あるいは将来権(現時点で想定していない権利)は明確に除外するのか。
本来、契約時に定められていない権利が生じた場合には、その取り扱いを巡って紛争になる可能性もあるため、「将来発生する一切の利用形態にも及ぶ」といった包括的な規定を入れるかどうか、事前に検討が必要です。
5-3. 著作人格権の不行使特約
前述のとおり、著作人格権は譲渡できません。著作物の改変や加工、修正などを自由に行いたい場合は、著作者に「著作者人格権を行使しない」旨を合意してもらう必要があります。
例:「著作者は本件著作物に関し、同一性保持権、氏名表示権、及び公表権を行使しない」
5-4. 対価と支払条件
譲渡の対価は、買い切り方式で一括支払いか、分割払いかなどを明確化します。
報酬形態がロイヤルティベース(著作物の売上や利用料に応じて支払う)になる場合は、計算方法や支払いスケジュールの取り決めが必要です。
5-5. 保証・補償
譲受人としては、将来的に著作権の帰属について第三者から訴えられたり、既存の著作物を侵害していないかどうかのリスクを考慮しなければなりません。そのため、契約書に「権利の瑕疵がないことを保証する」条項を入れることが多いです。
例:「甲(譲渡人)は、本件著作物が第三者の著作権その他の権利を侵害していないことを保証する」
もし侵害があった場合、譲渡人が損害賠償を負うのか、といった補償(Indemnity)についても確認が必要です。
5-6. 二重譲渡・ライセンスの防止
著作権がすでに他の第三者へライセンスされていたり、あるいは今後二重譲渡されるリスクを回避するため、「この契約に反するライセンス契約を結ばない」旨を明確にしておくことが望ましいです。万が一、二重譲渡が発生すれば当事者間の法的紛争に発展するおそれがあります。
6. 譲渡契約書(雛形)
以下は、著作権譲渡契約書の簡易な例です。実際には契約目的や作品の種類、業界の慣行などにより文言を調整する必要があります。
著作権譲渡契約書(サンプル)
第1条(当事者)
本契約は、甲:○○、乙:××の間で締結する。
第2条(目的)
甲は、乙に対し、下記に定める著作物に関する著作権を譲渡し、乙はこれを譲り受けるものとする。
第3条(著作物の特定)
本契約でいう「本件著作物」とは、次のとおり特定される作品をいう。タイトル:『○○○○』著作者:甲作品の種類:文章/イラスト/楽曲等、具体的に明記
第4条(譲渡する権利の範囲)
1 甲は、著作権法第27条および第28条に定める翻訳、翻案、二次的著作物の利用に関する権利を含む一切の財産的権利を乙に譲渡する。
2 甲は、本件著作物の著作者人格権を行使しない(不行使特約)。
第5条(将来発生する権利・利用形態)本契約締結後に技術の進歩等により新たに生じた利用形態についても、本条の規定により乙が利用できるものとする。
第6条(対価および支払い)乙は、甲に対し、本件著作物の譲渡対価として金○○円(税別)を支払う。支払い時期および方法は以下のとおりとする。支払い時期:○年○月○日まで
支払い方法:銀行振込/現金手渡し
第7条(保証・補償)
1 甲は、本件著作物が第三者の権利を侵害していないことを保証する。万一、第三者から権利侵害を主張された場合、甲は乙と協力し、その解決に努めるものとする。
2 前項の結果、乙が損害を被った場合の補償責任については、甲乙協議の上、別途定める。
第8条(二重譲渡・ライセンスの禁止)
甲は、本契約に基づき譲渡した著作権と同一の権利について、第三者に対する譲渡もしくはライセンス、またはこれに類する行為を行わないものとする。
第9条(契約解除)乙が本契約の義務に重大な違反をし、相当期間を定めて催告しても改善されない場合には、甲は本契約を解除できる。甲が前条に違反した場合、乙は本契約を解除できる。
第10条(準拠法および管轄裁判所)
本契約の準拠法は日本法とする。本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
【日付】 令和○年○月○日
甲(著作権者) 署名:
乙(譲受人) 署名:
※上記ひな形はあくまで一例であり、実際には契約内容に応じた修正が必要です。
7. まとめ
著作権の譲渡は、著作権者にとっては作品を手放すことを意味し、譲受人にとっては大きな権利を確保できるものです。両者の利害が大きく動く取引であるからこそ、「譲渡の対象範囲」や「不行使特約(著作者人格権の扱い)」、「対価や支払い方法」など、重要なポイントを明確化したうえで契約することが大切です。
また、将来発生する権利や新たな利用形態が登場し得る現代においては、包括的な譲渡にするかどうかや契約書の文言をどこまで広げるかといった点が、今後のビジネス展開を左右する場合もあります。さらに、契約後に二重譲渡やライセンスが行われてしまい、予期せぬトラブルが発生する可能性もゼロではありません。そうしたリスクを回避するためにも、弁護士等の専門家に相談したうえで契約書を作成し、慎重に取り扱うことを強くおすすめします。
以上が著作権譲渡契約に関する概要と、契約書の簡単な雛形となります。著作権法の改正や技術の進歩によって取り巻く状況は常に変化していますので、定期的に情報をアップデートしながら、適切な権利処理を行っていただければと思います。
