
北京のアダム・スミス(ジョヴァンニ・アリギ)
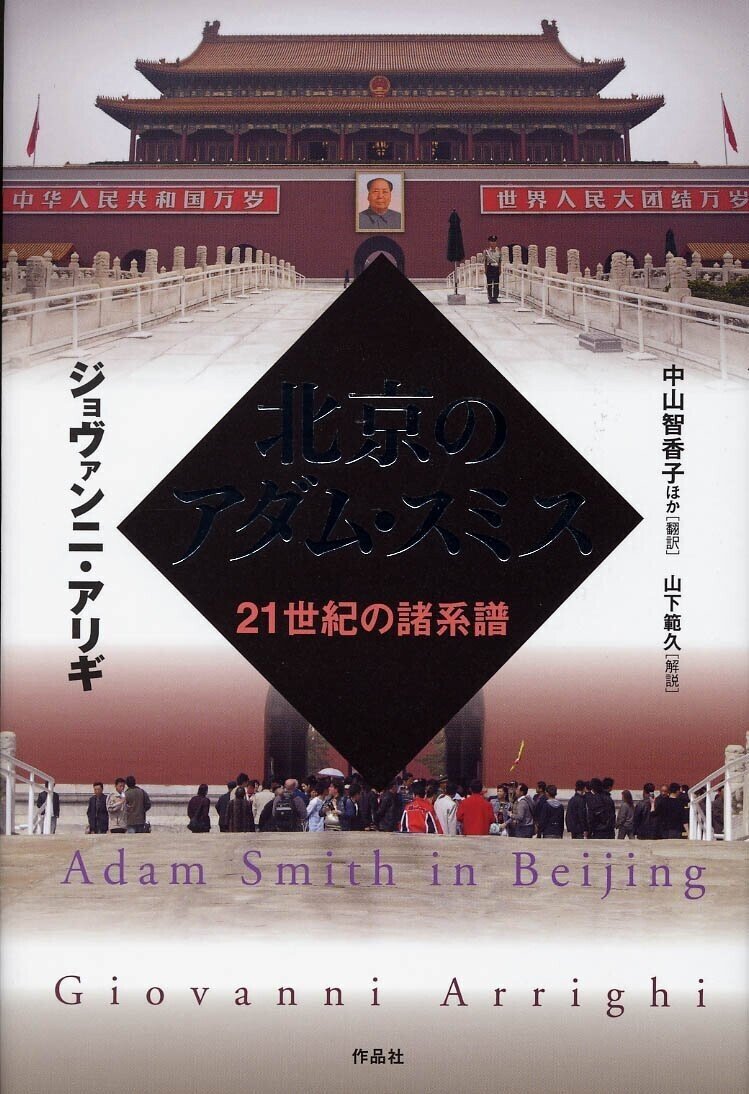
ジョヴァンニ・アリギ
中山智香子ほか訳 山下範久監訳
作品社2007
いきなりだが、「中国の特色ある社会主義」と聞いて、皆さんはなにを思い浮かべるのだろうか。
多くの人は、「意味不明」と答えるだろう。続いて「要は一党独裁体制」「全体主義」といった言葉が浮かぶかもしれない。中国通に聞いたら、「社会主義の皮をかぶった実質的な資本主義」、「国家資本主義」などの答えが返ってくるかもしれない。たぶん、なにを答えても間違いではないだろう。それだけ、曖昧な言葉だからだ。
このような曖昧な言葉を相手にしたとき、言葉の定義そのものから真意を見出そうとするのは無意味である。社会主義にせよ、資本主義にせよ、中国においてはどちらも単なる名詞に過ぎず、必要に応じいくらでも恣意的に解釈を変更できるからだ。今の中国が実際にどのような政治、経済体制の上に成り立っているのかを理解するには、中国の政治をとりまく言葉たちと言葉遣いの変化に細心の注意に払うと同時に、言葉に囚われることなく、中国が実際に採用した手法、政策の動向を観察し、現実から総合的に判断していくしかない。
そのように考えれば、おそらく中国語のできない著者・アリギは、最初から言葉に惑わされないで済む立ち位置にあるため、すぐに中国の現実に入って行けるのである。もちろん、後述のように、アリギの中国理解に偏りがあることが否定できないが、彼の意図は初めから中国を正しく理解することではない。彼が見ようとしているのは世界史的なヘゲモニーの変化、世界システムの変化であり、それを考察する過程で、ちょうど台頭する中国にぶち当たったと見るべきである。
さて、そのような世界システムの変化から眺めた場合、初めはオランダ、その後のイギリス、さらにアメリカと、世界的な影響力を持つ中心国家が絶えず変わり続けていることがわかる。そして、ベトナム戦争をきっかけにアメリカの力が少しずつ衰えていき、イラク戦争の泥沼にはまってからは「凋落」したとアリギは言う。その代わり力をつけてきたのが中国だが、なぜ中国がこれほどまでの成長を遂げることができたのか、そのことが今後の世界にどのようなインパクトを与えるのか、そのことがアリギにとっての最大な課題である。
アメリカを始めとする資本主義諸国のヘゲモニーと中国の台頭を説明するために、彼が使った理論は、大本をたどればアダム・スミスとカール・マルクスの2本柱となる。しかし、意外なことに、マルクス=社会主義=中国、アダム・スミス=自由主義=アメリカという図式ではなく、中国の成長を導いたのはマルクス主義ではなく、むしろアダム・スミスの市場経済の方であるとアリギは言うのである。
この結論だけを読めば、当然違和感を覚えるだろう。ぼくもはじめは「市場経済?何を言ってるんだ。市場経済は『見えざる手』を頼りにする。政府が経済に強力に介入する中国とは真逆じゃないか」と思っていた。そうした反論を予想したかのように、アリギは本書前半で世間のマルクス理解やアダム・スミス理解の重大な過ちを指摘する。
「マルクスとともに、彼(アダム・スミスのこと)はたしかにもっとも誤解された経済学者の一人である。とりわけ、三つの神話が彼の遺産を取り囲んでいる。一つめは、彼が『自己調整的な』市場の理論家や提唱者であったということ、二つめの神話は、彼が『終わりなき』経済拡張のエンジンとしての資本主義の理論家かつ提唱者であったということ、三つめは、彼が(中略)ある種の分業の理論家、提唱者であったというものである。実際には彼はこれら三つの説のいずれの理論家でも提唱者でもなかった。
(中略)
『国富論』は、最小国家ないしはまったく国家が存在しない状態でもっともよく機能する自己調整的市場を理論化しているどころか、(中略)市場を存在させるための諸条件を創造したり再生産したりする強い国家の存在を前提としていた。またこの国家は、統治の効果的な道具として市場を用いながら、市場の作用を調整し、また社会的、政治的に望ましくない市場の諸々の結果を修正したり埋め合わせたりするために積極的介入しようとする。」
アダム・スミスを読んでいないぼくには、アリギの言葉がどこまで正確なのかがわからないが、「国家が道具として市場を用いる」手法はたしかに中国とそっくりだ。こうした状態をアリギは「市場が国家に従属する」と呼び、それに対し、欧米諸国は「国家が市場に従属する」状態だとする。後者こそが、マルクスが描き出した資本主義発展論において、資本があくなき蓄積による資本主義の発展を求め、遠距離貿易の拡大、不均等発展による競争を基本的な特徴とするプロセスだ。このプロセスにおいて、資本はいずれ海外植民地の獲得を要請し、国家にとっては、資本の活動を庇護することが至上課題となり、そのために軍事力拡大、国家間競争に奔走する。この経路を極限まで推し進めのが20世紀のアメリカだ。故に、アメリカこそがマルクスの理論の最良の体現者であり、「デトロイトのマルクス」と呼ばれるのである。
そんなアメリカを極致とする欧米と異なり、東アジアは古代からマルクスの言う資本主義の道筋をたどる兆候がなかった。アリギによれば、東アジア諸国は国内市場優先の立場から短距離、周辺国との交易を重視する道を選んできた。ヨーロッパ型の発展が地理的拡大と絶え間ない国家間戦争を不可避的に伴っていたのだとすれば、東アジアでは15 世紀来の500 年間の平和を維持でき、スミスの言う「自然な」発展経路としての国内市場の維持成長を優先したというのである。
その後、西洋との出会いによって、東アジアも否応なしに資本主義に巻き込まれたが、従来の東アジア的な発展経路が完全に崩れたのではなく、両者の「ハイブリッド化」が進んだ。そして、アメリカの凋落に伴い、東アジア独自の発展経路が復活したのだとアリギは主張する。特に中国では、改革開放以降に農村の生産性の向上(生産責任制)に取り組んだ結果、農村に余剰資本と余剰労働力が生まれ、これらを吸収、利用するための郷鎮企業が設立され、地方の産業と経済発展の原動力となった。特に大都市周辺、 沿岸地域の郷鎮企業の発展が目覚しく、地方経済の発展は農村住民の所得の向上に貢献した。この過程をアリギはヨーロッパとの違いを際立たせるために、「収奪なき資本蓄積」だと呼んだ。この中国独自の資本蓄積に加え、対外開放によって流入してきた華僑資本が中国の成長の軌跡を支えたのだと結論づけた。
ぼくの個人的な感覚からいえば、アリギが捉えた中国の経済成長を支える事実はほぼ正確だ。しかし、それをどのように評価するかとなると話は別である。本書の基本的な出発点は、「アメリカの新自由主義がすでに行き詰まった」ということにあり、したがってアリギはなんとしても新自由主義に代わる理念、路線を見出したいように見えてしまう。今の世界でアメリカ以外に最も目につくのは中国であり、アメリカとの制度の違いも一目瞭然である。それなら、中国からヨーロッパ型の資本主義と違うものを見つけ出そうーー
その思考回路は、ややもすれば数世紀前のオリエンタリズム的幻想の再来と解されかねない。アリギが中国の現実にすんなりと入っていったとぼくは書いたが、見方によっては、彼が中国に見たのは、「中国の現実と欧米の現実の差異」だけであり、「中国の現実自体の構造や内実」ではなかった可能性がある。さもなければ、「収奪なき資本蓄積」などという表現が出てくるはずがない。良心ある中国人なら誰でも知っているように、改革開放以降も以前も、中華人民共和国の経済は収奪の上に成り立っていた、収奪の最終的な対象は農村に暮らす全人口の2/3以上を占める農民であり、農民から収奪されたものは中小都市に集まり、そこからさらに大都市、そして北京上海深セン広州のようなメガシティに収奪されていく。アリギは本書で欧米諸国が海外植民地を使って何重にも渡る収奪の構造を作り上げたことを描き出したが、中国はそれと同じことを国内だけでやってのけたと考えるべきだ。そうだとすれば、中国とアメリカのやり方には何の違いもなく、どちらもマルクスの資本主義発展理論通りに突き進んでいるだけだ。アリギは本書の最後で中国がよりエコロジカルな、より人々に思いやりを持った発展経路を取ることを願ったが、それも単なる部外者の虚しい願望に終わるだろう。
それでもなお、ぼくはアリギの試みを大いに評価したい。なぜなら、たとえアリギの中国に対する評価が間違いだとしても、本書が描いたヘゲモニーの移り変わり、東西の過去の経済発展経路の違いは事実である。アリギが指摘したアメリカの新自由主義の行き詰まりも確かで、トランプに投票するほどアメリカ人は追い詰められており、欧州でも同様なことが起きている。なにか別のものを探し出さなければ、現実問題に対処できる処方を見つけねばーーその焦燥感は痛いほどよくわかる。そうした自分自身の課題に向き合ったからこそ、アリギは中国という他者の自身に引きつけて理解しようとしたのであり、そこにはオリエンタリズムのような傲慢さはまったくなく、むしろ誠実に現実を思考しようとする責任ある学者の雄姿が立ち表れてくるのである。
ところで、アリギのように、近代以降に東アジア/中国が欧米を中心とする世界に巻き込まれながらも、独自性のある道をたどったと考える研究者はほかにもいる。また、アリギのように自分自身の課題に引きつけて中国を読むということは、まさしく日本の学者が古来より行ってきたことである。同じように「中国の現実を捉えていない」と批判される恐れのある彼らは、なぜ中国を経由地としたのだろうか。外国人としての彼らが見る中国と、ぼくが愛憎入り交じりながら見る中国にはどんな違いがあるのか。次回は、その中から代表的な人物を一人選び読んでみたい。
