
日本談義集(周作人)
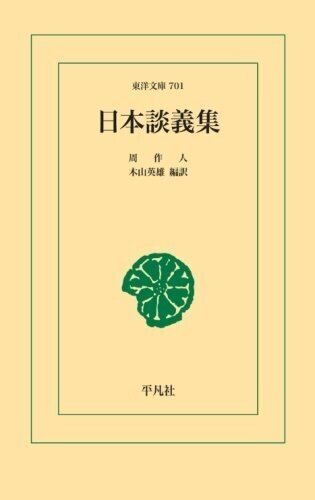
周作人 著
木山英雄 訳
平凡社2002
はて、ぼくはなぜ、周作人を読んでいるのだろう。
同じ日本で暮らす中国人として、自他ともに認める親日家・周作人の日本理解を読んでおきたかったのは、たしかである。魯迅の弟が、兄の冷徹なる目線とどこまで似通っていて、どこから稀代の読書家らしき彼なりの教養の深さがにじみ出るのかにも、興味がある。そして、なにより、日本軍が北京を占領したとき、彼がなぜ脱出せずに北京に残ることを選び、果てには傀儡政権の北京大学文学院長、文化部長をも務めたために、遂にその名声のすべてを失い、「漢奸」という最大限の罵詈雑言を一身に受けながら後半生を生きたのかこそが、ぼくの関心事である。
彼が戦前、戦中に書いたものを読み込んでいけば、少しは答えが見えてくるという楽観的な見通しでぼくはページを捲った。しかし、読めば読むほど、困惑は深まるばかりだ。周作人の筆致は、とりわけ日本を書くにあたっては、とにかく変化がないのだ。満州事変後に抗日の風潮が強まる1932年も、日本の中国侵略が益々本格化してきた1936年も、毛沢東が延安で彼を名指しして「漢奸文芸」と批判した1942年も、彼はただ淡々と日本留学を懐かしみ、東京の書店を思い出の中でめぐり、日本人の清潔感や繊細さに裏打ちされた文芸を激賞した。時折日本語の単語がそのまま交じる文章からは硝煙どころが、世俗的な臭いさえも消されており、この男は一体いつの時代を生きているのかと、ぼくは眉間にシワを寄せながら読み進めていった。
もちろん、最も素直に考えれば、周作人は深い考えがあってそうしたのではなく、ただ見て見ぬ振りで忌々しい外界の激変をやり過ごし、自分の世界に沈潜したかっただけと言うことができる。国破れて山河ありの状態で自分一人だけ平時と同じように暮らそうとしたのである。そうだとすれば、まさに老舎が『四世同堂』で彼と思しき人物を登場させ痛罵したように、「平時と同じ」などは荒唐無稽な幻想であり、そうした無抵抗な姿勢そのものが共犯だと言える。とりわけ、北京占領前までの彼が日本の軍国主義に一定の批判を行っていたが、それも「漢奸」となってからは完全に消えてなくなったことを考えれば、なおさら彼を劣悪なる文人根性の権化だと見なさざるを得ない。そして、これは大多数の中国人の周作人理解でもある。
だが、木山英雄は違う。良くも悪くも、完全に異民族に占領・統治された経験を一度も持たない日本に生きる彼は、戦前生まれとはいえ中国人の民族大義を感情の面で完全に理解することが難しい。しかしそのことはまた、彼がぼくのようにそれらの感情にとらわれることなく、「漢奸」の視点から自由になれることを意味する。木山は同情的に周作人の書いたものをとことん読み込み、彼が戦争についてほとんど書かなかったこと、いつの時代でも文芸しか語らなかったことこそが、文人としての一種の抵抗の現れであると考えた。あのような何を書いても政治色になってしまう時代において、腐心して政治の臭いをできるだけ文章から取り除いたと言うのである。その背後にあるのは、政治・軍事などより文学・芸術の方こそずっと価値があるとする周作人の信念であり、その信念に基づいて、彼は国家に殉じるのではなく、文学・芸術と、その底流をなす個人の日々の暮らしを全うすることを選んだのだと言うのである。
中国での一般的な見方における周作人を現実逃避だとすれば、木山の読みでの彼は現実を受け止め、より高い次元で現実を乗り越えようとしたと言える。素直な前者と比べ、後者は何重にも屈折しているが、周作人と兄の魯迅の屈折して読みづらい文章を考えれば、案外木山のほうが真意に迫っているのかもしれない。新史料が出てこない限り、いや、出てきたとしても、論争は延々と続くだろう。だが、今のぼくは真実がどうなのかにもはや興味がない。「なぜ周作人を読むのか」という疑問の答えが、すでに見つかったからだ。
その答えとなる一文を引こう。周作人が日本の侵略に対する中国人の反応を揶揄した文章である。彼は朝鮮で対日協力した李完用を「逆徒」、日本に抵抗した朴烈を「忠良」と呼び、次のように書いた。
「もし日本(あるいはその他の国)が中国を併合する気を起こしたばあい、中国にはたくさんの李完用が出るだろうと信じているが、ただし一両人の朴烈夫妻が出うるかどうかは疑わしいと思う。」
木山はこの一文皮肉にも彼自身の後の運命を「予言」したと読んだが、ぼくにはむしろ、「宣言」したように思えた。周作人は知っていたのだ、いざ自分が占領地に身を置けば、たとえ自分の思いはそうでなくても、周りから見れば自分が「李完用」になってしまうことを。上の文章は国民を諌めるものではなく、自分の弱さ、国民の単細胞さ、それらをひっくるめた人間の弱さを自覚した文人一流の自嘲だったのである。
そしてぼくは知っている、おそらく自分も、周作人の立場に置かれたら同じように行動してしまうということを。だからぼくは、彼の文章を借りて自嘲することで、少しでも悪くなり続けるこの時代への恐怖を和らげ、彼と同じ状況に陥らないようにするヒントを得たかったのである。
