フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊
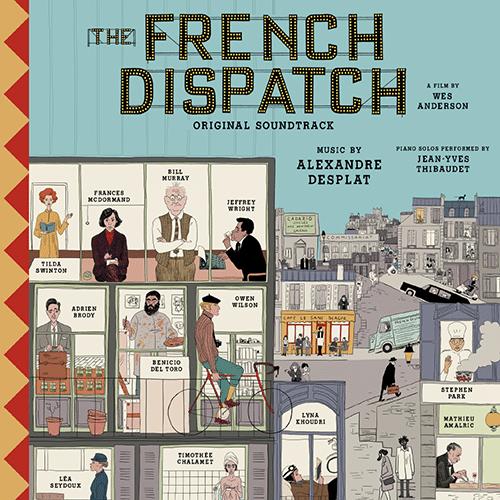
2022年
監督:ウェス・アンダーソン
出演: ベニチオ・デル・トロ
エイドリアン・ブロディ
ティルダ・スウィントン
レア・セドゥ
同監督作、グランド・ブダペスト・ホテル(2014年)を観賞してからの、劇場での本映画観賞。
雑誌を映画で表現してみたら
グランド・ブダペスト・ホテルでは、シンメトリーな構図、左から右、下から上へといった一定方向への動きが多用された。
そして何より、どのシーンを切り取っても、1枚の鑑賞作品となるような計算された画造りが特徴的な作風であるが、本作ではその画造りの緻密さはさらに増していた。
本作は廃刊が決まったフレンチ・ディスパッチという雑誌の最終号の記事を書く記者たちを描いたストーリーである。
そのため映画の内容自体が、フレンチ・ディスパッチという雑誌の記事を描いたものとなっており、まさに動く雑誌を映像作品として実現しているところが、本作の試みであり、他に類を見ない映像表現であると言えよう。
歯車仕掛けの映像
画作りの緻密さは、本作の冒頭から早速見て取れる。
ウェイターがトレーにグラスを置き、飲み物を注ぐシーンがあるが、その一連の動きだけを見ても、どれだけ緻密な手順を考えて撮影しているがよくわかる象徴的なシーンだ。
さながら歯車が幾重にも噛み合い、一つの動きから次の動きへ連鎖していく仕掛けのような映像となっている。
また静と動の使い分けも上手くなされており、基本的にある人が動いているときは、他の人は静止しているなど、常に一つのシーンの中に静と動が同居している。
文字とシーン
何故映画なのに、雑誌を読んでるかのような鑑賞体験になるのかと考えた時、やはりシーンの中に文字を入れていることが効果として大きいと思う。
アンダーソン監督の作品では、看板や刺繍、ラベルなど様々な物を使ってシーンに文字を入れることを多用している。
シーンに文字が入っていると観客はその文字がシーンのタイトルを表しているかのように、シーンと文字が紐付けされた一つのパッケージされた映像として見ることになる。
パッケージ化されたシーンは、まるで雑誌の挿画のような存在として観客の頭の中に印象づけられる。

一方で、文字の入ってないシーンもある。
文字を入れてないということは、自然と役者の演技やストーリーの展開の方へ観客の注目の力点が置かれる。
文字のないシーンは、いわば雑誌の文字面として表されているのだろう。
時に挿画のようなシーン、時に記事の文字面のようなシーンを織り交ぜることで、本作は1本の映画を雑誌を読んでいるかのような体験をさせることに成功している。
p.s
登場人物の回想シーンの役者と現在の役者の入れ替えを堂々と目の前でバトンタッチされる表現方法は初めて見た。
また今回、十数年ぶりにパンフレットを購入した。劇場に入る前は売り切れになっていたので落ち込んでいたが、映画が終わるころには再入荷していたためすかさず購入した。内容充実しており、劇中の補足資料や監督のインタビューが載っておりおススメ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
