
狩猟デビューまでの道のり①狩猟免許取得
狩猟デビューに向けて動き出してから約1年、ようやく狩猟免許を取得しました。
忘れないうちに、免許取得までの道のり、かかった時間や費用についてメモしておきます。
狩猟免許の取得までの道のり
前提として、狩猟デビューには、
① 都道府県が許可をする「狩猟免許」
② 都道府県公安委員会(=警察署)が許可をする「銃所持許可」
の2つが必要です(注)。取得は①「狩猟免許」と②「銃所持許可」のどちらからでもOKですが、わたしは最初、①の狩猟免許さえあれば即狩猟できると思い込んでいたため、先に狩猟免許から取得しました。
(注) そのほか、実際に狩猟を行うには、毎年9月頃に狩猟者登録を行う必要があります。
試験&予備講習の申込
狩猟免許取得には、狩猟免許試験に合格する必要があります。この狩猟免許試験にはⅰ)知識試験とⅱ)実技試験があり、
ⅰ)知識試験(=3択式の筆記試験)
ⅱ)実技試験→①距離の目測、②鳥獣の判別、③猟銃の取扱い
となっています。このほかに、視力聴力四肢に問題がないかの簡単な適性試験もあります。
北海道の場合は、猟友会の狩猟免許試験予備講習が実施されていました。参加費が11,000円かかりますが、テキストをもらえるほか、知識問題出題のポイント、猟銃の取扱いについてレクチャーを受けられるので、狩猟免許試験の受験申込と同時に予備講習の申込もしました(狩猟免許試験は都道府県が実施しているので都道府県に、予備講習は猟友会に申し込みます)。

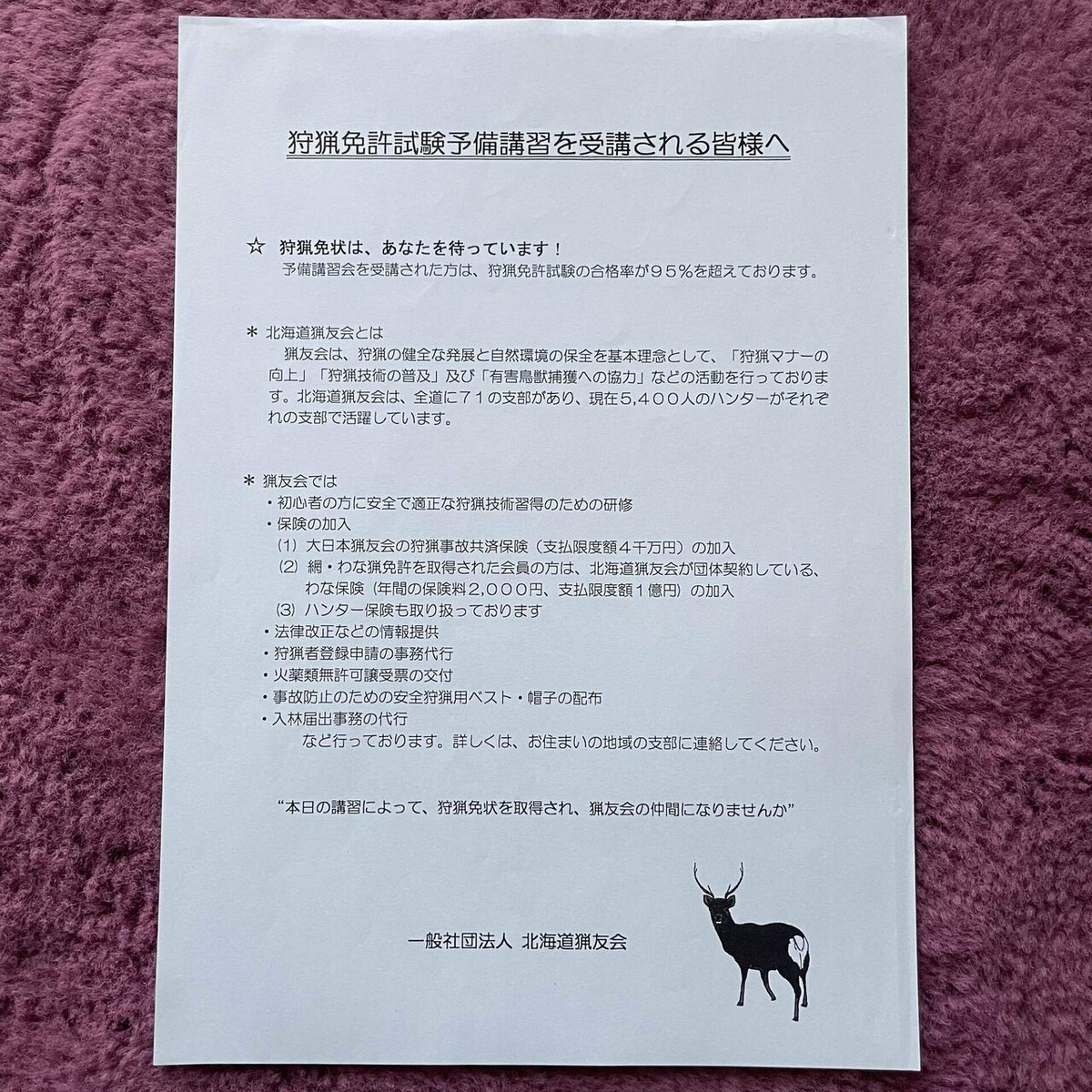
予備講習の申込は完了。
肝心の狩猟免許試験は定員制限が設けられ、毎回即定員に達し受付を終了してしまうため、受付初日の朝9時から北海道に電話をかけなくてはなりませんでした。最初は通話中のためつながらず…。何度かかけなおして何とか申し込みできました。お昼に北海道のHPを確認したら案の定受付終了していました。間に合ってよかった。
無事受付できたら、
受験料5,200円分の収入証紙を貼付した狩猟免許申請書
申請者の写真1枚(3.0cm × 2.4cm。6か月以内に撮影したもの)
住民票(コピー不可。マイナンバーの記載がないもの)
医師の診断書
切手を貼付した返信用封筒
を申請先に送付します。あとは後日受験票が送付されるので、忘れずに受験会場に持参します。
※ 医師の診断書は、統合失調症、そううつ病、てんかん等に該当しないことを記載してもらう必要がありますが、精神科医以外の医師による診断書も有効です。
わたしはかかりつけの病院がなく、どの病院でもこの様式の診断書を作成してもらえるのか分からなかったので、道職員の方にどの病院で書いてもらっている方が多いか聞きました。教えていただいた病院は、同じような目的で受診するハンターが多いようで、「狩猟免許申請用ね」とすぐに診断書を作成してくれました。費用は1枚3,300円でした。

予備講習と試験勉強
11月28日。朝9時集合(時間厳守)で、日が暮れるまでみっちり講習です。

予備講習の参加者は20人程度で、わたしのほかに女性は2名いました。部屋の机には銃と弾、金属製のわなが複数並んでいました。
予備講習に参加するまで知らなかったのですが、わなの使用にも狩猟免許が必要となります。狩猟免許といっても銃猟の免許とは限らず、何を用いて猟をするかによって以下のように免許の種類が分かれています。
第一種銃猟免許(装薬銃及び空気銃) ←今回取得するもの。
第二種銃猟免許(空気銃)
わな猟免許
網猟免許
午前中は受講者に配布される狩猟教本を使った知識問題についての講義です。狩猟に関する法令や、狩猟可能な動物の種類、銃の部位の名称、弾の口径と飛距離…覚えることだらけですが、試験に頻出するところ、試験関係なく大切なところをばっちり学べます。
お昼休憩は40分。買ってきておいてよかった。
午後はいよいよ猟銃の取扱いについて、模擬銃を使用してレクチャーを受けます(銃猟以外の免許取得を考えている人は午前の講義で終了)。日本で使用可能な猟銃には散弾銃とライフルがありますが、最初の10年間は散弾銃しか所持できないので、散弾銃の取扱いについて教わります。レクチャーの後は、1人ずつ銃の点検、組立て、分解、射撃姿勢など一連の動作を行ったほか、試験に出題される銃の受渡しなどの団体行動時の動作を3人1組で行います(これが緊張した)。
銃口を人に向けない、むやみに引き金に指を入れない、など当然に思えることでも、実際に銃を持ってみると無意識にやってしまいます。実技試験は減点方式。これをやってしまうと大きく減点されるので要注意。
この時初めて銃を手にしましたが、なかなか重い…。パーツのひとつひとつが大きくて重いので、組立てもスムーズにいきません。
ありがたいことに午後の時間は全て猟銃の取扱いに充てられており、納得がいくまで銃を触ることができました。予備講習は17時までの予定でしたが、「来週の試験はこれでバッチリだ」と思った人は先に帰ってもOKだったので、15時前に帰る人もいました。わたしは16時半くらいまで銃の組み立てを練習させてもらいました。
おかげで猟銃の取扱いはバッチリできるようになりましたが、知識試験や鳥獣の判別などの自力で覚える部分は、試験までの1週間で頭に叩き込む必要があり、予備講習でもらった例題集を1周しました。
鳥獣の判別対策はお手製のカード(狩猟読本の狩猟鳥獣のページをコピーして裏に鳥獣名を書いたもの)と、このサイトを活用しました。

試験当日
試験当日。会場に入ると予備講習に参加していた人を結構見かけて、少し緊張がほぐれました。最初の知識試験は、3択問題が30問出題され、21問以上の正解で合格です。試験時間は90分です。解き終わった人は30分経過すれば退出可能で、ほとんどの人が早く解き終わっている印象でした。試験後すぐに合格者が発表され、知識試験の合格者だけが次の適性試験・実技試験を受験できます。知識試験はほとんどの人が合格していました。
適性試験は簡単な健康診断という感じ、視力と聴力の検査の後、試験管の前で手足をプラプラ動かしたら「合格」と言われました。
「距離の目測」「鳥獣の判別」「猟銃の取扱」からなる実技試験は持ち点100点からの減点方式で、31点以上の減点で不合格です。

距離の目測試験は、試験官と外の見える窓がある廊下へ行き、試験官が指さす窓から見える建物や電柱などの距離を10m、30m、50m、300mの中から答えます。
鳥獣の判別試験も試験官と1対1で行われ、試験官が掲げる紙に描かれた鳥獣のイラストを見て、狩猟鳥獣かどうかを答えます。非狩猟鳥獣の場合は「獲れません」と答えればOKですが、狩猟鳥獣の場合は「獲れます。ニホンジカ」というような感じで鳥獣名も答えなければなりません。
猟銃の取扱試験は、3人1組での試験です。試験官数名に見守られ緊張しましたが、先週の予備講習で練習できたおかげで、一番心配だった銃の組立も問題なくできました。
これにて試験終了。最終合格者の発表は当日中には行われず、後日試験結果を郵送するとのこと。外に出れたのはちょうど13時くらい。
試験から3日後、試験の合格通知と都道府県知事名の狩猟免許が郵送で届きました。これにて無事、狩猟免許取得です。
銃所持許可の取得までの道のり
銃猟をする場合は狩猟免許に加え、銃所持許可の取得が必要です。
銃所持許可の取得までの道のりについては、次回の記事で↓
