
2024年9月のまとめと読書記録 「キュラソー・ビザ」展と講演会&デ・キリコ展その他
9月は、1日にチェコ研究旅行から帰ってきて、すぐに関西チェコ/スロヴァキア協会の機関誌『ブルタバ』に短文を執筆しました。字数が少ないコーナーだったので、旅先での発見を短くまとめて、「旅の記録をブログに書いていきます、見てね」みたいなことを書いたのに、その後、旅の記録はほとんど進んでいません。少しずつ進めていくとします。
そのあと一週間弱で大学の紀要に原稿を提出。春休みに半分くらい進めていたものを完成させました。こちら校正も済んで、11月頃には発行される予定です。大学教育実践系(読書促進モノ)です。
その紀要、所属学部の特集号というのがあって、そこにしか出せないものだと思い込んでいたら、年6回どの号でも投稿可能とわかりました。それなら、あれこれ手を付けているものを小まめに出せるやん! といって、授業期間中は厳しいので、次は春休み~GWあたりが勝負かな!
中旬には、ピースおおさかの展示と講演会に行ってきました。夏にU先生や学生君とも行ったところですが、今度は上息子とです。

企画展と講演会のテーマは、「キュラソー・ビザ ―ズワルテンダイク・オランダ領事と「命のビザ」の知られざる原点―」。杉原千畝が発行した通過ビザで、欧州の主にユダヤ人らが日本を通過して、第三国へ逃れることができましたが、それはオランダ領事が発行した通称「キュラソー・ビザ」があってこそのことです。

常設展示、企画展示を見て、みっちりお話を聞いたあとは、近くの山王美術館へ。

同館所蔵の佐伯祐三、荻須高徳、藤田嗣治の絵画を、ワンフロアごとに展示する企画です。
山王美術館は、スタッフの方の感じが良くて、無料のお茶コーナーもあって、川のそばという抜け感も〇!
そうしていると秋学期。ドキドキの健康診断の結果はオールAでひと安心!
授業も、各科目、今学期は人数が少なめで(悪評でも立ったか?)、より丁寧にできそうな予感。
月末には、久しぶりにお友達とお出かけ。神戸市立博物館に、デ・キリコ展を観に行きました。楽しかった♪

と、原稿執筆で月の1/3ほどを費やした分、読書はあまり振るわずでした。でもアウトプットも大事。そういうときもある!
9月の読書メーター
読んだ本の数:7
読んだページ数:2324
ナイス数:342

なぜ働いていると本が読めなくなるのか (集英社新書)の感想
現在の働き過ぎと読書を論じた自己啓発系の本かと思ったら、前半は明治からの労働と読書の関係を文献から読み解き、後半ようやくタイトルへの著者の考察が始まる。本全体の構成や流れ、文体の統一感や雰囲気などのバランスが若干悪い気もする。とはいえ興味深く読んだ。とくに前半は流れが良くスムーズに読めた。先行研究の蓄積が効いているのかな。
読了日:09月12日 著者:三宅 香帆
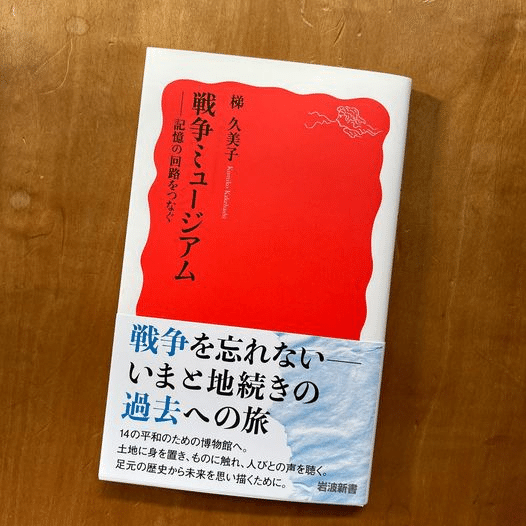
戦争ミュージアム──記憶の回路をつなぐ (岩波新書 新赤版 2024)の感想
国内14館の戦争関連の博物館・美術館見学記。いろいろ行ったつもりだが、このうち6館しか行っていない。存在や史実も知らなかったところもあり。もっとも衝撃を受けたのは石垣島の八重山平和祈念館。戦場にならなかったが多くの犠牲を出した「戦争マラリア」の悲劇を伝える。軍の命令でマラリア罹患の危険性が高い地域に強制移住させられた住民が多数病死したという。ほかの館も順に訪ねたい。
大久野島毒ガス資料館(済)、予科練平和祈念館(未)、戦没画学生慰霊美術館無言館(済)、周南市回天記念館(未)、対馬丸記念館(未)、象山地下壕(松代大本営地下壕)(済)、東京大空襲・戦災資料センター(済)、八重山平和祈念館(未)、原爆の図丸木美術館(未)、長崎原爆資料館(未)、稚内市樺太記念館(未)、満蒙開拓平和記念館(未)、舞鶴引揚記念館(済)、第五福竜丸展示館(済)
読了日:09月14日 著者:梯 久美子
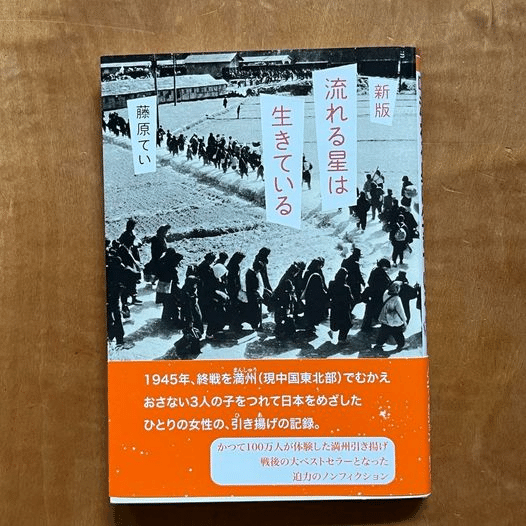
新版 流れる星は生きている (偕成社文庫)の感想
元同僚先生のおすすめ。見比べず買ったこのバージョンは児童向けに編集されたものだった。それでも満州からの引き揚げの壮絶さはこれでもかというくらい書かれているので、1949年の初版と読み比べようかなと思ったが、とりあえずこの作品を分析した末益智広氏の論文を2本読んでみた。すると、この作品は版によって手が加えられたり削られたりしているとのこと。そして、初版から大ヒットし引揚げ文学の代表格になるが、家族愛ばかりに焦点が当たっていったという分析がされていた。余力があれば、そのうち1949年版も読んでみよう。
で、初版のあとがきには、この作品は小説として書いたと明言されているとのこと。主人公と家族が実名なので、全編ノンフィクションと捉えられがちだが、実在の人物や実際の出来事、聞いたことなどを素材にしてはいるものの、人物名は仮名で、体験そのままを記録したものではないとのこと。読んでいて、こんなにあけすけに書いていいのかしらと思ったが、なるほど納得。とはいえ、絵空事ではないだろうなという生々しさがあって、苦難のときに出てしまう人の卑しさにげんなりするエピソードに満ち満ちている。
同じく貨車に詰め込まれて移送されたユダヤ人の経験談でも水がなくて苦しんだという回想が頻発するが(ただしそのほとんどは封印されていて水はバケツ一杯しか置いていない)、『世界でいちばん幸せな男』には、父が、なけなしの水を同じ車両の全員に公平にできるだけ長く行き渡るよう仕切って、長い移送を乗り切った話があった。その場に居合わせた人たちの関係性や、共同体または連帯意識の有る無し、優れたリーダーがいるかいないかで、これほど違うのだなぁ。災害時の避難所でも、こういう差が生じているのだろうなあ。
それにしても、女性子ども老人病人ばかりで放置されて、警護も武器もなく、財産も尽きて、しかも乳幼児を抱えた状態で、自分だったら生き延びられただろうか。まず無理だろうな… 読了日:09月15日 著者:藤原 てい

双頭の悪魔 (創元推理文庫) (創元推理文庫 M あ 2-3)の感想
夫氏が借りてきたのを私も。有栖川有栖氏の作品はランダムに何作か読んだが長編の方が好みかも。事件らしき事件が起きるまでの記述が丁寧で。本作は廃村跡につくられた私有の芸術村とその手前の過疎の村が舞台。謎解きよりも芸術村の面々とその暮らしや鍾乳洞、廃校となった小学校と過疎の村の情景、通信手段が電話か郵便しかなかった時代の雰囲気が面白かった。でも感想を見ているとそこが退屈と思う人が多いみたい? 殺人現場の横溝っぽさも時代を感じてにやりとした。
読了日:09月16日 著者:有栖川 有栖

南の島に雪が降る (ちくま文庫)の感想
読書メーターで教えていただいて、著者を意識せず読み始める。姉の沢村貞子、甥の長門裕之、津川雅彦と出てきて、えっ! 戦後も活躍された役者さん本人の手による回想記だった。著者が衛生伍長として渡ったニューギニアのマノクワリでは、戦闘はほとんどなかったが、食料が尽きて病気や飢えが蔓延していく。イモを育てるくらいしかやることがなく、先が見えない状況に、兵士の士気は下がり、いざこざが絶えなくなる。そこで、上官の命により、著者が班長となり、演芸会を催すと大盛況。本格的な活動を継続することになる。
幹部層の肝いりで資材も人材も惜しみなく投入され、立派な演芸場が造られる。各部隊から演芸班に参加したいという兵を集めてオーディションしたり、慰問に行ったときにスカウトしたりしてメンバーも揃っていく。誰もが観覧を楽しみにし、順番が回ってくるからと瀕死の兵が生きる気力を見せたり、観覧後に亡くなったりと、単なる娯楽を超えた活動になっていく。やるからにはと、メンバーもそれぞれの力をフルに発揮し、あるいは開拓して最高の芸を披露する。あまりに人気のため、毎日毎日、文字通り休むことなく上演したという。
とはいえ、演芸(演劇)だけではやっかみも生じるだろうからと、日中は畑仕事にも従事し、夕方以降は練習や上演と、休日どころか休む間もない日々だったとのこと。著者は、配置転換になる幹部に伴われて内地に戻るチャンスもあったが、自分たちを待つ兵と舞台を捨てられずマノクワリに残る。これほど充実した活動ができたのは、戦闘がなかったということもあろうが、上官らの決断力、リーダーシップが大きいように読んだ。涙を誘うエピソードもあるが(タイトルにまつわる部分などはとくに)、明るく軽妙な文章で、とても面白い。
読了日:09月18日 著者:加東 大介
関西ウーマン信子先生のおすすめの一冊で取り上げました↓

〈寝た子〉なんているの? ー見えづらい部落差別と私の日常の感想
著者は、関西の被差別部落出身で東京で解放運動に取り組む両親のもと東京で生まれ育つ。部落差別はないものと思われている環境で孤立感に苦しみ、解放運動の組織中心主義にも疑問を抱き、自分らしい取り組み方を模索する。高校卒業後は映画製作を学び、そののちwebでの活動にたどり着く。子ができる頃から、セクシュアリティなど、著者自身意識してこなかった、部落差別以外のマイノリティとマジョリティの問題にも目を向けるようになる。
読了日:09月21日 著者:上川 多実

聞く技術 聞いてもらう技術 (ちくま新書 1686)の感想
生徒・学生指導やプレゼンの心得かと思ったが、著者は臨床心理士で、もっと人間関係に寄ったものだった。編集者によるインタビューに対して語ったものをベースに作った本だそうで、とても読みやすく、あっというまに読み終わる。それだけに頭や心に残らなかった。でもそれは今現在の私には刺さらなかったというだけで、救われる人も多いのだろう。ただ、著者が会議で話を聞けずスマホをいじって注意されていたというエピソードにはなんというか…いやそういう人だからこそ、こうしたテーマを追究しようと思うのか…?
読了日:09月30日 著者:東畑 開人
読書メーター
