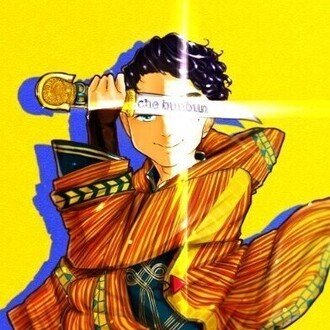映画と美術#3『何処』パフォーマンスアートにおける緊迫感について
※この記事は無料で最後まで読めます。
▷キーワード:パフォーマンスアート、キュビズム
赤き僧服を纏った男がゆっくりゆっくりとパリの街を歩く。時間に追われ忙しなく動く人々とは異なる時間がそこに流れる。ツァイ・ミンリャンがリー・カンションと共に撮り続ける「行者」シリーズは、30秒近くかけて一歩を踏み出す行者の姿を通じて我々に新しい感覚、思索、対話のチャネルを開く。「西遊記」のモデルとなった僧侶・玄奘に魅せられた監督は、世界の様々な場所をリー・カンション演じる行者に歩ませるまさしく《Reincarnation》といえる内容だ。
第9作目にあたる『何処』は、フランス・パリにあるポンピドゥー・センターにて開催されたツァイ・ミンリャン回顧展へ合わせて制作された作品である。本作は「行者」シリーズとして最高傑作のパフォーマンスアートに仕上がっており、「映画」という境界を通じて異なる時間が衝突する瞬間を目撃することとなる。
車通りの多い場所で行者は歩む。カメラは微動だにせず目の前を捉え続ける。当然ながら車が通りかかり、彼が見えなくなる時間が発生する。再び行者の姿が露わになると、背後のショーウィンドウから男が彼のことを覗き込み写真を撮る。扉を開けて出るかどうかの妙な時間が流れ、やがて開かれる。しかし、男は行者に話しかけず去ってしまう。
10作目の『無所住』と比べると、街行く人々の多くは行者に興味を示しているようで、遠巻きに、時に隣にピースサインで立ち写真を撮る。だが、行者は微動だに周囲の行動に応じることはない。パフォーマンスアートとは、パフォーマンスに対して他者がどのように反応するか、その関係性によって成立するもの。「行者」シリーズは無反応の役割を映画のショットとして並べることで理論化に成功しているといえる。人は異様な存在を観た時に、それに対する反応を期待しアクションを起こす。しかし、「無反応」だった場合に、次第に飽きて去って行ってしまう。学校でのからかいやSNSでのクソリプに対処法に「無視」があるのだが、その効能が描かれる。実際に、中盤では白人女性と黒人が意地悪に絡んでくる場面がある。パフォーマンスが失敗に終わってしまうかもしれない緊迫がありつつも、ひたすら無視し続けた結果、「やめちまえ、モンゴル野郎!」と差別的な言葉を吐きながら去っていくのである。現代社会は企業や国家が人々のアテンションを取り合うものとなっている。刺激的な情報が蔓延し、人々はそれに反応させられる。そのような社会に対する批判が込められているといえよう。
また、『何処』ではキュビズム作品を背に行者を歩かせたり、巨大な白い紙にランダムに線が引かれていく中を蛇行することなく踏み歩く場面がある。これらの場面からは、人間の肉体や行動に対する抽象化のプロセスが浮かび上がる。人間はどのように歩き移動するのか?複雑化する社会で自分を信じて前を進む様を象徴的に捉えているのである。
『何処』Where(2022年)
製作国:台湾
上映時間:91分
監督:ツァイ・ミンリャン
出演:リー・カンション

映画ブログ『チェ・ブンブンのティーマ』の管理人です。よろしければサポートよろしくお願いします。謎の映画探しの資金として活用させていただきます。