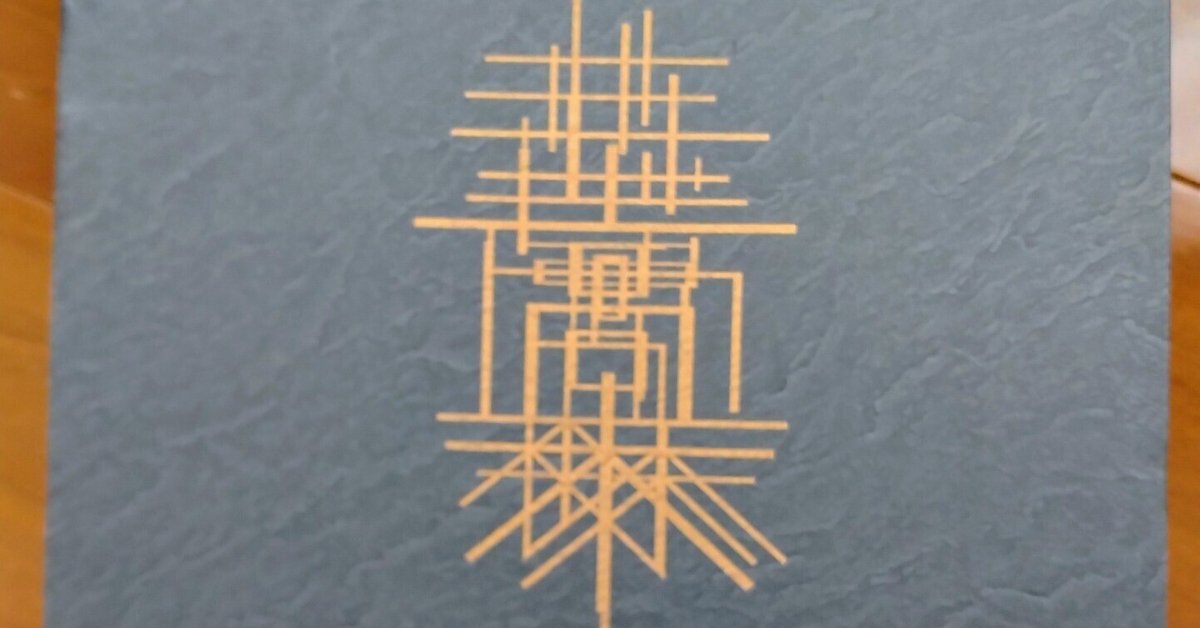
4月22日は「アースデー」なので藁のことを考えた
4月22日は「アースデー」だそうです。当日のラジオで知りました。
地球のために活動する日。地球のことを考える日。つまり環境について考えたり活動したりする日なのでしょう。
初めて聞いた言葉ではありませんが、意味をキチンと理解していませんでした。
私はこの日を「藁のことを考える日」にしました。
生活のなかの藁
現在の生活で身近な藁細工はしめ飾りです。年末になるとスーパーの店頭に並び、それを見ただけで「歳の瀬だな」と感じます。
それ以外には何があるでしょうか。
残念ながら答えがするりと出てきません。でも、現在も藁製品を作る人たちがいて、藁製品が売られています。鍋敷きとか猫のベッドというか猫の居場所(ネコチグラ)とか。
少数派です。藁という素材を考えると少ししか使われていないのは本当に残念です。
オヒツイレの思い出
かくいう私も藁製品を使っていません。子どもの頃に母の実家でオヒツイレを使っていたのをおぼえていますが、それ以外のものの記憶がありません。
ご飯が炊けると木製のオヒツにご飯を入れて、さらに保温のためにオヒツを藁製のオヒツイレに入れるのです。藁は保温に優れているので、しばらく温かいご飯が食べられます。しかも電気は必要なし。
現在のように電気代を気にしながら生活をしていると、これはありがたいものだったとつくづく思います。
現在もオヒツイレは作られていて、通販などで買い求めることができます。
循環する藁
藁の良さは何よりも、最後は肥料として使われて次の藁(稲)を育てることにあります。
お米の収穫とともに藁も収穫され、品物などになり、最後は肥料となってお米や藁を育てる…まさに持続可能な素材です。
この藁のシステムが社会にきちんと構築されれば、現在の環境問題なども解決されていきそう、と思います。
具体的に何をどうすればいいのかはわかりません。どうすれば藁がもっと利用されて環境が良くなるのか、もっと妄想をたくましくしないといけませんね。
写真は宮崎清著『図説藁の文化』法政大学出版局1995年の外函
