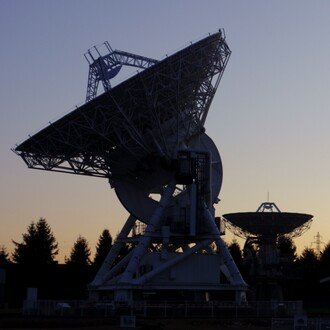H3ロケット5号機、打ち上げ日を再設定 - 天候不良で2月2日に
宇宙航空研究開発機構(JAXA)は2024年1月30日、H3ロケット5号機の打ち上げ日を再設定すると発表した。
当初は2月1日に予定されていたが、2日に変更された。天候の悪化が予想されるためだという。打ち上げ時刻は変わらず、17時30分00秒から19時30分00秒の間となっている。
また、2日の打ち上げについても、天候状況などを踏まえ、31日以降も引き続き確認するとしている。
H3ロケット5号機は、内閣府の準天頂衛星「みちびき6号機」を搭載して打ち上げる。また、4号機に引き続き、将来のロングコーストGTOミッションに向けたデータ取得も行う。
天候悪化の予報で打ち上げ日再設定
30日に開催された打ち上げ前ブリーフィングにおいて、JAXA H3 プロジェクトチーム プロジェクトマネージャーの有田誠さんは、再設定について、「2月1日は、打ち上げ時刻あたりで、射場周辺には雷、強風、雨の予報が出ている」と説明した。
打ち上げの制約条件では、ロケットの発射前、飛行中に空中放電(雷)を受けないことや、雨量や風速などが事細かに定められており、条件を満たせない場合は打ち上げができない。
また、ロケットの飛行経路上に、氷結層が発生する予報も出ているという。氷結層(雲の中の0℃~-20℃の領域)では、氷粒の衝突で電気が帯電しやすい。この中をロケットが通過すると雷を誘発し、機体に問題が生じる恐れがある。
さらに、雲が低く立ちこめ、雲底高度の制約も満たせない可能性もあるという。打ち上げの制約条件の中には、ロケットを打ち上げてからしばらくの間は、目視で機体が見えることが定められており、雲が低く立ちこめている場合(雲底高度450m未満)には、打ち上げができない。
なお、2日の打ち上げの可否についても、天候状況などを踏まえ、1月31日以降引き続き確認するとしている。
とくに、2月1日から2日に日付が変わるあたりで、前線が通過することが予想されており、悪いほうに傾くと、ロケットを組立棟から射点へ移動させる機体移動に影響が出る可能性があるという。
ただ、その後天候は回復し、打ち上げ時間帯はおおむね良好になる予報となっていることから、2日に打ち上げ日が再設定された。
機体移動時の天候について、有田さんは「予報は2つに割れている。そのうちひとつは前線の通過が遅れる可能性を示唆しており、その場合、機体移動の時間帯に、雷が発生するかもしれない。ただ、もう一方の予報では、少し早く前線が通過することを示している。私たちとしては後者に期待をかけ、天候を注視しながら、機体移動のタイミングを見計らいたい」と説明した。
そのうえで、2日が難しい場合には、「2月3日も打ち上げられる可能性がある」とした。
H3ロケット5号機のミッション
H3ロケット5号機は、内閣府の準天頂衛星「みちびき6号機」を搭載し、種子島宇宙センターから打ち上げる。
機体形態はH3-22S(LE-9エンジンが2基、SRB-3が2本、ショート・フェアリング)で、エンジンや、試験機1号機の失敗を受けた改修なども含め、3号機、4号機と同じ仕様である。
ロケットは種子島宇宙センターで組み立てられたあと、点検を経て、1月26日に衛星の入ったフェアリングを搭載した。そして、27日に最終機能点検、29日にリハーサルなどを行い、ここまで順調に準備が進んでいるという。
カウントダウンシーケンスでは、「射場系準備完了」のタイミングが、従来の420秒から410秒に変更された。従来は「安全系準備完了」と時間が重なっていたため、作業するうえで煩わしい、紛らわしいという問題があったことから、単に時間をずらしたためで、大きな変更ではないという。
ロケットは打ち上げ後、太平洋上を東南東方向に向けて飛行する。3号機、4号機と同様に、第1段エンジン燃焼フェーズにおいて、エンジン推力を100%から約60%に絞るスロットリングを行う。これは、加速度を緩やかにするためのものである。
そして、打ち上げから約29分後に、近地点高度約370km、遠地点高度約3万5586km、軌道傾斜角22度の静止トランスファー軌道で、衛星を分離する。
衛星分離後には、将来のロングコーストGTOミッションに向けたデータ取得も行う。これは、静止衛星を効率よく打ち上げる技術の開発のために行うもので、ロケットの第2段機体を通常よりも長く飛行させたうえで、第2段エンジンを再々着火する。これにより、衛星を静止軌道により近い軌道に送り届けることができるようになる。
このデータ取得では、ロングコースト中の第2段タンクや配管内の推進薬(液体水素と液体酸素)の状態や、エンジンが再々着火可能な状態かどうかを調べるため、温度や圧力などのデータを取る。
実施にあたっては、事前に解析を行っているものの、実際の宇宙空間でどうなるかをデータを取って調べることで、その解析の確からしさを確認する。
なお、実際のエンジンへの再々着火は行わない。
同様のデータ取得は、昨年11月に打ち上げた4号機でも行われ、正常にデータ取得を完了し、現在は解析を進めている段階だという。今回の5号機でも、基本的には同じデータを取るとし、データの数を増やし、確度を上げることが目的だとしている。
実際のロングコーストGTOミッションは、2025年度に予定されている「 技術試験衛星9号機(ETS-9)」の打ち上げで実施される予定となっている。
この技術が実用化されれば、H3ロケットの競争力の向上が期待される。商業打ち上げ市場への本格参入に向けた、重要な一歩となる。
参考
JAXA | H3ロケット5号機による「みちびき6号機」(準天頂衛星)の打上げ[再設定]
https://www.jaxa.jp/press/2025/01/20250130-1_j.htmlみちびき6号機×H3ロケット5号機特設サイト | ファン!ファン!JAXA!
https://fanfun.jaxa.jp/countdown/h3f5/
いいなと思ったら応援しよう!