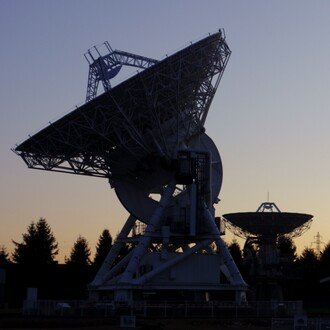「X線分光撮像衛星(XRISM)」と「小型月着陸実証機(SLIM)」の和名について
2023年8月28日、「X線分光撮像衛星(XRISM)」と「小型月着陸実証機(SLIM)」を搭載したH-IIAロケット47号機の打ち上げが予定されています。
XRISMはX線で宇宙を詳しく観測する衛星で、約7年前に悲劇に見舞われたX線天文衛星「ASTRO-H(ひとみ)」が担うはずだったサイエンスを、早期にかつ確実に回復することを目的としています。一方のSLIMは日本初の月面着陸を目指すとともに、将来の高度な月探査への応用を見越した探査機です。
XRISM(クリズム)という名前は、日本語の計画名である「X線分光撮像衛星」をそのまま英語にした、「X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission」の頭文字から取られています。また、X線の"分光"をする衛星であること、そして、理科の実験でおなじみなように、太陽の光などを分光するときはプリズムとも読みがかかっていることが選考の理由とされています。
SLIM(スリム)もまた、「Smart Lander for Investigating Moon」の頭文字から取られたものであると同時に、探査機が"小型"であるということにもかかっています。
ところで、JAXAの科学衛星――つまり旧ISASから続いてきた科学衛星は、伝統的に、アルファベットのコードネーム(「ASTRO-H」など)のほかに、関係者によって和名の愛称(「ひとみ」など)もつけられてきました。
アルファベットのコードネームは、打ち上げ前の開発段階から呼ばれ、またASTRO-A、B、C……というように、末尾のアルファベットは順番に、半ば機械的につけられてきました。一方、開発や運用に携わる関係者の方によって決められ、打ち上げ成功後に発表されてきました(例外的に、太陽観測衛星「ようこう」と月周回衛星「かぐや」は一般公募でした)。
この和名の発表は、宇宙ファンにとっては打ち上げ成功後の楽しみのひとつであり、いろいろと予想するのも楽しいものでした。

XRISMとSLIMには和名の愛称はつかない
しかし、XRISM、SLIMではともに和名の愛称はつけないとのことです。
その理由について、7月21日に行われたXRISMの機体公開時のぶら下がりで伺ったところ、
それ(XRISM)自体が、ミッションの性格をよく表すように、日本と米国のチームで決めた名前であること(「名は体を表すように考えてつけました」とのこと)
英語でも日本語のカタカナでも、どちらでも違和感なく読めるから
とのことでした。
思わず、「愛称をつけるのは伝統のようなものでしたが、あえてそれを止めるというのはなにか理由があるのですか」と聞いてしまったのですが、「ネガティヴな理由ではなく、あくまで前向きな想いから(の過去の慣例からの変更)です」とのことでした。
またSLIMについても、このときはXRISMの公開だったため直接の関係者の方はいらっしゃいませんでしたが、広報担当の方に伺ったところ、「SLIMについても同じ理由で愛称はつけず、SLIMのままです」とのことでした。
その後、SLIMのPeing -質問箱-で、「JAXAの科学衛星にはこれまで和名の愛称がついていましたが、SLIMに和名の愛称がつかないのはなぜでしょうか」という質問に対し、以下のように回答されています。
SLIMについては、打ち上げから着陸までの期間がそれまでの期間に比べて非常に短いこと、また、これまで長期にわたり一般公開などでSLIMとして親しんでいただいていることから、打ち上げ後もSLIMとして応援していただくことにしました。
少し残念ではあるのですが、大前提として関係者の想いは尊重されるべきだと思いますし、すでに「OMOTENASHI」、「EQUULEUS」という前例もあります。
なによりXRISMもSLIMも読みやすく、また、英語のコードネームと愛称とで2つ呼び名があり、さらに打ち上げ前と後で、主として使われる名前が変わるのは若干まぎらわしかったのも事実だったと思います(たとえば、打ち上げ前の時点での情報を調べたいときに和名で検索しても出てきません)。
(ちなみに、JAXA/ISASの科学衛星にはさらに、「第n号科学衛星」という名前もありましたが、これも第26号科学衛星ASTRO-H「ひとみ」を最後につけられなくなっています)。
今後、別の計画ではどうなるのかは注目です。たとえば「次期太陽観測衛星(SOLAR-C)」は、太陽観測衛星のSOLARシリーズのコードネームを受け継いだ名前で呼ばれています。
また、「火星衛星探査計画(MMX)」のMMXは、「Martian Moons eXploration」から取られたものですが、それ自体はなにかの単語にかかったものではなく、ちょっと味気ないようにも思います。また、科学畑、技術畑の人にとっては、intel製CPUのマルチメディア拡張命令セットのほうを思い浮かべてしまうかもしれません。
逆に、「初期宇宙・極限時空探査計画(HiZ-GUNDAM)」は、むしろ和名をつけずにそのままでいってほしいところです。
余談
ちなみに、XRSIMは「クリズム」が公式の読み方ですが、海外やJAXAの一部の研究者の方は「グリズム」と読むこともあるそうです。
Xanadu(ザナドゥ)やXerox(ゼロックス)など、英語ではXが頭につくと濁る発音になるので、ネイティヴ・スピーカーや海外生活が長かった方などは「グリズム」と読むほうが自然なのかもしれません。
この話は、前述のぶら下がりの中で出てきたもので、
Aさん「XRISMで『クリズム』は読みやすいですからね」
Bさん「あ、でもうちの⚪︎⚪︎先生は『グリズム』ですね。ESAの研究者でも『グリズム』って呼んでる人いますよ」
Aさん「ええ!広報さん、『クリズム』で統一するようにしといて!」
というやり取りがありました。
そのためか、この日以降、JAXAのWebサイトやTwitterでXRISMの話題が出てくるときは、「XRISM(くりずむ)」と表記されていることが多くなっています。

いいなと思ったら応援しよう!