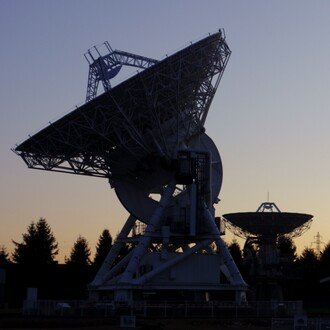H3ロケット3号機打ち上げ後 有田プロマネへの囲み取材 文字起こし
2024年7月1日、H3ロケット3号機の打ち上げ後に行われた、有田誠さん(JAXA H3プロジェクト・チーム プロジェクト・マネージャー)への、囲み取材の文字起こしです。
※基本的に発言をそのまま文字に起こしていますが、フィラー(「あのー」など)は削除しています。また、文章として読みやすくするため、元の発言の意味、内容を損なわない程度に、言葉を付け加えたり、削除したりしています。
Q:打ち上げを見ていたファンの方々に、メッセージをお願いいたします
A:JAXA H3プロジェクト・チームの有田です。この4月から、岡田前プロマネのあとを継いでプロジェクト・マネージャーを務めております。今回、3号機の打ち上げに向けて、皆さまの応援を頂戴し、誠にありがとうございます。
おかげさまで、3号機はほぼ完璧といえる成功ができたと思います。試験機2号機の成功がまぐれではないことを証明できたと考えています。
今後とも、応援していただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
※この部分については、NVS(ネコビデオ ビジュアル ソリューションズ)さんのYouTubeで、動画を見ることができます。
Q:記者会見で、「連続成功あるのみ、その一歩を踏み出せた」と発言されていました。あらためて、その意味合いや、連続成功の意義をうかがえればと思います。
A:まず、試験機2号機の成功がまぐれではなかったことを証明するということがありました。ここ(試験機2号機と3号機)で連続して成功させなければ話が始まらない、という思いがありました。
試験機1号機は失敗してしまいましたが、これからはもう1機も落とすことなく、連続成功させなければと(思っています)。一つひとつの機体に乗っていただく衛星は、それぞれが本当に大事なものですから、気持ちを込めて、一機一機、しっかり打ち上げていきたいと思います。
それが、ひいてはお客さまの信頼につながって、「自分の衛星を、ぜひH3に乗せたい」と言ってくださる方たちが増えていくことにつながるのではと思っています。
Q:有田さんが、ロケット開発の道へ行こうと思われたきっかけはなんですか。
A:思い返すと、兄が天文好きでした。兄に教わりながら、望遠鏡で星を見ることはありました。でも、どちらかというと、電車が好きだったり、家にある電化製品を片っ端から分解して母親に怒られたりと、機械が好きな少年時代でした。
なので、そのまま天文少年になるというよりは、宇宙と機械が結びついてロケット好きになったのかもしれません。そのへんは、あとから理由をつけて分析しているだけなのですけれども。
たぶん最初に(ロケットを)見たのは、小学校に入る前、5歳のときだったと思うのですが、「アポロ11号」の打ち上げで、これがおそらくきっかけじゃないかな。正直、はっきりとは覚えていないのですが、画面の向こうで、ボーっとした影の中で宇宙飛行士が動いているのがきっかけだったのか、あるいは「サターンV」ロケットを、子供ながらにすごいと思ったのでしょうね。
そうしたことが、心に焼き付いて、小学校の高学年になるころには「アポロ・ソユーズ・テスト計画」に夢中になりました。夜中だったにもかかわらず、ドッキングの様子をテレビで見ていました。
だから、そのころにはもうロケット少年になっていたのだろうと思います。それからずっと、変わらず来てしまいました(笑)。
Q:実際にロケットの開発に関わられるようになって、どんなことが醍醐味ですか。
A:機械っていろいろな音がするじゃないですか。その中でもロケットって強烈な音がしますよね。
じつは飛行機も好きで、飛行機もいい音がするんですよね。エンジンのゴォーっという音とか、コンプレッサーが回るキーンという音とか。回転する機械が大好きなんです。そして、ガスの噴射する音も大好きなんです。それを突き詰めると、ロケットに行き着くんですね。
なぜそれだけの音が出るかというと、強大なエネルギーを集約して、それをコントロールした状態で推進力に変えているわけです。ロケットというのは、ある意味人類が作り出した究極の機械だと思うんです。そこが醍醐味だと思っています。
Q:今回の打ち上げでは、30形態の実現に必須とされる、スロットリング機能の実証が行われました。今後、30形態の完成に向け、ほかにどういったことが必要なのでしょうか。
A:まだ、大きく2つ、越えなければならない課題があると思っています。
1つ目は、LE-9エンジンです。30形態は固体ロケットの助けを借りず、液体ロケットエンジンのLE-9だけで飛び上がるという、我々が経験したことのない、まったく新しいシステムへのチャレンジになります。
この成否を握っているのが、LE-9がきちんと力を出せるかどうか、しかも3基のエンジンが協調して、1基も乱れることなく、きちんと揃った推力を出せるかどうかにかかっています。
そのために、今号機のように2基形態での実績を積み重ねて、「LE-9は大丈夫だ」という自信をしっかり固めることが必要です。もちろん、いまでもかなり自信が固まってはいますが、さらに飛行実績を重ねていく必要があります。
2つ目は、ホールドダウン・システムです。30形態の発射では、LE-9が点火して燃焼がしっかり立ち上がったことを検知するまで、ロケット機体を地上の発射台に縛り付けておく必要があります。その仕組みをホールドダウン・システムと呼びます。
この仕組みがきちんと動作しないと、万が一、たとえば3基中1基のエンジンが途中で推力が落ちたときに、中途半端にリフトオフしてしまい、非常に危険なことになる可能性があります。それは絶対に避けなければなりません。
エンジンが正常に立ち上がったことを検知して、初めて4つのホールドダウン・システムを解放するという仕組みを、確実に作動させなければならないのです。
Q:今回のような22形態では、ホールドダウン・システムはどう動いていたのですか。
A:今回の場合は、X-18秒(打ち上げ18秒前)でホールドダウン・システムを開放しています。それまでは、風が吹くかもしれませんし、アボートしたときに安全に機体を戻すためという目的もあり、ホールドダウン・システムで機体を止めておき、X-18秒で火工品に点火して解放します。これは、試験機2号機でも同様の手順でした。
実のところ、22形態にとっては、ホールドダウン・システムは必ずしも必要というわけではありません。どちらかというと、30形態で必要なシステムです。ただ、30形態の打ち上げに向けた信頼性を高める意味もあって使っています。
また、30形態と2x形態では、基本的な考えが違います。2x形態では、2基のLE-9の推力が100%に達しても、全備質量を超えることはないので、リフトオフしません。固体ロケットブースター(SRB-3)に点火して初めてリフトオフしますから、ホールドダウン・システムは(本来は)いりません。
ところが、LE-9だけの30形態では、そうはいきません(=3基のLE-9の推力が立ち上がっていくなかで、あるタイミングで全備質量を超えてしまう)。固体ロケットは点火すればほぼ確実に燃焼を始めますが、液体ロケットはそうではなく、少し不安定になるときもありますので、推力の立ち上がりを、きちんと検知しないといけません。
LE-9の推力が立ち上がって、「上がりたい、上がりたい」と言っているロケットをぎゅーっと縛りつけておいて、発射のときにはバーンと火工品を爆ぜさせて解放する、そういう機構がきちんと動くかどうかは、未知の領域なのです。
Q:今後の打ち上げ予定について、しばらく22形態が続くのですか。24形態はいつになるかなどは決まっていますか。
A:次の4号機では、22S形態で防衛省さんの衛星を打ち上げます。24形態を初めて使うのは、「HTV-X」の1号機になるかと思います。
Q:LE-9のタイプ2について。6月から7月にかけて燃焼試験をやっているとのことですが、どういう状況ですか。また、タイプ2が完成と言えるまでに、どのようなマイルストーンがあるのですか。
A:LE-9をめぐっては、まず液体燃料ターボポンプ(FTP)のタービンの疲労が問題になっています。現在打ち上げに使っているタイプ1Aでは、性能を犠牲にしてタービンの共振を抑えるという対策を取っていますが、タイプ2に向けて、性能を犠牲にすることなく共振を抑えられる対策を施したFTPの試験を行っています。
対応策として、いわゆる「1の矢」と呼んでいる案のほかに、2の矢、3の矢と、転ばぬ先の杖で複数を用意していますが、当然、1の矢が最有力候補です。先日は、1の矢の対策を組み込んだ形態で試験を行いました。その結果は詳細な解析を行っているところで、発表はもう少しお時間をいただきたいのですが、悪い結果ではありませんでした。
それから噴射器についても、先日の試験で試しました。これについても、良さそうな結果が得られています。タイプ2の噴射器は、3Dプリンターを使って製造したものを使い、低コスト化を図っています。噴射器はとても複雑な構造をしていますので、3Dプリンターで造ることで、大きなコストダウンの効果が見込めます。
油断してはいけませんし、予断も許しませんが、もう少しで先が見えてくるのでは、という感触を持っています。
Q:その試験の結果、この対策仕様で行くとなったら、すぐタイプ2の完成となるのですか。それとも、また認定試験など、あらためて試験を行うのですか。
A:現在やっているのは、あくまでも、仕様を選定するための試験です。詳細に解析してみたらやっぱり駄目だった、ということもあり得ますから、試験結果のデータをよく見て、この対策でいいのか、2の矢など次の形態に変える必要があるのか、といったことを見極めることが必要で、いままさに、それをやっているところです。
そこで選定した仕様は、またちゃんと組み直して、あらためて認定試験をやる必要があります。
今後、最終的に選定した仕様で、エンジンを組んで認定試験をやって、そして打ち上げに供していく、という流れになります。
Q(鳥嶋):気が早い話かもしれませんが、H3の、次の世代のロケットについて伺えればと思います。H3の開発が始まってから10年が経ち、世界ではまた新しいロケットも出てきています。これから育っていくH3を、どう次につなげて、どんな次世代ロケットにしたいとお考えですか。
A:おっしゃるように、H3の先のことも考えなければいけない状況です。今回の3号機の成否が、まさにそういった(次世代のロケットの)話ができるかどうかの、大きな分かれ道だったのではないかと思います。
これまでは、H3の開発が2年遅れ、試験機1号機の打ち上げが失敗し、試験機2号機は成功したものの、まだ先はどうなるかわからないという状況が続き、なかなか次を見据えた流れが作れずにいました。
今回の3号機の成功は、その(次を見据えた流れが作れるようになるという)意味でも、大きな意義があったと思います。
この成功を受けて、いま進めているLE-9タイプ2エンジンや30形態のさらに先をどうするのか、JAXAの中でも考え始めていますし、文部科学省さんとも相談しながら、次世代のロケットをどうしていくのかを打ち出していければと思っています。
Q(鳥嶋): JAXAのロケット、日本のロケットといった枠を超えて、子どものころからの夢の延長線の先として、将来、どんなロケットを造りたいとお考えですか。
A:JAXAの社員として残された時間ももう長くないので、定年になったら、まずはちょっとゆっくりして、でもきっと、ゆっくりしているのも1年くらいで飽きるでしょうから、そのときには……そうですね、天才技術者の真田志郎が造ったような、波動エンジンが造りたいですね。昭和の相当マニアックな話で恐縮ですが(笑)。
あんな夢のような、無からエネルギーを生み出すようなエンジンができれば、理論的にはどこまででも飛んでいけますから、そんなものが造れればいいな、と思っています。
じつは、私自身、土星に行きたいとずっと思っているんです。
いま、イーロン・マスクが火星に行くって言っていますが、私は昔から、さらにその先に行きたいと思っていたんですね。JAXAで課長になる試験のときに、面接で「君は何がやりたんだい?」と聞かれて、「土星探査機の開発をやらせてください」と言っていたんです。
土星って、どの惑星の中でも一番きれいじゃないですか。だから、自分の目で見たいじゃないですか。そのためなら死んでもいいと思っているくらいなんです。
でも、それは許されないだろうから、せめて探査機を造って土星に飛ばしたい、なんてことを面接で言ったら、「さっさとやればいいじゃないか」と言われたんですけれども、そのあともずっとロケット開発から離してもらえず、ここまで来たという、そんなJAXAでの人生でありました(笑)。
だから、土星に行けるような宇宙船を造ることが、夢かもしれません。
Q:LE-9のターボ・ポンプの開発について。(タイプ2で導入予定の)共振を抑えるための対策によって、コストが増大することはないのでしょうか。それとも、量産することで増えた分は打ち消せるのでしょうか。
A:ターボ・ポンプはIHIさんに造っていただいていますが、我々(JAXA)もIHIさんに投資をしていまして、福島県の相馬市にIHIさんの大きな工場があるのですが、LE-9専用のエリアを作っていただき、そこにターボ・ポンプの部品を製造するための、かなりいい機械を複数導入してもらいました。
その稼働率がまだ上がっていないのが正直なところですが、当初考えていたところまで上げられれば、十分量産にも応えていけますし、同時に品質は上がり、コストは下がっていきます。課題もありますが、時間をかければ必ずうまくいくと思っています。
私もそこにはとても期待しており、H3のプロマネになって、初めて行った企業さんの工場でもあります。「期待しています。よろしくお願いします」とお願いしてきました。

いいなと思ったら応援しよう!