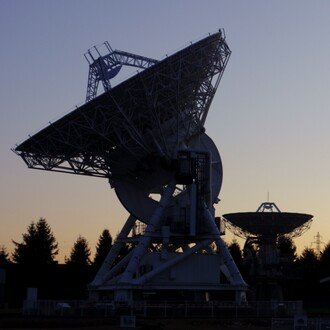中国の謎の衛星「遥感四十一号」は、世界最先端の"静止光学地球観測衛星"か?
中国航天科技集団(CASC)は2023年12月15日、地球観測衛星「遥感四十一号」の打ち上げに成功した。
遥感という名のつく衛星はこれまでに何十機も打ち上げられているが、その詳細はあまり明らかになっていない。そして今回の打ち上げは、これまで以上に謎や奇妙な点が多く、遥感四十一号はまったく新しい、革新的な衛星の可能性がある。

静止衛星、大型ロケット、新型フェアリング
公式発表によれば、遥感四十一号は中国空間技術研究院(CAST)が開発した衛星で、高軌道(静止軌道)を周回する光学地球観測衛星であるとされる。
遥感とはリモートセンシングという意味で、今回のような光学衛星のほか、合成開口レーダー(SAR)を積んだ衛星などがあり、そのデータは国土調査や作物収量推定、環境対策、気象予報、総合防災・減災などに用いるとされる。一方、米国など西側の専門家の多くは、軍事目的の偵察衛星として使用されているのではと推測している。中国の他の地球観測衛星と異なり、衛星の運用を担う組織、機関が明らかにされていないこと、撮影した画像が公開されていないことからも、そうした見方に拍車をかけている。
いずれにしても、その数字が表しているように、これまで数十機の衛星が打ち上げられている。
しかし、これまで打ち上げられた遥感衛星は、いずれも地球低軌道か太陽同期軌道に投入されており、静止軌道を回る衛星はこれが初めてである。なお、米宇宙軍による観測からも、遥感四十一号が高度176km × 3万5812km、軌道傾斜角19.5度の静止トランスファー軌道(GTO)に入っていることが確認されており、静止衛星であることが裏付けられている。
さらに、これまで遥感衛星の打ち上げには長征二号、四号、六号といった、小型や中型のロケットが使われてきたが、今回の遥感四十一号の打ち上げには、中国で最も打ち上げ能力の大きい大型ロケット「長征五号」が使われた。
長征五号のGTOへの打ち上げ能力は14tであり、その性能がフルに活用されたかどうかはわからないが、少なくとも長征三号(GTOへの打ち上げ能力は約5t)では打ち上げられないほど大質量の衛星である可能性が高い。
それを裏付けるように、今回の打ち上げで用いられた衛星フェアリングは、長さ18.5m、直径5.2mという大型の、これまで長征五号で使われたことのない新しいものだった。
こうしたことから、遥感四十一号は10t前後もある、寸法も大きな大型の静止衛星にして、光学地球観測衛星(偵察衛星)という、前代未聞の衛星の可能性がある。
静止軌道の光学地球観測衛星は、近年世界中で研究が活発な技術のひとつである。
従来の地球観測衛星は、地球を南北に回る極軌道に投入されるため、あるひとつの地点を常時、継続的に観測することはできない。複数の衛星を使えば擬似的に継続観測することはできるものの、それだけの数の衛星を打ち上げ、運用するハードルは高い。また、観測できる範囲が小さいという問題もある。
一方静止衛星であれば、赤道上空のある一点に静止し、眼下に見える地表の全体、あるいはそのうちのかなり広い範囲を、常時・継続的に観測することができる。
ただ、極軌道衛星が高度数百kmの軌道を回っているのに対して、静止衛星は高度約3万5800kmと桁違いに高い軌道を回るため、分解能(地表のものをどれだけ細かく観測できるかという能力)はあまり高くできない。たとえば極軌道衛星なら、数十cmの分解能をもつ衛星も多く、人の数や、車の台数や種類などを見ることも可能だが、静止衛星の分解能は100~数百mと粗く、従来は台風や雲の動きを見るくらいしかできなかった。
しかし近年の技術の発展により、静止衛星でも数十mから数mの分解能を実現できるようになり、広い範囲を継続的に、それも動画で観測できるようになりつつある。これにより、静止衛星でありながら、なにが、どこへ向かって動いているかなどをつぶさに見ることが可能になり、災害や気象、環境観測などに大いに役立つと期待されている。また同時に、軍事利用においてもメリットは大きい。
推定される遥感四十一号の性能
中国は2015年に初の静止光学地球観測衛星「高分四号」を打ち上げている。高分四号は約400×400kmの範囲を、可視波長では地上分解能50m、赤外線イメージャーでは分解能400m以上の解像度で撮影できるとされる。また2020年に打ち上げられた「高分十三号」は、分解能15mを達成しているとされる。
高い分解能を得るためには、望遠鏡を大きくすることが最も重要な要素のひとつである。遥感四十一号が長さ18.5m、直径5.2mのフェアリングが必要なほど大きな衛星であれば、主鏡のサイズは約4mに達するものとみられ、分解能数mを達成することも可能とみられる。
なお、中国科学院長春光学精密機械・物理研究所は2016年から2018年にかけ、直径3mのモノリシックSiCミラーと、 直径4.03mのSiCミラーの製造に成功したことを発表しており、この技術が使われた可能性がある。
仮に静止軌道から数mの分解能で観測できる性能があれば、中国が公式に主張するように国土調査や作物収量推定、環境対策、気象予報、総合防災・減災への活用のほか、米軍の空母など軍艦の動きや、場合によっては飛行場にある軍用機の動向なども監視できる可能性がある。
ちなみに、米国航空宇宙局(NASA)の「ハッブル宇宙望遠鏡」の主鏡は直径2.4mであり、そのもととなった光学偵察衛星「KH-11」も同じとされる。NASAの次世代宇宙望遠鏡である「ナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡」の主鏡も同じく直径2.4mであり、その主鏡はもともとKH-11などの偵察衛星を運用する国家偵察局(NRO)から提供されたものであることから、米国の光学偵察衛星は、現在も主鏡の直径は2.4m程度とみられる。したがって、もし遥感四十一号が一枚鏡を採用していれば、世界最大の望遠鏡をもった衛星である可能性がある(ただし、米国が秘密裏に、より大きな主鏡をもった偵察衛星を打ち上げている可能性は否定できない)。
一方で、折りたたみ式の主鏡である可能性もある。たとえばNASAの「ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)」は、主鏡を折りたたみ式にすることで直径約6.5mを達成している。ただ、JWSTは赤外線で宇宙を観測する宇宙望遠鏡であり、地球を可視光で観測する大型の分割式望遠鏡の実用例はなく、また技術的にも難しいため、中国が実用化できたかどうかは不明である。
また、中国が主張する光学地球観測衛星というのが嘘であり、巨大なアンテナによるSIGINT(電波諜報)衛星である可能性もある。同様の衛星は米国国家偵察局(NRO)も「オライオン」という衛星を打ち上げ、直径100mにもなる巨大なメッシュアンテナを広げ、通信やレーダーなどから出る電波を収集しているとされる。
なお中国は、今年8月13日に「陸地探測四号01星」という衛星を打ち上げ、準天頂軌道に投入している。この衛星は合成開口レーダー(SAR)を搭載しているとされ、中国本土および周辺地域の、全天候の準リアルタイムの観測が可能になるものとみられる。陸地探測衛星は、中国科学院(CAS)空天信息創新研究院(AIR)が運用する民間向けの地球観測衛星に位置づけられており、防災・減災及び地震観測、国土資源調査、海洋、水利、気象、農業、環境保護、林業などに活用するとされている。遥感四十一号もこれと同等、あるいはこれ以上の性能をもった、しかし軍事利用に重点を置いた衛星である可能性もある。
静止地球観測衛星をめぐっては、中国のほか、インドも2021年に、「EOS-03(GISAT-1、Geo Imaging Satellite-1)」を打ち上げている。ロケットの不具合により打ち上げには失敗したが、同衛星はマルチスペクトルで42mの分解能をもつとされ、早ければ2024年にも、代替機となる同型機「EOS-05(GISAT-2)」の打ち上げが計画されている。
また、日本でも宇宙航空研究開発機構(JAXA)が、2000年代初頭から「静止光学観測衛星」を研究している。

トップ画像クレジット (C) CASC
参考文献
China launches new remote sensing satellite - CASC
http://english.spacechina.com/n17212/c4011640/content.htmlYaogan-41 - CZ-5 - Wenchang - December 15, 2023 (13:41 UTC)
https://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=59865.0;allChallenges and strategies in high-accuracy manufacturing of the world’s largest SiC aspheric mirror | Light: Science & Applications
https://www.nature.com/articles/s41377-022-00994-34メートル口径SiC非球面光学反射鏡を中国が開発 | SciencePortal China
https://spc.jst.go.jp/news/180804/topic_3_01.htmlGSLV F10 EOS-03 Brochure
https://www.vssc.gov.in/pdf/PressKit/gslv_f10_eos-03_brochure.pdf静止光学観測衛星の研究状況について(宇宙航空研究開発機構 令和元年5月17日)
https://www8.cao.go.jp/space/comittee/27-anpo/anpo-dai32/siryou1-1.pdf
いいなと思ったら応援しよう!