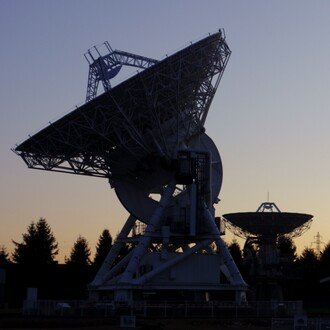H3ロケット4号機、26日打ち上げへ―初の静止衛星打ち上げ、将来の能力向上に向けた布石も
宇宙航空研究開発機構(JAXA)は2024年10月26日に、H3ロケット4号機の打ち上げを予定している。
4号機には防衛省の通信衛星「きらめき3号」を搭載する。H3にとって初めての静止トランスファー軌道への打ち上げとなり、さらに衛星分離後には、将来の打ち上げ能力向上を見据えた、飛行技術のデータの取得にも挑む。

H3ロケット4号機のミッション
H3ロケット4号機は、防衛省のXバンド防衛通信衛星「きらめき3号」を搭載し、静止トランスファー軌道(GTO)に投入する。H3にとってGTOへの衛星投入は初となる。
機体形態はこれまでの1~3号機と同じ「H3-22S」で、これはLE-9エンジン(タイプ1A)が2基、固体ロケットブースター(SRB-3)が2本、ショートフェアリングを使用することを示している。
打ち上げ予定時間帯は、10月26日15時44分から17時30分に設定されている。正確な打ち上げ時刻は、打ち上げ2日前に開催される打ち上げ前ブリーフィングで発表される。また、打ち上げ予備期間として10月27日から11月30日まで確保されている。
当初、打ち上げは同月20日に予定されていたが、H-IIAロケット49号機が天候による延期を経て打ち上げられたことを受け、再設定された。
H3は、JAXAと三菱重工が共同開発しているロケットで、現行のH-IIAロケットに比べてコストを下げ、商業打ち上げ市場での価格競争力を高めることを目指している。
9月18日には、三菱重工がフランスの衛星通信会社ユーテルサットと、H3の打ち上げで合意したと発表した。10月11日にはアラブ首長国連邦(UAE)宇宙庁との間で、H3を使った小惑星探査機の打ち上げ輸送サービス契約を結んだことを発表している。
H3は、昨年3月の試験機1号機の打ち上げは失敗したが、今年2月の2号機で打ち上げに初成功し、7月の3号機も成功した。こうした中、4号機も成功すれば、さらなる受注獲得への弾みとなることが期待される。

種子島からの打ち上げ制約を克服する「ロングコースト」飛行を見据えたデータ取得
今回の打ち上げでは、「きらめき3号」の軌道投入後に、将来の「ロングコースト」ミッションを見据えたデータ取得を行うことが計画されている。
「きらめき3号」のような静止衛星は、「静止軌道」と呼ばれる軌道で運用される。静止軌道は、赤道の上空約3万6000kmのところにあり、この軌道に乗った衛星は地球の自転と同じ速度で移動する。そのため、衛星から地球を見ると、ある面のみ見続けることができ、逆に地上から見ると常に衛星がある一点に静止しているように見える。この特徴から、通信衛星や気象観測衛星などが多く打ち上げられている。
ただ、この静止軌道に、ロケットで衛星を直接投入するのは難しい。そのため、通常静止衛星を打ち上げる場合には、静止トランスファー軌道(GTO)という静止軌道の一歩手前の軌道に投入する。GTOから目標の静止軌道までは、衛星が自力で、つまり衛星自身の燃料を使って飛行する必要がある。
ここで問題になるのが緯度である。静止軌道の真下、つまり赤道上からロケットを打ち上げたとすると、GTOの軌道傾斜角(赤道からの傾き)は0度になる。赤道上空にある静止軌道の軌道傾斜角は同じ0度であるため、衛星はすんなりと静止軌道に入ることができる。

ところが、H3が打ち上げられる種子島は北緯約30度にあることから、なにも工夫せずに打ち上げると、GTOに約28.5度もの大きな軌道傾斜角が付いてしまう。そのため、衛星はこの軌道傾斜角を打ち消すために、より多くの燃料を消費し、大きなエネルギーが必要となる。
具体的には、赤道直下から打ち上げた場合のGTOから静止軌道に乗り移るのに必要な増速量が約1500m/sなのに対し、種子島から打ち上げると約1830m/sにもなってしまうのである。
このため、その分衛星に燃料をたくさん積む必要があったり、あるいは同じ重さの衛星でも、赤道上から打ち上げた場合と比べて運用できる期間が短くなったりするという欠点があった。また、世界的には増速量約1500m/sへのGTOに打ち上げることがデファクト・スタンダード(事実上の標準)となっており、商業打ち上げにおいても足かせとなる。

それを緩和する方法として考えられたのが、「ロングコースト(長時間の慣性飛行)」という技術である。
通常の打ち上げでは、第2段機体がGTOに到達したところ(だいたい発射から約30分後)で第2段ロケットエンジンを停止し、衛星を分離する。今回の「きらめき3号」も、その飛行プロファイルで打ち上げられる。
一方ロングコースト・ミッションでは、その後も衛星を分離せず、数時間の慣性飛行を行い、静止軌道と同じ高度3万6000kmまで達したところで、第2段エンジンを着火(再々着火)して燃焼させる。そして、軌道傾斜角を約20度まで減らし、軌道の反対側の高度(地表に最も近い近地点高度)も上昇させたうえで、衛星を分離する。こうすることで、衛星を静止軌道により近いGTO(ロングコーストGTO)まで運ぶことができるのである。
もっとも、この技術は、言葉を変えれば衛星が負担するはずだった増速量をロケット側が肩代わりするようなものであり、ロケット側の打ち上げ能力は減ってしまう。ただ、打ち上げ能力の限界まであるような重い衛星を積んで打ち上げるケースは少なく、なにより世界的な標準の軌道へ打ち上げられるメリットのほうが大きい。

この技術はもともと、H-IIAロケットの「高度化プロジェクト」の一環として開発されたもので、2015年のH-IIAロケット29号機の打ち上げで使用された実績がある。また米国の「ファルコン9」や「ヴァルカン」なども、同じように静止衛星の効率的な打ち上げを目的に、同様の飛行ができるようになっている。
JAXAは、今回のミッションで必要なデータを収集し、将来的にH3にもこの技術を適用することを計画している。
H3のロングコーストGTOへの打ち上げ能力は6.5t以上になるとされ、H-IIAの約4.8tから大幅に向上し、より大きな質量の静止衛星を打ち上げることが可能になる。さらに、この技術は、複数の衛星をそれぞれ異なる軌道に投入する打ち上げや、惑星探査機の打ち上げにも応用できる。
H3の活躍の幅が広がれば、商業打ち上げの受注機会の拡大や、世界の宇宙開発における日本のプレゼンス(存在感、影響力)の向上につながるだろう。
H3の発展により、日本の宇宙開発がより高みへ至るための新たな航路が切り開かれ、宇宙への挑戦が末永く続いていくことを願いたい。
参考文献
JAXA | H3ロケット4号機によるXバンド防衛通信衛星「きらめき3号」の打上げ[再設定]
https://www.jaxa.jp/press/2024/09/20240927-2_j.htmlミッション概要 | ファン!ファン!JAXA!
https://fanfun.jaxa.jp/countdown/h3f4/mission-about.html防衛省・自衛隊|令和6年版防衛白書|4 宇宙領域での対応
https://www.mod.go.jp/j/press/wp/wp2024/html/n310404000.html第20回宇宙安全保障会 - Xバンド衛星通信中継機能等の整備・運営事業(きらめき2号の打上げについて)平成29年2月 防衛省Xバンド衛星通信整備事業推進グループ
https://www8.cao.go.jp/space/comittee/27-anpo/anpo-dai20/siryou2.pdf基幹ロケット高度化とH-IIAロケット29号機への適用 | ファン!ファン!JAXA!
https://fanfun.jaxa.jp/countdown/f29/f29_upgrade.htmlH3ロケット3号機 プレスキット
https://fanfun.jaxa.jp/countdown/alos4-h3/files/h3_f3_presskit-a_240619.pdf三菱重工 | 仏ユーテルサット社と三菱重工、H3ロケットでの複数の打上げに関して合意
https://www.mhi.com/jp/news/24091803.html三菱重工 | UAE、次期UAE国家ミッションで三菱重工と再び提携 UAE宇宙庁が2028年に打上げを計画する小惑星帯探査ミッション「Emirates Mission to the Asteroid Belt」に向け、UAE宇宙庁と三菱重工がH3ロケットでの打上げで合意
https://www.mhi.com/jp/news/241011.html
いいなと思ったら応援しよう!