
間違ったキャリア自律がもたらす組織の末路('ω')
こんにちわ。世界の多様な働き方を研究・実践しているYaccoです('ω')
「さて、もっと自律的に働こう!」
「キャリア自律だ!」
と叫ばれて、長く年月がたちます。
企業によっては、自律型研修を導入し、実際の業務も社員に裁量を与える、任せる、自由に異動するなどの後押しをしているようです。
まだ、この取り組みをしている企業は多くはありませんが、素晴らしい取り組みですよね('ω')
しかし、間違った進め方をしてしまうと、こういった末路もあるようです。
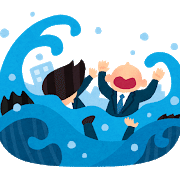
キャリア自律を全面的に導入したAさん
「これからはキャリア自律の時代だ!」とある、部門のリーダーのAさんは、全面的に社員に裁量や権限を与え、自分のキャリア実現に沿うように行動するよう促したそうです。
その結果、、
こんな人が出始めたそうです。
・勝手に他の部署の仕事に入っていき、(親切心かもしれないが)他部署の仕事を混乱させる人( `ー´)ノ
・会社の目標とは違う、自分がやりたいことだけに取り組み始めた人( ;∀;)
・自分の武勇伝を語るセミナーを企画し、無理やりメンバーを参加させている人(^^)
などなど、本業の業績達成と正反対の効果になってしまったという話です('ω')
もちろん、他のメンバーでは、自律的な取り組みが功を奏したこともあるのですが、一方で、上記のような方も存在するのも頭が痛いところです。
キャリア自律は、ある程度の仕組みが必要
上記は、なぜ起こってしまうのか? 自律を自分のいいように解釈して、好きなようにやる人は、必ずどんな組織にも一定割合います。
一律自律といっても、こういった方をどう自制させるのかも、大きな課題であり、それが同時に達成されないと「キャリア自律」は成り立ちません。
だからこそ、JOB型?
上記の事例は、会社の業務の進め方が、メンバーシップ型だからという理由も少なからずあるでしょう。
メンバーシップ型というのは、一人ひとりの仕事の範囲を曖昧にし、敢えて、チーム間で助け合わせる仕組みです。よって、とある人が、他の仕事をしても文句は言えないことになります。チーム全体がモラルが高く、モチベーションが高い状態なら、成り立つという諸刃の剣的な仕組みです。
JOB型ですが、これは欧米型であり、ある程度、その人の仕事範囲を明確にし、成果基準も共有します。自分のやるべきJOBを選ぶというところと、そのプロセスに自律を促し、一方で、勝手なことをしないよう、目標と範囲は合意しておくという事です。このJOB型であれば、自律で暴走する社員に歯止めをかけられます。
もともと欧米もJOB型はそういった意図もあり、導入されているものらしいです。
自律的キャリアは大事です。しかし、今の日本型メンバーシップの働く仕組みの元で、導入してしまうと、上記のような末路もありえますので、注意しましょう('ω')
★転職!複業!ギグワーク!貴方のキャリアにプロが伴走 -Bansou.net👇
