
類型論を学ぶ①『心理学とパーソナリティと類型論&特性論』
この記事について
以下、本文は口頭説明用の原稿を書き写したものです。
どれも文献の情報を参考にしていますが、表現を口語体で伝わるように直しているので厳密な表現ではありません。また、スライドの情報は最大限正確性を期していますが、本文の原稿についてはスライドほど正確でない可能性がありますし、私見も含みます。
「~~」はスライドに記載した文言をそのまま読むのを想定した目印です(どの文言に対応するかは文脈を読んで判断してください…)。
【導入】

1つ目が今日の最大のテーマ。かつての私もそうだったが、類型にはまると、類型の枠組みだけで人間を観てしまう癖ができる。私もむかしはMBTIにのめり込んでいたが、あれもいまは宗教みたいなものだと思っている。
何を信じるかはそれぞれの選択だけど、できるだけ広い視野から眺めた、バランスの取れた情報を共有したい。そういう意図で話させていただく。
類型界隈ではオリジナルのアイディアも見かける(独自理論)。ただ、これまで学術の世界で議論されて発展してきた知見を理解しないままであれば、高い質のアイディアも生まれるはずがない。独自理論を出したいのであれば、既存の理論を鋭く批判し尽くして乗り越えるほうが有意義だと思う。単に知らないのと、知った上で乗り越えるのは全然違う。このプレゼンがその助けになるなら私としてもうれしい。
心理学そのものから、パーソナリティ・精神分析の概念に簡単に触れて、さらに類型論・特性論に関わる分野に絞って話していく。
【心理学とこころ】

心理学はそもそも哲学から分化した。心理学、正確には近代心理学(もしくは実験心理学)が始まったとされるのは1879年。ヴントという学者がいて、ライプツィヒ大学で公式ゼミナールを始めた。ヴントは、心理学を、哲学や自然科学とはちがう独自の対象と方法を持つ研究領域として取り決め、その実験化と体系化に努めた。
⇒ 再評価されるヴント(日本心理学会 コラム)
分類はwikipediaを参考にしたが、どういう分類をするかやネーミングに特別な意味はないのでこだわらなくていい。
⇒ 心理学 - Wikipedia

心理学を学びたがる人はだいたいどこか病んでいる、といううわさを聞いたことがあるような。今の世の中まともな感性を備えていたらおかしくなるのもしかたない。
目に見えないこころというのをみんな知りたい。知るだけではなくて、自分自身を救ったり、大変な境遇に置かれた誰かを救いたい。そういうモチベーションが心理学の理論を築き上げてきたのは間違いないんだろう。
そうすると、「こころ」とはなんなのか? が問題になる。

まずこころの定義を示そう。~~ 内的過程というのは、刺激と反応の間にあるものとされる。スライドの右の図をみてほしい。人に刺激を与えると、もちろん人によっても反応が違うが、同じ人でも状況によっては反応が変わる。そうすると、刺激と反応の間になんらかのプロセスを仮定する必要があるし、その価値が出てくる。~イラストの例
内的過程を考えるというのは、実は現代的な考え方。現代的といっても1930年代以降の話なんだけど。【第1期】ヴントが心理学をはじめたときは、研究対象は私たちが直接に経験する意識内容だとした。で、被験者が意識したものを正確に報告するという内観法で研究すべきだと主張した。ただこの内観法は、被験者にもトレーニングが必要だった。そうでないと十分信頼できる内観報告が手に入らないから。
これに反発する形で、【第2期】1912年にワトソンが行動主義を宣言した。彼によると心理学というのは、「客観的かつ実験的な自然科学の一部門」であって、その目標は行動の予測と統制にあるのだと。そうすると、心理学で取り扱うべきなのは「刺激と反応」ということになった。いまふうにいえば、どういうインプットをすればどういうアウトプットがなされるか、その関係を調べようとした。しかしこれもやがて非難されるようになる。
そうして出てきた一つの考え方が、【第3期】新行動主義。刺激と反応の間に内的過程というのを想定する。この考え方も、細かくみれば多くの立場がある。
【パーソナリティと精神分析】

先ほどの例で示したように、同じ状況や刺激を与えても、人によって違った反応を見せる。この常識的な現象を観察するところからパーソナリティの研究は始まった。
パーソナリティの肝は個人差にある。その個人差を類型や特性によって表そうというのがパーソナリティ心理学(もしくは人格心理学)の方法。ただ、教科書ではそれだけではなく、~~
ミシェルによれば、パーソナリティ心理学という分野では、個人差だけではなくて、その個人差が社会と関わるにあたってどんなふうに影響を及ぼし、及ぼされるのかにまで目を向けるべきだと主張した。そこでスライドに書かれているような幅広い分野の記述があると考えられる。
オールポートという特性論研究のさきがけとなった偉大な学者がいて、この人がパーソナリティの定義を考えた。この方は、英語のパーソナリティの語源となった「ペルソナ」ーこれは古典ラテン語の言葉だがーから考察を始めて、神学的、哲学的、生物社会的などなどパーソナリティに関する49種類の定義を見通して次の定義をした。
~~なるほど、これでスッと頭に入る分かりやすい定義ではないので、次のパターンでこの定義をかみ砕いていく。

あるパーソナリティの教科書によると、パーソナリティは要するに次の5つの要素を持っていると説明している。この説明が分かりやすかったので、この5つの要素と定義を対応づけていこう。
③:システム化されているということ。統合が失調してしまうと大変。まとまりがあるからこそ①へ。
④:社会とどう関わるかというのは、社会にどう適応していくかという話でもある。もしくは「適応しない」という決定も含まれる。そして、その決定がなされれば、その意図や意思が外に表現される。これが②
⑤:パーソナリティというのはソフトウェアだけではない。脳や神経、内分泌系といったハードウェアにも関わる概念であるということ。
ちなみに、現代的定義もあるが、定義とはいえないレベルで複雑で長い。パーソナリティの要素を無理矢理一文にまとめようとしている。ここで話した5つの要素を押さえていただければ十分だろう。
(▼New!!)たとえば若林(2009)は、パーソナリティを一種の現象を指す用語と考えるべきだと指摘し、①基本(気質)的定義と②心的表象としての定義の2つの定義を提唱した。覚えるのは無理だろう。
①基本的定義は、「パーソナリティとは、時間や状況を通じて個人(個体)の行動に表れる比較的安定したパターンとして外部から観察可能なものであり、他者(他個体)との違いとして認識されるもので、それは発達段階を通じて遺伝的要因と環境との相互作用の結果として表れるとともに、それは神経・内分泌系などの生理・生物学的メカニズムによって媒介されているものである」
②心的表象としての定義は、「パーソナリティとは、各個人が認知している自己の行動や情動に現れる比較的安定したパターンについての心的表象であり、その基礎には(自覚されている程度には個人差はあるが)遺伝的要因によって規定された固有の神経・内分泌などの生理・生物学的メカニズムと環境との相互作用がある。これは主観的には主に他者との違いとして認識されるものであるが、常に個人の行動に何らかの形で影響を与え、発達過程を通じて維持されるが、その安定性と変化の割合には個人差がある」
⇒ 若林 明雄(2009)、パーソナリティとは何か : その概念と理論(版元ドットコムへのリンク)

まず真ん中あたりに書いた症例から。フロイトが直面した患者のエピソードだそう。~~
いろいろな検査をしても、身体に異常はない。しかも患者たちは死に物狂いで自分の症状を抑えようとしてもコントロールが効かない。そこで~~(フロイトの洞察)
臨床観察を経てフロイトが体系化したのが精神分析学。精神分析という言葉には2つの要素を含む。治療のメソッドとセオリー。そこで鍵となるのが無意識という概念。定義としてあらためて読むと~~
フロイトが現れるまで、人々の行動は意識と理性のコントロールのうちにあると考えられていた。フロイトがその考え方をひっくり返してしまった。これまで私たちに行動するよう駆り立てるソフトウェアは意識だけだと思っていたのが、実は意識は氷山の一角に過ぎなかった。意識の下には遥かに広くて深い無意識の世界が広がっていると考えた。
この無意識という考え方は、心理学だけでなく、思想、文学、芸術などにも影響を与えたらしい。フロイト自身も文学作品にたくさん触れていて、ギリシア古典からゲーテ、シェイクスピア、ドストエフスキーなどを読んでいた。これには理由があって、詩や作品を読むことは夢を解釈することと同じだから。解釈というのは無意識過程から意識過程へどのように変換されるかを明らかにしようとすること。文学作品はその素材を提供するものだと考えていた。
(▼New!!)精神分析と対照的なのが、行動主義に基づく行動療法。行動主義では、こういう刺激があれば、こういう反応や行動に現れるというのが基本的な考えかた。そうすると、おかしな症状も何らかの刺激に結びついた行動に他ならない。ということは、この刺激と行動の結びつきを強めたり、弱めたり、ある刺激に対して別の行動を結びつけて治療をするという条件付けの考えを持っていた。
⇒ 精神分析とは(コトバンク)
日本大百科全書(ニッポニカ)の解説が分かりやすくておすすめ。

フロイトの考えの根底にあるのは次の2点。動機決定論と無意識
①は~~ ①の意味は、奇妙な行動がたまたま起きたとは考えないということ。行動には心理的な原因があると考えた。②は~~
フロイトは無意識を探るために夢を利用した。夢は、人が直接的に表に出せない願望を満たそうとする無意識的な努力なのだと主張した。ところが分析を進めた結果、病気の動機はすべて性衝動という答えが出た。
ただ、ここでいう性欲は、常識的な意味とは違う。そういう生物的な本能とは別の心理的な事実として性欲をみなした。~~だから、思春期になって現れるものでもないと考えられている。
アドラーもユングもフロイトとの交流があったが、途中で二人ともフロイトと決別してしまった。ここは私も詳しくないので調べてみて。「劣等感」というキーワードはアドラーの心理学からきているらしい。劣等感はどこからくると他人との比較からやってくる、そこで社会的関心と結びついていくらしい。ユングはあとでタイプ論に絡めて敷衍していく。
【類型論と特性論】
導入

パーソナリティを考えるうえで核心となる個人差をどのように説明するか。そのアプローチが2つある。類型と特性。ご存じの方も多いでしょうが、類型論は多様なパーソナリティを質的に異なるカテゴリーに分けていくやり方、特性論はひとりひとりがある特性をどれだけ持ち合わせているかについて、数直線の上にひとりずつ点数をプロットしていくことをやる。これを難しく言うと、数値化可能、かつ尺度化可能という。要は何らかの形で数値化して比較することで個人差を表していく。
パーソナリティを測定するという考え方を、論文で早くから示したのはゴールトンという人。ゴールトンは進化論で有名なダーウィンのいとこで、1884年にMeasurement of character というタイトルの論文を出していた。1920年代に入った頃から、パーソナリティの研究がさかんになった。これまでは個人差や個性を誤差としか扱ってこなかったが、この頃から研究対象にもなっていった。地理的な話をすると、類型論は主にドイツで発展して、特性論はイギリスやアメリカで発展してきた。
話を一歩進めて、さてパーソナリティを測定しようといわれても、測定するツールがなければ意味がない。そのきっかけとなったのがビネという19世紀後半の心理学者。この人が精神の発達が遅れている子どもの診断をするために、1905年に知能テストを開発した。これがきっかけで集団式知能テストも作られた。この検査の形式が性格の研究にも持ち込まれて、パーソナリティの計測に使われるようになったといわれている。
類型論

では類型論からみていこう。伊坂による新しめの定義によると、3つの要素がある。はじめ2つが手段、~~、最後が目的で、~~
類型論は、人となりの全体像を大まかに捉えるのがポイント。特性論のように細かい分析をするのが本質ではない。
この定義にはないが、少数に分類することもポイントだと思う。なぜかというと、何百もの類型があったら理解は容易にならなくなってしまうから。

書いてあるとおりで、みなさんのほうが詳しいと思うので、割愛
ひとつトリビアを話すと、人間のパーソナリティについて体系的に書かれた世界最古の本があって、古代ギリシアのテオプラストスによる「人さまざま」というタイトルの本。紀元前4世紀頃の人物。日本語版も岩波文庫から出ている。

精神分析のスライドで話したように、ユングはフロイトの考えを受け継いでいる。だから、ユングのタイプ論も精神分析の枠組みで説明するのが歴史的な経緯には沿っている。でも複数の文献で、ユングを類型論の人として解説されているのでここで話す。ユングのパーソナリティの考え方は複雑で、一貫した理論というよりも観察の集まりという側面がある。タイプ論に入る前にまだ話すべきことが残っている。1点目をみてほしい。
心というのは意識だけでなくて無意識もある。ここまではフロイトと一緒。ユングはさらに、無意識にはいくつもの層があると考えた。ここで、自我と自己という2つの概念を立てる。自我は、意識の層、つまりペルソナ層をまとめる中心的機能をいい、自己は、意識の層と無意識の層をまるごとひっくるめたこころ全体をまとめあげる中心的機能をいう。さらに、意識と無意識はお互い対立し、しかも補うように働く。そして、自己は、自我によるまとまりやバランスを崩してでも、高みに向かおうと働きかけをおこす。ユングはこれを、個性化の過程、自己実現の過程と呼んだ。個人の成長はこのようにしてなされると考えた。
このように、意識や無意識には、その人を何らかの行動に駆り立てるエネルギーが動いている。ユングは臨床経験により、そのエネルギーが内と外のどちらへ向くかや、機能の現れ方が人によって違うことを見いだした。その個人差に着目することでタイプ論につながっていく。
まずユングは、リビドーという心的エネルギーが、外に向かう人と内に向かう人がそれぞれいることを見いだした。このリビドーは、フロイトの性欲よりも広い意味を指す。このリビドーが外に向かうと、自分の外側に存在するもの重視してそれを基準に判断を下す傾向があるし、内に向かうと、主観的な認識を基準として判断して行動する傾向があるという。これによって内向と外向に分類できる。また、人が持っている心理的機能には4つある。それが思考、感情、感覚、直観。2つの方向と4つの機能を掛け合わせて、8つのタイプができる。これがユングのタイプ論。
ここから先はタイプ論の本を読んでほしい。

代表的な批判の3点目は、ユングのタイプ論には当てはまらないように思う。
オールポートは、類型の学説は個性の研究法としては中途半端なものとして批判した。1つめ~~類型論は、理論家の主観的なニュアンスが付け加えられている。2つめ~~類型論は共通の物差しがないので、どれがより正しいのかを検証することもできない。
特性論総論

まず定義の1行目と3行目を補足。精神神経的な体系というのは、パーソナリティの定義と同じく、精神的なものにとどまらないという点がポイント。特性も、身体的、生物学的な要素を含む。また、3行目もわかりにくい言い回しだが、要するに特性というのは、外に現れる行動に一貫性をもたらす役割があることをいっている。
次に2行目の説明、これは下の例をみてほしい。もし友好的という特性を持っている人がいたとする。この人はTPOが変わっても、友好的という特性を通じて同じような反応を示す傾向がある。知らない人と会うときも、同僚と会うときも、ご近所さんに会うときも、恋人と会うときも、感じが良かったり温かさのある反応を示す。多くの刺激を等価たらしめるというのは、こういうことをいっている。

オールポートは特性には2種類あると考えた。個別特性と共通特性。さっき類型との比較で説明した特性の特徴は、おそらく共通特性のことをいっている。今の特性論の研究は共通特性にばかり向けられている。
まず個別特性から。~~その人に特有ということは、誰もが持っているわけではない。そうすると、数字で比較できない。だから統計的なアプローチをとれない。そこで個性記述のアプローチがとられる。
一方、共通特性は、~~。どうして共通の特性があるかといえば、同じ社会の人たちは同じような経験と文化も共有するから。法則定立アプローチが今の特性論研究の中心だろう。
さてひとつ問題。オールポート本人は、個別特性と共通特性のどちらを重視したか? 実は個別特性。彼の著書をみても、個別特性を第一義的にとらえていたことが読み取れるらしい。特性は常に個人にあり、社会一般にあるのではないとも言っている。しかしそんな思いとはうらはらに、共通特性の研究が発展してしまった。
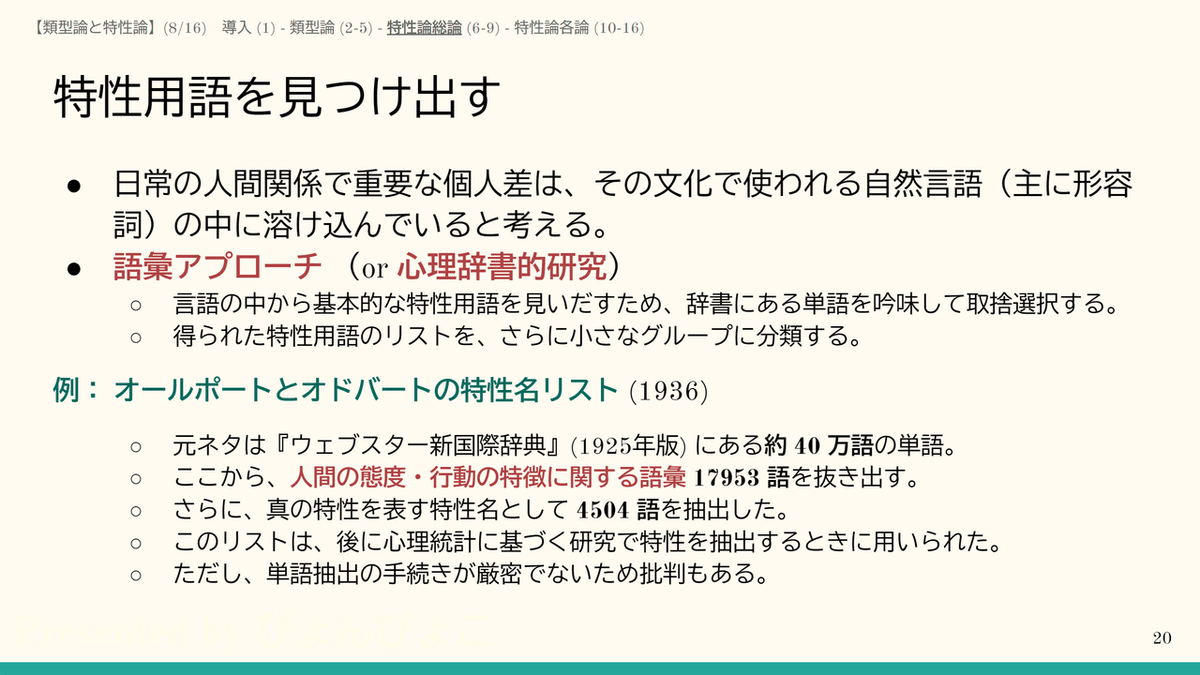
では、これまで問題にしてきた特性はどうやって表現されるのか。言葉によって表現される、あたりまえ。より正確に言うと、その文化で使われる~~
では、その言語の語彙を調べ尽くせば、特性が出てくるはず。そこでとられるのが、語彙アプローチという方法。~~

特性用語は何千もある。しかし、これだけの数のパラメータがあると研究はとてもやりづらい。そこで、もっとシンプルに整理したくなる。ここで因子分析という統計的な手法を使う。何をするのかを一言で言うと、特性用語どうしの意味の近さを数値化して、特性をまとめていく。
因子分析にかけるデータをどうやって集めるか。まず特性用語のリストを作る。これをアンケート形式にして被験者に配る。特性用語を見ながら、自分自身でもいいし、よく知っている他人を想像しながらでもいいので、その人にどれくらい当てはまるかを判断してもらう。そうすると、同じような意味を持つ特性は、どれも連動して当てはまるか、当てはまらないかという結果になる。例えば、物静かな、打ち解けない、抑制的なという特性がリストにあったら、3つとも当てはまるか、3つとも当てはまらないというデータがたくさん集まりそうである。このような特性の組み合わせをまとめていって少数の特性にしていく。~~(②無関係・独立した因子へ:例えば「控えめ」という特性を、統計的な分析をすることによって内向性と協調性に分解する。控えめベクトルを、0.50内向性+0.87協調性のようにできる。)
特性論各論
ここまでで、特性論研究では何をしているのかをみてきた。特性は言葉で表現される、言葉をターゲットにして研究していけば特性の構造が見えてくると考えた。ここからは各研究者の具体例のはなし。研究によって特性の構造がそれぞれ違う。はたして1つの結論にまとまっていくのだろうか? ということで、キャッテルの研究からみていこう。
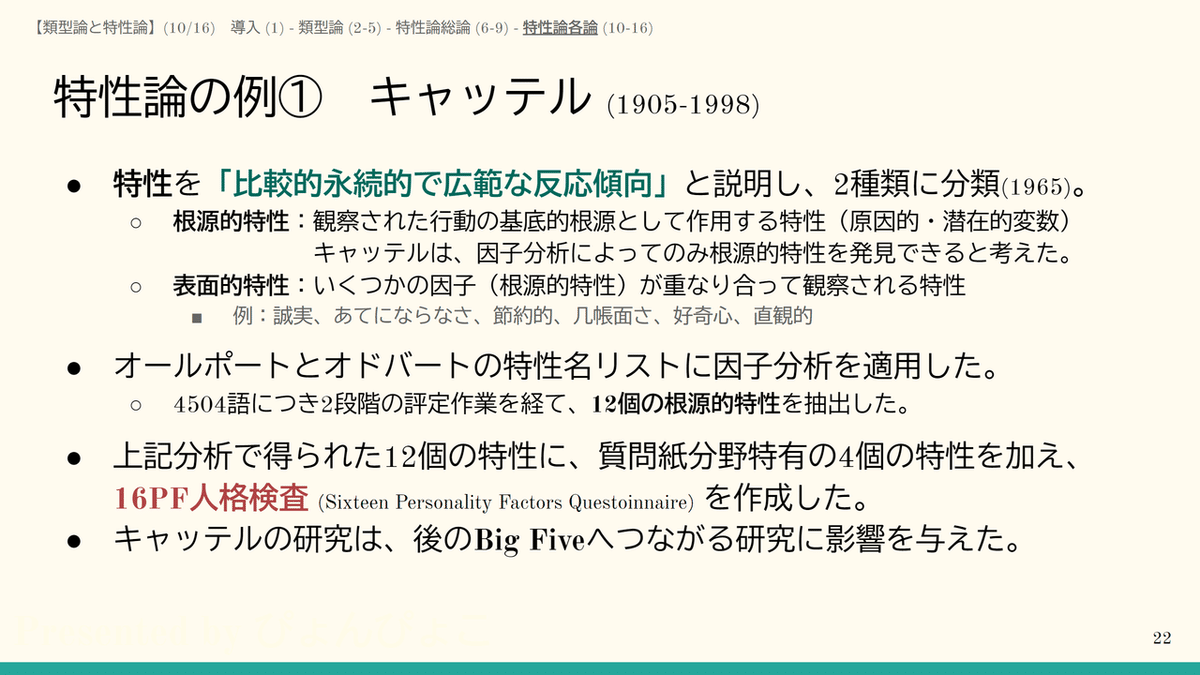

下4つが質問紙分野特有の4特性。


このYG性格検査は就職活動でも使われる場合がある。私も一度受検した記憶がある。就活対策のサイトを見ると、性格検査の受け方のアドバイスまで出てくるので読んでおくと得かもしれない。似た内容の設問で迷いに迷ってどっちつかずの回答をしてしまうと、回答の信頼性が落ちて損かもしれない。そういう指標をチェックする仕組みが作られている。嘘でない範囲のテンプレなキャラクターを想定してから受検するといいかもしれない。

外向型と内向型で、脳波や循環器系の活動の違いを調べた研究がある。たとえば、内向型は外向型に比べて、低い周波数の音に対して脳波の活動が大きく変化することが示された。これは、同じ刺激に対しても内向は外向よりも脳が過敏に反応するということ。そのような強い生理的な反応に苦しめられるから、内向型の人は活発な行動から離れようとすると考えられた。
誰でも、物事をうまくやり遂げられるのにちょうどよい刺激の量がある。職場環境でいえば、病院のICU勤務と工場倉庫系のライン作業とでは、刺激の量が大きく違う。その人にとっての快適な刺激量を基準として、外から降ってくる刺激が少なすぎると退屈するし、多すぎると覚醒しすぎてうまく作業できなくなる。内向と外向はこの水準が違うので、望む環境や適性も変わってくると考えた。


最後に、パーソナリティや特性も批判的にとらえられている話をする。1960年代の終わりになると、パーソナリティが本当に人間の内側に存在するのか、という問題提起がなされるようになった。この一連の動きを、人間―状況論争といったり、一貫性論争という。ここで強い批判をした代表的な人がミシェルである。
ミシェルがいうには、人間には状況を超えた一貫性がない。これは膨大な実証データから明らかになった。もしパーソナリティが人間の内部にあるというなら、時間や状況が変わっても一貫性があるはずである。これを~~という。しかし、ほんの少しでも状況が変化すれば、個人の行動は必ずしも一貫しないことがわかった。
それでも、われわれの素直な感覚からすると、誰しも一貫したパーソナリティを持っているようにみえる。ミシェルは、攻撃的な子どもの行動を分析して、攻撃的な子どもはいつも攻撃的なのではなくて、決まった状況下のときだけ攻撃的になったと指摘した。これをイフゼンのパターンと呼んだ。一貫したパーソナリティを持っているように見えるのは、このイフゼンのパターン、こういう状況ではこういう行動をするというパターンが一貫しているからだとミシェルは主張した。
また、ミシェルは特性についても批判した。①~~、彼が不安そうに見えるのは、不安だからだといっても、何も説明したことにはならない。特性でパーソナリティを説明したことにはならないのではないかという疑問がある。②~~、因子分析の手法も、特性をまとめているだけで、潜在的な特性を見つけているとはいえないのではないかということ。③~~、パーソナリティをわれわれはどのように認知するかの枠組みを示したに過ぎない、とはいうが、パーソナリティを言葉で表現する以上、認知の枠組みを見ているという点からは逃れられないようにも思える。
こうしてミシェルは、状況も組み込んだ新しいシステムを考案している。
⇒ 認知―感情システム (cognitive-affective units) のGoogle画像検索結果
結び
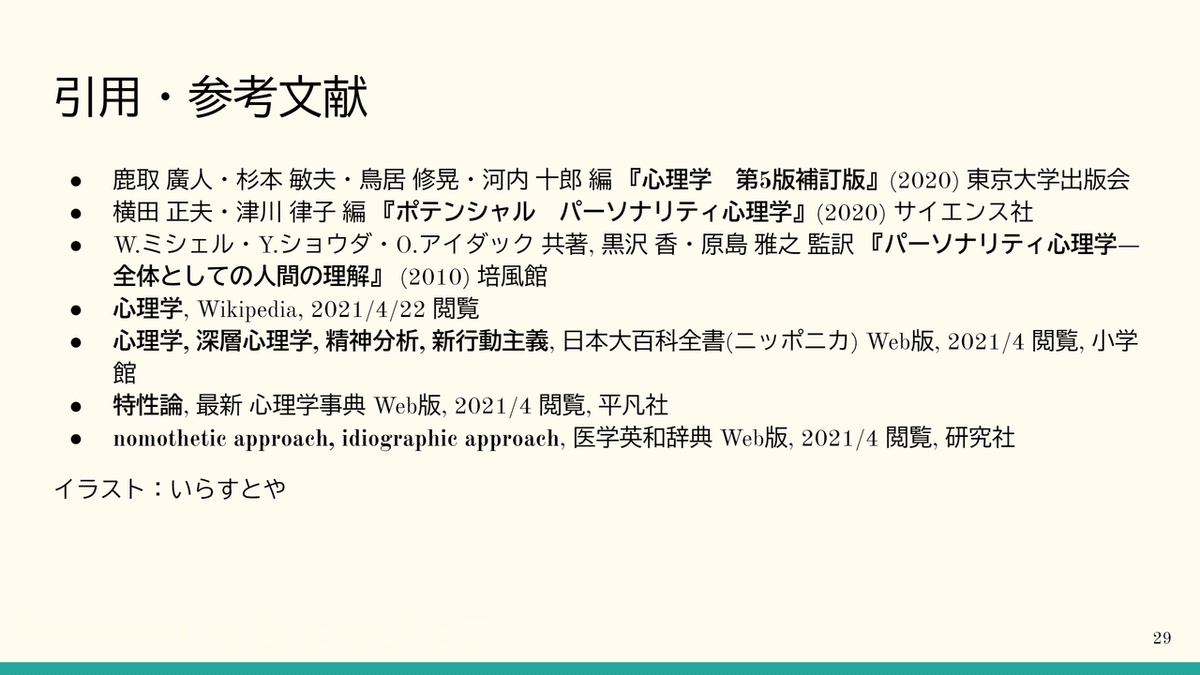
第2回:心理統計、第3回:MBTIの妥当性や信頼性等についてプレゼン予定。
