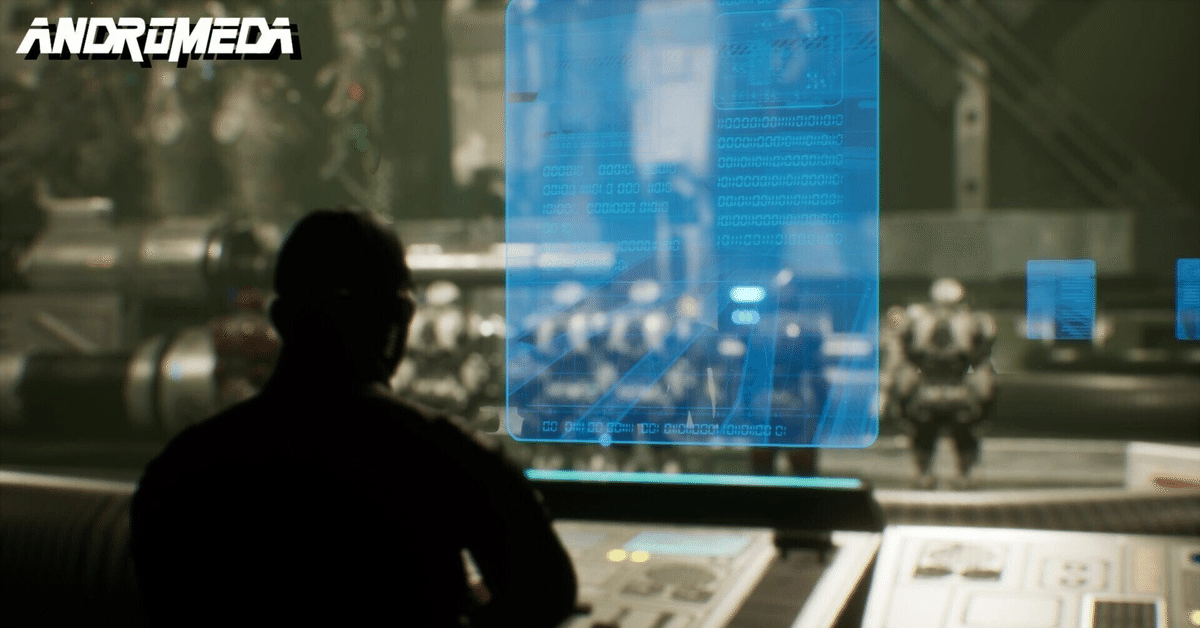
エンジニアという生業と世間の感覚のズレ
仕事とは異なる集団と関わるという部分での気付きです。
イノベーション・改善に対する感覚
良いことで直ぐに、新しい取り組みという部分では、おそらく先進的なのではないかと思います。それを共通の意識として仕事をしている部分では、多くの社会の人からすると浮世離れはしているのかなと感じました。
生業ではない共同作業
4年ぶりに自治会でお祭りを実施するということで、子ども会の役員として参加していますが、当時と前提条件が異なることをまずは考えてしまうわけです。
実際、5,6年生ゼロの子ども会、自分の息子も2年生、小学生の親としても2年生。まずその視点ありきで考えてしまいます。
ポスター作製
1年生、2年生は字もままならないスタート、夏祭りなんてものも記憶の中に無いスタートなので、そこは、文字の部分や、イメージのテンプレートを用意しました。とはいえ、前例のないことなので、まず実行委員会の承認から入り、という所で、あぁそうだなと、いう躓きをしました。
確かにそうなのです。承認ありきなのです。例えば、エンジニアが、如何に刺さるプレゼンをするために、知識を総動員することと、世の中はちがうという部分であります。
当日の準備品等
お神輿を子供に引かせるという部分では、大人もさることながら、子供の2時間のコンディションを最優先に考えようと思いましたが、実際、前例からの状況でどう考えるかという部分で終始しました。
現代的にどう考えるか、過去を踏襲するかという部分で考えが違えました。まぁこれも職業的な浮世離れということなのかなと思います。
力を入れるポイント、抜くポイント、判断基準
資源回収を行った際のことですが、土曜日の実施に際して、月曜日くらいから天候を読み始める訳です。
木曜日くらいからは、1時間単位の予報と雨雲レーダーを見て判断します。ただ、それは実行する現場の感覚であって、前夜に雨が降っていないという判断で、ご協力者様はかなり準備をされていました。
ということで、子ども会的には順延ですが、既に出しているものの回収は実施しました。
この辺は、やはり何を基準に生活しているという部分で、エンジニア、現役世代と、そうではない人たちとで乖離はあるのだなと思います。
力を抜くポイント、という意味でも、イノベーションをうまく利用するかを大切にしたいと考えますが、その分注力しないといけない部分、これからで言えば、熱中症対策等やはり考えは乖離があると認識しました。
もう1つ
たぶん、熱量の差もあると思います。なんか、やるからには的なのが出ちゃいますね。知ってます、そうでもない人が多いことも。
今日はこんなところで。
いいなと思ったら応援しよう!

