
わたしたちが“グッときた”オードリー・タンのことば『何もない空間が価値を生む AI時代の哲学』好評発売中!
『何もない空間が価値を生む AI時代の哲学』とは?
オードリー・タンさんの最新作『何もない空間が価値を生む AI時代の哲学』(オードリー・タン語り アイリス・チュウ著)が7月14日に発売されました。本作は、台湾IT相である彼女が、自らの体験をもとにネット空間を生きる99の心構えについて語った1冊です。
タンさんの「ネット空間を生きる99の心構え」とはいったいどんなものなのか? 電子書籍編集部の部員が本作を読み、心に残ったことばをコメントと共に紹介します。
今回登場する部員は、おかわり君・無脊椎46・猫背部員M・眼鏡狸E・25年物OLの5名、部員によって、ささるフレーズはさまざまな様子。
さっそくご紹介いたします。
電子書籍部員が、グッときたオードリー・タンさんの言葉

「学校に通い続けるかを悩んだタンさんは、既存の教育を否定するのではなく、そこから抜け出し、なおかつ改善することを目指しました。社会をよりよくするのは二項対立ではなく、第三の道」(おかわり君)

「あるものに同一性を認めるときそれ以外のものを『排除』してしまうことになる、という考えにハッとしました。これまで私どうだっただろう。今後は『経験の共有』をしていきたいと思います」(無脊椎46)

「不安や恐れの感情は排除したくなるものですが、考えれば考えるほど頭を離れないもの。〈心のゲスト〉として迎える発想は気持ちも軽くしてくれそうです」(猫背部員M)

「タンさんは13歳の時に『あなたはもう大人なんだから、自分の判断に責任を持ちなさい』と母親に言われて、成長したといいます。自立した大人へ。子育ての極意ですね」(眼鏡狸E)

「不思議です。顔を合わせて、仕事をしたり、食事をしたりするから親しくなるわけではなく、大切なのは身体ではなく心の距離のようです」(おかわり君)

「『十分な休息時間をとり、寝て、朝起きたら自分の思考の一部になっている』とタンさん。まさに『寝る子は育つ』。自分に合う学習と睡眠のパターンを探したい。実は私の狸寝入りも学習の一部!?」(眼鏡狸E)
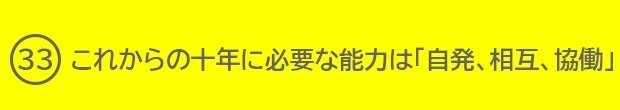
「仕事でも何でも一人で完結できることなどあまりないような気がします。難しい件なら尚更。自分の視点と共に様々な人、考えへのリスペクトを大事にしたいとあらためて」(無脊椎46)

「相手を理解したくても、想像には限界がありますよね。『積極的傾聴法』を習慣化し、さまざまな人の立場を知ることが、自分を知ることにもつながるように思います」(猫背部員M)

「会議の司会って難しくないですか? より良い会議にするための極意がこのひとこと。次から心がけてみようと思います」(25年物OL)

「ネット上だけでなく、打ち合わせや会議の雰囲気でも同じことが言えそうです。その場に惑わされず意見の本質に焦点を当てる重要性を再認識しました」(猫背部員M)

「タンさんは『過度に煩雑な仕事はAIに任せるようになる』といいます。延々と続くExcelのコピペみたいなものはAIにやってもらい、人間はより創造的に。目の前が明るく開けたような気がします」(25年物OL)

「『今日学べることがあれば、今日学びます。(中略)今日中にできなければ、その先のことは考えません。』このスパッとした割り切り方。思わずポンと腹鼓を、いや膝を打ちました。いてっ」(眼鏡狸E)

「『デジタル技術はすべての世代を包含するものであるべきで、誰も犠牲になる必要は』ないのだから、双方歩み寄ることが必要なんですよね」(25年物OL)

「『挫折は、その問題に対する重要度と緊急度から来るものです』。タンさんが言うのですから重みがあります。そうならないためのアドバイスも心に留めておこう……」(無脊椎46)

「相手が若く見えるから、エラそうにしたり、年配に見えるから、謙虚になったり……。ネット上では、年齢に関係なく教えたり、教わったり。可能性は無限に転がっています」(おかわり君)
オードリー・タンの考えが詰まった99の哲学は、ほかにもたくさん
タンさんの幼少期の経験を交えながら、仕事、インターネット、人との関係についてやさしい言葉で語られるこの作品。オードリー・タンさんが気になっていたという方には、彼女を知る最初の1冊としてもおすすめです。
ふとめくったページから、今の自分にふさわしい言葉や、新しい発想を生み出すきっかけになる言葉が見つかるかもしれません。
電子書籍の特典にもご注目!
この作品の電子版には「Q&A 東大生がオードリー・タンに聞く」が特別付録として収載されています。「フェイクニュースをなくすためにSNSが果たすべき役割は?」「AIは人と人との交流を多様化させるか?」「デジタルリテラシーを義務付けるべきか?」など、東大生からのさまざまな質問にタンさんが答えます。
全16問の充実した質疑応答は、とても読み応えがあります!
『何もない空間が価値を生む AI時代の哲学』各電子書店で発売中
※電子版特典の対話は、東京大学グローバルリーダー育成プログラム GLP-GEfIL (Global Education for Innovation and Leadership)と、台湾国立政治大学科技与人文価値研究中心が共同企画した夏季プログラム「Taiwan’s Democracy and Asia-Pacific Countries」(2021) の講義の一環で、その抜粋版です。
