
感染症と宗教考える コルモス研究会議
※文化時報2021年1月14日号の掲載記事を再構成しました。
宗教者と研究者が宗教について共に考察を深める「現代における宗教の役割研究会」(コルモス)の第67回研究会議が12月26、27 日、オンラインで開催された。新型コロナウイルス感染拡大が続く中、「新たな感染症の時代と宗教」をテーマに、会員約50人が議論した。
会長を務める大谷光真浄土真宗本願寺派前門は、26日の開会あいさつで「今回のテーマは、研究会議そのものの在り方を変えたことにもなる」と指摘。「宗教に今何ができるか、現代文明と現代社会にまで考えを深めたい」と述べた。両日の登壇者による主な発言は次の通り。

あいさつする大谷光真前門
コロナの中で考えたこと
奥田知志氏(東八幡キリスト教会牧師)
この国は今、さまざまな給付金で持たせている。それらが2021年3月に一斉に切れるため、生活困窮者支援の現場は戦々恐々としている。コロナ禍による悲劇が起きたのではなく、コロナ禍以上に深刻な現実を、私たちはすでに内包していたのではないか。
自宅で過ごす「ステイホーム」が命を救うというのは噓だ。世界中の人々が外出を控えると、人類は滅亡する。人は、一人では生きていけない。
政府は「まず自助で」と言う。だが、「私も頑張って助ける。国も役所も絶対に見捨てない。だから君も頑張れ」という前提を欠いては、非人間的な社会になるのではないか。
私たち大人は、他人に迷惑を掛けないのが立派な人間だという誤った人間観を社会に蔓延させた。子どもは「助けて」と言ってはならないと信じ込んだ。だから改めて、助けられながら生きていくしかないのが人間だ、と伝えなければならない。
新型コロナは人から人に感染する。だからこそ、世界は半径2㍍以内の人間同士でつながっていたことに気付かされた。自分の物を分けたら減ると考えるのでなく、「分けたら増える」と捉えることが、コロナ終息後の新しい倫理になるのではないか。
新型コロナとは違って、私たち自身は変異することを拒み、他者を受け入れようとしない。「自分のことで精一杯で、他人を助ける余裕がない」などと言い訳をする。いつになれば「自分のこと」ができるのか。このままでは新型コロナと共存できても、人間同士は共存できない。

奥田知志氏
ハンセン病と叡尊教団
松尾剛次氏(山形大学名誉教授)
現代よりも制約があった過去の仏教者の活動をかがみとして、現代のコロナ下の宗教者の活動を顧みることができる。今回は「叡尊教団」を取り上げたい。
叡尊教団は、奈良・西大寺の叡尊(1201~90)を開祖とする鎌倉新仏教の教団で、15世紀半ばまで栄えた。従来は戒律復興運動を行った旧仏教の改革者として理解され、教団を形成できなかったと見られていたが、叡尊の時代は末寺1500カ寺、信者10万人以上に上っていた。
特徴的な活動の一つが、ハンセン病患者の救済だ。叡尊の高弟、忍性(1217~1303)が中心になって取り組んだ。
共同体や家族から見捨てられ、官僧から穢けがれた存在として忌避されていた患者たちに対し、忍性は自ら背負って市まで送り迎えをし、服を売って施しをした。後年、活動の拠点とした鎌倉の極楽寺には、患者の療養所を設けた。
特効薬のなかった時代に、利他の精神で行ったこうした活動は、コロナ下でも参考になるはずだ。
叡尊教団のもう一つの特徴的な活動が、葬式従事だった。官僧は死を穢れとみなし、避けるのが義務とされていたが、叡尊教団は日々厳しく戒律を護持することで、穢れから守られると主張した。「清浄の戒は汚染なし」という理屈で、死者の救済という社会活動を、教団として行った。
葬式仏教の成立は、慈悲の精神に基づき、穢れへの恐怖を乗り越えた僧侶集団による革命的な行為だった。コロナ下でも、宗教者はそうした意義を認識し、積極的に葬式に取り組んでほしい。
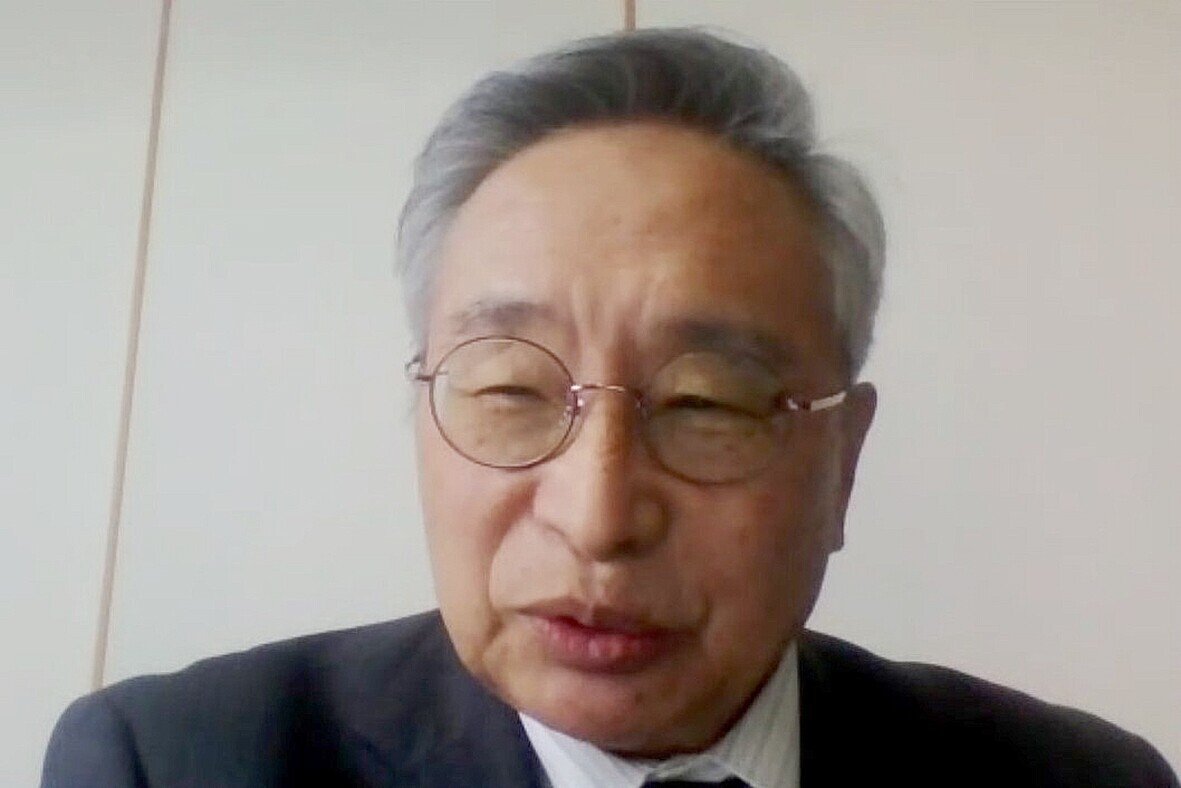
松尾剛次氏
信者のための教会へ
中村憲一郎氏(立正佼成会京都教会)
立正佼成会は、新型コロナ対策に関し①正しく恐れる②信者さんの健康と安全第一③早めの自粛、遅めの再開―を基本に取り組んだ。
京都教会では「離れても、つながる」をコンセプトに、医療従事者らにエールを送る活動などを行ってきた。会員には、無料通話アプリ「LINE(ライン)」による法座や電話・手紙、直接訪問による相談で、孤立化への不安を少しでも和らげようとしている。
コロナ禍によって、これまでは教団行事だけを信仰活動と捉えていなかったか、教会で役立てば修行しているという錯覚はなかったか―との気付きがあった。個が求めるものにどう応えていくか。教会のための信者から、信者のための教会に転換しなければならない。
オンラインの活用を
原知昭氏、金森成裕氏(全国曹洞宗青年会)
全国曹洞宗青年会は原則41歳以下の青年僧侶により、加盟49団体・会員数約2600人で構成されている。執行部会・理事会などの会議はオンライン中心となったが、これまで対面でも紙資料を使っていなかったので、スムーズに移行できた。
動画投稿サイト「ユーチューブ」の公式チャンネルで、自宅で行う坐禅の方法や精進料理の作り方、新型コロナ退散祈願のオンライン法要などの動画を公開した。いずれもとっぴな取り組みではなく、本来の活動がオンラインに移行したという感じだ。
たとえ感染拡大が終息しても、オンラインの利便性に慣れた以上、やめるのは難しい。宗派や寺院での活用が必要だろう。
隔離は正しい手法か
野村康治氏(浄土真宗本願寺派瑞松寺)
社会福祉法人至心会(大阪市東淀川区)の理事長として、介護老人福祉施設などを運営している。
新型コロナを巡る厚生労働省の通達などに基づき、訪問介護の現場は熱を出した独居高齢者宅にも行くという厳しい状況に直面した。入所者との面会は、ウェブを通じて行うようになった。
ただ、仏教婦人会の方々が定期的に差し入れてくれる一輪の花を楽しみにしている施設入所者もいる。このため、面会を家族に限定することはなかった。
ハンセン病患者への差別は国の隔離政策に起因したのだと、あれほど学びを得たのに、コロナ下で隔離が進められている。愛しい人の見舞いや葬儀・法要への参列が許されない状況は、改めなければならない。

オンラインで開催されたコルモス研究会議
コロナ下での祇園祭
仲林亨氏(八坂神社)
疫病平癒を祈る7月の祇園祭は、コロナ下でも中止するわけにいかなかった。3月から境内に茅の輪を設置し、4~6月には伝統の御霊会を臨時で行った。
神輿渡御は断念せざるを得なかったが、氏子の提案で神ひもろぎ籬 を背にした神しん馬め が渡御し、御神霊を宿す御幣を載せた台車が地域を巡行した。手を合わせてくださる大勢の方々を見て、神が年に一度会いに行くシステムを作った先人のすごさに、改めて気付かされた。
神がいることを感じながら、皆でやれることをやろうという一体感で営むことができた。氏子・崇敬者の望みを聞き、先例に倣いつつ実現することが宗教者の役割だと実感した。
【サポートのお願い✨】
いつも記事をお読みいただき、ありがとうございます。
私たちは宗教専門紙「文化時報」を週2回発行する新聞社です。なるべく多くの方々に記事を読んでもらえるよう、どんどんnoteにアップしていきたいと考えています。
新聞には「十取材して一書く」という金言があります。いかに良質な情報を多く集められるかで、記事の良しあしが決まる、という意味です。コストがそれなりにかかるのです。
しかし、「インターネットの記事は無料だ」という風習が根付いた結果、手間暇をかけない質の悪い記事やフェイクニュースがはびこっている、という悲しい実態があります。
無理のない範囲で結構です。サポートしていただけないでしょうか。いただければいただいた分、良質な記事をお届けいたします。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
いいなと思ったら応援しよう!

