
客観的に"好き"を書く|京都ライター塾第3回後半編
江角悠子さん主宰「京都ライター塾」を受講中です。1/11(土)~3/29(土)の毎週土曜日に塾があり、受講後はレポ記事を書いてnoteに公開しています。
▼京都ライター塾についてはこちら
先日1/25(土)に第3回の講義がありましたので、昨日は前半編、本日は後半編を書き留めます。本当は1つのnote記事としてまとめたかったのですが、全然要約できず、こういう形での公開となりました(書いていると、自分の課題が見えてきます、本記事最後に忘れぬよう記載します)。
▼第3回の[前半編]はこちら
書き方を学んだら実際に書いてみよう~課題:私の好きな○○~
前半編では、インタビュー原稿を書くこと、原稿を書くためのステップについてまとめた。書き方を学んだら、次は実践。実際にライティングしてみよう!と私たち受講生へ以下の課題を与えられた(緊張とワクワク!)。
●課題内容
「私の好きな○○」について、450~500文字で書いてみよう
(2月1日(土)〆切)
●商業ライターとして書いてみること
主観的ではなく客観的に書くこと。私の場合、noteでは主観でしか書いてこなかったので、客観的・第三者として書く難しさに直面している。好き好き!の気持ちが入りすぎると自分が入りすぎてしまう。どれだけ自分から引いて書けるかが、書く上での課題の1つになる。
●記事の見た目も大事
公開する記事はもちろん、原稿の段階でもパッと見たときの読みやすさが大事とのこと。クライアントやデザイナーさんに提出する原稿の見やすさを配慮することで、チェックしやすくなり、記事の内容も伝わりやすくもなる。
確かに、パッと見て文字が詰まりすぎていたり、句読点の位置が改行されたあとすぐにきたりすると、それが気になり見るのを止めてしまう経験がある。江角さんからご教示いただいた内容を元に、自分の書いた記事を使って確認してみた。
▼配慮前

▼配慮後

どこに何が書いてあるか分かるようにするだけで、見やすさが全然違う。自分以外の誰かが見るものなんだ、ということを意識しながら見た目を整えていこうと思う。
誰に向けてどういう記事を書きたいのか
普段書いているnoteは、誰に読んでほしいか、何を伝えたいかを明確にしていない。ただその時に思いついたことをつらつらとパソコンで打つだけで、書いたものがどう届くか意識してこなかったのが現状だ。
江角さんより、書く前に考えておきたいことを4点教えていただいた。
●誰が読むのか?
●文体はどうするか?
●この記事を通して何を伝えたいのか?
●読んだあと読者にどうなってもらいたい?
この4点を聞き、今まで自分が書いてきたものは、読んでくださる方を迷子にさせていたかもしれないと思った。書く目的により変わってくるものだと思うが、伝えたいことを書くのであれば、書き手側が書く先を見据えていることが大事だと、改めて痛感した。上記を考える習慣をつくりたい。
振り返り
今回のレポ記事は2つに分かれてしまいました。講義の中で上述した課題の書き方について質問が飛び交っている際、「まずは文字数を気にせず書いて、そのあとに削る」という話が出てきました。
あれも伝えたい、これも伝えたいと書いた記事から削るのはかなり苦しい作業なのではと思ったのです。レポ記事は文字数制限がないものの、削るところは削って濃縮した記事に仕上げる、というのも1つの書く練習だと思います。これが今できていないので、削る難しさを思い知らされました。
また、何かを書くときの自分なりのスタイルがまだありません。
江角さんは、素材集めや構成を考えるときなど全てノートに書きだすと仰っていました。その後一気に原稿を書き上げて、記事を寝かして、推敲していくとのことです。
文字数が多くなるほど私の頭の中が混乱しているのが分かります。課題やレポ記事を書くときは、プロである江角さんを真似てみようと思います。
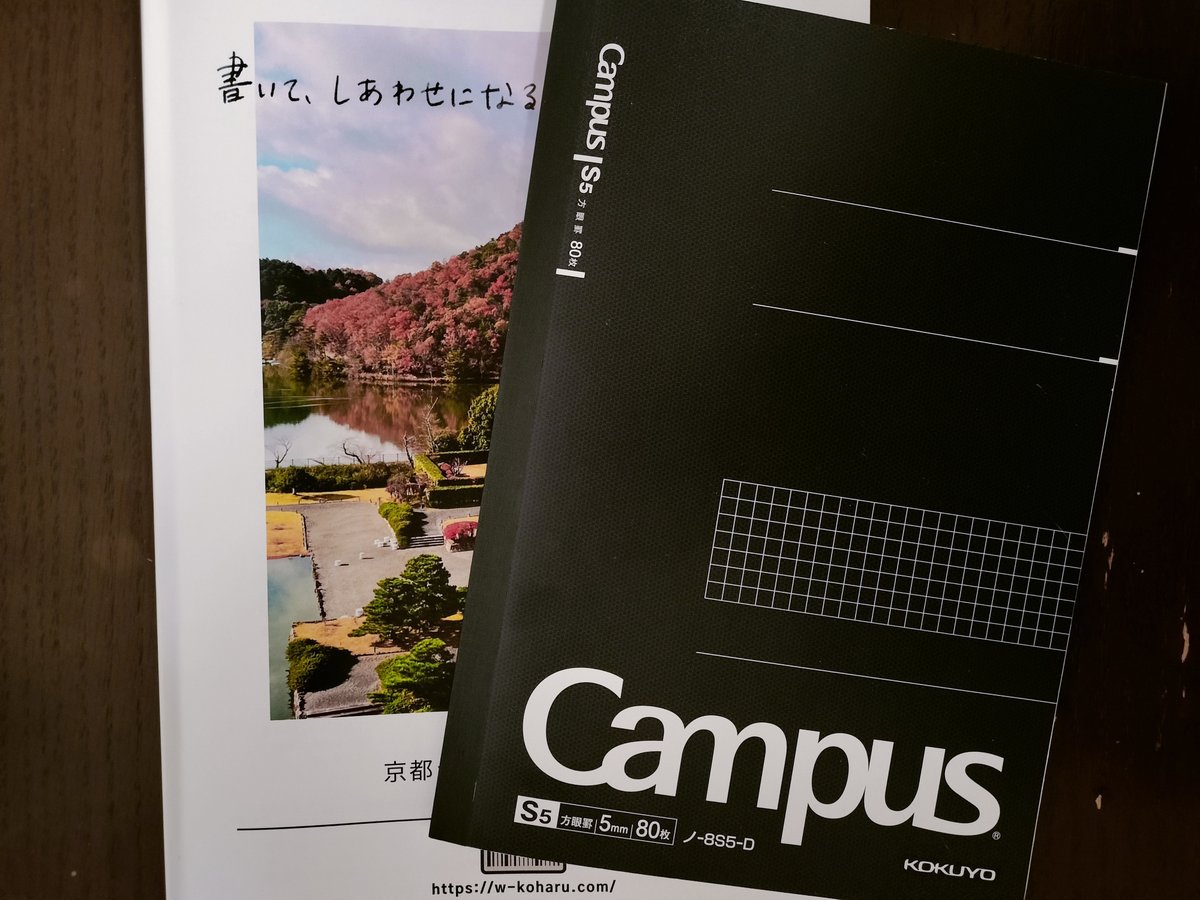
「インタビュー原稿が書ければ応用がきく!」
という言葉を講義でいただきました。
ここで書く基礎をどんどん作り上げていきます!
次回の講義は2/1(土)です。
毎週レポート記事を書いていきますので、ご興味のある方はぜひご覧いただけると嬉しいです!
お読みいただきありがとうございました。
