
「法人がお金を預かる意味」~特別編:教えてほしい!お金のこと💴
皆さん、こんにちは。早いもので、今年も残りわずかとなりました。
noteの投稿を始めて、約4か月が過ぎたでしょうか。
たくさんの方に届いているとうれしいな、と思います🍃
さて、前回の投稿で、東京家政学院大学(東京家政学院大学公式ホームページはこちら)の小野由美子教授のもとを訪ねた、という話をしました。
小野教授とのやり取りがとても勉強になったので、ぜひ読んでくださっている皆さんと共有したい✨と思い、今回は特別編でお届けします❗
前回の投稿はこちら▶▶▶
じぶんの大事なお金のこと。
自分の暮らしと切っても切り離せないものが「お金」。大人になってから、ようやく大事に使うとはどういうことなのか、適切に使うためにはどんな知識が必要なのかを考えるようになった気がします。
社会に出ると色々な誘惑があちらこちらに散らばっていて、とても難しいお金の流れや「契約」などがありますね。
クレジットカードの使い方、通信販売の利用方法、ゲームの課金など、暮らしの中でなんとなく蓄積していく使い方の知識ですが、たまに間違って、失敗することもあります🤦♀️💦
知っていますか?消費者教育📝
障害がある人の社会参加が進むことで、上記のような経験をする機会が増え、時には「消費者被害」に巻き込まれることも・・・。
しかし、障害がある人が社会に出て、自分の暮らしを作っていくこと、楽しんで暮らすことは、決して特別なことではなく、
「被害に遭うから」、「自分では管理できないのだから」という理由で、外出やお金の使用を制限することは誰にもできません。
とはいえ、家族や支援者の心配は尽きない・・・。
被害に遭わないための予防手段や、もし被害に遭ってしまった時には、早期に対応できる手段が知りたい❗
東京家政学院大学の小野教授は、当事者の消費者トラブルの早期解決には、予防的支援として「消費者教育」が求められると話されています。
▶ここからは、先日のお話の内容をもとに、インタビュー形式でお届けします。

センターかねこ: 消費者教育について、家族や支援者はどのように向き合えばいいのでしょうか。

小野教授: 知的に障害があっても、本人は消費生活を送る立派な市民、消費者です。消費者教育を受けることは、「消費者の権利」の一つです!本人が地域で安全に暮らしていくためには、消費者である本人の「消費者力」を高めていくことと、本人を見守る人の「見守り力」を高めていくこと、この両方が必要です。

センターかねこ: 「消費者力を高める」にはどうすればいいのでしょうか。

小野教授: 消費生活に配慮が必要な本人を支援するためには、本人の力を伸ばすことと、また見守る側の力も伸ばす必要があるということです。見守る側とは、親や家族、支援者や福祉関係者などを指します。本人は、困った時に「相談する力」、「つながる力」を伸ばすこと。そして、「断る力」を身に付けることが大切です。
また、見守る側の力とは、本人の変化に「気づく力」をつけること。実際に、本人に声をかける時の工夫などが身に付いてくると良いと思います。

センターかねこ: 困った時は地域に相談する場所はありますか。

小野教授: 地域には消費生活センターがあります。身近な家族や支援者に相談することはもちろんのこと、消費生活センターを活用することのメリットや利用方法を知ることも大切です。また、消費生活センターと支援者のみなさんの連携が必要不可欠です。
消費者ホットライン188を利用すると地域の消費生活センターにつながります。本人だけで難しいと思った場合は、信頼のおける身近な人と一緒に相談してもよいですね。
*全国共通の電話番号「消費者ホットライン188」ご案内👇
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/assets/local_cooperation_cms204_220815_01.pdf
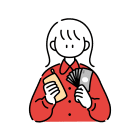
センターかねこ: 失敗しないために、お金の賢い使い方だけ知っておけばいいですか。

小野教授: 消費者教育は、適切なお金の使い方を学ぶことが大切です。本人が主体的に消費生活を送るために必要な教育ですから、そこに本人の「意思」、「判断」がきちんと反映されているかが重要です。本人の自己実現を支えていくための消費者教育です。
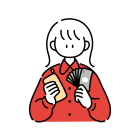
センターかねこ: どのような時期にどういう内容を身に付ける必要がありますか。

小野教授: ライフステージに応じて身につけたい内容は違います。4つの領域とライフステージに応じて、消費者市民社会を形づくる消費者になるために必要なことの一覧があります。(以下にリンク👇)
また、最近の特別支援学校(高等部)での実践では、より生活に身近な実践を繰り返し行っています。買い物の場面などの積み重ねでは、本人が体で覚えていくことも大切です。
【消費者教育の体系イメージマップ~消費者教育ポータルサイトより】https://www.kportal.caa.go.jp/pdf/imagemap.pdf
安心・安全に暮らしていくために
今回は、小野教授にお話しいただいた内容をご紹介しました。
障害がある人も、消費生活をおくる一市民。
暮らしのカタチは様々です。そして、必要な配慮も人それぞれ。
私たち支援者は、本人の力をよく理解することが必要になると思います。
そして、本人の力を高めていくことと同時に支援者も「気づく力」が必要ですね。
気づいた時には、つい「なんで?」「どうして?」と問い詰めたくなってしまうものですが、ここはグッと堪えて、状況の確認をしながら、本人の色々な思いに寄り添いたいものです😊
もしもの時、本人から迷わずに「困ったよ・・・」と言ってもらえる空気感を作っておきたいな、と思います。
おわりに
今、地域で暮らすご本人の中には、こういった教育や情報提供を受けてこなかった人も少なくないと思います。
特別支援学校との連携はもちろんですが、地域における消費者教育の拠点として、消費生活センターとの連携が必要だと思います。
支援者は、どうしても事業所内で解決していこうという気持ちが働きますが、消費活動、消費生活の専門家に頼りながら、本人の暮らしを見つめることも大切ではないでしょうか。
最後に、この場をお借りして、小野先生、お忙しい中、本当にありがとうございました✨
以下、小野教授が寄稿された記事をご紹介します。
当センター運営委員である佐藤彰一先生の記事も掲載されていますので、ぜひご覧ください ▶▶▶
📝次回は、再び「法人がお金を預かる意味」として、今後の法人の取り組み、支援現場で展開する「預り金の支援」について、お話したいと思います!
それでは、皆さま、よいお年を~👋🎌
