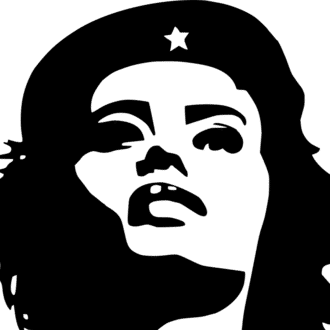李啓充『アメリカ医療の光と影』読み直した
だいぶ前にさらっと読んでそのままになっていた本を読み直したのだ。
初版は2000年なのでもう20年以上前なんだなあ。当時は(今もかもしれないが)ネオリベラリズム全盛期で、マネジドケアなどのアメリカ風の医療制度の導入が叫ばれていた。当時は欧米の医療は技術的にも制度的にも日本より優れているとなんとなく思っている人が多かった、今もかもしれないが。
そのころ私は医学生だったり研修医だったりして、そういう世間の風潮に異を唱える医師らの意見をよく聞いたものだ。本書はそうした一冊である。著者の李啓充先生はアメリカの医療制度に明るい医師で、この手の本をたくさん出されている。
本書の前半は医療過誤の防止についてのアメリカの歴史で、データを活用してエラーを減らしていくというのはアメリカの得意なところで、数少ない日本が学ぶべき分野であろう。ただしちょっと古くて今ではわりと当たり前のことばかりである。それでも歴史を知るのは楽しい。
後半はいかにアメリカの医療保険が残念かこれでもかと書いてある。公的な保険が機能していない。民間の保険会社は、加入者を増やすために保険料を抑えなくてはいけないが、利益を出すためには支出を抑えなくてはいけない。だから医師は十分な治療をできない、ということが普通におこる。
これを初めて読んだときは酷いことだと思ったものだ。しかし今はちょっと違う感想である。日本では思う存分治療できるのはいいんだけど、保険料の負担がわかりにくい。現役世代に社会保険料という形で過剰な負担を強いているのだが医療の受益者にも提供者にもわかりにくいのである。これがいろいろな形でモラルハザードをおこしている。
アメリカではそのようなモラルハザードはおこりにくいだろう。過剰な医療が行われれば保険料の高騰という形で加入者に跳ね返ってくる。まあそれでも国民医療費は日本はアメリカよりはるかに安いので単純には言えないのだが。。。
アメリカの医療制度を知ると、同時に日本の国民皆保険の利点も明らかになる。まず問答無用で全員加入なのでチェリーピッキングがおこらないのだ。自由がない、選択の余地がないというのは一般にはデメリットと思われがちだが、より一般的にいうなら自由になると人間はろくなことをしなかったり、なにもしなかったりするので、自由は適度に奪われているほうがいいのである。
他に興味深かったのは、Amazonの子会社などがオンライン薬局を運営し始めているという話だ。オンラインで購入するほうが実店舗よりも安いという、医療費の高いアメリカならではの出来事であるが、こういう思い切ったサービスを許容するゆるさは経済や技術の発展を促してきたのだろうと思う。先に述べたとおりこれは20年以上前の本である。日本ではいまだにリアルな薬局にいかないと処方薬は手に入れることができない。
というようなことをツラツラ考えながら読んだのであった。
同じ著者の続編的なものもあるのでそのうち読みたいと思っている。
関連記事
いいなと思ったら応援しよう!