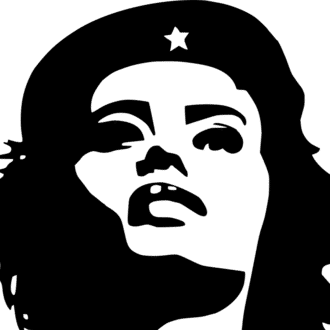『クライテリオン』5月号、コロナ疲れとEURO2020
サッカーヨーロッパ選手権(EURO2020)盛り上がってるね。
私はあんまり見れてないけど。
ハリー・ケイン最高。
盛り上がりにともなって、欧州各地でDelta Variantが拡散しているようだ。
しかし、ワクチン接種が進んでいるのもあってか、当局は軽く諌める程度で、強く自粛を呼びかける雰囲気ではない。少なくとも本邦の専門家()のような悲壮感はない。
もう日常がないのが我慢できないって感じにみえる。
こうした堪え性のなさが、白人国家が世界を制した要因とも思えてくるし、ワクチンの開発にもいち早く成功した理由かもしれない。
堪え性があったら大西洋を渡ろうとか思わないだろう。中国だって鄭和がええとこまでいってたんだから、技術的には大航海時代やっててもおかしくはなかったのに。まあ当時の欧州には強大な帝国がなかったので、大航海時代やってるひまあったら中央アジアの騎馬民族と戦ってくれよとはならなかったのだろう。
というようなことを考えつつ、保守系雑誌『クライテリオン』5月号を読んでいたのであった。
テーマは「コロナ疲れの正体」だそうだ。
面白かったのは、東浩紀氏らの対談かな。東氏が保守系雑誌の対談に登場しているところに時代の流れを感じますな。
東氏は、リベラルを自認していた言論人たちが徹底自粛や、政府の強固な対応を求めるのを半ば呆れつつ批判してきた。私も、「え?あなたたちが今まで言ってきたことはなんだったの?」と思ったりしたものである。これに関連する箇所を引用しておく。
皆が「自分が叩かれるのは避けたい」と考えて行動した結果、下の世代、子供たちの世代から教育の機会や人との出会いの機会を奪っている。仕方ないところもあるけど、これに対する自責や反省の念みたいなものがもう少し欲しいなとは思います。そういうものがほとんどないことに、ちょっと呆れ果てている。
これに応えて、藤井聡編集長がひどいことをいってるので、引用しておこう。
実際に僕の回りの過剰自粛に陥った言論人たちの共通項って、いわゆる常識的な社交をしない人たち、あるいは、円滑な社交をする能力が元から限定的だったっていう点だったんですね。
円滑な社交をする能力が元から限定的
まあまあ刺さりました、、、
気を取り直して、次は政治学者三浦瑠麗氏と宮崎哲弥氏と藤井聡編集長の対談。これもけっこう面白かった。
印象的だったのは三浦氏の冒頭の発言。
本心ではインフルエンザと同様の扱いにすべきだと思っていますよ。けれども、一旦、こういう感染症の指定にしてしまった以上は、ここから何ができるかというふうに、現実的に考えていますね。
良い意味でリアリストでプラグマティストでマキャベリストなんだなあと思った。対談でもそういう氏のそういう側面は何度か表れていて興味深かった。
他にも佐藤優氏、小林よしのり氏の対談などもまあまあ面白かったが割愛。
本号で藤井氏は、西浦博氏のモデルが計量行動学の界隈でフルボッコにされていると何度も指摘している。それは私は知らなかった、というかそんな界隈があるのを知らなかった。西浦氏のモデルの批判は大手メディアでは流されないから、その事実を知りようもないのだが、まあそうでしょうねって感じである。なお医師で西浦氏を批判する人がほとんどいないのは、言論統制されているからではなく、医師の数学力ではモデルを理解するのが困難だからである。ちなみに私もよくわかっていない。
書評欄で、私も翻訳に協力したステファニー・ケルトン『財政赤字の神話』が良かった。え、Audible版いつのまに出たん、、、
評者は金濱裕さんという方で、わかってるな、という感じだった。たしかMMTのシンポジウムで質問されているのを見たことがある。MMTをちゃんと理解していなければ書けない書評だと思った。
いいなと思ったら応援しよう!