
雑談*サンタクロースとトナカイとキリスト教
クリスマスにちなんだお話を。
日本にはキリスト教会もあるしキリスト教徒もいるけれど、割合的に日本は非キリスト教国です。

非キリスト教国だったこととヨーロッパから遠かったおかげで、血を洗うような宗教革命には巻き込まれずに済みましたが、日本人はカトリック&イエズス会嫌いが多い気がします。
秀吉が奴隷貿易に日本人を利用としていたバテレン(ポルトガル人)を追放したという話はさて置き、建前上の鎖国時代にプロテスタントのオランダから受けた影響なんでしょうか。
進化生物学者リチャード・ドーキンスは、脳内情報の単位を「ミーム」と定義し、文化的な情報は模倣によって自己複製しながら人から人へ(脳から脳へ)と伝達され、文化を形成すると主張。その振る舞いは「ウイルス」と同義であり、コロナ禍で異様な光景が広がったのも「ミーム感染」によるものが多い。 pic.twitter.com/vGxA2lFS5H
— あいひん (@BABYLONBU5TER) December 20, 2024
でも、イースターやハロウィンやクリスマスのイベントが好きな人は多いように見えますね。
キリスト教が好きなわけじゃなく(キリスト教について、よくわかっていない人が多いし)、神秘的な雰囲気が好きだったり、祭事として捉えているから好意を感じたり、みんなで集まって騒ぐのが目的だったりなんでしょう。
要するに「カブレ」なんですよね。
私も人のことは言えませんが(苦笑)
私はキリスト教徒ではありませんが、子どもの頃に父親に「聖書を勉強するといい」と言われてキリスト教にカブレました(苦笑)
****
鹿児島の田舎育ちの私がクリスマスというものを知ったのは、駄菓子が詰まった「サンタブーツ」(クリスマスブーツ)がきっかけでした。

クリスマスの原型
クリスマスの原型は、古代ローマのサートゥルナーリア祭です。
農耕の神サトゥルヌスを祝した祭りは、12月17日から12月23日まで(ローマ暦およびユリウス暦で)を開催期間としていました。
公的な儀式の他に各家庭でも個別に祝う習慣があり、小さなプレゼント (saturnalia et sigillaricia) を作って贈り合いました。
12月25日をイエス・キリストの誕生日としたのは大人の事情(キリスト教会の事情)でした。
ローマ帝国がキリスト教の支配下に入ると、非キリスト教徒が祝っていた「冬至祭」(冬至の後の太陽の復活を祝う)をイエスの誕生日に置き替えたのでした。
(ぶっちゃけ、イエスは12月25日に生まれていません)

紀元1世紀ごろの初期のキリスト教徒がイエス・キリストの誕生日を知っていたという歴史的証拠はない。実際、当時のユダヤ人の法律や慣習では、誕生日は全く記録されなかったと見られている。
World Book Encyclopedia(第3巻、p416)によれば、初期のキリスト教徒は誕生日を祝う習慣は異教徒のものだと見なしていた。
実際イエスが自分の生涯について何らかの記念に類することを命じたのは、死に際してのことだけだった(ルカによる福音書、22:19)
昔、イギリスやアイルランドでは、12月25日は冬至祭を行い、新しい種まきと刈り取りのために休息し、豊穣を祝いました。
農場労働者は、この日に1年間の給料を支払われ、春まで3か月間休暇を取ったそうです。

日本初のサンタクロース
日本に初めてサンタクロースとクリスマスが入ってきたのは、明治時代にあった外国人居留地からだろうと察します。
Wikipediaには、「1874年、日本では築地居留地にあった学校で開催されたクリスマス会にて、戸田忠厚扮する殿様姿のサンタクロースが登場した」とありました。
戸田忠厚(とだ ただあつ、1851年〈嘉永〉 - 1922年〈大正11年〉5月26日)は、現在の埼玉県行田市にあたる武蔵国忍藩(おしはん)の藩士、水谷右衛門の次男として生まれ、幕臣の戸田家に養子に入りました。
戸田家は、清和源氏の流れを組む家柄だそうです。

戸田忠厚が日本人初のサンタクロースに扮したのは、築地居留地6番にあったプロテスタント長老派のミッション・スクール、原女学校で開催されたクリスマス行事だったそうです。
築地居留地
1869年に築地鉄砲洲、今日の中央区明石町一帯の約10ヘクタールに外国人居留地が設けられました。
主にキリスト教宣教師の教会堂やミッションスクールが建ち、青山学院や立教学院、明治学院、雙葉学園の発祥地となっています。
現在この地区のシンボルになっている聖路加国際病院も、キリスト教伝道の過程で設けられた病院が前身でした。
最盛期には、9カ国300人以上の外国人が暮らしていたそうです。欧米では被差別対象者であったユダヤ人も商人に多かったとのこと。
1899年の治外法権撤廃で法的に廃止されたあと、1923年の関東大震災で立ち並んでいた洋館は全て失われたそうです。

原女学校の創立者ジュリア・カロザース(ジュリア・ドッジ)は、1869年(明治2年)7月に夫であるアメリカ合衆国長老教会の宣教師クリストファー・カロザースとともに来日し、東京で伝道を開始しました。
1874年当時、原女学校には23名の生徒がおり、長老派女学校(Presbyterian Mission Female Seminary)と呼ばれていたそうです。
夫のクリストファー・カロザースは、築地居留地に隣接する新湊町4丁目に寄宿舎付きの英学校を開設しました。
米国長老派が運営するこの学校は築地大学校もしくは東京大学校とも呼ばれていました。
築地大学校は外部生を含め約150人の生徒が在籍し、都筑 馨六(つづき けいろく)、尾崎行雄などの明治時代に活躍した人材を育成しました。

尾崎行雄は、東京市長時代の1912年(明治45年)にアメリカ・ワシントンD.C.のポトマック河畔にソメイヨシノの苗木を寄贈したことでも知られ、返礼として日本に初めてハナミズキをもたらした。聖公会信徒。
築地大学校の学生でカロザースから洗礼を受けた、原胤昭(のちに築地に東京第一長老教会を設立します)が洗礼への感謝の催しとしてクリスマス会を開き、その際に戸田忠厚がサンタクロースに扮したのです。
戸田忠厚は裃を着用し、大小の刀を差し、鬘をかぶった純日本風のサンタクロースだったと伝えられています。

原胤昭の父は江戸南町奉行所吟味方与力・佐久間健三郎、母は南町奉行所年番与力・原胤輝の娘とき。兄佐久間長敬は江戸幕府の与力、明治維新後は東京裁判所職員になりました。
原は洗礼を受けた同年にキリスト教書店の十字屋(銀座三丁目にある、現在は楽器販売会社)を創業し、1876年(明治9年)にジュリア・カロザースが辞任したあとの学校を改組して原女学校を開設しました。
*****
サンタクロースのモデル
サンタクロースのモデルは、「ミラのニコラオス(ニコラウス)」と言われています。 ニコラオスは現在のトルコのリキュアで生まれました。
ニコラオスが司祭だった頃の逸話として・・・
かつては豪商だったが財産を失い貧しくなった商人の家の三人の娘たちが身売りをしなければならなくなったとき、ニコラオスは真夜中にその家を訪れ、窓から(あるいは煙突から)密かに2度、金貨を投げ入れました。
この金貨のおかげで娘たちが身売りをしなくて済んだので、商人は大変喜び、誰が金を投げ入れたのかを知ろうとして見張っていたところ、3度目に金を投げ入れたニコラオスを見つけ、商人は涙を流し感謝したと伝えられています。

この逸話が由来となり、「夜中に家に入って、靴下の中にプレゼントを入れる」というサンタクロースの伝承が生まれたようです。
聖人として列聖されているため、「聖(セント)ニコラオス」と呼ばれています。
オランダ語では「シンタクラース」となり、オランダでは14世紀頃から聖ニコラオスの命日の12月6日を「シンタクラース祭」として祝う慣習がありました。
その後、17世紀アメリカに植民したオランダ人が「サンタクロース」と伝えたのが、サンタクロースの語源になったと言われています。
ドイツの古い伝承では、サンタクロースは双子で、一人は紅白の衣装を着て良い子にプレゼントを配り、もう一人は黒と茶色の衣装を着て悪い子にお仕置きをする(クネヒト・ループレヒト)。
容姿・役割共に日本のなまはげに似ており、民俗学的にも年の瀬に来訪する年神としての役割の類似が指摘される。
現在、ドイツでは聖ニコラウスは「シャープ」と「クランプス」と呼ばれる二人の怪人を連れて街を練り歩き、良い子にはプレゼントをくれるが、悪い子にはクランプス共に命じてお仕置きをさせる。

Wikipediaによると、日本では1900年に発行された子供向け教材の道徳教育の教科書に初めてサンタクロースが登場したそうです。
ただし名前は「北國の老爺 三太九郎」。
小説の表紙には、アジア人っぽい顔で頭にはフードをかぶり革のバッグを掛け、手にはツリーを持ちロバがプレゼントを運んでいる。
寒い北国に住む貧しい少年が、迷子の旅人を助け、病気の父の看病に精を出し、三太九郎からたくさんの贈り物をもらうというストーリーであった。
1914年、『子供之友』誌に、赤い帽子に赤い服を着て太いベルトを腰に巻いた、現代と同じイメージのサンタクロースが盛んに描かれるようになったそうです。

サンタクロースのトナカイ
トナカイが引く橇に乗っているサンタクロース像が定着したのは、アメリカのデパートのクリスマス販促キャンペーンがきっかけだったそうです。
でも、このトナカイに名前がついていたのは、アメリカ以外ではほとんど知られていません。
(私もさっき知りました(苦笑)
日本では『ルドルフ 赤鼻のトナカイ』のほうが知られている気がします。

1823年12月23日に『センティネル』紙(Sentinel))に無名で発表された子供向けの詩『クリスマスのまえのばん』(原題:“A Visit from St. Nicholas”)で、8頭のトナカイの名前が付けられました。
詩の内容は、クリスマスの前の晩に子供たちの父であると思われる「私」が、トナカイの引くそりに乗ったサンタクロースが贈り物を持ってきてくれた様子を目撃するというものです。

それはクリスマスの前の夜だった・・・
ワシよりも早くトナカイたちは飛んできて
サンタさんは大声で名前を呼んだ。
「そらダッシャー、そらダンサー、それプランサー、ヴィクセン、
行けコメット、行けキューピッド、ドナー、ブリッツェン、
ポーチの上まで、煙突の上まで!
早く走れ、それ走れ、みんな走れ!」
作者とされているニューヨークの神学者クレメント・クラーク・ムーア(1779年 - 1863年)は、イングランド系アメリカ人で、ニューヨーク市のプロテスタント聖公会総合神学校で東洋・ギリシア文学、神学、聖書学の教授を務めていました。

父ベンジャミン・ムーアは、1775年に、現在もウォール街向かいのブロードウェイ89番地にある、ニューヨーク市の最初の英国国教会であるトリニティ教会の副牧師に任命されました。

アメリカ独立戦争後、アメリカ合衆国聖公会(ECUSA)は英国国教会から独立し、1815年にベンジャミンは第2代ニューヨーク主教になりました。
またアメリカ合衆国聖公会はキングス・カレッジ(現在のコロンビア大学)の創設に関与していたので、ベンジャミンは コロンビア大学の5代目学長でもありました。
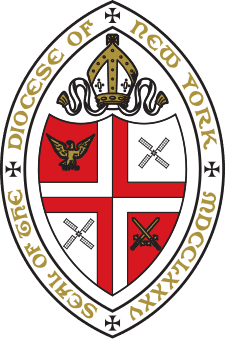
クレメント・クラーク・ムーアの母チャリティは、イギリス人将校トーマス・クラーク少佐の娘でした。
トーマス・クラーク少佐は、マンハッタンに広大な土地を所有し、ロンドンにあったロイヤル・チェルシー病院にちなんでチェルシーと名付けました。現在もそこは「チェルシー」地区と呼ばれています。
祖母サラ・フィッシュは、マンハッタンの初期開拓者の一人であるエリザベス・フォーンズとジョリス・ウールジーの子孫であった。
エリザベス・フォーンズ(エリザベス・フォーンズ・ウィンスロップ・フィーク・ハレット、1610年1月21日 - 1673年頃)の母は、アン・ウィンスロップ(熱心なピューリタンで後にマサチューセッツ湾植民地の総督となったジョン・ウィンスロップの妹)。

そのほとんどはもともとムーアの邸宅の一部だった。
ムーアは、チェルシーの66区画の土地を聖公会に寄付し、1817年に建てられた米国聖公会総合神学校は、現在も運営されています。
ほかにもムーアが寄付した土地に、セント・ピーターズエピスコパル 教会が建てられています。

クリスマスの思い出
私の子どもの頃のクリスマスは、今では人気がないバタークリームのクリスマスケーキでした。懐かしいです。
たくさんの種類のケーキがない時代、クリスマスは唯一ケーキが食べられる日でした。

クリスマスにちなんだ童話や絵本、小説もたくさんありますね。
私が一番好きなのは、ディケンズの『クリスマス・キャロル』かな。
エベネーザ・スクルージという名前のごうつくばりのお爺さんが、クリスマスに現われた過去、現在、未来の精霊によって不思議な体験をさせられ、スクルージは改心して、温厚な慈善家に変容します。
「メリー・クリスマス」というフレーズは、『クリスマス・キャロル』で使われたことでヴィクトリア朝の人々に広まったとも言われています。

ディケンズを読んだのは文学少女の端くれだった何十年も前ですが、作品には良い印象しかないです。孤児のオリバーの話『オリバー・ツイスト』も良かったです。
ちなみにディケンズは、愛人と結婚するために妻が子供たちを愛しておらず精神障害を患っていると言って妻を施設に入れようとしたしょうもない男です(苦笑)
****
現代の日本を見ていると、江戸時代まではポルトガルもオランダも(一部を除き)日本人をキリスト教に改宗させることはできなかったけれど、明治以降、あの手、この手でちょっとずつキリスト教化は進められていたんだなぁと思いました。
でも、世界統一宗教を急いでいる層は、そんな日本にじれているでしょうね・・・今までのように安穏としていられない感じがしています。
今日はこのへんで。最後までお読みくださりありがとうございました。
