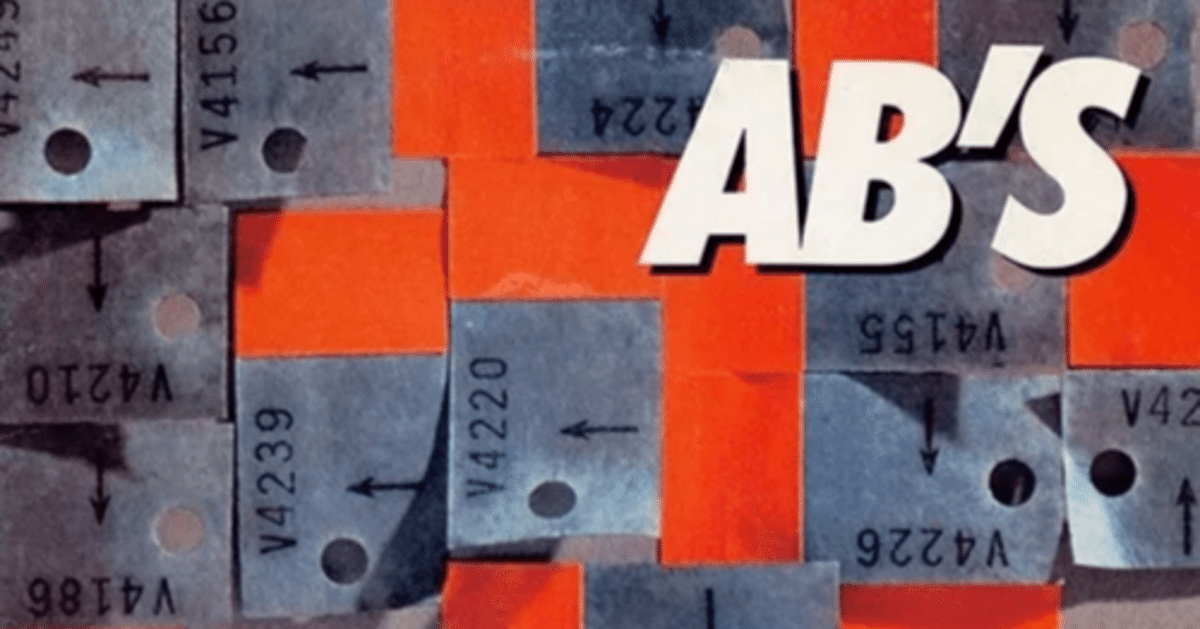
AB'S 『AB'S』 (1983)
━━━少し前のことだが、私はブルーノ・マーズとアンダーソン・パークのスーパー・デュオ、シルク・ソニックのアルバム『An Evening with Silk Sonic』を聴き終えて、音楽のチーム・アップがいかに理にかなっているかを再確認した。ドクター・ドレーとスヌープ・ドッグであれ、マイケル・マクドナルドとジェームス・イングラムであれ、スーパースターの才能を組み合わせれば、素晴らしい結果がもたらされる。例えば、このジャンルを代表する2人のクルーナー、松下誠と芳野藤丸が伝説的なタッグを組んで結成したAB'sがそうだ。本日はシティ・ポップ・リバイバルによって掘り起こされた名盤、『AB'S』をご紹介する。
AB型の飛行演習
AB'S(エイビーズ)は1982年、SHŌGUNの芳野藤丸(G,VO)、スタジオ・ワークとソロ活動中心の松下誠(VO,G)、元PARACHUTEの安藤芳彦(Key)、元スペクトラムのリズム隊、渡辺直樹(B)、岡本郭男(Dr)により結成された。芳野が「よろしく哀愁」「いちご白書をもう一度」「恋の暴走」「Bad City」などでギター演奏をしていたことをはじめ、全員が豊富な音楽キャリアを持っていた。ツインギターのバトルやノリの良いリズム隊と、コーラスワークが特徴。芳野の本格的な英語歌詞のボーカルに、渡辺のファルセットボイスが交じり合っていた。

松下自身のデビュー・アルバム『FIRST LIGHT』(1981年)を聴いた藤丸は、同じような雰囲気と美学を生み出すために、アルバム制作のコラボレーションをしようと彼に声をかけた。2人はまた、1979年から1981年までブラス・ロック・バンド、SPECTRUMに在籍していたベーシストの渡辺直樹とドラマーの岡本郭男ともそれぞれチームを組んだ。岡本は吉野のAORグループSHOGUNのバンドメイトでもあった。さらに、キーボードの腕前と作詞作曲の才能を買われ、元パラシュート・バンドの安藤芳彦(あんどう・よしひこ)も加わった。吉野、松下、渡辺がAB型(数年後、藤丸は自分がB型であることを知る)、安藤と岡本がA型だった。このAB型が最初に手掛けたプロジェクトは、実は吉野の個人的な1982年のソロアルバム『YOSHINO FUJIMARU』であった。その後、彼らは桑名自身の1982年のアルバム『ムーンライト・アイランド』のバックを一緒に務めることになる。固い結束を築いた後、彼らは自分たちのアルバムのレコーディング・セッションを開始し、1982年12月にはシングル『Girl/Django』を、1983年1月にはセルフ・タイトルのデビュー・アルバム『The AB's』をリリースした。彼らはまた、1984年にイギリスの伝説的なコンピレーション・レーベル、Streetsoundsから、彼らの最初のトラックである Deja Vuをシングルとして、またコンピレーションの一部としてイギリスで非公式にリリースした。『デジャ・ヴ』は 全英オフィシャル・トップ100アルバム・チャートで80位を記録。
もう二度と恋をすることはない
多くのジャンルや音楽ムーブメントと同様に、シティ・ポップは驚くほど幅広いジャンルだ。それもそのはずだ。シティ・ポップは、その全体像が海外のリスナーにとって魅力的で、インターネットを通じて新たな命が吹き込まれてきたジャンルである。山下達郎や大貫妙子、竹内まりやなどの著名なアーティストたちが、インターネット文化で人気を博したことも一因だ。全盛期にはその人気は圧倒的で、今でもこのスタイルのポップスに挑むアーティストは存在するが、当時ほどの勢いはもはや感じられない。
シティ・ポップの時代には、様々なバックグラウンドを持つ人々、例えばビジネスを拡大しようとするモデルや、プロとしての道を志す若者たちが、地元や全国規模で音楽シーンに挑戦したが、その中で目立った存在となったのはごくわずかだった。競争の激しいシーンでは、スタイルが一つの方向に偏り、ラジオの再生回数が販売の鍵となる時代に突入したため、多くのレコードが期待されるシングル曲に依存した、平均的でつまらない内容のものとなってしまった。アルバム全体として高い完成度を持つ作品を提供するアーティストは一握りであった。これらの要因により、多くのアーティストは数回の活動で消え去るか、一度のヒットで満足し、その後は引退していった。その結果、彼らの音楽は80年代というシティ・ポップの海の中に埋もれてしまった。 それでも、シティ・ポップが比較的短命で限られた日本の音楽ムーブメントだったことは、興味深い点を浮かび上がらせる。少しでも興味を持ってこのジャンルの様々なアーティストやアルバムを掘り下げると、どの時期のどの作品であっても、同じ名前がクレジットに繰り返し登場することに気づくだろう。これは驚くべきことではない。というのも、80年代の日本では経済が不安定であり、大衆的人気を博さない限り、ラジオ放送やレコードの売上だけで生計を立てることは難しかったからだ。さらに人気アーティストであっても、ソロ活動で収入を得るためには、ライブパフォーマンスの成功に頼る必要があった。そのため、多くのミュージシャンは自分のプロジェクト以外にも参加していた。コマーシャルのジングル制作や、俳優業、ライブやスタジオでのバックアップミュージシャンなど、多岐にわたる活動に関わり、結果としてシーンの裏側では多くの人々が互いに顔見知りとなっていた。こうした背景があったため、特別な出会いが生まれ、そこから素晴らしい成果が何度も生まれたのは自然なことだ。
確かに、シティ・ポップは過剰に供給されたジャンルではあったが、それでも平凡さや埋め草の中にあっても、ユニークさと才能で光り輝くプロジェクトやアーティストが存在した。その一例が、1980年代のジャズ・フュージョンとシティ・ポップのスーパーグループ「AB’S」なのだ。
デ・ジャ・ヴュ
AB’Sの結成の背景は非常に特異だが、彼らがスタジオ録音で提示した音楽スタイルもまた一風変わっている。例えるなら、当時のカシオペアが見せていた音楽性に近いものがあるだろう。AB’Sのデビュー作は、シティ・ポップに対するよりテクニカルなアプローチを示しており、ジャズ・フュージョンやジャズ・ファンクの要素を取り入れつつ、ポップの構造と融合させたユニークなサウンドが特徴だ。作品ごとに異なる雰囲気へと発展していくが、完璧とは言えず、曲作りの面で細部が不足している部分もある。それでも、それらは些細なことであり、全体の体験を損なうことはない。
特にプロダクションは非常にクリアで、時代を先取りした仕上がりとなっている。各メンバーがミックスの中で自分のスペースを確保し、明るく活気に満ちたサウンドを生み出している。楽器の演奏自体は革新的とは言えないが、吉野のソロアルバムで見られたスタイルをさらに拡張したもので、その高い技術によって際立っている。バンドの才能あるメンバー全員が力を尽くしており、安藤芳彦が大半の曲の作詞を担当し、吉野と松下が主に作曲を手掛けている。この組み合わせにより、アルバム全体にはノスタルジーや幸福感、情熱が溢れる雰囲気が醸し出されている。
オープニング曲を見るだけでも、バンドのポテンシャルと才能が十分に伝わってくる。最初の曲「Déjà Vu」は比較的穏やかだが、その一方でベースとギターの掛け合いが特に際立っており、非常に動的な構成となっている。バンドの名刺代わりとも言えるこの曲は、メンバー全員の化学反応が感じられ、ボーカルの特徴的なパフォーマンスと楽曲の構成が絶妙に調和している。渡辺の作曲であることは、その重厚でグルーヴィーなベースに焦点が当てられていることからも分かる。リズミカルなギターアレンジ、シンプルながら効果的なキーボードの雰囲気づくり、そして素晴らしいドラムが全体を引き締めている。ボーカルの掛け合いも魅力的で、メンバーが一斉に歌いながら、独特の魅力的なトーンを生み出している。この曲がバンドの代表曲の一つとして人気を博したのも不思議ではない。1984年にはシングルとしてリリースされ、2枚目のアルバムのプロモーションに使用された。そのキャッチーで魅力的な性質が人気の理由だろう。6分間のランタイムをフルに活用し、フェードアウトして次の曲「Dee-Dee-Phone」へと続く。
「Dee-Dee-Phone」は、アルバムの2曲目で、ムードとトーンが一変する。特にプロダクションやミックスの特性を活かし、楽器は控えめながらも非常に効果的に機能している。音量が通常に戻ると、松下のギターが喜びとエネルギーに溢れた演奏を見せ、曲のタイトルが歌われる部分で爆発的に響く。渡辺のベースラインと岡本のドラムが完璧に補完しており、アルバムのハイライトの一つと言えるだろう。技術的な側面を最大限に活かしつつ、非常にキャッチーな曲となっており、メンバーの能力を見事に発揮している。
ギターソロが徐々にフェードアウトすると、次に登場するのは「Django」で、アルバムのプロモーション用にリリースされた2曲のうちの一つであり、松下の作曲である。この曲は、ソングライティングのアプローチが他の曲とは一線を画している。特にメインメロディを担うギターのアレンジが独特で、トーンやテンポが節ごとに変化し、メローでありながら魅力的なコーラスセグメントが印象的だ。構造自体は標準的だが、非常にうまく処理されている。インスト部分が最後までしっくりこない箇所もあるが、全体として楽しめる曲であり、バンドの才能と独自のアプローチが際立っている。
その後すぐに、より明るく、やや一般的な曲「Fill The Sail」が続き、吉野がアレンジを担当している。アップビートなメロディに、シンプルでメロディックなギターコードが使用されており、構造は非常にうまく目的を果たしている。ドラムはよりインパクトがあり、ベースも全体的に存在感を増している。特に最後のブレイクが素晴らしく、ギターのデュエルが繰り広げられる中、メンバー全員がコーラスのリプライズを歌い、アルバムの前半を明るい印象で締めくくっている。
アジアン・ムーンと夜の熱気
アルバムの後半は、「Déjà Vu」と似たようなスタートを切ろうとしているかのように感じられる。「Asian Moon」は、ほぼ同じ長さのトラックでありながら、オープニング曲「Déjà Vu」だけでなく、アルバムの前半全体に対しても大きなコントラストを提供している。最初はややメローな雰囲気を醸し出しているが、短いキーボードのイントロを経て、再びアップビートでテクニカルなアレンジに戻り、ボーカルが繰り返されることで、後半で展開されるトーンが定まっていく。再び渡辺の作曲で、ジャズとポップのユニークな融合が見られるが、特に際立っているのはベースラインで、曲全体の重要な要素として、他のパートと見事にシンクロしている。ここで、意外な展開が訪れ、アルバム全体のハイライトの一つとなる。ポップ寄りではなく、純粋で丁寧に作り込まれたジャズ・フュージョンのインストゥルメンタルセクションが登場し、プロダクションも非常に洗練されている。インスト部分ではボーカルも使用され、ドラム、ギター、ベースがリードする非常に強烈なブレイクがあり、雰囲気のあるキーボードが再び後退し、曲の終わりを告げる。技術的な面では「Déjà Vu」をさらに上回る仕上がりで、非常にユニークで磨き上げられた、記憶に残る一曲となっている。これはまるで真夜中に輝く月の光の下で、感情と情熱が祭りのように繰り広げられているかのようだ。
続く「In The City Night」は、より一般的なポップの構造を持っており、岡本が唯一作曲した曲だが、松下の作風に似た部分も多く見られる。それでも、「Asian Moon」の夜の雰囲気を引き継ぎながら、バンドが前半で見せた独特なポップアレンジとは異なるアプローチを提供している。キャッチーなコーラス、メローな感覚、そしてもちろんベースとギターの見事な技術が際立っている。アルバムの流れの中で意外なブレイクとして非常に効果的に配置されており、この特異なブレイクは、次のシングル曲「Girl」によってさらに強調される。この「Girl」は、アルバムのメインシングルであり、素晴らしい輝きを放っている。夜の雰囲気を保ちつつ、よりアップビートなコーラスとハーモニーを提供し、力強いギターがセグメントごとに際立っている。ラテン音楽の影響が感じられるギターソロは、まるで1970年代のサンタナを彷彿とさせるようなもので、情熱的でエネルギッシュなギターアウトロへとゆっくりと盛り上がり、月光の中へフェードアウトしていく。短くも感情豊かなトラックで、5人のメンバー全員が見事にボーカルパートを担当している。シンプルでありながら非常に魅力的で、特に「I'll Never Fall In Love Again」や「Wanted Girl」といった印象的なフレーズが楽曲を彩っている。
そして最後に登場するのが「Just You」で、非常に独特なクロージング曲だ。これは間違いなくアルバム全体で最も異質で特異な楽曲だ。アップビートな要素を全て排除し、完全にメランコリックなエネルギーで統一されている。トーンの変化や予期しない展開はなく、楽器の雰囲気とムードが一貫している。持続するギターの音色は、曲の冒頭から終わりまでこの特有の感覚を支えており、メローで感情豊かなボーカルパフォーマンス、そして重々しいベースソロが特徴だ。この曲は、最初に提示されたムードに忠実であるため、どこか場違いに感じられる部分もあるが、それでも記憶に残る魅力を持っている。アルバム中で最も弱い曲かもしれないが、その特有の哀愁が独特の魅力となっている。間違いなくユニークで、非常に感情的な楽曲だ。孤独や夜の悲しみをテーマに、過去の愛を思い起こさせるような情熱的なクロージング曲であり、適切なインストゥルメンタルアレンジによってこれらの感情が伝えられ、ほろ苦いエンディングを迎えている。
朝の珈琲店
AB'Sのデビューアルバムは、シティポップの世界において非常にユニークな存在である。その理由は、単にジャズ・フュージョンとポップの非常に印象的で独特なブレンドを提示しているだけでなく、一見シンプルに見える構成にもかかわらず、ダイナミックで魅力的な体験が詰まっているからだ。最初のトラックから最後の一音に至るまで、AB'Sはその才能、情熱、そして明らかなポテンシャルを披露している。楽曲のコレクションは多彩でユニーク、そして非常に楽しめるものであり、アルバムの前半はアップビートでエネルギッシュな曲調、後半はメローなトーンを取り入れて、ソングライティング、プロダクション、パフォーマンスの異なる側面をそれぞれ深化させている。
「Déjà Vu」のアップビートで魅力的なイントロダクションから、エネルギッシュで感染力のあるリズムを持つ「Dee-Dee-Phone」、テクニカルな面での見事なインストゥルメンタル・ケミストリーを見せる「Django」、メロディアスなギターと力強いドラムが印象的な「Fill The Sail」、深夜のムードが漂うジャズ・フュージョン色の強い「Asian Moon」、そして「Girl」や「In The City Night」の印象的な歌詞とハーモニー、さらには「Just You」における独特の哀愁と孤独感の表現まで、異なるスタイルに飛び跳ねながらも一貫した雰囲気を持った多様な体験を提供している。このアルバムは、従来のソングライティングのアプローチに対するユニークな解釈が光り、キャッチーな楽曲構成とともに、時折訪れる意外な展開がリスナーを驚かせる。特に楽曲の多くがライブでの演奏を念頭に置いて作られていることが明らかであり、バンドの即興性が発揮されることで、非常に記憶に残るクオリティの高いパフォーマンスが実現している。例えば、オリジナルメンバー全員によるエネルギッシュで爆発的な「Dee-Dee-Phone」のライブ映像は、YouTubeで視聴できるが、素晴らしい演奏が繰り広げられている。
吉野藤丸は、自分が求めていたサウンドに合うものを無意識のうちに探してバンドを結成したのかもしれないが、結果的にはそれ以上に特別なものを手に入れた。このバンドは、個人プロジェクトでも、誰か一人が注目を集めるようなものでもない。全てのメンバーが輝く瞬間を持ち、ソングライティングやアレンジにも全員が協力している。レコードのプロダクションとミキシングは非常に優れており、非常に洗練されてバランスが取れているが、曲ごとのスコープに応じて独自の要素を見せる点も際立っている。当時としては革新的なアプローチであり、レコーディングで使用された全ての要素に独自のスペースを提供することで、各メンバーの楽器が際立っている。その結果、5人の異なる音楽的背景と影響が融合し、非常にユニークで爆発的なレコードとなり、リスナーをさまざまな感情的かつテクニカルなサウンドスケープに導いていく。これは、1988年の最初の解散以前の初期において最も効果的で記憶に残るラインナップと素材であり、その理由の多くは、特に吉野と松下のギター間のインタラクションに見られる初期のケミストリーにある。このデビューアルバムは非常に印象的であり、バンドのポテンシャルと才能を最高の形で示しており、将来的なフォローアップでさらに磨かれた作品を期待させる出来栄えであった。
しかし、残念なことに、その後の展開は期待とは異なった。1984年に松下がバンドを離れ、セカンドアルバムの制作にわずかに関与しただけで、自身のバンドである日本のプログレッシブ・ロックバンド「パラダイム・シフト」に専念することになった。それ以降、AB'Sはさまざまなセッションミュージシャンを起用することに注力するようになったが、主要メンバーは「AB'S 3」までほぼ変わらずに続いていた。しかし、吉野藤丸がバンドの中心的な存在となったことで、エネルギーやケミストリーが変化したことは否めなかった。それでも、その後のアルバムも良作であり、音楽的に多くの魅力を持っていた。もしこの才能溢れるオリジナルメンバーが続いていたらどうなっていただろうという思いは拭えないが、デビューアルバムは素晴らしい要素を全て詰め込んだ遺産として今なお輝いている。日本のポップスの隠れた名盤であり、その音楽に身を委ねた者すべてを魅了し続ける一枚である。
もしTOTOのようなタイトでテクニカルなミュージシャンシップが好きで、かつLevel 42のジャズ/ファンクと、トッド・ラングレン風のアート・ポップの中間に位置するサウンドを探しているなら、AB’Sはまさに理想的な一枚だ。これは、シティポップのクラシックであり、親しみやすいグルーヴィーなサウンドを持ちながらも、適度に境界を押し広げ、聴き手を飽きさせない工夫が施されている。未聴の方はぜひ聞いてみてほしい。
