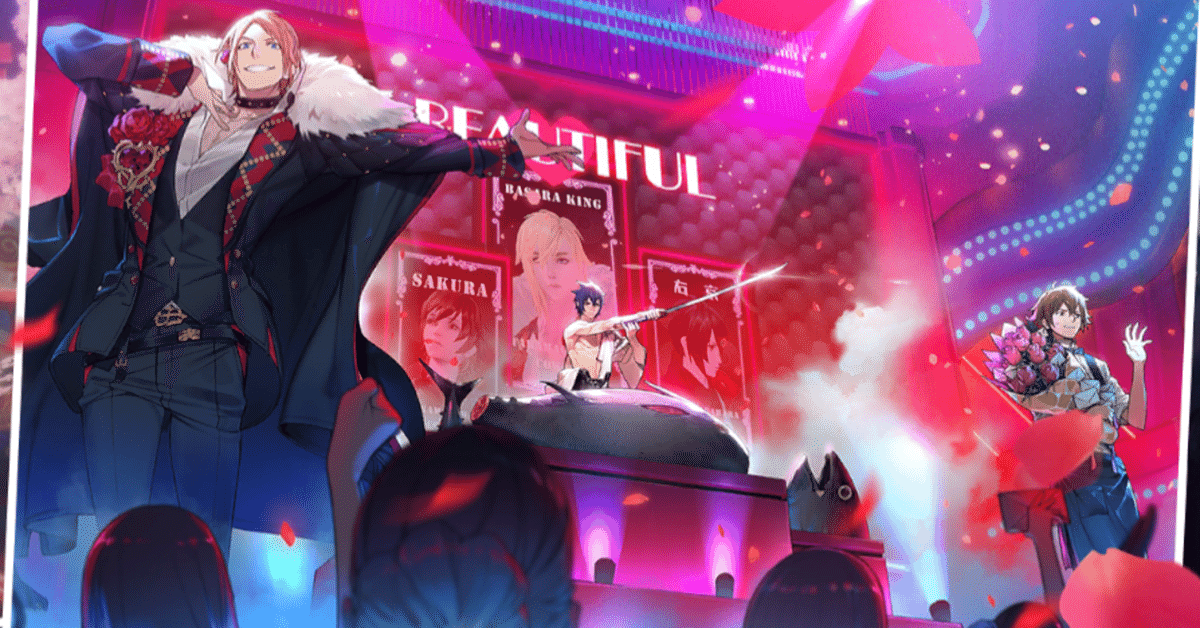
『龍族Ⅲ 黒月の刻』中編・第六章:男の花道
悔いのない恋だとか、彼の記憶の中にそんなものはなく……それらしいものがあるとすれば、あの時、ダイビングスーツを脱いだノノが泳ぎ出した時だ。微笑みながら彼にダイビングスーツを着させていると、その背後に突然龍の黒い影が現れて……。それは、二人が人生の中で最も近い場所に居た瞬間だった。ロ・メイヒは泣き喚いて彼女を抱きしめたいと思った一方、そんな資格は無いとも理解していた。自分はただの姉貴の子分、死の狭間にある彼女に泣いてやれる資格があるとでも? 死の淵で抱きしめてやる資格があるとでも? だからこそ、彼はただノノに全てされるがまま、潜水鍾に押し込められるまでの一切をぼんやりとみていただけだった……そこには後悔もなければ、愛らしい愛もない。
まるで波の上に浮かんでいるみたいだ――ロ・メイヒは、太陽光の柔らかな指先に身体をまさぐられているような感じを覚えた。
ここはどこだ? カリブ海? グレート・バリア・リーフ? それとも……天国? 本当に死んでしまったのかもしれない。そうでなければ、日本で雨の日の夜中に銃撃されて、目覚めたら日光きらめく海水あたたかなリゾートにいるなんてことに説明がつかない。
ラベンダーと海藻の香りが鼻腔いっぱいに広がり、海水が彼の下で波うち、緩み切った全身の毛穴が全開になっている……彼は恐る恐る細目を開け、一筋の視界だけを動かして辺りを見回した。
昔からずっとやっている習慣だった。子供の頃に見せられた革命的教育映画では、毎回日本兵が地下政党構成員の顔に水をぶっかけ、地下党員がおぼろげながらに目を覚ますと、日本兵は声を荒げて、暗号電報はどこだ、と叫ぶ。地下党員はそれに唾を吐いたり、革命的美辞麗句を誇らしげに叫んだりし、それを聞いて怒り狂った日本兵に向かってもう一度やってみろとかまで言ったりする。しかし革命的慧智の足りないロ・メイヒはいくらバケツの冷水を頭からぶっかけられても寝たふりをし続けるだろうし、日本兵に死にそうなのだと勘違いされて医者を呼ばれたりすらするかもしれない。
日光の下の霧の中、紫色のスカートを穿いた金髪女性が隣に座り、胸元に垂らした紐付きの小鈴をチリンと鳴らした。
エッッッ!? 日光浴に海水浴、おまけに美女と混浴してる!? ……ロ・メイヒは心の高鳴りを押さえられなかった。
ロ・メイヒが目覚めたのに気づいたらしい彼女は身を乗り出し、日光の下で海水のように澄んで輝くアクアマリンの双眸でロ・メイヒを見た。彼女がさらに身体を近づけると、少女の甘い香りがロ・メイヒを包み込み、視界全体が豊満な胸でいっぱいになり……巨大な胸は今にも服がはちきれそうだ。ロ・メイヒは羞恥と緊張を同時に起こし、この脚本いきなり変わりすぎだろ! と心の中で叫んだ。アクション・ホラー映画のごときヤクザ銃撃戦に巻き込まれた無辜の通行人を演じていたと思ったら、突然純愛アイドルドラマの男主人公になって、心を身構える隙もありゃしない!
いや……待てよ、この金髪、蒼眼、巨胸の形はどこかで見覚えがあるような気がする。なんだかよく見知った人のような……こんな外国人の逸者に会ったことなどないはずなのに。
「起きたのか!」その美女はロ・メイヒを海水から引き上げた。「すごいぞ! まずは冷たい一杯だ!」
即刻、氷入りウォッカが喉まで注がれ、ロ・メイヒはむせながら飛び上がった。「君……君は誰!? 僕……僕はどこ!?」
「落ち着け、落ち着け! お前、相当長い間寝てたんだぞ。不安になられても困るから酒を飲ませただけだ。まあ、見る限り元気そうだがな」逸者は力強く彼の肩を叩いた。
なんかこのヘビーパワフルボイスもすごい聞き覚えあるぞ!? 本当にどこかの知り合いなの!? ……ロ・メイヒは驚き定まらない視線を相手に向けた。
……そして、彼は再び水中で横になって目を閉じた。「何か変な世界で目覚めちゃったみたいだ。もう一回寝なおそう……」
「何千回寝直してもここにいるのは俺だぞ。それともソ・シハンと一緒がいいか?」逸者はシガーを咥えていた。
「いやいやいや、ボス、そういうことじゃなくて……誰が一緒に入るかとかじゃなくて、僕は多分、変な平行世界に来ちゃったみたいなんだ。だってボスが男の娘だよ? あのボスが男の娘っておかしいよ!?」ロ・メイヒは起き上がり、水に身体を預けた。
辺りを見れば、そこは熱帯ビーチでもなんでもなく、四方を松の木板で区切られた日本式の浴室だった。ロ・メイヒは深さ一メートル程の大きな浴槽に浸かり、芳しいラベンダーの香りは湯に混ぜられたエッセンシャルオイルだった。彼の隣に座っていた逸者はまさしくシーザー・ガットゥーゾその人、よく見知った金髪蒼眼の巨胸だが、その胸は300ポンドのバーベルをベンチプレスできる……。しかしロ・メイヒを本当に辟易させたのは、シーザーのその外観だった。シーザーは全身紫色のタイトスーツに身を包み、ヒョウ柄のシャツのボタンを三つほど外して大胸筋の谷間をこれとばかりに露わにし、シルバーチェーンのネックレスにシルバースカルのペンダント、クリスタルピアスにクリスタルリング、まるで真夜中のポルノ番組の司会者のようだ。
加えて化粧まで完璧で、パーマのかかったブロンドロングヘアを垂らして片目を隠し、青紫のアイラインをけばけばしく引いている。
「とりあえず、一服して落ち着け」シーザーはシガーをロ・メイヒの口に突っ込んだ。
ロ・メイヒはちらりとそれを見下ろして言った。「ねえ、こんな間接キスはちょっと……ボスも分かってるでしょ、僕はまだ単純にボスより若いし、全然ピュアなんだよ……」
シガーには真っ赤な痕が一周くっきりと残っていた。シーザーのバラ色の唇は滴るが如く豊潤、所々キラキラ光っているのは金箔なのだろう……口紅が分厚く塗られているのだ。
「僕、どれくらい寝てたの?」ロ・メイヒは聞いた。
「60時間ちょっとだ。ラッキーだったな、弾が動脈を少し掠めただけで。殺し屋が使った弾は7.62mm鉛芯弾、もし直撃していたら命中した瞬間変形して、茶碗ぐらいの穴が開いていたところだ。それでもお前は動脈が切れて出血多量、気を失って体温も下がってたから、俺とソ・シハンが毎日二回お前を風呂に入れてやってたんだぞ。何も食べれないから、わざわざブドウ糖を買って注射までしてやったんだ。起きたらバカになってるかもと心配もしたんだが、こんな元気になるとは思わなかったぞ」
「元気なものか! ボスが凄いことになってるからびっくりしてるだけだよ!」ロ・メイヒは強調した。
「本当は医者に連れて行ってやりたいんだが、今俺達が外に出たら犯罪者扱い、テレビを付ければ俺達の事が放送されてない方が珍しいくらいだ。容疑は核燃料の密輸にテロ未遂、幼女強姦と来た」
「僕たちいつの間にそんな大事やらかしたわけ?」ロ・メイヒは唖然とした。「っていうかさ、密輸とかテロとかはすごい思想入ってる感じなのに、最後の一つだけやたらしょぼすぎない? なんかロシアギャングとビソ・ラディンに一人だけ中年露出狂ヘンタイが混じってるみたいじゃん」
「もちろん、誰かのでっち上げだろう。俺達が凶悪犯罪で指名手配されれば、警察の手を借りて俺達の行動を制限できるというわけだ」シーザーは言った。「誰かさんが俺達と学院本部との連絡を絶ちたいんだろう」
「そんなの、オロチ八家のゾウガメ以外ありえないじゃん!」ロ・メイヒが言った。「救援を呼ばれるのを恐れてるから!」
「まあ、ネットにファイアウォールを掛けているのは輝夜姫で間違いない。俺達がネットを使ったり電話を掛けたりすれば即座に身元がバレる。輝夜姫の追跡監視能力にはEVAともそう変わらんというしな」
ロ・メイヒはしばらく考え込んだ。「……いいこと思いついた! 僕、まだ誰にもバレてないQQアカウントがあるんだ。それでスター・クラフトのグループに入って、同じプレイヤーのネッ友を通じてシュナイダー教授に連絡を取るっての、どう!?」
ロ・メイヒが言っているのは、あのデブ従弟をからかう為だけに作ったネカマアカウントのことだ。長らく放置していたあのアカウントが今頃役に立つと思うと、つい得意げになってしまう。
「ああ、『刻痕ユウヒ』のことか?」シーザーは肩を竦めた。「ノノでも調べの付くアカウントをオロチ八家が見つけられないと思うか? EVAや輝夜姫の計算能力の前じゃ、人間一人の生活なんて簡単にすっぱ抜ける。どんなに隠し事をしようと、膨大な計算の前にはプライバシーの欠片も残らん。アメリカ大統領だろうが、グーグル検索に出てこない一般人だろうがな」
ロ・メイヒは驚きながら、天井を仰ぎ見て、心の中で考えた。普通に考えてみれば、自分の二十年の人生の何と長いことか。色々な人と出会い、色々な煮え湯も泥水も啜って来た……だが、本当によく考えてみればシーザーの言う通り、人生での重要な登場人物はほんの一握りだし、心に残った出来事も多少でしかない……もとより、人間ひとりの人生ひとつなど、コンピューターで量ってしまえばせいぜい数キロバイト程度の情報にしかならないのだ。
「まあいい、しばらく浸かっていろ。酒を飲んで熱い風呂に入れば汗をかいて身体にもいい」シーザーは床に転がっていた斧を手に取り、薪を拾って割り始めた。「湯加減はどうだ?」
和風な木製浴槽の底は鉄製で、本物の火で直接湯を沸かすようになっている。唐僧が妖怪を鉄鍋で煮るように、薪をくべ続ければそれだけ熱くなる。
ロ・メイヒは無言でシーザーの背中を見た。紫色のセクシースーツを着たイケメン貴公子が斧を上下に振るい、胸筋のデコボコが現れたり消えたりする……。そこで彼はロ・メイタクが極淵で言っていたことを思い出した。ちょっと言ってくれればこの世界からシーザーはおさらばだ、シーザーさえいなければ世紀の婚礼も無いし、悲恋も脅威も何もなくなる、のだと。そうすればノノは未だシカゴへのナイトトリップの相手を見つけられない女の子になって、階下で車を走り回らせ、誰かシカゴに行く奴はいないか、誰か私と一緒にシカゴに行く奴はいないのか、と叫ぶだろうし、そして今度こそ自分が最初に飛び降りて、彼女の心を掴めばいい……ただ「この世界にシーザーなんていない」と言いさえすれば、ロ・メイタクの力でその通りになってしまうのだろう。
実のところ、ロ・メイヒ自身もそう望まないわけでもなかったのだが、その瞬間の彼はどうしてもその通りに言う事ができなかった。たとえロ・メイタクにこめかみに銃を突き付けられても。それはこのシーザーというイケメン気取りこそが、彼の人生の中でも一握りの重要な人だったからだ。自分を踏み台にして命令ばかりしてくる金持ちの御曹司、何度心の中で唾を吐いたことか。それでも、彼は自分の為にアスパシア・ホテルの部屋を取ってくれたり、大袈裟な会場を用意し、自分好みのスーツを一式用意してくれたりもする。あるいは「俺達金持ちハンサムからすれば金ですらない」とでもばかりにドヤ顔で食事代を全額払ってくれたりもするし、自分のプライドを守るためだけに、自分より先に知り合いが死ぬのが耐えられないというだけで、自分が死ぬかもしれないと分かっていながらも率先してツェッペリン装備で潜水艇から出て行ったりもする人なのだ。
ひとの人生に、重要な人はどれだけいるのだろうか。その中の一人をそんな簡単に消せるものなのだろうか。だから、何も分からない……だから、彼を庇って弾を受けた時も、何の考えも思いもなかった。
ロ・メイヒは深呼吸し、身体を丸め、湯の中に完全に沈んだ。
「ねえ! そういえばここってどこ!?!?」ロ・メイヒは突然立ち上がった。
まったく! こんな時にセンチになってどうするんだ! 警察に追われ、極道にも追われているというのに、悲哀に暮れてお風呂に入ってる場合じゃない!
「……高天原だ」シーザーは淡々と言った。
「タカアマ……!?!?」ロ・メイヒは茫然とした。あの古代都市は地殻の裂け目にすべり落ちていったはずだ。高温で溶けていないというなら、今はマントル層のマグマの中にでも浮かんでいるはずだ。
「そう、高天原だ。同じ名前の場所だがな。日本神話でいう高天原は天国と同じ場所らしいから、天国にいるとも言えるな」
「ボス、あまりにもフワッとしすぎてて何も分かんないよ」
ロ・メイヒは辺りを見回した。木製浴槽だけ見れば素朴な感じだったが、浴室自体は全然素朴どころか、むしろ真逆、控えめに言って豪華そのもの……ややチャラすぎる感じすらする。壁に貼られた木板には華美な模様が彫られ、普通の木材とも違うように見える。ロ・メイヒが入っていた木製浴槽はメノウのように真っ赤、叩けば爽やかな音が響き、どう考えても安物ではない。さらに四方の壁には精緻な浮世絵が描かれており、着物姿の男女が絡み合って接吻し合い、半裸の女性は真っ白な肌を露わにし、恐らくはジャパニーズ・ハーレムをテーマにした「ハルガ」とかいうやつだ。隅に置かれたアロマランプはサンダルウッドで作られた大きな観音菩薩像で、その手が捧げているオイルボウルはどうやら金で作られているらしい。
「ああ。説明するより、見た方が早いだろうな」シーザーはロ・メイヒにバスローブを投げた。
浴室は本格的和風浴室だったが、外はヨーロピアンスタイルの廊下だった。装飾は全然違うが贅沢なのは一緒だ。ゴールデンチーク材の床板が敷き詰められ、壁には井戸の傍で水を汲む裸の少年の油絵が飾られ、その上にはクリスタルのシャンデリアが点々と吊り下げられている。
「ボス、使えるクレジットカードあるの? 絶対ここ高いよね!?」ロ・メイヒは歩けば歩くほど不安になっていった。
「ああ、確かに高いな」
廊下の先にはエレベーターがあり、シーザーとロ・メイヒはエレベーターに足を踏み入れた。彫刻が施されたブロンズのドアがゆっくりと閉まり、エレベーターが少しずつ上昇していく。ロ・メイヒは、音楽や人声がだんだんと上の方から沸き出してくるのを聞いた。
「言っておく。しばらくの間、お前は何を見ても泣くな、喚くな、吠えるな。いいな?」シーザーは囁いた。「ここの決まりはキビしいんだ」
「ねえ、いつものボスみたいじゃないよ。ボスが決まりを気にするなんて。いつもなら『俺達ガットゥーゾ家の言う事こそが規則だ』とか言うでしょ? 校則だって――わはーっ!?!? なんだこのデカい尻!? ああぁ貴重品を投げないで!!」
開いたエレベーターの扉の外で、タイトスカートに包まれた大きな尻が熱情と激情と共に激しく揺れ、ロ・メイヒの視界を釘付けにした。
ダンスフロアで無数の男女が揺れ、地面がリズミカルに震動する。そこは壮大な仮面舞踏会だった。女たちは全員ミニスカートにハイヒール、顔には精緻な装飾のマスク、スカートにはゴージャスなスパンコールあるいはクジャクの羽根があしらわれている。彼女たちのダンスパートナーはフェミニンハンサムだったりマニッシュワイルドだったり、そのほとんどが俳優級に顔が良く、シーザーと同じような服装をしている……いわば、ドラァグクイーンのドラマティックなドラフトパーティ!
「泣くな、喚くな、吠えるな!」シーザーはロ・メイヒの口を塞いだ。「藤原先輩にゴアイサツだ」
大きな尻が振り返るが、累々とした横肉は未だにロ・メイヒの視界を占めていた。正面から見てもデカ尻じゃないか! ロ・メイヒは心の中で叫んだ。センパイセンパイコンニチワ、アナタはホントはお尻妖怪ですか?
大きな尻はロ・メイヒに見下すような表情を見せ、それからダンスフロアに続く道を譲った。身長2メートル、体重も120キロを超えるだろう巨漢で、サイズが30センチ以上はあるハイヒールを履き、1メートル半はある腰回りにタイトな超ミニスカートを穿き、手足を投げ出せば全身の横肉が水面のように波打つ。こんな奴がセンパイ? 「肉山大魔王」以外の何だって言うんだ。
「ドーモ、センパイ! 本日もオツカレサマドス!」ロ・メイヒは頷いてお辞儀をした。シーザーはこのデブ男を相当尊敬しているらしく、お辞儀をした後、ロ・メイヒを引きずっていった。
デブ男は再び激情的ダンスを始め、その贅肉を不尽の淫靡に捧げたが、彼の張り詰めた顔は怒りも威厳もなく、どこかの密教仏寺にある金剛明王像にも似ていた。
ダンスフロアの雰囲気は更に淫靡で、酔っていない者はいなかった。酔い潰れた女が酔い潰れた男に腕を回し、その首元にシャンパンを注ぐ。ダンサーリーダーが歓声の中でシャツを引き裂き、筋肉隆々の胸元を露わにする。ウェイターが銀粉のトレイを持って人々の間を歩き、女たちはその銀粉をベタベタと手に漬け、ダンサーの胸元や背中に手の痕を残す。ライトが消え、人々が乱舞、蛍光灯はダンサーを照らし、細い銀色の掌の模様が浮かび上がって刺青のようになる。
「Basara Kingだわ!」ダンスフロアの一角にいた小さな黒ドレスを着た若い女性が突然飛び出してきて、綿の上を歩くような覚束ない足取りで、シーザーの側に辿り着いてその頬にキスを迫った。
シーザーは彼女が渡したシャンパンを取り、それを飲み干した後、その酔っ払いを振り払った。
「ボス、ここの人みんなみんなボスのこと知ってるの? もしかして、ここって日本の高級クラブハウス?」ロ・メイヒはしかし、何かがおかしいことに気付いていた。
ダンスフロアの外には、輪状に並べられたソファが並べられたデッキがあり、フルメイクの女性たちが何人かのキラキラな男達と大声で話したりグラスを挙げたりして、満面の欲情的な笑顔を浮かべている。しかしその男たちは礼儀正しく接し、時折女性たちの耳元で何か囁いたりすれば、女性たちは火照った笑みを浮かべて男の胸を小突いたりする。ある女性は笑いながら男を叩くふりをしたりして、他の女性たちも大体同様だった。テーブルの上のシャンパンボトルはすぐに底を打ち、ウェイターが席の間を絶え間なく行き来している。時々女性がウェイターにクレジットカードを投げ、ワインの注文をしたりしているのも見える。
ロ・メイヒは突然、漠然と感じていたおかしなところを理解した。ここでお金を払っているのは女性だけだ。ハンサム男たちは財布を見せすらもしない。
「しばらく見ていろ。大体わかるだろう」シーザーはロ・メイヒを引きずり、カーテンの後ろの影に隠した。
サンバダンスが終わり、フルートなのかオカリナなのか分からない笛が奏でる孤高古風な曲に切り替わった。この音源を聞いていると、まるで大都会のナイトクラブが突然古代の日本に巻き戻り、秋風の吹く野橋の辺に立っているような感覚になる。大幕が開き、ゆっくりと上がっていくステージの上に、一人の孤独な姿が見えた。灯りは消え、ただ孤独な男を真上から照らすランプだけが点っている。白い和服に青い袴、長い髪は顔の半分を隠している。送風機が桜の花弁を吹き散らし、大きな袖が風になびき、輪郭のハッキリとした前腕を露出させた。
男は白い服を脱いで袖を腰に巻き、裸の胸を息で上下させた。手を伸ばして抜刀するその動作には詩的な美があった。
大きな拍手が沸き起こった。男は落ち桜の中で刀を舞わせ、走り込んだり、前後ステップしたり。ファンタジーではない本物の格闘刀術だった。実戦的な格闘刀術はあまり見栄えしないと言われるが、時折興奮して叫ぶ女性もいたりして、男が刀を振るう時の筋肉のラインはそれなりに悦ばしいものらしい。ステージ上の男は単純な筋肉の量で言えばシーザー程ではないが、細くも力強い身体は竹枝のようなしなやかさを思わせ、美少年武士の孤寂の美を表すにはピッタリという感じだ。
この男のトップレス姿に関してはロ・メイヒも何度も見たことがあったが、今日ほどセクシーだと思えたことはなかった。
「ボスどうしよう。僕、元の世界に戻れるかな?」ロ・メイヒは振り返り、心の底からシーザーに尋ねた。
「現実を受け入れろ。あれが今のソ・シハンだ」シーザーは彼の肩を軽く叩いた。
黒服黒面のウェイターが長さ二メートルのまな板をステージに置き、まな板の上を角氷で覆い、その上に一匹のマグロを置いた。ソ・シハンは長刀を使って魚肉を牛捌きが如く切り崩し、暗紅色の背肉とピンク色の腹肉をそれぞれ美しい角柱の形に切り出し、各部位を分類ごとに分け、紙で包み、木製の格子の中に詰め込んでいく。最も美しい大トロ部分はピンク色の大理石のようで、ウェイターたちは木の板に乗せた貴重な魚肉を持ってステージを一周するように並んだ。
女性たちの拍手喝采が沸き起こった。このマグロ自体は最高級というわけではないかもしれないが、ソ・シハンの絶妙な剣術によって切り分けられることで、いわば芸術へと昇華したのだ……しかも、ソ・シハンは刀を操るときに上半身裸になっているのだ。女性が脱げばただのポルノだが、男性が脱げばある種の芸術である。こんな芸術的かつセクシーな魚肉を嫌いなどとはいえないだろう。シガースモーカーが、キューバの少女の太腿の上で巻かれた最高級シガーロールを嫌いなどと言わないのと同じだ。
ソ・シハンの演目が終わる前に、ゲストたちは既に彼の手で切られた魚を注文していた。最も珍しく最も脂肪の多い大トロ部分はオークションの形で販売され、入札は絶えず更新され、最終的にこの長方形の魚肉は70万円の高値がついて落札された。「競り」に買った女性は立ち上がり、ゲスト達の拍手を誇らしげに受け取った。ソ・シハンはゲストの要求に応じて魚の各部分を適切な厚さにスライスし、ウェイターたちがそれらを皿の上に新鮮なワサビと一緒に盛り付け、松や竹、梅といった名札を付けた。松皿は三万円、竹皿は六万円、最も高価な梅皿は九万円という高値が付いている。
生鮮魚肉は流水のようにステージを降り、各テーブルへと運ばれていった。食べた女性らは陶酔した表情を露わにし、度々頷いては度々褒め称えた。「生は夏の花のごとし」を提供したオロチ八家のシェフも、これほど満場一致で賛美されたことはなかっただろう。
すっかり酔っ払った一人の女性がサシミを食べて興奮し、ステージに駆け付けてソ・シハンにシャンパンを振りかけると、それを見ていた全ての女性の熱情に火がついた。胸筋の縫隙に流れる酒を見て、女性たちは彼女の勇敢な行動に乾杯した。
「右京! 右京!」全場が歓声を上げた。
「ウキョーって……なに叫んでるの?」ロ・メイヒが細々と訊いた。
「ソ・シハンの芸名だ」シーザーはすっかり落ち着いていた。
「じゃあバサラ・キングって?」
「中国語で言えば『娑婆羅の王』、俺の芸名だ」
「じゃあまた聞くけど、ここって……?」
「『クラブ高天原』、新宿で最も有名なホストクラブだ。お前が今見たのは新人ホスト、ソ・シハンのデビュー公演。演目名は『サシミ・ブシドー』」
「ホスト……って、僕が理解している通りのホスト?」ロ・メイヒはなんとか自分を落ち着けようとした。
「そうだ。金を払うのは女性、俺達は彼女と一緒に酒を飲む」シーザーはロ・メイヒを支えた。「おい、大丈夫か?」
「あしあしあし……あしがちょっとしびれて……」ロ・メイヒはなんとかまっすぐ立とうとした。「ボス、分かってくれると思うけど……僕はまだ若くてピュアで……いきなりホストとかなんとかって、いきなり大人になったみたいで、なんかすごい緊張しちゃうっていうか……」
「だが他に行くところもない。セーフポートは死んでるし、連絡も付かん。テレビでは指名手配、金もパスポートもクレジットカードも無ければ言語も通じない。しかも俺とソ・シハンは日本では密入国者扱いだ。だから、日本に来たが仕事が無いからホストの仕事をしたい、と嘘をついて、ここで一時的に落ち着かせてもらうことにしたんだ」シーザーは手を広げた。「ホストクラブは俺達みたいな不法就労者を雇っても気にしないだろうし、日本語が話せなくてもなんとかなる。とにかく、顔だけあれば生きていけるからな。その点に関しては俺達ガットゥーゾ家の男は自信がある」
「家族の名前でうぬぼれてる場合じゃないよ、ボス!」ロ・メイヒはキレた。「ホスト! 僕たちがホストだって!? 僕の人生最初の仕事が日本でホストをやるのって、マジ!?」
「俺やソ・シハンみたいな家庭環境の奴がバイトしたことあると思うか? これは俺達全員の人生最初の仕事だ。安心しろお前だけじゃない」シーザーは完全に無関心なようだった。「お前ら中国人もよく言うだろ。『誰でも社会で実際勉強だ』とかな」
「こんなのを社会勉強って言うの!? 一歩踏み出した瞬間泥沼にドボンしてるようなもんじゃんか!?」
「そう言うな、どれだけドボンしようが這い上がればいいんだ」
「なんでだよ! ほんとボスの中国語って調子ばっかりいいよね! もしボスが『ホストのゲン』とか書いたって絶対に僕は流されないからな!」ロ・メイヒは懇願するような顔になった。「ボスも知ってるだろうけどね、僕たち中国人はすごい保守的なんだよ、全然違うんだからな、イタリア人はロ……ロ……ロマン! そう! ロマン! なんだろうけど! 中国だとホストってのはぶた……ぶち……豚カゴにぶち込まれるようなもんなんだよ! 豚カゴにぶち込まれたら、水に沈められちゃうんだ! 死んでも家のお墓に入れてもらえなくて、野良幽霊になっちゃうんだよ!!」シーザーは中国のことなど殆ど知らないだろうから、無茶苦茶な内容でも問題ないだろう、とロ・メイヒは心の中で思った。
「ああそうか、俺もノノと結婚したら半分中国人になるよな? お前の言う通りなら、俺も水に沈められるってことか?」
「そ……そんな……」ロ・メイヒは目をぱちくりさせて、どう返そうかすっかり困ってしまった。
「だからお前も理解してくれ」シーザーはロ・メイヒの肩に手を置いた。「お前もソ・シハンも中国人だし、俺も半分中国人だ。お前たち中国人的な規範に則れば、こんなホストは恥ずべき仕事だし、バレれば豚カゴにぶち込まれて水に沈められる、だろ? だから俺達はこの経験を秘密にしておかなきゃならん。俺達全員で口を揃えなきゃならん。俺達は潔白だ。そうだな?」
「ハイハイ! ボスはもちろんホストじゃありません! ハイ! ブラザー、裏切りません! 僕の叔父さん一家に誓って!」ロ・メイヒは速やかに弁明した。
「ところで、学生自治会唯一の絶対規則を覚えているか?」シーザーは微笑んだ。
「え、真夜中に山道を全裸で走っちゃいけないってやつ? ええやりましたとも! まったくだよ! 同級生に道端から写真まで撮られたんだ!」
「ああ。実は俺もやったし、写真も撮られた。でも俺の裸の写真をナイトガーディアン掲示板で拡散させた人は誰もいない。何故だと思う?」シーザーは循循と話を進めた。「全員やったことがあるからだ。全員やったなら、誰もやってないのと同じだ。もし誰かが他人の裸の写真を拡散しようものなら、他の全会員が総力を挙げてぶち殺すからな」
ロ・メイヒは突然全てを悟った。
「だから、堕落は全員で一緒にするのが一番安全なのさ」シーザーはロ・メイヒの肩を叩いた。満面の笑みで、深く重く。
ロ・メイヒは閉口した。「今の僕の心を表現できるとすれば、アンディ・ラウの『冰雨』くらいなもんだな……『心もズタズタに刺されて~』って……ズタズタにしてる張本人はボスなんだけど……」
ダンスフロアのライトが突然暗くなり、既にダンスフロアの上にせり上がっているステージの上に更に高いステージが現れ、上から落ちる光の束がステージの上の逞しい影を包み込んだ。彼は両手でやたら長いマイクを持っていて、まるで方天画戟を振り回す呂布のようにも見える。
「天使たちよ! 今夜は最高かい!?」男はロックスターかのようなポーズを取った。
ゲスト達は手を振って口笛を吹いた。
「俺達の花道に、エデンの園の温かみを感じられたかい!?」
ホスト達も立ち上がり、ステージ上に居る男に向かって拍手を送った。どうやらこの男の出現が今夜の最高潮を予感させているらしい。
「さあ、今夜、俺達の花道に新たに一輪の花が添えられた! さあさあ、その名は!?」
「右京! 右京!! 右京!!!」呼び声が波の如く押し寄せる。
「そう! 右京!! Basara Kingの兄弟、哀絶なる美少年、橘右京が今夜君達の所にやってきた! 人斬りの刀を振るその両手が君を抱きしめる! 君はその抱擁を受け入れるかい!? それともこの迷える若者に施しをするかい!?」男は高みから人々を見回し、大声で叫んだ。「今夜! 今こそ! 君達の愛と暖かさを! 彼の心に置いていけ!!」
舞台裏のスネアドラムが叩かれ、ウェイターが金色の箱を持ち上げ、ソ・シハンが深くお辞儀をした後、ステージの隅に立った。別のウェイターたちが桜色の花チケットの乗ったトレイを持ってテーブルの間を歩いていくと、ゲスト達は千円札を取り出してトレイに落とし、一枚ずつ花チケットを取っていく。ゆっくりだったドラムの音がだんだん激しくなっていくと、最初は一枚か二枚ずつしかチケットを買わなかったゲストも、一度に八枚や十枚と買い出すようになり、あるゲストが一万円札を一掴みトレイの上に置くと、ウェイターがすぐに数百枚の桜花チケットを数えて彼女の所にやってきた。
「さあさあ! もっと愛して! みんなの愛を、右京を抱きしめる狂乱の渦へと変えていこう!!」ステージ上の男は片膝をつき、マイクを空中に向けた。
「このヤバイ人誰!? あの女の人たち何を買ってるの!?」ロ・メイヒは小声で尋ねた。
「ヤバイ奴はここの店長、女性たちが買ってるのはソ・シハン投票用の花チケットだ。一票千円、チケットが多ければ多いほど奴の人気が高いということになる」シーザーは言った。
「チケットは何に使うの? 添い寝とかできるの?」
「それ自体で役には立たん。彼女たちがチケットに金を払うのは、ソ・シハンへの愛を示して、奴の目に留まりたいと思うからだ」
ドラムが豪雨のように急き立てると、紙幣が吹雪のように舞い落ち、金の箱を持ったウェイターが各テーブルでお辞儀をすると、ゲスト達はそれぞれ握った花チケットを箱に入れた。誰かが投票する度、ソ・シハンもステージ上で遠くから頭を下げた。最終的にチケットは、箱に収まりきらない程に山盛りとなった。
「右京、見てぇ~!! 愛してるわ!!」一人の女性が飛び上がって叫んだ。
ドラムが止まり、ナイトクラブには天地開闢の瞬間の如き寂静が広がった。ウェイターが金の箱をワイヤーロープに吊るして宙に上げ、もう一方のワイヤーロープに桜色の爆竹が下げられて店長の前まで行くと、店長はスーツのポケットから銀色の鋏を取り出し、皆に見せた。
「今夜までに、右京は既に320枚の花チケットを受け取っている。さて今夜、彼と離れたくない人は一体何人いるのかな?」店長は金の箱から花チケットを一掴みし、ソ・シハンの頭上に降りかけた。「20……40……60……80……」
彼が数え上げる度、ウェイターは金色の大筆で桜色の紙の上に正の字を書いた。箱が底を打つ頃には百近い正の字が書かれ、ソ・シハンを支持する花チケットは五百枚近くあったことになる。一枚当たり千円だから、ゲスト達は総額でソ・シハンに五十万円を投げたことになる。美味しいマグロの大トロや超高級シャンパンを買える金の無いゲストは、こうしてホストに数字で愛を表現する以外に金を使うことしかできないのだ。その場の全員が、店長が最終的な数字を言い出すのを待っていた。このナイトクラブの史上記録が更新されるかもしれないからだ。
「580枚! 我らが右京はたった三日で、合計900枚の花チケットを手に入れた! これは高天原史上第二位の快挙、昨日のBasara Kingの925枚に次ぐ数字だぞ!!」店長は腕を振り上げた。「愛を! 彼に! 愛を! 彼と一緒に飛ぼう! 彼を愛する天使たちに感謝を! 天使たちは翼を与え、共に征かん、愛と幸福の楽園へ!!」
彼は桜色の爆竹群を斬り落とした。「900の愛、我らが右京に!!」
ワイヤーロープがソ・シハンの前まで爆竹を下ろし、ウェイターが金色のライターをステージに運んで行った。ソ・シハンが信管に火をつけると、耳をつんざく大砲のような音が響き、桜色の破片が宙に舞い散った。特製爆竹は桜の花弁と混ぜ合わされていて、火薬自体も特殊なものらしく、爆発後には普通の爆竹のような硝煙の匂いではなく、優雅な花の香りが漂う。
「さあ、テーブルごとにシャンパンが無料サービスだぞ!」店長は背中にワイヤーロープを引っ掛け、背中に黒い羽根で出来た翼を広げ、ダンスフロアの上を飛んだ。「レディーズ、どうぞお楽しみ! 今夜は帰れないぞ!」
「なんかもうマジでヤバイ!!」ロ・メイヒは語彙を無くしながら称賛した。
キング・シャンパンの箱が運ばれてきて、礼砲のようなコルクの抜ける音が聞こえると、コルクは宙を舞い、パーティの熱気は最高潮に達し、何百ものグラスが一斉に掲げられ、ワインはライトに照らされて霞がかった金色に輝いていた。
ダンスミュージックが再び始まり、DJが腰をセクシーに揺らしながらステージ上に現れ、ホスト達とゲスト達がダンスフロアに飛び乗った。
「右京! 右京!! 右京!!!」四方八方からその名が聞こえる。
「Basara King! Basara King!! Basara King!!!」隠れていたシーザーも遂に見つかった。女性たちはグラスやら酒瓶を持って来ている。
シーザーはロ・メイヒの前に立ち、燦爛な微笑みと愛慕的な目で向き合い、一人の女性からシャンパンを受け取った。既にBasara Kingに懇意になっている女性もいるらしく、愛情たっぷりに抱き締めたりし、更に熱狂的な若い女性はスカートの裾を捲って真っ白な太腿を露わにした。ウェイターがシーザーにシルバーの蛍光ペンを渡すと、シーザーはその太腿に一つずつサインしていった。彼の豊富な経験を以ってすればこの太腿にサインしていくのも朝飯前らしく、ペン先は龍の如くうねり、すばやく太腿の上にきらめく「Basara King」の文字を刻み込んでいく。サインを貰った女性たちは興奮して叫び、シーザーの頬にキスをしようと集まった。シーザーは覇気たっぷりの微笑みを見せると、彼女達と肩を寄せて写真を撮った。このナイトクラブでは右京よりも人気があるらしい。
ロ・メイヒはシーザーの近くに立っていたが、女性たちに囲まれ、前後左右のふっくらした身体や痩せた身体に揉みくちゃにされ、目も虚ろに、頭も真っ白になってしまった。
終わった……完全に終わった……無数のカメラと携帯電話が目の前でフラッシュし、この証拠は永遠に消える事は無いだろう。そして彼は全ての名誉、道徳、潔白な経歴、そしてステキな英雄になる夢にも別れを告げた。文学史上でもホストが世界を救うだなんて設定なんてない……いや、今は何とも言えない。もしかしたら将来、恐らく日本かどこかの特撮だかアニメだかで「スーパー・ホストマン」みたいな奇天烈作品が登場するかもしれない。
結局のところ、これが彼の人生のターニングポイントになってしまった。若々しいひな鳥は、道徳と倫理の天塹を飛び越えて、一人の新人ホストに進級してしまった。
「僕たち不純だよ……そんで……彼女達も不純だよ!」ロ・メイヒはため息をつき、水面をバシャバシャ叩いた。「僕たちの貞操……僕たちどん底だあぁぁ……」
「貞操なんて関係ないだろう。まあどん底かもしれないが、これ以上落ちることも無くなったとはと言えるだろう?」シーザーは三つの木製浴槽のそれぞれに新しい薪をくべ、自分の浴槽に飛び込むと、気持ちよさそうにシガーを吸った。
仕事が追わればリラックスして日本風呂だ。三つの木製浴槽が並び、三人の裸の男がそれぞれ熱されている。シーザーはシガーを吸い、ソ・シハンは新聞を読み、ロ・メイヒは純潔が奪われたと思って感慨にふけっている。
「っていうか先輩、なんでそんな落ち着いてるのさ!? 先輩なんて潔癖そのものじゃなかったの!? それが今はホストなんかに落ちぶれちゃって! 僕と一緒に『これ風塵に愛さず、前縁の誤りを被るに似る』みたいな表情でもしてよ!? そんな呑気に新聞なんか読んで、こんなところ数日も居たら精も生もボロボロに枯れちゃうよ! 先輩を慕ってる学院の女の子たちになんて説明するのさ!」ロ・メイヒは激おこプンプンして言った。「っていうか先輩、日本語の新聞なんか読めるの?」
「最近の外の情報が知りたかったんだ。漢字だけ読んでも何となく分かるのが日本語のいいところだな。……どうやら最近、極道の中で幾つか暴力事件が起こってるらしい。極道が二派に分かれて大規模な戦闘を繰り広げている。オロチ八家が関係してるのは間違いないはずだ」ソ・シハンは淡々と言った。「それに言っておくが、俺達はまだホストじゃない。ただのホスト見習いだ。俺達が上手くやれなければホストクラブからは追い出されるし、そうすれば身を隠す場所も無くなる。金もないしな」
「ホストに見習いとかあるの? 自分の身体を売る心の準備とか?」ロ・メイヒは追い出されてドブネズミのような生活をしなければならなくなると考えると、突然心配になってくるのだった。
「この『高天原』は新宿区どころか、東京都でもトップクラスのホストクラブだ。顔だけでやっていける場所じゃない。ここに来る客はみんな金の事なんか気にせず、ただ楽しみたいだけの女性ばかりで……」
「わかったよ! 暇を持て余したセレブ美女たちなんでしょ!」ロ・メイヒは言った。
「セレブママやセレブおばさんもいるぞ」シーザーは肩を竦めた。「彼女たちは一晩に数百万円は使う。一人のホストの木を引くためだけに街の花屋の全てのバラを買い占めたりもできる。勿論、要求もそれだけシビアになる」
「何がシビアだよ! 120キロ越えのスーパーサイズデブもいたじゃん!」
「彼の名前は藤原勘助。ホストになる前はオオゼキ級のスモートリ・スターで、あと一勝で『ヨコヅナ』にもなれたそうだ。並み居る元ガールフレンドは日本のドラマスターばかり、日本人にとってはそれなりにアツい美男子だったらしい。だが彼の婚約を聞いた女性ファンが悲嘆に暮れて飛び降り自殺したっていう事件があって、小さな愛を捨てて大きな愛を届けるべきだと悟った彼は、スモートリとしての将来を捨て、ホストクラブとして生きるようになったらしい」ソ・シハンがタイムリーな知識を提供した。
「え……あんな女装クソデブがアツいって、ホストの世界マジ……?」ロ・メイヒは目を大きく見開いた。
「要するに、高天原でホストをやるってだけで大した役者なわけだ。それぞれに何千人ものファンが付いて、何百人ものゲストがいて、少し一緒に居るだけでも金がポンポン入ってくるような奴ばかりだ。だから高天原ホストクラブには厳格な選抜システムがある。全てのホストは見習い期間の内にトップパフォーマーとして頭角を顕して、一定以上の花チケットをゲスト達から貰い、更に店長との面接にも合格して、内面から完璧な男であることを証明しなきゃならんのだ」シーザーは言った。「俺とソ・シハンが花チケットを貯めるのは早かったな。俺は925枚、ソ・シハンは900枚だ」
「え、どれくらい集めればよかったの?」
「二週間以内に800枚。だから俺とソ・シハンはもうすぐ面接だ。面接に合格すれば、正式にホストになるわけだ」シーザーは青い煙をひと口吐いた。「まあ、この人気を見れば二人とも大丈夫だろうな」
「へぇ~すごいね本当にカンタンだったんだね! ちょースッゴイもう花だか鼻だかタッカダカじゃないの?」ロ・メイヒは悪意を込めて言った。「ガットゥーゾ家の人が誰かを悦ばせる為に働くなんてスンゴイビックリだよねぇ!」
「女性は例外だ。女性を悦ばせることに恥などない。美しかろうが醜かろうが、彼女達は天使として扱われねばならない。上流社会に入る前に学ぶべき礼節だ」シーザーは手を広げた。
「そうだろうけどさあ、ボスの上流社会だと押し倒してくるセレブとかいないでしょ? ここだと分かんないじゃん! 僕たちは身体を売ってるわけなんだから、酔った女の子たちが芸術だの身体だの売ってくれって言ってきたらどうするのさ!?」ロ・メイヒは変に心中穏やかでなかった。「僕の二十年間の貞操が!!」
「俺を押し倒そうとする上流社会セレブが居ないなんて誰が言ったんだ?」シーザーは誇らしげに眉を上げた。
「やめて! そうじゃないって! だからなんでホストクラブに隠れなきゃいけないの!? なんでホストクラブに隠れてるの!? どういう変り身だよ!? もし僕たちのこの経験がクソラノベだったら、作者のセンスは底辺以下だよ!!」
「そうか、あの晩撃たれた後何があったか、お前に説明してなかったな。ソ・シハンと俺はあの後バイクを奪って、お前の銃創を直してくれる医者を見つけに走った。だが道行く先の外科医院には大小問わずパトカーが止まっていたんだ。大概オロチ八家が警察を動かして、千鶴町から東京までの道に配備したんだろう。俺達はただ進むしかなかった。途中の交差点に極道の奴が居るのを見つけて、裏通りや路地に逸れたりもしながらな。躱して隠れて躱して隠れて、ようやく新宿区の看板が見えて、東京に戻れたことが分かった。どうしようもなかった俺達は一台の広告トラックに目を付けた。『男の花道、女の楽園』って書かれたいわゆるクソ広告の類だったが、チラシ配りの人が親切でな、大丈夫かって手を貸してくれたんだ。俺達は仕方なく、密入国した外国人だってこと、友人が極道に襲われて怪我した事を話して、病院を探す手伝いを頼んだ。そいつも親切でな、俺達は店で休んで医者は電話で呼べばいいと言ってくれたんだ。それで俺達は広告トラックに乗って、そいつの導きで高天原に来たというわけだ」
その夜の事を思い出すと、まるでおとぎ話のようにも感じてしまう。マンボ・ネットカフェに辿り着いた時ですら既にシーザーとソ・シハンは疲れ果てていたし、戦ったり走り回ったりで更に体力を消耗してしまった。盗んだバイクで坂を駆けあがり、新宿の明るい摩天楼群が目の前に現れた時、彼らは唖然としてしまった。極道から逃げるどころか、オロチ八家の根城に戻ってきてしまったことに気が付いたからだ。江戸時代以降、繁栄を極めた新宿はオロチ八家の「首都」であり、警視庁すら極道組合の力には及ばない。彼らはいったいどこに行けばいいのか分からなくなってしまった。敵の巣穴に正面突撃すべきか、それとも厳重封鎖された千鶴町に戻るべきか? しかし丁度その時、道路わきにけばけばしいライト満載の広告トラックが止まっていて、車の屋根の上にあるスピーカーから悠揚な音楽が響き、どことなく気取った男の声が理解不能な宣伝をまくしたて、ゴージャスな服装の若い男が車の前や後ろで割引券やら一口スイーツやらを配っているのが見えた。それはいわば、餓えて渇いて脚も腕も精根尽き果てた深夜の山中遭難者が、突然高所の茂みの中に光を見つけ、山の中腹に小さな焼肉屋台を見つけたようなものだ。その時に限って言えば、高天原の広告トラックはこの上なく美しいものに思えた。
「それがホストクラブだと知ったのはだいぶ後だった。ここの奴らは約束通り、すぐに医者を呼んで包帯を巻いてくれた。それから店長が俺達に話しにきて、俺やソ・シハンの才能を見抜いて見習いにしてくれたのさ。証明書が無くても問題ないし、高天原はただの新宿の大型ナイトクラブで、コンプライアンス遵守重点で警察が来る場所でも無いらしい。要するに、俺やソ・シハンが見習いホストになるのを受け入れたからこそ、こうやって庇護を受けられてるってわけだ」シーザーは続けて言った。
「そりゃいいさ! ボスや先輩は裸になってもキレイなんだから。でも僕は関係ないぞ! 僕はただの怪我人だ! 泥沼に引きずり込まれるなんてごめんだぞ!」ロ・メイヒは顔をゆがめた。
「いや、そういうわけにはいかないな。店長はお前の顔を見てすぐに何か感じるものがあったらしい。その時お前を評価して言ったのは……ソ・シハン、何だったけな?」
「……楚々可憐なる稀世の宝物、だったか」ソ・シハンは一語一句清々楚々に言った。
「ウッ――はあ、胃の中がすっからかんで吐けなくて助かったけど、吐いてやれなくて残念だよ!」ロ・メイヒは顔を覆った。「ねえ、この店がオロチ八家に通じてて、罠を仕掛けてるとか、ないよね?」
「確かに最初はそれも疑った。だがどんなにオロチ八家の反応が鈍かろうが、数日たっても何も起こらないというのはそういうことだろう。俺達がここの奴らにあったのはただの偶然で、オロチ八家もまさか同じ道を通って新宿に戻るなんて思わなかったんだろうな。だからあの広告トラックも検問とかされなかったわけだ」シーザーは言った。「とにかく、このホストクラブは今考えられる範囲では一番安全な隠れ場所だ。食費も宿代も無料だし、給料は週払い、ゲストが酒を一瓶頼むごとに一割のチップも付く。俺はこの三日間でもう十数万円は稼いだ」
「ガットゥーゾ家の若旦那が、日本円の十数万程度でそんな鼻高くしちゃっていいの? この程度の小銭なんか道に落ちてても拾わないでしょ?」
「そうではないさ。確かに家の金ならこの程度拾う気にもならんが、これは俺が自分で稼いだ金だからな」
「っていうか、ここってどういうとこなの? 顔にお金投げられて一緒に寝てって言われたらどうすればいいの? 警察呼ぶの?」
「お前はまずは日本のルールを知った方がいい。日本では、ホストクラブ自体は単なる交際場に過ぎない。娯楽と酒を提供するだけの、合法な飲食店だ。もっと安めの小さなホストクラブだと違法な前後行為もあるかもしれないが、高天原は東京のホストクラブでも『最上級』に位置する。つまり、ここのホスト達は遊女の最上級たる『太夫』に相当するわけで、コンパニオンはやっても身体を売るなんてことはない」シーザーは自信ありげに言った。「『ジャパニーズ・エロティシズム・ヒストリア』っていう本に書いてあったんだが、店の中での太夫の地位っていうのは相当高く、金に糸目のつけない貴族だろうがお目にかかるのは簡単ではなかったそうだ。まず店で膨大な金を使って、ハンサム金持ち風度翩々たる様を店長に認めてもらって、そこで初めて太夫に遇う為の『招待状』が届くわけだ。太夫が会いに行く時には少年少女が灯りを持って先導し、背後には棍棒を持ったボディガードが控える。太夫は全重二十キロの服を着て、半メートルの高さの下駄を履いて、奇怪な外八文字歩きで、街じゅうの道を巡って客に会いに来る。そして街じゅうの道行く男たちがその客を男の中の男だと認めて、羨ましがったり嫉妬したりする」
(くそが! 要するに、お前の彼女が映画に行くためにフェラーリで迎えに来るようなもんなんだろ!)ロ・メイヒの心はわずかに震えた。そうだ、あの紅いフェラーリ……そりゃ、誰だってシーザーには羨ましがったり嫉妬したりするだろう。
「それも精々挨拶程度のものだ。もし太夫が一目見て気分を悪くして、踵を反してしまえば、全ての金は無駄になる。太夫が座って話をする気になっても、手も足も届かない遠くから会話することになるかもしれない。だから風度翩々多才多芸たる一面を見せ続けて太夫を喜ばせなきゃならないし、太夫が帰った後は、埃まみれの自分の家に帰るしかない。会い続けたいと思うならまた金を使って風度翩々を見せつけなきゃいけない。つまり、太夫を抱きたいなら交際しなきゃいけないのさ。その代わり一度太夫を抱いたら他の太夫を抱くことは出来ないし、太夫もその客以外の客を取ることはなくなる」シーザーは木製浴槽から片脚を出し、その上にシェービングクリームを塗った。
「うわっ! セクシー!! セクシーすぎっ!!!」ロ・メイヒは顔を背けた。「直視できないよ!」
「明日は俺の出番、演じるのはアポロン。革のショートパンツに金色マントで、全身にオリーブ油を塗るんだ。スネ毛が生えてたら金髪オランウータンみたいになっちまうからな」シーザーはカミソリを取り出した。「まあつまり、今の俺達のホストクラブでの立場は遊女館での太夫みたいなもんで、地位があるわけだ。ゲスト達も俺達に親切だし、最悪でも精々飲み潰れて胸の中で泣かれるくらいさ」
ロ・メイヒは考えこんだが、それでもまだ少し心配が残っていた。「でもさ、もし僕たちが日本でホストクラブやってるなんて学院に知られたら……罰金とかとられない?」
「フッ、EVAの目も届かないこの日本で、学院がどうやってそんなことを知るんだ?」シーザーは微笑んだ。「それに、だ。このチームのリーダーが誰だか忘れたか?」
「そりゃ、ボスでしょ」
「恐らく俺達が学院に戻ったら、日本で何をしていたか説明するレポートを書かなきゃいけなくなるだろう。だがその時俺達はこう書く。オロチ八家の捜索から逃れるために、ある種の心理療養機関で働いていた、とな。助けを求める女性に手を差し伸べたり、心理的な問題を抱えた女性に必要であれば乾杯を挙げたりして、彼女達が人生に希望を取り戻すケアをしていたということだ。当然これは校則にも違反しない。『ホスト』という言い方さえ避ければ、俺達はいわば特殊な女性向けサービスの心理カウンセラーといえるだろうさ」シーザーは指を鳴らした。「合理的だろ? 口裏さえ合わせれば全員合格だ」
「なんかもう完全に役にハマってるじゃん、ばさらきんぐ!」ロ・メイヒは再び顔を覆った。「僕が寝てる間に内なる欲望が目覚めて、もう人生の方向性決めちゃった感じなの!?」
「そうだな。とりあえず他の誰かが居る時はお前も俺をBasara Kingと呼べ。シーザーとかソ・シハンとかロ・メイヒなんて男はここにはいない。ここにいるのはBasara Kingとタチバナウキョウ、チェリーチャンだ」
「チェリーチャンって何……!?」
「寝てる間にお前に付けられた芸名だ。日本語ではSakura、中国語で言えばチェリーチャン」
ソ・シハンが新聞を投げて身を起こし、浴槽の中から黒鞘の長刀を引き上げた。
「刀を洗濯でもしてたのか? まるで戦国時代の浪人武士だな」シーザーはライバルをからかう機会を逃した。
「しかし、ここでホストをやるのが唯一生き延びる道というわけでもないだろう、シーザー」ソ・シハンは淡々と言った。「お前にはまだ言ってない理由があるはずだ」
「フン、どういう意味だ?」シーザーは眉をひそめた。
「ロ・メイヒはともかく、お前と俺は野外サバイバル訓練を受けたはずだ。それに俺達には武器があるから、お前と俺の能力だけでも神戸山中で三ヶ月は生きられる。お前は狩りも得意だろう?」ソ・シハンは壁に固定されたシャワーヘッドの下に頭を突き出し、焼き入れられたばかりの刀を冷却するかのように、湯気の火照った肉体を水で冷やした。「お前がこの高天原を選んだのは、源氏重工から地下鉄二駅程度しか離れていないという絶妙な距離にあったからだ。お前が望んだのは隠れ家ではない、反撃の為の拠点だ。音もなく消えるなんて不本意なんだろう?」
シーザーはしばらく沈黙すると、にぃっと口角を挙げて笑い、身体の力を抜いて浴槽の壁にもたれかかった。「ああ! よく分かってるじゃないか。他人は自分よりも自分の事をよく了解しているとは、哲学者の言葉だったか」
「学院本部の人間が東京に来れば、現状は全部引き継がれて俺達は学院に送り返され、特にお前はローマに引き戻されて、家の人々に全身の傷一つ一つまで観察される。お前はそれが嫌なんだろう?」
「オロチ八家は俺の顔に泥を塗ったんだ」シーザーは無表情に言った。「奴らに代償を払わせなければ気が済まん」
ロ・メイヒは突然理解した。あの女の子、麻生真の死は普通の人間からすれば単なる悲劇なのだろうが、シーザーのプライドからすれば恥辱なのだ。恥辱は贖われなければならない。アカゾナエを指揮していたのは当然オロチ八家だろう。彼らはシーザーの逆鱗に触れてしまったという事だ。
「ねえボス、その事はもう……」ロ・メイヒはため息をついた。「真ちゃんを守るためにボスは頑張った、最善を尽くしたよ。ただ、予想外の事が起こっただけで……」
「予想外? ガットゥーゾ・ファミリーの辞書に予想外などという言葉は無い。予想外とは、ただ臆病者が言い訳する為に使う言葉だ」シーザーは浴槽の中で立ち上がり、密封袋の中に入ったデザートイーグルを引き上げた。
ロ・メイヒは戦慄した。シーザーもソ・シハンも、源氏重工にほど近いこのナイトクラブが安全な隠れ家などとは全然思っていなかった。だから風呂に入っていても武器を手元に置き、神経質になっていたのだ。貴公子シーザーにとっても冷酷無比ソ・シハンにとっても、ホストをすることは楽しいことでは全然ないし、むしろ人生の恥ずべき過ちの一つにすらなるかもしれない。だが彼らにはそうするしかなかった。欺瞞にも失敗にも耐えられなかった二人は、この日本列島に舞い戻って来たその時から、復讐の時を待ち続けていたのだ。
浴室の扉がノックされた。シーザーは即座にデザートイーグルをソ・シハンに投げ、一秒も経たないうちに両手に武器を持ったソ・シハンがアジアンスクリーンの後ろに隠れると、シーザーはバスタオルを身体に巻いて扉を開いた。
扉の外にはかつての相撲界の絶世の美男子、藤原勘助がいた。武士風チョンマゲに条紋模様の和服を着て、襟元には「風林火山」という四文字がダイナミックな書道で描かれている。この時の藤原勘助はもはやブヨブヨ贅肉のカタマリなどではなく、ましてや女装の猥雑男でもなく、闘牛の足のような前腕を袖から覗かせ、大きな顔には一糸の表情も見せず、両目で真っ直ぐにシーザーを見つめていた。もはやロボットめいたその風情は、ロ・メイヒに何百キロもの体重の相手の腰の褌を掴んで土俵から放り出すこの男の姿を想起させた。このホストクラブはまさに藏龍臥虎、何が隠れているかわかりゃしない!
「10分で身支度しろ。店長がお呼びだ」藤原勘助は英語でそう言うと、即座に扉を閉めた。
「面接か? 早すぎだと思わないか?」シーザーはスクリーンの裏のソ・シハンに目を配った。
扉が再び開き、藤原勘助がまた言った。「ああ、Sakuraも一緒だ。店長は三人同時に面接するらしい」
ロ・メイヒは湯気立つ浴槽の中で身震いした。「早すぎないか!? 僕まだ何もしてないのに!」
「高天原において最初に学ぶことは、ここで店長に逆らう奴はいないということだ」シーザーは言った。「『クジラ』の名を持つ男だからな」
「えええ……え、どういうこと?」ロ・メイヒは謙虚な心でアドバイスを求めた。いつもテスト前に頭と足を抱えている彼が、突然10分後の面接試験を伝えられてしまえば、教示を乞う以外にできることなどなにもなかった。
「日本は海に囲まれているから、日本人は海を崇拝する。クジラといえば海の中では最強の生物、クジラ肉は媚薬の材料にもなる。だからクジラの名を持つ男は、男の中でも最強というわけだ」ソ・シハンは言った。
「最強って、あの変な羽根つけてダンスフロア飛び回ってたあのバカっぽい奴の事?」ロ・メイヒは疑念を抱いた。
「バカっぽいといえばそうだが……校長先生もたまにバカっぽく見える時があるだろ?」シーザーは言った。「『バカっぽい』と『最強』は別に矛盾する要素じゃないぞ」
黒いマセラティが曲りくねった山道の突き当りで止まった。アンジェは腕を組んでエンジンルームのカバーの上に座り、遠くの山中で火を灯している隊列を眺めた。
白衣の僧侶たちが隊列の最前に位置し、長谷川義隆がその後に遺影を持ってついて行き、霊柩車の周りは真っ黒な服の女たちが囲み、最後尾には黒スーツと白ネクタイの一族幹部が続き、提灯や花籠を持って歩いていく。泣き声もなければ飛び交う紙幣もなく、山中には滔々と続く僧侶の悠然な読経だけが響き渡り、まるで万巻の仏経が海波のようにうねりながら山並みへ染みわたっていくかのようだ。十字路に差し掛かったところで琴美が「犬山家式場」と書かれた白い旗を地面に刺すと、長蛇の列はその傍を通り過ぎて、声もなく進み、さらに山の上へと登っていく。そこには山頂まで真っ直ぐ伸びた急な石階段があり、山頂のカエデ林には焼けただれた鳥居が隠されていて、その奥には朱色の建物の神社がある。
オロチ八家の神社だ。平安時代から、全ての当主は神社の裏の墓地に埋葬されている。墓は全て同じ形であり、唯一の違いは墓碑の上に書道体で彫られた文字だけだ。かつてはアンジェもこの墓地の参りに誘われたものだが、今では彼が足を踏み入れる事は許されない。
明日、犬山賀の葬式が行われる。今夜は犬山家の人たちが遺体を山へ運び、明日は極道の面々の車が山から谷までの道という道を埋め尽くすに違いない。
オロチ八家がアンジェを許したとしても、アンジェは葬式に出席しなかっただろう。彼には哀悼の意も、家族に挨拶する言葉もなく、香を焚くという習慣もなかった。彼はこれまでの人生であまりにも多くの葬式に出席し続け、このような事には疲れてしまっていた。ここで霊柩車を眺めるだけに留まっているのは、そういうことなのだ。
長谷川義隆が石階段の前で立ち止まり、辺りを見回すと、犬山家の女たちも彼に倣って首を回した。アンジェは一本のシガーを取り出し、明るいエタノールライターに火をつけた。長谷川と女たちは向かい側の山に小さな火の光を認めると、整然としたお辞儀をした。
黒い隊列が山を登り始めると、アンジェは踵を反してマセラティに乗り込み、振り返ることなくその場を去った。彼にはまだやるべきことがたくさんある。喪に服す時間はないのだ。
車のBluetooth電話がコール音を発して、アンジェは応答ボタンを押した。「もしもし?」
『アンジェ様のお電話でお間違いありませんか? こちらは三丼不動産でございます。お預かりの案件に関して、新しいお知らせがございます』電話の向こう側の人間が嬉しげな声で言った。
「すまんが、運転中なのでね。三十分後にそちらのオフィスに伺わせていただきますよ」アンジェは電話を切ると、マセラティを激しく加速させ、紅いテールライトが山道に光の孤を流した。
藍色のネムノキが描かれた扉が次々と開き、それぞれの扉の近くには背の高い屈強な黒服ボディガードが立っていた。ロ・メイヒはまるで自分が就職面接というよりも、宮殿へ皇帝謁見に行くかのように感じていた。もしかしたらお姫様か誰かが自分を選んでくれて……あるいは宦官として採用されるのかもしれない。
ここは高天原の最上階だ。このナイトクラブはかなり荘厳な四階建ての建物にオープンしていて、一階には壮大なパフォーマンスが催されて女性客が酒を飲んで踊るダンスフロアとステージ、二階にはSPAと美容室、三階には「藤壺」という名の懐石料理屋と和風喫茶店。また三階には住み込みの先輩ホスト達が暮らすスイートルームもあり、Basara Kingや橘右京といったニューフェイスの住む地下室とは格の違う暮らしをしている……正確には、この二人とSakuraの三人は浴室に住んでいるのであって、だから何度も何度も風呂ばかり入っているのだ。そして四階は禁区、店長に認められた者だけが足を踏み入れることを許される。高天原の四階には、「大海原」というあだ名もある。
巨大な鯨は当然大海原に住むべきであり、それはここでも同様、この四階全体が店長の住居になっている。階全体のメインカラーはシーブルーに統一され、シーブルーの壁、シーブルーのカーペット、シーブルーのカーテン、そしてダイニングテーブルやその上にある陶器まで全てシーブルー。そしてボディガードのハゲ頭の上にはウミガメやヒトデ、カニといった海洋生物が刺青されている……。
「なにこれ……どれだけクジラアピールしたいんだよ、あの店長……」ロ・メイヒは小声で呟いた。
最後のシーブルーなドアの前で藤原勘助は立ち止まって手を伸ばし、止まれの合図をした。
「俺がつくのはここまでだ。面接前に一つ言っておく」藤原勘助は三人それぞれの目をまっすぐ見て言った。「この店の人間としてではなく、センパイとしてだが……」
「もしかしてセンパイ、模範解答とか持ってたりするの?」ロ・メイヒは無性に興奮した。もしや目の前のこの屈強な男は日本版フィンゲルなのか? フンドシの中からカンペ取り出してきたりするんじゃ?
「この面接に回答はないんだ」藤原勘助はゆっくりと首を振った。「店長の質問に答えは無いし、質問を聞き返してもダメだ。同じ答えでも、ある人には正解で、他の人には不正解ということもある。大事なのは、自分の心に誠実であることだ」
「はいはいはい!! 誠実!! 僕たちちょー誠実です!! 僕たちは日本に来て、誰の助けもなくてこの街に流れ着きました! 店長が受け入れてくれなかったら明日の衣食住はどうしたらいいですか!? 店長に誠実じゃないなんてぜったいあり得ないないですよぉ!!」ロ・メイヒの顔は「誠実」の二文字でいっぱいになった。
藤原勘助はゆっくりとうなずいた。「そういう意識があるのはいいぞ。心の底から店長に感動を与えたいという心意義! 店長が言うには、面接は男と男のぶつかり合いらしい。火花が飛び散り、血が滴る、そういう取組だ」
そう話した後、彼は脇に寄った。「まあ、ガンバレ!」
最後の扉がゆっくりと開いていく。新鮮な海藻の香りが押し寄せ、まるですぐ傍に荒れ狂う海が迫っているかのように、水の音が耳元に響き渡った。
扉の後ろには一間の円形ホールが広がり、それを囲む壁は巨大な盃形の水槽になっている。岩の上に大きなサンゴの群れが生え、人工波の中で海藻が揺れ、ウミガメが悠々と浮かび上がっていく間に、体長二メートルのイタチザメがゆっくりとホールを一周した。
贅沢の雰囲気はシーザーを落ち着かせた。この円形ホールに入るまで、四階は彼にとってまるで幼稚園のように思えていた。そしてここに着た後は……最高級のゴージャス幼稚園だ! 中に水族館があるとは!
開放的なホールの中には二列の本棚と、その前に巨大な机があり、光の中には屈強な巨熊のような男が座っていた。シーブルーのサテンスーツからシーブルーの革靴に至るまで全身シーブルー、薬指には巨大なアクアマリンの指輪、胸には赤サンゴのブローチをつけている。彼はシーブルーのソファに座って巨大なチャーチルシガーを吸い、ヒマラヤン猫を撫でてている。ワイングラスいっぱいの氷が揺れ、色とりどりの光を反射した。
店長としてだけでなく、プライベートでも彼は圧倒的な存在感があった。巨大なサングラスと、光沢に包まれて草も生えない頭、ファンタジー的な極道のトップのような気概である……そのハゲ頭にシーブルーのクジラが乗っていなければ、の話だが。
三人は互いを見合わせ、全員で警戒した。店長のオーラは神秘的というか、予測をはるかに超えるものだった。……中二病と神経病の間、しかし、ただものではない雰囲気。
店長は扉の傍のソファを指差し、次いで目の前のシングルソファを指差した。分かりやすいジェスチャーだ。一人は前に出て面接、もう二人はソファで待て、ということだ。
俎板は既に置かれた。誰が最初に捌かれるかだ。三人全員が躊躇した。こういった面接試験は三人とも人生初めての経験であり、三人とも自分の受け答えに確信が持てなかった。
「俺がキングだ。俺が行く!」結局、最初に前に出たのはシーザーだった。
ロ・メイヒは安堵のため息をついた。やはりボスはボスだ。ガットゥーゾ家のイタリアン狂人とジャパニーズ狂人の店長、一体どちらが勝つのだろう。
この店に留まるためには、シーザーに失敗は許されない。彼はゲスト達を迎える時と同様のフルメイクとタイトスーツ、筋肉の透けて見える銀色のシャツにクリスタルスカーフを巻いていた。その後ろ姿を見れば、タイトなズボンが尻の筋肉をしっかりと包み込んでいるのが見える。
「ボス、本気だね……」ロ・メイヒはソ・シハンに囁いた。
「ガットゥーゾ家の男だからな。一度目標が決まれば手段を選ばず努力を惜しまない。奴らの一番恐ろしいところだ」ソ・シハンも囁いた。
だが店長はシーザーの見た目や服装については全くコメントしないどころか、机の上の毛筆を手に取って走り書きした。大袈裟に止め、また止め、はらい……どうやら熟練の書道愛好家のようだ。
墨汁滴る半紙がシーザーの面前に突き付けられた。「Basara King、俺が君に問うのは……ホストの道だ!」店長は中国語で言った。
半紙には飄逸な「道」の字が描かれている。シーザーは唖然とした。彼はあらゆる状況を想像し、どんな嫌味な質問でも心の防御は万全だと自負していたが、この店長はわずか一文字で彼の防御を揺さぶってしまった。
ホストの道だって? これはホストになるための面接なのか、それとも状元になるための殿試なのか!?
「日本では、どの職業にも己の道があり、道が無い人は世の中の迷える子羊だけだ。女たちを連れてパラダイスを探すのも男の花道だ」店長は混乱しているシーザーを見て言った。「Basara King、君の花道はなんだ?」
それからおよそ三十秒、シーザーは絶句したままだった。
「わ……わからん」シーザーは自分の呑み込めなさを素直に認めた。
「ではもう少し簡単な質問、君の女性観を聞こう。女性は春の風か、夏の花か、あるいは秋の実か冬の雪、どれだと思う?」店長はもう一度訪ねた。
ロ・メイヒの額は汗まみれだった……シーザーが完全に流れに呑まれている。もしシーザーの手に豆腐があったら、彼は迷わずそれで自分の頭を叩いていただろう。
「もう少しちょっと……具体的な……」シーザーの心理的防御はさらに揺らいでいた。
店長は小さく首を振った。無知な若者を見るプロの職人のような典型的な表情で、シーザーの反応を嘆いているようだった。
「では、最も簡単な方法で訊こう。Basara King、『女』を三つの言葉で説明してくれ。ある一人の女性ではなく、世界中の女性たちを、この世に存在する数億人の女性をだ」
シーザーは一瞬沈黙した後、突然力を抜いて微笑んだ。「ああ、それには三言も必要ない。一言でいいんだ。この世の女性は、いわば海だ」
「海、かい?」店長は眉をひそめた。
「全ての女性は一つの海だ。穏やかなものもあれば、荒れ狂うものもあり、バレンツ海のように冷たい海でも、氷の下にはイッカクやシャチの群れが泳いでいる。喜望峰のような危険な荒波でも、その岬を回れば豊かな東方への航路が広がる。勿論、カリブ海のように美しく、神秘的で、しかし海賊が出るような女性もいる」シーザーは笑った。「店長、船に乗ったことはあるか? 船に乗るなら、俺の言いたいことは分かると思うが」
「俺にも二十万海里を渡った経験がある。君が言いたいことは大体分かった気だが、もう少しBasara Kingの説明を聞きたいな」店長は厳粛な表情を見せた。
「この世の海に一つとして同じ海は無い。海流、色、塩分濃度、生物。ロマンティックな感覚を齎す海もあれば、命の危険を匂わせる海もある。だが海を愛する船乗りであるなら、暖かいインド洋をひたすら回るだけでなく、もっと他の海を見てみたいと思うはずだ。一路北上し、北極海の氷河を見てみたいとかな。だが最終的には自分の最愛の海に戻ってきて、大きな船は小舟に代わって、白い帆をひとつ掲げてゆったりとした航海に戻る。全ての男は船乗りだ。全ての海を見ようとしても、結局は自分の居るべき海に戻り、ゆっくりと老いていくものだ。……これが全てだ」
「なぁんにも分んないけど、すごい哲学的っぽい!」ロ・メイヒは心の底から称賛した。
店長は一瞬沈黙した後、軽い拍手を送った。「上手いこと言うな。さすがは新人王、Basara Kingだ。では君は戻って」
次に店長の前に座ったのは、橘右京ことソ・シハンだった。
「右京、今Basara Kingに聞いたように、君にも一つ質問をしよう」店長は二枚目の書道半紙をソ・シハンの面前に掲げた。そこには飄逸な文体の「術」の字が書かれている。
「何事も極致を成そうと思えば、心には道が、手には術が無ければならない。ホストの術とは、何だと思う?」店長は一度そこで言葉を止め、反応を伺って続けた。「もうすこし単純に言おう。女性を惹き付けるにはどうすればいいと思う? 女性たちに気兼ねなくお金を使ってもらう為には、どうすればいいかな?」
「二日ほどの実践で得た経験で……」ソ・シハンはまったく落ち着き払っていた。「俺のゲスト達のデータを分析した。この二日間で参加した酒の席は13回、相手をしたゲストは72人。最年長は37歳、最年少は23歳、平均年齢は28.3歳、その内の86.7%は既婚だった。これに対し、シーz……バサラ・キングの平均年齢は25.6歳、そのほとんどが未婚であり、俺のゲストは比較的成熟しているといえる」
「すごいな右京、数学の才能もあるのかい?」店長は驚きを露わにした。
「彼女たちは単に酒を飲みにではなく、心理的な癒しを求めて高天原に来ている。俺は日本語が分からないが、ウェイターに通訳してもらって話を聞けば、彼女の内27人は家庭内暴力を受け、31人は夫が不倫、16人は離婚間近だということが分かった。つまり、彼女達は結婚生活に失望し、心を抑圧された女性達であり、俺のこの場での役割は異性の友人と心理カウンセラーとの中間に位置すると言える。俺の日本語が流暢であればより良いサービスが提供できるが、日本語力をすぐに上げるというのは難しい。しかしウェイターの通訳に頼るというのも問題がある。ウェイターがいると女性達にはパブリックな場という意識が生まれ、プライベートな話題を振りづらくなる」
「当然だね。もし俺が傷心の乙女だとすれば、心の悩みは是非、右京のような美少年にこそ聞いてもらいたいと思うだろうさ」店長は何度も頷いた。ソ・シハンの回答はシーザーよりも店長の興味を引いたらしい。
「いや、彼女達が期待しているのは心の内を吐き出すことではなく、更に強く圧迫されることだ。臨床心理学的に言えば、彼女達は典型的なストックホルム症候群にある」
「難しい学術用語だね。右京自身の解釈と説明を聞きたいな」店長は尊大な態度を隠しもしない。
「英語で言えばストックホルム・シンドローム、別名人質同情症。人質に取られた人に見られた精神状態で、警察による救助を信じる事ができなくなると、犯人に依存し、好感すら抱くようになる。犯人が彼女達を優しく扱う限り、彼女達は犯人に協力し、自由と引き換えに犯人の要求を満たすような行動をとることもある。心理学的に言えば、彼女達は見捨てられるのを恐れ、犯人とはいえ長時間同じ空間に居る人間に注意を向け続けることで、女性的な感覚として犯人に親近感を得てしまうというプロセスだ。女性は無視されるくらいなら粗雑にでも扱われることを好む。酔ったゲスト達が一番愚痴を零すのも、夫の無関心だ」
「右京! 君はホストの術に新たな理解を開こうとしている! 続けてくれ! もっと聞かせてくれ!」店長は身を乗り出し、大袈裟に耳に手を当てた。
「ゲストの精神状態を理解すれば、適切な『薬』はおのずとわかる。彼女達の期待に応える為には日本語が流暢である必要もない。俺が敢えて悦ばせる必要もない。何を言われても動じることなく、冷漠に接すればいい。彼女達にとって俺は人質事件の犯人のような、同じ空間に居ながらも近寄り難く、心理的な抑圧を与える存在になる。ストックホルム症候群のように、彼女達に『この人はわざとこんなぶっきらぼうにしてるんだ』と思わせ、意識が向けられているということを感覚させる。そういった注目こそが、彼女達の求めるものだ」
店長は興奮して手を高々を挙げた。「いいぞ! いいぞ!!」
「俺が学んだ日本語は一文だけ。ゲスト達が終わりにしたいと思った時に言う言葉だ」ソ・シハンは粛穆とした表情で、舌に力を込め、マントラの9文字を唱えるかのように言った。「『今日はここまでにしてやる。帰って、泣いて、さっさと寝ろ』こういった乱暴な言葉がゲスト達の自尊心をさらに刺激し、競争社会を生き抜く女性の成功を促し、また酒を買いに来てくれる。そして俺の名の下での酒の消費量も増えるというわけだ」
橘右京先生の完全進化! これが先輩の究極完全体なの!? ロ・メイヒはこれほどソ・シハンが尊大傲慢になれるとは思わなかった。まさにホスト界の使徒、預言者にして征服王!
ソ・シハンがソファに戻る。ロ・メイヒはこわばった頭を振り払うようにして立ち上がり、大きく伸びをして小さく縮んだ。いまや自分は背水の陣の勇者、思い切ってやるしかない。
ロ・メイヒの心は、これから鬼が出されるのか龍が出されるのか、不安に揺らいで仕方がなかった。シーザーもソ・シハンも同じ新人だが、彼らには女の子との縁がある。所謂「豚肉食わねど走るは見し」といったところである……しかしロ・メイヒが最近気を寄せた女性といえば、チン・ブンブン、ノノ、夏弥の三人くらいであり、しかもその内二人には既にボーイフレンドないしボーイフレンドのような人がいて、残る一人もチャオ・モウカと手を繋いでウェディングロードを往き、ホストに身を落とした自分とは似ても似つかない世界の人となってしまった。
「Sakura」店長がゆっくりと言った。
「はいぃ!」ロ・メイヒは恐怖に震えた。
店長の鉄のように硬い顔が突然笑顔に綻び出し、ポンポンと自分のすぐそばを叩いた。「Sakura、俺の隣に来るんだ。君だけはこの位置で面接をするよ」
シーブルー色のソファは三人がゆったり座れるだけの幅がある。店長が中央に、左側はヒマラヤン猫専用。その右側がロ・メイヒの為に取っておかれていたのだ。高天原の新人ランキング史上一位のBasara Kingも、二位の橘右京も、ここまであからさまな待遇を受ける事は無かった。断ることなどできず、ロ・メイヒは震えながら腰を下ろし、両手を膝の中でがっちりと握った。店長のコロンの強烈な匂いに眩暈を覚えたが、今倒れるのはまずい。倒れたら店長の腕の中に堕ちてしまう。
店長はロ・メイヒの肩に手を置き、軽くなでた。「初めて見た時思ったんだ。Sakura君はまるで若い頃の俺のようだってね」感嘆の意のこもった語気だった。「繊細で、感性的で、簡単に悲しみに暮れてしまう」
この威圧感ある男を見たロ・メイヒの心の中には、とある場面が浮かび上がってきていた。熊が田んぼの際に座ってカワウソに腕を回し、「カワウソ君、世界広しといえども僕のセンチメンタルな繊細さを分かってくれるのは君だけだよ」などと言っている場面だ。
「少年の心はさながら詩だ。朝には座して愛を説き、蘭と頭を垂らし合い、蟋蟀と音を紡ぎ合う……」店長は完璧な中国詩を詠み上げた。「若い頃の俺の作さ。当時は漢詩に夢中になっていてね」
ロ・メイヒはゆっくりと目を見開いた。まるで詩に込められたあらゆる意味を完璧に理解したかのように、あるいはこの素晴らしい詩に心を洗われたかのように、懸命に表情を作っていた。
「Sakuraにはガールフレンドはいるかい?」店長がいきなり気さくに聞いてきた。
「いません」
そう言った瞬間、ロ・メイヒは自分の事を本当に馬鹿だと思った。これではまるで「この業界での経験が無い」と言っているようなものだ。
「いいよ、いいよ、さながら詩たる少年の心だ。詩とは言葉にされる前こそ完璧だが、言葉にされた後は庸俗になってしまうものだ」店長は賞賛に呟いた。「Sakura君には、心に決めた女性がいるのかい?」
シーザーとソ・シハンは顔を見合わせた。二人に面接していた時の店長は気も抜けない怒張した雰囲気だったのが、今では全然雨風も立たない、遠い親戚の叔父と甥っ子のようになっている。
「はい、おります」藤原勘助が店長の前では正直になれと言っていたのを思い出して、ロ・メイヒはなるべく大人らしく答えた。
「アネゴとロリータ、どっちが好きだい?」店長は興味津々な様子を示した。「俺の予想では……アネゴ! Sakura君は姐御のような女性が好き、だね?」
このクジラ男は数えきれない人間を見てきている……ロ・メイヒはそう悟った。姐御好きだというのも見抜かれてしまった。藤原勘助のアドバイスは本物だった。彼が今まで好きになったチン・ブンブンやノノがどういう人間か……チン・ブンブンは文学部部長、自分を足で使う立場。ノノも先輩、自分を顎で使う立場……ロリータのような女性など見たこともなかった。零はロリータに見えなくもないが、彼女もダンスシューズを履いて突然背が高くなった時にはノノのような威圧感を発揮し、完全に女王殿下と化してしまう。
「告白したことは?」店長はまた尋ねた。
「な……ないです」
「告白しないのかい? 彼女たちは君の告白を待っているかもしれないんだぞ。それとも女の子に心を推し測って欲しいのかい? しかし女性とは様々なものを怖がる生き物だ。特に若い時はね」店長は何か深く感じ入って言った。「だから女の子の最初のボーイフレンドは屈強な武士のような人になる。彼女を外の世界に連れて行ってくれるからだ。しかし多くの女の子にとって、最初のボーイフレンドは悲劇になってしまう。大抵の場合、そういう男の子はバカだからね」
「どんなに美人がバカを愛しても、バカは美人を大切にできない。だから……」ロ・メイヒの口から無意識に言葉が飛び出してきた。
「詩的だ、とても詩的だよ、Sakura君! 人生というのは、そういった悔いばかりの旅なのさ」店長はロ・メイヒに顔を向け、目の高さを合わせて言った。「ではそこで君に問おう。Sakura君、悔いのない愛とはなんだい?」
「くぃ……?」ロ・メイヒが口を開いた。これだけ聞けば、シーザーやソ・シハンの質問より答えやすい質問のように思える。中国の高校社会の試験で「あなたにとって『四有新人』とは何を意味するか」とか聞くような、政治学の先生が平均点を上げようとして出すような問題、文字数を稼ぐためだけのナンセンスな問いだ。
「Sakura君、藤原君も君に言ったはずだよ。この質問に模範解答は無い、とね。君の誠意と真心でこの質問に答えるんだ。悔いのない愛とは? 悔いとは? 愛とは? Sakura君、よぉく考えるんだ」店長はゆっくりと言った。「回答のチャンスは一度だけだぞ」
アットホーム的な雰囲気は一変し、シーザーやソ・シハンすら竦むようになってしまった。ロ・メイヒは優遇されたのではなく、むしろ最大の挑戦を突き付けられたのだ。店長は気さくな雑談で彼の恋愛遍歴を手早く汲み取り、背後から突き付けるナイフのような質問を投げかけた。もし愛について考えた事が無ければ、当然悔いも愛もありえない。店長は確かに業界のプロだった。一挙一動がロ・メイヒの弱いところを突いて来る。
ロ・メイヒは全身に冷や汗をかいていた。「チャンスは一度だけ」、いわば丸裸にされているようなものだ。もし答えを間違えたら即刻クビなのか?
彼は自分の知っている愛の事案を思い出そうと心の中を探った。チャオ・モウカとチン・ブンブン? あれが悔いのない愛? どこが? あれはただの級友への友情であって、リュウ・ミャオミャオも泣いていたじゃないか。
シーザーとノノ? アレはおかしな人同士の風雲際会、ノノがどれだけシーザーを愛しているか、シーザーすらも理解しちゃいない。
自分の両親は……そもそもどうやって会ったんだ? 生まれる前は一緒に居たのだろうが、顔すらまともに覚えていない……。
ソ・シハンと夏弥……ダメだ、何も言えない。彼の涙はまだ流れているままだ……。
悔いのない愛なんて……そんなものがあるとすれば。完全無欠でなくても、良い結果でなくとも……何年も経った後にふと人混みの中で顔を上げた時、遠くに一人で立っている彼女の姿が見えても、動悸がしたり震えたり涙が溢れたり、恨みとか悲しみとかが沸き上がったりもしないような……。
悔いのない、純粋な愛……。
ホール全体に死んだような寂静が広がる。ロ・メイヒは頭の上に蒸気が噴き出すような感じすら覚えながら、渾身功力で驚天動地の絶世一撃を店長に見せてやろうと思っていた。
((せめて変な事だけは言うな――))シーザーとソ・シハンは心の中で繰り返した。二人はロ・メイヒの特性をよく理解していた。緊張状態のロ・メイヒはいつナンセンス皮肉悪口ラジオと化すかわからない。
「悔いのない愛とは……全身全霊でぶつかって、何も考えず、恐れず、勇ましく……」ロ・メイヒはゆっくりと、捻り出すように、脳汁まで絞り尽くすかのように話したが、そこまで言ったところで口が止まり、力が抜けてボールのように膨らんでしまった。
シーザーもソ・シハンもダメだと悟った。あまりにも陳腐な回答、論理的にも混乱していて要領が掴めない。店長は長いため息をついた後、首を振った。
「ぼ、僕、僕……ウェイターでもいいんだ!! お料理出しながら僕の花道を見つけます! だから――」ロ・メイヒはどもりながら言った。
「Sakura、君の奥底にある悔いのない愛とは、恐れず、退かず、代償も気にせず、報いも求めない……」店長は感嘆しながら言った。「と、いうことだね? 素晴らしい! パーシー・シェリーはこう言った、『愛とは光のようなもの。同時に二人を照らしても、光は弱まることを知らない』。そしてバイロンもこう言った、『愛には喜びと痛みが交互に現れるものだ』と。詩人たちは異なる言葉を使いながら、一つの真理を言い表している。愛とは百パーセントの幸福でもなければ、公平なる取引でもない。悔いのない愛に勝者はいない、誰もが敗北者となるが、それこそが悔いが無いという事だ。なぜなら、それが愛だから! 愛は、二人を照らす光だ。この偉大な光が無ければ、生きていたって意味が無い!」店長は興奮しながら立ち上がって、偉大な演説をする古代ギリシャ哲学者のようにホール中を歩き回った。「恐れたり、退いたり、代償を気にしたり、報いを求めるような愛は、どれも欲望の化身たる悪魔の業だ。Sakuraの大いなる愛の前では、そのような愛など全て灰燼と化す……」
シーザーもソ・シハンも茫然とするばかりだった。ロ・メイヒはギリギリまで使った歯磨き粉のように言葉を二つ三つ絞り出しただけなのに、店長にかかれば壮大な雄文へと変わってしまった。古典詩集まで引用して、リズミカルでパワフルな言葉へと変えられてしまった。
ロ・メイヒは喜びを露わにした。自分が捻り出した二つ三つの言葉にこれだけ深い思想が隠れているなど思いもしなかった。いわゆる「文章本より天に成す、妙手之を偶に得る」というのはこういうことなのだろうか? 高校で文芸部に入った経験がこんなところで役に立つとは。
店長が手を叩くと、ホールの扉が開き、ウェイターがシャンパン満載のカートを押してやって来た。次いで藤原勘助率いる高天原のハンサムたちが列を成して入ってくると、ホール中央のクリスタルシャンデリアに光が点り、水槽の中の魚たちを照らした。
「おめでとう諸君! 君達は合格だ! 今日から晴れて高天原の一員になるのだ。君達の花道で、女性たちをエデンの園へと連れて行ってくれたまえ!」店長はシャンパンカートからグラスワインを持ち上げた。「もちろん、Sakuraはあと800枚の花チケットを貰う必要がある、がしかし! この天才若者なら造作もないことだろう。聡明にして善良、英俊にして可愛い若者を好きにならないわけがない! 高天原の未来を祝福して、乾杯!」
店じまいからさほど経っていないこの時間、全員が一晩中飲み明かすつもりで、栓の抜かれたボトルが次々現れ、冷えたグラスの中で黄金の酒が渦を巻く。店長のリーダーシップの下でホストクラブは『銀河英雄伝記』のイゼルローソ要塞のように、「伊達と酔狂」の理念に貫かれてしまった。ホスト達は代わる代わるやってきて握手を求め、この睦まじき大家族に新たに加わった三人を祝福した。
そして誰も知らないうちに、店長はその場から姿を消した。
背もたれの高いソファが二つ並べて置かれている。黒影がグラスの中の緋色の酒を揺らし、透き通った青い水の向こう側、壁を隔てた先で開かれているシャンパンパーティを見た。
一匹のシルバーアロワナが優雅に泳ぎ、海藻から小さな気泡が浮かび上がる。水槽の壁は実際には覗き窓にもなっていて、奥面はマジックミラーでできている。秘密の部屋の中の者はホールの内部をはっきりと見る事ができるが、ホールからこのゴージャスな秘密の部屋を見ることはできない。この秘密の部屋こそ、真のオーナーのオフィスである。クリスタルシャンデリアと大理石の床は互いを映し合い、壁には過去数十年に渡る英雄的ホストの写真が並び、高天原の輝かしい歴史を見る事ができる。ソファから机までアンティーク家具で揃えられ、旧式のレコードプレーヤーがプッチーニの『蝶々夫人』を演奏している。ここにおいて、クジラの名を持つ男はただ恭しくソファの後ろに立つのみで、その腕に巻かれた白いディナークロスは彼のこの場での地位を示している。
そこに座るのは真のオーナーのみ。彼女二人だけが輝くことを許される。
左側には清爽な長髪の「森ガール」。右側には漆黒の髪を上に赤いリボンで纏めた古風な美女。二人はダークレザーのドレスに黒ストッキング、膝まであるパテントレザーブーツを履き、シルバーメタルのハイヒールは人すら殺せそうな鋭さだ。
「どうしてこんな格好を?」酒徳麻衣は裾をピンと張った。しかしレザースカートはそれでも短すぎて、座ると見えそうになってしまう。「ホストクラブのオーナーになったのに、私達自身まで売るみたいじゃない」
「何よ! この服凄くカッコいいでしょ!」ス・オンギは肩を揺らした。「裏社会に溶け込むための服なんだからね。これに比べてスーツケースの中の服はダメダメ。白シャツにスーツ、ドレス、どれ着てもまるで経理じゃない」
「経理が無理してアバズレ女になっちゃったわけね」酒徳麻衣は首を振った。「服を変えるのは簡単だけど、気質は簡単には変わらないわよ」
「しゃらくさいわね! 短い人生、セクシーでないと!」ス・オンギは興奮して太腿を叩いた。
「あのねぇ……そうやって足を叩くの、ヨーロッパの男みたいで全然セクシーじゃないわよ」
ス・オンギはガラスに映った自分を見て、不格好に歪んだ自分の表情を抑えた。ホストクラブは彼女にとってもワクワクする場所だった。何事にも無関心な態度を取っていた彼女が、この時は一言一動から溢れる本心を隠せずにいられなかった。
「ミス・スー、今日の面接はお気に召しましたか?」ザトウクジラが恭しく訊いた。
「気に入った、わけではないけど。目から鱗ではあったわ。これまでああやってホストに面接してたの? 哲学者にでもなりたいわけ?」ス・オンギは笑いながら揶揄した。
「哲学、芸術、歴史は全て内面の投影です。それらを見ないと完璧な男は選べません。彼らの心に咲く、一輪の花を見なければ……」ザトウクジラは自惚れたように言った。
「心の花が何ですって? 女がホストクラブに来るのは、ハンサム男の時間を買う為じゃなくて? 一緒に酒を飲んで、めちゃくちゃになって、身体を寄せ合って筋肉を触らせたり、虐めたり遊んだり虐められたりして、最後に『愛してる』って言えばいいのよ。私は女なのよ? わかる? 女の考える事は女がイチバン分かってるんだから!」
ザトウクジラは戸惑い、数秒ほど凍り付いた。「……男の審美というのは、赤ワインにも似て、少しずつ醸成されていくものなのです。最初は外見の美を評価しますが、やがて魂を評価するようになる……いわゆる最高の悦楽というのは、肉欲ではなく、直接心を高鳴らせるものなのですよ」
「チップスぅ~? 要するにアナタ、男を見る目が無いって言われてるのよ」酒徳麻衣がダメ押しとばかりに付け加えた。
「なに!? 私に男を見る目が無いっていうの!? 私にはないって!? ないぃ……」
「恋愛経験ゼロの女は、こういう話題になるとますます声が小さくなっていくのね? フフフ……」酒徳麻衣は悪い表情を浮かべ、しょげたス・オンギを撫でた。「私はザトウクジラの言葉が正しいと思うわ。男を愛する女の中には、自分の心の中に作り上げた空虚な影に恋してしまう人もいるのよ」
彼女はロ・メイヒを興味深く見つめた。人々が集まって何度もグラスが掲げられる中、高天原史上最も早く花チケットを集めたBasara Kingと橘右京はホスト全員に認められたが、ロ・メイヒは水槽の前にしゃがみ込んで、酒徳麻衣のいる方向に顔を押し付けていた。もっとも彼には実際には麻衣は見えず、水槽の中の銀色の小魚しか見えないはずだ。ロ・メイヒはガラスに気付かずぶつかり続ける小魚を脅かそうと、水槽に顔を押し付けているらしい。彼の鼻がガラスの上で扁平につぶれ、バカっぽく見える。
ホールにはハンサムやイケメンが溢れかえっているが、酒徳麻衣の目はこのバカでアホ臭い顔に合わせられたままだった。彼の目線は定まるところなくフラフラと、まるで孔雀たちの宴会に放り込まれた鶉のように彷徨う。
「お客様~? うちのSakuraがお気に入りでございますかぁ?」ス・オンギは媚び媚びの風で言った。「お目が高い! 今うちで一番活きのイイ子ですわよ!」
「そうね、とても面白いわ。まるでカイコがゆっくりと糸を吐いて、繭の中に閉じこもるのを見てるみたいで」酒徳麻衣は幽々と言った。
「そういえばアンタのした三つの質問って……あのスモートリが言ってた通り、本当に模範解答がないわけ?」ス・オンギは好奇心から聞いた。
「男の花道ですからね、嘘はつきませんよ。そうです、模範解答はありません。私はただ、彼らの答えから花の心を見出すだけです」ザトウクジラは恭しく言った。
「あら~! ではお聞かせなさせ? シーz……Basara Kingの花の心ってどんな花なのかしら? 命知らずの貴公子、やっぱり花と言えばバラなのかしら?」ス・オンギは興味を持ったらしい。
「いいえ。Basara Kingの花はむしろ、Sakuraの名の元になった花……彼の心にはサクラの花が咲いております」
「ソ・シh……右京がサクラなら私も分かるけど、シーザーがサクラってどういう? もっとゴージャスカラフルじゃなくて?」ス・オンギは納得いかないようだった。
「サクラという花は、実は男の花であり、華美にして貞節堅いものです。サクラの開花期間は僅か一週間、一週間でピークに達し、その後は一晩で枯れてしまうのですが、その凋落する一夜こそ最も美しい瞬間なのです。古代の名将軍のように、生きている間は心赴くままに激烈熱烈な人生を歩み、しかし床に伏した時には刀を置いて、孤寂な禅の詩をしたためる。Basara Kingはそのような男です。彼の答えた女性に対する尊重と愛は、たんなる高潔さや凛々しさよりも注目すべき所でしょう。彼は高い枝の上に生まれ、その美しさを以て天下を見下ろし、美しいものが汚されるのを許さず、己が汚れるのも許さない男なのです。彼の頑固さは武士の刀の如く激しく、落ち桜の如き美を生み出すでしょう」ザトウクジラは詩情たっぷりに言った。
「酷い言い方するのね。要するにシーザーの背中には『我こそ犠牲とならざらん』とでも書かれた旗でも刺さってるってことでしょ?」ス・オンギは言った。「じゃあ、ソ・シh……右京はどんな花なのかしら?」
「菊の花です」
ス・オンギは鼻から赤ワインを噴き出し、鼻血のようになった。
「!? ……オーナー、大丈夫ですか!?」ザトウクジラは即座に反応した。「もしや、このワインはお口に合いませんでしたか?」
酒徳麻衣はテーブルナプキンを手渡して、淡々と言った。「大丈夫よ、オタク女が過剰反応しただけだから」
「ダイジョブダイジョブ」ス・オンギはテーブルナプキンを受け取って鼻を拭いた。「続けて」
「彼は吹雪の中の矢車菊です」
「ドイツの国花のアレ?」
「ええ、普通の菊の花です。寒冷な気候をこの身、比類なき生命力を持ち、氷雪の中でも満開の花を見せてくれる。花言葉は『忠誠』と『憧れ』、『優雅』と『一人』、『出会い』、そして『再生』」ザトウクジラは言った。「我らが右京の醸す香りは、矢車菊の香りなのです」
「なんか目の前に浮かんでくるみたいだわ。ドS属性の矢車菊が鞭を振って客に向かって言うのよ。『今日はここまでにしてやる! 帰って、泣いて、さっさと寝ろ!』」ス・オンギは言った。「ねえ! おかしくない! 彼のどの答えから無口で優雅なハンサム男が出てくるのよ! 出会い? 再生? アンタが聞いた答えも、ドSのクソ男が女から金をより多く搾り取るための技術論でしかないじゃない!」
「いえいえ。あの右京の答えからは何も分かりはしません。私はただ、彼の目だけを見て判断したのです」ザトウクジラは真剣そうに言った。「右京のような菊のように上品な男に会ったのは何年ぶりでしょう。まったく冷寂にして貞節堅し、素晴らしい! 彼は本当に素晴らしいですよ!」
(それって彼がコンタクトレンズしてるからでしょ? コンタクト付けてない時の彼の目を見てみればいいのよ)ス・オンギは心の中で吐き捨てた。
「オーケー、オーケー、じゃあSakuraは? Sakuraの答えは悪くないと思うわ。今回は珍しくナンセンスおしゃべりじゃなかったし」ス・オンギは言った。
「いえ……私の経験から判断すると、Sakuraはホストに向いているとは言えません。ですがお二人方のボスが彼の面倒を見てほしいと仰ったので、仕方なく褒めることにしました」ザトウクジラはため息をついた。「私のプロ意識としては、恥になりますが」
「アンタ大丈夫? 変なお薬でも飲んだの?」ス・オンギは手を伸ばして彼の禿げ頭をバシバシと叩いた。「アンタが上手くまとめたんでしょ!? 『恐れず、退かず、代償も気にせず、報いも求めない』って、もしロ・メイヒみたいなバカじゃなくて風土翩々な美男子に言われたら、私感動しちゃうわよ!?」
「いえいえ、ミス・スー、Sakuraは愛の理解に力を使い果たし、絶望のオーラに変えてしまったんです。あなたの言うそれも、孤独な人の呼びかけ合いでしかありません。愛とは太陽と雨露、人の心を潤わせる良薬。しかしSakuraは渇死しかけて天に雨乞いをしている。Sakuraはつまり、愛の無い男なのです……ああ、いえ、彼にも愛はあるのですが、ただあまりにも少なすぎるといいますか、心の奥底に大切にしまい込まれているのです。そんな人が他人と愛を分かち合えると思いますか?」ザトウクジラは残念そうに手を擦った「少なくとも、ここのゲスト達にはあまりウケが良くないでしょうね」
「ということは、Sakuraの花は……オオイヌノフグリ? 雑草? ピクルス?」ス・オンギは頭を掻いた。
「いえ。彼は白いヒナゲシのような男でしょう」ザトウクジラはため息をついた。「あまり縁起のいい花言葉がないのですが――」
「そういうのいいから。なんで白ヒナゲシなの?」
「実際、ヒナゲシというのは美しい花です。中国では虞美人草とも言われますしね。ですが極致の美とは死の美。人を窒息させ、荊棘に纏われ抱かれた、天使と悪魔の化身。白ヒナゲシが表すのは初恋と忘却。ヒナゲシの花言葉を持つ男は、少しずつ破滅に近づいていく……。このホストクラブの歴史上、ヒナゲシの花言葉を得た男は二人しかいません。以前の人は上流家庭出身のゲストと相愛の恋に落ち、しかし身分の差で結婚できず、練炭自殺を遂げてしまいました」
「まさか、あの哀れな子供が本当に練炭自殺みたいな芸術的なことできると思う?」ス・オンギは笑った。「彼の何処に滅びの美だの荊の愛だのがあるわけ? 具体的にどこに? お尻?――」
「はいはい、オタクちゃん可愛いわよ。そんくらいでやめなさい」酒徳麻衣は遂に我慢できず、ス・オンギの声を遮った。「付き合って以来、あんたも色んなものにハマって来たわよね、星座だのタロットだの紫微斗数だの。そういうのは分かるわ。オタク女が寂しさを紛らわすために運を計算して信じたくなる気持ちもね……でも、店長の言う花道ってちょっと大げさすぎない? 所詮、ホストと女の間には買う買われるの関係しか無いじゃない」
「ミス・サカトク、これが私の長年の経験なのです! 私の慧眼は無数の美男子を見てきました。寸分違うはずもありません!」ザトウクジラは赤白な顔で弁明した。
「この業界では長年の経験があるってこと?」酒徳麻衣はあざ笑うかのように、流し目で彼を見た。
ザトウクジラは突然羞恥を覚えた。「ただの自慢ではありません。二十年前、私は歌舞伎町で一番の男でした。私に会おうとする女性は一ヶ月前から予約しなければならず……」
「つまり、自信があると? ……来なさい、ちょっと顔貸して」麻衣が手招きした。
ザトウクジラは唾を呑んだ。彼も世の多くの顔を見て来た男だが、このミス・サカトクを間近で見ると、女王に謁見してるかのような緊張感と幸福感があった。
酒徳麻衣はザトウクジラの顔を持ち上げ、皺の一つ一つまで確かめた。「チップス、中国人は年月を何に例えるんだっけ?」
「肉切り包丁」
「あ、そうね」酒徳麻衣はザトウクジラの顔に、ふぅっと息を吹きかけた。「Sakuraの花がイヌノフグリだろうがヒナゲシだろうがハナミズキだろうが、彼が将来練炭自殺しようがホスト界の太夫になろうが関係ない。アンタが高天原を存続させたいなら、彼を守りなさいよ。名前も顔も外に漏らさず、衣食住を提供し続けるの。でも優しすぎてもダメ、守られてると気取られたらダメよ。で、Sakuraが正式なホストになるためには花チケットが800枚要るんだっけ?」
「ええ、高天原のルールでは、見習いホストは二週間以内に800枚の花チケットが必要です。彼を留め置きたいゲストはわずか1000円から、彼を支持する花チケットを買えます」ザトウクジラは言った。「ですがSakuraの才能では、花チケット800枚は簡単には……」
「彼を全面に押し出して。セクシーに着飾って、客が好きになるようにして、とにかく一枚でも多くチケットを集めるのよ。どうしても集まらないなら――」酒徳麻衣はカバンから万札の束を取り出し、ザトウクジラの胸に向かって投げつけた。「80万円あるわ。十分でしょ? 客にも本人にも気取られないように、数字を裏から操作するのよ」
「……お二人はもうここのオーナーです。Sakuraを置いておきたいなら一言仰ってくれればいいのに、なぜこんな金を……」ザトウクジラは恐れ入ったようだ。
「早くその金を持って外行くの。いいコンパニオン見つけて、Sakuraに貢がせるのよ」酒徳麻衣は無表情に手を振った。「何も無ければもう終わり。余計な挨拶は御免よ」
ザトウクジラは何か悟りでも開いたかのように、一瞬で理解し、目を見開き、禿げ頭を明るくさせ、水槽の向こう側のロ・メイヒを呆然と見つめた。ザトウクジラの表情は喜哀に溢れ、思いもよらずに変化する。ス・オンギは彼に目をやると、何となく不気味な気分になるのだった。
「なるほど! 凋零寸前のSakuraを大切にするわけですね! これこそ世間一切の美男子の宿命か……早すぎる開花と凋零、ただその残香だけが人を悲しませる……」ザトウクジラは深々とお辞儀をし、悲し気な表情で去っていった。
「アイツなんか誤解してない?」ス・オンギはザトウクジラの後姿を見て言った。
「知らないわよ。ボスはほんの遊びだって言ってたけど……どう思う?」麻衣は眉をひそめた。「ただあの三人を守りたいだけなら、ホストクラブに置いておく必要なんてないはずよね? しかもステージ公演なんて。Basara Kingと右京は意外にも大好評みたいだし、もし新宿ホスト史に名が刻まれるほどになったら、オロチ八家にもその名を知られちゃうわよね?」
「ボスが何考えてるかなんて分かるはずないじゃない。とにかく、ここの仕事は私にとっては悪くないわ。ハンサム男たちが飲んだり騒いだりしてるのを毎日見られるんだもの。保育士するよりも全然楽々よ」ス・オンギは言った。
「楽々?」酒徳麻衣は首を振った。「嵐の前の静けさってやつじゃないの?」
ザトウクジラは扉の外の階段に腰を下ろし、一本のシガーを取り出して口に含み、寂しさと喜びを織り交ぜた表情をした。
数日前、彼はこのナイトクラブのボスであり、東京ホスト界で最有力な人間だった。しかし今はただの店長である。破産してしまったのだ。
高天原ホストクラブは最人気、収益も最高だが、コストも最大だった。この四階建ての建物は、元々は第二次世界大戦前にフランス人によって建てられたカトリック教会であり、高天原は何十年もこれを借り続けてきているが、毎年の賃料もバカにならない値段である。一流ブランドのデパートにもなり得るほど広い土地が、ホストクラブの敷地になっているのだ。しかしザトウクジラはこの巨額の賃料に見合うだけの価値があると理解していた。彼の客はみな東京の最上流階級のトップセレブ、宮殿級の場所を用意しなくて何だというのだ?
彼は小道具にもトップレベルを追求した。イタリア製のソファ、ヴェネツィアのクリスタルガラスのワインセット、ドイツ製の純銀ナイフとフォーク、壁に掛けられた絵も全て本物だ。
東京男性サービス業協会の理事長でもある彼は毎年会費を捻出し、その手腕もダイナミック。昔からホスト界の慈善家として知られ、ザトウクジラのニックネームも彼の覇気を示すというよりは、ぺんぺん草も生えない彼の頭の様を表しているに過ぎない。
だがホストクラブの運営だけではこの莫大な出費には追い付かなかった。ザトウクジラの口座は日ごとに枯渇し、遂に多額の借金まで抱えてしまった。そして先週、ザトウクジラはホスト達と人員削減に関する話し合いの場を設けたのだが、彼はそこでも悲しむばかりで、桜の美を好む時代は終わった、今の女性はテレビドラマの男性アイドルに媚びる事しか知らない、古風で優雅な男の花道を味わうことは出来なくなってしまったとかまくし立て、感傷の果てに泣いて突っ伏してしまうだけの結果となってしまった。
だが一昨日の正午、二人の女性が高天原に足を踏み入れた瞬間、状況は突然全く変わってしまった。サンサンと晴れた日の午後、経理室に居たザトウクジラは床をカツカツ鳴らすヒールの音に慄き、その足音が近づく度に血まみれの未来が迫ってきているかのように感じていた。彼は高利貸しの極道がやってきたのだと思って、スーツの下に短刀を一本隠して経理室から走り出た。
しかし、ス・オンギという女性はただ一枚、数字の書かれていない小切手を手渡した。「アンタが破産してるのは知ってるわ。一度だけチャンスをあげる。コレにアンタが好きな数字を書いて、私が満足したら、アンタのクラブを買ってあげるわよ」
ザトウクジラはそんな取引の仕方を聞いたこともなかった。まるで高みから見下されているような殺気凛然、オブラートも無しにお前は生贄の仔羊だとでも言わんばかりだったが、彼に拒否権はなかった。
彼は再三考え、それ以上何か聞く事も無く、怯えながら自分が合理的だと思った数字を書き入れて、小切手をス・オンギに返した。ス・オンギはそれを一瞥すると、ザトウクジラが書き入れた数字の後ろにゼロを一つ追加し、小切手をザトウクジラに返した。それを見ていた酒徳麻衣という女性は微笑み、謙虚なのね、と笑った。出自不明の二人の女性はこの破産したナイトクラブを120億円で瞬く間に即決してしまった。これだけの金額があればヨーロッパのサッカーチームを一つ買う事だって出来てしまう。
その日の夕方、借金取り極道が門の前に現れた。ザトウクジラは銭箱の上に座り、高天原の門の前に銀行の現金輸送車を停めさせて待っていた。取り立ての代わりにナイトクラブから値打ち物を差し押さえるつもりで来た極道たちは、その光景を見て口をあんぐり開けてしまった。
「俺の心は死んでいない。俺の花道も、途絶えないのさ」ザトウクジラはクールな仕草でタバコに火をつけ、女々しくも雅な姿で手を振った。体重120キロ超の藤原勘助が二箱の現金箱を持って招かれざるお客に押し付け、極道たちは失禁寸前になった。
その日のうちにザトウクジラは新宿での名を更に上げた。同業者クラブのホスト達も、ザトウクジラが一体どこでこんな大金を集めたのか不思議に思いながらも祝いにやって来た。ザトウクジラは相も変わらず「愛の土に根がある限り、花は再び咲くのさ」などと、雲に巻くような言い回しをしてゲスト達を見送った。
新オーナーはこの取引を公表しないように要求し、ザトウクジラも新オーナーの背景を詮索しないという認識を得た。もっとも実際には詮索できないというのが真実だ。これだけの大金を持っている人間なら、身分など隠そうと思えば簡単なのだから。
だが詮索できないというのは推測できないということではない。ザトウクジラは二人の若い女性がなぜホストクラブなど買ったのか考えてみた。少なくとも二人のうち一人、ス・オンギと呼ばれていた女性は明らかに金融領域のエキスパートだ。彼女が数秒で導き出した高天原の損失額は、ザトウクジラが会計士に依頼して計算してもらった損失額と殆ど同じだった。しかしそれこそが疑問になる。わざわざゼロを一つ足した値段で高天原を買うなど不合理だと知っておいて、一体何故? ス・オンギと酒徳麻衣の醸し出すオーラ、彼女達の年齢……ザトウクジラは、彼女達はどこか由緒正しい家柄の出身なのだと推測した。しかし、一体どこの富豪の女がホストクラブなど買うのだ?
唯一の答えは――極道! 彼女達は極道ファミリーの女継承者なのだ。ホスト産業を征服する為に、巨額の資金を投入しているのだ!
新宿のあらゆる産業の中でも、ホストクラブには極道の介入が少ない。女と酒を飲むナイトクラブは保護費を支払うだけでなく、極道の株式保有も受け入れ、時折選りすぐりの女を極道の玩具として捧げる必要もあるが、男と酒を飲むナイトクラブ、つまりホストクラブには、極道もつい最近保護費を徴収するようになっただけである……極道の幹部たちが今までホストに興味を示さなかったからだ。だが極道ファミリーが継承者に女性を選んだとすれば? 彼女達からすれば、ホストクラブとはすなわちハーレム! モデル会社が極道幹部のハーレムであるのと同じことである。
それからザトウクジラは二日間ほど落ち着かなった。二人の女王の内、どちらが先に、どのホストに手を出すのか分からないが、誰が彼女達の手に落ちるとしても……多分、そのホストは幸せだろうが、しかし……。
だがその後はよく分からない展開になった。二人の女王はザトウクジラの大切な若いホスト達に手出しするかわりに、突然夜に広告車を出すよう命じたのだ。店員たちは新宿の外れの交差点などに配置され、女王達が探し求める人間を待ち伏せた。シーザーは自分がどの道を行っているのかも分からず、高天原の広告車に拾われたのも偶然だと思っていた。しかし高天原の広告戦略を見れば一目瞭然、一度に三十台の全く同じ広告車が出動させられ、新宿へ続くあらゆる道でクーポン券が配られており、どの道を行こうともその内の一つにぶつかるようになっていた。さらにこの三十台の広告車はオロチ八家の捜索網と連動するように動く。三人が千鶴町に着いたその時から、ホストクラブの網はすでに投げられていたのだ。
ザトウクジラは自分の推測が間違っていたらしいことを理解した。女王二人はホストを求めて意中の店を買ったのではなく、自分が望む男を捧げるためにクラブを買ったのだ。いわば年配の金持ちが突然制作会社を買収し、特定の女優を祭り上げようとするようなものだ。
少年達は八方塞がりな感じで極道に追われ、取り込むのにもちょうどいいタイミングだったようだ。その上彼らは自分が女王達の罠にはまったことにも気付いていない。これはいわば家畜化のプロセスだ。彼女達は金を使って挑発し、欲まみれの環境で堕落させ、最後に報いを要求する。新人の雛たちは女王の腕に抱かれて泣き、人生を懸けて彼女に侍ることを約束する……果たしてホストは魔女の支配から逃れる事なく、美少年達の青春は墓の中までお預けされる……Basara King、橘右京、Sakura、彼らを犠牲にしてクラブを救うというのは、ザトウクジラにとっても不道徳と思える。だがそれ以外に彼に何ができる? 男の花道を続けるためには、仕方のないことだ。
彼は自分の禿げ頭を叩いて、ため息をついた。
夜は更に深くなっていくが、シャンパンパーティはまだ続いていた。ロ・メイヒは地下鉄二駅ほど向こうの源氏重工ビルを眺めながら、一人でテラスに立っていた。あそこにある醒神寺でサシミを食べていたあの夜を思い出すと、源稚生が日焼け止めを売りたいとか言っていたのは本気なのかもしれないとも思えた。だが自分たちを海溝の奥底に見捨てたのは、当主の権力を捨ててでも日焼け止めを売りたかったあの男だ……世界はあまりにも複雑だ。複雑すぎるこの世界は、自分のような衰れな子供の目には見通せない。
ロ・メイヒはテラスの床に座ると、叔父の家の屋根に座っているような感じを覚えた。
その後長い年月が経って、龍殺しの大学に進学して、世界最強のハンサムや金持ちと出会い、何度も死の縁に立たされて……それでも未だに、自分という存在がこの世界にどう関係しているのかは分からない。周りの人間は大人ばかり、自分だけが子供のまま、皆の後ろをつまづきよろめきながらついて行き、皆の言う事を学び、皆のやる事をやってみせるが、永遠にその動きは半拍遅れたまま。自分が追い付こうとすれば、皆はすでにその向こうにいる。
腰から「グェー」という声が聞こえて、ロ・メイヒは一瞬驚いた。手を伸ばしてポケットから取り出したのは、黄色いゴム製のアヒルだった。海の中の最後の記憶はこのゴム製アヒルと、アヒルの向こうに居た少女だ。彼女の暗紅色の髪が海の中で浮き広がり、潜水ヘルメットのライトが彼女の顔を照らし……海は漆黒一辺倒、彼女だけが光り輝き……本当にノノのようだった。現実のノノではない、ロ・メイヒの記憶の中に居るノノ……降臨する度、天使のように見える彼女。
その時、ロ・メイヒは本当に自分は死ぬのだと思っていた。目の前の少女も瀕死の幻覚だろうと思ったが、それでも、必死に幻覚に向かって泳がずにはいられなかった。
人は何かを抱きしめてはじめて己の存在を知るのだ。たとえそれがただの幻影であろうと。
彼が浜辺で目覚めた時、小さなゴム製アヒルは彼の手に握られてグワァと鳴いた。すると海底の幻覚が現実になった。ノノに似た少女が自分を助け、潜水ヘルメットと小さなゴム製アヒルを渡してくれた。しかし、その時の自分はただのバカにしか見えなかったんじゃないか? 初めて会った少女、名前も呼び名も知らない女の子を、自分は熊のように抱き締めるしかなかった……緊張に涙を流しながら。
店長の質問に答える時も彼に嘘はなかった。口ごもってしまったのは、しばらく適切な表現が見つからなかったからだ。悔いのない恋だとか、彼の記憶の中にそんなものはなく……それらしいものがあるとすれば、あの時、ダイビングスーツを脱いだノノが泳ぎ出した時だ。微笑みながら彼にダイビングスーツを着させていると、その背後に突然龍の黒い影が現れてきて……。それは、二人が人生の中で最も近い場所に居た瞬間だった。ロ・メイヒは泣き喚いて彼女を抱きしめたいと思った一方、そんな資格は無いとも理解していた。自分はただの姉貴の子分、死の狭間にある彼女に泣いてやれる資格があるとでも? 死の淵で抱きしめてやる資格があるとでも? だからこそ、彼はただノノに全てされるがまま、潜水鍾に押し込められるまでの一切をぼんやりとみていただけだった……そこには後悔もなければ、愛らしい愛もない。
しかしこれが悔いのない愛の物語だとしたら? その時物語は最高潮に達し、決意と勇気の魅せ所、彼は荒々しく小さな魔女の腕を掴み、告白に変えて激しくキスをする。水中にいる彼らには語る術なく、必要もなく。彼はノノの両手を反して彼女を潜水鍾に押し込め、彼女にどう抵抗されようとも、代わりにノートンに刺されて、潜水鍾でノノを水面に送り出すのだ。この物語なら小悪魔の提供する超能力も必要ない。そも、愛には超能力など必要ない。ただ、決意と勇気とだけがあればいいのだ。ノノの愛だってシーザーが銃を撃って階下に飛び降りた時に起きた恋だ。ロ・メイヒも、未来がどうなるとか足が折れそうとか考えなければ、あの少女の愛を一身に受けるチャンスだったのだ。
自分の委縮が自分自身の人生を退縮させる。こんな自分が時々、本当に嫌になってしまう。
彼がふと絞ったゴム製アヒルはグァーグァーと、彼を嘲笑うかのように鳴いた。
