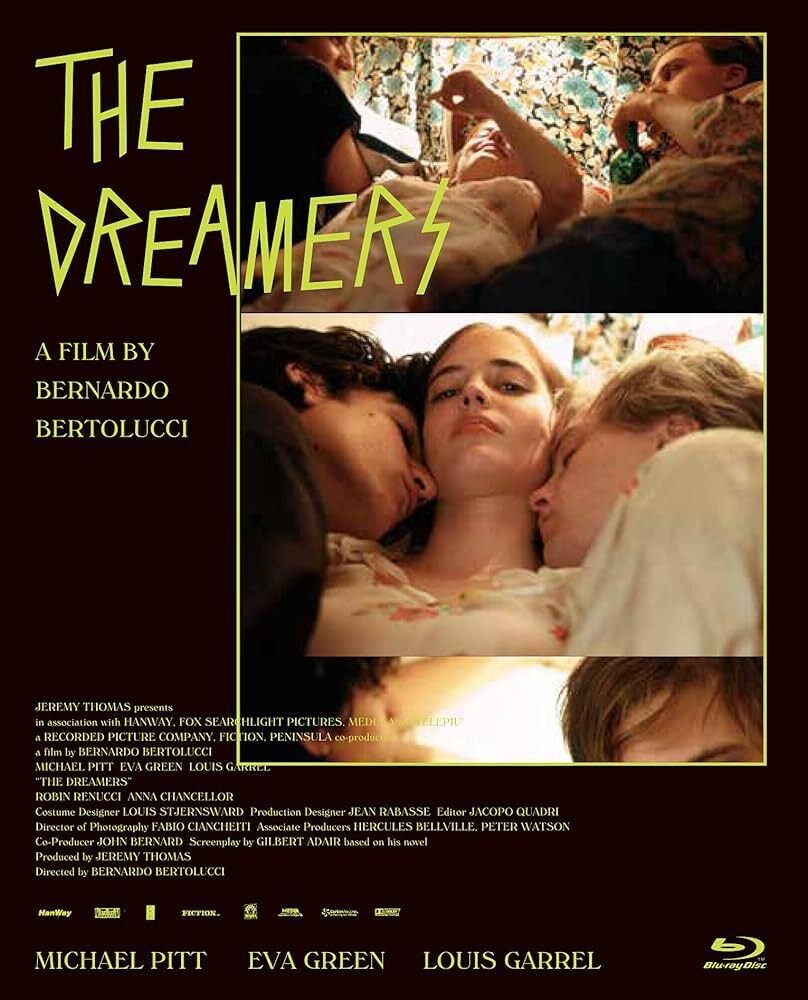新文芸坐xオノセイゲンx『フィシスの波文』
☆プロローグ
池袋にある新文芸坐のリニューアルの報が流れたのは2022年の春。例えばこういうのね。
ぜひ観に行こうとは思っていたのだが、観たい映画とタイミングが合わなかったのと、そんなに期待できるものでもないかもなどと疑っていたのもあって、時は流れて、今になった。
新文芸坐は「ラグジュアリーなオーディオルーム」をイメージした、オノセイゲン氏をフィーチャーした「オーディオルーム新文芸坐」という企画をやっており、今回、監督/撮影/編集・茂木綾子、また、製作・河合早苗、音響・ウエヤマトモコの女3人で各地でロケをして撮りあげた『フィシスの波文』(2023)を観ることにした。
まず、新文芸坐のリニューアルには興味を割と長く抱いていたので、リニューアルにともなってどういう変更がなされていたのかを振り返る。次に、『フィシスの波文』の映画評。最後に、映画館とオノセイゲン氏による音響の調整についての寸評。
☆名画座系初4Kのプロジェクター
リニューアルした新文芸坐のXにおける告知で、ゴッドファーザー3作を上映するにあたり、4Kレーザ-用に採用したクリスティ社のプロジェクターのコントラスト比は「5000:1」であり、ハイコントラストな映像を実現するから、「黒の締まりを是非体験して下さい」としている。ホンマかいなと思った。実際にクリスティ社が示しているCP4430-RGBのスペックを見てみると、確かに「コントラスト比は最大で6000:1」となっていた。ホンマなんですね。。。私のJVCのネイティブコントラスト比は160000:1。民生機はとっくに「プロ用」を追い抜いているのは認知していたけど、ここまでとは。。。ホンマかいな。
☆名画座系初4Kのスクリーン
「スクリーンは、セバートソン社製のパーフォレーション(穴)のないスクリーン「SAT-4K」を導入。音の透過率が良く、きめ細やかな映像を楽しむことができる」と、映画.comの記事は書いてある。多くの映画館のスクリーンに穴が空いているのはご存知だろうか。スクリーンの裏側にはLCR(左チャンとセンターと右チャンのことね)のスピーカーがあるので、その音を無数の穴から「透過」させて、観客は映画の音の大部分を享受しているのである。こういう透過型のスクリーンを特にサウンドスクリーンという。ところで、穴が空いていないのであれば、音の透過率が高いというのはありえないと思うのであるが、、、
映画は、音楽同様に、モノラル1chから始まった。この1chとはC(センタースピーカー)のことである。音楽は今でも1chに拘る人もいるにはいるが、60年代には2chステレオに移行した。映画館が構造的に変わらないのであれば、映画は相変わらずセンタースピーカーという昔からの呪縛から解放されず、大切な映像を穴の空いたスクリーンに投影するという妥協をせざるを得ない。私のホームシアターのスクリーンは真珠のランダムな粉末を手塗りしたもので、裏張りまであるので、穴など1つもないので、光も透過しないが、音を透過することもない。そりゃそうだよ。投射光を反射してこそ画が結ばれるのだから。
スクリーンに穴があいていないならば、樋口泰人氏の「爆音映画祭」のように外付けのスピーカーを用意しないと、既存の映画館のスピーカーセッティングではLCRの音が籠って迫力がなくなるということになるのではないか。
☆音響装置

7chの中域、低域用ドライバーは全て15インチ、 0.1chの4台あるサブウーファーは全て18インチに揃えたそうである。高域は大型のホーンであるとのこと。ホーンって映画館みたいなリスナーがどこに座るか分からない空間に本当に適切であるのかは知らない。

☆セイゲン・オノ・プレゼンツ
このような内容のリニューアルを敢行した新文芸坐は2023年の春に新しい企画を打つ。長い音響エンジニアとしてのキャリアをもち、自らも曲を作り、エレキギターを演奏するオノセイゲン氏をフィーチャーしたのである。
「目指すはラグジュアリーなオーディオルーム。」をテーマに、今年4月から開催されている東京・池袋の新文芸坐で世界的音響エンジニア、オノ セイゲンさんによるプログラム「Seigen Ono presents オーディオルーム新文芸坐」。
セイゲンさんは日本でちゃんと映画を観たい人には大切な仕事をしている人。フェリーニやヴェンダースのものを合わせると、私の家にもセイゲンさんの手がけた映画作品は20本はある。また、あまり皆さんは聴かないし、知らないかもしれないが、セイゲン氏は他人の映画や楽曲に携わる以外にも、自身の音楽活動をしている。私もSACDを4枚持っている。一番好きなのはこれ!
サラウンドで爆音にして聴いてください。ブルーノート東京が出現する。センターに並んだ金管がエロい。ライブに行きたかったなぁ~、なんて感じないくらい立派なマイキングとエンジニアリングで、暗騒音をライブ感に変えており、妖艶さのなかに没入する。格好いいよ~、このSACDのサラウンド。
今回、新文芸坐に行くとセイゲンさんがカウンターの奥にいたので、あつかましく声をかけた。音楽の話をしていると、本当に嬉しそうな顔をしていた。「自分の作品をやってください」と私が偉そうにいうと、少し顔が陰った。事情があるのかもしれない。でもやってほしい。マルチチャンネルサラウンドをやらない人には何の話か分からないだろうが、「センター使っているんですか?」と聞くと、「もちろん使っている!」と。「今回の(『フィシスの波文』)はあまり入っていないけどね」と。DSDでやるんならセンターchを使わないでほしいです。映画ソフトもいらない。Zガンダムのnew translationのUHDがありますけど、あれ4.1chです。センターなしでも、アニメらしいスプリットスクリーンでのセリフだって、ばっちりばちばちに動的に定位しますし、Cって固くてダイナミズムがないから。。。などと、イイタイコト、ツタエタイコトはたくさんあった。セイゲンさんは気さくに上映後の打ち上げに「来なよ」と誘ってくれるフレンドリーなお方だったが、身重の連れがいたので遠慮した。皆さんも、セイゲンさんの手がけた映画はもちろんですが、彼の音楽を聴いてください。一言でいうとノイズ系です。

☆映画評:『フィシスの波文』
監督に直接尋ねたのだが、デジタル撮影である。素晴らしいショットである。特に湿度を捉えた一連のショット、野の花や茶室での湯気。採光が素晴らしいんだろうね。後半はちょっと失速したか。アイヌの集落とか雪の乱反射のなかでどうかなと思った。京都でのショットが一番良かったし、京都で丹念にやればよかったのじゃないか。
ところで、そのモチーフが月並みなのは、差異よりも同一性を求め過ぎる脚本とカットが早すぎる編集のせいである。このドキュメンタリーが《文様》を探求するものであるならば、クリシェはクリシェであるという月並みさを耐え忍ばねばならない。それに耐えられずに、クリシェとしての《文様》はある深い次元においては同一の意味に帰着するという類いの脚本になってしまっているので、《文様》の表層に滞留できない。ロングテイクで踏みとどまらないと、《文様》を鑑賞者の網膜に刻印できないのに、カットしてしまい、《文様》を語りながら《文様》の彼方という《文様》ではないものへと向かってしまう。脚本と編集がショットの威力を削いでいるのである。
タルコフスキーの『アンドレイ・ルブリョフ』(1966)のラストシーンはアンドレイ・ルブリョフのタブローの超クロースアップのロングテイクである。超クロースアップなので、それは絵画というよりも《文様》としての撮り方なのである。執拗に舐めるようにカメラをタブローの表面に這わせるので、それが何の絵なのか?や、何を意味しているのか?は、この映画のラストシーンでは与えられない。なぜなら、既に与えられているからだ。タルコフスキーの映画を注視する鑑賞者の精神の中に。そうした精神の中にアンドレイ・ルブリョフのタブローの《深い意味》を打ちたてるべく、タルコフスキーは超クロースアップのロングテイクで、ある絵画の「それは結局何なのか?」が分からないようなショットをラストに配置するのである。

こうしたタルコフスキーという偉大な映像作家の芸術に接近するチャンスが、本作『フィシスの波文』にもあったのだが、異なるものの同一性を安易に想定する脚本と文様としての文様に留まれない編集こそが、奥深いものの達成を阻んでいる。率直にいって、「京都に400年受け継がれる唐紙文様を《起点に》」などというのは戯言である。400年という代物を起点にして、別のものへと移り変わっていくことが本当に可能であるのか?性急にも大局的視座を得ようとして、真摯に事物を見つめる代わりに、自分の想念を歴史的な文様や自然の形象に仮託してオリジナルであろうとしている。こういうのを我有化appropriationであると、中沢新一は言わないのであろうか。
☆新文芸坐で視聴してみた感想
ブーミングはまったくなかった。嫌な音が出ていないのは、さすがにセイゲンさんが調整しただけのことはある。いいかがげんな調整で金を取る劇場が多すぎるのだ。上に書いたように、セイゲンさんによればセンターの音はこの映画にはあまり使われていない、とのことであるが、新文芸坐のスクリーンに穴が空いていないのであれば、この映画のサウンドと新文芸坐のサウンドシステムはフィットしていたのだと思う。
上映後のトークショーで製作の河合早苗さんは「他の劇場で聴こえなかった音がいっぱい聴こえた。セイゲンさん、ありがとうございます。」とコメントしていたが、他の劇場ではなく、他の映画作品と比べると、どうなのだろうか?

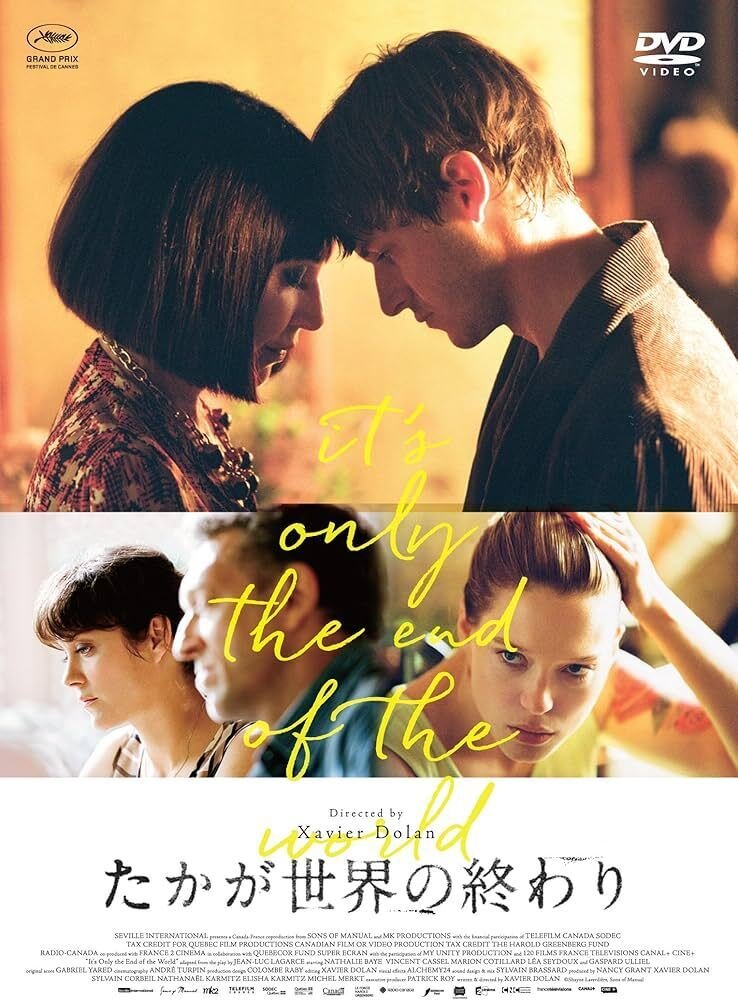
一緒にいった嫁に音響はどう思ったかと尋ねると、「よく分からなかった。座席の背もたれが高くて、、、」と。全ての座席の背もたれが高いので、全周囲の音が遮蔽されて、音が来ない、ということである。私も同じことを感じた。さらに、中央少し前よりの席であったが、ちょっと仰角が厳しい。スクリーンが高すぎるのだ。だから、☆音響装置のところでふれた、高域用のホーンスピーカーはその高すぎのスクリーンの中央にいると思われる。そうすると新文芸坐は、①ホーンの位置が高く、②座席の背もたれが高い、となるので下からの音はほぼ無であり、頭の上を大事な音が通り過ぎていく、そんな聴感なのである。サウンドに関する話をまとめると、この劇場では音に関して、後ろ目の席でなんとか、こだわりの片りんを体感できるかもしれないが、基本的に聴きにくいということになる。
サウンドスクリーンに関しては、センターの音源が少なめというドキュメンタリーであったので、これまた、よく分からないが、悪くないのかもしれない。ぐっとは来ないが、悪くなかった。セイゲンさんが粗を上手く隠したからなのかもしれない。
画なのだが、上で書いたように、素晴らしかった。どこまで優秀なのか分からないが、大出力の業務用4Kレーザープロジェクターの光量を穴のあいていないスクリーンはしっかりと受け止めて、監督が狙った表現を達成していたのだと思う。デジタル撮影は自然光の透明感が、ビニールを通したような偽物の光沢になりがちなのだが、素晴らしかった。
しかし、首を痛くする仰角つきなので、サウンドのこともあわせて、この劇場は後ろ目の席がよろしい、ということになりそうだ。
私自身は後ろ目の席は好きでない。ベルトルッチは『ドリーマーズ』(2003)で、「スクリーンの光を一番最初に吸い込みたい」みたいなセリフを言わせて、端っこでも最前列に自分役の役者を座らせていた。一番最初に捉えた映写の光は清潔なのだ、とかなんとか言っていたような。まあ、色々な考え方はあるだろうが、端っこは違うのかなと。壁際の音は歪むし、映画館のスクリーンは広角なのであろうが、いくらなんでもね。