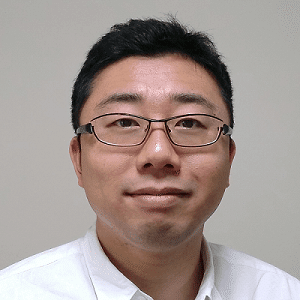第4回 「なぜ勉強しなくちゃならないの?」
こいけかずとし(フィロソフィア英語教室代表)

好きな科目ならともかく、好きではない科目をなぜ勉強しなくてはならないのでしょうか?
教室でも生徒から尋ねられることがあります。
結論から言うと根本的な理由は見つかりません。
勉強しない生き方を選択することも可能です。
しかし目的によっては勉強をする必要が出てきます。
だから勉強する理由はどのような目的をもつか、によって決まります。
つまり、「何のために生きるのか?」という問題を考える必要があるわけですね。
人生の意味
ここでV. E. フランクル(1905-1997)の実存分析の理論を紹介します。

フランクルはオーストリアの精神科医・心理学者です。
第二次世界大戦中、ユダヤ人という理由でナチスの強制収容所に収容されました。
かろうじて死を免れ、その体験を著書『夜と霧』に記しています。
フランクルは「人生の意味とは何か?」という問いに対して、万人に共通する一般的な答えは見つからないと言います。
人生の意味は人によって、および時によって異なるからです。
フランクルはこれをチェスにたとえます。
チェスでは「特定の場面に対する最善手」は存在しても、「あらゆる場面に当てはまる最善手」は存在しません。
人生の意味も同じです。
具体的な状況を離れて、抽象的な人生の意味を求めるべきではないのです。
人生のそれぞれの状況が人間に解くべき課題を投げかけます。
人間は人生の意味を問うべきではなく、むしろ問われているのは自分であると認識しなければなりません。
我々が問うのではなく、我々が人生によって問われているのです。
自分で答えを出すことでのみ、その答えを出すことができます。
いわば天動説から地動説へのような視点の転換が自分の人生の意味を見つけるためには必要なのです。

答えのない問い
フランクルは答えを出すのをひとりひとりにゆだねます。
ひとつの答えを出さないのはずるいと思うかもしれません。
学校教育ではほとんどの場合、問いに対して答えが用意されています。
しかし現実には答えのない問いはたくさんあります。
未知の事柄に向き合って答えを探る力を発達させるのは大変です。
学校では教えてくれませんし、そもそも教えられる性質のものではありません。
人に会う、本を読む、経験を積む、頭で考える、など方法はいろいろあります。
試行錯誤しながらその力を発達させると自分が勉強する理由も自然と見えてくるでしょう。
日本の教育では効率や協調性を優先する一方、主体性が軽視されがちです。
多人数の集団授業という性質を考えると仕方ないのかもしれません。
主体性にまかせると多くの学生はなまけて勉強しなくなる、という側面もあります。
ひとつ言いたいのは、主体的に勉強する場合は勉強する理由が問題になりません。
勉強する行為が「自己目的的活動」になるからですね。(第1回で紹介)
勉強に限らず何でもそうですが、活動を充実したものにするには主体性がキーワードです。
やりたくてやっていたら、なぜそれをするのかなんて考えませんからね。
余談ですが、禅問答にも似ている部分があります。
禅の師匠は修行中の弟子に公案という問いを出しますが決して答えは教えません。
弟子は師匠に認めてもらえるまで問いの答えを探し続けます。
これもまた教育や学習のひとつの形だと思います。

なぜ英語を勉強するのか
最後に私の個人的な考えを少しだけ。
英語を教える身として「なぜ英語を勉強するのか」についていつも意識しています。
大きくいえば「時代の流れ」です。
国際化の進展と英語圏の政治・経済・文化の影響力の強さが大きく影響しています。
小さくいえば「活躍の機会が増える」です。
仕事・研究・留学・旅行・受験など、英語ができると幅広いところで活躍の機会が増えます。
この2つが強いので、英語については勉強する理由を尋ねられても説明するのがわりと簡単です。
もちろん他にも「異文化に触れる」、「英語学習が楽しい」、「脳トレ」など理由はいろいろあります。
英語学習の道は無数にあります。
ぜひみなさんなりの英語道を見つけて頂ければ幸いです。
おまけ
実存分析(ロゴセラピー)に興味を持ったらフランクルの著書『夜と霧』もおすすめです。
一般の読者に向けて、具体例もいれてわかりやすく書かかれています。

ヴィクトール・E・フランクル(みすず書房)

Viktor E. Frankl
(朗読音声はaudible.comで購入可能;約5時間)
英語版の英語もそれほど難しくありません。
多読多聴で児童書のレベルをクリアして次の段階にステップアップしたい場合にちょうど良いでしょう。
こいけかずとし
東京大学仏文科卒。
フィロソフィア英語教室代表。
『マンガ こんなに効く!英語多読多聴マニュアル』(ベレ出版)
『英文が読めるようになる マンガ英文法教室』(ベレ出版)