
【無料で一気読み!】遠藤正二朗 完全新作連載小説「秘密結社をつくろう!」 ─無料版─
【New!】「ひみつく」初の単行本が発売されました!(2024/07/18)
鬼才・遠藤正二朗氏による完全新作連載小説「(略称)ひみつく」を無料でお届けしていきます!
「魔法の少女シルキーリップ」「Aランクサンダー」「マリカ 真実の世界」「ひみつ戦隊メタモルV」など、独特の世界観で手にした人の心に深い想いを刻んできた鬼才・遠藤正二朗氏による完全新作小説「秘密結社を作ろう!(※略称 : ひみつく)」。

2023年に連載開始した本作は、いよいよ重要なシーンへ突入していきます。2024年から毎週月曜と金曜に1章ずつを配信する一方、無料で読めるパートを大幅に拡大! 定期的に無料枠を追加していきます。
気になる続きは本編で最新話を公開していき、追いかけで順次無料枠を公開していきます。
底辺からの逆転人生を目指す男たちの戦いに注目!
ある日、手にした謎の「鍵」によって無敵の身体能力を手に入れた山田正一(やまだ まさかず・28歳)が、弁護士の伊達隼斗(だて はやと)と、その「力」を有効活用するべく立ち上がり、数奇な運命をたどります。

遠藤正二朗氏の描く波瀾万丈の物語をぜひみなさんもご覧ください!
【無料版】第1話 ─変身!正義のヒーローになろう! Chapter1
エプロンが波を打つ。小さく、時には大きく。それはそうだと納得できるほど、彼は落ち着きを取り戻そうとしていた。つい先ほどまで震えるほど怯え、落涙し、ショックで漏らしてしまうほどだったというのに。
建物の屋上で助走をつけ、走り幅跳びの要領で灯りの海を跳ぶ。すると、身に付けていた血まみれのエプロンが波を打つ。
段々とわかってきた。踏み込む力に対する跳躍の距離というものが。青年は、貴金属買い取り店の看板が設置された七階建ての屋上に降り立った。跳躍の頂点は10メートルほどで、本来なら無事では済まない落差である。しかし息は荒いものの、その身体はなにひとつ損傷を負っていなかった。
看板は四方を板で囲んだがらんどうであり、その中に降りてしまった青年はすっかり視界を塞がれてしまった。
天然パーマのちりちり頭を右手でひとかきした彼は、途方に暮れていた。周囲を見渡しても看板の裏側だ。こういった様式の看板の屋上に跳ぶのは避けなければ。彼は、かつて誰もしたことない禁止事項を自らに科した。
青年の左手には金庫が抱えられていた。大きさは1立方メートル足らずの金属製、それを片手で抱えられるほど身長170センチ足らずの彼は屈強な体格ではなかった。それでも自身の体重の数倍はあるはずの金庫を抱えたまま、彼は垂直に軽く跳ね、右手で看板の縁を掴むと次の屋上へと水平に跳んだ。
ここまではすぐ隣の屋上を目的地としていたが、強く踏み込めばもっと遠くへ跳ぶことができるはずだ。ならば、次は全力でやってみよう。幾度かの経験で、青年はそのような手応えを得ていた。このまま総武線沿いに東へと跳んでいけばいいはずだが、安心できる場所はまだまだ遠い。体力が持つのか不安だったが、そもそもこの奇妙な力の限界というものがわからない。だから彼は、ただ次の着地先を探すしかなかった。
奥平隆昌、二十三歳の彼は七人の同僚と共に、歓楽街である東京都新宿区歌舞伎町の街明かりに照らされていた。幹事を務めた五月の呑み会も無事に終えることができた。まだまだ呑み足りないこの七人と共に、二次会の店を探していた彼は適当な看板を求めて顔を上げた。
我が目を疑う。そんなことは大人になってからは経験したことがない。エプロン姿の青年が、大きく黒い塊を抱えて宙を舞っている。ああいったのはパルクールとかいう競技だったっだろうか。それにしてもおかしい。人はあんなに軽々と跳べるはずがない。見たままを自分の知っている理には当てはめられない。アルコールの影響で何かを見間違えたのだろうか。「奥平〜! 酔っ払ったんか?」わずか先を行く同僚たちがそう叫んできた。今夜は酒に強いところを見せてやる。そんな啖呵を切っていた彼だったから、慌てて七人の元に向けて駆け出した。目撃してしまった異常は頭の隅に追いやってしまおう。あれはどうでもいい、二軒目探しが大切だ。そのような結論に至った奥平隆昌だった。
夜の歌舞伎町で金庫を抱えたエプロン姿の青年が跳ぶ姿は、ゲームクリエイターとして新たな開発会社に転職したばかりだった町谷良子の目にも飛び込んできた。リビングのノートパソコンで彼女が見ていたのは動画配信サイトの、歌舞伎町の様子を定点カメラで映すライブカメラの映像だった。五月二十二日の午後十一時過ぎのことであった。巻き戻しができない動画だったため、もう一度確かめる術はなかったが、確かにカメラの対面にあるビルの屋上を跳ぶ何者かを見た。ゲームの中ならあり得るが、現実では辿りつけない跳躍距離である。既にカメラのフレームから消えてしまったのでその姿を追うことは叶わなかったが、配信動画の視聴者の中に同じ異常事態を目撃した者はいないだろうか、そう考えSNSで検索をしてみたところ、期待していた結果は得られなかった。そもそもこの動画自体、同時視聴者が六十人しかいなかったので、それなら自分が書き込もうかとも考えた。しかし本名のアカウントしかない上に証明しようのない目撃談を投稿したところで、明日にはスタジオのスタッフたちからからかわれるだけだ。それよりも優先するべきは、締め切りが迫っている新しい企画のプレゼン資料の仕上げである。モヤモヤとした気分のまま、町谷良子はブラウザを閉じた。
金庫を抱えた青年がこの夜スタート地点として跳んだのは、歌舞伎町にある五階建ての細長い雑居ビルだった。全ての階がひとつのフロアしかなく、最上階は『カルルス金融』という金融業社が賃貸契約を結んでいた。
入り口近く、そこから最も遠くの壁の傍、そして『社長』と書かれた札が置かれた机の下、そのそれぞれに男が倒れていた。いずれもが血の池の主となっていて、息をすることもなく彼らの時は永遠に止まっていた。
三揃いの灰色のスーツを着た青年が、ハンカチで壁を拭いていた。革手袋をした人差し指でときどき眼鏡を直しながら、机や床も熱心に、念入りに拭いていた。途中、倒れていた屍のひとつを跨ぐこともあったが別段気に留めることもなく、拭くことを続けた。
ここまで平然としていられるとは。血の臭気にも慣れてしまうとは。頬を赤く腫らした眼鏡の青年は、右手を熱心に動かしながらも自身の順応性の高さに感心してしまっていた。
これは彼にとって極めて重要な清掃だった。根こそぎ証拠を隠滅しなければ、今夜以上の絶望が訪れるだけである。ここで起きた凄惨な事案について、決して容疑の目を向けさせてはならない。三人の被害者の身元から考えると、当局の目はおそらくこいつらの同業他社か、自分もよく知る類似した稼業に向けられるとは思うが、手を抜くことは許されない。
最後に、床にあった血混じりの足あとを拭き取り、青年は作業を完了させた。ポケットからバイクのキーを取り出した彼は、それをじっと見つめた。「ヤマダ、マサカズといったな。アイツ、なんなんだ、一体」そう呟いたその口元は、ごくわずだが緩んでいた。
東京都の東の端、江戸川区の小岩駅から徒歩で東に二十分ほどの江戸川近くの住宅街の路地裏に、金庫を抱えた青年が舞い降りた。日付はとっくに変わってしまった深夜である。この不思議な力はここまで持ってくれた。そう安心した彼は『江戸リバーサイドハイツ』という三階建てのアパートの外付け階段を上っていった。三階の角の部屋に入り、抱えていた金庫を床に下ろすと、青年は敷きっぱなしだった布団に倒れ込んだ。すると、カチャリ、という小さな金属音が六畳のワンルームに鳴った。
「もうダメ。活動限界ってやつか。限界になると、鍵、勝手に外れんだ」
そう言うと、彼はデニムパンツのポケットからひとつの鍵を取り出した。それは、ロッカーなどで使われている様な小さくありふれたものだった。
「あのダテ先生って人、あのあとどうしたんだろう」
最後にそう呟くと、青年は鍵を握りしめたまま深い眠りに落ちた。
青年、山田正一にとって、この鍵こそが今夜の地獄から脱出できた唯一の手段であった。
【無料版】第1話 ─変身!正義のヒーローになろう! Chapter2
地獄としか言い様のなかったあの夜から六日前、東京都と千葉県を隔てる江戸川からほど近い草むらの中で、山田正一は呆然としていた。つい先ほどまであの川を潜っていたはずなのに、ちぢれ毛の髪や指先まで水滴ひとつ垂らしてはおらず、コミックのキャラクターがプリントされたTシャツやデニムパンツも乾いたままだった。
この三日間、毎日仕事を終えた夜、マサカズはある実験を続けていた。彼はポケットから南京錠を取り出すと、鍵を外した。
「すげぇ、水中戦もできんのかよ。無敵じゃん」
手にしていたロッカーキーは、この夜から四日前に突然、なんの前振りも心当たりもなくマサカズのポケットに入っていた。
バイト先のロッカーのそれと全く同じ形をしていたから、記憶にないうちにスペアを受け取ったのだろうか。それとも同僚の誰か、あるいは店長がいつの間にかポケットに入れたのだろうか。いずれにしても覚えというものが微塵もない。少しばかり気持ちが悪いが鍵があまりにも凡庸な見た目だったため、明日にでも職場で尋ねればいいだろう。アパートの自室でそんな答えに至ったマサカズは、スマートフォンで本日更新のウェブトゥーンを読むことにした。
翌日、マサカズはこの心当たりがない鍵が自分のロッカーのスペアキーなのかどうか試してみることにした。小岩駅構内のショッピングセンターの書店、『イマオカ書店』がマサカズの職場だった。アパートからは徒歩で二十分ほどで通勤の便もよかったのが応募の動機であり、採用され、アルバイト勤務を始めてから半年ほどが経っていた。
細長く狭いロッカールームまでやってきたマサカズは、昨日手に入れた鍵を自分のロッカーの鍵穴に差し込み、いつものようにそれを回してみた。九十度まで捻ったその瞬間、マサカズは全身にうっすらとした痺れを感じた。扉を引くと、鈍い摩擦音と共に勢い良く開いた。
違う、鍵が適して開いたのではない。強引に、力尽くで扉は開いてしまったのだ。ロッカーを閉ざしていた金具の部分がぐにゃりと変形していたので、マサカズはそう理解した。気がつけば腕に力が漲っている。この腕力でロッカーの扉を壊してしまったのか。もちろん、そのような怪力が自分にあるはずもない。鍵を回したそのときから、不可能を可能にできる力が備わった。そうとしか考えられない。急な異常事態にマサカズは恐れをなしつつ鍵を引き抜いてみると、今度はすっと身体中に寒気が走った。何やら力の滾りが消えてしまったようでもある。
もう一度、鍵を扉の鍵穴に差し込んで回してみると、再び痺れが走った。両腕両足、胸や背中までも波打つように震える。これはひょっとすると増しているのは腕力だけではないかもしれない。
そして再び抜いてみる。またもやひんやりとして震えが止まる。これはつまり、ビデオゲームの操作の様に、自分の意思で現象のオンオフを切り換えられるのではないだろうか。段々と面白く思えてきたマサカズが何度か鍵を抜き差ししていると、「山田さん。おはようございます」と背中から声をかけられた。彼は抜いた鍵をポケットに入れ、振り返った。挨拶をしてきたのは七浦葵という、ショートカットで眼鏡を掛けた小柄な女性だった。彼女は三ヶ月前に入店したマサカズとは八歳年下の、今年二十歳になる新人のアルバイト店員だった。
「おはようございます、七浦さん。まいったよ。ロッカーさ、鍵壊れててさ」
壊れた扉を開け閉めして、マサカズは苦笑いを浮かべた。
「古いですものね、それ。店長に報告ですね」
「あ、ちなみに僕が壊したわけじゃないよ。たぶん」
「たぶんって?」
「あ、いや、どうなんだろう」
後輩ととりとめのないやりとりをしながらもマサカズは興奮していた。この鍵をきっかけとして自らにもたらされた現象をもっと試してみたい。結果しだいではできることの可能性も広がり、何よりも面白そうで仕方がない。
マサカズの前で、七浦葵は不思議そうに小首を傾げていた。仕事の覚えが遅く、店長に叱られることが多いため何かと自分を頼ってくれる、この小さな後輩とのやりとりはそれなりに楽しかった。しかし彼女には既に彼氏がいるらしく、関係性の進展は望めそうにない。それより、今は鍵だ。マサカズはポケットに手を突っ込み、小さなそれを握りしめた。
まず解明するべきは、このロッカーキーの正体である。実際のところ鍵を捻っても金具が動く音もせず、扉は力任せに壊れる形で開いてしまっただけだ。となると、これ自体はあのロッカーに適した鍵ではなかったわけである。しかし適合しない鍵など、そもそも差し込むことが自体ができなかったはずだ。なのに捻ることまでできてしまった。そうなると、そもそもこれが鍵なのかどうかも怪しい。仕事をこなしつつ、マサカズはポケットに入れた不可思議な存在のことばかりを考えていた。
その日の仕事を夜に終え、自宅アパートまで帰ってきたマサカズは、例の鍵をアパートの自室の鍵穴に差し込み、それを回してみた。すると、職場のバックヤードで感じた、あの痺れから始まる全身への滾りが確かに認められた。
「カギ穴ならなんでもいいんかーい!」
鍵を抜いたマサカズはそう小さく、嬉しそうに呟いた。
その翌日の夜から、マサカズはこの説明ができない機能を持った鍵とそれが生じさせる力について、実験をしてみることにした。まずはいつでも試したいという理由から、近所の金物屋で南京錠を購入した。鍵穴はわずかに小さかったものの、驚くほどすんなりと差し込められ、あの現象が発生した。そこからは何ができるのか、どこが限界なのかの見極めである。
どうやら、尋常ではない腕力と脚力が身についたのはわかった。腕力は駐車していた大型トラックが垂直になってしまうほど持ち上げることができ、脚力は一度の跳躍で江戸川を東京側から千葉側の河原にまで達するほどだった。破壊力については家にあったダンベルで試してみることにした。金属製のそれを握りつぶし、拳で折れ曲げさせると、購入してから五年の間ほとんど使っていない変わり果てたトレーニング器具に、彼は少しばかり申し訳ない気持ちを抱いてしまった。痛みを耐える力に対しても試してみようとも考えたが、こればかりはいい方法が思いつかなかった。試しに自分で自分を殴ってみたが、これはいつも通りの痛みがあった。腕力自体は上がっているはずなので防ぐ力も向上しているようには思えるが、外部からの暴力を確実に試す手段は見つからなかった。
そして三日目のこの夜は、江戸川での水中実験だった。十分ほど川の中で過ごしたのだが、驚くべき事に水中であるのにもかかわらず呼吸ができ、濡れることもなかった。つまり、この力は目に見えないなにかを纏っているということになる。おそらくだが、火の中や煙の中でも平気だろう。
わずかな実験期間の中で、鍵の力のデメリットも判明していた。力を使ったのち、鍵を抜くとひどい疲れが生じることである。疲労の度合いは実験中の運動量や体調にも比例していて、昨日の脚力実験では風邪気味のなか河原で全力疾走したり、江戸川越えの跳躍を繰り返したりしたところ、突然目眩を覚え草むらに倒れ込み気を失ってしまった。巡回中の警官に起こされ、朝日のもと着の身着のままバイト先に向かったのは今朝のことであり、後輩の七浦葵に遅刻をからかわれてしまった。
三日間に渡る実験で、マサカズはこれ以上力の研究をするのは難しいと感じ始めていた。夜な夜なダンベル相手に暴力を振るったり、江戸川を跳んだり潜ったりなどといった奇行めいた行為は自室や人気のない深夜を狙って行ってきたが、昨日の警官の件もある。試すことを繰り返すうちにいずれは誰かに目撃され、最悪の場合動画配信で晒される可能性さえもある。鍵の力はまだ天井を見せてはいないように思えるため興味はあるのだが、ひとまずここで止めておこう。
大前提として、鍵の力は自分だけの秘密にしておきたかった。他人に知られれば政府に通報され、よくわからないが何らかの公的機関に取り上げられる。そして自分自身もどこかの研究機関に送られ、人体実験をされる恐れもある。なんの根拠もなく漠然とはしていたが、秘密の公開は恐ろしい結果しかもたらさないような気がする。ともかく、鍵の力でできることはなんとなくだが判明した。今夜の晩飯はコンビニで買っていこう。背を丸めて江戸川の河原を歩きながら、マサカズはスマートフォンで電子マネーの残高を確かめた。
鍵の力はある程度理解できた。そうなると、次はその使い道である。この力はダンベルを握りつぶし、一級河川も軽々と跳べる。少年漫画に登場するヒーローキャラクターで言えば、いわゆる近接パワー型と定義してもいいだろう。能力を使ったあとの疲労が弱点だが、それもヒーローらしくてそれっぽい。注意していればカバーできるだろう。これで人助けでもして稼げる手段はないだろうか。書店での仕事をこなしながら、マサカズは力の使い道について考え続けていた。
ところが、いくら考えても思いつかなかい。難しいのは秘密を保ったまま、という点である。稼ぐという意味において手っ取り早く考えるのなら、犯罪行為への利用が近道だ。
例えば強盗だ。夜に宝石店に乱入して貴金属を根こそぎ奪っていく……で、そこからどうする? 貴金属を転売する? お店で? ネットで? いやいやそれ以前だ。そもそもなんで強盗なんてしないといけない? 我ながらあまりにもひどい選択肢だ。新刊漫画の単行本を空いた本棚に入れながら、マサカズは首を振った。違う、今でも普通に生きていけるんだ。犯罪者になんかなりたくない。力がもたらす誘惑をすぐさま拒絶したマサカズだった。
週末の夜、マサカズは新宿の歌舞伎町を訪れていた。この、なんとなく悪そうな連中がはびこっていそうな街で力の使い道が見つけられないだろうか。多くの人々が行き交う賑わいの中、彼はそんな淡い期待を高めていた。
ここは歌舞伎町でも特に治安が悪いと報じられている、シネコンが入ったビルを中心とした界隈だ。ここで事件が起きる様な気がする。確かネットのニュースでもいくつかの事件を見た覚えがあるし、ここを舞台のモデルにしたヤクザたちの抗争を描いたビデオゲームがあったような記憶もある。人助けや強盗の阻止に鍵の力を極秘のうちに使えれば、人を悲しませずに済ませられる。街の治安を守ることは力の使い道としてとてもふさわしい。
例えばこうだ。女の子とかが悪い大人に乱暴されそうになる。事情はわからないが。それをバレないように注意して鍵で助ける。女の子はとても感謝する。そしてその子にこう告げる、「キミみたいな若くて可愛い子がこんな危ない街にいちゃあいけない。早く家に帰ってご両親を安心させなさい」と。すると女の子は突然泣き出す。
「帰る家なんてないんですぅ! あんな家! あんな親!」
「おやおや、どうやらワケありってやつか? なら、僕のところにこないか? 狭いワンルームだけど」
「いいんですかぁ!?」
「もちろん、だって、可哀想な子を放っておくなんてできないだろう」
「行きます、行きます! 転がり込みまーすぅ!」
「よし、そうと決まったら、まずは涙をお拭き」
我ながら不毛なシナリオだと思いながら、マサカズはうつつを抜かしていた。すると、右の手首を唐突に掴まれた。彼は反射的に身を引いた。
「…………」
手首を掴んだまま、ひとりの少女がマサカズを睨みつけていた。歳はおそらくは十代、ピンクのブラウスにミニスカート、リュックを背負っていて年相応の可愛らしい身なりだが、何か違和感がある。その正体をマサカズはすぐに察した。着ている全ての衣類が薄汚れているのだ。遠目では気づかないが、ここまで近くだとよくわかるし、何やら嗅覚を刺激する生々しく嫌な臭いもする。自分にも覚えがある、これは一週間以上風呂に入っていない体臭というやつだ。無職時代に経験がある。
マサカズは突然の予期せぬ事態に怯え、恐る恐る「は、離して」と要求してみたところ少女は手を離した。
「プチ八千、ゴあり一万五千」
呪文のような言葉を、少女は嬉しそうな様子でマサカズに放った。言葉の意味はわからないが聞き返す勇気も湧いてこないほど、少女の態度は堂々として一方的に感じられた。手首が自由になったマサカズは引き攣った硬い笑み浮かべると、対する少女はため息を漏らした。
「選り好み?」
「は、はい?」
戸惑ったままのマサカズに、少女は彼の向こう脛を軽く蹴った。
「あんな、お前結構イケメンだから、こんなん突っ立てたらウチ的なのぎゃんぎゃん寄ってくるよ。やる気ナシって迷惑なんですけど」
そう言い捨てると、少女はマサカズの前から立ち去り、千鳥足の若いサラリーマンに駆け寄っていった。
恐らくだが、ここで鍵の使い道は見つけられない。見知らぬ少女から得体の知れないやりとりを持ちかけられ、それに圧される様な未熟な自分では、この街に巣くっていてくれるはずの悪に辿り着くことなど不可能だ。そう思い至ったマサカズは、困惑のまま新宿駅に引き返した。
【無料版】第1話 ─変身!正義のヒーローになろう! Chapter3
歌舞伎町での活躍を断念して二日経った月曜日、マサカズはいつものように書店でのアルバイトに励んでいた。超人的な力を得ても日銭を稼がなければ、アパートの家賃も支払えず食っていけない。結局のところ、現状とは偶然拳銃を手に入れたようなものであり、それは使い道に困る力でしかなかった。
バックヤードで午後の休憩をとっていたマサカズは、店長に呼び出され事務室までやってきた。
「山田君、あんまり待たせるのはね、よくないよね」
椅子に座る店長の小坂は三十代半ばの男性で、マサカズにとっては少々小言の多い苦手な相手だった。休憩中の呼び出しにも関わらず、ひと言目がこちらへの不満というのもいささか腹立たしく思える。マサカズは「はぁ」と力なく返事ともつかない声を上げた。
「あのね、本社からね、秋にね、山田君を正社員にね、迎えるのを検討してるって連絡があったんだ」
告げられた内容に、マサカズは少しばかり驚かされてしまった。
「正社員? 僕が?」
「君のね、あのね、“店員さんのオススメ漫画”の売り上げがいいし、実際そのあと“書店大賞”とか、“このコミックがすごい!”とかにもノミネートされてるし、先見の明? わかんないけどおかげで売り上げいいしね。あとあと、こないだ君が出してくれた、クリーンワーク提案も本社から評価されてね。これで納得?」
たたみ掛けるような店長の説明に、マサカズは戸惑ってしまった。『店員さんのオススメ漫画』とは、マサカズたち店員が推奨する漫画を、特設したコーナー配置するというもので、漫画を愛好するマサカズにとってその目利き発揮する機会でもあった。そしてクリーンワーク提案とは、このイマオカ書店を経営している本社がアルバイトも含めた従業員たちに募集した、今後の働き方への意見や提案である。マサカズが応募した提案の内容とはパワハラやモラハラの根絶、労働の従事者のメンタルや体調をできるだけ考慮する、といった実にありふれたものであった。
「今とどう違うんです? 正社員になると」
「あれ? 山田君って過去イチ正規雇用経験なかったっけ?」
「ええ、ですけど、一応」
「雇用期間が無期になるし、月給になるしボーナスも出るし、社会保障ももっと良くなるし、いいこと尽くめだね」
ようやく驚きや戸惑いが消え去ったマサカズは、深々と頭を下げ、「あ、ありがとうございます」と礼を言った。
「まだ正式決定じゃないけどね、山田君ぼちぼち契約切れるしね。正社員になりたいなら、一応契約継続してくれない?」
「もちろんです!」
これまでの働きぶりや、積極的な姿勢が認められたということか。推薦漫画の精度が高いのは最新の漫画に精通しているからであり、そもそも採用の決め手ではあった。正直なところそれら新作は違法アップロードサイトを通じて読んでいたため、人に誇れるような知識やセンスではない。正社員になって生活が安定してからは正規のルートで漫画を購入して償っていこう。そんな身勝手な贖罪をマサカズは誓った。
「山田さん、正社員になるんですって?」
再び休憩室に戻ったマサカズは、同じく休憩に入っていた後輩の七浦葵から声をかけられた。
ソファに腰掛けたマサカズは、テーブルの上にあった梅味のキャンディを手に取ると、それを口にした。
「山田さんのオススメ、的確ですものね。本社からの評価もそりゃそうだ、ですよ」
マサカズの対面に座る七瀬は、少々興奮気味にそう言った。違法な手段で漫画への知識を蓄えていたマサカズは後ろめたさもあり、「ま、まぁ……そうね」と、歯切れの悪い返事しかできなかった。
「わたしもいつか正社員になれればいいけど、ムリかなー? トロいしミスばっかりだし」
「いやまぁ、そうだね、マジメにコツコツやっていれば、いずれはなれるかも」
「ですかね? わたしも山田さんみたくなれますかね?」
電灯の灯りで眼鏡を光らせ、期待を込めた笑みを向ける後輩にマサカズは照れくささを感じ、チリチリの頭をひとかきし、他愛のないやりとりを続けて間を持たそうと思った。
「七浦さんは、どこ出身だっけ?」
「葛西です。あ違った、出身か。実家は千葉の勝浦ってとこです」
あまり馴染みのない地名だったため、マサカズは次の言葉に詰まってしまった。
「山田さんは?」
「あ、僕は栃木の芳賀ってところ」
「いつこっちに?」
「高校まで地元で、就職で上京って感じ」
「どこに勤めて……あ、ごめんなさい、ぐいぐいし過ぎだ、わたし」
ぶるぶると小さく頭を振る彼女を、マサカズは可愛らしいと感じた。
「別にいいけど、勤めたのは四ッ谷にある教材販売の会社。超絶ブラックの」
「教材、販売?」
七浦はキョトンとした表情を浮かべ、小首を傾げた。おそらく業務内容の想像がつかないのだろう。七浦の反応からマサカズはそう思った。
高校を卒業後、教材販売の会社に営業職の正社員として雇用されたマサカズだったが、そこでは販売ノルマ達成のためなら鉄拳制裁まで行われるという、現代においては時代錯誤の指導方針をとっていた。彼がその鉄拳に晒されることはなかったものの、殴られ、過酷な残業で心身共に傷ついていく同僚を見るに見かね、入社半年後には会社の惨状を労働基準監督署に通報した。しかしその行為は被害者であるはずの同僚の密告によって経営側に知られることとなり、マサカズは退社を余儀なくされた。それ以来、若干の人間不信に陥った彼は、非正規職を転々として今ではこの休憩室で飴をなめている。そのようなこれまでを思い出したマサカズは、暗鬱とした気持ちになった。
「どーしたんですか?」
七浦は身を乗り出し、マサカズの顔を覗き込んだ。距離の近さに戸惑ったマサカズは身を引き、思わず飴を呑み込んだ。
「あ、いや、アラサーなりの、ブルーな気分、とか?」
「でもでも、これから正社員じゃないですか」
身体を戻した七浦は、あっけらかんとした笑みをマサカズに向けた。
「あ、そうだね。確かに」
「これからですよ。そう、これから逆転ですって。まぁ、そうですね。山田さんしだいって感じですけど?」
「ああ、ありがとう、うん、逆転だね」
後輩のおかげで憂いが少しだけ晴れた。マサカズは気持ちを前向きにし、目の前にいる七浦という女性への好意を高めていた。彼女には彼氏がいるらしい。しかし、このやりとりから想定すると今後のワンチャンスがあるかもしれない。そんな期待まで抱きつつあった。
その日の勤務は夕方の十七時までだった。書店をあとにしたマサカズは、今日の晩飯をどうしようかと駅のショッピングセンターをぶらついてた。
あの休憩時間から、七浦葵の姿や声が頭から離れない。心配をして励ましてくれたのがとても嬉しい。もっと彼女のことが知りたい。いやいやそれよりも正規雇用の件だ。これについては栃木の両親に知らせなければならない。あの悪夢の教材販売会社を半ばクビにされて以来、両親はこちらの暮らし向きを心配している。晩飯のあと、電話でもしておくか。そんな結論に至ったマサカズは、駅前の牛丼店に入り、大盛りの牛丼を注文した。大盛りは贅沢だが、正規雇用へのご褒美ということにしておこう。紅生姜をたっぷり乗せた大盛りの牛丼にありついたマサカズはふと、あの鍵について考えを巡らせた。
使い道がない。と言うか。使うことによる秘密の露呈によって、不幸な事態にも陥りかねない。せっかくの正社員というチャンスを失うこともあり得る。一度はこの力を使って人助けや犯罪阻止といった、言わばスーパーヒーローになるという夢想もしていたが、危機や悪行に対してアクセスする手段などあるはずもなく、現実の壁はどこまでも高かった。
湯飲みを手にしたマサカズは、今もデニムパンツの尻のポケットに入っている半ば厄介者とも言うべきこの鍵を、今後は存在自体を無視し、封印することを決めた。
牛丼店を出たマサカズは、アパートに向かって歩き始めた。ここ小岩は駅周辺に飲食店や風俗店が立ち並ぶ、いわゆる歓楽街である。アジア系外国人が溢れ、昼から酒を提供する店もあり、時には日中でも小競り合いの揉め事やアルコールを起因とした無軌道な振る舞いで警官が出動することも多く、これまでに物騒な光景をマサカズは何度も見てきた。しかし十分ほど歩いてしまえば風景は閑静な住宅街に移り変わる。家や集合住宅が建ち並ぶ人気のない通りを、マサカズは歩いていた。
鍵は、今後万が一でも使うことがあるかも知れないし、さすがに捨ててしまうのはもったいなくもあるので、自室のどこかにしまっておこう。立ち止まり、ふと目を落としたマサカズは、職場のユニフォームであるエプロンを着けたままであることに気づいた。いつもなら退店の際にロッカーに収めておくはずだったのに、今日は考え事で頭がいっぱいでついつい仕事着姿のままの退店となってしまった。どうしよう、店に戻るかこのまま帰宅してしまうか。夕暮れのなか迷っていると、背後から「山田正一さんですか?」と、男の声がした。「はぁ」と返事をして振り返ろうとした次の瞬間、マサカズの目の前は真っ暗になった。何かを被せられた。なんで? 誰が? 疑問だらけだったが今度は強引な力で身体ごと引きずられ、横倒しにされ、後手にされた手首は何かで拘束された。この間、僅か数十秒である。考える猶予もないまま、マサカズはスライドドアが閉じる音を耳にした。
【無料版】第1話 ─変身!正義のヒーローになろう! Chapter4
「死んでるわ。コレ」
「おいおいおい、ちょっとカンベンしてくれよ」
「って、オメーがやりすぎたからだろ」
「え? いやだって、まさか」
「いいから内藤さんとこ連絡しろ」
「あい」
マサカズの耳に飛び込んでくるやりとりは、明瞭で単純だったが理解が追いつかず、頭の中にはまるで入ってはくれなかった。跪かされ、後ろに回された手首は結束バンドで拘束され、今の自分はまるでいつかテレビで見た中東のゲリラに拉致されたジャーナリストの様でもある。
マサカズは書店でのアルバイトからアパートに帰宅する途中、突然袋の様なものを被せられ、両手の自由を奪われ、車に詰め込まれ、この蛍光灯が灯る事務所まで連れ攫われてしまった。ここには彼も含めて六人がおり、それぞれ二つのグループに分類できた。脅す側と、自分たち脅される側だ。脅される側は手の自由を奪われ、一列に並ばされ跪かされていたのだが、マサカズの右隣にいる中年の男性は少し前、脅す側のひとりに拳銃を突きつけられ、膝で蹴り上げられ仰向けに倒れ、足先がピクピクと痙攣したのちピクリとも動かなくなってしまった。
早く深い呼吸を繰り返す。マサカズは少しずつだがわかってきた。蹴り上げられたアロハシャツを着た男はおそらく死んでしまった。動かなくなったサンダルのつま先を横目に、いま起きてしまったアクシデントを彼は整理してみた。しかし、死んでしまった者のグループになぜ自分が含まれているのかそもそも心当たりがなく、不可解でしかなかった。
「五百万、どーすんだよ」
マサカズの傍らに立っていたタンクトップを着た巨漢が、拳銃を手にしたポロシャツ姿の華奢な男をそう叱りつけた。男は「すんません」と詫びたが、巨漢は「すんませんじゃねーんだよバカヤロウ。ますらお、あとでカタきめるからな」と返し、男を軽く小突いた。
巨漢と華奢、そしてもう一人、先ほどからずっと無言で『社長』と書かれた札の置いてある席に着く、紫のカットソーを着た煙草をふかす小太り。この三人が脅す側に属する男たちだった。いずれもが強面の青年たちで、マサカズにとっては繁華街でたまに見かけたり、テレビの警察密着ドキュメンタリーやドラマで目にする、普段は付き合いのない類の者たちだった。
マサカズはこの状況をあらためて把握してみることにした。この数十分ほどの出来事でわかったことは、脅す側の三人は金貸し業者であり、隣で死んでしまったかもしれない男は債務者であるということだ。金貸し業といっても拳銃を突きつけ暴力を行使するような連中だ、銀行のようなまともな金融業者ではないのは明らかである。なぜ自分はこんな者たちに拉致されてしまったのか。動かなくなったサンダルの彼は本当に死んでしまったのか。人の死に際など五年前の祖父以来であり、殺害現場などもちろん経験がない。マサカズは目の端に入る足先に怯えつつ、ひどく困惑してしまった。「いいから借りたものは返せよ」「期限が過ぎてんだよバカヤロウ」「本物だぞ。サバゲとかのじゃねーんだよ」「どうやって返すんだよ。テメーの汚ぇ内臓なんか、誰も買わねーぞ」彼らは要求している内容の全てが物騒なのにも関わらず、言葉や表情に全く起伏が感じられず、ただ淡々と作業をこなしているだけの様でもあり、それが不気味でしかない。
「な、な、なんなんだよ。なんで僕がここに? お金なんて借りた覚えはないぞ」
恐怖を堪え、震えた口調でマサカズが疑問をぶつけると、“ますらお”と呼ばれた華奢なポロシャツが屈んできた。こいつはアロハシャツに膝蹴りを見舞わせたやつだ。マサカズは緊張を高め、目を合わせないようにした。
「山田正一だっけ、あんたウチ、カルルス金融に百万円借りてんだよ」
「え?」
「連帯保証人だっつーの。ハンコも押してんだろ? なにすっとぼけてんの」
ますらおは抑揚のない口調でそう言った。マサカズはようやく心当たりに辿り着いた。前のアルバイト先で同僚だったある女性に泣きつかれ、借金の連帯保証人になったことがあった。しかし、確か翌月には完済したと連絡があったし、そもそも金額も五万円で彼女には返済できるアテがあったから契約書に押印したわけである。そう、貸主は確かにカルルス金融という名前だった。風変わりな名前だったので憶えている。
こういった連中から借りたのか。半年で五万円が二十倍になるような契約だったかは記憶も定かではないが、事実を覆すのは容易ではないだろう。それにしても百万円などという大金があるはずもない。となるとこれから何をされてしまうのか。自分もこの男から膝蹴りを食らうのだろうか。ぶるぶると小刻みに震えるマサカズは額からとめどなく噴き出る汗を拭いたかったが、両手の自由も奪われそれも叶わなかった。
しばらくすると事務所に二人の男が入ってきた。いずれもがジャージ姿で屈強な体格をしており、マサカズは威圧感を覚えた。
「内藤さんには明日振り込むって伝えておいて」
巨漢がそう告げると二人は無言でうなづき、マサカズの右隣に倒れていたアロハシャツの男の足と頭を持ち上げ、それを事務所の外へと運び出していった。これはおそらく、『内藤さん』なるその道のプロに遺体の処理を依頼したのだろう。そう理解したマサカズはますます恐れおののいた。すぐ隣の他人が呆気なく死んでしまうなど、これは自分の知らない世界だ。たったひと晩を共にした女のせいで異世界に拉致され、結果によっては殺されるかもしれない。どうすればこの悪夢のような事態を切り抜けられるのか、マサカズが必死に考えを巡らせているとタンクトップの巨漢が、左隣に跪かされていたスーツ姿の青年にしゃがみ込んだ。
「じゃー、次は伊達先生な」
ダテ、と呼ばれた眼鏡をかけた青年はガタガタと強く震え、うめき声を上げていた。
「今日で八百万円なんだけどさ。どーすんの?」
「か、か、返します。必ず返します」
「じゃあ返してよ」
「…………」
「なに黙ってんだよ!」
巨漢が怒鳴ると、眼鏡の青年は顔を背け、咳き込んでしまった。すると、社長の札の席に座っていた男が初めて口を開いた。
「沈黙は俺たちの世界じゃイチバンムカつくんよ。だって、なんもならんし。アンタ喋りのプロなんしょ? ホラ、なんか言えや」
「登別社長、夏にはボーナスが出るんで、それで返済します」
「額、違うんよ。そのころには一千万よ。足りんのよ。差額はどーすんの? あんたも悪質だから、一括返済しかないんよ。あんだけ遊んどいて踏み倒すつもり?」
「そ、それは……」
「そーよ、伊達先生のお父さんも同業よね。勝ち組の」
「いや、ちょっと、父を巻き込むわけには……」
こいつらは、債務者に返済能力がないと判断した場合は親類にまで取り立ての手を伸ばす。つまり、自分の場合栃木の父に迷惑が及ぶ。それだけはダメだ。マサカズは俯き、歯をガタガタと鳴らした。
「さとくん」
登別社長に“さとくん”、と呼ばれたタンクトップの巨漢が眼鏡の青年のネクタイを掴み、強引に立ち上げさせた。登別はうっすらと笑みを浮かべた。
「お父さんに電話するんよ。あ、なんならこっちからかけるかぁ?」
「や、やめてください。それだけは」
涙混じりに懇願する青年を横目に見ながら、マサカズは最悪な展開を想定していた。隣の彼がどのような結果を迎えるかはわからないが、次は自分がこうなる。一方的な暴力に晒され、運しだいで殺されてしまう。契約内容もよく確認せずたった五万円だという思いから保証人になったがために、自分が返済能力のない底辺のアルバイターだったために。気がつけば、マサカズは頬を涙で濡らしていた。
「さとくん、先生に言うこと聞かせてくれるかなぁ?」
薄笑いを浮かべたまま登別社長は指示を出した。それを受け、巨漢は青年の頬を強く張った。それは二度、三度と続けられ、乾いた音と共に青年が吐いた血がマサカズの頬に飛び散り、涙と混じった。
このままでは、隣の彼は違法な暴力に晒され続ける。そして次は自分だ。なんとかしてここから逃げ出さなければ。あとのことはそれから考えよう。もう、なんの余裕もない。なら、取るべき手段はたったひとつしかない。ようやく覚悟を決めたマサカズは、後手に拘束された両手をお尻のポケットに突っ込み、鍵を錠に差し込み、それを回した。
痺れが走り身体中に滾りを感じたのち、自由を奪っていた結束バンドは枯れ葉のごとく呆気なく千切れ、マサカズは涙を拭い、立ち上がった。
三人の金貸しは想像していなかった事態にいずれもが困惑の表情を浮かべた。巨漢の“さとくん”は眼鏡の青年から手を離し、首を傾げながらマサカズに掴みかかろうとした。伸びてきた両腕を、マサカズは思い切り手で払った。身長百七十センチ足らずと二メートル近くの体格差だったので払いきれるものではなかったはずが、今のマサカズにはできてしまった。さとくんはラケットで打たれたピンポン球のように軽々と弾き飛ばされ、壁に激しく叩きつけられた。やりすぎてしまったか、そう感じたマサカズの背中に軽い衝撃と痛みが走った。振り返ってみると、ますらおが両手に拳銃を構え、銃口からは硝煙が生じている。信じたくないが、状況から考えるとどうやら撃たれてしまったようだ。ますらおは恐怖を顔に貼り付かせたまま、マサカズとの距離を詰めてきた。近距離なら射撃の結果が希望通りになるかもとの意図だろうか。命の危険を感じたマサカズは、荒い息で銃口を突きつけてきた華奢な男を、がむしゃらに不細工なフォームで蹴り飛ばした。男はサッカーボールの様に吹っ飛ぶと、入り口に叩きつけられ、ガラス戸には亀裂が生じた。
マサカズが振り返ると、登別はガタガタと震えながら拳銃を構えていた。銃弾を肩に受けながら、マサカズは社長の机に詰め寄った。
「先に手を出してきたのはあんたたちだろ!? 拳銃とかあり得ない! 早く救急車呼べよ!」
強くそう叫び、脅すために大きな音を立てようと机を押したところ、それは登別の腹部を強く圧迫し、壁に挟まれてしまった彼は顔を引き攣らせ強く吐血し、対面していたマサカズのエプロンを赤く染めた。意図せぬ結果にマサカズが「ごめんなさい!」と叫びながら慌てて机を引くと、登別は机の下に力なく崩れ落ちた。
制御しきれない力で瞬く間のうちに三人をノックアウトしてしまった。これは望んでいた結果だったのだろうか。困惑しながらもマサカズは、蹲っていた眼鏡の青年の結束バンドを千切った。
「あ、う、あ、うう……」
立ち上がった青年はただ呻き、マサカズを見つめるばかりだった。マサカズは引き攣った笑みを向け、混乱を深めていた。
数分ほど、二人は呻きと引き攣りを向け合っていたが、革手袋をした指で眼鏡を直すと、青年は咳払いをした。
「後始末をする。あんた、もしかしてあの金庫を運び出せるか?」
青年は事務所の隅、登別の机のすぐ傍らに置かれていた金庫を指さした。アレはますらおが拳銃を取り出したものである。「た、たぶん」マサカズはそう返事をした。
「なら持っていってくれ。アレには重要書類が入っているはずだ。他の名簿とかは俺の方でやっておく。もし金庫を……いや、さすがにそれはムリか」
「ちょっと待ってください。それって泥棒じゃないですか。あと警察とか病院とか、先にやることが……」
マサカズがいい終わらぬうちに、青年は右の掌を突き出してきた。
「その辺は俺に任せてくれ。俺とあんたにとって、今の状況下でできうる最善の提案をしているつもりだ」
「いや、でもいくらなんでも泥棒はムリですよ」
「中身は債務契約書のはずだ。以前保管するのを見たことがある。そこには俺や連帯保証人であるあんたの名前も記されている。だから、その証拠を隠すしかない」
「隠すって、今夜のこれを僕たちとは関係なくしてしまうってことですか?」
「そうするしかないだろ! 過剰防衛で三人も大ケガさせてるんだ。いくらこいつらがヤミ金でもあんたは実刑を免れないんだぞ。軽い気持ちでなった連帯保証のせいで、刑務所入りして一生を棒に振りたいのか!?」
青年の剣幕にマサカズはすっかり気圧されてしまい、仕方なく金庫を抱え上げた。
「問題は、監視カメラか……」
そうつぶやいた青年に、マサカズは首を振った。
「跳んで行きます」
「跳ぶ?」
先ほどまで晒されていた暴力への恐怖はまだ消えてはいないし、今では自分がやってしまった暴力にも怯えている。マサカズはいち早くこの場から去りたかったため、事務所の窓を開け何歩か後ろずさりをした。周囲を見渡すと、登別だけではなく、巨漢と華奢な二人も吐血しているらしくいつの間にか血だまりの元にいた。
三人を殺してしまったのだろうか。だとすれば、この悪夢を地獄にしてしまったのは自分だ。しかし、やるしかなかった。マサカズは忸怩たる思いのまま、助走をつけて窓の外へ跳んだ。眼下には、つい二日前に力の活用を諦めた歌舞伎町の繁華街が広がっていた。
【無料版】第1話 ─変身!正義のヒーローになろう! Chapter5
これは、映画やドラマでしか見たことがない量の札束だ。マサカズは顔を顰め、そのひとつを掴み取った。
あの、初めて鍵の力を人間に対して使ってしまった夜、アパートまで戻ってきたマサカズは、敷きっぱなしだった布団に倒れ込み、翌日の夕方になってようやく目を覚ました。せっかくの休日をムダにしてしまった彼が真っ先に試みたのは、ヤミ金から持ち去った金庫の中身の確認であり、それは鍵の力によって強引に達せられた。眼鏡の青年が言っていたように、中には債務契約書が入っていたのだが、同時に大量の札束も保管されていた。正確な総額はわからないが、おそらくは数千万円はあるだろう。傷害の上、大金の強奪という罪を背負ってしまった。理不尽で圧倒的な暴力に晒され、あの事態そのものから逃れるために行った結果ではあったが、大金を得た喜びなど全くなく、犯罪者となってしまったことにマサカズは恐れしか感じていなかった。これからどうしよう。警察に自首するという道が最も真っ当ではある。だが、あのダテ先生と呼ばれていた青年が言っていたように、あのような命の扱いを淡々とやりとりをして暴利を貪る連中のせいで刑務所に入れられるのは、今ひとつ納得ができない。それに、あの夜の状況をつまびらかに説明した場合、鍵の秘密についても警察に知られてしまう。いや、刑務所に入れられる時点で鍵も失うのだから、そこは気にする点ではないのか。マサカズはひどく混乱してしまい、その日は一食も口にすることができなかった。
それでも日常は訪れる。どうするべきかの答えは出なかったが、予め何をするかは決められていたので、マサカズは翌日、アルバイトのため書店に出勤していた。昼の休憩中、マサカズは店長に呼び出され事務室を訪れた。
「山田君、こないだの件ね、アレ白紙ね」
唐突な切り出しに、マサカズは頷くことなく返事の言葉も出なかった。
「だからさ、正社員って件、アレ白紙ね」
そもそもが正社員採用の可能性についてはマサカズにとって降って湧いたかのような話だったため、彼は「はぁ」と気の抜けたような言葉しか返せなかった。
「でね、多分なんだけど、今の契約も次ので最後になりそうなの」
つまり、年内にはここでの職を失う。そう理解したマサカズは目を細め、アパートにある札束を思い浮かべた。
「いやね、チェーン全体の経営がキツくなってきたのよ。今ってみんな電子でしょ? ウチみたいな本屋はどこも苦しくてね。まだ閉店にならないだけマシなんだけどね。ごめんね」
最後の“ごめんね”がひどく早口で、形式だけの謝罪であることは明らかだった。マサカズは小さく頭を下げ、事務室から休憩室に戻った。
「山田さん、何でした?」
ソファに座って弁当を手にした後輩の七浦葵が声をかけてきた。
「正社員の件、なしだって。それと、次の契約で最後になりそうだって」
マサカズの言葉に、七浦は弁当箱を机に置き、目を丸くした。
「じゃあ、わたしも次でクビ?」
マサカズは疲れ果てた様子で七浦の対面に座った。
「知らないよ。七浦さんがどうなるかは」
「だって、わたしなんかより全然優秀な山田さんがですよ? わたしみたくポンコツが残れるはずない」
「知らない。店長に聞けば?」
「やです。わたし、店長苦手ですし」
「そうだったの?」
「なんかあの人、わたしをジロジロ見るんです。その目付きがNGって言うか、うぇって言うか」
嫌悪感を隠さぬ表情と口調で、七浦はそう言った。マサカズにしてもあの店長は決して得意な相手ではなかったが、彼女から感じた拒絶は想像以上であった。
「ならさ、辞めて他行けばいいんじゃない?」
「仕事慣れてきたからダルいなぁ。できれば折り合いつけつつ、このままがラクかも」
「七浦さんは例えば将来の夢とかってないの?」
「あります。すっごい具体的なの」
今度は目を輝かせ、七浦は腕を組んで胸を張った。
「夢は小説家デビューしてアニメ化されて、推しの声優さんがキャスティングされることです」
「確かに、具体的だ」
「山田さんは推しの声優さんとかいます?」
「あ、いや、僕、あんまりアニメとか見ないから」
「えー!? あんなに漫画にお詳しいのに?」
「アニメとかドラマって、自分のペースで見れないのが、それこそダルくってさ」
「あー、なるほど。でも最近だと倍速もできますよ」
「僕の場合、遅く読みたいこともあるんだよ」
「はー、さすがに漫画読みの上級者は違いますね」
「小説、書いてるの?」
「ネットの投稿サイトで鋭意連載中です」
「なんての? 読んでみたいな」
「やです。男名義のペンネームなので身バレNGですし」
ストレートな拒絶に、マサカズはそれ以上の要求を諦めた。
「けどけど、興味をもってもらうのは嬉しいです」
後輩の喜びと屈託のない笑みに、マサカズは犯罪者という重荷と失職という危機から少しだけ気持ちが癒されるのを感じていた。
夜、仕事を終え書店をあとにしたマサカズは駅近くのラーメン店に入り、カウンターで醤油ラーメンを注文した。よく使っている店だったが今日は経路を変え、遠回りをしてしまった。いつもの道筋だと交番の前を通らなければならず、一昨日やってしまったことを考えると、なんとなくだが避けてしまっていた。
これからどうすればいいのか、考えがまとまってくれない。店の隅に接地されたテレビではニュースを流していた。内容は、もう一年以上続いている、はるか彼方の外国で繰り広げられている武力衝突についての報道だった。瓦礫の映像をぼんやりと見つめながら、マサカズはいずれ逮捕され、自分がこの番組で報じられるのではないかと思った。やはり、あの行動は間違いだったのだろうか。ダテ先生を見殺しにし、父に借金の返済をお願いするのが最適解だったのかもしれない。
ラーメン屋を出たマサカズは、家路につきながらスマートフォンを手にした。
「もしもし、俺、マサカズ」
電話した先は、栃木の実家だった。マサカズの実家は栃木県の南東部に位置する芳賀町という梨を特産品とする農地や工場が建ち並ぶ地域であり、マサカズの父は小さな町工場を営んでいた。
「仕事、年内で変えなくちゃいけないっぽいんだ。まぁ、なんとかするから心配しないで」
母親に現状を報告したものの、どうしても一昨日の件については打ち明けることができなかった。母と話をしながら、マサカズは段々とどうにでもなれ、という投げやりな気持ちを膨らませていた。
どうにも気分が悪い。アパートに帰ってきたマサカズは、救いを求めるような気持ちで後輩の彼女の笑顔を思い出した。ハッキリと端的に自分の気持ちを表してくるあのような子と付き合えたら、毎日はさぞかし起伏があり、精神的に豊かな生活を送れるだろう。しかし、明日にも傷害と窃盗の罪で逮捕されるかもしれない。そもそもあの夜の事件については発覚されているのだろうか。そう思ったマサカズはニュースサイトにアクセスしてみた。
歌舞伎町の金融店に強盗、経営者を含め三名が死亡
その見だしに、マサカズはスマートフォンを床に落とした。
死んでしまった。殺してしまった。自分が、この手で、あの三人を。自分が、殺した。
マサカズはその晩一睡もできず、アルバイトも休みをもらい、アパートで布団にくるまりただ震えていた。いや、アレは正当防衛だ。ダテ先生は過剰防衛と言っていたけど、アロハシャツの男のように殺されていた可能性があったはずだし、銃弾を二発も受けたのだ。ああするしかなかったのだ。いや、連帯保証人になったのは事実だし、たとえ法外な金利だったとしてもあの夜はなんとか凌いで、テレビとかでやっている借金専門の法律事務所に相談して正当な金利で返済するという道もあったはずだ。マサカズの中で、二つの相反する考えが交互に繰り返し押し寄せていた。
それでも日常というものは避けられない。一日休んだのち、マサカズは書店に出勤し、職務に就いていた。そろそろ六月のお薦め漫画を決めなければならない。今度は違法アップロードではなく、正当な手段で選ぶことにしよう。法を破った強盗殺人犯として、せめてそれぐらいはしなければ。翌日もマサカズは仕事に没頭した。忙しければ考えごとの余裕もなくなる。夜は酒を呑んで寝てしまう。そんな二日間だった。警察の手はまだ伸びてこない。だが、日本の捜査機関は世界に誇る優秀さだと聞いたことがある。少しずつ覚悟を決めつつあったマサカズだが、それでも自首という勇気は湧いていなかった。
その日の仕事を終えたマサカズは、家路についていた。すると目の前に紺色のスーツを着た手ぶらの中年男性がやってきた。髪はオールバックでネクタイはしておらず、黄色のワイシャツは第二ボタンまで外されていた。「山田正一さんですよね」
見も知らぬ者に名前を呼ばれる。あの地獄の夜のように。マサカズは腰から首まで固まらせ、膝をガクガクと震えさせ、「やだ」と漏らした。
【無料版】第1話 ─変身!正義のヒーローになろう! Chapter6
マサカズは九階建てのマンションの屋上に着地した。すぐ近くには首都高があり、あちらに着地していれば誰かの目に捉えられていただろう。だからここは我ながらベストな着地先だと思う。屋上の防犯カメラも自分に対しては明後日の方向を向いている。六本木という繁華街にやってきたのは初めてだったが、今夜の目的は飲食や遊びではない。吉田と名乗るオールバックの男から依頼された用事を済ませるためだ。
正義のヒーローと見込んで、悪の一味を倒してくれ。小岩駅前の喫茶店で、吉田は熱心な口ぶりでそう語ってきた。昨日、自宅アパートの近くで名前を呼ばれたときには、また拉致されるのか、あるいは遂に警察が突き止めてきたのかと怯えきってしまい、その場から逃げ出してしまいたがったが、吉田の接触してきた目的はそのいずれでもなかった。慎重に言葉を選び、探るようなやりとりをしてみたところ、対するオールバックのこの男はあの夜、カルルス金融において自分が銃弾をものともせず、あっという間に三人を殺害したことを知っていた。しかしどうやら超能力が鍵によって発動するということまでは知り得ていない様である。
「カルルスの登別なんてね、ありゃ金貸しの中でも平気で殴る蹴る、おまけに拳銃を突きつけるような武闘派の外道ですよ。生きてる価値なんてこれっぽっちもない。山田さんが成敗してくれたおかげで、救われる人は大勢いるんです。すばらしい! 僕はですね、拳銃にも真っ向から立ち向かう山田さんに、すっかり惚れ込んでしまったんですよ」
グラスに注がれたトマトジュースを前に、吉田は熱を込めた口調で訴えてきた。
「でね、まだまだ世の中にはあんなド外道の悪党がわんさかいるんですわ。山田さんの正義の力で、ちょっとそいつらをこらしめてもらえればなって、そう思ってお声がけをしたしだいで。段取りさえお任せいただけたら、あとは山田さんは、ちゃちゃっとやってくれましたら、それはもう」
ペラペラと調子よくお喋りをする吉田に、マサカズは警戒を緩めなかった。
「なんで僕があそこに住んでるって知ってるんです?」
そう問うと、吉田は表情を消し、静かにゆっくりと「そりゃ、わかるでしょ」と呟いた。
何者かはわからないが、力を見込まれ、それで悪党を倒して欲しいとのお願いだった。秘密を知られているということもあったためマサカズは吉田の依頼を断れず、六本木のマンションの屋上で次の跳び先を探していた。
目的地である交差点近くにあるビルの屋上まで跳んできたマサカズは、階段へと続くドアをこじ開け、ビルの中に侵入した。階段を駆け下り、向かった先は『ラムダ』とガラス戸にプリントされた事務所だった。入ってみると、そこには六人の男たちがいた。彼らは特殊詐欺や強盗の計画と指示を繰り返す反社会的な集団である。吉田は喫茶店でそう説明していた。確かに見ただけでわからなくない。六人全ての人相や髪の色や形、服装がいちいち荒々しい。突然飛び込んできたマサカズに対して、六人はそれぞれ怒気を向け、そのうち五人がめいめいに距離を詰めてきた。マサカズはそれに対して何度か足を払うようにした。腰に力が入っておらずフォームこそ見られたものではなかったが、目にも留まらぬほどの速さであり、五人の荒くれたちは向こう脛を砕かれ、転倒し悶絶した。顔を歪め、ゴロゴロと転がる男たちを見下ろしたマサカズは、なんとか殺さずに無力化できたことに安堵した。
残りの一人が、事務所の奥で震えていた。視線をあちこちに移し、なにかを探しているようでもある。マサカズが様子を窺っていると、背後から声が響いた。
「まだひとり残ってます。やっちゃって」
その声は、昨日喫茶店で吉田に引き合わされた、トシという若い男のものだった。マサカズは振り返り、情けなく口元を歪めた。
「でもだってあの人、もう戦闘意思がないっていうか、すっかりビビってるよ」
「やっちゃって、やっちゃって、いいからいいから。でないと終わらないの」
つかみ所のない指示に、仕方なくマサカズは事務所の奥まで進んだ。嗚咽を漏らし、両手をボクサーの様に構え、恐怖を貼り付かせた顔をブルブルと何度も振るその男の向こう脛を、マサカズは蹴った。絶叫と共に男はその場に崩れ落ちた。
「ローキックナイスぅ! じゃ、あとは俺たちがやっときますんで」
トシという男に小さく頷いたマサカズは、事務所を出てビルの屋上へ向かった。
六本木をあとにしたマサカズは池袋に向かった。飲食街のとあるガールズバーまでやってきた彼は、店の事務室にいた吉田に軽く頭を下げた。
「言われたようなことはやってきました。トシさんが来て、あとはやっておくって」
マサカズの報告に、椅子に座っていた吉田は破顔一笑して親指を立てた。
「山田さんならやってくれると思っていましたよ。またお願いしますよ。正義の戦いはまだまだ終わらないので」
六人の荒くれにローキックを食らわせ、骨を砕き悶絶させる。今夜行ったそれが正義の戦いかと言われれば違和感はあったが、吉田の言葉を信じるのなら、自分は悪い奴らをこらしめたということになるのだろう。マサカズは一応だが納得し、小さく何度も頷いた。
「ではでは、コレ」
吉田は封筒をマサカズに手渡した。チラリと中を覗くと紙幣が数十枚入っていたので、マサカズはぎょっとして吉田に目を向けた。
「アニメやドラマみたく、タダ働きってワケにはいかないでしょ。それは山田さんの正当なる報酬ってやつですよ。何も言わずに受け取ってください」
この札束は、いったいどこからきたものなのだろうか。ガールズバーの収益からか、吉田という愛想のいい男のポケットマネーだろうか。疑問はあったものの、くれると言うのならもらっておこう。マサカズはそんな結論に達し、ちりちり頭をひとかきした。
三日後の夜、マサカズは鬱蒼とした真っ直ぐな山道に降り立った。眼前に十名、背後に三名、男たちに挟まれた状況である。総勢十三名は突然降ってきたマサカズに、いずれもが困惑の表情を浮かべていた。すかさず、マサカズは前に並んでいた十人との距離を詰め、あっという間にその足を次々と払った。振り返り、残りの三人の向こう脛を砕こうとしたが、そのうちの一人には避けられ、ジャージ姿のその男は腕をバタバタと振り、停めてあった黒塗りのベンツに向かって駆け出した。吉田からの指示は、この場にいる全員の無力化である。それを果たすためマサカズは即座にジャージの男まで駆け寄り、背後から胴を抱きしめ、一緒に転がり込んだ。男は気を失っており、吐血していた。胴を締め付ける力が強すぎたのか、もしかすると内臓を痛めた可能性もある。やりすぎてしまった制圧に、立ち上がったマサカズは恐ろしくなり、周囲をキョロキョロと見渡した。
「山田さ〜ん。お疲れ様っス。すげぇよ、すげぇ!」
そう言いながら現れたのは、トシと同様に吉田から紹介された、ケンという若い男だった。
「あっという間でしたねー。すげぇや」
「えっとさ、この人、血を吐いてるし、それにみんな足折れてるから、救急車呼んだ方がいいと思うんだけど」
「あ、はいはい、それとかこのあとについては俺とトシでやっておきますから。山田さんはなーんも気にせず帰ってください」
地元の小岩駅から電車を乗り継ぎ二時間ほどかけ、マサカズは隣県の千葉県市原市の高滝という、初めて訪れる辺鄙な私鉄駅に降り、そこから1キロほど進んだ先がこの山道だったのだが、移動時間に対して依頼の遂行時間はあまりにも短く呆気なかったので、彼はもっと自分が行った行為の内訳を確かめたい気持ちにかられた。
「あのさ、吉田さんが言ってたけど、これって本当に麻薬の取り引き現場なの?」
マサカズの疑問に、ケンという男は目線をベンツに向けた。
「多分っスけど、あそこにありますよ。ブツは」
「そうなんだ。で、どうするの? 処分とかってするんですか?」
「あー、するっスねぇ。するする」
軽い口調に、マサカズは頬を引き攣らせ、「ならいいけど、麻薬なんてなくさないとね」と返した。
「にしても山田さんの超絶攻撃力って、やっぱ超能力的な何かなんですか? ある日異能に目ざめた、とか、誰かから能力を授けられたとか」
しゃがみ込み、倒れている男たちの懐からスマートフォンを抜き取りながら、ケンはそう尋ねた。
「鍵の力は僕にもよくわからないんですよ。ある日突然って感じで」
マサカズの説明に、ケンは「へー」と、ぶっきらぼうに返した。うっかり“鍵の力”と口を滑らせてしまったが、あまりにも生返事だったため恐らくは気にもされないだろう、マサカズはそう思い込むことにした。
それから何度か、マサカズは吉田からの依頼を受けた。内容はどれも似たようなものであり、指定された場所に向かい、その場にいた者達を暴力で制圧しトシやケンに後始末を任せる、といった段取りである。もう何名もの男たちの足をローキックで破壊し、時にはそれでは済まされないほどの怪我を負わせてしまうこともあったが、一切が報じられることはなかった。そう考えれば、あの連中は警察に被害届など出せない存在、つまり吉田の言うところである悪党、ということになるのだろう。だとすれば、自分が行っているこれらは正義だと言ってもいい。最近だと、鍵を差して回す際に「アンロック」と、ヒーローの変身の合図のようなことを口にするようにもしている。持て余していた鍵の力の使い道がようやく見つかり、依頼を果たす度、吉田からは三十万円ほどの報酬も支払われている。良いことづくめである。
それなのに強い違和感がこびりついたままだ。何かが違う。布団の上であぐらをかいていたランニング姿のマサカズは、天井を見上げた。
ガラの悪そうな連中に問答無用のローキックで立ち向かう。小さいころ憧れた正義のヒーローとは何やらかけ離れている。「人相知れちゃう危険もあるから、今後は仕事のとき、これつけて下さいな」ガールズバーの事務室で吉田から手渡された黒い目出し帽を手にし、それを見つめたマサカズは深いため息を漏らし、「仕事……か」と呟いた。
【無料版】第1話 ─変身!正義のヒーローになろう! Chapter7
新宿区高田馬場に、一軒のゲームセンターがあった。ここにはプリクラやクレーンゲーム、メダルゲームといった普通のゲームセンターにあるような遊具はなく、ビデオゲームのみを揃えた店舗だった。用意されたゲームは七十年代からゼロ年代にリリースされた古いものが多く、いわゆるレトロゲームを嗜好するマニアたちは、ここに足繁く通い、いつの間にかレトロゲームの聖地とも呼ばれる存在となっていた。
電子音が鳴り響く中、椅子に座り筐体に身を屈め、食い入るようにモニターを見つめる伊達隼斗も、そんな常連客のひとりだった。
「懐かしいな……あ、いや、違うか」
しゃがれた声が伊達の背中にかけられた。彼は背を向けたまま、「これは1986年にリリースされた、いわゆるリメイク版のブロック崩しです」と、早口で答えた。ボールの形をしたドッドが画面の下へ通過していくと、彼は起ち上がって振り返った。
三つ揃いのスーツを着た眼鏡の長身、目付きにやや険はあるものの整った顔立ちをした伊達隼斗は、今年三十三歳になる、中年に差し掛かろうとしていた青年だった。
対する男は初老のワイシャツ姿で、ハンチング帽を目深に被り、豊かな口髭をたくわえていた。二人は二つの椅子が並んで置かれた筐体にそれぞれ腰を下ろした。
「井沢さん、どのキャラ使うんです?」
筐体に百円玉を入れながら、伊達は隣に座った男にそう尋ねた。
「あっと、いつものかな」
井沢はそう返すと、選択画面の中から派手なメイクをした力士のキャラクターを選択した。伊達は小さく笑みを浮かべると、愛用している米国軍人のキャラクターを選んだ。
二人のキャラクターが画面の中で向き合っていた。しかし互いに何かをするわけでもなく、ただ待機の挙動を繰り返すだけだった。井沢は傍らに置いていた鞄の中からA4大の封筒を取り出すと、それを伊達の膝に置いた。伊達はすぐさまそれを自分の鞄にしまい、筐体のレバーを握った。
「山田正一ってな、ここ何日か猫矢に貼り付かせてみたんだが、ありゃとんでもねーな」
井沢の言葉に、伊達は興奮した強い笑みを浮かべ、鼻を鳴らせた。
「でしょうね。俺が見たあいつは、まさしく化け物でしたから」
「プロフィールは至って平凡なんだよな」
「でしょうね。そんな感じの男でした」
伊達の返答に、井沢は相撲取りをなんとなく前後に動かしてみた。
「でよ、その化け物に、お前はどうするんだよ?」
「アレ? 珍しく詮索ですか?」
「そりゃまぁね。どうやっても伊達先生とは結びつかねぇ案件だしよ」
「…………」
返事をせず、伊達は待機モーションを繰り返す画面を見つめていた。そう、結びつかない。自分にとって、あの夜見た超人的な力は。だが、あのチリチリ頭の青年は、悪人ではないがおそらく頭脳明晰というタイプではなく、あのデタラメな超能力を有効には使えていないだろう。自分の知能と経験があれば、もっとよい活用方法を示せるはずである。そして、それによってヤミ金に追い詰められてしまうほど自堕落でこの愚かなこの生き方を変えられるかもしれない。事実、あの夜から何日も経ったが、自分の中で何かが変わりつつあるような気がしてならない。借金をしてまで溺れていた遊興にも一切の関心がなくなり、青年が見せた信じられない力が何度も思い浮んでしまう。だから、もう一度会って確かめる必要があった。自分はなにができるのか、そしてどうしたいのか。これまで漠然という感覚を一切排除してきた人生だったので、このもやもやとした気持ちは早期に解決したかった。
井沢は席を立つと、鞄を手にした。
「あ、やらないんですか? 対戦?」
伊達の問いに、井沢は「やんねーよ。勝てねぇし」と言い放ち、ゲームセンターをあとにした。伊達は木偶人形と化している相撲キャラを叩きのめすと席を立った。画面には二戦目のアナウンスが表示されていたが、米国軍人と相撲取りはただひたすら全身を上下させるだけであった。
「アンロック」
そう呟いたマサカズは鍵を南京錠に差し込み、それを回した。口にしたのは正義を守るヒーローへの変身という願いを込めた呪文だったが、今の自分は黒い目出し帽に黒いTシャツに手袋と、鏡で見ればまるで犯罪者のような出で立ちである。その夜、今日の“仕事”を果たすため、彼は目黒の雑居ビルの屋上に着地した。
いつもの様に現地へ赴き、そこにいるガラの悪そうな連中を蹴り倒し、若い二人組にその後を一切任せ、池袋のガールズバーまで報告に出向く。今夜の仕事も実に容易だった。目黒の事務所にいた、たった七人を無力化するだけで終わりだ。そのうちのひとりはまだあどけなさを残した少年だったが、容赦はしなかった。最初の件から今日でもう四週間ほどが経ち、何回も同じ様なことを繰り返していたが、段々と恐れはなくなり、同時に葛藤も失いつつあった。それが気持ち悪い。このままではいけない。今一度自分というものを取り戻さなければ。ビルの屋上まで出たマサカズは、目だし帽を脱ぎ、「辞めよう、もう」と呟いた。
ガールズバーの事務室までやってきたマサカズは、座っていた吉田から報酬の入った封筒を受け取った。
「助かるわー。“山田ちゃん”のおかげで関東から悪が滅びつつあるんだから」
最近ではすっかりなれなれしい口調になっていた笑顔の吉田をマサカズは睨みつけ、「このお金、どこから出てるんです?」と尋ねた。すると、吉田は表情を消した。
「あんね、山田ちゃんはそんなの気にしなくっていいのよ。細かいことはこっちにお任せして、ビシバシ蹴ってりゃそれでみ〜んなが幸せなの」
とくとくと語る吉田に、マサカズはある決心をした。
「あの、そろそろ僕、こういうの辞めたいんですけど」
「なんで? 本屋のバイトより全然ワリがいいでしょー。もう年収以上は稼げてるんじゃない?」
決意に対して、吉田の返答は食い気味で素早かった。
「何て言うか、おかしいんですよ。こう、上手くは説明できないんですけど、僕のやってることって、吉田さんの言う正義とは違うって言うか」
「正義じゃん。どー考えても。だって、山田ちゃんの必殺ローキックは、悪い連中専用なんだし」
「確かにあの人たちはヤクザっぽくって悪いって感じですけど、僕、吉田さんの説明以上のことは知りませんし。実際のところはどんな人たちなのかなって?」
「あ、オレが嘘ついてるかもってこと?」
「そうは言いませんけど、なんか、なんかしっくりこないんですよ。それにここ最近、吉田さんの態度も変わってきちゃってるし……」
吉田はマサカズを見上げたまま、煙草に火を点けた。
「あのさ、山田ちゃん。自分の立場わかってる?」
これまでになく低い声に、マサカズは戸惑った。
「こっちはさ、お前の殺し、知ってんだよ。それにド田舎のジジイとババアの居場所だってな」
脅迫である。これは、まさしく。これがこいつの本性というやつか。煙草の煙を吹きかけられたマサカズは咳き込み、とぼとぼと事務所を後にするしかなかった。
マサカズはアパートまで帰ってきた。鞄を放り投げると布団に大の字となり、彼はうめき声を漏らした。このような奇怪としか言いようのない力があるばかりに、得体の知れない連中に暴力を奮わされている。先ほどの吉田の態度からすると、怪我をさせたあと、トシとケンが救急車を呼んでいるかどうかも怪しい限りである。それによくよく考えてみれば、悪いと称される彼らを蹴り倒したところで、何がどうなるというのだろうか。トシとケンが説教して、改心でもさせているのだろうか。
これからどうすればいい? このまま吉田の言いなりになるしか道はないのか? 逆らえば強盗殺人犯として密告されるか、両親に危害が及ぶ可能性がある。しかし、やはり今やらされている行いは、何もかもが不明瞭すぎて気持ちが悪い。詳細を尋ねたところではぐらかされるか、脅されるかのいずれかだろう。悶々とした気持ちを抱えたまま布団の上をゴロゴロとしていると、玄関の呼び鈴が鳴った。身体を起こしたマサカズは、扉ののぞき穴に目をつけた。
長身の、三つ揃いのスーツを着た男の姿があった。忘れるはずもない、眼鏡の彼は、歌舞伎町であの強烈な体験を共にした“ダテ先生”だ。マサカズは扉の鍵に手を伸ばした。
【無料版】第1話 ─変身!正義のヒーローになろう! Chapter8
「伊達さんって唐揚げにレモンかける方ですか?」
スーパー銭湯の食事処の座敷席に、パジャマのような青い館内着姿のマサカズと伊達が向き合って座り、両者の中央には机に置かれた鶏の唐揚げがあった。
「かけない」
伊達がキッパリと答えたので、マサカズは手にしたレモンを引っ込めた。
柏城法律事務所に所属する弁護士。アパートを訪れた伊達というこの男が真っ先に差し出した名刺には、そう記されていた。だから“ダテ先生”だったのか。確かにいちいち言葉が明瞭だし、銀縁の四角い眼鏡もよく似合い、いかにも法廷で活躍していそうな雰囲気でもある。
それにしてもなぜ、自分は伊達に対してなにも考えずに扉を開き、部屋に招き入れてしまったのだろうか。もしかすると、初対面が“脅される側”という同じ立場だったため、そこから仲間意識が働いたのだろうか。あの晩を生き延び、血まみれのあと何をするべきか、彼は指示を出してくれた。今のところ警察の手は伸びてきていないのだから、伊達という男は仲間として信じてもいい、そう思ってアパートのドアを開けたのかもしれない。マサカズは唐揚げのひとつにレモンを絞ると、それを口に放り込んだ。
唐揚げをもぐもぐと頬張るマサカズを見ながら、伊達は中ジョッキのビールをひと呑みした。
ひどい有様だった。今はまだ少しマシのようにも見えるが、一時間ほど前、アパートの狭い一室で名刺を渡したこの青年は、いずれは自分から命を絶つのではないかと思うるほどの状態だった。目は落ちくぼみ、口はだらしなく半開きで、視線は定まらず、精神疾患を診断されるのは明白である。仕事柄、このようなことになってしまった人間は何人も見てきた。このままでは、彼は望まぬ結果を迎えることになるだろう。そうなってしまったら、今日用意してきた計画も水泡に帰してしまう。立て直してみせる、言葉で。伊達はジョッキに注がれたビールをごくごくと呑み、「ぷはぁ!」と声を上げた。
「あんたは人間離れしたアレができて、今はどうしてるの? 本屋の店員?」
質問を切り出したのは伊達の方だった。
「そうです」
「ほんとに? 他にはなにかしてないの? アルバイト的な」
「してません」
青年があるグループからの依頼で反社会勢力に対して暴力を以てして制圧していることは、井沢から受け取った資料で知り得ていた。そうだったので、伊達はマサカズのウソの付き方を観察していた。返答の内容と長さ、目の泳がせ方、手の動き、口元のゆがみ具合といった様々なポイントを次々とチェックしていく。まだ十年足らずのキャリアではあったが、才能を所長に認められ、刑事裁判の場数を同僚たちより優先的に踏んできた中、辿り着いた手法だった。
「伊達先生は僕に何の用なんです? こんなところに連れてきて」
伊達の提案でこのスーパー銭湯、「いざないの湯」までタクシーでやってきたのだが、よく考えてみればなぜこうなっているのかが不可解だ。どうやら自分は教材販売会社をクビになって以来、いささか流されやすい人間になってしまったようであり、そのせいでことごとく望まぬ結果に陥っている。二十八歳にしてようやくそれに気づいたマサカズは、睨むように目を細めた。
「そりゃ、あんたがゲッソリと元気なさそうだったから、酒でも呑んで気分転換でもしてもらいたくてね。ひと風呂浴びて、サッパリしただろ?」
確かに、つい先ほど入った天然温泉は有難かった。今夜の仕事は労力が少なく鍵を外した後の疲れも大したものではなかったが、久しぶりに浸かる大きな湯船のおかげで、悶々と布団を転がり回っていた最低な気分も少しは晴れていた。
「あんたは、いま困ってることがあるんじゃないのか?」
そう告げると、空のジョッキを手にした伊達は座敷を立ち上がった。
「あ、そうだ。さっきはよくない答え方だった。質問の要点は俺がなんであんたに会いにきたか、だよな。カルルスでの件について、礼が言いたかったんだ。名前はわかっていたから、知り合いの井沢さんというプロにあんたの経歴や個人情報を調べてもらった。あと、ここ数日は尾行もつけさせてもらった。理由は、あんたに強い興味があるからだ。俺はこれまで、暴力や欺瞞をよしとする連中を相手に、案件をいくつもこなしてきたから非常識については耐性があると自認していた。しかしあの夜見たアレは、なんと言えばいいのか……そう、それも知りたかったから、訪ねることにした。そうそう、それと、あんたの力をいい形で使う方法も考えてきた」
言い終えると、伊達は配膳カウンターに向かった。
できるだけ手の内は明かしてみる。マイナスに生じることはないはずだ。三杯目のビールが注がれた中ジョッキを受け取った伊達は、座敷席に戻った。すると、涙目のマサカズが唐揚げを頬張りながら見上げてきた。
この人は態度や言葉こそ冷たいが、誠実である。吉田と比べ、自分自身のことについても明かしてくれる。頼りたい、この人を。逃げ込みたい、この人に。唐揚げをレモンサワーで流し込んだマサカズは、大き目のポーチから鍵を取り出し、それをテーブルに置いた。ビールジョッキを手にした伊達は腰を下ろしながら鍵を見て、「なにこれ?」と呟いた。
「僕の、最大の秘密です。この鍵を差し込んで……」
マサカズの言葉を伊達は左手で遮り、深く息を吸い込むと右手でビールをゴクリと呑み込んだ。
「すまない、失礼だとは思う。けど、ここから先は今の関係性だと互いにとってよくない」
青年のこの告白にはおそらくはウソがない。マサカズの真剣な様子を伊達はそう分析した。
「関係性って、どういうことです?」
「署名捺印は後日でいい。口頭でも契約は成立できる。なぁあんた、俺と顧問契約を結ばないか?」
伊達の提案に、マサカズは理解が追いつかずキョトンとした顔で何度も瞬きした。
「顧問弁護士として、これから聞くあんたの秘密は墓場までもっていく。守秘義務というやつだ」
「つまり、伊達さんが僕の、僕なんかの弁護士に?」
「そうだ。今ここで依頼してくれればいい。どうだ?」
「で、でも……伊達さんみたいな人って、その、お高いんでしょ?」
月収二十万足らずのフリーターが顧問弁護士をつける。どうにも現実感に欠ける。吉田から渡された、合計して三百万円ほどの報酬も、もちろん金庫の大金にも手はつけておらず、マサカズは今後もそうするつもりはなかった。消極的な彼に、伊達はジョッキを手にしたまま身を乗り出した。
「しばらくはいらない。契約上、毎月顧問料は発生するが、いずれまとめて支払ってくれればそれでいい。気持ちだけでもってことなら、月に千円でもいい。もちろん、月額を千円って意味じゃなく、月額顧問料の一部って形だけど」
「けど、二十八にもなってフリーターの僕じゃ、ちょっとムリかな」
伊達は鍵を見下ろし、ゆっくりと頷いた。
「俺はある計画を持ってきた。あんたの力を有効的に使い、社会貢献もできる。そうすれば、あんたは想像以上の金額を手に入れられる」
力強い言葉にマサカズは表情を強ばらせ、しばらく視線を宙に泳がせ、首をゆっくりと傾け、素早く瞬きを繰り返すと、穏やかな様子で深く頷き返し、「じゃあ、お願いします。顧問弁護士になってください」と口にした。伊達はジョッキを置くとマサカズに手を差し伸べ、二人は唐揚げの上で握手を交わした。
「吉田って、オヤジが顧問してる池袋ドラゴンって半グレグループの幹部だぞ。何でもアリの犯罪集団だ」
「えっ!? そ、そんなはずは」
「オールバックで嫌な目をしたヤツだよ。マサカズはあんな連中の手伝いをさせられてたのか」
マサカズは握手ののち、鍵の力や吉田からの接触と、彼の依頼で何度も荒くれたちを蹴り倒してきたことを説明した。伊達はそれをシャープペンでノートに書き記していた。
「えっと、伊達さん。二つほど質問いいです?」
「うん」
「“オヤジ”って誰です? あと、“あんた”から“マサカズ”呼び?」
「“オヤジ”は、あ、ついついか。俺のところの所長の弁護士。ウチは吉田たちみたいなヤバ目の顧客が多いんだよ。それと名前呼びなのはオヤジゆずりだ。オヤジは顧客を必ず名前で呼ぶんだよ。理由は聞いたことないけど、相手が頑ななヤツばかりだからかな? なんとなくいいなと思って。俺はそれをパクっている」
他人から“マサカズ”と呼ばれるのはいつ以来だったか。いや、それよりも問題は吉田が反社会勢力であるという点だ。考えをまとめたマサカズは、それを伊達に語った。
「えっと、つまりこういうことですか? 吉田は競合する反社の相手を、僕を使って潰していった?」
「ああ、そしてそのあと手下に金目のもの、金庫やクスリ、名簿なんかを運び出させる。これはいわゆるタタキって言われる手口だ。どういった方法かはわからないが、吉田はカルルスを監視していたんだろうな。で、お前の超能力に目をつけた。ちなみになんだが、お前が潰した相手のうちいくつかはウチが顧問をしている団体だったよ」
状況をテキパキとまとめた伊達がマサカズに目を向けると、彼は顔を下ろし小さく震え、嗚咽を漏らしていた。
「なんとなく、なんとなくですけど……そーなのかなって思ってはいたんですよ。僕、強盗の手伝いをして、悪いことしている連中とは言っても、それに大ケガさせてきたんですね。これじゃ兄貴にまたバカにされる」
声も震えている。これでは持ちかけようとしていた計画も実現は難しい。伊達は人差し指で眼鏡を直し、「もうやめればいい。お前にとっては難しい方法かもしれないけど、俺に考えがある」と告げると、マサカズは顔を上げ、何度も首を縦に強く振った。
自分の顧客関係の中でもとびきりの悪党をピックアップし、井沢から得る情報を駆使して完璧なタタキの絵作りをし、それをこの目の前で嬉しそうに唐揚げを食べている青年に実行させる。それこそが伊達の立てた計画だった。だが、彼の性格では無理だろう。大金を得られるチャンスを提案しても彼はおそらく拒絶し、こちらを軽蔑する。彼は驚異的な力を持ちながら、望まぬ暴力には心を病んでしまう善良な青年だ。
伊達は腕を組み、「じゃあ辞め方を説明する」と、マサカズに告げた。今はともかく、このチリチリ頭の彼から信用と信頼を得ていく時間帯である。彼にとって最優先に望む結果を与えなければ。伊達は考えを切り換え、マサカズに説明を始めた。
彼の言うことを聞く。それが最優先とするべき方針だ。マサカズはそう心に決め、伊達の説明を熱心にスマートフォンのメモアプリに入力した。
【無料版】第1話 ─変身!正義のヒーローになろう! Chapter9
再び湯船に浸かっていたマサカズは、つい先ほどまで伊達と食事処でやりとりした内容を改めて整理していた。
歌舞伎町の夜、金庫を抱えて窓から飛び出したあと、伊達は指紋や頭髪、名簿や記録書類など、弁護士としておよそ考えられる証拠を隠滅したと言っていた。あの当時、夜の雑居ビルには自分や登別たち以外誰もおらず、二度の銃声にも反応する者がいなかったため、時間は充分にとれたらしい。自分たちと繋がる名簿や貸し出しの記録、物的証拠も消えた。そうなると自分や伊達は、捜査当局から嫌疑をかけられる様な存在ではないらしい。従って捜査線上に上がるとも考え辛いということだ。反社会的勢力である非合法の金貸しへの強盗殺人の疑いの目は、同様の組織に向けられているはずだそうだ。
奪い去った金庫をアパートで保管している件についても話をしておいた。ただ、中にあった札束については触れてはいないままだ。
今後の問題としては、一部始終を知っている吉田である。対処方法は伊達から伝授された。とても簡単ではあるのだが、できる自信が今ひとつない。マサカズは今後の段取りをあらためて頭の中で確認しつつ、湯船を出た。伊達は今ごろあのサウナにいるはずだから、また食事処で落ち合おう。アドレスは交換済みなので、居場所はメッセンジャーで送っておこう。そう決めたマサカズは、着替え場に向かった。
誰もいない着替え場のロッカーの前でマサカズがトランクスを穿くと、その背中に低く掠れた声で、「山田正一だな」という言葉がかけられた。マサカズはすかさずロッカーの中のポーチから錠前を取り出した。鍵を刺し込みそれを回したものの、マサカズは、強引に振り向かされた。目の前にいたのは、とてつもなく大きい男だった。ポロシャツに短パン姿で、その全身には顔も含めて入れ墨が掘られていた。痺れを感じながら、マサカズは怪物との遭遇に恐れおののいてしまった。そして力の滾りが走り始めたその時、入れ墨の右ストレートを食らってしまったマサカズは、ロッカーに叩きつけられた。防御はなんとか間に合ったようだが、衝撃で背中がじんじんと痛む。銃弾をものともしなかったのに、拳でここまでの被害を受けるということは、つまり鍵の力は本格的に発動するまでに、若干だが時間がかかる様である。マサカズはなんとか体勢を立て直した。
手にしていた鍵は、錠から露出している持ち手の部分が折れてしまった。後手でロッカーから目出し帽を取り出したマサカズは、怪物の出方を伺った。左手を下ろし、右手を胸の高さまで構え、巨体には似合わぬ軽やかなフットワークで全身を上下させている。格闘技に詳しくはなかったが、こいつがその道の習熟者であることはマサカズにもなんとなくだがわかった。「吉田さんの言うこときく?」男はそう呟いた。マサカズは「いやです」と返事をすると、パンツ一枚、目だし帽を被った姿でその場から逃げ出した。できるだけ速く走りたかったが、思ったほどの速度は出ず、追ってきた男との差はそれほど開いてはいない。
裸足のまま店を出たマサカズは、この事態を解決するべき場所を探した。すぐ目に入ったのは、電気の落ちているゲームセンターだった。マサカズはガラス戸を蹴破ると、店内に足を踏み入れた。非常灯も消えており、ここは確か先月廃業したばかりだと伊達が言っていた。マサカズは振り返り、呼吸を整えた。
「吉田さんに頼まれたのか!」
真っ暗な店内にやってきた怪物に向け、マサカズは問うた。
「言うこと聞かねぇんなら、聞くように躾けるってことだ」
反抗的な態度を取った途端、暴力で脅迫をしてくるとは油断のならない相手だ。しかしおかげで伊達の立ててくれた計画も迷いがなく実行に移すことができる。両拳をぎこちなく構えたマサカズは頬を引き攣らせ、ありったけの闘志を寄せ集めた。すると、男が素早く掴みかかってきた。マサカズは拳を放ったが、それは鋭く風を切る音と共に宙を切り、次の瞬間、腹部を抱きかかえられ、そのまま押し込まれた。メダルプッシャーの大型筐体に背中を打ち付けたマサカズは、これまでにない衝撃に呻きを漏らした。入れ墨の男はマサカズの胴を抱き締めたまま尚も前進して圧迫してきたが、マサカズは踏みとどまり、遂には押し返した。胴締めを解いた男は目を丸くし、口をぽかんと開けた。
子供のころからじゃれ合うことはあったものの、きちんとした喧嘩などしたこともない。戦闘の経験もなかったが、刺客であろう怪物のキョトンとした様子を見るうちに、マサカズは対抗できる自信を抱きつつあった。
入れ墨の男は攻撃手段を打撃に切り換えた。手足の矢がつぎつぎと降りかかったが痛みはなく、くすぐられる態度であり、マサカズはビクともせずその全てを受けきった。死んでもおかしくないほどの打撃を何度も受けた。もういいだろう。顔を歪めて息を荒くする怪物に、意を決したマサカズは突っ込んだ。弾丸のような速度で相手の分厚い胸板に肩からぶつかると、衝撃に男は吹き飛ばされ、クレーンゲーム機に頭から激突した。ガラスの割れた筐体に頭を突っ込んでいた男は血を吐き、気を失っていた。全力での体当たりだったはずなので、かなりのダメージを負わせたはずだ。マサカズは戦いの終わりに安堵したが、怪我を負わせた相手への心配する気持ちはほとんど沸いてこなかった。
「マサカズ、ここか?」
店の入り口から伊達の声がしたので、マサカズは手を振りながらそちらへと向かった。
「風呂から見させてもらったけど、マサカズがやったアレは、瓜原って男だ」
「どんな人なんです?」
『いざないの湯』からほど近いファストフード店の二階のカウンター席に、マサカズと伊達は並んで座っていた。チーズバーガーを手にしていた伊達はスマートフォンを取り出し、しばらくそれを操作すると画面をマサカズに向けた。そこにはひとりの男が映し出されていた。上半身は裸で、薄く指の出たグローブをはめた両手を挙げ、なにやら勝ち誇っているようでもある。解像度こそ低かったが、この男はつい先ほどまでゲームセンターで果たし合いをした入れ墨のあの怪物である。マサカズは小さな声で「格闘家?」と尋ねた。
「瓜原って、地下格闘技大会のチャンピオンだ。動画で試合を見たこともあるけど、尋常じゃないほど強い。まぁ、真っ当なカタギじゃないし反社の用心棒もやってるから、裏の試合しか出られないわけだけど。で、吉田の依頼でマサカズを脅しにきたってことだよな」
「たぶん……でも文句を言ったのは今日ですよ。いくらなんでも早すぎません?」
「躊躇や迷いがないんだよ。奴らはフローチャートを最短の工程でテキパキと進める。ムダがないんだよな」
早口でそう語る伊達を横目に、マサカズは紙コップのコーヒーを口に運んだ。
「だったら俺たちも速攻だ。例の計画、上手くいくようなら今夜にでも済ませよう」
「ええ。吉田は土日の夜だったら、必ず池袋のガールズバーにいるって言ってましたから」
“ガールズバー”という言葉に、伊達は僅かだが鼻を鳴らせ、口の端を吊り上げた。
「服とか荷物とかロッカーから持ってきてくれて、ほんと助かりました。あのままだとパンイチで目出し帽の変質者でしたし。唐揚げ代もちゃんと清算してくれたし、伊達さんってキレ者って感じです」
「まあね」
判断の速さは吉田との共通点とも言えるため、伊達はそれを自慢したくはなかった。
マサカズはポケットから鍵を取り出した。二つに割れてしまったそれは、今となってはここに来る途中、ホームセンターで購入したラジオペンチを使うしか付け外しができず、不便な代物である。このままでは着替え場でやれた様に、咄嗟には鍵の力を頼ることはできない。
「なんなんでしょう。コレって」
「俺にわかるわけないだろ」
掌に鍵を乗せたマサカズの疑問に、伊達は素っ気なく返した。
「昔、子供のころだったんですけど、僕、鍵で父親を助けたことがあったんです」
「ん? それは井沢さんの調査報告書にはない情報だな」
「結果的には大事には至らずに済んだんですけど、親父の工場で誤ってシャッターが閉まってしまった状況で火事があって、親父が中に閉じ込められていて。たまたま親父に合鍵を届ける用事があったから、それでシャッターを開けたんです。消防署に電話したあと、親父、すっごく喜んでくれて。僕も嬉しくって」
「小さな英雄だな。つまりだ……それはお前の超能力が具現化したものであって、過去の成功体験から鍵という形となって現れた。そう言いたいのか?」
伊達の指摘に、マサカズは目を大きく見開いた。
「です、です、です。あー、それだ。言いたかったのは。凄いですね、伊達さん。伊達さんこそ能力者だ」
「違う。これは仕事で覚えた通常能力だ。もちろん、人より高いという自信はあるけど。それより今からの件が上手く行ったら、明日には事務所に来てくれよ。正式契約を結びたい」
「はい、あ、午後でいいですか? さっきも話したようにこの力って使いすぎると後でドッと疲れてしまうんです。今日ぐらいだと、たぶん午前中は寝てると思うんで」
「じゃあ午後二時だ。実印を忘れるなよ。場所はわかるよな」
「名刺のですよね」
淡々としたやりとりを続ける中、マサカズは手にした紙コップが小刻みに震えているのに気づいた。瓜原という地下格闘技王者のタックルや打撃を全て凌ぎきり、たった一発の体当たりで失神させてしまった。なんの取り柄もなく冴えないフリーターでアラサーの自分が。この震えは恐怖ではなく、興奮から来るものである。コップをカウンターに置いたマサカズは、力を持ってから初めて、確かな充実感を得ていた。
【無料版】第1話 ─変身!正義のヒーローになろう! Chapter10
ガールズバーの事務室には、マサカズと吉田の二人しかいなかった。投げつけられたスマートフォンを、椅子に腰掛けていた吉田は両手で受け止めた。髑髏のデザインが施されたケースを見て、吉田は「瓜原……?」と漏らした。
「ムダだったね。あんたはオレの力を見たことないから間違えた。それの持ち主、あの入れ墨男程度じゃオレには太刀打ちできない」
抑揚をできるだけ抑え、冷淡さを心がけ、マサカズは座っていた吉田を見下ろし言い放った。吉田の表情は強ばっており、いつもの余裕は消えていた。
「もう、アンタからの仕事は請けない。ここで縁を切る。立場をわかっていない? なら好きにしろ。そうなったらアンタには瓜原にしたこと以上の暴力でお返しをする」
告げたのち、マサカズは壁に拳を打ち付けた。穴が空いたが壁材は思っていたより脆く、期待していた圧力を吉田には与えられないだろうと思われる。あの入れ墨の怪物以上のデモンストレーションをする必要がある。そう思ったマサカズは事務所の中を見渡した。
「わかった! わかったって! なんだ? カネか? それとも女か? ここには両方あるぞ!」
吉田の言葉に、マサカズは眉を顰めた。
「あ、どっちもいらないです。僕はただ、もうこれ以上半グレ同士の潰し合いに加担したくないだけです」
想定外だった吉田の狼狽ぶりに、マサカズは口調を作らず返答してしまった。
「えっと、あれだ。オレ、相棒ができたんだよ。超キレ者だ。今のオレならアンタや池袋ドラゴンの動向や、なんなら住んでるところとかオンナや家族だって特定できる。井沢さんとパイプもできたんでね」
吉田と縁を切るためには、単純に暴力で脅し、これまでにない冷淡な態度で接し、まだ山田正一が知り得ていないであろう情報をチラつかせ、吉田にこれまでとは違う自分を見せつけるだけでよい。伊達の用意した脚本は暗記できなかったが、内容はこれで概ね合っているはずである。井沢という裏稼業のベテランは吉田も利用しているらしいので、その名前を出すことも効果的であるはずだ。
「な、なんで井沢? お、お前、なにがあった? え? さ、さっきだよな。五時間ぐらい前? な、なんで?」
吉田は伊達という知恵袋ができた自分に対して困惑しているようでもある。マサカズは屈み込み、吉田の肩を軽く掴んだ。言葉にもならない小さな悲鳴を漏らし、吉田は首を横に振った。
「これっきりだ。瓜原をぶつけてきたのは好都合だったよ。おかげで僕はいつもより乱暴になれる。あんな化け物みたいなの制裁に仕向けるなんて頭にきたよ、さすがに。いいか? 今から僕とアンタは出会う前に戻る。約束してくれ。それを破ったら、お互い今よりひどいことになる。随分と儲けたんだろ? ならもういいじゃないか」
すんなりと脅迫できてしまったことに、マサカズは軽く驚いていた。吉田は無言のまま何度も首を縦に振った。
「じゃあ、スマホ、ちょうだい」
マサカズの要求に、吉田は目を逸らした。それを拒絶と受け取ったマサカズは両手に力を込め、吉田を肩から圧迫した。座っていた椅子の脚が床を軋ませると吉田は遂に首を縦に振り、「はい〜」と、情けない声を上げた。
事務所から出たマサカズは繁華街の路地裏まで進み、電柱に寄りかかっていた伊達に、吉田から没収した三台のスマートフォンを手渡した。

「上手くいったみたいだな、マサカズ」
「言われた通り、スマホは全部自動ロックを解除させました。軽く中を見ましたけど、赤いのは情報がそれなりに入っていて、多分メインのやつだと思います」
「池ドラはセキュリティ意識が薄いってオヤジが言ってたけど、こりゃ相当だな」
赤いスマートフォンを操作しながら、伊達は嬉しそうにそう言った。
「壁を壊して肩を掴んだだけなのに、吉田があそこまでビビったのは、正直予想外でした」
「暴力使わせるヤツは暴力に弱いんだよ」
「そうなんですか?」
「いつ自分が逆に被害者になるか、あの類はそれを常に恐れている。目の前に迫る暴力に対して、いつもの狡猾さや卑劣さは発揮できなくなることが多い。吉田がマサカズの力を直接見てこなかったこともいい結果に繋がったな」
伊達の説明は経験に基づいたものなのだろうが、マサカズは納得までには至れなかった。
二日後、マサカズはいつもの様に書店での仕事を終え、折りたたんだエプロンをロッカーに収め、私物のリュックを背負った。
「お疲れさまでーす」
七浦葵に声をかけられたマサカズは、「お疲れ様」と返事をして書店を後にした。
夕暮れのなか家路につきながら、マサカズは想像してみた。瓜原のような屈強な化け物を瞬殺する自分を見たら、あの小柄な眼鏡の後輩はどう思うのだろう。おそらく、怖がるのだろう。いわゆるドン引きというやつだ。そんな結論に至ったマサカズがアパートの前まで帰ってくると、そこには銀色のオートバイとヘルメットを手にしたスーツ姿の伊達の姿があった。
「井沢さんに調べてもらった。今のところ吉田に動きはない。俺たちの計画は成功したと言ってもいいだろう。あと、瓜原は入院した」
六畳のワンルームで、伊達に向かってマサカズは二度小さく強く頷いた。
「それで、これからどうするんです? 伊達さん、温泉で言ってましたよね、鍵の力をいい形で使う方法があるって? どんなのです?」
マサカズの質問に、あぐらをかいていた伊達は気まずそうに顔を顰めた。
「すまない。あの時点で俺が考えていたのは、俺が知っているワル中のワルをその力で叩き潰すって手段だったんだ」
「あ、いいじゃないです、それ」
「いやムリだろ。潰すだけじゃなくて、連中の持ち金を奪い取るまでがセットなのだから」
「あ、それは嫌ですね。だったら奪い取らなきゃいいじゃないですか」
「それだとタダ働きだろ? どうやって俺の顧問料を払う? あ、吉田からもらった金があったか」
伊達が掌を拳で叩くと、マサカズはのそのそと立ち上がり、部屋の隅にあるタオルが被せられた四角い塊まで足を運んだ。
「それ、なんだ? 前から気になってたんだけど。やっぱりアレか?」
その問いに、マサカズは無言のままタオルを手に取った。現れた黒い金庫に、「やっぱりアレか?」の見込みが的中した伊達は眼鏡を人差し指で直した。マサカズは金庫を開けると札束の一つを取り出し、それを伊達に見せた。
「吉田からの報酬も……これも、僕は今のところ使うつもりはありません」
「そうか……すまない、金庫に現金が入っているとは……って、そりゃそうか」
「伊達さんは悪くないですよ。でも結果的には強盗殺人ってやつですよね」
「まぁ、そりゃそうなんだけどな。だけどな、罪悪感は持たなくていい」
「ムリですよ。そんなの」
「罪と罪悪感を切り離すんだ。鍵の件を秘密にしたいのなら、そうするしかない」
「まぁ、努力はしますけど」
吐血した登別の引き攣った顔は、いわゆる断末魔のそれだったのだろう。思い出してしまったマサカズは恐ろしくなり、札束を金庫に戻して伊達の前にドスンと座り込んだ。
「俺に時間をくれ。鍵の使い道について、最適な絵図を描く」
「お願いします」
「それとな、ヘルメットを用意してくれ。俺の移動手段は主にバイクだ。共に行動する機会も今後増えていくだろうし」
「はい」
「いいか? タイプはなんでもいいけど規格が重要だ。俺のSRXは排気量が400CCだ。買うとき、店員にそう説明しておいてくれ」
「規格? そんなのあるんですか?」
「安全規格だ。規程されたものじゃないと、万が一のとき適正な賠償を受けられない」
「は、はい」
しかしそつのない人だ。マサカズは伊達に尊敬の念を抱いていた。これまでの人生で、彼のようなテキパキと指示を出す人物と出会ったことがない。そうなると、ひとつ大きな疑問が浮かんでくる。
「そう言えば、なんで伊達さんは借金なんてしたんです? 弁護士さんって儲かるんでしょ?」
「…………」
伊達は即答しなかった。しばらくの沈黙ののち彼は、「この部屋、煙草ってOK?」と尋ねた。
「別にいいですけど、灰皿とかないですよ」
リュックから携帯灰皿と煙草、オイルライターを取り出した伊達は、「あのな。俺はギャンブルと女遊びに目がないんだ」と呟いた。
「伊達さんが? 冗談でしょ」
「マジなんだよ。下手なクセに負けず嫌いで計画性も吹っ飛んでカネを突っ込み、女からは気前がいいって思われたい見栄っ張りだからアホみたいに貢ぐ」
煙草をくわえた伊達は、それに火を点け、深くひとふかしした。
「意外ですね。なら伊達さんの場合、自業自得ってやつなんですね」
「言いやがるな。まぁけど、おっしゃる通りだ。しかしな、マサカズのあの力を見てから、サッパリそっちへの興味を失った。登別たちに脅されたってこともあるのかもしれないけど、今の俺はお前に賭けることにしか興味がわかない」
「あー、じゃあ良かったのかも」
「ああ」
マサカズは窓を開け、バイクに跨がる伊達を見下ろした。スーツ姿にジェットタイプのヘルメットを被り、黒い革の手袋をはめた伊達は、とにかく凛々しく格好が良い。走り去るバイクを見送りながら、マサカズは自分もいずれ免許でも取ろうかと考えていた。なぜなら、その方が正義のヒーローっぽいと思えたからだ。窓を閉ざそうとしたマサカズだったが、ヤニの臭いがまだ消えていなかったため、パタパタと手をはらった。
第1話「変身! 正義のヒーローになろう!」おわり
【無料版】第2話─可哀想な女の子を救ってあげよう!」Chapter1─
扉を開け、アパートの外廊下に出たマサカズは、外気の様子を窺うと部屋に戻った。
六月も後半に入ろうとしているのに、今日は妙に寒い。おかげで昨晩は扇風機をつけることもなく快適に過ごせたのだが、外出となると話は別だ。スマートフォンで天気を確かめてみたところ、夜になるともっと冷え込むらしく、この異常なまでの涼しさ、というか寒さは明日いっぱいまで続くらしい。ここ最近はずっとTシャツ一枚で外出していたのだが、今日、明日はなにか上着が必要だ。マサカズは四月以来となる紺のテイラードジャケットを羽織ることにした。
去って行くオートバイを見送ってから二日が経っていたが、伊達からの連絡はなかった。「俺に時間をくれ。鍵の使い道について、最適な絵図を描く」そう言っていたから、次に連絡があるとしたら何らかの計画を持ちかけてくるタイミングのはずだ。マサカズは仕事中でも常にスマートフォンを気をかけ、いつ伊達から知らせがあっても即座に対応できるように心がけていた。
その日のアルバイトを終えたマサカズは、駅のショッピングセンターにある合鍵作製の専門店までやってきた。店主である中年の男とカウンター越しに向き合ったマサカズは、持ち手の部分が折れた鍵を見せ、「これ、直してくれます?」と尋ねた。スーパー銭湯の着替え場で 瓜原の右ストレートを咄嗟に防ごうとした際、このロッカーキーは折れてしまった。今では抜き差しするのにラジオペンチが必要であり、緊急事態に対応するためにも不便は解消しなければならなかった。店主は鍵を観察し、「それなら、合鍵作った方が早くて安くつきますよ」と言ってきた。
「そうなんですか?」
「ウチの店だと修理の場合、機材の関係で本社に送る必要があるんですよ。だいたい一週間ぐらいはかかりますね。合鍵でしたら今の時間なら十分ぐらいいただけましたら」
「じゃあ、一応お願いします」
この鍵がどういった理屈で現象を生じさせるのか、マサカズは全くのところわかっていなかった。しかしいくらなんでもコピーでは力は奮えないだろう。諦めながらそれでもマサカズは鍵を店主に渡し、喫茶店で十五分ほど時間を潰し、再び専門店まで戻り、合鍵と折れた鍵を受け取った。いずれは修理を頼むべきだが、ひとまずこの合鍵を試してみよう。そう考えたマサカズは、ショッピングセンターの公衆トイレの個室に入り、便器に腰を下ろした。
鞄から南京錠を取り出したマサカズは、合鍵を差し込み、それを捻った。全身が痺れが入り、力の漲りを確かに感じる。「なんなんだよ。これ。デタラメ過ぎるだろ」マサカズは小さくそう呟いた。
合鍵でもあの力は使えてしまう。その事実にマサカズは困惑してしまったが、やるべきことを決め、合鍵の専門店をみたび訪れた。
「すみません、さっきのコレ、もう九本ほどコピーしてもらえませんか?」
「九本? でしたら申込書に記載をお願いします。ウチだと三本以上は必要なんですよ。あと、受け渡しは明日になります」
「わかりました。それでいいです」
マサカズが答えると、店主はA4大の申込用紙とボールペンを持ってきた。申込用紙の必須項目に『合鍵作製の用途と理由』という項目があったため、マサカズは少しばかり考え、『会社のマスターキーのコピー。従業員に配布するため』と書き込んだ。
翌朝、マサカズは九本の合鍵と折れたオリジナルの鍵を専門店で受け取り、料金を支払った。これで折れたマスターキーが一本、スペアキーが十本となった。力が使えるのなら、鍵の修理は必要ない。一週間もマスターキーを預けるのはそもそも不安がある。今後はこのスペアの方を使っていこう。そう決めたマサカズは折れた鍵をジャケットのポケットに入れ、十本のスペアキーを腰に提げていたポーチに納めた。
鍵を受領したあと仕事に就き、書店のレジに立つマサカズはレシートと釣り銭を客に手渡した。すると突然、瓜原の入れ墨だらけの強面が頭の中をよぎった。
しばらくして休憩室のソファで休んでいたところ、吐血した登別の断末魔が浮かんだ。ここ数日、フラッシュバックとでも言うのだろうか、凄惨な記憶が何度も甦る。自分は人殺しだ。伊達は当局の目が自分たちに向くことはまずない、と断言していたが、今でも交番の前は避けるようにしているし、スマートフォンで“カルルス金融”というキーワードで検索をし、事件の捜査状況の進展を見守るようにしていた。だが、“歌舞伎町ヤミ金強殺事件”という名称が付けられていた事件についての報道は、三日ほどが経過してから全く取り扱われなくなり、今では風化してしまっているとも言ってよいほどだ。瓜原の件については報じられてすらいないが、伊達の話によると入院後スーパー銭湯への不法侵入で逮捕されたらしく、余罪についても事情聴取を受けているらしい。
山田正一脅迫のため、不法侵入した。そんな真実を瓜原は語らない。依頼主の吉田を守り、今後も彼らから高い利益を享受するためには、不法侵入の理由など酒に酔ったから、などとお茶を濁すのが連中のいつもの手段だ。アパートで伊達はそう言い切った。あれから何日か経つが警察からの連絡もないので、彼の予想はおそらく外れてはいないのだろう。マサカズはソファで背を丸め指を組み、両の踵を小さく上げ下げした。
「貧乏揺すりは行儀が悪いですよ~」
軽やかな口調でそう注意をし、目の前のソファに腰を下ろしたのは後輩の同僚、七浦葵だった。マサカズは慌てて両膝を押さえ、彼女に顔を上げた。
「最近、山田さんってなんか最近……うーん、なんだ? なんだろ?」
「ボーッとしてたり、考え事して反応が鈍かったり、とか?」
マサカズがそう言うと、彼女は目を丸くし、人差し指でマサカズを指した。
「うーわー、それそれそれ、自己分析できてるんですね」
「まぁね」
「よければ原因や理由など」
「人、殺しちゃってさ」
その即答に七浦葵は両手を膝に乗せ、表情を消し横を向いて俯いた。機嫌を損ねてしまった。そう感じたマサカズは両手を広げて、「冗談、冗談、ちょっと体調悪いだけ」と早口で弁解した。七浦はゆっくりと顔を向けると笑顔になった。
「ですよねー」
「ですよ。ですよ、ですよ」
冗談としてではあったが、秘密の告白で暗鬱とした気分が少しは晴れたようにも思えた。しかし、二度と使える手段ではない。マサカズは何度かうなずき、腰を上げ売り場へ戻っていった。
仕事を終えたマサカズは、アパートの自室であぐらをかいてカップラーメンを啜っていた。腹を満たした彼はスマートフォンを手にし、動画閲覧アプリを立ち上げた。“格闘技入門”、そのようなキーワードで検索してみたところ、いくつもの動画のサムネイルが表示された。
マサカズは立ち上がると、動画が表示されたスマートフォンをカラーボックスの上に置いた。そして身構え、横目で腰の高さほどの画面を見た。動画は『初心者に蹴ってもらった 熱血指導! これであなたもプロの入り口!!』というタイトルだった。現役のキックボクサーが初心者にキックを教える内容である。概要欄にはそう記されていた。フォームを確かめ、見よう見まねで右足を蹴り上げてみたが、バランスを崩して壁に倒れ込んでしまった。すると「うるせー!」という叫びと同時に、壁を強く叩く音が鳴り響いた。
伊達からの連絡があるまで、鍵の力をもっと使いこなせるようになっておきたい。そんな思いつきからの格闘技の練習だったが、六畳しかないこの狭さではその環境を充たしていない。マサカズは「ごめんなさい!」と叫び、ちりちり頭をかいた。
【無料版】第2話 ─可哀想な女の子を救ってあげよう! Chapter2
「格闘技をタダで勉強する方法って、なんかあるかな?」
職場の休憩室で、マサカズは対面のソファに座る七浦にそう尋ねた。
「一日体験とか?」
「それだとなぁ。ある程度のレベルは覚えたいし」
「知り合いのツテとか?」
「いないなぁ」
「そもそもなんで?」
「あ……」
後輩に説明できる理由ではなかったので、マサカズは言葉に詰まった。
「格闘家にジョブチェンですか?」
「あ、いや、まぁ、なんとなく、格闘技できたら格好良いかなって、その程度の気持ちだよ」
なんとか嘘の返事を取りまとめたマサカズは、テーブルに置かれていたレモン味の飴を取った。
「わたしはなんとなく、嫌だな」
「え?」
「格闘技とかする人って、なんか、怖い」
「そうなんだ」
「男の人の暴力って、やだ」
話題を変えるべきだ。口元を歪ませ、顔を顰める七浦の様子を察したマサカズは、「バイクの免許」と口走った。
「取ったんです?」
「いいや、取りたいなって。最近知り合いになった弁護士の人がバイク乗りでさ、ビシっとしたスーツに黒い革手袋で、えらい格好いいなって」
マサカズの説明に七浦は視線を落としてしばらく黙り込み、「あー」と声を上げた。
「情報を処理しました。黒革手袋でスーツの弁護士ライダーに憧れたから、山田さんもバイクの免許を取りたいって話。私が格闘技の話でげんなりしたから、話題を変えてくれたんですね」
「そう、そういうこと」
飴を口にしたマサカズは、それが思っていたより酸っぱすぎると感じた。
「なんか最近、わたしと山田さんってお話する機会が増えてますよね」
「休憩のタイミングが重なることが多いしね」
「わたし、山田さんとお話しするの、好きですよ」
「そうなの?」
「別段話題が面白いってわけではないですけど、なんでしょう。気分がよくなるんです。山田さんの気づかいとかが感じられるので」
「彼氏ともそんな感じなの?」
尋ねてから、マサカズは踏み込みすぎだと後悔した。すると七浦は再び視線を落とした。
「なんでしょう。なんでしょうね。あの人は、山田さんみたく優しくないです」
踏み込みに対してそれを深掘りする返事があったため、マサカズは心をざわつかせ、鼓動が早まり言葉が出なくなった。
「あー、ごめんなさい。本当にごめんなさい」
深々と頭を下げると七浦はソファから立ち上がり、休憩室を出て行った。
次の日の夕方、梅雨らしく蒸し暑く湿った空気の中、仕事が休みだったマサカズは夕飯のため小岩駅までやってきた。今日は何を食べようか、家か外食か、家ならスーパーかコンビニか。多様な選択肢に悩んでいたマサカズは背後から肩を小さく叩かれた。
「さすが地元民、ですね」
マサカズが振り返ると、そこにはリュックを背負った小柄な後輩の姿があった。
「七浦さんは、仕事終わり?」
七浦がエプロン姿ではなかったので、マサカズはそう尋ねた。
「もちろんです。山田さんは?」
「僕は晩メシ」
「あ、わたしも腹ぺこだったりして」
七浦はにっこりと微笑むと、小さく跳ね、マサカズに背中を向けた。
「ラーメンでいいの?」
「大好きです。ラーメン女子と呼んでください」
ラーメン店のカウンターに、マサカズは七浦と並んで座っていた。ここは十二席のU字のカウンター席のみの小さな店舗であり、マサカズにとっては週に一度は足を運ぶ行きつけだった。店員から二人の前に醤油ラーメンとチャーシューメンが差し出された。七浦は大盛りのチャーシュー麺に笑みを浮かべ、箸を割った。
「ここ変わっててさ、ラーメンのあとはサービスでコーヒー頼めるんだよ」
「回転率はどーなるんでしょ?」
七浦は、勢い良くチャーシューメンを啜った。
「だよなー、結構人気店なのにな」
「けどいいですね。山田さんとお話できます」
「あのさぁ……」
言いかけたところで言葉を止め、マサカズは目の前で湯気を立てるラーメンに集中することにした。
二人の前にはラーメンの丼ではなく、アイスコーヒーのグラスが入れ替わるように置かれていた。
「小説、書いてるの?」
「絶賛連載中です。現在物語は佳境にさしかかり、いわゆるクライマックスというやつです」
「本にはならないの?」
「そんなのごく一部です。ほとんどがわたしみたくサイトにアップしても読者だってふた桁がせいぜいですし」
ネットでの小説家活動というものがどういった実態なのかマサカズには想像もできなかったため、彼はただ頷くしかなかった。
「でもアニメ化の夢、捨ててませんし。そのためにもまずは書籍化と漫画化ですね」
「あー、ラノベ原作の漫画、多いもんな」
「山田さんは読んだりします?」
「あんまりかなぁ。なんかああいうのってRPGとかのゲームとか詳しくないと前提自体がわからないのが多いような気がするし、最近だと女性向けのも増えてて、僕はそっちは読まないし。けどそうだ、アニメにもなったアレ、生まれ変わって松明になるやつ、アレは一巻だけ読んだ」
「『転生したらタイマツになって、台風襲来でまさに風前の灯火だったけど、美少女パーティーに握られまくった』ですよね。アレ、面白かったです」
「七浦さんってやっぱり読書家なの?」
「はい」
グラスを手にした七浦は、それを口に運んだ。横目でそれを見ながら、マサカズは苛立ちを覚えつつあった。異性と並んでアイスコーヒーを飲む。会話も弾み、彼女もなにやら楽しそうではあるが、これ以上は、ない。ひと月ほど前には、この小さな後輩との関係が進展する可能性もワンチャンスあるような気もしていた。こうやって夕飯を共にするようになったのでそれは叶ったのかもしれないが、この先はさすがにない。そう言えば、昨日彼女は彼氏が優しくないと言っていた。あるいは近々、別れてしまう可能性もある。いや、そもそも自分はこの子のことが好きなのか、その感情自体も曖昧だ。マサカズはアイスコーヒーをひと飲みすると、グラスをカウンターに置いた。
「ここのラーメン、美味しいですね」
「また食べに来るといいよ」
「じゃあ、また一緒に」
「僕と七浦さんだと、シフト的になかなかタイミングを合わせるのが難しいよな」
「だから今日みたくわたしが働いてて、山田さんがお休みのときとかに」
「あぁ、なるほど」
納得はしたものの、この後輩がなぜ自分にここまで懐いてくるのか、マサカズにはそれがわからなかった。
「七浦さんって男の友だちとかって、いるの?」
「まさか。アイツ、すごく嫉妬深いし」
「なるほど」
となると、この並んでコーヒーと会話を楽しむ光景など、“アイツ”の嫉妬の対象にはならないのだろうか。それとも自分は男友達ではなく職場の先輩だから、もし知られたとしても問題がないのだろうか。マサカズは軽く混乱していた。
眼鏡を外した七浦は、それをカウンターの上に置いた。
「わたし、九月で契約終了ですって。さっき、店長から」
彼女の横顔にマサカズは目を移した。目は潤み、何かを言葉にしようとしているのか口を小さく開いたり閉じたりしている。言っている事実はわかるが、なぜこのタイミングで言うのか、その心の道程はまったくわからない。マサカズは「うん」と漏らすように返すだけだった。
【無料版】第2話 ─可哀想な女の子を救ってあげよう! Chapter3
きのう、隣にいたのは小さな後輩だった。彼女は失職を悲しんでいたのか、悔しかったのか、マサカズにはわからなかった。関係も浅くそもそも心情を察する洞察力も持ち合わせておらず、言葉でそれを探れるほどラーメン店のカウンターは落ち着ける場ではなかった。そして今、隣でコーラのグラスを傾けているのは眉間に皺を寄せた弁護士だった。「すまない。鍵の件だが、まだいい絵図が描けない」彼はそう告げた。
「でしたらなんで?」
「定期的に会っておくべきだと判断した」
日が沈んだころ、バイクで小岩のアパートまでやってきた伊達は、都道沿いのバーまでマサカズを連れてきた。初見だったが、こぢんまりとした落ち着ける雰囲気の店だ。伊達とマサカズは同じ感想を抱いていた。
「そうそう、コレ」
マサカズは腰のポーチを開けると、そこから鍵を一本取りだし、伊達に手渡そうとした。伊達は身を引き、首を振った。
「なんなんだ?」
「駅のお店で修理を頼んだところ、合鍵はどうだって話になったんです。で、作ってみたらオリジナルと同じ様な力が出せたんです。若干パワーは落ちてるっぽいんですけど、全然イケますね」
マサカズの説明に、伊達は人差し指で眼鏡を直し、眉を顰めた。
「理解の必要もないということか。それについては」
「わけ、わかんないですよね」
「ああ」
「で、コレ、十本作ったんで、一本は伊達さんに」
そう言うと、マサカズは合鍵を伊達に突きつけた。
「なんで俺が?」
伊達は嫌悪感を顕わにしてそう言った。
「いやだって、この秘密は僕と伊達さんだけでしょ。僕、気になってることがあって、それを伊達さんに試してみて欲しいんですよ」
常に相手の言葉を注意深く読み取り、先回りしてその意図を探ることを生業としていた伊達だったが、マサカズの試して欲しいことが何であるのか想像ができなかった。
「つまりですね、この力って僕以外でも発現するのかって。伊達さん、お願いします。それって最初はコントロールにコツがあって、最初はバランス崩して転んだりしちゃうんですけど、僕、ちゃんとアドバイスとかしますし」
その説明に、伊達は小さく首を横に振った。
「断る」
「どうしてです?」
「解明できていない、理解できない。有り体に言えば得体の知れないそれを試したくない。なんの副作用が俺に降りかかるかもわからない」
「えー、伊達さんそれってちょっと卑怯じゃないですか?」
「卑怯? 俺が?」
慌てる伊達を横目に、マサカズはウイスキーのロックをひと呑みした。いつもならアルコールはビールかサワーだったのだが、店の雰囲気がいかにも小洒落たバーだったため、いつ以来かも思い出せないほど久しぶりのウイスキーだった。
「だってそーでしょ。僕とこの力で関わりたいっていうのに、副作用の危険は僕だけに押しつけてるって……アレ? 違うかな?」
「いや、そう思うのは間違っていない。確かに運命を共有しようってほどの覚悟はない。ただ、現状お前になにも異常が起きていないことを考えると……」
「結果オーライ?」
「そうそうそれだ。新しい試みに対しては慎重にしていれば、俺たちは成功できる」
「でもでも、これは一本持っておいてください。えーと、可能性ですかね? そういった選択肢は広げておきましょう」
突き出されたロッカーキーを、伊達は受け取った。
「悪くない考え方だ。そうだな、知り得た者として俺は受け取っておくべきだな」
高学歴であり、喋ることを生業にしているため自分よりずっと語彙に富んでいるはずの彼だが、出会ってから常にわかり易い言葉を選んでくれている。これがプロの弁護士というものなのか。鍵を受け取り、それをスーツのポケットに入れる伊達を見ながら、マサカズはそう思った。
「伊達さんって独身ですか?」
コーラのグラスを持った伊達の手を見ながら、マサカズはそう尋ねた。
「キャバクラ通いで借金してたんだぜ。彼女もいないよ」
「えっ、伊達さんイケメンで弁護士なのに?」
「モテ期なんて一度もねーよ。だいたい、付き合ってもすぐに言い合いの喧嘩になって別れちまう」
「あー、だからキャバクラか」
グラスに残っていたウイスキーをあおると、マサカズは喉が焼けるような刺激を感じた。
「だ。彼女たちは男を怒らせるようなトークはしないからな」
「伊達さんは僕のこと調べ済みなんでしょうけど、僕はそっちのことなんも知らないし、今後は色々と教えてくださいね」
「まぁ、おいおいな」
「趣味とか好物とか……、あ、ビールがお好きってのはこないだの温泉でわかりましたけど。今日はなんでコーラなんです?」
「バイクだからな」
「あ、そーか」
「サウナでもあれば、一杯やりながらひと晩のんびりしていくんだけど、小岩ってどうなんだ?」
「どうだっけなぁ。銭湯には行ったことがあるけど、サウナはどうだっけ」
「確か……昔はスーパー銭湯があったって聞いたけど」
「あ、それって僕がこっちに越してきたころにはなくなったっぽいです。建物が老朽化して取り壊したって」
「へぇ」
取り留めのないやりとりをしながら、マサカズは二杯目のロックをバーテンに注文した。
「あ、それとなんですけど、目出し帽ってアレ、どうにかなりませんかね?」
「犯罪者っぽいもんな」
「けど顔はかくしておいた方がいいですし。なんかヒーローっぽい仮面とかって、アキバとかで売ってるのかな?」
「それについちゃ、俺に任せてくれるか?」
「心当たりあるんですか?」
「それこそ俺の趣味の領域でな。適当なマスクを見繕っておく」
「カッコイイのでお願いしますよ。あと、できるだけお安く」
「例のカネは、やっぱり手付けずなのか?」
「ええ、自分で納得できる使い道がまだ見つからないので」
「あのさマサカズ、若干踏み込んでもいいか?」
「はぁ?」
「これまで色々な人間を見てきたけど、あれだけの大金に誘惑されないのって、ハッキリ言って破格だぞ」
「そりゃ、道で拾ったとかだったら、とっくに使ってましたよ。もっといいタワマンに越したりとか、海外旅行とか。けど、アレってアレですよ。あんな形で持ってきたりもらったりしたモノですよ。正直なところ怖さの方が勝ります」
マサカズの言葉に、伊達は歌舞伎町での夜を思い出した。登別たちは次々と命を絶たれ、血溜りに身を沈めた。それをしてしまった当事者であるマサカズの気持ちを、これまで数々の犯罪者の弁護人となりその心に深入りしてきたにも関わらず、ここに至るまで伊達はよくわかっていなかった。
二杯目のロックで気持ちが高揚してきたマサカズは、伊達の肩を人差し指でつついた。
「なんだそれは?」
「力とは全然関係ないんですけど、いいです?」
唐突なマサカズの相談に、伊達は「なに?」と突き放すような早口で返答した。
「バイト先の女の子がですがね、妙に親しげにしてくるんですよ。彼氏いるのに」
「へー」
「素っ気ない返事ですね」
「これっぽっちも興味が沸かないからな」
「まー、モテない伊達さんに相談してみるだけムダか」
「嫌味だな。その子はお前を浮気の対象にしているかどうか、真意を知りたいってことか?」
伊達の指摘に、マサカズはグラスを手にして背筋を張った。
「さすがは伊達さん! 僕、そこまでハッキリとした疑問とかってまだだったんですけど、伊達さんはいつも先回りで答えを出してくれる」
「その子とはどこまでいったんだ?」
「昨日、そこの駅前でラーメン食べました。並んで」
「昼飯?」
「晩メシです」
「ほう……」
伊達は小さく何度か頷いた。
「次の確認段階があるとすれば、酒席だな。サシ呑みに誘って乗ってきたら、脈はかなりある」
「そりゃそうですよね」
「好きなの? その子?」
「わかりません」
「なら、慎重にいかないと。歳の差は?」
「八歳年下です」
マサカズの返答に、伊達は身体を大きく引いてコーラをひと口飲んだ。
「そりゃほんと、慎重に行け」
「兄貴的枠って可能性も残念ながらワンチャンありますよね」
「あのさ、マサカズ」
「なんです?」
「“ワンチャン”の用法、間違ってるぞ。ワンチャンス、それは好機を期待した場合の言葉だ」
伊達の指摘に、マサカズはちりちり頭をひとかきし、「そーでしたっけ?」と間抜けな声で返した。
【無料版】第2話 ─可哀想な女の子を救ってあげよう! Chapter4
「無実じゃねぇなんてあり得ないっしょ」
東京地方裁判所の小さな待合室で、伊達は若い坊主頭の青年に毒づかれた。鼠色のスウェットの上下で手錠をかけられ、腰を縄で巻かれ、両隣を刑務官で固められたその青年は椅子に座らされ、立っていた伊達を鋭く睨みつけた。
「なんか言うことねぇの!? この無能!」
「判決は出た。控訴するならその手続きまでは面倒を見る。だけど、そこまでだ」
「はぁ?」
伊達はこの粗野な青年に、今の言葉が理解できていないことをよくわかっていた。
「情状証人をつけるだけつけて、普通なら十年でもおかしくないのを五年にまで縮めたんだ。無能と言われるおぼえはない」
「なにさっきからペラペラペラペラ」
「俺の仕事はここまでだ。これからはお前が考えろ」
最後に、青年でもわかるであろう言葉でそう告げると、伊達は刑務官たちに会釈をして待合室をあとにした。背中に何やらわめき声がぶつけられてきたが、伊達はその言葉の意味を受け止めず黒い革手袋をはめた。
伊達は霞ヶ関の地裁から十分ほどかけ、バイクで水道橋までやってきた。昼過ぎの街路には昼食を求めるビジネスマンたちが溢れていた。バイクを停めた伊達は、駅近くの古びた雑居ビルを訪れた。ビルの三階に、刑事裁判を終えた伊達の目的とする店舗があった。狭い店内は壁一面に本棚が設置され、そこにはプロレス雑誌や試合のパンフレットがぎっしりと詰まっていた。ショーケースにはプロレスラーのサインや、チャンピオンベルトの複製品が飾られ、店内のスピーカーからは勇壮な入場曲が鳴っていた。伊達は、ショーケースのひとつに屈み込んだ。中には頭部だけのマネキンがいくつも置かれ、そのいずれにもマスクマンの着けるそれが被せられていた。
「岩井さん、マスク買いたいんですけど」
伊達に声をかけられた長髪の中年店員が、カウンターから身を乗り出した。
「伊達ちゃんが? マスク?」
「ええ。できればマシーンみたいに顎まで覆っているやつがいいんですけど」
「い、いや、ほんとに? 伊達ちゃんが? あの、伊達ちゃんが?」
店員は伊達の要求に即応できず、疑問を口にするばかりだった。
「あ、俺じゃなくって代理購入ですよ。欲しいって依頼人がいるもので」
「だよねー、伊達ちゃんがマスクになんて、いくらなんでもねぇ」
「別に、マスクマンやルチャ否定論者じゃないですよ、俺」
「いやいやいやいや。前も大激論したでしょ。武道館近くの居酒屋で。あんなのチャラくて認めないって」
「そうでしたっけ」
伊達は記憶を辿ってみたが、武道館近くの居酒屋にてプロレスについて怒声混じりの大激論をした記憶は幾度もあったため、そのいちいちを覚えていなかった。
「じゃあ、岩井さんに修正をお願いします。俺はいい加減で無能なレスラーやプロレスが大嫌いなだけで、スタイル自体は全肯定派です。ルチャであろうと、デスマッチであろうと」
伊達の言葉に岩井はしばらく無言ののち、笑顔で頷いた。
プロレスショップでマスクを購入した伊達は、神保町のカレー店で昼食を摂ることにした。ここは四十年近く続くヨーロッパ風カレーの老舗店であり、司法修習生当時、その濃厚な味に魅了された伊達はそれ以来、月に一度ほどの頻度で足を運んでいた。純喫茶のような上品な内装の店内のテーブル席で、伊達は大盛りのビーフカレーを注文した。
別皿に蒸したジャガイモが丸々二個提供され、これを客の好みのタイミングで食べられるのがこの店の特徴である。伊達は常にカレーライスを半分食べてから、全てのジャガイモを投入するスタイルを好んでいた。
おかしい。今日はなにやら食べ足りない。そんなことはないはずだ。わざわざ大盛りのストロングスタイルで挑んだのに。そんな疑問を抱きながら、会計をすませた伊達は店を出てバイクに向かった。
奇妙な空腹感をかかえたまま、伊達は高田馬場までやってきた。駅から五百メートルほど離れた六階建てのビルの地下駐車場にバイクを停めた彼は、ヘルメットと鞄を手にエレベーターに乗り込み五階まで昇った。エレベーターを降りた伊達は、『柏城法律事務所』と記されたガラス戸を押し開け、壁に付けられたパネルを操作して内扉を解錠し、先に進んでいった。
「五年なんて上出来じゃねぇか」
男にそう言われ、伊達は小さくお辞儀をした。椅子に座る男は伊達とは親子ほど歳が離れており、彼よりはずっと小柄である。三揃えのスーツ姿であり、その色は伊達と同じ灰色だった。
「新件の資料が届いている。デスクに置いといたから、今日中に目を通してくれ。明日の朝にでも打ち合わせがしたい」
「わかりました」
この柏城という男は伊達が所属する法律事務所の所長であり、“オヤジ”と呼び尊敬している人物だった。刑事事件を専門に扱い、暴力団や半グレといった、いわゆる反社会的勢力の弁護を数多く請け負い、経験豊富で無法者に対しても威厳を損なわない胆力を持っていた。彼の言葉は全面的に従うべきと考えていたため、伊達はすぐに自分のデスクに戻り、置かれていたファイルに目を通した。それは先ほどの午前中に判決が下され、依頼人から“無能”呼ばわりされたものと似たような傷害事件であり、伊達にとっては法廷でどう戦うべきかも即断できてしまうような、ありふれた内容でしかなかった。
だから、つい別のことを考えてしまう。あの人懐っこいちりちり頭の青年が持つ異能を、どのように使うべきなのか。最新の情報としてはあの鍵は複製が可能であることだ。もしマサカズ以外に利用ができるのなら、組織化も可能であるのかもしれない。異能者たちがその秘密を守り活動する、これはそう、いわゆる秘密結社というものだ。ぼんやりと浮かんできた計画に、伊達は本業を隅に追いやり没入していった。
夜、自宅である飯田橋の高層マンションまで帰ってきた伊達は、十三階の自室の扉を開けた。2LDKのここには五年前に入居し、窓から見える都会の夜景も気に入っている。上着を脱いだ彼は冷蔵庫から缶ビールを取り出し、広いリビングのソファに腰を下ろした。伊達がスマートフォンの着信を確認してみたところ、十件を超えるメッセージが届いていた。
“ハヤトちゃん、ぼちぼちお店に来てほしい!”
“ダテせんせい、さみしいよう”
“こら! 伊達隼斗! 遂にワタシを怒らせたわね。怒・怒・怒!!!!!!!!!!!!!!”
メッセージに目を通した伊達は、ため息を漏らしビールの缶を開けた。いずれもが以前まで足繁く通い、貢ぎ、その挙げ句殺されかけ、身を滅ぼしかけた原因であるホステスたちからの来店を促す内容である。思えば、なぜ自分はあのような無意味で無価値な遊びにのめり込んでいたのだろう。仕事のストレスが原因なのだろうか。
依頼人の権利を守るため、できうる限りの事情と情状を裁判所に認めさせる。それは誰にでもできる簡単な仕事ではないのに、依頼人からは無能だと罵られる。今日もそうだった。自覚こそなかったが、無意識の不満を溜め込んでいたのだろう。尊敬されたい、誉められたい。そのような欲求を満たすため、彼女たちの待つネオン街に通い詰めていた。我ながら情けないが、そんなところだろう。
“オヤジ”は以前、高田馬場の海鮮居酒屋で、「これは仕事だ。俺たちはカネをもらって連中の自由を勝ち取る。ろくでなし共にどんな態度をとられようが、ただ淡々と接するだけだ。それが嫌なら別の事務所を紹介してやる」と言っていた。その言葉に同意し、あくまでも冷徹にこの仕事をしてきたつもりだったのに、午後からずっと“無能”という言葉がこびりついている。これまではそれをごまかすため、夜の女たちを求めた。しかし、なぜだか今夜はそのような気分になれない。
ホステスたちからのメッセージを全て削除すると、伊達は五十五インチの大型テレビを点け、ゲーム機の電源を入れた。このゲーム機は、三十年ほど昔に発売された家庭用の機種をリメイクしたものである。パッドを手にした伊達は、横スクロールのシューティングゲームを十分ほどプレイした。これもやはり、その当時にリリースされたレトロゲームである。途中で止めてしまった伊達はゲーム機の電源を落とし、テレビのリモコンを操作して動画配信サービスのアプリケーションを起ち上げた。
カブトムシの観察、昭和のプロレスの試合、テレビアニメ-ションのレビュー、そんな三本の動画を立て続けに見た伊達は、ビールを一気に飲み干し、二本目を冷蔵庫に求めた。再びソファに腰掛け、プルトップを引き、ネクタイを緩める。片膝を細かく上下させると伊達は舌打ち混じりに「無能じゃねぇ」と呻った。
テレビを消した伊達は、テーブルの上のノートパソコンを開き、テキストエディタを開いた。彼はまず、『事業計画書』と打ち込んでみた。すると、なにやら晴れやかなそよ風が心の中を吹き抜けていくような気がした。伊達は不敵な笑みを浮かべると「これだ」と呟いた。
その晩、五本目となるビールの空き缶を手にしたまま、伊達はソファで眠りに落ちてしまっていた。その顔は苦悶で歪み、苦しげなうめき声を漏らしていた。ノートパソコンのエディタ画面には、『事業計画書』以上の文字は打たれていなかった。
【無料版】第2話 ─可哀想な女の子を救ってあげよう! Chapter5
伊達がまったく進まない事業計画書に頭を悩ませていた次の日の夜、小さく狭いもつ焼き屋のカウンターに、マサカズと七浦葵の姿があった。「晩メシどう?」ちょうど仕事の上がりが同時刻だったため、ロッカールームでそのような軽い気持ちで誘ったのがきっかけだった。
「かんぱーい」
レモンサワーのグラスを傾けてきた薄い紫のサマーニット姿の彼女に、マサカズも同じようにビールの中ジョッキを傾けた。ガラスが音を立てたのち、二人はひと口目になるアルコールを含んだ。「なら呑みにいきません?」軽い誘いに、七浦葵はそう返してきた。マサカズにとってそれは想定外の答えであり、バーで交わした伊達の言葉を思い出させる内容だった。
この店はロッカールームで慌てて“小岩 飲み屋 オススメ”などといった文言で検索をした結果であり、マサカズも初めての来店だった。伊達と呑んだ都道沿いのバーの方が雰囲気も落ち着いていて、後輩との交流には適しているとも考えられたが、あの店は料金もそこそこ高く、そもそも食事向きではない。ここは十四名がけのカウンターに、テーブル席が三つの小規模な飲食店で、店内には豚の内臓や肉、野菜を炭で焼く煙が立ちこめていた。
駅から歩いて五分もかからない立地だが、ここに辿り着くまでの路地で風俗店やガールズバーを何軒か通り過ぎることになり、マサカズはその都度気まずさから視線を泳がせてしまった。
だが、これは当たりだ。串に刺されたカシラと呼ばれている肉を食べてみたところ、しっかりとした噛み応えと同時に濃厚なタレの味が広がる。あらためてメニューを見ると一本百五十円と書かれているが、これは料金以上の価値がある。マサカズは軽く興奮してしまった。
「山田さん、さすがです。いいお店知ってるんですね」
同じようにカシラを頬張った七浦は笑顔でそう言うと、左の肘でマサカズの腕を軽くつついた。
「違うよ。ついさっき検索して見つけたんだ。僕もここは初めて……というか、あんまりお店じゃ呑まないから。いつもは家でだよ」
「なら今日はいっぱい呑みましょう。ここ、安いです。うん、そうしましょう。あ、もちろん割り勘ですね。おごれなんてセコイのナシですから」
食べ終えた串を木製の容器に入れた彼女を横目に、マサカズは彼女がこういった店に行き慣れているのだと思った。
二杯目の中生ビールを注文するためマサカズが店員を探そうとしたところ、まだ夕方にも関わらず店がすっかり満席になっていることに気づいた。
それから三十分ほど、二人は互いの趣味や好物といった他愛のない話をした。喧噪で聞き取れぬことも多く、何度も同じ事を言ったり聞いたりするうち、マサカズはこの小柄な後輩と互いの距離が縮まろうとしている手応えを感じ始めていた。

「こーゆーのってさ、彼氏にバレたらヤバくない?」
そう言ってマサカズが視線を右に移すと、彼女の目はすっかり座り、頬は赤く上気していた。
「なー、蹴られまふねー! 何発もでふねー! アイツ! 腹を!」
呂律も回らずそうまくし立てる七浦に、マサカズは苦笑いを浮かべるしかなかった。
「あと山田クン!」
人差し指を突きつけた七浦は、マサカズを覗き込むように屈んで見つめた。
「わたしは“葵”でお願いっス」
「そうなの?」
「ですよ~! もうそのぐらい仲良ひじゃないれすか~わたしたち」
「明日になったら忘れたとか、そーゆーのはナシでお願いね」
「だいじょーぶ!」
上体を起こした“葵”は、語尾を強くしてそう言い、五杯目となるレモンサワーのグラスを手に取った。
「葵さん、そのぐらいのでストップしない? 明日、朝からシフトでしょ?」
「店長キライ!」
支離滅裂で会話が成立しない。マサカズは首を大きく揺らす葵に、どう接すればいいのかわからなくなっていた。
「山田さん、弁護士さんと知り合いなんてすごい」
「あ、伊達さんのこと?」
「うん?」
葵はレモンサワーをあおるとグラスをカウンターに置いた。
「わたしも弁護士欲しい」
「なんで?」
「法律で守られたい」
「無料相談とかやってるらしいから、調べて行ってみたら?」
「ダテさんがいい。山田さんとおそろい。弁護士ライダーの」
にんまりとした笑みで、葵はそう言った。
「あの人は高いよ」
「…………」
笑みを消し、カウンターをじっと見つめた葵は小さく肩を震わせた。
「いいことなんてちっともない」
喧噪の中、そこから二人の間には沈黙が続いた。アルバイトも契約解除で彼氏との関係も今ひとつのようでもある。隣で黙り込むこの彼女は、自分のことを不幸であると憂いを抱いている。このような場合、どう対応すればいいのだろうか。あくまでも職場の先輩という立場を前提として、アルコールで正常ならざる状態となっている彼女に対して。
「まぁ、頑張ってれば、そのうちいいこともあるよ」
陳腐で意外性もなく、なんとも無意味な言葉だ。マサカズがそう自覚していると突然、葵が崩れ落ちた。酔いが回りすぎたのだろう、そう思ったマサカズはもたれかかってきた葵に慌てて身体を向けた。
抱き止めると、彼女のサマーニットがめくれた。その腹部に見えたのはいくつかの青痣だった。つい先ほど言っていた。「腹を蹴られる」と。事情など知らない。しかし、重い証拠を見てしまった。そして今夜のこの状況は、この痣を増やしかねない。ニットを下ろし直したマサカズは、店員に会計を告げた。
「面目ないです」
「そんなの、久しぶりに聞いた言い回しだ」
マサカズと葵は六畳のワンルームの壁に、背を着けて並んで床に座っていた。飲酒で意識を失った葵を、マサカズは悩んだ末背負って自宅アパートまで連れてきた。マサカズは葵にスポーツドリンクのペットボトルを手渡した。
「ありがとうございます」
「葵さんでよかったんだっけ?」
「あ、ああーそこは覚えてます。葵でオッケーです」
「バスだったよね。まだ時間大丈夫?」
マサカズはそう言うと、カラーボックスの上の時計に目を移した。葵もそれに倣うと「まだ、一時間ぐらいは」と漏らした。
「本当にごめんなさい。わたし、調子に乗ってバカみたいで」
「あのさ、葵さんってプライベートとかで問題抱えてる?」
しばらく黙り込むと葵は膝を抱え、何度かうなずいた。
「優しいところもあるんですよ。こないだ、優しくないとか言っちゃいましたけど」
言っている意味を理解するのに、時計の秒針が一回りするまで必要だった。マサカズは天井を見上げ、小さくため息をもらした。
「でも痛いのはダメだと思うな」
マサカズの言葉に葵は目を見開き、顔を向けた。
「あー、そっか、言っちゃってましたか。わたし」
「どうするかは結局、葵さんしだいってことにはなるけどさ」
「どうしたいんだろ、わたし」
「例えばさ、選択肢を増やすとかって、どうだろう?」
「あー、アリかもです。逃げ場を増やすってことですよね」
「まぁ、切ない言い方だとそうなるかな」
「いえ、いいと思いますよ。ステキです」
葵はペットボトルに口を付け、小さく微笑んだ。
「仕事を辞めさせられるのはキツいけど、考えようによっては環境を変えるいい機会にもなる可能性だってあるわけだし」
マサカズの言葉に、だが葵は反応せず前を向いたまま黙り込んでいた。
「引越とかさ、いっそ実家に一度戻るとかってのもアリかも。僕も一度真剣に検討したんだけど、おかげで確かに退路があるって安心感をあらためて認識したと言うか……」
返事がなかったため、マサカズは語彙を削り込まれるほど語ってしまった。すると、葵は勢い良く立ち上がり、マサカズにペットボトルを返した。
「ありがとうございました。帰りますね」
しっかりとした足取りで玄関に向かう葵の背中を、マサカズは追った。葵はドアを開け廊下に出ると、向き合うマサカズを見上げた。
「山田さん」
「なに?」
葵の目がなにやら輝いているように思えた。マサカズはそれを受け止められず、思わず視線を外してしまった。
「山田さんはわたしの選択肢になってもらえますか?」
そう告げると、葵は返答を待たずに駆け出していった。閉ざされた扉の前でマサカズは言葉の意味を考えた。最も容易な答えは導き出せたが、そこに潜む危険も察してしまい、彼はぶるっと奮えた。
【無料版】第2話 ─可哀想な女の子を救ってあげよう! Chapter6
次の日、昼前に書店までやってきたマサカズは、ロッカールームで店長と葵に出くわした。
「あのね、七浦さん。三時間の遅刻なんてね、あり得んのよね」
「すみません……」
「謝っても済まないのね」
「ごめんなさい……」
小坂店長は腰に手を当て胸を張り、威圧するような態度であり、相対する葵は両手をエプロンの前で重ね頭を垂れていた。葵は今日、朝からのシフトになっていたので、店長の発言からするとちょうど今、遅刻しての出勤となってしまったのだろう。マサカズは状況をそう察し、二人に軽く会釈をすると自分のロッカーに向かった。葵の遅刻はおそらく昨晩の深酒の影響もあるはずで、だとすれば自分にも責任の一端はなくもないのだが、それを店長に告げたところで話がややこしくなるだけだと思い、二人のやりとりに介入する気にはなれなかった。店長の小言はそれからもしばらく続き、準備を終えたマサカズが売り場に出るまで止まなかった。
“わたしの選択肢になってもらえますか”
昨晩、葵から最後に告げられた言葉だ。販売している文具の確認をしながら、マサカズは後輩に対してこれからどう接すればいいのか考えていた。言葉を額面通りに受け取れば、それは“わたしとお付き合いしてください”ということになる。しかしそれを受け入れるということは、彼女に暴力を振るう現在の彼氏との間に諍いが発生する可能性も含んでいる。鍵の力があれば、暴力への対応はできるのだが、そもそもそこまでして彼女を救う動機がない。よく笑い、朗らかで小さく可愛い子ではある。好き嫌いで言えば前者には該当するが、なにやら逃げ場所として求められている様でもあり、そうだとすれば受け止めきれる自信がない。自分も年内にはここでの仕事を失い、経済的な見通しも立っていない。社会的に一人前とは言えない立場だ。
エプロン姿の葵がロッカールームから出てきた。ようやく店長のねちねちとした説教も終わったということか。マサカズは葵に目を合わさず、書籍の在庫確認を始めた。
「あ、あのう」
背中から葵に声をかけられたマサカズだったが、「ごめん、いま取り込んでて」と早口で答え、本棚から離れた。
午後、マサカズは休憩室のソファに腰を下ろし、サイダー味の飴を口に含んだ。
「やっまださ~ん!」
休憩室に入ってきた葵が楽しげに声をかけてきた。
「う、うん」
「昨日は楽しかったです。またあのお店に行きましょう。美味しくって最高でした! あ、今度は酔っ払わないように気を付けます」
「う、うん」
「良かった。すっかり嫌われたと思っちゃってたんですよ」
「う、うん」
「見捨てられたか、これは!? なんて」
「う、うん」
向かいに座った葵を、マサカズは目を合わさずに同じ返事を繰り返すばかりだった。昨晩の最後の言葉、あの要求への返答をいつ求められるのか、彼はそれにただ怯えていた。受けるも断るも憂鬱な結果が待っているような気がする。従って、できるだけ接触の機会自体を今のところは減らしておきたい。マサカズは立ち上がり、本来ならまだ五分ほど残っていた休憩時間を打ち切ることにした。
よりによってのタイミングだった。在庫補充の仕事を終えたマサカズがレジに入ると、そこには葵がいた。
「あ、どもどもー」
明るく小さな声だったが、マサカズは返答せず接客に集中しようとした。しかし運もなくマサカズがレジに立ってから客は一人も訪れず、並んでいた二人の間には沈黙が続いた。業務上の話であれば、少しはしてもいいだろう。そう思ったマサカズが隣の葵に目を向けると、彼女は俯き、震え、泣くのを堪えている様に見えた。マサカズはどう接すればいいのかわからず、沈黙は継続された。
夕方となり書店にも帰宅客が増えてきたころ、マサカズは店長に声をかけられた。就業契約の期限が迫っており、年内までの契約延長を結ぶため、書面に署名捺印が必要とのことだった。それは事前に知らされていた内容だったため、今日は実印を持参していた。店長から書類を受け取ったマサカズはロッカーからポーチを取り出し、契約書を壁に貼り付けて名前を書き込んだ。この職場ともお別れだ。あとたったの半年か。マサカズは苦い思いを抱えつつ、実印を押した。
「山田さん! レジ入れます!?」
インターホンから男性店員の声がした。どうやら客が増えてきて手が足りていないようだ。残りの半年、せめて仕事での貢献はしておきたい。マサカズは店長に契約書を渡すとポーチをロッカーに戻し、急いで売り場に戻った。その途中、葵とすれ違ったが、特に声をかけることもしなかった。
いくらなんでも可哀想なのではないだろうか。レジでの業務をこなしながら、マサカズはふとそう思い至った。昨晩は楽しく酒も呑んだのに、このような底辺のアラサーに好意を向けてくれているのに。要求への答えを求められたとしても保留という選択もできるはずだ。葵に対する冷たいとも言えるほどの態度をマサカズは反省した。接客のピークを過ぎたころ、彼はレジから店内を見渡した。しかし、そこに葵の姿はなかった。シフトでは彼女はまだ勤務中のはずである。
「あれ、七浦さんって、休憩?」
マサカズが隣の男性店員にそう尋ねると、彼は「七浦さん体調不良で早退だって。遅刻の上だから、店長めっちゃ怒ってるよ」と言った。自分の冷たい態度に心を痛め、悲しみ、それに耐えきれず帰ってしまったのだろうか。心当たりのあったマサカズは床に目を落とし、小さく呻いた。
アルバイトを終えたマサカズは、ロッカールームまでやってきた。ロッカーの鍵を差し込み、それを回したところ扉は開けず逆に鍵がかかってしまった。契約書の手続きでロッカーを開けてポーチを取り出したあと、呼び出しがあったので鍵をかけ忘れてしまったのだろう。マサカズは中を確認してみたが、リュックやポーチもそのままで、財布やアパートの鍵もあった。ポーチの中にも複製した“例の鍵”が何本も入っている。それはそうだろう、ここは関係者以外立ち入り禁止であり、関係者で盗みを働くような者がいるはずもない。マサカズはそう納得すると、エプロンを脱ぎ、リュックを背負って書店から出た。
夜の路地を歩きながら、マサカズは葵のことを考えていた。とにかく今日のぎくしゃくとした態度を謝ろう。彼女の連絡先はわからなかったので、明日職場で謝ろう。そう決めた彼は、夕飯を買うため自宅アパート近くのコンビニエンスストアに入った。
テレビやネットのニュースでは、こういった店舗が強盗の被害に遭うことも多いらしい。それならば、次の勤め先として検討してみるのもいいかもしれない。あの鍵の力があれば、強盗も簡単に撃退でき、人から喜ばれる。しかし、そう都合良く強盗が来てくれるはずもないだろう。とりとめも無く、結論の出しようもない考え事をしながら、マサカズは陳列されていた弁当を選んだ。
瓜原を倒し、吉田に決別を告げてから半月ほどが経ったが、マサカズにはその間なにもなかった。アルバイトに通い、業務をこなし、飯を食べ、風呂に入って寝る。あれ以来、鍵の力を使う機会もない。アパートの自室でカレー弁当を食べながら、マサカズは部屋の隅に鎮座している金庫に目を向けた。伊達とは来週の火曜日に会う予定になっている。その時に鍵の使い道を示してくれるといいのだが。黙々とカレーを口に運びながら、マサカズは自分を取り巻く状況の代わり映えの無さにうんざりした。途方もない力と大金があるというのに、なにひとつ変わってくれない。いや、半年後の失職や後輩を傷つけたりと、むしろ悪化している。カレーを食べ終えたマサカズは、布団に仰向けになり、スマートフォンを手にした。
「俺、マサカズだけど、まだ寝てなかったの?」
栃木の実家に、マサカズは電話をかけた。出たのは父だった。
「今日さ、バイト先で残り半年の契約したんだよ」
「そのあと? まだ決まってない」
「なんとかするから大丈夫だって」
「十月に同窓会? 小学校の? ああ、出るって返事しといて」
「兄貴から連絡とかあった?」
「ああ、そうなんだ。いや、俺の方にもなんもないよ」
「そっちは変わったこととかない?」
「そうなんだ。忙しいのはいいことだね」
「じゃ、またなんかあったら連絡するわ」
電話を切ったマサカズはふと思った。今からでも父の元で仕事を覚えることはできるだろうか、と。規模も小さく従業員の数も数名だが、父が長きに亘って経営しているあの工場は後を継ぐ者が今のところいない。なんの変化もなく冴えない日常なら、いっそのこと徹底して当たり前の道を進むのもいいかもしれない。両親も喜んでくれるだろうし、確か三十歳を超えた新人工員もいたはずなので、まだ間に合う可能性もある。田畑が広がる故郷の風景を思い浮かべたマサカズは、静かに眠りに落ちた。
【無料版】第2話 ─可哀想な女の子を救ってあげよう! Chapter7
明くる日、書店に出勤したマサカズだったが、葵は体調不良を理由にアルバイトを休んでいた。同僚からその旨を知らされたマサカズは連絡する術も無いため、ただ彼女のことを心配するしかなかった。
この日も夕方まではあまり忙しくもなく、来る七月の『店員さんのオススメ漫画』のポップ作成をするため事務室のパソコンに向かっていた。商業施設内の店舗だったためバックヤードのスペースは非常に狭く、この事務室も机が二つしかなく、マサカズは店長の舌打ちや独り言を間近に聞きながら、画像編集ソフトを操作していた。
マサカズはパソコンの操作が不慣れで得意ではなく、このポップ作りも手作りで行いたかったのだが、字があまり上手くなかったため、申し出は店長から却下されてしまった。葵はパソコンに長けていたのでいつも自分はネタだしを担当し、ポップそのものの作成は彼女にお願いしていたのだが、休みということでそれも叶わなかった。
「店長、文字ってどうやって打つんでしたっけ?」
「キーボードで打つに決まってるでしょ」
「あ、いや、それはわかります。この画像ソフトで文字を入れる方法です」
「んもう」
隣に座っていた小坂店長が腰を浮かし、マサカズのモニターを覗き込んだ。
「前にも言ったでしょ。この“T”てボタンを押すのね」
店長の指示通りにしてみたところ、画面にはテキストを打つためのガイドが表示された。
「あ、そーだそーだ」
「山田君、あのね、七浦さんなんだけどね」
「はい」
「なんか、最近ダメじゃない?」
「遅刻とか、休んだりとか?」
「相変わらず仕事もミスが多いし。山田君なんか知らない?」
「いゃ、僕は、その」
彼女の昨日からの不調については、おそらく自分の冷たい態度が原因であるはずだ。確信にまで至っていたマサカズは、それを正直に言うべきだと思った。
「実は僕、おとといの仕事終わりに七浦さんとお酒を呑んだんです」
「うん」
店長は強く小さく何度かうなずいた。マサカズは彼が興奮している様に感じた。
「そこで色々とあったんですけど、ちょっと、彼女を傷つけてしまうようなことを僕がしてしまったようで」
「なにしたの?」
早口で店長は尋ねた。強い興味は管理職という立場からではなく、もっと下世話な期待からくるものだ。そう察したマサカズはうんざりとしたが、嘘をつきたくないため説明を続けようとしたものの、単純な問題ではないため言葉に迷った。
「なにもしてません。ほんと、細かいやりとりが原因だと思います。七浦さんが酔い潰れて、僕のアパートまで背負って、酔いが醒めて、彼女はバスで帰って」
「連れ込んだの? 山田君が? へー、意外ー」
「放っておくわけにはいかないでしょ?」
「で、ヤッたの?」
嬉しそうにそう尋ねてきた店長に、マサカズは身体を向け拳を作った。
「してません!」
「ははん、だから? 七浦ちゃんとこじせらせちゃった?」
「彼女には彼氏がいるんです。そんな展開自体あり得ません」
「へー、彼氏いるんだ。あんな地味子ちゃんでも」
店長のもの言いが品性を失う一方だったため、マサカズは説明を止めこの狭い事務室から出ていきたくなった。すると、インターホンから「山田さん、ヘルプよろしく」と、男性店員から声がした。マサカズは「すみません!」と言い放つと席を立ち、売り場に戻った。
今日こそ葵に謝りたい。次の日もそんな気持ちでマサカズは朝のルーティーンをこなしていた。洗顔、歯磨き、朝食は摂らず紙パックの野菜ジュースを飲みながらテレビで朝のニュースと天気予報を見る。毎日、朝はそのような過ごし方をしていた。
テレビでは、死亡事故のニュースをやっていた。場所はこの小岩から南に九キロほど離れた葛西の路地裏であり、身元不明の二十代から三十代の男性の遺体が発見されたとのことだった。死因の公表はなかったが、警察では殺人を視野に入れて目撃情報や防犯カメラの映像の収集をしているらしい。その報道にマサカズは、やはり錠前は常に手元に置いておくべきだとあらためて思い、出勤の準備を進めることにした。
「ちょっと七浦さん、急に休まれるとね、困るんだよね」
朝、ロッカールームにやってきたマサカズは二日前と同じ様な場面に出くわした。腕を組んでいた小坂店長は葵に「なんか言うことないの?」と、強い語調で詰め寄った。
「反省してます! もう休みません!」
明るく元気よく、はっきりとした口調の葵だった。店長は勢いに気圧されたようであり、小さく身じろぎすると事務室に戻っていった。
「葵さん、あのさ」
マサカズがそう切り出すと、葵は右足を軸にして軽やかに振り返った。
「おとといの僕の態度、謝るよ。ゴメン、どうかしていた」
「なんかありましたっけ」
あっけらかんとそう返してきた葵に、マサカズはちりちり頭をひとかきし、「ありは、しないか……」と呟いた。葵は人差し指で眼鏡を直すと、マサカズに向かって一歩踏み出した。
「ねぇ、またあのお店で呑みましょーよ」
「そ、そうだね」
いつもの明るい七浦葵だ。いや、いつもよりも元気が増している様にも思える。マサカズは軽く困惑し、彼女から目を逸らした。
「もしかして、早退からの病欠で心配しちゃったりしてくれてます?」
「うん」
「嬉しい! ありがとうです!」
葵はマサカズの両手首を掴み、何度か上下させた。
「でももう大丈夫です。ここをクビになったあとも何とかやっていける目処が立ったんです」
「目処?」
手首を掴つかまれたまま、マサカズは視線を葵に戻した。彼女は満面に笑みを浮かべていた。
「どんな目処?」
「それは、ひみつです!」
短くそう返した葵は、マサカズから手を離し売り場へと駆けていった。
マサカズは客からの要求のため、本棚からコミックの単行本を取り出し、それをカゴに詰めていた。まさか、全三十六巻をまとめ買いする客がいるとは予想していなかった。二つのカゴを両手に持ったマサカズは、レジに戻ろうとした。
「どーしたの泣いたりして」
マサカズは足を止め、声の方に目を移した。すると、葵がしゃがみ込んで未就学ぐらいと見られる小さな男児に声をかけていた。男児は目に涙を溜め肩を上下させ、今にも爆発しそうなストレスを抱えている様でもある。
「迷子? パパかママとはぐれ……いなくなっちゃったとか、かな?」
穏やかに優しげな口調で、葵はそう尋ねた。
「じいじ、いない」
震えた声で男児が答えた。
「じいじか。じゃあね、お姉ちゃんと一緒に行こうか」
「知らない人に……」
「大丈夫、ホラこのエプロン。お姉ちゃんこの本屋さんの店員さんなんだよ」
葵は身に付けていた“イマオカ書店”とプリントされたエプロンの端をつまみ、男児に根拠を見せた。
「そーなの?」
「うん!」
葵はそう返事をすると、マサカズに目を向けた。
「山田さん、そーですよ、ね!」
急に助けを求められたマサカズはカゴを床に置くと、葵たちの元まで進んだ。
「ほんとだよ。このお姉ちゃんは七浦さんっていう、僕の同僚……仲間の店員さんだ」
男児はマサカズを見上げると、小さく頷いた。
「葵さん、どうするの?」
「案内所に連れていきます」
「あ、そーか。僕、迷子対応って教わってなかった」
「店長、ザルですもの。じゃ、行ってきます」
葵は立ち上がると、子供の手を引き、売り場を出て行った。
「キミ、漫画とか好き?」
「アニメ、好き」
そのようなやりとりをしながら小さくなっていく葵たちの背中を、マサカズはじっと見つめていた。
「あぁ、好き……なのかも」
呟いたマサカズの背中に、女性客から「どうなってるんですか!?」と怒声が浴びせかけられた。彼は慌てて単行本の詰まったカゴまで戻り、それを持ち上げるとレジまで戻ることにした。
【無料版】第2話 ─可哀想な女の子を救ってあげよう! Chapter8
変わらない毎日だった、この日までは。
初夏にも関わらずうんざりするほど強烈な朝日がじりじりと照りつける中、マサカズは出勤のため駅までやってきた。すると、ショッピングセンターの入り口にはパトライトを点灯させたパトカーが停まっていた。何か事件でもあったのだろうか、そう思いながらマサカズがセンターに入っていくと、書店には“立ち入り禁止”と記された黄色いテープが張られ、出入りが規制されていた。どうやら事件は自分の職場で起きてしまったらしい。現在の時刻は開店前であり、書店という性格上強盗があったとは考え辛い。異変にまったくの心当たりが無かったマサカズは、背後から肘を軽く引かれた。
「殺人事件ですって。被害者は店長」
そう告げてきたのはTシャツにデニム姿の葵だった。
「え? え? え?」
突然飛び込んできた意外な言葉に、マサカズは困惑した。
「これ」
一枚の名刺をマサカズは葵から受け取った。それには小岩警察署の警察官の名前が記されていた。
「明日の午前中に、関係者として任意の事情聴取にきて欲しいって」
これまでしてきてしまったことを考えると、警察との関わりをできるだけ避けたいマサカズだったが、今日は夕方から伊達と会う予定もあったので、ひとまず彼に相談しようと考えた。
「なんでこれを葵さんが?」
「今日はちょっと早く来たんです。そうしたら警察の人が店員のみんなに言付けておいてくれって。今日お休みの田中さんたちには、さっき電話で伝えておきました」
「えっと……ちょっと待って、何なの? 小坂さんが殺されたって?」
「警察の人はそう言ってました。怖いですね」
葵の言葉を、だがマサカズは受け入れられなかった。
「お店で殺されたの?」
「事務室です」
「いつ?」
「昨日の夜です。犯人はまだわかっていないとのことです」
葵の返答があまりにもテキパキとしていたので、マサカズは違和感を覚えた。
「怖くない?」
「もちろん怖いです」
「なんか、怖がってなさそうだけど」
「怖くて仕方がないですよ」
葵の表情は硬く固まっていて、なるほどこの子は怖いときにこういった態度になるのかと、マサカズは一応の納得に至った。
「あ、で、今日って」
「どうなるんでしょうかね?」
昨日、事務室で小坂店長が何者かに殺された。売り場には警察官の姿も見え、現在も捜査が続いているようである。とてもではないが、当面の営業はできないだろう。しかしどこからの指示もなく、これからどうすればいいのかマサカズは決めかねていた。
「そーだ、山田さん」
「なに?」
「今日、デートしません?」
「は?」
唐突な申し出に、マナサカズは言葉を失ってしまった。
「こんな時に何を言ってるんだ、ってところでしょうけど、したいんです。デート」
「で、でもさ、葵さんって……」
「別れました。アイツとは」
「え?」
「もう過去の人です。わたしにとっては。ですので現在のわたしはフリーです。がら空き物件です」
苦笑いを浮かべそう告げる葵の横顔を、マサカズは感情の整理がつかないまま見つめるしかなかった。
「デート? 僕と?」
あらためて確認する意味で、マサカズはそう尋ねた。
「アドレス交換しましょう。どこへ何時に行くのか、わたしが決めるのであとで連絡します」
「いいけど……ってことは、今日はもう?」
「帰るしかないですね。でしょ? 言付けも山田さんが最後ですし」
いつもの職場は殺人事件の現場となってしまった。そして後輩からはフリー宣言され、デートに誘われた。目まぐるしく移り変わっていく現状に、マサカズはただ困惑する一方だった。
その日の夕方、マサカズは秋葉原のゲームセンターまでやってきた。ここは都道と首都高に面した小さなビルの二階にあり、普段ゲームセンターを訪れる機会がない彼にもわかるほど、古いゲームたちが稼働していた。そのうちの一台、宇宙空間をバックに戦闘機で横方向に進んで戦うゲームの前に、背中を丸めたスーツ姿の青年が座っていた。
「古いゲームですねぇ。周りのもみんなそんな感じだけど」
マサカズは青年の背中にそんな言葉をかけた。すると、画面の中の戦闘機が被弾し破壊され、“Game Over”という文言が表示された。
「ありゃ、負けちゃいましたね」
「いにしえの死にゲーだからな」
席を立ち、マサカズに振り向いた伊達は仏頂面でそう答えた。二人はゲーム台から離れ、“コミュニティエリア”と書かれた看板が掲げられた飲食スペースに行くと、それぞれ自動販売機で缶飲料を買った。
「すまない。まずは謝る。まだ例の件について計画はまとまっていない」
「あ、はい」
「それと、報道で見たけど、なんなんだ?」
「なんのことです?」
缶コーヒーのプルトップを引いたマサカズは、伊達に首を傾げた。伊達も炭酸飲料のプルトップに指をかけると、「店長。死んだって件」と声を低くしてそう言った。
「ああ、僕、あの事件なら何にも関係ないですよ」
「そうか。それならよかった」
「明日、事情聴取で警察署に来いって。そーだ、伊達さん立ち会ってくださいよ」
「そりゃムリだ」
「なんでです?」
「警察署は弁護士の立ち合いなんて絶対に認めない」
「あ、でもよく弁護士を呼べ、話はそれからだって、ドラマとかであるじゃないですか」
「ああいうのは逮捕、身柄の拘束後に弁護士と接見して方針を決めてから聴取に応じるって意味だよ。お前は今のところ容疑者じゃないようだし、事情聴取のケースで同行はあり得ない」
「あ、じゃあ何か今のうちにアドバイスを」
「特にないけど、まぁ、例の鍵とそれ絡みについて、うっかり喋らないようにしろってところかな」
「そうですね。それは肝に銘じておきます」
「店長殺害について、何か心当たりはあるのか?」
「ないですないです。あるはずもない」
「誰かから、恨みをかっていたとか? おそらく、これは明日警察からも聞かれるだろうけど」
「皆から嫌われてましたけど、殺されるほどでは……あ、僕もあんまり好きではなかったです」
「そうか……あ、今の僕も嫌ってましたは、明日言うんじゃないぞ」
「き、気を付けます」
伊達は炭酸飲料をひと飲みすると、ビデオゲームに視線を移した。
「伊達さんってテレビゲーム好きなんですか?」
「古いのがな。最近のとかスマホのはやらない」
「マニアなんですか?」
興味を示したマサカズがそう尋ねると、伊達は小さく笑みを浮かべた。
「まぁね。父親がコレクターでね。その影響かな」
「あ、そうそう。僕、今日の夜、葛西の観覧車で例の後輩の子、葵さんとデートなんですよ」
「へぇ」
「彼女、彼氏と別れてフリーなんです」
「店長殺害のその日にデートか? お前も大した図太さだな」
「違いますよ。彼女から誘ってきたんです」
「へぇ」
興味もなかったため、伊達は生返事しか返せなかった。
「それでですね、伊達さん、アドバイスなど……」
「ない」
伊達の即答に、マサカズはなぜだか申し訳なくなってしまい、缶コーヒーをごくりと飲み干した。
「そんなことよりな……」
そう言いながら、伊達は鞄の中から何かが薄く詰まったコンビニ袋を取り出し、それをマサカズに渡した。マサカズがコンビニ袋の中をあらためると、そこにはビニール袋に包まれたプロレスのマスクが入っていた。
「あっ、これってこないだお願いしたやつですね」
「そうだ。できるだけプロレスっぽくなくて、ヒーロー風のデザインを選んだ。顎まで隠せるから、歯並びとかでバレる危険も少ない」
マサカズはマスクを手にし、「なんてレスラーのです?」と尋ねた。
「北海道のインディ団体、レッスル旭川ってところの宇宙仮面フォースってレスラーの、ビッグマッチ用のマスクだ」
「へぇ、カッコイイですね。ありがとうございます。でもこんなのってどこで売ってるんですか? あ、通販とかかな?」
「水道橋に行きつけのプロレスショップがあってな。そこで店長に選んでもらった。料金は後日請求させてもらう」
「行きつけ……伊達さんって趣味が豊富なんですね。僕なんて漫画ぐらいだ」
「さて、今日はこのぐらいにしておこう。俺はゲームをやっていくがマサカズは?」
「僕、ゲームはやらないんで。デート行ってきます」
「そうか……」
少しだけ寂しくなった伊達は、空き缶をゴミ箱に捨てるとマサカズに背中を向けた。
「そうだ、一応だけど、デートの成功を祈ってるよ。次の機会に結果を聞かせてくれ」
その言葉を意外だと思ったマサカズは、空き缶を捨て伊達の前に回り込んだ。
「まだ時間あるんで僕、ゲームやってきます。伊達さん、なんかお薦めのゲームとかってあります?」
マサカズの申し出に、伊達は彼にしては珍しく満面に屈託のない笑みを浮かべ、「そうなの!?」と早口で返した。
【無料版】第2話 ─可哀想な女の子を救ってあげよう! Chapter9
その観覧車は東京湾を望む葛西臨海公園の名物だった。マサカズは夜景をただひとり、ぼんやりと見つめていた。アドレスを交換した葵からメッセンジャーで連絡があったのだが、“夜七時、この観覧車にひとりで乗り込んで欲しい”といった内容だった。奇妙に感じながらも何かの意図があるのだろうと思ったマサカズは、素直に従うことにした。
こうやって高い場所から夜景を眺めるのも何年ぶりのことだろうか。
このあと、葵さんがやってくるとして、またどこかに呑みに行く流れになるのだろうか。
あれは東京スカイツリーだ。
伊達さんのお薦めのゲームは正直言ってあまり面白くなかったけど、しかめっ面で何も言わずゲームセンターを出て行ってしまったのは、さすがに悪かったかもしれない。
葵さんはどんな姿で現れるのだろうか。
どうやら雨が降ってきたようだ。傘がない。
葵さんは彼氏と別れたと言っていた。なら、今夜自分たちの仲は何らかの進展があるのかもしれない。
迷子の手を引く葵さんが、たまらなく好きだと感じてしまった。これは、たぶん恋だ。
それにしても腹が減った。
ゴンドラの中で一人、とりとめもなく、ばらついた思いをそのままに巡らしていると、ゴンドラの扉が開かれ、突風が吹き渡った。係員が鍵をかけ忘れたのだろうか。既に地上から数十メートルは離れているので危険極まりない。マサカズは腰を浮かせた。
「どーです山田さん。なかなかの登場でしょ?」
目の前に突如として現れたのは、茜色のジャージを着た葵だった。

「こういうののドアって、外からしか開けられないんですよね」
彼女はどこからどうやってここに現れたのか。中腰のまま、マサカズは異常事態を懸命に理解しようとしていた。ゴンドラに乗り込んできた葵は微笑み、手を後ろに回し、マサカズに向かって屈み込んだ。
「デートなのにこんなダサい格好でごめんなさい。けど、動きやすくって。これ、高校のころのジャージなんです」
言い終えると、葵は最後にペロっと舌を小さく出した。
「手短に説明しますね。先週の水曜日なんですけど、わたし、山田さんのロッカーを漁ったんです。鍵かかってなかったので。なんでかって言いますと、何か山田さんの秘密とか知れれば、もっとわたしのことちゃんと相手にしてくれるかなって思ったんですよ。そしたら、ポーチに同じようなロッカーの鍵がいっぱい入ってるじゃないですか。あれれ、もしかしてこれってみんなのロッカーの合鍵を勝手に作って泥棒でもするつもりだったのかな? 山田さんって意外と悪い人だなぁ、なんて思って、そのうちの一本を試してみたんですよ。そしたら……です。ごめんなさい、手短じゃなくって」
ロッカーの鍵をかけ忘れたときのことか。ポーチに例の鍵があったのは確かめたが、本数までは数えていなかった。ポーチの中には八本入れていて、そのうちの一本を彼女は試し、自分と同じ経験をしてしまったということか。マサカズは情報を整理したが、これからどうなるかの予想はまったくできなかった。
「かっこいいですよね。いわゆる近接パワータイプって感じ? わたし、少年漫画もすっごく読むんですよ。バトルモノなんかも大好物です」
葵は両手で眼鏡をかけ直した。
「けど、視力とか聴力はそのまんまなんですよね。ちょっとそこが残念ですけど……もちろんマサカズさんは鍵についてもう把握済みですよね」
「あ、ああ……」
「やったぁ! でしたら一緒に組みましょう。わたしと二人でバディです。あ、なんならわたしがサイドキックでもいいですよ」
「なにを……言ってるんだ?」
「えー、だって正義でしょ。こーゆーパワーの使い道って。世直しということです」
「僕もそれは考えてみたけど、具体的にどうするか思いつかなかった」
「悪いのを撃破していけばいいんですよ」
「どこにその悪いヤツがいる?」
「いますよ。いくらでも」
「見つからないだろ」
マサカズの反論に葵は俯き目を落とし、彼の対面に座った。
「この力はある意味危険なんだ。遊び感覚やノリだけで使っていいモノじゃない。僕はもう散々な目に遭ってきた。葵さんに同じ失敗はさせたくない。鍵はいったん返してくれ」
そう告げたマサカズだったが、葵は返事をしなかった。
「葵さん、頼むから……」
葵は膝の上で指を組み、マサカズをじっと見つめた。
「わたしは本気だし、引き返せません」
「引き返せない?」
「あのクソヤロウをブッ殺しました」
「誰!?」
「クソヤロウです! 山田さんと呑んだのがバレて、蹴られて蹴られて、ロクに働きもしねーのに、風俗行けとか言い出すし、今度は顔を殴られそうで、反撃したら……」
葵は顔をくしゃくしゃに歪め、それでも口元には笑みを浮かべていた。ゴンドラは頂点を超え、下降を始めていた。
「首がぐるんって一回転。DVヤロウの悪党を一撃です」
「僕も……似たようなことをした。僕の場合、ヤミ金の連中だったけど」
言いながら、マサカズは先日の朝のニュースを思い出していた。確か、殺害現場は路地だったはずである。
「たぶん、警察は近いうちに君まで辿り着くと思う」
「あー、ですけどこの力があれば、警察なんて敵じゃないですし。ですから、大丈夫です」
倫理観に障害が生じている。おそらく、あのデタラメな力のせいだろう。自分の場合、それに対する恐れの方が勝っていたが、彼女は常に理不尽な暴力に晒されていたため、手に入れてしまった力の行使に躊躇がない。マサカズはそう分析をしつつ、この事態の解決方法にまでは至れなかった。
「山田さん、個人的な怒りってやつだって、まだそう思ってるでしょ。でしたらでしたら、昨日の夜のこともお話ししましょう!」
更なる告白にマサカズは口を開け、手を震わせた。
「残業になって居残りしてたら、小坂のヤローに事務室まで呼び出されて、契約延長してやってもいいけど、ヤらせろって。山田さんの家に連れ込まれるような尻軽なんだろって。ふざけんじゃねーよって、だっておかしいですよね? 尻軽なんて言葉、久しぶりに聞きましたよ。昭和か? って」
「だからって、殺すことはないだろ」
「いいえ、アレは女の敵、ヴィランと言ってしまってもいいでしょう」
「違う、今の君は力に振り回されて暴走している。これまでの鬱屈とかもあるんだろうけど……とにかく鍵を返してくれ!」
マサカズはそう言いながら、デニムのポケットに手を突っ込み、南京錠で鍵の力を発動させた。
「嫌です。もしかして山田さん、わたしの敵になるってことですか?」
「僕は葵さんの味方だ。好意だってあるし。というか、好きだ! だから、いったん元に戻ろう」
「けどムリですよ。わたしだってバカじゃありません。このままじゃ二件の殺人で逮捕でしょ。死刑もあるかも。そんなのあんまりです。わたしの人生、なんにもない!」
強い口調で葵は反論した。彼女は立ち上がり、ゴンドラが小さく揺れた。
「だいたい、ズルくないですか? 山田さんは正社員なのにわたしはクビだし、わたしから鍵を取り返そうなんて、いくらなんでもあんまりです!」
正規雇用の話は白紙となり、年内での契約解除になった件について、葵には話したはずだった。しかし、興奮を強めている彼女にそれをあらためて説明したところで、聞く耳持たずにしかならないだろう。マサカズは腰を浮かせ、葵をどうやって無力化するのか考えあぐねていた。
「好きって言ってくれたのは嬉しいですけど、敵になっちゃうんですね! あーあ、ガッカリです! なら、戦うだけです! 覚悟のない山田さんからすべての鍵を取り上げます! あなたにその力は相応しくない!」
そう叫び、葵はマサカズに掴みかかろうとしてきた。すると彼女は不自然によろめき、横に倒れ込むような形で肩を扉に強くぶつけた。鍵の力になれていない最初のころは、バランスを崩してしまうことが度々あった。マサカズは葵の変調を経験からそう察した。
解錠されたままの扉は衝突により呆気なく開かれ、放り出されてしまった葵は雨の虚空に落ちていった。マサカズは咄嗟に手を伸ばしたが、彼女はほどなく五十メートル下の地面に全身を打ち付けた。これまでの経験上、鍵の力があればこの高度なら無傷であるはずだ。だが、七浦葵は雨と血が混ざり合う泥濘の中ピクリとも動かず、その元には施設の係員が駆け付けようとしていた。
ゴンドラが地面に達した。係員がドアを解錠しようとやってきたが、マサカズは内側から扉を開くと力ない足取りで観覧車から離れた。背中から係員が慌てた様子で「お客様!」と声をかけてきたが、彼はそれを無視して雨の中駆け出した。
【無料版】第2話 ─可哀想な女の子を救ってあげよう! Chapter10
南からの風で、雨雲はすっかり姿を消していた。観覧車近くの公園のベンチで、マサカズは石像のように微動だにせず佇んでいた。そこに、ヘルメットを手にした伊達がやってきた。
「おー、フラれたか」
伊達の言葉に、マサカズはのろりと顔を上げた。その強張った表情から職業上のある推察をした伊達は、ベンチをハンカチで拭くとマサカズの隣に座った。
「まさか、アレとなにか関係あるのか?」
伊達が並木の向こうに見えるパトライトの灯りを指さすと、マサカズは力なく頷いた。
「俺がここにきたのは、お前があまりにも『バウンティーファイティング』をつまらなそうにプレイしてたからだ。あのゲームの楽しみ方をあらためて教えようとかと思ったからと……まぁ、デートの行方が若干だが気になったっていう出歯亀気分が働いたからなんだけどな。どうやらそれどころじゃなさそうだな」
今夜のデートが葛西の観覧車という情報は、すでにマサカズから得ていた。伊達はバイクで葛西臨海公園を訪れ、スマートフォンのGPSで交換済みの情報を元にマサカズの行方を探ったところ、観覧車にほど近いベンチを示したため、ここまでやってきた。隣で固まっている彼は朝の職場に続き、再び警察沙汰のトラブルに巻き込まれている。自分に役立てることはないだろうか。マサカズのあまりにも狼狽した様子に、伊達は彼の言葉を待った。
「葵さんはたぶん死にました。鍵を盗まれたんです」
マサカズの告白に、伊達は小さく呻いた。
「鍵の力を、彼女は自分を守るために使ったんです。できてしまったことに、葵さんは振り回された。苛立ちを解決することにまで使ってしまった。そんなこと、これじゃやり過ぎになっちゃうんですよ。なのに、彼女はこれまでがロクでもなかったから、別にいいやって、ヤケっぽくなっちゃって」
「死因は?」
「クールですね、伊達さんって」
「すまない」
「あ、いや、いいですよ。おかげで少しは気持ちが動いてきました」
「そんなつもりはなかった。本当にすまない」
「死因は落下死です。僕が乗っていたゴンドラに乗り込んできて、襲いかかろうとしてきたけどバランスを崩して扉から落っこちて。五十メートルぐらいだったかな? 僕なら平気な高さでしたけど、彼女は耐えきれなかったみたいで。動かなくなって、血だまりができて」
マサカズの説明に伊達は足を組み、親指を軽く噛んで考えを巡らせた。
「襲ってきた理由は?」
「僕と仲間になろうって、正義の味方になろうって。けど、彼女は彼氏と店長を殺したんです。僕は鍵を返すように言ったんです。けど、葵さんはそれを嫌がって、僕から鍵を奪おうとしてきたんです」
伊達は左足を忙しなく上下させると、掌を強く叩いた。
「マサカズ、お前の心情は察した。俺はお前みたいな目に遭ったヤツを何人も見てきた。だけどな、いま最善なのは今の最悪な気分をより悪くする行動だ。それでもいいか?」
「あ、はい?」
伊達の言葉がわからなかったマサカズは、ちりちり頭をひとかきした。
「あのパトカーまで行け。そしてここで自分に起きた件をあらいざらい話すんだ。もちろん、鍵のことについてはないってことを前提にな」
言いながら、伊達はスマートフォンを手早く操作した。
「葵さんがいきなりゴンドラに乗り込んできて……足を滑らせて落っこちたって?」
「いま、シナリオを書いた。簡単な内容だからこれを暗記して取り調べで話すんだ」
マサカズはスマートフォンに着信があったので、腰のポーチからそれを取り出した。すると、伊達からのメッセージが届いていた。
「いいかマサカズ、お前はあくまでもこの件の被害者だ。殺人犯の後輩に自首を勧めたが、逆上されて殺されかけたが勝手に転落した。どうやって彼女が稼働中のゴンドラに乗り込めた? そんなの知りません。自分にも理解できません。いいか? これを貫け。あと、しばらくはマスコミからの取材が殺到するかもしれないが、そいつらには俺の連絡先を伝えて俺を通すように言っておけ」
「マスコミ……ですか?」
対応できる自信がないマサカズは、震える声で返事をした。
「どうせ一日二日のことだ。お前は一方的な被害者なんだからな」
マサカズは頷くと、俯き、大きく深呼吸をした。彼はスマートフォンで一件のニュースを確認した。
「葵さん、やっぱり死んじゃったみたいです」
マサカズはスマートフォンの画面を伊達に向けた。そこには、観覧車から二件の殺人で指名手配になったばかりの女性が転落死したニュースが表示されていた。マサカズはがっくりとうなだれた。心配した伊達が様子を窺うと、マサカズの目からぼろぼろと大粒の涙がこぼれ落ちた。
「なんなんだよ。良いことなんてこれっぽっちもないじゃんか。こんな鍵なんてあったから、葵さんは踏み外しちまったんだ……こんな力……」
そう漏らしたマサカズは、頭をぶるぶると振った。
「違う。僕がちゃんと管理してなかったからだ。こんな物騒なもの、ポーチに入れっぱなしにして」
両指を組み身体を震わせ、マサカズは泣き崩れた。伊達は正面を向くと、小刻みに揺れるその背中をそっとさすった。
次の日の昼過ぎ、伊達は葛西警察署の受付にいた。パイプ椅子に腰掛けた彼は、喫煙所を探すため目を泳がせた。
「伊達さん。終わりました」
マサカズの声に、伊達は目を向けた。Tシャツ姿にリュックを背負ったマサカズは目を腫らし、少しやつれているようにも見える。伊達は立ち上がると、「どうだった?」と尋ねた。
「まずなんですけど、店長の件についての事情聴取はなくなりました。で、きのうについては葵さんが突然ゴンドラに乗り込んできて、二件の殺人を告白して、一緒に逃げてくれって頼まれて、僕はそれを断って自白を勧めたら、逆ギレした彼女が……」
「マサカズ、出よう。場所が悪かった」
伊達はそう告げると警察署の出口に向かい、マサカズもそれに続いた。
警察署を出た二人はどんよりとした曇り空のもと、あてもなく通りを歩き始めた。
「それから、店での葵さんの様子とか聞かれました。呑みに行ったことや、彼女が暴力を振るわれていたこととか、とにかく鍵以外については全部正直に話しました」
「後輩さんがどうやってゴンドラに乗り込んだのか、警察はどう理解していると思う?」
「そこはかなり聞かれました。もちろん、僕は突然扉が開いて入ってきたって言いました」
「えっとさ、マサカズ、気分は?」
「ぐちゃぐちゃです。きのうは悔しくて泣いてしまいましたけど、今じゃ可笑しくさえ思えてしまう」
「鍵を捨てたくなったか?」
「わかりません」
並んで道を進みながら、伊達はマサカズの様子を窺い、その心理状態を測っていた。
「なんだろう。刑事さんに色々と話していくうちに、落ち着いてきちゃったんですよね。で、それが気持ち悪くって、ぐちゃっとした気分になって。今は何も決めたりしたくないって感じです」
「まぁ……そりゃそうだろうな」
「あ、そうだ。マスコミってきませんね。今朝のワイドショーとかできのうの件やってたらしいのに」
「ああ、あいつらはさっきまでそこの警察署の前にいたよ。十人以上な」
マサカズは驚き、立ち止まって警察署に振り返った。
「俺が対応したよ。お前への取材は全部俺を通せって。直接取材するようなら精神的な苦痛を理由に訴える用意もあるって、まぁ、驚いてたよ、連中」
「そりゃ、僕みたいな無職のアラサーに伊達さんみたくエリートっぽい敏腕弁護士が出てきたら、驚きますよね」
「無職?」
「さっき本社からメールがあったんですけど、本屋、しばらく閉店して再開は未定ですって」
「なら無職じゃないだろ」
「いえ、これを期に辞めます」
「そうか」
伊達が再び歩き出したので、マサカズもその背中を小走りに追いかけた。伊達と言葉を交わしていると、何やら心が穏やかになっていく。マサカズはそれが嬉しかった。
「お前、きのうは良いことなんてひとつもないって言ってたよな」
伊達の言葉にマサカズは立ち止まった。伊達が振り返ると、マサカズはリュックのストラップを握りしめ歯を食いしばっていた。
「どうした、マサカズ」
「良いことなんて、そりゃあるわけないんですよ。やっとわかりました。だって、良くなろうと何もしていないんですから」
伊達はスーツのポケットから煙草とオイルライターを取り出した。
「伊達さん、僕は葵さんの不幸を救えなかった。だけど、もし踏み込む勇気があれば、それはできたはずなんです」
「それって」
「ええ、いまそう思いました。やっぱり、僕がしっかりしてないといけないんです」
「つまり、鍵は捨てないってことか?」
「はい」
マサカズの様子から生気を感じた伊達は、彼の肩をひと叩きした。
「なら、もう少しだけ待ってくれ、俺からの提案を」
「ええ、待ちます。あと……」
「ん? なんだ」
マサカズは伊達が手にしている煙草を指さした。
「それ、江戸川区でも禁止のはずですよ。路上じゃ」
マサカズの指摘に伊達は苦笑いを浮かべ、煙草のセットをポケットにしまった。
「なら、吸えるところで昼飯でもどうだ? ヒマなんだろ?」
「いいですね。警察じゃカツ丼は出ませんでしたし」
「このへん詳しいの? 俺はさっぱりなんだが」
「あー、僕も初めて来たんですよ」
マサカズと伊達は飲食店を求め、再び歩き始めた。何を食べるか、好き嫌いはあるのか、二人が交わす言葉はどこまでもありきたりで凡庸なものだった。
曇天は、いつの間にか快晴に移り変わろうとしていた。
第2話「可哀想な女の子を救ってあげよう!」おわり
【無料版】第3話 ─俺たちのアジトで旗揚げしよう!─ Chapter1
ミディタイプ筐体のモニターには、戦場を縦方向に進む兵士が映し出されていた。たった一発の敵弾で、兵士は大地に果てた。すると場面は幾分か巻き戻り、二人目の兵士が戦場に現れた。彼は今しがた果てた兵士と、うり二つの容姿だったが、同一人物かどうかはそれを操る側の想像力に任されていた。レバーを手にした伊達は兵士の行動を八方向から選択し、自動小銃で敵兵士を排除し、ここぞという局面においては数に限りのあるとっておきの手榴弾を投擲した。
「日本兵じゃねぇな」
背後からかけられたしゃがれ声に、ゲーム台と向き合っていた伊達は「たぶん、米兵です」と答えた。
「じゃあ相手はドイツか」
「です。おそらく」
最後の兵士が敵兵の銃弾に倒れると、スーツ姿の伊達は椅子から立ち上がり、ネクタイを締め直し、初老の男に振り返った。
ゲームセンター『エンペラー』は高田馬場の神田川に沿った路地にあり、所属する法律事務所から歩いて五分もかからなかった。店舗の特徴としては、八十年代以降の古いビデオゲーム筐体や基板を良好な稼働状態で維持し、提供しており、いわゆるレトロゲームの聖地としてマニアからの支持を集めていた。伊達にとっては“行きつけ”であり、今日も井沢との待ち合わせ場所として利用していた。
ゲームセンターを出た二人は夕暮れの中、神田川を望む歩道で肩を並べた。井沢は使い込まれた牛革のビジネスバッグからA4大の茶封筒を取り出すと、それを伊達に渡した。
「七浦の件だけどな。ありゃなんだ?」
「自分に聞かれても……」
伊達は困り顔を作った。この古豪に自分の動きが見抜かれていることは、これまでの付き合いでわかってはいたが一応そうしてみた。
「知ってるんだろ? 一課や科捜研の連中もハテナ出しっぱなしだぜ」
「いや、だから俺にわかるはずもないです」
あくまでも頑なな伊達に、井沢は鼻を鳴らすと川に目を向けた。
「まずな、人間じゃあり得ねぇ手口だ。ゴリラじゃねぇと、あんな殺しはムリだってよ。そして観覧車だ。山田がいたゴンドラにどうやって乗り込んだか、だ」
「彼も驚いていましたよ。一体どうやって地上百メートルまで登ってきたのかって」
マサカズはあの雨の夜、確かに七浦葵の出現に驚いてはいた。しかしその手段については確かな心当たりがあった。伊達の言葉には真実と虚構が入り交じっていて、井沢はそれに対して頷くことなく鋭い眼光を向けていた。井沢はかつて捜査機関で警部を務め、現場で長年に亘り叩き上げられた、もと敏腕捜査官である。人を値踏みする経験が豊富なこの古豪は、嘘を見抜いているはずである。それはわかっているものの、それでも伊達は鍵の異能について明かすことをしなかった。
「まぁいいや。あとな、“池ドラ”についちゃ、ありゃそもそも吉田が個人的に動いているだけで、組織としちゃ山田については認知してねぇようだ」
“池ドラ”とはマサカズを脅迫し、タタキを依頼した吉田が所属する反社会的グループ『池袋ドラゴン』のことである。伊達は頷いた。
「瓜原使って脅迫なんざ、吉田は本格的なアホだな。ありゃいつかしくじるだろうよ」
「珍しいですね、井沢さんが人物評なんて」
「山田正一絡みは、さすがに俺もクビを突っ込みがちになっちまってな」
井沢はそう言うと、被っていたハンチング帽を脱いだ。
「あー、お前さんの言う通りだ。確かにらしくねぇ。年甲斐もなくワクワクなんてしたら、コケちまうだけなんだよな」
「あぁ……」
伊達は井沢の言葉に軽く驚き、そして納得した。そう、自分もマサカズに対して関心だけではなく、期待を抱いている。経験を積み、大抵のことでは動じないはずの井沢でさえ、自身をつい見失うほどなのだ。三十は超えたもののまだまだ若造に類する自分など、冷静な判断を保てる自信もない。だとしたら、これからどうあのちりちり頭の青年と関わればいいのだろう。ネオンに照らされた七夕の夜空を見上げた伊達は、小さくため息を漏らした。
法律事務所まで戻った伊達は、自分のデスクについた。彼はパソコンをスリープ状態から復帰させると、あす法廷で争う、ある詐欺事件の資料を確認した。手口としてはある老人の息子になりすまし電話をかけ、金銭トラブルの懇願をしたのち、その被害相手を装った別の者が現金の振り込みを要求するといったものである。いわゆるオレオレ詐欺と言われている、最近となっては珍しくなった古い手法だったのだが、告げられた事態にうろたえた被害者は三百万円を振り込んでしまった。息子役であり、今回の顧客である二十代の男は犯行の全てを認めていた。通信履歴から足が着いてしまい、逮捕されたのだが、彼はネットでの闇バイトに応募したに過ぎず、犯行を指示したグループは別にいる。伊達にはそれに対しての心当たりがあり、連中が逮捕された際、おそらくこの事務所の誰かが弁護を担当することになることが予想できる。そこまで考えた伊達は、眼鏡を外して目薬を差した。
今回の依頼について、決して安くない弁護士費用は依頼者の父親である建築会社の代表が支払っていた。なんとか無罪、悪くても執行猶予でお願いできないか、などと彼は頼み込んできたが、どう努力しても実刑は免れないケースである。自分にできるのは、動機に凶悪性が薄く、再犯の可能性も低く、今後は両親のもと更生していく、といった主張を裁判所に対して訴え、できるだけ量刑を軽くするだけである。無論、これらの主張は全て自分の描いた物語でしかなく、拘置所での接見でこれまで知り得た依頼人の、法令を軽視する発言や態度から判断すると、あの青年は再び道を踏み外す。だが、だからと言って依頼を請けた弁護人としての責務は全力で果たす必要があった。
所長の柏城は「ウチがこんなクズ共を弁護するのには理由がある。あいつらの金で潤ったぶん、恵まれない連中に救いの手を差し伸べるんだ」と語っていた。そう、すべては持たざる者たちに法律の加護を受けさせるためだ。伊達は改めてその基本的な理念を「仕方ねぇんだよな」と言い換え、つぶやいた。
「なにが仕方ないんだよ」
デスクの脇までやってきてそう尋ねてきたのは、所長の柏城だった。伊達は眼鏡をかけると、わざとらしく下唇を突き出した柏城に身体を向けた。
「あ、いや、なんでもありません。ただの独り言です」
「ならいいんだけどな。明日はしっかり頼むぞ」
「それなんですけど、一応聞いておくべきだって思ったんですけど、そもそもこの案件ってどういったルートでウチに来たんです?」
「父親がな、アッチと繋がりがあってな。どうやら仕事で関係しているって話だ」
柏城は苦笑いを浮かべ、立てた親指を自らの肩越しに後ろへ向けるとそう言った。“アッチ”とはこの事務所とも契約を交わしているある暴力団のことである。所長の様子からそう察した伊達は、「あー」と漏らし納得した。
「俺らの稼業は人のつながりで仕事が回ってくる。お前も時間のある限り人脈を作るといい。いずれ独立するときの財産になるぞ」
「それ、もう三度目ですよ」
「四度だって言ってやるぞ」
「そもそも独立なんて考えてませんよ。まだまだ半人前ですから」
「あのな、客観的に見りゃ、お前はもう独り立ちしてもおかしくない実績を積んでるんだぞ」
「いやぁ、全然ですって」
伊達の言葉に柏城は額の皺を深め、彼の肩に手を当てた。
「冗談抜きで言わせてもらうけどな、自己評価の低いヤツはこの稼業に向いてないぞ。今のお前の態度、ただの謙遜だと受け止めておくからな」
そう言い残すと、柏城は所長室に戻っていった。
弁護士としての能力は決して低くない。伊達はそう自覚していたが、独立について現実的に考えたことはなかった。そして、その理由について考えを深めたことはなかった。
飯田橋のマンションまで帰ってきた伊達は、鞄を置くと真っ先にシャワーを浴びた。Tシャツとスウェットに着替えると、彼は冷蔵庫からビール缶を取り出し、ソファに腰掛けた。井沢から受け取った書類に目を通しながら、伊達はビールを勢いよく呷った。
書類は、井沢が独自のルートで手に入れた七浦葵についての捜査資料を取りまとめたものだった。ゴンドラの外側には葵の指紋が僅かだが検出されていたため、マサカズの証言は裏付けられたが、どうやって地上百メートルはあるそこまで達したのか、手段については明記されていない。監視カメラの映像から葵が行ったと断定された二件の殺害についても、遺体が強大な暴力によって撲殺されたといった検死資料はあったものの、彼女がいかなる方法でそれを実現できたのかという点については、やはり記載はなかった。いずれにしても犯人は既にこの世に無く、今後については被疑者死亡のため不起訴となる。そうなれば犯行の手段について法廷で述べる必要もないため、検察が司法警察へ捜査の深掘りを要求することもないはずである。だが、これまでの被疑者死亡のケースとは異なり、あまりにも奇妙な事件の経緯に対して、興味を示す者が現れても不思議ではない。それがもし一定以上の地位にいる場合、自分では想像が及ばぬ手段で一連の犯行について調査を始める可能性がある。葵の遺品にはマサカズから盗んだあの鍵もあるはずだ。ありふれたものなので注目されることもないはずだが、今後は懸念するべき点ではある。
資料を読みながら、仏頂面の伊達はこの件についてこれ以上考えるのが無駄だと感じた。彼はビールを飲み干すと、二缶目を冷蔵庫から取りだした。
伊達はテレビとゲーム機の電源をつけた。ゲーム機には六十本のゲームタイトルがプリインストールされていて、伊達はその中から一本のパズルゲームを選んだ。
ゲームパッドでカラフルな宝石を模したブロックを操作しながら、伊達はマサカズとの今後について考えを巡らせ、口元に笑みを浮かべた。
【無料版】第3話 ─俺たちのアジトで旗揚げしよう!─ Chapter2
あらためて見る。身長は百五十センチにも満たないのだろう。マサカズは目の前で缶ジュースを飲む七浦葵を見て、なんとしてでも彼女を守ってあげたいと思った。
ここはどこかだ。天気はわからない。わかろうとすればわかるのだろうが、意識をしなければ気候は感じられない。どこかは知らないが、繁華街だ。風景は何やらぼやけ、輪郭がはっきりとしないが、なんとなく、それがわかる。なぜ彼女とここにいるのか、それはわからない。しかし、ジュースを飲む葵は楽しそうな笑顔でこちらを見ている。なら、それでいいのではないか。考える必然性を見つけられなかったマサカズは、葵の左肩に掌を乗せた。
「あのさ、“葵ちゃん”でいいかな?」
「いいですよー。その方が恋人っぽい。あ、ならわたしは“マサカズさん”かな?」
「いいよ、伊達さんも“マサカズ”って呼んでるし」
「伊達さんとお揃いかー! いいかもー!」
両手でジュースの缶を持った葵は上体をくねらせ、マサカズは彼女の肩から手を離した。すると、葵はマサカズの手首を掴んだ。缶ジュースは、いつの間にか消えていた。
「頭、撫でてもらっていいですか? 好きなんです。子供みたいだけど」
「いいよ」
マサカズは葵の頭を撫でようとした。さらさらの黒髪の感触を指で確かめる寸前、彼は布団の上で寝転んでいた。
「だよな」
幻だ。死を否定する感情が、睡眠中にねじ曲がった幻想を現出させている。あの雨の夜から四日が経ったが、このおぞましくも儚い妄想に惑わされたのはこれで二度目のことだった。前回のそれは、ラブホテルのベッドでお互い裸のまま横になって語り合う、といった内容だった。警察署前の通りでは伊達に対して前向きな気持ちを表明したものの、あれから仕事もせず自室に籠もりきりであり、マサカズは自分の心の動きを分析できるほど暇を持て余していた。
この停滞は、自ら選んだ。だが、そろそろ先に進まないと悪夢が繰り返すだけだ。窓から夕日が差し込むなか身体を起こしたマサカズは、呼び鈴が鳴ったため玄関まで向かった。
「これって昔のゲームですよね」
薄暗い店内でテーブル筐体を前にした、安物のTシャツにデニム姿のマサカズは、対面に座る灰色のオーダーメードスーツ姿の伊達にそう言った。伊達は「そうだ」と返すとビールジョッキを口に運んだ。
マサカズはバイクでアパートまでやってきた伊達に連れられ、秋葉原と御徒町の中間に位置するバー、『ジョイスティック』までやってきた。昭和通りから路地に入った路面型店舗のここは、レトロゲームマニアをターゲットにした飲食店で、テーブル席はかつての喫茶店に設置されていたゲーム筐体であり、本棚には八十年代から現在に至るまでのゲーム雑誌のバックナンバーが収められ、店内音楽としてシンプルな構成の電子音楽が流されていた。
「まずな、毎度のことですまないのだけど、まだアイデアはまとまってない」
「いいですよ……あ、よくないかも」
レモンサワーのグラスを手にしたマサカズはそう言った。
「だよな。さすがに無職のままってわけにもいかないしな」
「それもそうなんですけど、ちょっとヤバいっぽいんです、僕」
「後輩のことか?」
「“さす伊達”ってとこですかね。正解です。こないだは言いそびれたんですけど、僕は彼女のことを好きだったんです」
「……助言のしようもないな」
「できる人なんていないと思いますよ。あ、だから話を変えましょう」
淡々とそう語るマサカズに対して、伊達は強い興味を抱いた。職業上、人と接する度に相手の性格や気質を探ることが多いのだが、マサカズの様な人物は珍しい部類に当たる。彼は迷いや悩みを隠さず吐露するのだが、その解決を他者に求めず自分でなんとかしようとする。そういった人種は大抵の場合、鈍感で楽観主義者なのだが、彼は感受性も豊かであり、どちらかと言えば悲観論者だと思われる。これまで接してきた者達と比較すると随分と現実主義に傾倒している様だ。伊達は二杯目のビールをバーテンに注文すると、木皿に盛られたポテトチップスをつまんだ。
「あ、伊達さんバイクなのにお酒っていいんですか?」
「上野に行き着けのサウナがある。今日はそこに泊まっていくよ」
「お酒からのサウナはヤバいんじゃないですか?」
「すぐに寝て、アルコール抜いてから朝にサウナだ」
「なるほど」
「あのさ、マサカズの両親って、どんな人なんだ?」
「普通ですよ。調べ済みでしょ?」
「データはあっても性格とか、お前をどんな風に育てたとか、そういった情報はない」
「あぁ、うーん……」
マサカズは腕を組み、首を捻った。
「いやー、普通ですよ。特別なこととか、心当たりはないかなぁ」
「じゃあさ、お兄さんいるだろ? そっちはどうなんだ?」
その質問に、マサカズはうんざりとして口元を歪ませた。
「あんまり、いい人ではないですね」
「ん? だけど前科とかはないだろ」
「スレスレはありましたよ。不起訴、だったかな? とにかく兄貴はいわゆるダメ人間って感じです」
「どの辺りが?」
「そもそも行方が知れないんですよ。もう何年も……三年ぐらいかな? 連絡が取れないんです。僕も実家も」
「仕事は?」
「さぁ?」
マサカズはポテトを鷲掴みしてそれを口に放り込むと、レモンサワーを呷った。“ダメ人間”の根拠は聞き出せていないが、伊達は今夜の深入りは酒が不味くなるだけだと思い、沈黙を保った。
「伊達さんって、ご兄弟は?」
尋ねられた伊達は長い足を組もうとしたが、背後がすぐ本棚であり、手前のテーブル筐体が邪魔だったのでそれを諦めるしかなかった。
「俺は一人っ子だよ」
「ちょっと羨ましいです」
「逆に俺は兄弟がいる方が羨ましいよ」
「鬱陶しいですよ。僕の場合。兄貴はいちいち偉そうなんです。そのクセ、地元のイベントとかバックレるし、勉強だってできないし」
子供っぽい愚痴だと感じた伊達は、鼻を鳴らせた。
「伊達さんのご両親はどんな人なんです?」
「うちの父は弁護士だ」
「じゃあ二世弁護士だ」
「いや、父は俺とは違って民事裁判専門だ。いわゆる企業案件を中心にやっている」
弁護士なら結局のところ一緒ではないだろうか。説明された内容を理解できなかったマサカズだが、特に興味のある分野ではなかったので、それ以上質問する気にはなれなかった。
「キャバクラ行ってるんですか? 最近」
急に話題が変わったため、伊達はマサカズの興味の理由を測りかねてしまった。
「行ってない」
「それはなによりですけど……実際、ああいったお店ってどうなんです?」
「どうって……酒呑んで、話して……」
「昔のゲームの話とかってするんですか?」
マサカズの質問に伊達は少しだけ身を乗り出し、ビールジョッキを手にした。
「全然ダメ。わたしわかりませーん、てな感じでさ」
「あー、やっぱり」
「ところがだ、二回目はそうはいかない。彼女たちはしっかり予習してくるんだよ。むしろあっちからレトロゲーの話題を振ってくる」
「うわっ! さすがはプロだ」
驚くマサカズに伊達は身を乗り出した。
「だろ? 俺も驚いたよ」
「うわー、そりゃハマりますよね」
マサカズがそう言うと伊達は顔を思い切り顰め、頷いた。
「そうそうそう!」
「なのに、最近は行ってない……やっぱりお金とかですか?」
「いや、借金はチャラになったし、金はまぁ……」
言いながら、伊達はさて自分がなぜキャバクラ通いに熱意を失ったのか、あらためて考えてみた。
「なんでだろうなぁ? なんで俺、キャバに興味がなくなった?」
今日の昼過ぎ、東京地裁でオレオレ詐欺の実行犯の弁護をしてきた伊達だったが、依頼者である被告人は記憶力に乏しく、アドバイスした内容の十分の一も供述ができなかった。こういったストレスのある現場のあとは、大抵の場合キャバクラやギャンブルで発散してきたものだったが、今夜目の前で酌を交わしているのはちりちり頭の青年である。伊達は上体を捩らせ、思考を巡らせ、美味しそうにポテトを頬張るマサカズを見た。
「あ」
伊達は間抜けな声を上げ、あることに思い至った。目の前で幸せそうにレモンサワーをグビグビと呑むこの彼は、もしかすると自分にとって初めてできた“友人”なのかもしれない。かりそめの話し相手よりも自分は彼を選んでいるということは、おそらくそうではないのだろうか。伊達はなにやらもどかしくなり、両肩を前後させた。その仕草があまりにも滑稽だったため、マサカズは吹き出してしまった。
すると、二人の鼓膜を重さと鋭さが入り交じる強い空気の振動が刺激した。
【無料版】第3話 ─俺たちのアジトで旗揚げしよう!─ Chapter3
バー『ジョイスティック』に面する夜の路地で、マサカズと伊達は並んで呆然と立ち尽くしていた。二人の視線の先には七階建ての細長いビルがあり、その六階、道路側の窓ガラスは割れ、中からは煙が立ち上り、炎がちらちらと見られた。ビルの出口からは口を押さえた者達が路上に逃げ出し、その場に蹲って咳き込む女性もいた。
店内で酒を呑みながら聞こえたあれは、おそらくこの災害のきっかけとなった爆発音だろう。あのビルで、何かが爆発した。路地に散らばる看板のや窓ガラスの破片を見て、マサカズと伊達は言葉を交わさずとも同じ認識に至っていた。そして雑居ビルの火災という緊急事態に、二人はこれからなにをするべきかの結論も共有していた。
「いけそうか、マサカズ? 消防と救急が到着するのに、おそらく最短でも五分はかかる。それにこの狭い路地ではハシゴ車は入れないだろう」
そう言った伊達は、風に流され漂ってきた煙に咳き込んでしまった。
「川の中でも息ができたんで、やってみます」
マサカズは背負っていたリュックからプロレスのマスクを取り出し、それを被って南京錠を手早く解錠し、「アンロック」と呟いた。周囲には火事場見物の野次馬もいたが、皆が災害に注目していて、マサカズたちの動向を気に留める者はいなかった。
「もし逃げ遅れている人がいたら、できる範囲でいいから運び出すんだ。チャンスは一度きりだと割り切ってくれ。もし助け出すべき相手の選択が必要なら、それはお前に任せる。助けたあとは、この路地側ではなく……」
「わかってます。できるだけ見られないように、ですよね」
マサカズは反社会的勢力の無力化をこれまで何度か行い、力の秘匿については自分よりわかっているようである。彼の様子から自信を感じた伊達はそう納得すると、「なら、任せた。俺はできるだけフォローする」と返した。
伊達が言い終えるのを待たず、仮面をつけたマサカズはその場から空中に舞った。旋風を浴びた伊達が視線を上げると、その先には燃えさかる雑居ビルと隣のビルの隙間に入り込んでいくマサカズの姿が在った。見物人は十数名ほどいたが、マサカズの姿は煙越しだったため、自分のように“あのビルの六階の側面目がけて跳躍して侵入する者がいる”ということが前もってわかっていなければ、視覚から得られる情報をその通りには解釈できないはずである。伊達は両手を握りしめ、煙を上げるビルの傍まで駆けていった。
煙に圧力があるはずもない。だが、マサカズは燃えさかるスナックの店内で白煙に圧されていた。おそらくこれは風圧を伴っているからだ。彼は煙の中で火花や炎をときおり目に入れながら、呼吸に何の支障もなく無臭の中、耐えきれないはずの熱気も感じずにいた。ただ、視界だけが不明瞭だった。うめき声、叫び声、泣き声、人の苦痛が音となって耳に届く。マサカズは聴覚を支配する絶望にひるみもしたが、この中にあって自分はまったく物理的な辛さがなかったため、特別な存在であるのだと思い込むことで勇気を奮い起こした。
僕はこの中で立っていられる。
僕にしかできないことがある。
救いを求める声に、僕は応えることができる。
「誰かいますかー!」
マサカズは、手で煙を払いながらそう叫んだ。鍵が発動してからでもこちらの声は届くはずである。奇しくもそれは、葵とのゴンドラでのやりとりであらためて証明されていた。しかし、明確な返答はなかった。
足元にワンピース姿の中年の女性が倒れていた。マサカズはそれを抱え、店内を進んだ。視線を下ろしてみると煙の中、ソファや床におびただしい数の人々が倒れていた。鍵は剛力を与えてくれてはいたが、ここから運び出せるとしてもせいぜい一度に三名が限界であり、救えるのはあと残り二名である。咳き込み、呻き、炎に焼かれながらも生存が認められる者はそれより遙か多くいた。救える命の選択は伊達に任されたものの、マサカズは即座に判断できなかった。女子供、そして老人が救助する優先順位としてよく言われていたが、スナックに高齢者と子供の姿は見当たらず、マサカズは目についた女性たちを両脇に抱え、背負い、三人の命と共に白煙の立ちこめる店内をあとにした。背中ではむごたらしい阿鼻叫喚が繰り広げられていたが、心を殺し、前に進むしかなかった。
三人の女性と共に、マサカズは隣のビルとの狭間に着陸した。救急車のサイレンが鳴る中、彼は女性たちをゴミ箱の傍に下ろした。
「こっちです!」
伊達の声が響いた。おそらくだが、自分の行動を追った上で救急隊員を誘導しているのだろう。マサカズはそう解釈し、その場から跳んだ。
「助かったんでしょうか?」
「おそらく。あのあとすぐに救急車で搬送された」
マサカズと伊達は、火災現場からほど近い御徒町の小さな公園で合流した。二人はベンチに並んで座り、ときおり明滅する、まだLED化されていない街灯に照らされていた。
「辛くないか?」
「辛いですね。例えばコンテナとかあれば、もっと沢山運び出せました」
「だけど、三人は救えた」
「それは、そうなんですけど……」
人の命を選ぶなど、これまでなら想像もできなかった。だが、いまの自分はそれができてしまう力を持っている。マサカズはあらためてそう感じると、拳を作った。
「なんでしょう、えらいことだって、それはわかります」
「だよな。嫌か?」
「嫌ではないです。ただ、ちょっと怖いかなって」
「それについては、俺もフォローするよ」
「ありがとうございます。そうですよね、僕なんかより伊達さんの方が正しい判断ができますし」
マサカズの言葉に伊達はベンチから立ち上がり、地面を蹴った。
「あのな! それは違うぞ! 俺は知識があるだけだ。判断についちゃ、お前だって中々のものだ」
怒声に、マサカズは困惑してしまった。それを察した伊達はネクタイを締め直し、咳払いをした。
「あー、悪い悪い。違うな、そうじゃないんだ。あー、な、なんだ? なんて言えばいい?」
「へー、喋るのが仕事の伊達さんでもそんな風になっちゃうんですか?」
「正直に言おう。マサカズ、お前は自己評価が低い。もっと自信を持て」
「いやでも伊達さんみたいな完璧超人といると、どうしたって僕みたいな負け組は気後れしちゃいますよ」
「俺はそんな大した人間じゃない。考えてみろ、キャバとギャンブルにハマってヤミ金に金借りて殺されかけたんだぞ? どちらかと言えばロクでなしに分類される」
「それを言ったら僕だって保証人になっちゃいましたし」
「だから同等だ。いや、あの件についちゃお前の方が上等だ。俺は自分の欲望のための借金だけど、お前は人を助けるための連帯保証人だろ?」
そう言われて、マサカズは目を落とし背を丸めた。連帯保証人は、前のバイト先の同僚の女性に頼まれ、ベッドを共にすることをぶら下げられ、邪な気持ちから引き受けてしまったものである。人を助けるという動機は希薄だった。
「えーとですね、あの連帯保証人は、前のバイト先の女の子に頼まれて、その、なんて言いますか、スケベ心からなっちゃったもので、立派な理由じゃありません」
「お前な、どこまで正直なんだ?」
「伊達さんには嘘をつきたくないんですよ。どうせあとから見抜かれちゃうだろうって気もしますし」
伊達は勢い良くマサカズの隣に腰を落とし、煙草とライターを取り出した。
「煙草、やめないんですか?」
「やめない」
「健康に良くないですよ。僕の父親や兄貴も吸いますけど」
「なら喫煙者の気持ちもわかるだろ」
そう言うと、伊達は煙草をくわえ、火をつけた。
「わかんないですよ。吸いたいって思ったことないですし」
伊達は煙草をひとふかしすると、左の踵を上下させた。
「今後についてだけどな、一週間以内に絵図を仕上げる」
「どうしたんです、急に」
「あのさ、三人の命を救ったんだぞ。凄いことだと思わないか?」
「まぁ」
「鍵の力は有効に使えるってことが、今夜証明されたんだ。なら、急ぐ必要がある。世の中の役に立てられるってことなら、早ければ早いほど救える人たちも多くなる」
伊達の言葉にマサカズは胸を張り、大きく息を吸った。
「そうか、三人も助けられたんですよね」
「やっと、実感か?」
「火事から人を助けたのはこれで二度目です。前に言いましたよね、実家の工場の火事」
「父親の命を鍵で救ったってことだっけ?」
「そうです。この鍵って、やっぱり人助けのために使うべきなんですよね」
「ああ、さっきみたいな人命救助もそうだし、困窮者や弱者の救済という考え方もできる」
「伊達さん、“エズ”ってなんだかよくわかりませんけど、計画的ななにかですよね。そっちは任せるので、よろしくお願いします」
マサカズは伊達に右手を差し出した。伊達は煙草をくわえたまま、その手を握り返した。
【無料版】第3話 ─俺たちのアジトで旗揚げしよう!─ Chapter4
御徒町の公園でマサカズと握手を交わしたあくる日の午後、伊達は渋谷区恵比寿までバイクでやってきた。恵比寿は渋谷と目黒の間に位置し、駅の近くにはオフィスや美術館、高級レストランの入った複合商業施設が建つ大都会の一角であり、昼を前にした駅前は多くの人々で賑わっていた。
駅からバイクで広尾方面に少しだけ進むと、そこは一転して都会の喧噪も届かない閑静な住宅街になった。
“伊達”と刻まれた表札の一軒家の前で、バイクを降りたポロシャツ姿の彼は、ヘルメットを脱ぎ額の汗を拭った。
「まずはお昼よね。食べてないでしょ?」
広々としたダイニングで、ブラウス姿の細身で壮年の女性にそう尋ねられた伊達は、「うん。まだ食べてないよ。母さん」と返し、イタリア製の黒いダイニングテーブルについた。その対面には、やはり初老の男性がいた。彼は白いワイシャツ姿で白髪を七三にきっちりと分け、銀縁の四角いフレームの眼鏡をかけており、鋭い目と真っ直ぐに結んだ口からは厳格な佇まいを醸し出していた。伊達は男に「父さん、最近腰はどうなの?」と尋ねた。
「だましだましだな。なんとか付き合っている、というところだ」
低く、やや掠れた声で“父さん”はそう返事をした。そして、そこから二人の間にしばらくの沈黙が訪れた。父は新聞を、息子はスマートフォンを手に取り、それぞれの方法でこの静寂を情報収集の機会として利用していた。すると“母さん”がワゴンを押してやってきた。その上にはざる蕎麦のセットが三人分用意されており、母は慣れた所作でそれぞれ配膳をした。伊達は目の前にせいろが置かれると、母に小さく会釈をした。
学生だった夏の昼、この生家でざる蕎麦を啜る機会が多い伊達だった。訪問は五年ぶりで、三時間ほど前に突然の連絡だったため、これしか用意ができなかったのだろう。「いただきます」と呟いた伊達は、ざる蕎麦に手を着けた。父も母も同じ様なタイミングで昼食に取りかかった。
「ゴールデンウィークなのに、お休み取れなかったの?」
母の質問に、伊達は首を振った。
「ちょうど明けから新件のラッシュでさ。休みは取れなかったよ」
それは事実ではあったのだが、五月の初旬は、ヤミ金、カルルス金融の取り立てが苛烈になってきた時期でもあり、母が望むように休暇を利用して生家で骨休めというわけにはいかなかった。摺り下ろされたわさびをつけ汁でかき回した伊達は、エアコンの効いているダイニングであるのにも関わらず、脇の下に汗を滲ませた。あのままだと、この両親にまで連中の取り立ての手は伸びていた。経験豊富で民事に精通した弁護士である父なら、自分よりもずっと巧妙な手段で対応をできたはずではあるが、そのような迷惑はかけたくなく、しかも借金の理由がキャバクラやギャンブルであることを知れば、この温厚で穢れのない人生を送ってきたであろう母は、自分に対してどのような気持ちを抱くか計り知れない。わさびの刺激が鼻を抜けていくのを感じながら、伊達はつくづくマサカズがやってしまった行為に感謝するしかなかった。
「お盆はないわよねぇ」
「赤日じゃないからね。裁判所が開いている以上、俺たちは休めない」
「あら、けどお父さんのところ、代わりばんこでお休み取れるんでしょ?」
話を振られたものの、父は返事をせず黙々とざる蕎麦に取り組んでいた。
「父さんのとことウチじゃ、規模が違うんだよ。それにウチみたいなところは緊急の案件も多くてさ、全員が臨戦態勢ってやつだよ」
「大変ねぇ」
「仕事だし、しょうがないよ」
伊達のその言葉に、父の眼光はいっそう鋭さを増した。
「ちょうどね、スイカ、買ってあるのよ。隼斗、スイカ好きよね」
「好きだよ」
「じゃあ、お昼のあとに出しましょうね。お父さんもいる?」
妻の問いに、夫は「ああ、書斎で」と短く返した。
「今年の梅雨明けはずっと先ですってね。全然雨なんて降らないのに」
「いい加減、梅雨入りとかやらなくてもいいのにね」
「ほんと、そう思うわ」
「ごちそうさま」
父はそう告げると立ち上がり、食べ終えた食器をワゴンに戻した。彼は伊達を一瞥すると、仏頂面のままダイニングから出ていった。
「お父さんね、こないだの健康診断、ちょっと数値が良くなかったのよ」
「どの辺が?」
父はこれまで酒や煙草を一切やらず、持病の腰痛以外はいたって健康であると認識している伊達だったので、母の言葉を意外に感じた。
「心臓よ。不整脈の疑いがあるの。来週にも精密検査」
「なんともないといいね」
「ほんとそう。引退してから人生楽しむんだって、いつも言ってるし」
ざる蕎麦を食べ終えた伊達は腰を浮かせ、人差し指で眼鏡を直した。
「父さんが? あの父さんが?」
仕事一筋の人生であり、ビデオゲーム以外は無趣味で旅行などにも興味がない父だったはずである。伊達は思わず父が消えた書斎へと続く階段を見上げた。
「ゴルフを始めてみたいとか、スペインに旅行がしたいとか。すっごくウキウキして話してくるのよ」
自分の知らない父だ。伊達は口元を歪ませ、小さく何度も頷いた。
二階にある書斎の二面の壁は、無垢材の本棚で天井まで埋め尽くされしており、そこには法律、文化史、心理学、そしてゲームの攻略本といった書物が収められていた。父と息子は革張りのソファに並んで座り、それぞれの手にはゲームパッドが握られていた。
「柏城の元で学べているか?」
最初に口を開いたのは父だった。二人の前には二十八インチのブラウン管のテレビが台の上に設置されていて、画面には縦方向に進行するシューティングゲームが映し出されていた。青い機体を父が、赤を息子が操作し、敵機を次々と倒していった。このゲームの特徴としては二人で同時に遊べ、ときおり画面に出現するベルと接触することでボーナス得点やパワーアップを得られる点にあった。
「まぁ、ぼちぼち」
「どうなんだ?」
「なにが?」
短く乾いたやりとりだった、息子である伊達が今日この生家を訪れた理由は特になく、なんとなくの思いつきでしかなかった。しかし同じ都内で暮らしているにも関わらず、五年もの間正月ですら一度も顔を出してこなかった。父から理由を尋ねられるだろうと思っていた伊達だったが、会話の皮切りがそこではないことに軽く苛立ちを覚えた。そして、彼の操作する赤い機体は敵弾によって爆散してしまった。
「父さんは何が聞きたいんだ?」
腹の探り合いのようなやりとりを打ち止めるため、伊達は単刀直入にそう尋ねた。父は軽快なパッド捌きで敵弾を回避すると、小さくため息を漏らした。
「柏城のヤツ、その昔に父さんにこう言っていた。ロクでなし共から高額で弁護を引き受けるのは、貧しく正しい人たちに手弁当で法律の加護を受けさせるためだ、ってな」
大学在学中、司法試験の受験に備えていたころ、父から紹介された柏城の理想に賛同した伊達だった。だからこそ父の事務所ではなく、柏城を選んだ。全ての事情をとうに把握しているはずの父がなぜ今さらそのようなことを言ってくるのか、伊達は疑問を抱いた。
「もちろん、オヤジの理念は俺もよく理解しているさ」
「だからさ、できてんのか? それ?」
父に問われると、伊達は返す言葉を失ってしまった。そう、できてはいないのだ。二十三歳という若さで司法試験に合格し弁護士となり、父の紹介で現在の柏城法律事務所の門を叩き、十年が経とうとしているのだが、所長や自分以外のスタッフが、そういった恵まれない人に対して無償で弁護を引き受けたことなど、これまで一度もなかった。父はその事実をおそらく知っているはずである。であるのに、わざわざそれを聞いてくるのは自分の口から理想の敗北を自白させたいからだ。父の意図をそう察した伊達は、画面の中で降ってきたベルに赤い機体を接触させ、ボーナス得点を獲得した。
「俺は、いずれはそうしたいって思ってる。オヤジができてない人助けは、俺が引き継ぐ」
「十年できてないのにか?」
「十年経ったからできるようになったこともある」
「それはまぁ、そうかもな」
「そうなの!」
声を荒らげた伊達の赤い機体は、敵機との接触によって再び爆散した。父はテレビから目を離さず、仏頂面をより険しくした。
「残機、イチ。あとがないぞ、隼斗」
「もうミスらないさ」
「これのアーケード版って、隼斗はやったことあるのか?」
「ある」
「アーケード版と比べたらこんなチープな様になっちゃいるが、これが発売された当時、みんなが目を輝かせたもんだ。家でいくらでもプレイできるってな」
父らしくない。彼は昔話をすることなどあまりなく、こういった場合は大抵何かの別の意図を含んでいる。だが、理想を否定され、ゲームオーバーに追い詰められていた伊達には、それに対して思案できる心の余裕はなかった。
「何が言いたいの?」
父の言葉を回りくどく感じた伊達は、早口でそう返した。
「理想を現実にするには一歩踏み出す必要がある。現実がどんなに厳しくても理想のために前進しなけりゃ、なにも実現しない。どんなチープな形でも理想を実現にすることで、人々を救えることだってある」
ありきたりで十人並みの内容だった。しかもそれを口にしているのは、民事裁判の世界では最強の一角とまで呼ばれている父である。今の自分は、この民事法廷の魔術師を以てして論評するのに言葉を失うほど落ちぶれてしまっているということなのか。残機を全て失った伊達は、うなだれ、パッドを膝に起き、眼鏡を外した。
「いつでもウチに来い。お前は子供のころ、父さんの仕事を悪い企業の味方をするから嫌いだ、なんて言っていたけど、それだけに限らんぞ。逆のケースだっていくらでもあるし、隼斗にはそういった案件を優先して回すことだってできる」
父の提案に、だが息子は返事をすることなく、彼は眼鏡をかけ立ち上がると書斎を後にした。
決してゲームオーバーではない。赤い機体はすべてが爆散したが、自分の理想はまだスタートさえしていない。バイクに跨がった伊達は、ジェットタイプのヘルメットをしっかりと被った。
【無料版】第3話 ─俺たちのアジトで旗揚げしよう!─ Chapter5
マサカズにとって、千代田区の飯田橋とは捉え所が難しい地域だった。新宿や渋谷、池袋といった山手線の主要駅と比較して著名なランドマークがなかったため、山手線の内側の都心ではあったもののこれまで訪れる機会もなく、理解度は極めて浅い。栃木の工業団地出身の彼にとって、夕日に照らされた首都高が通るこの街に対しては、名もなき都会といった印象しか抱けなかった。裁判所は霞ヶ関にあったはずであり、所属先の法律事務所は高田馬場だったので、交通の利便性からここに伊達は住んでいるのだろう。そのような薄い認識のまま、マサカズはSRXのタンデムシートからマンションの地下にあった駐車場に降り、フルフェイスのヘルメットを脱いだ。
Tシャツにデニム姿の彼が背負っている安物のリュックには、三日分の着替えと歯ブラシやタオルといった生活用品が詰められていた。
ビル火災での救助から三日が経った午後、アパートまでやってきた伊達は、強く、速い語調で反論を与える余地も与えない命令のような要求をしてきた。
「今から俺のマンションにきてくれ」
「何日か泊まり込みになるから準備をするんだ」
「飯田橋の駅からまぁまぁ近いから、不足分の補充はできる」
「現在、いくらの現金があるのか数えてくれ。もちろん、金庫の中や吉田から受け取ったぶんも含めてだ」
バイクに乗せられ、この高層マンションまでマサカズは連れてこられた。二人乗りにも少しは慣れてきたが、単気筒の振動に胃と腸を刺激されたマサカズは、伊達に続いて乗り込んだエレベーターの中で便意をもよおすのを感じていた。
伊達が住むマンションの、ヤニの臭いが充満したトイレは、自分が住むアパートのそれと設備としてはあまり違いは感じなかった。広さは負けるものの掃除は自分の方が行き届いている。床の汚れを見つめながら、便器に座ってたマサカズは頬杖をついた。
それでもやはり、思い知らされてしまった。各中央省庁の庁舎からも近い立地、首都高を望む二十階建ての立派な建物、オートロックを用いた玄関や、高級そうな建材だと思われる暗い色をしたエントランスの床や壁など、自分の住まう小岩の古ぼけたアパートとは格というものが違う。2LDKの間取りはまだリビングしか見ていないが、広々としていて、家賃もそれなりの金額であることだろう。伊達はここに住めるべき実績をもった弁護士であるはずだから、やはり自分のような底辺のアラサーとはかけ離れた存在である。マサカズはそれをあたらためて自覚しながら、トイレから出た。
「忙しくなるぞマサカズ」
いつもの仏頂面ではなく笑顔でそう言うと、伊達はマサカズをリビングのソファに促した。マサカズが腰を下ろすと、伊達は忙しない様子で迷ったのち、隣の部屋から椅子を持ち出し、マサカズの斜め向かいに座った。
「どうしたんです伊達さん。なんか、唐突過ぎて驚いているんですけど」
「すまん。そりゃそうだろう。まずはな、三千万円を資金洗浄する。本来なら五千万円まるごとが理想なんだけど、井沢さんは一度の機会だと三千万円が限界らしい。残りの二千万円は後日ってことになる。ただ、当面の資金については俺が用意する。四百万円だ」
興奮がちにそう言っている伊達の言葉がまったく理解できなかったマサカズは、ちりちり頭をかき、頭をぐるぐると回した。
「この当座資金で事務所を借りる。そこから実印と定款を作って公証役場で認証だ。取引先銀行に資本金を入れ、法務局に登記申請、これで俺たちの第一歩だ」
やはり何を言っているのかわからない。マサカズは座り心地のいいソファに身体を埋め、大きくあくびをかいた。
「マサカズ、お前が代表取締役で、俺も取締役になる。副社長ってポストでいいだろう。社名はお前が決めてくれ」
マサカズは身体を横に倒し、痒くもない首をポリポリとかいた。
「マサカズ? マサカズ?」
伊達は横になっていたマサカズを覗き込んだ。
「伊達さん、意味不明です。なんなんです、さっきから。伊達さん大暴走って感じ」
その呆れきった態度に伊達はうめき声を漏らし、全身を震わせた。
「あ、ああ、前提をすっ飛ばしていたか」
「そーですよ。急にウチにきて、三日分の着替え持ってバイクに乗れって、ここまではまぁまだいいですよ。いや、ヘンですけど。で、ここに連れてこられて、さっきからテーカンとかわけわかんないこと口走って、病気ですか?」
「すまん、すまん。興奮しちまって、大前提を忘れてた。あー、まずどこから説明していいのか……」
伊達は立ち上がると、ソファの周囲をぐるぐると歩き回った。
「僕の予測ですけど、例の“エズ”ってのができたんですよね」
マサカズの言葉に伊達は足を止め、彼の背後から嬉しそうに身を乗り出した。
「そうそうご名答。鍵の力の有効活用のため、会社組織を発足するって提案だ。それにお前が同意した場合、少なくとも一週間、俺たちは密接に行動を共にする必要がある。だから着替えを持参してもらっての泊まり込みが必要なんだ」
マサカズは浅く上体を起こすと、ソファの背後にいた伊達の鋭い顎を見上げた。
「えーと、僕が社長で、伊達さんが副社長ってことです?」
「そうそう」
「会社設立ってのも衝撃ですけど、役目が逆じゃないですか? 僕に社長なんて務まりませんよ」
「ああ、このままじゃ務まらない。だけどそこは俺がフォローする。この会社において最も重要なのは鍵の力だ。そしてそれを行使できるのはお前だ。従って、最終的な責任者はお前以外には考えられない。だから……」
言いながら、伊達はテーブルの上のノートパソコンを開いた。
「そうだ、これを読んでもらうのが先だったな」
そう促されたマサカズは身体をしっかりと起こし、ノートパソコンの画面に目を向けた。カブトムシの壁紙を背景にしたそこには、“事業計画書”と記されたプレゼン資料が映し出されていた。
「これ、僕にわかる内容になってます?」
「大丈夫だ。事業計画書ってやつは、中学生程度の学力でもわかるようにしなくちゃいけない」
そう言われたマサカズは、資料に目を通した。新たに会社を設立し、革新的な新技術を用いて、人命救助、危機対応、紛争解決を破格で行う。代表、山田正一。読み進めると具体的な業務内容が記されていて、そのどれもが鍵の力を用いなければ不可能なスピードと規模となっていた。確かに内容は理解できる。だが、マサカズにはいくつもの疑問が湧いてしまっていた。
「伊達さん、ヤバいですよこれ」
マサカズの感想に、伊達はにんまりと笑みを浮かべた。
「ヤバいだろ?」
「あ、勘違いしてる。僕が言ってるヤバいって、この計画、それこそ大前提がヤバいです」
「どの点がだよ」
「事業を成り立たせるための革新的な新技術って、つまりは鍵の力でしょ? それを取引相手に教えるんですか?」
「まさか。そこは秘密だよ。そう、今後雇用していく従業員に対しても、鍵については基本的に秘密としておく」
「そんなの、可能なんですか?」
「やるしかないだろ?」
いつもの伊達とは違う。その言葉から彼の知性が低下していると感じたマサカズだったが、現在の自分はやるべきことがなにもなかったため、ひとまず話を続けることにした。
「じゃあこの計画を進めるとして、何から手を着けるんです?」
「事業所を決める。どこでもいいけど、できるだけ都心がいいだろう。それと、会社名を考えてくれ」
「えっと、お金ですけど、あのお金、使うんですか?」
「人助けのための事業資金だけど、嫌か?」
「いえ、ようやく使い道が決まったって感じなので、気持ちの踏ん切りはつけますけど」
「でだ、あのカネ、五千万円だったよな。アレは違法な手段で手に入れたものだから、資金洗浄する必要がある」
「よくドラマとかで聞きますけど、それってなんなんです?」
「出所が違法なカネを合法化してしまうことだ。井沢さんに依頼してひとまず三千万円を洗う。もちろん、時間はある程度かかるから、当面の資金は俺が四百万円用意する」
「なんだかよくわかんないですけど、ヤミ金にお金借りてた伊達さんが、四百万円も持ち出せるのが疑問です」
「十年間コツコツ貯めてきた、とっておきだ」
「なら、少しは借金返済に充てるべきでしたよ」
「まぁ、そりゃそうなんだが……」
あまりの正論に、伊達は答えに窮した。
「なんか、色々とおかしくないですか? 鍵は秘密のままだったり、強盗したお金を資金にしたり。会社設立って言いますけど、これじゃまるで悪の秘密結社だ」
「まぁ、ぶっちゃけ秘密結社だな」
「嫌ですよ、そんなのの社長なんて」
「“悪の”が付くからだろ? 俺たちが設立するのは、恵まれない人たちを救う、悪じゃない秘密結社だ」
「聞いたことがないですよ、そんなの」
「それはお前の知識不足だ。世に在る秘密結社のすべてが、自分たちが悪だとは考えていない」
「うわー」
声を上げたマサカズは、再びソファに倒れ込んだ。これはおそらく屁理屈だ。しかしそれを指摘できるほど、マサカズは豊富な言葉を持っていなかった。自分はどうするべきか、結論がでないマサカズだったが、ひとつの大きな疑問が湧いてきたので、仰向けになって伊達を見上げた。
「伊達さん」
「なんだ、マサカズ」
「伊達さん副社長って言ってましたけど、弁護士はどうするんです?」
「事務所には今朝、辞表を出してきた」
その言葉に、マサカズは身体を起こそうとしたが誤ってバランスを崩し、床に転げ落ちてしまった。
【無料版】第3話 ─俺たちのアジトで旗揚げしよう!─ Chapter6
生家を訪れた二日後、伊達は所属する柏城法律事務所に辞表を提出していた。理由はマサカズと共に起業するためであり、まだしばらくは引き継ぎなどもあり完全に籍を外せたわけではないのだが、基本的には自由な立場となっていた。これについて伊達は「オヤジがマジで何も言わずに送り出してくれた。感謝しかない」と、マサカズに言った。マサカズは伊達のマンションに泊まり込み、マットレスとタオルケット、枕を与えられ、伊達と寝食を共にすることになった。会社設立に伴う事務作業はすべて伊達がリードする形で進められ、マサカズが自分だけで決めたのは社名だけだった。
「株式会社ナッシングゼロ?」
「ダメ、ですかね」
昼下がり、マンションのリビングでデリバリーしたモモ肉のフライドチキンを囲み、伊達とマサカズは社名について意見のすり合わせをしていた。
「由来を聞かせてもらおうか」
「なんも思いつかなかったからです。あと、まぁゼロからの出発って意味も含んでます」
「わかった。ならそれで登記しよう」
チキンを手にした伊達は、それに囓りついた。
「あ、リテイクはないんですか?」
「この点についてはマサカズに任せたんだ。代表の意見には従うよ」
ウエットティッシュで指を拭いた伊達は、チキンの脇に置かれたノートパソコンを手早く操作した。
「類似商号もクリアだな」
“ルイジショウゴウ”が何を意味するのかわからない。そう、起業を決めて以来、伊達の言っている単語は聞き覚えのないものばかりであり、最初のころはいちいち尋ねてもいたのだが、二日もすると物量が多すぎるためすっかり諦めてしまい、メモを取って夜に検索しておそらくこれのことだろう、という浅いレベルでの理解をするだけに留まっていた。
数日したのち、マサカズと伊達はバイクで渋谷区代々木までやってきた。新宿の南、渋谷区の北端に位置するこの街は、代々木駅が山手線と総武線、地下鉄大江戸線が通っているため、都内各方面へのアクセスは快適と言えた。街には予備校や専門学校がいくつか建ち並び、新宿と比べても行き交う人々の平均年齢は若く、彼らの集客を目的とした安価な飲食店も軒を連ねていた。
二人は代々木駅から渋谷方向に南下した住宅街にひっそりと建つ、何の変哲もないありふれた外観をした、三階建て鉄筋コンクリートの小さいビルまでやってきた。三階とも南側は窓になっていて、陽当たりの良さは前回の下見の際に確認済みである。問題があるとすれば、あまりにも特徴のない見た目であり、周辺にも似たような雑居ビルが点在しているので、うっかり見逃してしまうかもしれない。だが、そのうち慣れるだろうとマサカズは懸念を楽観に切り換えた。
二人は階段を二階まで登ると、マサカズが扉の鍵を開けた。このビルは一階あたりひとつのフロアしかなく、この階も中に繋がる扉はこれしかなかった。
「詰めれば十人は入れるけど、会議や打ち合わせ場所は作れないな」
がらんとした四十平米ほどのフロアを見渡した伊達は、不動産屋から渡された見取り図を鞄から取り出した。このフロアの他にもトイレがひとつ、とても狭いものの給湯場所が設けられてた。ここは二人で吟味し賃貸契約を結んだ、株式会社ナッシングゼロの本店となる事業所であり、机やパソコン、通信機材はまだ一切なく、そういったものの導入はこれからだった。
「トイレはひとつだから、当面は男しか雇えないな。男所帯でもトイレ問題は深刻化するケースもあるから、儲けを出してもっといい事業所に移転しような」
会社設立に伴う知識を必要としたものとは異なり、生理現象を起因としたよくわかる懸念の言葉だったため、マサカズは大きく頷いた。
「実印も定款も作ったし本店もできたから、ここからは登記と資本金の払い込みだ。そこまでいけば、もう会社設立は終わったようなものだ」
「えっと、定款だと事業目的は災害救助補助、危機対応補助、紛争解決補助ってありますけど、それって役所に審査が通るんですか? なにか、実績とかいるんじゃないんですか?」
「だから、全部“補助”って名目にした。これなら公証役場ははねることはない」
“公証役場”という単語は何度か出てきていたので、マサカズにも伊達の言っている意味はわかった。
「いずれちゃんとした資格とか取りたいですね」
「そうだな」
伊達は頷くと、マサカズに首を傾げた。
「それよりさ、どうなんだよ」
「なにがです?」
「小さいながらもここで俺たちはスタートするんだ。何か、感慨とかないかな?」
伊達はそう言うと、決して広くはないフロアをあらためて見渡した。マサカズもそれに倣い、穏やかな笑みを浮かべた。
「実感、さすがに沸いてきましたね」
「だよな!」
マサカズの背中を軽く叩いた伊達は表情を苦く崩し、上ずった高い声でそう言った。思えば彼の提案に流されっぱなしでここまできてしまった。もう流される生き方はしたくはなかったのに。だが、わかる。これまで仏頂面が貼り付いていたのに、この起業計画を持ち込んでからの伊達は、生き生きとして朗らかな笑顔になる機会が増えていた。マサカズはただそれだけで、今のところはこのまま進んでしまってもいいと考えていた。
事務所を借りてから、会社設立は順調に進んでいった。定款を公証役場に提出し、そこから一週間ほどの認証期間があったので、その間にパソコンや机や椅子、棚といった什器の手配を進めることになった。伊達は立ち上げ時点で、あと四人ほどのスタッフが参加すると言っていたので、マサカズは予備も含めて七人分の設備の手配や事務所で使う電話やネット関連の手続きに追われた。伊達のマンションで暮らす日々が続き、暇になればゲームでもやっていてくれと言われたものの、リビングのゲーム機には古いゲームしか入っておらず、マサカズにとってどう楽しんでいいのか今ひとつわからなかったため、ほとんど手は着けなかった。
定款は認証され、事務所に近い信用金庫へ資本金を払い込み、機材や什器の搬送も完了した。これまでにかかった資金は全て伊達が貯蓄から調達し、現在の資本金は二百万円だが、のちに一千万円に増資する予定になっている。マサカズが増資の必要性を伊達に尋ねてみたところ、彼は「体裁だ。資本金は会社の体力や資金調達能力を顕す。株式会社なら、資本金一千万円は最低限のラインだ」と、百度近いサウナの中で説明してくれた。
伊達がアパートを訪れてから二週間ほどが経った七月二十七日、株式会社ナッシングゼロは業務を開始することになった。会社の設立準備を終え、自宅アパートに戻っていたマサカズは、朝九時前に総武線で代々木駅までやってきた。生き物を滅ぼすかと思えるほど強過ぎる夏の光の中、駅前のゆるやかな坂道を渋谷方向に下っていき住宅街の路地に入ったマサカズは、気分が高揚していた。まさか無職だった自分が社長になるとは想像もしていなかった。何もかも伊達のリードで事は進み、自分がやったことなど関係書類の署名捺印や設備の注文、そして会社名の決定ぐらいだったが、今日という門出の日を迎えられたという達成感はある。
ビルの階段を駆け上がったマサカズは、事務所の玄関のドアノブに手をかけた。どうやら伊達が先に出社しているようであり鍵はかかっておらず、彼は中に入った。
七つの事務机のうち、四つに男の姿が在った。どうやら彼らが自分より先に出社した面子のようである。いずれもが年老い、枯れ果てた植木が列をなしているようだった。マサカズが戸惑うと、老人たちも同じように困惑した表情を浮かべた。
「その四人は前に言っていた創業スタッフです。あとみなさん、彼が山田社長です」
マサカズの背後から伊達は、よく通る声で事務所の全員にそう言った。老人たちは穏やかな様子になると、それぞれがうなずき、「社長かぁ」「若い!」「山田社長」「Tシャツなんだ」と呟いた。マサカズが振り返ると、三つ揃いのスーツを着た伊達がいた。
「左から、経理担当の木村さん、総務助手の浜口さん、事務担当の寺西さん、ネットワーク担当の草津さんです」
その説明に、マサカズは納得するしかなかったのだが、釈然とはしていなかった。
営業初日にマサカズが行ったのは膨大な量の署名と捺印だった。できるだけ理解を深めるため、伊達や老人たちから回ってきた書類について、マサカズはデスクのパソコンで検索してみた。どうやらそのほとんどは、公的機関への届け出書類のようである。税務署、年金事務所、労働基準監督署、そしてハローワーク。これら公的機関に対して法人としてそれぞれ社会保険や厚生年金、労働保険といった社会保障などの届け出書面を提出する必要があった。なるほど、まだまだ日本はハンコ文化なのだな。マサカズはそんなありきたりな考えに至りつつ、書類と向き合うことになった。
鍵を使った実務はマサカズ、そして総務と営業は伊達の担当と決めていたため、伊達は取引先の確保のため、心当たりに対して次々と電話をかけていた。
昼は六人で近所の定食屋に行き、マサカズはそこで老いた仲間たちから話を聞いた。木村は銀行に、浜口は商社に、寺西はアパレルメーカーに、草津はソフトウェア開発会社にそれぞれがかつて勤務した経歴があり、定年退職後にシルバー人材に登録し、そこでナッシングゼロの情報を知り、応募してきたということだった。トビウオの焼き魚定食を口に運びながら、マサカズは老人たちの話を淡々とした気持ちで聞いた。
「なんでおじいちゃんなんです?」
定時の午後五時となり、パートタイマーたちが次々と退社したのち、マサカズはデスクにいた伊達にそう尋ねた。
「パートとして安価で雇えるからな。嫌か?」
「嫌じゃないですけど、四人やってくるって聞いたから、てっきり鍵を使える若い連中だと思ってて」
「ああ、戦隊モノの発想か、悪くない。だけどな、鍵の拡散運用についちゃ慎重を極めないと」
伊達の言葉に、マサカズはゴンドラから転落していく葵の姿を思い出し、身震いした。
「わかりました。そうだ、金庫を買いましょう。残り七本のスペアキーは、ここで厳重な管理が必要です」
「わかった。それについてはお前に任せる」
「いつから初仕事になりそうですか?」
マサカズの問いに、伊達は顔を曇らせると煙草をくわえ、火をつけた。この事務所は契約上禁煙ではなく、会社のルールとしても老人たちが退社後の定時外は喫煙を認めることにしていた。
「いま、営業をかけている。もうちょっと待ってくれ」
「僕たちやおじいちゃんたちの給料もありますし、早くバリバリと働きたいですよ」
「待ってくれ。今はそうとしか言えない」
「アテにしてますよ、伊達さん! あ、それと……」
「なんだ?」
「おじいちゃんたちの前で僕に敬語使うの、アレやめてくれませんか?」
「上下関係上、そうするのが当たり前だ」
「けど気持ちが悪いです」
「草津さんたちからヘンだと思われるけど、いいのか?」
「慣れますって」
「わかった。なら明日から説明した上でそうする。しかし、今後取引先には別だぞ。俺はお前を代表と呼び、敬語を使う。一人称も“私”か“弊社”だ」
なにやら面倒だ。しかし、これが知人同士で起業した際に生じるルールのひとつなのかもしれない。マサカズは紫煙を手で払うと、ふとあることに思い至った。
「あ、伊達さん」
「なんだ?」
「僕と伊達さんって、友だちなんですかね?」
「少なくとも俺はそう思っているぞ」
小さく微笑んでそう返事をした伊達に、マサカズは胸の奥からむずむずとこみ上げてくる何かを感じた。
「じゃあ、役員会議はこれぐらいでいいか?」
「帰るんですか?」
「ああ、ちょっとアテにしている会社の社長さんと呑んでくる」
「あ、それなら僕も一緒に行きますよ」
「いや、俺だけでいい。接待のスキルにつては、おいおい教えるから、それからだな」
「なんだか伊達さんに頼りっぱなしだ」
「実務は全部お前に任せるんだから、これぐらいはさせてくれよ」
伊達は灰皿に煙草を押しつけると、席を立って上着を着た。
「戸締まりは任せた。じゃあ、お疲れ様」
挨拶を残し、鞄を手にした伊達は事務所から出ていった。ひとり残されたマサカズは、南側の窓のひとつを開け、縁に半分腰を下ろした。穏やかな蝉時雨のコーラスの中、ひとり路地を行く伊達の小さな背中を、マサカズはぼんやりと見つめた。

【無料版】第3話 ─俺たちのアジトで旗揚げしよう!─ Chapter7
Tシャツにスウェット姿の伊達は洗面所で歯を磨き、口をすすぐと、リビングに向かい冷蔵庫から小さな紙パックのトマトジュースを取り出した。時刻は朝の七時で出社までは二時間ほどある。ソファに着きトマトジュースをストローで飲み干した伊達は、天井を見上げた。
昨晩、新宿の居酒屋での接待は、己の現在というものを悪い意味で思い知らされた酒席だった。相手は警備会社の代表であり、伊達が提案したのは確保率百パーセントを保証する追跡システムだった。不審者を発見しだい、追跡を開始し確実に身柄を確保する。その実行者はマサカズではある。成功の根拠については企業秘密であり、疑義については無料お試し期間での実績をもってただす、と説明したのだが、経験豊富な老経営者はにこやかなままおちょこで酒を呑むばかりであり、いつまで経っても前向きな話には進んでくれなかった。弁護士としての実績がなければ、おそらく相手はプレゼンを終えた直後に店を後にしていただろうと思われる。別れ際には「会社がんばってね。またなんかいい話があったら連絡ちょーだい。あと、柏城ちゃんによろしく言っといて」と言われてしまった。つまり、今日説明したビジネスプランについては、すべて聞き流されてしまったということになる。
今日は新会社を始動して二日目だが、実のところマサカズが起業に同意した二週間前から、水面下で営業活動は始めていた。これまで十件ほど、会社や関係省庁の会議室や夜の店でプレゼンをしてきたが、結果は昨晩と似たり寄ったりであり、空振りの連続となっていた。弁護士をしていたころは法廷で検察官や証人、裁判官を弁舌で制してきた伊達だったが、商取引となると話は別である。経験を重ねればいずれは結果が伴うはず。当初はそう思い込んでいたのだが、半月近くも同じような営業活動が続くと、敗因の分析も捗ってしまう。根拠の説明が必要だ。考えてみれば当たり前のことだった。それこそ自分のこれまでの仕事とは、それを万人に証明することだったのだから。被告人が犯罪にいたる汲むべき事情の根拠。被告人が再犯をしない根拠。いくつもの“根拠”をかき集め、それをもっともらしく明らかにする。徹底して磨いてきた仕事のテクニックを、今回に至っては全く使えない事態に陥っているのだ。これまでの自分なら、このように簡単な欠陥は事前に気付き、対策なり対応なり施してきたはずだ。背中を押すような焦りから、甘い見積りをしてしまったということになる。昨日はマサカズに待って欲しいと言ったものの、いつまで待たせてしまうのか伊達自身わかってはいなかった。しかし、もう矢は放たれた。退路を断ち、この商売をできるだけ早く軌道に乗せなければならない。資金洗浄が済めば当面の維持費は捻出できるが、元は汚れた金であり、それを投資などではなく運転資金に投入し続ければ、おそらくマサカズは心を病んでいくことだろう。
伊達は洗面所で顔を洗った。洗面台は綺麗に掃除され、これは数日前まで泊まり込みで起業の準備を共にしたマサカズがやってくれていた。これまで二日以上このマンションに人を泊めたことがなかったため、マサカズと生活を共にした十日間は新鮮な体験だった。食事はマサカズが作ってくれることもあった。簡単なパスタやチャーハンなどだったが、これまでほとんど使われることのなかった調理器具や食器が活かされたのは、可笑しくもあった。台所にはあらたに調味料が補充されたのだが、今後自分か誰かがこれを使う機会が訪れることはないだろう。そう判断した伊達は、最終日にそれら全てをマサカズに待ち帰らせた。「自炊しないとお金、もったいないですよ。僕もあんまりやらないですけど」マサカズはそんなことを言いながら、レジ袋に調味料を詰め込んでいた。
ひとつ不満に感じたのは、自分が所持していたビデオゲームを彼がほとんどプレイしてくれなかったことだ。そもそもスマートフォンのパズルゲームぐらいしかゲームはやらず、しかもここにある、いわゆるレトロゲームには関心を示してくれなかった。一度、その理由を尋ねてみたところ、彼は「いや、だって古くさいって言うか、画面が大雑把だし……」と、申し訳なさそうな様子で返答した。ゲームの話自体、ホステスとしかしたことがなく、彼女たちは職務のため勉強をして強い興味を示すふりをしてきたのだが、その会話を楽しみたいがため、ビジネストークであると意識するのは無粋だと心がけていた。なので、古いゲームに対しての興味はマサカズの反応が一般的なものなのだろう。プロレスについても話をしてみたが、やはり申し訳なさそうに彼は「ヤラセ……でしょ?」と呟き興味を示してくれなかった。
唯一、サウナだけは共に楽しむことができた。興味を示してきたので、楽しみ方を教えて共に実践してみたところ、彼はすぐにその素晴らしさに目ざめてくれた。サウナと水風呂、そして外気浴によって温冷刺激を受けることを“セット”という単位でカウントする。目的は“整う”と呼ばれるトランス状態を得ることにあるのだが、通常だと三セットほどを要し、自分もそうだったのだが、マサカズは最初の一度でその領域に達してしまった。湯上がりの飲食スペースで炭酸飲料とイオンウオーターのカクテルジュースのグラスを手にした彼は「今までの人生、損してました! 取り戻さないと!」と、興奮気味に言ってきたので思わず大笑いをしてしまった。
タオルで顔を拭った伊達は、再び今後のことを考えた。どうすれば仕事が取れるのか。これまでとは方法を変える必要があるのだろうか。新たなスタッフを招き入れるのはどうだろうか。しかしいいアイデアなど即席で出るはずもなく、身支度を終えた彼はヘルメットを手にマンションを出た。エレベーターで地下駐車場まで降りた彼は、停めてあったシルバーのSRXのシートを軽く叩き、ため息を漏らした。
マサカズの超能力を見せられれば、これまでに行った十件の営業はどれも成功していたのだろうか。目に見える根拠を示せればよかったのだろうか。しかし、あの不可思議な力を見せられた相手は、如何なる反応を示すのだろうか。これまで現実的な証拠を積み重ねることで、極めて常識的な世界である法廷で実績を積んできた伊達にとって、非常識の開示という未知の領域については想定が全くできなかった。
自分はどうだろう。結束バンドを引きちぎり、巨漢を吹き飛ばし、弾丸にビクともしないあのちりちり頭の彼のことを、自分はどう受け止めたのだろうか。都道をバイクで駆けながら、伊達はあらためて当時の出来事を整理してみたが、すぐにそれが無意味であることがわかってしまった。ヤミ金に拉致され、債務者のひとりが死に、巨漢に胸ぐらを掴まれ脅迫された。あのような状況は平時ではなく異常であり、その中で見せつけられた力だった。あるいは、営業相手を何らかの危機的状況に陥れ、マサカズにそれを解決させるというのはどうだろうか。我ながら愚にも付かない発想だ。交差点で信号待ちをしていた伊達は、うんざりして頭を傾けた。
ここまで行き詰まると、考え方を変える必要がある。営業手法を検討するのではなく、営業先の方向性を変えてしまうのだ。その発想に至った伊達は信号を渡るとバイクを停め、ヘルメットを脱ぎスマートフォンを手にした。
「仕事の斡旋ねぇ」
井沢はハンチング帽を目深に被り直すと、手にしていたあんパンを口にした。伊達と井沢はこの日の正午過ぎ、秋葉原の公園で落ち合っていた。二人はミンミンゼミの大合唱のなか、公園の端のベンチに並んで座り、高いネットを背にしていた。伊達の手にはカレーパンが握られていた。二人の前では低学年の小学生たちがサッカーボールを蹴り合い、幼い歓声が上がっていた。
「ぶっちゃけこの二週間、空振りなんですよ」
「つーかよ、事務所辞めて起業なんて、正気か?」
「このままじゃ正気を保てないと思ったから、マサカズとの起業に至ったんです」
「まぁ、お前は刑事弁護人に向いてるとは思っちゃいなかったけどな」
井沢の指摘に、伊達は呆然となり、顎を落とし、目を見開いた。
「だってよ、お前はおセンチな理想主義のロマンチストだ。自分ではわかっちゃいないかもしれねぇが、決して現実主義や合理主義者には徹せられない」
「いや、それは……」
あまりにも直球の指摘だったため、伊達は反論の言葉が浮かばず、そもそも自分は反論自体したいのかどうかもわからなかったため、ひどく動揺してしまった。
「山田の力が活かせるような仕事。しかもその方法について一切詮索をせず、結果だけを求めるクライアント。それでいいんだよな」
「はい。見つけられそうですか?」
「心当たりはいくつかあるが、条件はないのか?」
「えっと、それって……」
「荒事もあるんだよ。そういった案件は。池ドラのときみたいなヤツだ」
その説明を理解した伊達は、カレーパンを頬張りそれを紙パックの牛乳で流し込んだ。
「暴力系は、ちょっとマサカズの心が持ちませんね」
「もったいないな。いい稼ぎになるんだけどな」
「瓜原みたいな猛者相手だったらそうでもないみたいですけど、一方的な暴力はマサカズにとって精神的に苦痛になってしまいます」
その言葉に、井沢は鼻を鳴らしてため息交じりの笑いをこぼした。
「ならいっそよ、格闘技デビューはどうだ? ボクシングに総合でも最強になれんだろ?」
「強さがデタラメ過ぎて、力の秘密を勘ぐられるだけですよ」
「その力ってやつだけどよ、お前にもわかってないのか?」
「然るべき研究機関に調べてもらえれば、何かが判明する可能性もありますが……すみません、ちょっとあの力は色々と面倒な部分があって、井沢さんにも自分が知っていることを教えられません」
「いいよ。依頼があったら調べるだけだからよ」
つまり、自分たちに興味を持つ者が現れて、そこからマサカズの力の秘密の調査を依頼されれば、この隣に座る凄腕の情報屋は容赦なく調べ上げるということだ。井沢の返事を伊達はそう解釈した。
「それってつまり、こちらが対価を支払ったら、調査はしないってことですか?」
「まさか。カネになるネタなんだ。当然調べる。で、お前が口止め料を支払えば、先方には仕事をしくじったって詫びを入れ、依頼料を全額返金する」
「怖いですね。井沢さんって」
「だからお前のわがままな依頼だって受けられるんだよ。何日か待ってろ。都合のいい案件を仲介してやる」
そう告げると、井沢はあんパンの欠片を口に放り込み、腰を上げた。
「けどよ、伊達先生。お節介だが忠告しておく」
その声はいつになく低くくぐもっていた。伊達は井沢を見上げ、人差し指で眼鏡を直した。
「山田と関わるのはリスキーだ。お前はあの奇妙な力に取り憑かれている。これから、らしくない失敗が続くかもしれねぇ」
「認めます。けどあいつは友だちなんです。おそらく、俺の人生にとって初めての」
「失敗の先に満足があるとは限らねぇぞ」
背中を向けたままの忠告に、だが伊達は返事をせず、ストローをくわえて牛乳を吸い込んだ。すると、彼の足元にサッカーボールが転がってきた。
「すみません」
男子小学生がそう言いながら伊達の元まで駆けてきた。伊達は軽くボールを蹴り戻した。井沢の姿は、もう公園にはなかった。
【無料版】第3話 ─俺たちのアジトで旗揚げしよう!─ Chapter8
「そう、俺、社長になったんだよ」
事務所の電話機を耳に当てたマサカズは、栃木の母親にそう報告した。四人のパートタイマーたちは彼の言葉に耳をそばだてていた。
「いや、すっげぇ弁護士さんと友だちになってさ、その人がほとんど考えてくれたんだけど、俺にしかできない仕事なんだよ。人助けとかやる……とにかく、もう無職じゃないから安心してって」
母親にそう言いながらもマサカズは、ともかく実績を上げるまでは両親を安心させられないと自覚していた。受話器を置いたマサカズは両手を頭の後ろで組み、座っていた椅子を腰で回した。
「あ、そーだ。草津さん」
マサカズは席から立つと、ひとりのスタッフに声をかけた。創業スタッフのひとり、草津は四人のスタッフの中で最も小柄で痩せていて、ふさふさの白髪で常に柔和な笑顔を絶やさないネットワークエンジニアだった。担当するのは会社の通信関係の整備と管理だったが、サイト構築の技量もあったため、空いた時間を利用してナッシングゼロのウェブサイトを作ることになった。ひとまず、トップページと会社案内のページを公開し、ここに山田正一はナッシングゼロの代表として、全世界の誰もが知りうることができる名前となった。もちろん、公開初日のアクセス数は一桁であり、その全てのIPアドレスが事務所のものと一致していたのだが。
「きのうから、アクセス件数どうです?」
その日の朝、草津のデスクでマサカズは恐る恐る尋ねてみた。
「いやぁ、それこそゼロだよ。だって周知もできてないしね。これからだよ。それと、知名度を上げるには、SNSも活用しないと」
草津はおっとりしした調子でそう返した。
「SNSかぁ、なんかアレっていっぱい種類があるんですよね」
「アレ、マサカズ社長はやってないの? 若いのに」
「してないですね。なんか面倒なんで」
「今どきの子にしちゃ珍しいね。承認欲求が低いのかな?」
「そういうのもよくわかんないんですよ」
マサカズはそう言うと、ちりちり頭をひとかきした。本日は七月末日であり、始動から四日が経っていた。四人の老人たちは伊達から自身のマサカズへの言葉遣いへの説明を受け、マサカズとも協議した結果、自分たちも内部では彼に対して敬語を使うかどうか、呼称をどうするかについてもそれぞれの判断で決めることになった。
「まぁでも、おいおいつぶやきとかアレとかそれとかやっていきましょう。草津さん、色々と教えてくださいね」
「もちろんもちろん、いつでもどうぞだよ」
これは会社の社長とパートの老人ではなく、なにやら孫と祖父のようなやりとりである。マサカズはそう感じながら、自分のデスクに向かおうとした。すると、いくつもの視線を彼は感じた。どうやら、残りの三人の老人たちがこちらに濃淡はあれど意識を向けているようである。草津との接触を、自分たちにも施して欲しい。マサカズは年寄りたちの気持ちをそう察したが、応えられる自信もなかったので、ぎこちない笑みを浮かべるだけだった。
伊達からは朝一番に連絡があり、今日は出社せず直行して仲介業者と打ち合わせをするとのことだった。電話を受けた事務担当の寺西は、マサカズに「井沢さんと会ってくる、と伝えてくれですって」との伊達からの伝言を伝えてきた。伊達は事務所開き以来、営業のために事務所を空けがちだったが、彼がいないとなにをすればいいのかわからなかったマサカズは、今日も暇を持て余すことになった。
おそらく、ついさきほど草津以外の三人がコミュニケーションも求めてきたのは退屈を紛らわしたいためだろう。マサカズはそのような結論に達したが、この状況を長く維持できるとは思えなかったので、早く何らかの仕事が決まってくれないかと焦れていた。
正午が過ぎ、マサカズと四人の後期高齢者は恵比寿駅前の中華料理屋にいた。合わせて五人だったので、四人掛けのテーブルに三人で一組と、カウンターに二人といった編成での着席となった。マサカズは社長ということでテーブルを勧められ、草津と寺西と同席することになった。
「ヒマですよねぇ」
レバニラ炒め定食に箸を付けながら、一割しか頭髪が残っていない寺西はゆっくりとそうぼやいた。すると、すぐ傍のカウンターに着いていた木村と浜口の二人も振り向いて強い口調で同意した。
「うーん、そうですねぇ……とは言っても僕から皆さんにお願いできることはありませんし」
パイコー麺を平らげたマサカズは四人にそう言った。現在、基本的には業務の指示はすべて伊達から下りてきていて、マサカズから要請できることは、小間使いや書類の確認といった実に小さな範囲でしかない。だが、四日が経って暇を持て余し気味なパートタイマーたちには不満も芽生えつつある。マサカズが自分から出せる実りある命令を考えていると、隣で麻婆春雨定食に取りかかっていた草津が口を開いた。
「まぁ、伊達副社長が営業に奔走しているわけだから、ヒマは仕方ないと割り切ろう」
「だけどね、僕なんかはカネに困ってないけど家にいてもヒマで仕方ないから、山田社長のここに応募したわけだよ。なんかした〜い」
最初は早口で、最後はふざけた語調で、カウンターの浜口はそう言い放った。草津は白髪を撫でつけると、ため息をもらした。
「マサカズ社長、ちょっとヤンチャすることになっちゃうけど、いいですかな?」
草津は右指の親指を立てた。マサカズはその真意を測りかねたまま、パイコー麺のスープを丼から啜った。
「全員、インストールはできたようですね」
草津はマサカズたち四名のパソコンの画面を次々と見て回り、自分のも含めてどれも同じゲームのタイトル画面が表示されているのを確かめた。
「えっと、“マイニングクラフト”って読むんですよね、これ」
マサカズがそう問うと、草津は「そう。みんなはマニクラって略してるよ」と、返した。草津は皆を見渡すと、ひとつ掌を打った。
「えーと、いま皆さんのパソコンにインストールしたのはゲームです。みんなでプレイできるマニクラというもので、四角いブロックばかりの世界で採掘をして資源を得たり、それを使って建築したり、牧畜、狩り、モンスターとの攻防戦、とにかくなんでもアリのゲームなんです。まずはゲームをしながら僕が指示を出しますので、“なに言ってやがんだ”とか思うかもですが、とにかくまずは従ってください」
草津の説明にマサカズは頷いたが、他の三人の反応は鈍かった。それを察したのか草津が笑顔で「あ、これは暇つぶしです。副社長がお仕事をとってくるまでのです」と付け足すと、彼らはようやく鼻を鳴らして同意した。
それから二時間ほど、草津の指導のもとマサカズたちは“マニクラ”に興じた。マニクラは二億本以上販売されている、全世界で最も売れているゲームソフトであり、マサカズもプレイしたことはなかったが、その存在は知っていて興味もあったので、スムーズに楽しむことができた。五人はすぐに役割を分担し、草津が全体の指導と管理、木村が食糧の調達、浜口が武器やツールの作成、寺西が拠点の建築、そしてマサカズが探検を行うことになった。担当部分の多くは重複する内容もあったが、草津以外は初心者ということもあり、仕様の理解を深めるための分担だった。
「草津さん、どうしてこのゲームを?」
マウスを操作しながら、マサカズは草津にそう尋ねた。
「孫がやってるんだよ。上手いんだよね」
草津は顔をほころばせた。
「孫なんてさ、マニクラで動画配信やってて、大人気で登録者数も五万人もいっちゃってるんだよ」
「凄いですね! いや、僕の兄も動画配信やってたんですけど、登録者なんて十人ですよ」
「どんな動画やってたの?」
「もの申す系ってやつですか? 世の中の出来事に文句を言うしょうもないヤツです。しかもアップロードとか全然できないから、結局僕がやる羽目になって。僕だってネットはそれほど得意じゃないのに。再生数もやっとふた桁だったんで、兄貴もへこんで三回でやめちゃいましたよ」
「社長、お兄ちゃんいるんだ」
身を乗り出してそう尋ねてきたのは浜口だった。
「いますけど、もう何年も連絡とってないです」
「やっぱり社長みたく、イケメンなわけぇ?」
浜口はにやけ面のおどけた調子だったので、マサカズは少しばかりうんざりとした。浜口は老人にしては大柄でしっかりとした体格の持ち主で、ぎょろりとした目の禿頭だった。
「どーなんでしょうね? 少なくとも僕よりは目立つ感じです」
その説明に浜口は頷くと、興味を失ったのか素面でモニターに向き直った。
夜の八時、事務所ではひとりの青年と四人の年寄りたちがモニターに向かってキーボードとマウスを忙しなく操作していた。
「チェストにパン入れといたから」
「パン、ありがたいねぇ」
「ちょ、ちょ、スケルトンが邪魔!」
「うわっ、マグマだらけですね」
「いやー、それにしても経験値ってなんの意味があるんだ?」
午後二時のプレイ開始から六時間が経っていた。五人はすっかり“マニクラ”の協力プレイにはまり込んでいた。その間、宅配便の受け取りや電話、支払いなどといった細かな仕事はそれぞれこなし、会社の業務に穴は開けなかった。
「弓ってどうやったら作れるんだ?」
マサカズが独り言を漏らすと、背後から「棒と糸だ。あと弓には矢も必要だ」と、声がした。振り返ると、そこには額から汗を垂らした伊達の姿があった。伊達は何度か手を叩き、皆の注目を引いた。
「定時を三時間超えてますよ! 残業代は出ませんからね!」
老人たちはそれぞれマウスとキーボードから手を離した。草津は席を立つと伊達に頭を垂れた。
「ごめんなさい。皆がヒマって言うものなんで。ソフト代は私が負担しますんで」
草津の謝罪に、伊達はハンカチで額の汗を拭うと、ネクタイを緩めた。
「いいですよ。自分が仕事を持ってこれないから、皆さんもヒマなんですし、ソフト代は後で会社に請求してください」
伊達は穏やかな口調でそう告げると、あらためて一同を見渡した。
「せっかくなんで、今から呑みに行きませんか? 会社持ちで」
その言葉に老人たちは沸き上がったが、マサカズは伊達の優しすぎる態度に違和感を覚えた。伊達は自身のふがいなさを理由に、いつもの鋭さや険しさを失っているように思える。いつもの彼ならゲームにうつつを抜かす自分たちを一喝するはずだ。マサカズはパソコンの電源を切ると、楽しげにパートタイマーたちと談笑する伊達の背中を不安げに見つめた。
【無料版】第3話 ─俺たちのアジトで旗揚げしよう!─ Chapter9
不安は杞憂に過ぎなかった。八月四日の夜九時、マサカズは伊達のバイクで群馬県嬬恋村の人里離れた山間の国道までやってきた。国道と言っても二車線しかなく車の姿や人気は全くない。そこから枝分かれした小道を進むと灯りも届かなくなり、伊達は持参した懐中電灯で足元を照らした。梅雨もとうに明け、今夜も三十度近い熱帯夜だったが、緑が豊富なここは涼しい風が通っていた。周辺では梟が鳴いていたのだが、二人は生でそれを耳にするのは初めてだった。
少し進んで行くとその先に、三階建ての木造建築物が現れた。それは二十年前に廃業した旅館であり、営業を停止してからは、壁材などに使われていたアスベストの処理工事が行われた以外、誰の手も入らず、経年によって建物は腐敗し朽ち果てていて、その姿は正に廃墟としか形容しようがなかった。傾いた看板は最初の“縁”と最後の“温泉”という文字が読み取れたものの、どうしても二文字目は識字できなかった。
「こりゃ、肝試しスポットですね」
「実際そうだ。動画配信者とか、よく来るらしい。俺はそいつらの警戒に当たる」
暗闇のなか、物言わぬ廃墟にマサカズは言い知れぬ圧迫感を抱いていた。宿泊施設としては小規模な建物だったが、これまでの自分であれば、これからたったひとりで対するには手に余る巨大さであり、得体の知れぬ怪物の様にも思えた。
二人にとってここは、業務開始から八日目にして受注できた、初仕事の現場だった。
「マサカズ、どうだ、できそうか?」
「なんとか……」
答えながらマサカズは、リュックから黄色いヘルメットを取り出した。額の部分に電灯が取り付けられていたそれはトンネル工事などに用いられる作業用であり、今夜の仕事のため会社で用意したものだった。
依頼内容はこの廃墟の基礎的な解体だった。権利問題や費用負担などの押し付け合いで二十年も放置されていたのだが、先月ようやく解決の運びとなり、ここには新たに旅館が建つらしい。依頼主はその経営母体であったのだが、解体費用をできるだけ抑えようとしたため、業者の選定に難航していたとのことである。井沢の情報網はその困窮を捉え、伊達の元に今回の仲介となった。報酬はあくまでも依頼内容を成立させた場合にのみ支払われ、保証の類は一切ない。そのかわり、法に触れない限りどのような方法をとっても構わず、それについての詮索はしないという条件も取り付けられた。
「破片の長さは最大で二メートル。幅は……」
「二トントラックの荷台に積み込める大きさ、ですよね」
「そうだ。俺は群馬県って初めてなんだが、やっぱり対立煽りとかってあるのか? 栃木とは隣同士だろ?」
「ありませんって。あんなのテレビとかで言ってるだけですよ。僕にも群馬のツレだっていますし、なんなら結婚したヤツだっていますよ」
「そうか」
「それよりもさすがは伊達さんだ。一週間ぐらいでこんな大きな仕事を持ってくるなんて」
「奥の手を使ったんだ。井沢さんっていうな。だから実際は恥じ入ってる」
「いやー、にしても井沢さんって凄い人なんですね。何でも屋さんだ」
「すべては人脈だよ。あの人は元刑事だ」
「かっこいい……そんな人と知り合いなんですね」
「元はオヤジのツテだよ。俺なんて大したもんじゃない」
「またまた……」
「そう、前もって言っておくけど、今からやる仕事は完全に合法じゃない。こういった解体には免許が必要だけど俺たちにはそれがない」
「そこは引っかかりますけど、僕たちがやらないと次の旅館が建たないんですよね」
「ああ、どの業者も条件が合わなくて及び腰どころか無視を決め込んでる。俺たちしかこの仕事はできない」
「誰かが助かるんなら、やりますよ。じゃあ、ぼちぼち始めますね」
マサカズはヘルメットを被り、ベルトのバックルにゴム紐でくくりつけていた南京錠に、力の源を差し込み「アンロック」と呟いた。
「周辺に人は住んでいないし朝まではパトロールもこないはずだけど、騒音に反応する動きもあり得る。できるだけ手早く頼んだ」
「はい!」
気合いを入れる意味も含めてマサカズは元気よく返事をすると、その場から宿の屋根に跳び、蹴りを入れてそのまま内部へと突入した。その光景を見た伊達は、震える手で煙草に火をつけた。鍵の力が発動するのを目の当たりにしたのはこれで三度目になるが、やはりどうあっても平静ではいられない。二十メートルもの高さを一度の跳躍で到達できる生物など、この世にはいないはずだ。
非現実的なそれは、理由もわからない興奮を呼ぶ。あるいはこれを感じたくて、自分は無謀で無計画な起業をしてしまったのかもしれない。だが、今は考えを巡らせるより先に自分の仕事をしなければならない。伊達はマサカズに背を向け、懐中電灯を手に周囲に人がいないか見回った。すると草むらに何かが動く影あった。電灯の灯りを定めると、そこにはタヌキの親子がいた。けたたましい破壊の音に、親子は走り去っていった。そして、木々に停まっていた梟たちも一斉に夜空へ飛び立っていった。マサカズの作業がどうやら本格的に始まったようだ。伊達は事態をそう呑み込むと、警戒を再開した。
手刀、回し蹴り、肘打ち。格闘技の素人ではあったが、マサカズの生み出す破壊力は生物としては地上最強であった。屋根瓦は煎餅のように砕け、柱はバナナのごとくへし折れ、床板は障子さながらに踏み抜かれた。この力を破壊に、それも気兼ねなく使ったのは初めてであり、マサカズ自身、その威力に対して戦慄と高揚感を同時に抱いていた。思った以上にストレスなく、やりたい放題が可能である。これは、まるで漫画やアニメに登場する能力者の力だ。作業を始める前は怪物だと感じていたこの旅館も、今では蹂躙し放題の遊び場のようである。
解体についても初心者だったので、できるだけ上階からの破壊を心がけていた。これなら途中で意図せぬ崩落が起きる心配もない。伊達と知識のない者同士で立てた計画だったのだが、どうやら正解だったようだ。それにしてもこの旅館はなぜ廃業に至ったのだろう。足元にある破れた掛け軸を見下ろし、マサカズはそんな疑問を抱いた。
開始して三十分ほどで三階建てだった廃墟を二階建てにしたマサカズは、周辺を警邏する伊達の背中を見下ろした。この仕事が成功すれば、前例となって次にも繋がる。モグリという点が憚れはするが、その辺りはあの敏腕弁護士がなんとか丸め込んでくれることだろう。伊達を信頼していたマサカズは、法に触れるようなことは二度としないと決めてはいたのだが、先行きが不安な現状だったので、その遵法意識は棚上げするしかなかった。憂いが強くなる前に、この仕事に集中し、達成し、喜びと充実感ですべてを覆ってしまおう。そう決めたマサカズは、二階部分の解体に取りかかった。彼の上空では、梟たちが宿り木を求めて旋回を繰り返していた。
日付が変わるころ、およそ三時間かけ、マサカズは旅館を粉々にしてしまった。報告しようと林道まで出ると、伊達はある中年の男と話をしていた。
「その人が保司さんですか?」
マサカズがそう尋ねると、パナマ帽を被ったジャンプスーツ姿の痩せた男は「ども、保司です」と挨拶を返してきた。
保司の後ろには、大型のトラックが三台ほど停まっていた。今夜解体した破片は、井沢から紹介された廃棄物処理業者である、この保司という男が運び出して処理をする段取りになっていた。
「伊達さん、解体は終わりました」
「マジで? ほんとマジで?」
保司は目を丸くすると、マサカズたちを指さした。
「見てもらえばわかるでしょう」
そう言うと、伊達は保司を解体現場まで案内した。
「いや確かに……これを三時間で?」
懐中電灯に照らされた、木材などの瓦礫の山を前に保司は身体を震わせていた。伊達はマサカズの肩を軽く叩き、その仕事ぶりを労った。梟たちもマサカズの仕事を待っていたかのように再び木に戻ると、合唱を再開していた。
「まぁ、どうやったのかは聞かない約束だったわけで、でもなぁ……ちょっと凄くない?」
顎髭を撫でつけ、保司は首を傾げた。マサカズは瓦礫の山に向かうと、大黒柱だった長さ二メートルほどの木片を担ぎ上げた。
「なにするんだい? えっと……」
「山田です。これ、あのトラックに積み込めばいいんでしょ?」
「いや、搬出と整地はオレっちの担当だから」
「あ、サービスです。朝までまだ時間ありますから、デカブツだけは僕が運び出しますね」
「あ、あんがと……」
パナマ帽を脱いだ保司は、軽々と破片を持っていくマサカズを見送ると、伊達に目を向けた。
「なんなの? あの山田って力持ち。彼が解体したの?」
「それは秘密です」
伊達は返事をしつつ、今すぐ高らかに笑い声を上げたい欲求にかられていた。
「あーそうだな。オレっちらしくもねぇってヤツだ」
「山田……マサカズを見たら、みんなそうなりますよ」
「うん。でな、ここまで上手くいくとは思ってなかったよ。アンタのとこ、スケジュールとかぎっしりなんじゃね?」
「いえ、これが初仕事だし、当面の予定は白紙です」
「よし、だったらオレっちからもさ、なんかあったらお願いしてもいいか? 手口を詮索してこねぇヤツなんて、いくらでもいるからよ」
その申し出に、伊達は目を輝かせ「ぜひとも!」と強い語調で返した。
初めての仕事を終えた二人は保司にあとを任せると、国道沿いのサウナに向かった。カラフルな館内着の二人は飲食スペースの畳の上で、ビールジョッキを鳴らせた。
「初仕事、おめでとう! やったなマサカズ」
「おめでとーう! けどまぁ明日はお休みですね。たぶん僕、ここで一泊どころか明日も動けないと思います」
「付き合うよ。どうせ土曜で寺西さんたちもお休みだし」
伊達は生ビールをごくごくと呷った。マサカズもそれに倣い、二人は笑顔を向け合った。
保司という廃棄物処理業者の人も喜んでくれ、今後は仕事を回してくれるかもしれないという話だ。会社の老人たちとも楽しく仕事やゲームもでき、あとは私生活さえ充たされれば言うこともないのだが、まだそれは先のことだ。冷たいのどごしを満喫しながら、マサカズは幸福というものを感じていた。
「別れ際の保司さん、すっごく喜んでましたよね」
「お前の搬出サービスが決め手だったな」
「そうなんですか?」
「木の廃材はささくれ立っていて、ある程度下処理をしないと搬出が難しいって、なのにお前、ものともせず担いでいっただろ?」
「力のおかげですよ。チクチクもしませんでしたし、ほんと、ちょっとした重さしか感じないんです」
「今日のはモグリだったけど、今後は違法性がない仕事で稼いでいこう」
伊達はマサカズに気を遣い、そう告げた。
「別にいいんじゃないですか?」
「え?」
その発言が意外だった伊達は、ジョッキを机に置いた。マサカズはポテトフライを鷲掴みにすると、それを口に放り込んだ。
「だって、あのままじゃ次の旅館が建てられなかったんですよ。それに、普通だったら養生や足場の設置から始まって何ヶ月もかかる工事をたったひと晩で、しかも料金も向こうからの提示額から下げた形で受注したんですよね? なんて言うのか、誰か迷惑した人って、います?」
むしゃむしゃと揚げた芋を食べながら、マサカズは伊達に目を合わせずそう言った。法律家である伊達には、いくらでも反論できる破綻した内容ではあったが、彼は言葉を胸の内にしまい込んだまま、ビールジョッキを再び手に取った。
【無料版】第3話 ─俺たちのアジトで旗揚げしよう!─ Chapter10
嬬恋村の夜から週も明け、月曜日になった。事務所の電話が鳴るのは今日になって何度目のことだろうか。総務助手の寺西が対応しているのに注意を向けたマサカズは、聞こえてくるやりとりの内容から、それが仕事の依頼であると推察した。
群馬県嬬恋村での初仕事は、保司の後始末のおかげもあってか依頼主からも喜ばれ、契約した五百万円の作業代金はすぐに振り込まれた。そして、井沢や保司から仲介された解体業の依頼が朝から数件入っていたのだが、伊達の判断で次の仕事は保留になっていた。
「全部請けましょうよ。二日に一度にしてくれれば、僕、なんでもぶっ壊しますよ!」
定時過ぎ、二人きりの事務所でマサカズはデスクで帳簿の確認をしている伊達にそう言った。
「ほどほどにな。全部受けるつもりはない」
「いや、ここは稼ぎ時ですよ。僕のことなら気にしないでください。これまで伊達さんに頼りっぱなしだったんですから、ここからは僕が馬車馬ってヤツです」
「ほどほどと言ったのは、お前の消耗に対する気遣いじゃない」
「あ、そうなんですか……」
マサカズがしょんぼりとした様子だったので、伊達は僅かに戸惑ってしまった。
「あのな、受注金額が破格で普通だったら何ヶ月もかかる作業期間がひと晩なんて、お前の力のおかげで儲けは大きいけど、業界の注目はどうしたって集まってしまう。そうなると……」
「この力を探られる……とか?」
「そうだ。そうなんだよ。当面は業界が被らないように、ローテーションで仕事を回していくしかない。例えば週二で実務をするとして、解体業は月イチとかのペースでやるとか、同業他社から目立たないように気を付けないといけない。井沢さんや保司さんにもそちらの方向性で仲介をお願いしているところだ」
嬬恋村の件は運の良さにも恵まれていた。例えば壁材などに用いられ、人体に悪影響を及ぼすとされているアスベストの処理が十年前に済んでいたり、近隣に全く住人がいなかったりしたため、マサカズの力を遠慮なく存分に振るうことができたが、あのような案件は中々巡っては来ないだろう。伊達はマサカズにその点を説明しようと思ったが、一度に多すぎる情報量を処理することはできないと考え、それを諦めた。
「この力に目を向けさせないって、よく考えてみると結構難しいですよね」
マサカズが懸念を共感してくれたので、伊達は嬉しくなって席から立った。
「まさしくそうなんだよ。仕事が取れずに悩んでいたけど、いざ成功したら今度はどうやってその方法に注目されないか腐心しないといけない。今後はスパイだって懸念される。まったくお前の力は面白いほど厄介だよ」
「なんて言うか、根本的な解決策って、いずれは必要ですよね」
「ああ、当面は実績ベースで仕事は回せるだろうけど、会社を大きくしていこうとしたら、誰もがそうだと納得できる力の証明ってやつが必要になる」
「伊達さんなら考えつきますよ」
「その信頼に応えられるといいんだけどな」
苦笑いを浮かべる伊達に、マサカズはちりちり頭をかいた。
「えーと、伊達さん」
「なんだ?」
「こう言っちゃなんですけど、伊達さん、随分と行き当たりばったりで会社をやろうって決めたんですね」
自覚もしていたその指摘に伊達は顔を顰めた。
「すまない」
「いや、謝る事じゃないですよ」
「正直なところ、お前のあの力は冷静を弱気って勘違いさせる。無謀、無策を勇気って思い違いさせる。お前はどうなんだ?」
「旅館壊して初めて感じたんですけど、あれ、これって何でもできるじゃん。僕、無敵じゃんって。あんな大きな建物を、なんて言うか、プラモデル……じゃないな。粘土でもないし……とにかくスパパパパン! って粉々にできちゃって。あー、だから無敵ってのは違いますね。戦いとかじゃない。だいいち敵もいないし」
マサカズの困惑に対して、伊達は明確な回答が引き出せなかった。彼は煙草をくわえると、それに火をつけた。
「わっかんねぇことばっかりだよな。実際。俺はこれまでわかることしかない世界で生きてきた。いわゆる予定調和ってヤツだ。しかしお前のアレについちゃ、目隠ししてジャングルの中を手探りで進むような関わり方だ」
その喩えがわかり易かったため、マサカズは強く同意してうめき声を漏らした。
「だからさ、面白いんだよ。攻略しがいがある」
「ゲーマーの血が騒ぐってやつですか?」
「うまい、適切な表現だ」
「なんか賞品とか出ます?」
「一杯おごるよ」
「あ、それでしたら駅前のバーにしてもいいです? なんか高そうな」
「いいよ。そのかわり、今日はたっぷりゲームの話をさせてもらうぞ」
「マニクラの話ならいいですけど」
「まぁ、それでもいいか。俺はほとんどやったことないけどな」
「あれ、でも弓のレシピ教えてくれたじゃないですか」
「たままただよ。よくぞ俺の狭いマニクラ知識が活用できる疑問を抱いてくれたと思ったものだ」
「助かりましたよ。弓のおかげで防衛戦がラクになりました」
ゲームの話になったので伊達は心が弾み、帰り支度に取りかかった。その所作を察したマサカズは伊達に倣うことにした。
昨晩、マサカズは終電まで伊達と駅前のバーで呑んだ。カウンターで交わされた話題は最初は“マニクラ”についてだったが、伊達はしだいに古いゲームやプロレスのことを語るようになり、マサカズがそれに対して生返事を繰り返し、あまり乗れない態度を取ると、テーマがサウナに移り変わった。
趣味については噛み合わない部分こそあったものの、伊達との会話は楽しい。弁護士としてこれまで十年の経験談は驚かされたり爆笑させられたり、時には眉を顰めたりと、人間の様々な清濁がくみ取れる。「本出せますよ、伊達さん“メガネのイケメン弁護士のここだけの話”なんてタイトルはどうです?」マサカズが冗談でそう提案すると、伊達は首を横に振り「本なんてダメだ。本気で面白くしようと思ったら、守秘義務が壁になる」と素っ気なく返したあと、「しかしそのタイトルセンス、昭和だな」と付け足し吹き出した。
ここしばらく人との交流もなかったマサカズにとって、伊達は久しぶりに現れた話し相手であり、気の合う友人だった。その伊達は営業のため今日から出張で、しばらくのあいだ事務所を空けることになっていた。旅館解体の実績をもってして、日本中のめぼしい相手にプレゼンをするらしい。その間、自分はどうすればいいのかと尋ねてみたところ、伊達は「勉強するもよし、爺さんたちとマニクラをするのもよし」と言っていた。さすがに暇つぶしでゲームをするわけにはいかないと返したところ、老人スタッフとのコミュニケーションも代表として重要な仕事だとさらに付け加えられ、確かにそれもそうだと納得したマサカズだった。
「伊達さんが戻ってくるまでの間、基本業務以外はマニクラをやりましょう」
マサカズの提案に、パートスタッフたちは賛意をあらわした。強弱はあれど、四人はサンドボックス形式のこのゲームを気に入っており、最近ではそれぞれノルマを課したプレイに興じたりと、さながら仕事の一環のような錯覚まで起こそうとしていた。
「あ、ただですね、ゲームをただやるんじゃなくて、互いの連携とか、進捗の確認とか、ホウレンソウってのを意識してプレイしましょう」
マサカズはそう忠告したものの、四人は既にそれを意識したプレイをしていて、試みについては先回りをしていたのだが、誰もが素直に若社長に同意した。
日常的に発生する事務処理や電話対応といった通常の業務をこなしつつ、マニクラをプレイして定時になった。マサカズは席を立ち、四人に「定時超えはナシなんで、ここでゲームも終わりにしましょう」と声をかけた。すると呼び鈴もならず、出入口の扉が開かれた。
「マサカズ、ちわっす」
それは、聞き慣れた鼻声だったため、マサカズは思わず目を移した。そこにはアロハシャツ姿の兄、山田雄大の姿があった。不敵な笑みを貼り付かせていた彼は右手で銃を構えるような仕草をすると、「バンっ!」と声を上げた。もちろん、何も起こるはずもなく、これは彼の昔からのクセである。「マサカズよ、隠れてお楽しみのつもりでもオレはお見通しさ」そのような意図が、これには含まれていることをマサカズはよく知っていた。
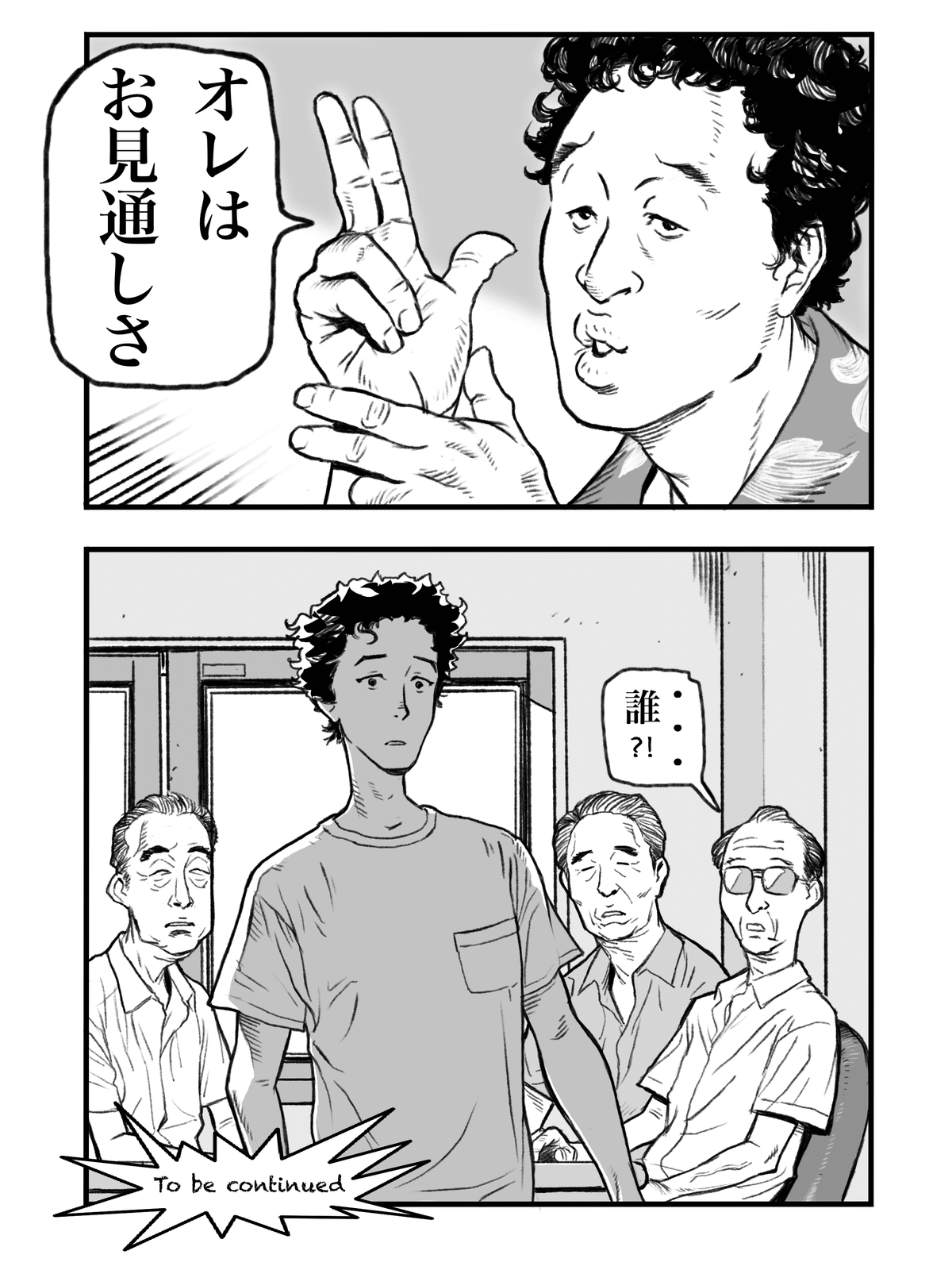
第3話「俺たちのアジトで旗揚げしよう!」おわり
【【無料版】第4話 ─鉄の掟を作ろう!─ Chapter1
大柄な体躯には赤いアロハシャツ、下半身はあちこちが破れたダメージジーンズ、そして素足にはサンダルを。これが三年ぶりに相対した兄、山田雄大の身なりだった。マサカズもコミックのキャラクターがプリントされたTシャツにデニムとスニーカーを履き、四人の老人たちもネクタイをしていなかったので、兄の服装自体は場違いと異端視するほどではなかった。だが、見かけではない。その中身はここにいる自分たちとは違う。背中を軽く丸め両手にポケットに手を突っ込み、頬を引き攣らせ人を食ったような不敵な笑みを浮かべ、鼻をふんふんと鳴らしながら物色するような目で事務所じゅうを見回している。そう、自分たち五人と彼は違う。品性に欠け、粗野で、抜け目がない。同じ檻に混ぜてはいけない存在だ。マサカズは警戒心を強め、分析を進めた。
相変わらずだ。二十年以上、この兄とは関わってきた。ここ十年では断続的な情報しか知り得てはいないのだが、彼自身を取り巻く状況は好転していないはずだ。前科こそないが法律に触れる悪事に手を染め、逮捕されたものの不起訴になったこともあったはずだ。マサカズは兄の動向に警戒しながらも責任者として求められる対応に当たることにした。スチールの扉を背にした兄にマサカズは注意をするため声をかけようとした。
「いやぁ! ミッシングゼロ? マサカズ-! お袋から話は聞いたし、ホームページ見たぞー! よもやお前が社長になるなんてな。狭いながらもたいしたもんだよ! 兄として、この山田雄大、深い敬意を現したく存じ上げます」
兄はポケットから手を出し、左手を腹の前でL字に曲げ、執事の真似をするようにうやうやしく頭を下げた。パートの四人は唐突に現れた兄に対して理解が追いついていないようであるが、その答えを自分に求めてくる者はいない。そう、つまり兄はここにいても良いという許可証を勝手に発行し、それを控えめにちらつかせているのだ。マサカズは記憶を総動員して、現れた予想外の個性に対して身構えた。
機先を制された。いつもこうだ。自分や両親が何か注意をしようとすると兄は気配を察し、こうやっておちゃらけた様子でユーモアを交え、会話のペースを握ってしまう。当事者に対してくだらないと呆れさせ、面倒だと思われ、その隙にそれ以外の興味を惹き、つけ入る。マサカズは兄との過去のやりとりを、具体的な出来事ではなく感覚として思い出し、焦れた。
「ほんとはさ、花輪とかなんだけよね。そりゃあボクだって兄として祝福したかったよ。だけど金欠でさぁ。だってボク、お人好しでしょ? ねぇマサカズ」
これ以上ペースを握られては危険だ。マサカズはそう判断すると、デスクから出て兄の前まで進んだ。
「ここへは何の用です? 呼び鈴も鳴らさずに突然入ってくるなんて、非常識で……」
言い終えぬうちに、兄はマサカズの背後に回り込み、太い腕を彼の首に回した。
「ごめんごめん、謝るって。だってよ、お前が社長なんて嬉しくってさ、呼び鈴とかってあったっけって感じ!」
嘘だ。この間合いを成立させるための奇襲でしかない。そのやり口をよく知っていたマサカズは、兄を突き放した。
「用件はなんです? 弊社にお仕事のご依頼ですか?」
硬い語調を崩さない弟に、兄は顎に手を当て首を傾げ、口先を尖らせた。
「マサカズ。ボクを雇ってよ」
想像していた要求のひとつであったが、もっとも忌諱するべき内容だったため、マサカズは身を引き、「冗談!」と吐き捨てた。
「マジよマジ。親族は信用できるだろ? ベンチャーにおいて信用できる仲間が一番の武器だ。あ、もちろんいきなり正社員なんてムシのいいことは言わない。最初はバイトでいいし……」
唇に人差し指を当てた兄は目を泳がせると、情けなく微笑んだ。
「申し訳ない! そうなったらマサカズ殿はボクのボスってことになりますです! ラッシングゼロ参加の暁には、敬語で接するしだいであります!」
最後に不格好な敬礼をして、兄はそう締めくくった。不安になったマサカズが背後の様子を探ると、四人のうち木村を除いた三名から、朗らかな様子が窺い知れてしまった。三人共、緩んだ笑みを浮かべ、目の前のユーモアを楽しんでいるようでもある。兄が繰り広げている茶番を彼らは好意的に受け入れてしまっているということだ。この空気を膨らませるわけにはいかない。マサカズは更に焦れた。
「兄貴、ここは会議室も応接もない。話があるからちょっとついてきてくれ」
その提案に、兄は「従うであります!」と弾んだ声で返すと、四人の老人に小さく手を振りウインクをした。
代々木駅の近く、とあるハンバーガーチェーン店の客席に兄弟は向き合っていた。周囲は学生たちで賑わい、兄弟は店内の平均年齢を引き上げるのに貢献していた。
「社長なのにファストフードのハンバーガー? ショボいねぇ。あ、前の大統領もハンバーガー死ぬほど好きだって言うから、いいのか。もしかしてマサカズ、パクってる?」
「まず……」
マサカズが切り出そうとすると、兄は掌を突き出して言葉を制しようとした。しかし、弟は正面から強行突破するため、分厚いそれを手の甲で弾いた。マサカズの行為に兄は顎を引き、彼を睨みつけた。
「ウチじゃ兄貴は雇えない。理由は余裕がないのと、今のところ人が足りているからだ」
「あんなジジイ共、戦力外だろ?」
「いや、みんな有能だ」
「でも通院とか多いんじゃねーの?」
兄の指摘は正しかった。事務所を開いてから十日ほどが経つが、四人のパートスタッフは老体をケアするため通院を理由に何度か直行、直帰をしていた。営業で外出しがちな伊達は別として、四人が丸一日定時の勤務を満了したのはたった一日だけだった。
「ホラ、そうだろ? それにあんなショボい事務所っつっても、お前ひとりじゃムリだろ。会社なんてできないだろ? つーか、よく起業できたな? なんか、そーゆーパッケージ的なサービスとか利用したのか?」
早口でまくし立てた兄は、アイスコーヒーのストローを口にした。マサカズは左の頬を吊り上げ、フィッシュバーガーを片手に兄を指さした。
「残念。ホームページ見ただけじゃわかんないだろうけど、今の俺には強力なビジネスパートナーがいる」
兄からリアクションがなかったため、マサカズは説明を続けた。
「取締役で副社長だ。しばらく営業に出てて事務所に戻るのは先だけど、一流の弁護士で、俺の顧問も引き受けてくれている」
兄はアイスコーヒーを吸いきると、乱暴な所作で紙コップを叩きつけるように置き、ドスの効いた声で低く呻るように「聞いてねーぞ、それ」とだけ返した。
「ある事をきっかけに、俺たちは友だちになった。まぁ、伊達さんが兄貴を認めるって言うのなら、入社を認めてあげたっていいけど。まずムリだろうね。伊達さんは兄貴みたいな厄介者専用の刑事弁護人なんだ。兄貴なんて、すぐに“見抜かれる”よ」
自信に満ち、高揚した口調のマサカズだった。兄はテーブルで人差し指と中指をタップダンスのように忙しなくステップさせた。しばらくすると手を止め、マサカズに強い眼差しを向けた。
「マサカズ、テメー、オレを売るつもりか?」
「脈絡がわかんないって。今の兄貴がどんな状況かはわからないけど」
マサカズの即答に、兄は臆したように大柄を縮み込ませると両手を合わせた。
「きっと親父たちだって喜んでくれると思うんだよ。な、マサカズ、兄貴を助けてくれよ」
「けど、伊達さんに相談しないと」
視線を外したマサカズに、兄は身を乗り出して見下ろし、野卑な笑みを浮かべた。
「さっきから聞いてりゃなんだよ、いちいち“ダテさん”“ダテさん”“ダテさん”って、お前、社長なんだろ? すこしはテメーで物事を決めてみろよ。あ、それとも“ダテさん”ってお前のアレか?」
小指を立ててきた兄のおどけ顔に、テーブルのコーラをかけてやりたくなったマサカズだったが、それをさせることがこの態度の目的だと察した彼は、じっと堪えるしかなかった。
「とにかくよ、もう一度あの事務所に行こうや。オレにできることが見つけられるかも知れねぇ。そうすりゃ“伊達さん”にもオレを売り込めるだろ?」
あまりにも一方的だったが、ここで無下な態度で兄を撃退すれば、このあと栃木の両親とも厄介なやりとりが生じてしまう可能性もある。マサカズは兄に押されるまま、彼を事務所まで連れて帰った。
「あらためまして皆様方! ちょいとお邪魔させてもらいますよ」
作り笑いで手を揉みながら、兄は事務所の中を進み、伊達のテーブルにつこうとした。
「ああ、ダメです。そこは副社長の席です」
兄を止めたのは寺西だった。やや小太りで目の細い彼に対して、マサカズは極めて温厚かつ常識的な人物だと感じていたため、この制止も彼としては当然の行動だと思った。
「あ、“伊達さん”のなんだ。どーりでなんか、理知的な香りがしてくるでありますなぁ。さすがは敏腕弁護士!」
「おお、伊達副社長をご存じで?」
浜口に問いに、兄は大きく頷き「うい」と返した。
「伊達さんのことは僕がさっき教えたばかりです。兄は伊達さんと知り合いとかじゃありませんから」
伊達の性別すら知らぬのに、まるで以前からの知人であるかのような態度である。苛立ちを覚えたマサカズがそう説明すると、兄とマサカズの間に木村が割って入った。
「で、この人、どうするんですか社長」
木村は低音で暖かみのある声をした整った顔立ちの老人であり、四人の中では最も合理的な考え方の持ち主だったが、その反面、融通の効かない一面もあった。マサカズにとっては、高校のころの数学教師を思い出させる人物でもある。兄は木村と寺西を見くらべると笑みを消し、下唇をにゅっと突き出した。これは、彼が慎重さを発揮する際の癖でもあり、マサカズにとっては警戒するべき所作だった。
「あ、つまりですね、これって、この状況ってのは兄が、僕の親族が起業を祝って訪ねてきてくれたって、それだけです」
「しかし、さっきは雇ってと……?」
「雇いませんよ。親族がお祝いで訪ねてきた。それだけのことです。ねぇ兄貴。歓迎するよ」
マサカズにそう振られた兄は、わざとらしく肩を落として残念そうに表情を曇らせた。
「あーあ、弟と一緒に働きたかったなぁ。仕方ない。皆々様、どうかウチの弟をしっかりと盛り立ててくださいであります! また遊びにきますであります。次回はお土産持参であります!」
ともかく、横暴で無礼で態度の大きい兄の撃退には成功した。事務所を出て行くその後ろ姿を見ながら、マサカズは拳を強く握りしめた。ただひとつ疑問だったのが、ハンバーガー店で言っていた「オレにもできることがあるかも知れねえ」と言っていたことだ。一度は事務所まで連れて帰ったが、彼は何もせず挨拶だけをして引き下がっていった。あの下唇の癖にヒントが隠されているのだろうか。マサカズは、兄の速やかなる撤退がひどく不気味に思えてしまった。
【無料版】第4話 ─鉄の掟を作ろう!─ Chapter2
マサカズが代々木の事務所で突然の来訪者への対応に追われていたころ、伊達は千葉県木更津市の中央市街から離れた県道沿いにある、四階建てのビルまでバイクでやってきた。ビルの袖看板には『木更津クリーンサービス』と記されていていた。ヘルメットを脱いだ伊達は、ビルの入り口を開け、「失礼しまーす! ナッシングゼロの伊達です!」と挨拶した。
「きたきた。伊達ちゃ~ん」
パーテーションのドアを開け出てきたのは、ツナギ姿の保司だった。彼はナッシングゼロの初仕事で廃棄物の処理と整地を下請けしてくれた廃棄物処理業者の代表取締役であり、伊達とはちょうど二回り年上の中年男性だった。
「初対面からまだ一週間たってないのに、“ちゃん”呼びですか?」
「あ、ダメ?」
「いいですよ」
群馬での旅館解体の夜、彼とは初めての仕事だったのだが、人懐っこく明るい男という印象を受けた。おそらくこれは彼の処世術であり、本質は柔和な笑みの奥にある。伊達は経験からそう推察していたため、彼の陽性を額面通りには受け止めていなかった。
伊達はパーテーションで区切られた応接スペースに案内された。ガラステーブルに革張りのソファが対する形で配置され、伊達は上座に座るように促された。
「伊達ちゃんはなに吸うの?」
「パーラメントです。保司さんは?」
「オレっちはチェリー。ロマンの味ね」
二人はそんな言葉を交わしながら、それぞれ煙草とライターを取り出した。パーテーションの向こうでは電話に応じる女性事務員の柔らかげな声が聞こえ、伊達は無意識のうちに小さく頷いた。
「これが次の件、五件あるから吟味してちょーだい」
保司はテーブルに一冊のクリアファイルを置いた。表紙に貼られたシールには“伊達ちゃん・山田ちゃん案件”とマジックで書かれていた。
「ありがとうございます。五件もですか……すごい」
ファイルを受け取った伊達は、それを革製のビジネストートバッグにしまった。保司は煙草に火をつけると、ひとふかしして足を組み、ソファの背もたれに肘を置いた。
「いやいやいや、大阪万博狙えばキャパオーバーなぐらいの案件があるよ」
「けど、さすがに官の仕事は、手段を詮索されずにってわけにはいかないでしょ」
伊達が煙草に火をつけると、事務員の中年女性が麦茶を運んできた。
「いやいやいや。万博、いま大ピンチなんだよ。工期が遅れまくっててさ、しかもどさくさちゃんで予算倍増してっけど、風当たり強いでしょ、やっぱし」
保司は身を乗り出すと吸っていた煙草をふかし、伊達に向けて目を輝かせた。
「そこであんたらだよ。怪力山田ちゃんの超スピード搬入、しかも料金は相場の十分の一。嬬恋での実績ちらつかせりゃ、連中は何もかも目をつぶってあんたらへ発注する」
保司の言っている内容には説得力があり、魅力的でもあった。しかし、万博に手を出すのは自治体と関わるということになる。窮地に陥っている万博関係者は詮索してこないかもしれないが、担当部署ではない他の目ざとい者の注意を引きかねない懸念材料を内包している。
「ま、伊達ちゃんにその気があるんなら、いつでも言ってよ。渡りはつけられっから」
一本目の煙草を分厚いガラスの灰皿に押しつけた保司は、二本目を取り出した。
「ところで会社の方は順調?」
「営業は上手くいってないですね。なんだかんだ言っても自分は素人なんで」
「慣れてくりゃ、伊達ちゃんだったら成功するよ。オレっちが保証する」
「だといいんですが……それと、事務系を回すのに苦戦してますね。スタッフを後期高齢者に頼ったんですが、能力には満足していますが、通院や孫の相手とかで、ちょくちょく休んだり早退したりが多いんですよ」
「まぁ、爺さんって、あれで意外と結構忙しいからね。特に幸せなのほど、家族関係のイベントが多いし。伊達ちゃん、いい人材雇ってるよ」
「おかげで自分にも事務仕事が回ってきたりして、深夜までかかることもザラですけどね」
「我らが山田ちゃんは?」
「マサカズは、そっちはてんで素人ですよ。器用なヤツだとは思うので、教えればテキパキとやってはくれそうなんですが、その教えるヒマがありません」
伊達も二本目の煙草に火をつけた。紫煙が二人の頭上で交わり、小さな雲を形作っていた。
「大変だな。だけどさ、山田ちゃんは絶っ対、手放しちゃダメだよ」
“絶っ対”の部分が特に強い語調だった。保司がマサカズを評価しているのはなんとなくわかっていたが、まだ出会って一週間も経っていない彼がなにを確信しているのか、伊達は興味を抱いた。
「そりゃ、ウチの社長ですし、知っての通りの怪力ですし。代えがたい戦力です」
「怪力だけじゃない。あいつは激レアキャラだよ。一度会っただけでわかった」
「どこが貴重なんです?」
「ちょいと興味が沸いたんで、ウチのトラックに搬入してるのをずっと見させてもらったんだけど、山田ちゃん、速いんだよ。判断や理解が。そして恐らくだけど、流されやすいって短所があって、それが長所を殺しちまってる。だから、あいつの力を活かしたいんならできるだけ納得をさせるんだ。納得したあいつは一直線で強いぞ」
淀みのない口調で言い切られた人物評に、伊達はある程度の心当たりもあったため呆然としてしまった。
「一度でそこまでわかります?」
「オレっちの業界はさ、生き馬の目を抜くってヤツでさ、虎視眈々と抜け駆けするようなヤツが外にも内にもいる。そんな世界で三十年もやってりゃ、わかるってもんだよ弁護士先生。山田ちゃんみたいなのは、これまであんまり見たことがない。伊達ちゃん、ツイてるよ」
納得させれば一直線で強い。確かにこれまでマサカズは、自分の想定を上回る結果を出すことが度々あったと思える。そのいずれもが、彼自身が腑に落ちたうえでの行動だったような気もする。だとすれば、自分の役割としては、望むべき結果を得られそうな状況に直面し、だが彼が疑問を抱いた際、いかに納得させられるかだ。かなり頑固な面もあるので事によっては難易度は上がるが、まさしくその攻略に自分のキャリアは活きてくれるだろう。
「保司さん、今後も弊社をよろしくおねがいします!」
伊達は勢いよく腰を浮かせ、保司に頭を垂れた。
「もっちろん。オレっちも期待してるよ~」
目を細めた保司は煙草をひとふかしし、顎髭を撫で、何度か頷いた。
木更津クリーンサービスをあとにした伊達は、夕暮れのなかバイクで木更津駅まで向かった。今日はこのあと駅周辺で夕飯を摂り、予約済みのビジネスホテルに泊まるだけだ。明日は成田空港までバイクで向かい、そこから北海道函館市のビルメンテナンス会社を初めとして、合計五社との顔合わせの予定となっている。
赤信号に差し掛かったのでバイクを止めると、ハンドルの中央部分にホルダーで取り付けていたスマートフォンが振動した。画面を見ると、非通知設定からの着信があった。伊達はバイクを路肩に停めると、降車してヘルメットを脱いだ。
「はい」
スマートフォンを耳に当てた伊達がそう言うと、「ナッシングゼロの伊達副社長ですよね」と、やや甲高く明瞭な声がした。
「そうですが。そちらは?」
「山田正一の兄、山田雄大といいます」
これは慎重に対応するべき事案だ。伊達はこれからの会話に備え、深呼吸をして相手の出方を待った。
「いや、今日おたくの事務所まで挨拶にいったんですよ。ノーアポなのが申し訳なかったんですが、なんと言いますか、弟が社長なんて驚いてしまいまして、いてもたってもいられなくなりまして」
すらすらとして、しかし微弱な上ずりを声から感じた伊達は、まだ無言を通すことにした。その脇を三台の小型トラックが過ぎ去っていった。
「あ、いや、でしてね、これからもちょくちょく遊びに行かせてもらおうかと。伊達副社長にも前もって言っておいた方がよいかと思いまして。あ、もちろんお仕事のジャマは決してしませんし、弟の社長っぷりを見て、田舎の両親に兄として報告などできればと考えてまして」
沈黙をなお、伊達は続けた。
「あの、副社長? 伊達さん?」
伊達は電話を一方的に切ると、内ポケットから煙草の箱とオイルライターを取り出した。煙草をくわえた彼がそれに火をつけようとしたところ、携帯が再び振動した。
「私からは特に言うことはありません。あなたがしてはいけないことについては、私から社長に伝えておきますので」
伊達はやや強い語調でそう言った。
「伊達さん? 僕ですよ。マサカズです」
画面を見直すと、そこには通話先として“マサカズ”と表示されていた。いつもなら相手を確認した上だったのだが、それを怠ってしまった。自分らしくもなく、早とちりをしてしまった。これは山田雄大に対して抱いた苛立ちに原因がある。伊達はそう、即座に自己分析した。
「なんだいマサカズ。保司さんから五件も案件の候補をもらえたよ。これからホテルで資料に目を通す」
「それはすごい。で、なんで電話したかって言いますと、今日、僕の兄貴が会社に来たんですよ」
「山田雄大がか? 何をしにきた」
「会社に入れてくれって。もちろん断りましたから、安心してください」
「どれぐらいの時間いた?」
「一度マックに引っ張り出しましたから、合計すると三十分ぐらいですか。また遊びにくるって言って帰りました」
「入社の件は諦めたのか?」
「たぶん……」
弁護計画を練っていたころのように、伊達はこの“問題”に対して要点を素早く絞り込んだ。
「マサカズ、俺のこの携帯の番号、お兄さんには教えたのか?」
「まさか。教えるはずもありません」
その返答に、伊達はスマートフォンを耳から離し、顎を引き、上目で県道の先に見える木更津市街の街明かりを睨みつけた。
「おもしろい」
そう呟いた伊達の左頬は引き攣り上がり、彼の脇には大型トラックが通り過ぎていった。
【無料版】第4話 ─鉄の掟を作ろう!─ Chapter3
ここ数日、伊達は事務所には戻れず国内を駆けずり回っていた。本来なら出張は三日間の日程だったのだが、営業先で別の会社や公的機関を紹介されたため、二日の延長となってしまった。世間はお盆休みの真っ最中だったが、正社員が自分とマサカズの役員しかいないということもあり、ナッシングゼロは平日の全てを営業日としていた。老人たちの何人かはお盆のイベントに対応するため休みを取る者もいたが、その穴はマサカズがなんとか埋めているらしく、業務の進捗度合いは普段とそれほど変わらなかった。
会社を空けている間、マサカズとは毎日定時過ぎに電話で連絡を取り、情報は共有していた。だからこそ、この異常とも言える光景も驚きなく受け入れられてしまう。ヘルメットを抱え事務所にやってきた彼は、アロハシャツの大柄な男に注目した。
「寺西さん、まだこれからでも育毛はできますよ!」
「そうかなぁ。雄大くん、なんかいい育毛剤、知ってる?」
「探してみますね。うまくいきゃあ、寺西さんモテモテっスよ」
「浜口さ~ん! これ、ジャイアンツ原のサインボール。手に入れましたよ」
「うわっ! 凄い! ハラタツじゃ~ん! くれるのこれ!?」
「もちろんです。お宝ってのはファンのもとにあるべきです」
「草津さん、お孫さんのチャンネル、登録しときましたよ。あと高評価も入れときました。いやぁ、いいチャンネルだわ!」
「嬉しいなぁ。孫も喜ぶよ」
「今度、お孫さんにいい動画の作り方とか教えてもらおーかな?」
「木村さん、玄関からの導線ですけど、あのタイムカードの位置をずらすだけで、宅配業者さんとかの対応がずっと効率よくなると思うんですが」
「なるほどね。確かにそうかもしれないな」
「棚の寸法が問題になりますけど、もうひとサイズ小さいのに交換するという手もありますね」
あの山田雄大という男は、すっかり四人の高齢者との距離を詰めている。しかもそれぞれの個性に対して、実に的確な対応の使い分けをしている。時には優しく、時にはおどけて、時には真面目に。役者のように自身の個性を調整し、使い分けている。
マサカズとの電話のやりとりで、先週月曜日に初めての訪問があって以来、あの男は土日を挟んで一週間後の今日にいたるまで毎日この事務所にやってきていることを伊達は知っていた。マサカズも兄に抗議をしているそうだが、毎日一時間から二時間程度の滞在であり、しかも先週マサカズは水曜日から金曜日まで、ある資格を所得するため事務所を空けていたため、実のところ兄の訪問についてマサカズが把握できているのは火曜日しかなかった。全ては間隙を縫うように、なんとなくじわじわと山田雄大は事務所の空気の一部になろうとしている。そしてこの事態を最も憂慮しているはずのマサカズと言えば、如才なく老人たちに取り入る兄の姿を、苦々し気に睨みつけているだけだった。
「あなたが伊達副社長!?」
伊達の出勤に気づいた雄大は、両手を広げて近づいていった。
「山田さん、今日は何の用事で?」
「いやぁ、浜口さんがジャイアンツの原監督のファンって聞いて、水道橋のスポーツショップで掘り出し物をゲットしたんですよ。それを渡しにね」
「嬉しいよ~ハラタツはね、昔は歌も出してたんだよ」
浜口はすっかり上機嫌で、握りしめたサインボールを伊達に向けた。マサカズの話では、どうやら雄大はここに来る度、次の訪問理由を作ってくるらしい。野球殿堂で表彰されるほどの名選手のサインボールが容易に手に入るはずもなく、誰のサインなのかは自明である。おそらく、明日は寺西にお勧めの育毛剤でも持参してくるのだろう。中身がなにかはわからないが。
こいつは典型的な詐欺師だ。しかもこれまでに弁護してきた顧客と比べても有能な等級に属するといってもいいだろう。伊達は人差し指で眼鏡を直し、あふれ出てきた闘争心に口の端を吊り上げた。
「ではさらにお尋ねしたいのですが、よろしいかな?」
伊達の言葉に雄大は戸惑い「い、いいですよ」と詰まった声で答えた。マサカズはデスクから兄の背中を見つつ、奇妙な違和感を覚えていた。なにやら、目の前にいるのは自分の知らない兄のように思えてしまうのだが、それはなぜなのか、その理由はまだわからなかった。
「雄大さん、あなたは私のデスクを見ましたか?」
「そりゃこんな狭いオフィスだし、全部の机は見えるから……」
「見たんですね?」
「ああ」
「どのぐらいまで近づきましたか?」
「はぁ? な、なにそれ」
「あなたが私のデスクにどの程度まで近づいたかと質問しているんです」
これが伊達隼斗なのか。兄に対する滔々とした問いかけに、彼はあらためて弁護士という仕事を生業にしているのだと思い、マサカズは軽い興奮を覚えた。兄がなかなか答えないと、寺西が手を上げた。
「副社長、雄大さんは、机のすぐ傍まできましたよ。僕、それでダメだって注意したんです」
「そうなんですか? 雄大さん」
念を押された雄大は、伊達から目を逸らし、「ま、まぁ……」と言い淀んだ。
「マサカズ! ちょっと話がある。出られるか?」
マサカズは席を立ち、ポーチを手に出口に向かった。途中、兄を背中から追い越す形になったので横目で見たところ、彼は頬を引き攣らせ、エアコンが効いているのにもかかわらず額は汗ばみ、うなり声を漏らしていた。
マサカズと伊達は駅近くの喫茶店までやってきた。今日は気温が三十五度を超える酷暑日であり、事務所から徒歩で十分圏内だったのにも関わらず、二人は額や首筋から汗を垂らしていた。
「兄貴のやつ、なんか伊達さんにビビってるって感じでした」
嬉しそうにマサカズはそう言ったが、アイスティーのグラスを手にした伊達は仏頂面を崩さぬまま、足を組んだ。
「三年、会ってなかったんだっけ。その前は?」
「えっと、兄貴は高校出てから家も出て、そこからは年イチで会うぐらいでしたね。動画配信チャンネル始めるって時期は頻度は上がりましたけど。なんだかんだで……十年以上は疎遠って感じかな」
「そうか……なら、お兄さんに対しての認識は少々アップデートした方がいいな」
広々とした店内ではバロック音楽が流れていて、布張りの椅子に座っていたTシャツ姿のマサカズは、居心地の悪さを漠然と感じていた。
「なんとなくだけど、わかります。って言っても先週の月曜日と火曜日しか見てませんけど、なんて言うか、あんなテキパキとしたヤツじゃなかった。もっと怠け者で、ぐうたらした感じでしたよ」
「十年間の積み重ねだろうな。あいつは大したタマだよ」
「でも伊達さん、さっきは兄貴を追い詰めてたって感じですけど」
「俺みたいなのに慣れてないだけだ。すぐにアップデートしてくるよ」
「そうなんですか……」
マサカズにとって、兄の成長はあまり歓迎したいものではなかった。なぜなのか、これもまた理由がわからなかったのだが、すぐにもいくつかの感情が結びつき、彼は「おおー」と声を上げた。
「兄貴、すっかり悪党になってしまったんですね」
「そりゃ言い過ぎだ。ただ、なかなかの詐欺師だとは評価できる」
伊達がそう評価するのであれば、疑問を挟む余地はない。マサカズは顔を曇らせ、絨毯に目を下ろした。
「どーすりゃいいんだよ。アイツ、爺さんたちとも仲良くなってて、すっかり馴染んでて」
「彼の目的はなんだと思う?」
「ウチを利用して自分だけ儲けようとしている。もちろん、僕たちへの迷惑付きで」
「親族のお前に対しては言いづらいが、つまり、彼は敵と言うことだな」
「敵です。それに兄貴面するやつと一緒に仕事なんて、嫌です」
「提案がある」
伊達の提案は大抵の場合正しい。マサカズはそう思っていたので、次の言葉を待った。
「山田雄大を内側に置く。正社員ではなく、契約はしない。そこは俺がうまいことはぐらかす」
予想していなかった言葉に、マサカズは飛び出すように身を乗り出した。
「ダメです! 絶対にそれはダメです!!」
大声に、周囲の客や店員が二人を注目した。伊達はストローでアイスティーをすすると、一度だけ頷いた。
「そりゃそうだろう。しかし、それしか手がない。事務所を移転したところでホームページの情報は追える。住所記載をしないと取引先から不審がられるし、ごまかしようもない。部外者の立ち入りは社則で禁止されているって注意したところで、彼は口八丁手八丁でそれを受け流す。そうなると不法侵入で警察に通報するってことになるが、これはやったが最後、彼の自尊心を著しく傷つけ、肩書きが詐欺師から別の犯罪者に変化させることになるだろう。そしておそらくだが、彼は既にウチの嬬恋村の仕事を数字だけでも把握している」
情報量があまりにも多かったので、マサカズはひとつずつ指を折りながら内容を整理していた。
「そんなに、兄貴は優れているんですか」
「俺の携帯番号をラーニングしてる。机に残した小さなメモからな。大したものだよ」
「どういうことなんです?」
「仕事用の携帯電話の番号を浜口さんから聞いたとき、一緒にもらったメモに番号と“DT”と記されていたんだ。彼はそれをチラ見して。“DT”を“ダテ”と判断したんだろう」
「兄貴が?」
自分の知っている兄は注意散漫で、伊達のデスクを見たところで、せいぜい机や椅子のグレードを値踏みするぐらいしかできず、メモなど気にも留めない。父から「お前の目はどこについてんだ。その機械のランプが赤の時は近づくなって言ったろ」などとよく、注意力のなさを叱られていた。
「納得してくれたか?」
保司のアドバイスを思い出した伊達は、マサカズの顔を覗き込んだ。
「たぶん」
納得の強要などといった愚策は取れない。伊達は今日のところはこれ以上マサカズに求めることを諦めた。
「それにしてもさっきの伊達さん、カッコ良かったなぁ。さすがは弁護士ですね!」
無邪気な称賛に伊達は照れ、顔を背けて「そのアイスコーヒー、飲めよ」と促した。
「飲みますけど、そのセリフっておごる場合ですよ。これ、経費でしょ?」
マサカズの正論に、伊達は「そうだな」と静かに返した。
その日の夜、アパートまで帰ってきたマサカズは、栃木の実家に電話を入れた。出たのは母だった。
「もしもし、俺マサカズ」
「もう電話あったかも……ああ、あったのね。そうそう兄貴、ウチで仕事することになったんだよ」
「雑用かな? 伊達さんと相談して考えるよ」
「兄貴? うん、元気そうだよ」
話の中心は兄についてであり、母は彼の今後をひどく心配しているようだった。電話を切ったマサカズは、敷きっぱなしの布団に身を投げ出した。伊達に今回の件での納得を求められた。確かに彼が言うように厄介者は内側に取り込んで飼い殺しにしてしまうのが得策だとは思う。しかし、あの兄なのである。自分の心が果たして持つのだろうか。兄のおどけてふざけた顔が浮かんだマサカズは、それを打ち消すため、後輩だった小さな彼女を思い出すことで、穏やかな眠りに落ちた。
【無料版】第4話 ─鉄の掟を作ろう!─ Chapter4
足元にやってきた三毛猫に目を落とした伊達は、そのヘイゼルの瞳を見つめ、「こいつ、まさか鰻をエサにもらってないよな」と、こぼしてみた。向かいに座る山田雄大は何も答えず、鰻店の店内を見渡していた。三毛猫が跳ね、すぐ後ろの棚に着地した。少し手を伸ばせば撫でられる近さだったが、伊達は横目で動きを捉えるだけで直接の接触を試みるつもりはなかった。
ここは事務所から歩いて五分ほどの川魚料理店であり、伊達は“看板猫がいる鰻屋”という評判をネットで得ており、以前から興味を抱いていた。和風の内装は高級感もほどほどで、価格も松の鰻重が三千円であり、平日のランチタイムともなると鰻丼が千円で提供され、この地に学びを求める若者たちも客層を形成する一部となっていた。
窓の外では雨が降っていた。今日は朝から悪天候で、伊達も電車での出勤となっていた。だからだろう、定時間近に事務所を訪れ、老人たちやマサカズが退社するのを見届けると、雄大は「何日か前にお誕生日だったんですよね。八月十三日でしたっけ。一杯おごらせてくださいよ。ボク、伊達副社長ともっとお近づきになりたいんですよ」などと誘ってきた。伊達はちょうどいい機会だと判断し、会食の場をここに選んだ。テーブル席に対座する雄大がどのような店を想定していたのかはわからないが、周囲をキョロキョロと窺う、その落ち着きのない様子を観察する限り、どうやら考えの外だったようである。コップのビールをひと飲みした雄大は、人差し指をわざとらしく立てた。
「副社長は、ここって初めてなんですか?」
雄大の質問に、伊達は小さく顎を落とした。
「いやぁ、ほんと、ありがとうございます。こんなボクみたいなのを雇っていただいて。で、非正規なのはまぁ仕方ないとして、アルバイトの契約とかはいつなんです?」
「すみませんね雄大さん。ウチはまだできたばかりの法人で、アルバイト雇用にも色々と制約があるんですよ。けど、業務報告されている分の賃金については来月から毎月二十五日に振り込みますので。その点についてはご安心ください」
「なんか、裏技とか使うんですか?」
「ええ、いくらでも手はありますので」
「いやしかし流石は弁護士先生だ。副社長はどんなきっかけでマサカズと知り合うことになったんです?」
「まだ秘密にさせてください。いずれお話しします」
伊達はきっぱりとそう告げると、コップのビールで口を湿らせた。
一昨日、そして昨日、伊達は雄大に一日二時間の出勤を依頼し、データの整理や買い出しといった雑務を申しつけた。結果として、パソコンを使った作業はほとんど当てにできないクオリティであり、買い出しこそ確実な結果は残したものの、自分とそれほど歳の変わらない労働者としては、長所として評価することはできなかった。つまり、山田雄大という男は労働力という観点から見ると、今のところ年齢相応の価値はないと言い切れる。
だが、四人のパートタイマーたちはそこまで冷淡な査定はしていないだろう。なぜなら彼らは雄大と実に親しげな交流をしている。雄大はユーモアがあって気さくで情に厚い青年であり、少々の無能はむしろ愛すべき欠点だと認めていることだろう。この数日ほど出張もなくずっと事務所で観察していたので、伊達はそう確信していた。となると、誰もが看過できない別の短所を探り出さなければならない。
「しかしお仕事をお願いする結果でよかったのですかね?」
「あ、いやー、どーせヒマだし、マサカズのことも心配だし、親から面倒見ろってね、言われてんですよ」
「明日は定時出勤、それと日曜日はマサカズと出張仕事をお願いします」
伊達がそう言うと、雄大は少しだけ身を乗り出し、目に意欲を宿した。
「おっ、いよいよマサカズのウルトラ仕事に同行ですか?」
鼻息も荒く尋ねてきた雄大に、伊達は言葉という弾丸を、殺気を込めて念入りに選別した。すると、背後の棚でうとうとしていた三毛猫が目を覚まし、彼の元を去っていった。
「ウルトラ仕事、とは? 彼は普通の人ですよ。なんの根拠です?」
「あ、いやだってひと晩で旅館の解体をあいつひとりでだなんて、なんかスーパーなヤツがあるんでしょ?」
その事実をいつ知り得たのかはどうでもいい。現在の雄大は社内のネットワークにいつでもアクセスできる権限があり、帳簿を事細かく調べれば嬬恋村での初仕事の委細については知りうることができる。問題は、その“事細かく調べる”ことに対する動機である。伊達は無言のまま再びアルコールで唇を湿らせた。
「それと、あいつチェーンソーの資格とったんですよね。次は森林伐採でもやらせるんですか?」
「日曜日の仕事がそうです」
「あいつに何があったんです? せいぜい本屋でバイト止まりの負け組アラサーっスよ?」
「あなたはまだ、それを知りうる立場にはありません」
単純な拒絶を選んでみる。さて、この男は如何なる反応をするのだろうか。伊達は心のラケットを構え、相手の出方を窺った。すると二人の間に梅の鰻重と肝吸いが運ばれてきた。ふたを開け、小さな瓢箪から山椒を振りかける。今年になって初めてとなる鰻に伊達は箸をつけた。柔らかいそれはほんの僅かな力でカットされ、タレの香りを漂わせたまま伊達の口に運ばれた。
「なんか副社長、ドライっスねー。ボク、一応親族なんですけど」
「マサカズが得た力は特別です。それと同時に危険でもあります。アレを知るにはそれと向き合う覚悟と、気高さが必要なんです。申し訳ないのですが、私はまだあなたがそれを充たしていると査定できていません」
鰻を食べる。脂が口の中で広がる。山椒が舌を刺激する。大技を繰り出した伊達は、対面で重箱を見下ろす雄大を一瞥した。
「気高さなんて、アイツにはねーっすよ。副社長、あの爺さんたちみたくマサカズを過大評価してますね」
「ほう」
「だってさー、アイツ小学二年生になるまで、半年イチペースでおねしょしてたんですよ。それに片思いの女の子と結婚する妄想とかして、ノートに人生設計図書いたりしてね、まー恥ずかしいヤツですよ、実際」
伊達は箸を止めた。雄大は持ち上げた鰻重を勢い良くかきこみ、ふんふんと鼻を鳴らせていた。
「他にはアレだなー、オレのマネして本屋で万引きなんかもしたんですよ。ビビって返しちゃってましたけど。まー、つまり根性もねー」
雄大の重箱からつゆが乗った米粒が飛び出し、漆塗りのテーブルに散った。雄大は肝吸いの器を手に取ると、それを呷るように啜った。伊達は彼の喉が躍動するのを見ながら、静かに鰻と米を口にした。
「まぁまぁいけるっスね。この鰻。まぁまぁっスね。ランクBってとこかな?」
何度も出会った。この手合いは。値踏みをするつもりだったのだが、意図せず本性というものが透けて見えた。ならばもう、探りを入れる必要はない。ただ、最後にひとつ確認するべき点があった。伊達は肝吸いを啜り、精力的に鰻重に取り組んだ。
「しっかしあの爺さんたちは、ぬるいっつーか、さすがはリタイア組ってところですよねー」
「あ?」
できるだけ短い相づちを心がける。そうすることで、相手の本性をより多く引き出すためだ。
「あ、いや、だってあいつらよく休むし、こないだなんて草津がね、孫の誕生日とかで午後半休っスよ。いやー、舐めてますよね、仕事ってものを。オレだったらぜってーあり得ねーっスよ」
親しげにしている老人たちの悪口まで飛び出した。自分の価値を高めるため、易い言葉で。このような人物はよく知っている。顧客として、証人として。評価できるうる能力を持ちながら、なぜ不遇であるのかよくわかる。それを知り得ただけでもこの場は無駄ではなかった。伊達は言葉を選び、それを口にした。
「なぜあなたは、初めてウチにやってきた日、なにもせずに帰ったのですか?」
質問に雄大は箸を止め、重箱をテーブルに置いた。
「木村ともうちょっと仲良くしないといけないかなって。あと、寺西とも」
「それは、ウチをより知るためですか?」
「ええ、浜口と草津は、まぁいいかなって」
「ウチを知って、ウチに入って、それは叶いましたね」
「叶いましたね」
「我々の目的はご理解を?」
「えっと……人助けとか社会貢献ですよね」
「やりたいですか?」
「どーですかね。人に喜ばれてお金がもらえるんなら、悪くはないかなって」
「やはりあなたには、マサカズの秘密を当分のあいだ教えられませんね」
「急に、なんです?」
「マサカズの長所を、残念だけど兄であるにも関わらずあなたは理解できていない」
「長所って、秘密の力でしょ? ひと晩で旅館解体できるような」
「違います」
「いやいや、それぐらいしかないでしょ? だってさ、ついこないだまでフリーターよ」
「他にあります。考えてみて答えてくれますか?」
伊達にとって、その問いは最終尋問に等しかった。雄大は顎に指を当てると、首を大きく傾げた。
「まぁまぁイケメンなところっスかね。あー、あと意外と歌がうまい」
目を伏せると、伊達は席を立ってスーツのポケットから財布を取り出した。
「ごちそうさま。ここは会社から出します」
「あ、いや、ボクがおごりますって」
「いいですよ。この店にしようって言ったのは私ですから」
「なら、こっからキャバでもどーです? 区役所通りでいい店知ってるんスよ。副社長、結構そっちとか好き系でしょ?」
「二度と、行きません。マサカズがいる限り」
そう言い残すと、伊達は会計のためレジに向かった。石造りの床にいた三毛猫は尻尾を振り、湿らせた前足で顔を拭った。
【無料版】第4話 ─鉄の掟を作ろう!─ Chapter5
“南側から北に向けて倒す。そして何度も繰り返す。”それが今夜の心がけだった。兄の運転するレンタカーで山梨県北部のひと気のない山中までやってきたマサカズは、手刀と前蹴りで次々と杉の木を破砕していた。保司の紹介でサービス業者から発注された作業内容は極めて単純であり、指定された区域に生い茂る樹木の伐採だった。直径七十センチメートルを超える樹木の伐採については免許が必要であり、マサカズは伊達の指示で三日間に亘る講習を受け、それを取得していた。内容としては伐採に用いるチェーンソーの取り扱いについてが大半を占めていたため、それを用いる必要のないマサカズにとっては興味深くもあり退屈でもあった。
後ろ蹴りで巨木をへし折ったマサカズは思った。例えば時速百キロで走れる人間には車輌と同等の走行能力を有しているが、彼にはその能力を用いるために免許は必要とされない。解体業のように他者への影響が発生するものは、間違いを起こした際に責任能力を問われる可能性があるため、ライセンスが必要になるのは理解できるが、伐採についてはさてどうなのだろう。次々と大木をなぎ倒しながら、マサカズはぼんやりとそんなことを考えていた。
昨日の土曜日、秋葉原のゲームセンターで落ち合った伊達はこう言った。「お前の兄は悪党だ」と。それはとうにわかっていたが、法律家に断定されると貼られたラベルの文言に太さが伴う。
「俺のミスだ。すまない」
ゲームセンターのコミュニティエリアと名付けられた飲食スペースで、伊達は頭を垂らしてそう言った。
「ミスってなんです?」
「見誤りだ。お前の兄は悪党だ」
「それはわかってましたし、そんなようなことは僕も言いましたよね」
「ああ、しかも組織に入れてはいけないタイプの悪党だったってことだ」
「根拠を解説してもらえますか?」
「木村さんにも確認したんだが、あいつはお前を売って、人気を固めている」
珍しく、伊達の言葉が呑み込めなかった。マサカズはそれを顎を落とすことで伝えた。
「つまりな、あいつは自身しか知り得ないお前の恥ずかしい過去や弱味を爺さんたちに喧伝して、それをきっかけに相手の懐に取り入ってるってことだ。実際、つい先日俺もそれを食らった」
「あー、兄貴っぽい」
「能力はあるのになぜくすぶっているのか、よくわかったよ。あの人心掌握は最低のやり口だ。いっときの注目は集められてもいずれは破綻する」
「でしょーね。昔っからそうでしたよ。兄貴は人の悪口ばっかりで、そうなると吹き込まれた方もいつ自分の悪口をネタにされるんじゃないかって思って、兄貴とは距離を置くようになる。要するに人望がなくって孤独なんです」
「マサカズ……その論評って……」
「伊達さんの指摘を呑み込んで、いま組み立てました。なんだかモヤっとしてたことがハッキリとして、ムカつくけど気持ちいいです」
「でだな……」
「切りましょう。兄貴は。あ、けど明日の山梨の仕事はさすがに外せないか」
「そうなると、月曜日以後になるか……縁切り、俺がやろうか?」
「僕がやります。社長ですし」
「いや、しかし俺のミスだし」
「親族でもありますから。兄貴、なにもかも伊達さん任せかよって、バカにしてくるので、その減らず口を閉じさせてやりますよ」
「これまで、そういったケースの成功例はあったりするのか?」
「どうでしょうか? ないかも」
「ない?」
「ごめんなさい、なんだが自信なくなってきたかも」
「やっぱり俺がやる?」
「いえ、僕がやります。なんて言うのか……」
ようやくあの鬱陶しい兄との決別ができる。自分の口から欠点と難点を宣告し、人として否定し、拒み、関係を断つ。両親は決して快くは思わないだろうが、あのようにねじ曲がった人間との接点はもう持ちたくない。これはおそらくいいきっかけだ。
五十を超える木々を打ち砕いたマサカズは、周辺を警戒しているはずである兄の姿を捜した。今夜の伐採業務は自分が実行担当であり、兄がレンタカーでの移動と周辺の警戒を担当していた。この仕事が終わったのち、兄には決別を告げよう。そう考えていたマサカズだったが、具体的な文言についてはまとめきれてはおらず、ぶっつけ本番でいいと思っていた。
兄の姿が見当たらないので、マサカズは木こり仕事を再開した。それから二時間ほどが経ち、そろそろ日の出に差し掛かろうとしていた。発注されていた区画の伐採も全て終え、マサカズは手刀で倒木を二メートルほどの長さに切断していた。あとしばらくすれば保司がトラックでやってくるので、それまでにトラックに積み込める大きさにしなければならない。マサカズは手際よく大木を切り刻み、それは一時間足らずで終えられた。
さすがに若干の疲れを感じる。同行の相手が伊達であれば、このあとサウナにでも寄っていくのだが、兄となるとその選択肢はない。兄が会社に押しかけてきてから半月近くが経っていたのだが、事務所で言葉を交わす機会はほとんどない。四人の老人たちとは定時後に呑みに行き、コミュニケーションをとっているようだが、兄は自分に対してまったくと言っていいほど接触してこない。何か良からぬことを企んでいるのだろう。その結論が最も素直に頷けるものであり、我ながら血縁への認識がろくでもないと呆れるしかないマサカズだった。

「マサカズ! ごめん!」
林の奥から姿を現してきた兄は、真っ先にそう謝罪した。マサカズは切断した木に腰を下ろし、兄を見上げた。
「見回りサボってたってこと?」
「いや、周辺警戒は怠りなしだ。ついさっき、三台目の車が県道を通過するのを確認した」
「なら、なにが“ごめん”なの?」
「いやさ、今日の仕事、お前が何をしてんのか見ちゃダメって約束だっただろ?」
「うん」
「ごめん、見ちゃった」
約束を守るとは思っていなかったので、マサカズは驚くこともなく頬杖をついた。
「なんなんだ? バトルマンガの強キャラか? お前、なんであんなことできんだよ」
「ひみつ」
「おいおい、兄に対してそりゃないだろ。どーせ副社長は正体知ってるんだろ?」
「それもひみつ」
「なぁ、オレにもなんかお裾分けしてくれよ。薬かなんかなんだろ?」
「ひみつ」
「お前、それしか言えねーのかよ? こんな真夜中に、なれねー車の運転までさせといてよ」
「とにかくひみつ」
どうやって減らず口を封じるのか、マサカズはそれだけを考えていた。兄はしばらく言葉なく弟の周囲をうろうろとすると、やがて背後で立ち止まった。
「ごめん」
「今度はなにが?」
「お前がすげぇってのはわかったし、だから社長なんかになれたんだよな。オレとは無関係なことだ。なのに根掘り葉掘りだし、挙げ句の果てには分け前なんて、ひっでー兄貴だ。オレ」
「自覚してんだ」
「そりゃ、さっきまで森だったのが、すっかり広々としてさ、見てたらオレが相応しくもないおねだりをしてたって、わかるよ」
「珍しい」
「ひみつ、なんだよな。オーケーオーケー。だったらオレの役割もハッキリとしてきた」
「へぇ」
「オレはお前の秘密を守る盾になる。探りを入れてくるような連中を片っ端からシメていく」
「やめてよ」
「任せろって。慣れてんだよ、お前の兄貴はそーゆーこと」
兄とやりとりをしていくうちに、マサカズはひどい疲れを感じ始めていた。心身共に、やたらと重苦しい。今日は特にスピード重視の作業だったため、短時間において集中しての能力発揮だったからかもしれない。そして、背中から浴びせられる兄のひどく軽いアピールに心底うんざりしているからなのかもしれない。
「兄貴」
「なんだいマサカズ」
「寝る。あとの段取りはわかってるよね」
「保司ってツナギのオッサンがきたら、このゴミを持ってってもらうんだろ?」
「請求書を受け取って。あと、俺のことなんだけど……」
「任せろって、おぶって車まで運ぶから。えっと、小岩のアパートでいいんだよな」
「ついたら起こして」
「任せろ、任せろ。お兄ちゃんを頼りにしてくれって」
「いまはそーする」
結局、兄に決別を告げられなかった。眠りに落ちてしまったマサカズは、頬に冷たい感触を得て目を覚ました。
「コーラ、好きだったよな」
缶のコーラを手にした運転席の兄が、笑顔を向けていた。まだ覚醒には至らぬまま、マサカズは缶を受け取り助手席から路地に出た。小岩のアパートは目の前である。うつらうつらとしながらもスマートフォンで時刻を確認してみたところ、もうすぐ正午になろうとしている。兄はレンタカーでここまで運んでくれたようだ。腰に提げたポーチを確かめてみたところ、木更津クリーンサービスからの請求書が入っていた。どうやら、兄は申しつけた仕事をすべてこなしてくれようである。全身が鉛のように重く、今日は一日寝入ってしまうだろう。兄に別れを突きつけるのは明日にしよう。今回の仕事を過不足なくこなしてくれた兄に対して「あなたはタチの悪い悪党だ。だからここで縁を切る」とは、なんともひどい通告だとは思うが、伊達との約束は何よりも勝る。アパートの外付け階段をのろのろと登るマサカズは、明らかに困惑の中に在った。
【無料版】第4話 ─鉄の掟を作ろう!─ Chapter6
山梨県北部での森林伐採は成功と言っていいだろう。アパートに戻り、疲れを癒すため夕方まで寝入ってしまったマサカズは、材木の回収を担当する保司に電話をし、自分が意識を失ったのち、兄がそつなく段取り通りに業務の引き継ぎを行ったと聞いた。だが、彼との縁は切らなければならない。他者の評価を下げることで注目や関心を惹く人心掌握や、人や仕事に対して根本的に尊敬を感じられない態度など、鍵の秘密を守りつつ共に仕事をしていくには不安しかない人間性の持ち主だ。ある程度の手切れ金が必要になる可能性もあるが、井沢による資金洗浄で、ある程度まとまった金額は預金されているのでどうにかなるだろう。その日の夕方から夜にかけ、マサカズは布団に大の字になって、兄の不遜さに満ちた悪辣とした笑みを思い浮かべていた。
翌日の夜、マサカズは代々木駅近くのとある居酒屋のカウンターにいた。コの字型のカウンターの右角の向こうに設置されたテーブル席には、木村と寺西の二人の老人と、アロハシャツ姿の兄が酒席に興じていた。マサカズはレモンサワーのグラスを手に、身体を丸めて三人のやりとりに耳をそばだてていた。
「いやね、とにかくマサカズは昔っからトロくて困っちまうんですよ~アレは小学五年のころだったかな? ボクが教えたエロ動画サイトを親父のパソコンで見たんですけど、履歴を消さないままだったんで、すーぐバレてやんの。しっかも見たのがなんだったかな……まぁいいや、とにかくしょーもない動画だったんで、親父は怒るよりすっかり呆れちまってね! お袋なんざメソメソと泣き出す始末っスよ」
よく通る高い声で、楽しそうに兄は二人に語った。しかし木村は仏頂面を崩さず、寺西はただ苦笑いを浮かべるだけで、内容に興味を示す素振りはない。マサカズはお通しの枝豆を摘まみ、中身を口に含んだ。
事の発端は、つい十分前に届いた木村からのショートメッセージだった。「居酒屋“よよキング”にて、雄大氏、想定Aを実行中」短い内容ではあったが、それをきっかけにマサカズはこの居酒屋を訪れ、いま兄の動向に注意を向けていた。今日は伊達が出張に出ているほか、浜口と草津は通院のためそれぞれ欠勤と早退になっており、定時と同時に兄は木村と寺西を食事に誘っていた。木村には先週末の時点で、今後もし兄が酒席などで自分の悪口を言うことになったら連絡を入れてくれるよう、指示を出してあった。木村は実直で、おそらくは兄とは相性がよくないと踏んでの依頼だったが、どうやら上手くいったようである。次々と飛び出す過去の恥ずかしいエピソードを耳にしながら、マサカズは兄に対しての怒りを溜め込んでいった。
それにしても、である。あのような真似をしなくとも能力を発揮することで、木村たちの心を掴めるはずなのに、なぜ兄はあのような好ましくない手段を選ぶのだろうか。少し考えを巡らせたマサカズは、ある結論に達した。要するに、兄は自信がないのだ。あれは不安がさせている行動だ。この会社の仕事は詰まるところ鍵の超能力による破壊業務が収入源であり、他の仕事と言えば車の運転や事務、雑務といった兄にとってあまり得意とは言えない内容ばかりだ。伊達の目利きによると、兄の得意分野は人の目を欺いたり、出し抜いたり、お喋りで関心を集めるといった、言わば詐欺師に必要とされる科目だ。マサカズは思わず呑むつもりのなかったレモンサワーをごくりと呷った。
「しっかしボクもいつ正社員なんスかねぇ? な~んか副社長がストップしてるっぽいっスけど、あいつなんかケチっスよね。なんか、アイツについて知ってることとかあります?」
兄の問いに、だが木村たちは首を小さく傾げるばかりだった。
「弁護士だかなんだか知らないけど、アイツにはいずれ出て行ってもらわねぇとな」
「雄大さん、な、なんて?」
寺西は怯えた声で、曖昧な問いかけをした。兄はビールを呑み干すと、空のジョッキをテーブルに打ち付けるように置いた。
「ベンチャーってのはね、結局信頼関係なんスよ。伊達だかなんだか知らねぇけど、あんなの全然信用ならねぇっスよ。で、いまウチにはボクがいる。マサカズの兄のボクがですよ? これ以上信頼できる人材なんていないでしょ。必然的に、副社長はボクがやった方が会社のためなんスよ。と言うわけで爺さんどもも、今のうちからボクと仲良くしといた方がいいよ~」
「今すぐ荷物をまとめて出ていけ」
できるだけ怒りという感情を抑え、低く呻るような声でマサカズはその言葉を兄の背中に浴びせかけた。自分に対する悪口によって怒りを溜め込み、それを推進力として兄に対して縁を切る通達をする予定だったのだが、その毒牙が伊達にまで及ぶと知ってしまった以上、推進剤はタンクの容量を超え溢れきってしまい、ちょっとしたきっかけで大爆発を起こしてしまいそうだった。
「よう、マサカズ。お前も一杯やりにきたのか?」
振り向いた兄は、とぼけた口調でそう言った。
「雄大さん、悪いね。社長から頼まれてて。キミが社長の悪口とか言うようなら連絡をくれって」
木村の正直な告白に、兄は何度もゆっくりと頷き、追加の中ジョッキを注文した。
「どーりで長えトイレだと思ったんだよなぁ。この古狸め」
そう毒づいた兄は、背後に立つ弟を睨みつけた。
「座れよ。隣、空いてるし」
「嫌なことは聞かないフリって、あんたの基本だったよな。思い出したよ」
「ホラ、はよ座れ。兄弟仲良く呑もうではないか」
「もう一度言う。ナッシングゼロの代表として。山田雄大、あなたはすぐにでも私物などの荷物をまとめ、事務所から退去しなさい。そもそも雇用契約も結んでいないから、今のあなたは事実上ウチで労働をしているってことになっているけど、我々はいつでもあなたを不法侵入者として当局に通報することができる」
土曜日に秋葉原のゲームセンターで、伊達からアドバイスされた単語をいくつも織り交ぜてみた。兄は再び背中を向けると、運ばれてきたビールジョッキを手にした。
「伊達に言われたのか?」
「違う。あんたを切るって言い出したのは私だ。理由が知りたいか?」
「いや、いい」
ビールをひと呑みした兄は、ゆっくりと振り返った。
「テメー、誰に向かって口きいてんだ? あ? ふざけんじゃねーぞこのヤロウ」
静かに、兄にしては低い声での脅しだった。だが、スーパー銭湯で襲撃してきた顔まで入れ墨の怪物と比べれば、仔猫の威嚇のようにしか感じられない。すでに鍵を“アンロック”していたマサカズは、兄の肩をしっかりと掴んだ。
「私は二つのことをしたくない。ひとつめは、不法侵入者としてあんたを警察に突き出すことだ。そしてもうひとつは、このままあんたの肩をぶっ壊してしまうってことだ」
それは吉田に対して行った脅迫と同じ行為だった。耐えきれないほどの負荷を兄の肩に対してかけている。その証拠に彼の大きな身体は小刻みに震え、表情こそ見えないが苦悶に歪んでいるはずである。マサカズは「どうなんだ?」と念を押した。
「わかった、わかったよ」
兄が両手を降参するように上げたので、マサカズは肩から手を離した。
「よーするに、試用期間でオレ、クビってことね? 荷物まとめて出て行け? オーケー、オーケー。だけどさ、今すぐってのはさすがに無茶振りだろ? せめて今週いっぱいは時間をくれよ。副社長から頼まれた伝票の整理とか、明日、明後日で届くあれやこれやの対応とか、任されてる仕事もあるし、こいつらへの引き継ぎとかさ。もちろん、それまでの給料は払ってもらうからな。あと三日、金曜までだ、いいよな」
「ああ、それは問題ない」
危険人物である兄には即刻立ち去って欲しかったが、口達者な彼と交渉するのも面倒に感じたため、マサカズは譲歩した。背を向けたままの兄は、いまどのような顔をしているのだろうか。だが、マサカズはそれを確かめる気になれず、会計を済ませたのち居酒屋をあとにした。
八月二十四日、二日の出張を終えた伊達は、久しぶりに代々木の事務所に出勤した。山梨県での伐採業務は業界でも噂になっているようであり、同業他社の動向に細心の注意を払っていけば、安定した収入源になるだろう。だが、まだこのままではあの力を有効に使えているとは言いがたい。より以上の案件を引っ張ってくる必要がある。伊達は今日一日の業務内容を考えつつ、もうひとつマサカズがやり遂げたという成果をいち早く自分の目で確かめたかった。おのずと、階段を登る足取りもいつもより忙しなかった。
「あ、副社長、おはようございます」
伊達が事務所に入ると、段ボール箱を抱えてた雄大が頭を下げてきた。
「すみません。お役に立てなくって。ボク、社長からクビって言われちゃって」
伊達は小さく頷くと、デスクでパソコンに向かうマサカズに目を移した。彼は一瞬だけ伊達に視線を向けると、再びモニターに戻した。おとといの夜、マサカズから電話で雄大の排除が成功したとの連絡はあった。当然ではあるのだが、その声は重く、濁り、うわごとのようにも感じられた。彼の精神のバランスが悪い方向に傾いていないか、それを心配していたのだが、業務に打ち込んでいる姿を見る限り、それは杞憂に過ぎなかったようである。伊達はひとまず安心することにした。
それから一時間ほど経ったころ、雄大は伊達のデスクまでやってきた。
「じゃ、オレ上がります。まだ十時ですけど。残りは明日。と言うか、明日で最後です。たぶん、一時間ぐらいの作業かな? じゃあ今日もう一時間やってけよってのはナシで」
「報酬は八月分として月末締めで支払う。時給ではなく日当として。それでいいんだよな、社長」
伊達に話題を振られたマサカズは「いいです」と短く返した。
「いやぁ、太っ腹ですねぇ。こんないい条件でのお仕事、そうそうございませんよ」
雄大の軽口に、伊達は返事をすることはなかった。
「なぁマサカズ、鍵なんだけどさ、どこに返せばいい?」
兄からの問いに、だがマサカズはすぐに答えることができず、すっと視線を壁際のロッカーに移したのち、「鍵って何の鍵?」と聞き返した。
「んなの、ここの事務所の鍵に決まってんだろ。クビなんだからオレがもらったヤツはお前たちに返さないと」
「それなら明日帰るときに、僕に返してくれればいいよ」
「わかった。そうするよ」
なぜ自分に尋ねる。会話の流れから考えれば伊達に聞くのが自然だ。マサカズは心をざわつかせたが、兄と関わるのも明日の一時間で終わりだと考えると、詮索する気も起こらず、目の前の事務仕事に取り組むことにした。
その日の仕事を終えた伊達はマンションに戻り、リビングのソファに腰を落とした。マサカズにできるか不安ではあったものの、雄大の件は無事、解決できたようだ。これなら今後、彼にお願いできる業務の範囲を広げてもいい。伊達はテーブルの上のノートパソコンを起ち上げると、ブラウザの検索窓に“せっと”と打ち込み変換した。すると検索窓には"鍵" "キー" "超能力" "パンイチ" "目出し帽"といった複数のワードが表示された。これは会社設立を決めて以来、伊達が毎日のノルマとして夜に行う検索だった。すべてはマサカズの力に関連するものであり、昨夜に至るまで、特定されるような情報はなにひとつヒットしなかった。
「が」
喉を鳴らしてしまった。ブラウザに表示された一件の検索結果に、驚き、目を疑い、心の中の非常ベルが鳴り響く。伊達は立ち上がってノートパソコンを畳むと、それとヘルメットを抱え、玄関に向かって駆け出した。
【無料版】第4話 ─鉄の掟を作ろう!─ Chapter7
火曜日に決別を告げ、二日が経った。明日の金曜日を最後に、兄は遠い存在になる。おそらくはもう会うこともないのかもしれない。原因もはっきりとは説明できないまま暴力で屈服させ、言ってしまえば追放するような形での別れだ。せめて、明日は送別会でも開ければいいのだが、明日も今日や昨日の様に、九時から一時間だけの出勤になるのだろうからそれも叶わないだろう。
気分を変えよう。アパートの台所で、新たに発売されたばかりのカップ焼きそばの湯切りをしたマサカズは、史上最強と自称されている激辛ソースを麺にかけ、それをよく混ぜ合わせた。どの程度の刺激なのだろう。悶絶しているうちに、兄のことも忘れられるといいのだが。馬鹿馬鹿しい期待を抱いたマサカズが割り箸で真っ赤な麺を掬おうとしたところ、玄関の呼び鈴が鳴った。のぞき窓を見るとヘルメットを被ったままの伊達が扉を叩いている。マサカズが解錠した途端、扉は乱暴に開かれ、スーツ姿が弾丸のように飛び込んできた。
「伊達さん、何事です!?」
「緊急事態だ。マサカズ、お前は兄の配信動画を削除できるか?」
要求は明確だが、それは理由によって選ぶべき答えの数が多すぎる。であれば、最悪からアプローチしてみよう。伊達の期待に応えたかったマサカズは、彼とは逆にできるだけ冷静さを保つことにした。
「できると思います。以前にアップロードしたのは僕なんで、兄貴がパスワードとか変えてなければできます」
マサカズの言葉に頷き返すと、ヘルメットを脱いだ伊達は鞄からノートパソコンを取り出した。
「Wi-Fiはないな。LANケーブルは?」
「あ、いや、そーゆーのは」
「わかった。ならなんとかする」
伊達はノートパソコンを床に置くとそれを起動し、スマートフォンも同時に操作して、マサカズにパソコンのブラウザで動画配信サイトの画面を見せた。
「これを見て欲しい。そしてできれば見ながら、こいつを削除する手を打って欲しい」
「兄貴のチャンネルですね。わかりました」
画面に、ひとつの動画が再生された。どこかはわからないが、薄暗い部屋にアロハシャツ姿の兄が映し出されている。動画のタイトルを確かめてみると『鍵で超能力って信じられる!? 前編』と記されていたので、マサカズは青ざめ、隣に座った伊達を横目で見た。
「どもどもおひさー! YouDaiちゃんねるのユーダイでーす! 今日はですね、ボクが知ってしまったとんでもない超能力について、みなさんにお知らせしていきたいと思いまーす! いやー、びっくりしちゃいましたよ。あのですね、ボクには弟がいるんですけど、こいつがアメコミヒーローみたいな超能力者でしてね。ぶっとい大木も素手のチョップで粉々にできちゃうんですよ。でですね、そんなことできるわけねーだろってことで、なにか秘密があると思って探ってみたんですけど、どーやら弟は不思議な鍵で超能力を使えるようになったみたいなんですよね。見ちゃったんですよ、力を使い切ったあと、弟のポケットで南京錠が外れたのを。まーまーまー、誰も信じないよね。このアロハオヤジ、なーにふかしてんだよって思っちゃいますよね。と言うわけで、後編ではこの鍵のスーパーパワーについて、もっと詳しくお知らせしようと思います。とんでもないモノ、見れるかもよ~。それではこの動画がいいと思った人は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いしまーす!」
時間にしては五分足らずだったが、その内容はマサカズに激辛という事実を忘れてカップ焼きそばを口に運ばせるほど衝撃的だった。マサカズはひどくむせ返ると、ペットボトルのお茶をごくごくと飲み込んだ。
「消します」
マサカズはブラウザを操作して、兄のチャンネルにアクセスをした。予想通り開設当時からパスワードは変更されておらず、動画はサイトから削除された。そして、マサカズは念のためにパスワードも変更した。
「伊達さんはなんでこれを?」
「毎日一定のキーワードで鍵の力が漏れていないか検索していたんだ。そうしたらこれがヒットした」
「ごめんなさい……山梨の伐採のあと、疲れて寝てしまって、兄貴に運んでもらったんですけど……」
「そのリスクはある程度見込んでいたけど……鍵が力の源泉だって結びつけられるとはな」
「伊達さんの評価を前提とした場合なんですが、僕、兄貴にクビを言い渡すとき、鍵をアンロックしたんです。ポケットの中で。もしかするとそれをチラ見してた可能性もあります」
「そうか……動画のアップロードは二十四時間前、昨日の夜だ。後編で詳しくって言っている以上、雄大はお前に何らかのアプローチをしてくるかもな。例えば、瓜原みたいな輩をけしかけて、鍵の力を撮影したりとか。明日しれっと出勤してくるかどうかは、微妙なところだな」
「打つ手はひとしかないでしょう」
マサカズは立ち上がると、フルフェイスのヘルメットを手に取った。
「どうするつもりだ?」
「兄貴の住んでる場所はわかってますから、今から乗り込みます。そして、脅します」
その対策に、伊達は腰を上げてマサカズの手首を握った。
「できるのか? 実の兄を?」
「居酒屋で一度やってますから。もちろん、今度はもっと強く脅しますけど」
「こういったケースだと口止め料って手もあるけど……雄大みたいなヤツは、キリがないパターンに陥る……」
伊達が言い終えぬうちに、マサカズは「一円も払わなくていいです」と、強い口調で逡巡を打ち消してきた。二人の間に沈黙が流れると、カラーボックスに置かれていたマサカズのスマートフォンが揺れた。拾い上げてみると、一枚の写真が着信されていた。ロックを解除して写真を見たマサカズは嗚咽を漏らし、伊達に画面を見せた。
大柄なアロハシャツの男が事務所のような一室で跪いている。両手は結束バンドで拘束され、顔には数えるのが躊躇われるほどの痣が浮かんでいる。頭髪は乱れ、腕には煙草を押しつけられたと思しき火傷の跡も認められる。そう、それはつい先ほどまでノートパソコンの画面で軽妙なトークをしていた男の変わり果てた姿だった。すると、再びスマートフォンが振動した。どうやら非通知での着信である。マサカズは伊達に再び画面を向けた。伊達が僅かに頷いたので、彼は電話に出た。
「あー、山田ちゃん。久しぶり。吉田だよ。写真見た? お兄ちゃん拉致ったんだわ。でね、鍵持ってんだよね。それ、持ってきて。持ってこないとお兄ちゃん、ちょっとヤバいよ? 動画消したのは山田ちゃん? 手遅れだったね。昨日見ちゃったのよ。こっちも色々と検索しててさ。ケンちゃんが、山田ちゃんから鍵の力が云々とか言ってからさ。ダメ元で自動検索してたのよ。そしたらお兄ちゃんの……ああ、もういいや面倒くせぇ。とにかくさ、あのクソ動画がマジだって認定したんだよ、こちらとしては。で、もう一度言うけど、鍵もってこい。一時間後にもう一度電話する。出なかったらお兄ちゃんのボコられ動画、送りつけちゃうよ」
一度の返答の余地もなく、吉田からの電話は一方的に切られた。途中からスピーカーモードに切り換えていたので、最悪の状況は伊達も共有していた。
「マサカズ、選択肢を一つ潰させてくれ」
「嫌です」
「交渉に応じるフリをして、吉田たちから雄大を救出……悪手もいいところだ」
「僕にはそれができる力があります」
「人質を取ってる吉田たちの方が、遙かに有利な状況だ。残念だけど鍵の力は限定的だし、お前ができる内容は吉田たちも把握している」
「ならどうするんです?」
「井沢さんに吉田周りの情報を集めてもらう。二日もあれば住まいや女の家とかわかるだろう。前に奪った携帯の情報は、これだけ時間が経っているとアテにはならないからな」
「兄貴はどうなるんです?」
「いくつかのケースが考えられる。例えば一時間後に電話に出なかった場合、数十分おきに写真や動画が送りつけられる」
「兄貴が拷問されている動画ですか?」
マサカズの声は掠れ、震え、それは伊達としては顧客や証人から幾度か耳にした心の乱れを感じさせる言葉だった。
「救出は奇襲しか成功する見込みがないと考えてくれ。今夜は連中が一番警戒し、万全を期してお前の力に備えている。今夜じゃない。わかってくれ」
「見殺しにしろって?」
「殺されるとこはない。この件での吉田の切り札は雄大だ。絶対に命を奪うことはしない」
「死んだ方がマシって思えるような目にあわせるんでしょ?」
マサカズの震えた問いに、伊達は返事ができなかった。これまでの弁護士稼業で、ああいった種類の人間がどれだけ惨たらしい仕打ちをするのかはよく知っている。だから、言葉として伝えることはできなかった。マサカズはヘルメットを床に置くと、大きく深呼吸をした。
「わかりました。こうしましょう」
スマートフォンを手にしたマサカズは、それを部屋の隅に鎮座していた金庫の角に打ち付けた。画面は割れ、中の基盤は剥き出しになり、それは通信端末としての機能を全て失った。マサカズの思いきった行動に、伊達はうめき声を漏らした。
「井沢さんに連絡お願いします。そして、作戦を立てましょう。なにがあっても絶対に兄貴は助け出します。たとえ、どんな状態になってしまっていても」
その決意に至るまで、どれほどの葛藤があったのだろう。このように短い時間で達するには、自分ではおそらく不可能だ。伊達はマサカズに敬意を抱き「今から俺のとこに行くぞ。ここは吉田にもバレてるだろう」と、取るべき具体的な方針を伝えた。
激辛カップ焼きそばは半分も食べられることがなく、誰もいない部屋に取り残されることになった。
吉田の情報収集能力と、それに費やすコストが読めないため、伊達は彼らが何をどこまで知っているのかを把握しあぐねていた。無論、そういった場合は最悪を想定するのが最良なのだが、そうなると打てる手がまったくなくなってしまうので、ある程度は楽観的に舵を切る必要もあった。吉田は自分のことをどこまで把握しているのだろうか。伊達隼斗とはアプローチしだいでいくつもの肩書きが得られる存在だ。カルルス金融の債務者。柏城法律事務所に所属していた弁護士。株式会社ナッシングゼロの役員。これらの情報を全て掴んでいた場合、マサカズの有する力の深部を知り得る協力者ということになる。
飯田橋のマンションまで彼をバイクで連れてきたものの、ここも吉田たちに知られている可能性もある。どのような肩書きの伊達隼斗がこの十三階に住んでいるかによって、見張りを置くなどといったコストを吉田は支払うだろう。だが、それでもあの小岩のアパートにいるよりはずっと安心でき、こちらもそのコストを毎月支払っている。最善とは言いがたいが、ここで作戦を練るのがまだましであると伊達は判断していた。
「マサカズ、夕飯は?」
「食べる気になれません」
エレベーターに乗り込み、ヘルメットを抱えていたマサカズは力なくそう返した。
結局、この夜は交替で睡眠を取ることにしたのだが、マサカズはリビングに敷かれたマットレスに横になったものの、一睡もできなかった。そして、伊達もやはりそうだった。
翌日、マサカズと伊達が事務所に出勤すると、浜口と寺西がいた。木村は休みで草津は午前半休なので、本来なら今日が最後の出勤になるはずだった雄大を除けば、これが本日におけるナッシングゼロのフルメンバーである。マサカズがスマートフォンを破壊して以来、吉田からの連絡は一切なく、これは伊達にとって吉田が電話番号などの情報や、マサカズとの関係性を詳しく知り得ていないことの証左にはなる。だが、事務所の電話となれば話は別だ。少し調べれば容易に辿りつける情報だ。伊達はデスクの固定電話に最大限の注意を向けた。
定時から十五分ほどが過ぎたが、事務所の電話は鳴らなかった。マサカズは無意識のうちに目を壁際のロッカーに移した。あの中には、七本の鍵を収納した手提げ金庫が入っている。昨日、兄に鍵の返却先を尋ねられた際、つい、見てしまった。“鍵”という今のところ最も重い言葉に対して、ついつい、見てしまった。
なんだ、アレ。
ロッカーの引き戸、少しズレてる。
血相を変えたマサカズは勢い良く立ち上がり、ロッカーまで駆け寄るとそれを引き開けた。そこには大きめの弁当箱ほどの大きさをした手提げ金庫が入っていた。だが、しっかりと閉ざされていたはずの鍵は力尽くで変形させられた挙げ句、強引に解錠されていた。金庫の中身を確かめてみたところ、鍵は六本入っていた。マサカズの行動を不可解だと思った伊達は、彼の傍までやってきた。
「一本、足りません」
もっとも聞きたくなかった報告に絶望して伊達は、浜口と寺西に振り返った。
「浜口さん、寺西さん。物理的なセキュリティに問題が生じました。泥棒です。自分と山田社長は今からその対応にあたります。本日の通常業務は現時点で終了。二人はここで帰ってください。草津さんへはこちらから連絡しておきます。もちろん、有休扱いにしますので。月曜日の出勤についてもこちらからの連絡を待ってください」
我ながら情報量を詰めすぎだと伊達は悔やんだ。案の定、浜口は眉を顰め困惑しているようである。すると、寺西が浜口の肩を人差し指でつついた。
「浜口くん。泥棒だって。今日はもう上がってくれって」
「け、けどよ。それなら俺たちだって容疑者になるだろ?」
「伊達さんは刑事弁護士だよ。そんな事とうにわかった上での指示なんだから、考えがあるんじゃないのかなぁ?」
帰り支度をしながら、寺西はのんびりとした口調でそう言った。浜口は細かく頷くと、「よっしゃ! 非常事態っつーこったな」と納得を言葉にし、伊達に歩み寄った。
「あのロッカーなんだよね。伊達さん」
「はい、そうです」
「なら、ひとつだけ心当たりがある。昨日なんだけど、夜にここまで引き返したんだ。お恥ずかしい話なんだけど、かあちゃんの土産をデスクに忘れてさ。そーしたら、雄大くんがいたんだよ。ロッカーの前でなんかごそごそしてて、アレ、朝のうちに帰ったんじゃねーのってさ。そしたら雄大くん、社長に頼まれていた忘れ物を取りに来たって言うじゃん、なにそれ? って聞いたら、鍵だっていうのよ」
浜口からの情報に、マサカズたちはあまりにも単純な結論に達するしかなかった。伊達は浜口に軽く頭を下げ唇を噛んだ。
「事務所の鍵が壊されていない以上、鍵の窃盗は雄大によって実行された。これは確定していい」
「今思えばですけど、なんで兄貴、きのう鍵の返却場所なんて聞いてきたんだろうと思いましたけど……」
老人たちを帰した事務所で、マサカズと伊達は互いの椅子を適当な場所に運び出し、向き合うように座っていた。
「雄大は盗んだ鍵を、次の動画でお披露目するつもりだったんだろう。もちろん、ヤツは鍵については無知だし、自分で発動させられるか半信半疑だろうが……いや、スペアキーの存在で……南京錠は持っているのか? いやいやいや」
天井を見上げた伊達は、煙草に火をつけた。マサカズは手をパタパタと払い煙を払った。
「伊達さんをしても兄貴はわかんないヤツですか?」
「読みが当てはまりづらい。優れた能力と愚か者のパーソナリティーが、なんとも言いがたい混ざり方をしている。だからこれ以上考えるのはやめて、次は状況について整理しよう。雄大は鍵を盗み、その帰宅途中か帰宅後、吉田たちに拉致された。しかし吉田は雄大が鍵を持っていることまでは突き止めていない。それが、あの写真の傷や火傷だ。雄大が動画で伝えた内容に対して、連中はいきなり“鍵持ってんだろ、出せよ”とは言わない。実はそれが一番近道なのに、だ。雄大に拷問し、動画の内容を執拗に追求したんだと思う」
「ちょっと待ってください。おかしいですよ」
「なにが?」
「だって、攫われた時点で兄貴は鍵を一本持ってるわけでしょ。あんなにボコられる前に、兄貴だったらとっとと鍵を渡してしまうと思います」
「逆転を狙っている可能性は? 鍵の力で、吉田たちを叩きのめす」
伊達の推測に、マサカズは両手で頭を抱えた。
「最悪だ……たぶん、南京錠とかまだ買ってませんよ。どう使うのかもわかっちゃいない。なのに、ポケットなんかにそれは入っている」
「雄大にとって今ごろ、おそろしい量の選択肢にパニックを引き起こしているかもな」
「今ごろ……」
マサカズは、その言葉に重苦しい違和感を覚えた。
「しかし、なんであんな手提げ金庫に保管した?」
「もっとちゃんとした金庫も注文したんですよ。けど、なんか途中で注文ミスのトラブルとかあったり、品不足とか色々と言われて……ちゃんとしたのは九月に届きます。けど、兄貴もよく開けられたな」
「あんなの、ベネズエラだったら五歳児でも目をつぶってバールでこじ開けられるぞ」
二本目の煙草に伊達は火をつけた。
「しかし、もうひとつ読めないのが吉田の動きだ。あの電話から半日経っているのに、なんの接触もない。人質を取っている以上、連中にとっては長期戦が一番の負担になる。正直な、事務所に切られた片耳でも送りつけられて揺さぶってくるんじゃないかとも考えていた。なんで、動きがない?」
二度ふかしただけで、伊達は煙草を灰皿に押しつけた。マサカズはゆっくりと立ち上がると、「昼飯買ってきます。そこのカレー弁当。何カレーにします?」と告げた。
食事は確かに大切だが、マサカズがなぜこのタイミングでこのような提案をしてくるのか、伊達にはわからなかった。
「僕はチキンカレーにオムレツをトッピングします。2辛で。伊達さんは?」
「なら、俺はシーフードカレー。3辛で」
「行ってきます。僕が戻ってくるまでに、伊達さんにお願いがあります」
三本目となる煙草を取り出した伊達は、背中を向けたマサカズに目を向けた。
「お願い? なんだ」
「落ち着いてください。伊達さんがそうしてくれないと、僕たちに勝ち目なんてありません」
兄の危機に対して、なぜこの弟はここまで落ち着いていられるのだろうか。似たような事案において、ひどく困惑し、取り乱し、感情を剥き出しにした者たちの相手をこれまでしてきた。それだけに、カレーを買いに事務所を後にしていくちりちり頭が不思議に思えてならなかった。
「井沢さんとすり合わせた方針を話そう」
その日の午後、夕日の差し込む事務所でマサカズと伊達は再び向き合っていた。
「今回はスピード重視だ。だから吉田に尾行をつけることにした。いずれ、そいつから連絡がある。いまはそれを待つしかない」
「吉田が落ち着いたところを襲撃するって感じですか? 鍵を取り戻さないといけませんしね」
「ああ、そして雄大の拉致先を聞き出す」
そう言われたマサカズは、顔を横に向けた。伊達はそれを軽い拒絶であると感じた。
「なんだ、マサカズ。さっきからお前、妙だぞ」
夕日を浴びたマサカズの横顔が僅かに引き攣った。
「もう、日没だ。もう、夜だ」
脈絡のないマサカズのつぶやきに、伊達はニコチンまみれの手で口を覆った。
彼はまだ、諦めていない。そして彼はもう、諦めてしまっている。
取り返さなければならない力を。そして、取り返しのつかない命を。
伊達はがっくりとうなだれ、「すまない」とくぐもった声で漏らした。
【無料版】第4話 ─鉄の掟を作ろう!─ Chapter8
ベランダに据え付けられていたジャグジーバスから一直線だった。一日の疲れを癒していた吉田はマサカズに頭を鷲掴みにされ、全裸のまま客室まで投げ飛ばされた。キングサイズのベッドに軟着陸した吉田は上体を上げ、金魚の様に口をパクパクと上下させ、何もわからぬひな鳥の様に頭を上げ周囲をキョロキョロと見渡し、両手で股間を隠した。時刻は深夜二時、街灯はベランダにいるTシャツとスーツ姿の二人の青年を穏やかに照らしていた。
この赤坂の一泊十万円ほどの四つ星ホテルに吉田が宿泊しているのを知ったのは、つい一時間ほど前のことだった。井沢の手下である猫矢という青年が尾行し続けた結果、得られた情報である。電話で連絡があった際、伊達は猫矢を労ったが、マサカズは尾行の継続を依頼してきた。意外に思った伊達がその理由を問うと、マサカズは「終わらない場合を考えたんです」と、解釈し難い返答が戻ってきた。
ベランダから客室に乗り込んだマサカズと伊達は、日付が変わる前から代々木の事務所で練ってきた策を、できるだけ素早く実行に移した。マサカズは目に入ったガウンを手に取ると、ベッドの上の吉田にそれを投げつけ、彼の胸を左手で押さえつけた。伊達は室内を歩き回り、衣類や鞄、ノートパソコンやスマートフォンなど、目に付いた吉田の私物を探った。
「なんでとか、どうしてとか。なしだよ吉田さん。あんたは今から僕たちからの質問に答えるだけ。それ以外を望むんなら、ローキックだ。うん、これは脅迫なんだ」
一度はガールズバーで力を示し、脅迫したこともあった。これは有効だろう。そんな想定をしていたマサカズに対して、吉田は関節の壊れた人形のようにカタカタと頷いた。
「なんであれから要求がない? 兄貴はどうなった? どこまで知った? これ、質問ね」
「あ、いや、その、あの」
「なに隠してるの?」
淡々とした様子のマサカズと怯えるばかりの吉田とのやりとりに、伊達は懸念を抱いた。
「マサカズ、その様子だと、説明したら自分に不利になる状況が発生しているはずだ。つまり、質問への返答には期待ができない」
「なら伊達さん、どうします?」
「こいつを使おう」
伊達は赤いスマートフォンを手にしていた。ベッドの吉田まで近づくと、彼はその通信機器を突きつけ、画面をタップして顔認証でロックを解除し、ホーム画面まで達した。まさか顔認証が通用するとは思っていなかった伊達は、吉田のセキュリティ意識の低さに辟易とした。
「どうせ、動画は撮っているはずだ。俺たちを脅すための材料をな」
吉田のスマートフォンを操作した伊達は、眉を顰め舌打ちをした。
「伊達さん、何か見つかりました?」
「マサカズ、今から俺はこの動画を見る。お前はどうする? 見るに堪えない動画だと思うから、俺だけが見て内容をお前に言葉で伝えるって方法もある」
「見ます。僕は見ないといけない」
「わかった。なら、吉田を頼む」
マサカズは吉田の胸板を押さえつけ、無理矢理仰向けにすると、伊達が手にしているスマートフォンに目を移した。そこには、ある動画のサムネイルが表示されていた。どこかの一室だ。昔のゲームで見たような、真横から捉えたアングルである。左側には黄色いスウェット姿の吉田が、右側には跪き、送りつけられてきた写真と同じ姿をした傷だらけの雄大の姿があった。
動画の再生ボタンを押す前に、伊達はあらためて吉田の様子を窺った。彼は唐突すぎる現在に対していまだ混乱しているようではあるが、自分に対して注意を向ける様子もない。
「自称吉田、俺は伊達だ」
井沢からの情報で、“吉田”が偽名であることは知っていたので、探る意味も含めてあえて“おまけ”をつけてみた。しかし吉田は震えて上ずった声で「ダテ? あ、ダテ?」と、唱えるだけだった。どうやら、この男は自分が見立てていたよりも総合的な能力はずっと低い。おそらくだが、ナッシングゼロのことも把握していないだろう。彼は特定した情報に基づき、対象への接触や拉致といった実行面においては有能ではあるかもしれない。しかしそれを発揮するのは単純なケースに限られる。つまり、情報をどのように手探りしてみるかの想像力には乏しい。レシピがわかっている場合、食材を集めるのは得意だが、料理からレシピを想定するのは不得手である。闇社会において、歪に特化したスキルだけでこれまで渡ってきた人間、と言っていい。しかも反撃の可能性があったのにも関わらず、屋外に面したジャグジーバスでのんびりしている様な間抜けだ。この男のパーソナリティを予め知っていれば、昨晩の行動も違っていたものになっていただろう。より迅速に隙を突き、被害を食い止めて事態を解決できたはずだ。伊達は端正な顔を歪ませ、歯ぎしりしながら動画を再生した。
「電話、出ないね。弟。どーしよ」
画面の中の吉田はそう言うと、革靴のつま先で兄の顎をすくい上げた。憔悴した様子の兄は返事もなく、咳と吐血を繰り返していた。吉田の背後には二人の男がいた。それはマサカズにとって見覚えがある、トシとケンだった。アングルは固定されたままで、登場人物の全てが横を向いている。それはまるで、テレビの舞台中継を見ている様でもある。マサカズは押さえつけている現実の吉田の様子をときおり窺いながら、画面の成り行きを注視した。
「お兄ちゃん、スケジュール言うね。いまからもっとラグジュアリーなお仕置きするからさ、それをね、弟に動画で送りつけるの。だってさ、仕方ないでしょ。お兄ちゃん、もう何もしらないっぽいし。そーしたら弟に鍵ってヤツをもってきてもらって、使い方教わるしかないもんね。お仕置きは、三十分にいっぺんのペースでやるから。どんどんグレード上がっていくから。そうだなぁ、最終的には社会復帰ムリって感じ? 弟さんの冷血度しだいだけどさ」
動画に映されていた吉田は饒舌であり、いつもの彼だった。マサカズは兄の様子に注意を注いでいた。彼は血を流し、震え、その命の灯は痛々しいほど儚げだった。
「マサカズ! ごめんな!!」
そう叫んだ兄は、もそもそと上体を揺らすと、結束バンドで拘束されていた両手をズボンのポケットに突っ込み、そこから小さな鍵を取り出した。トシとケンが慌てて兄に駆け寄ったが、彼は取り出した鍵を呑み込み、その場に倒れ込んだ。吉田たちは目の前で何が起こったのか全くわかっていないようであり、ただ戸惑い、踊るように兄の周りをただじたばたしていた。すると兄は大きく咳き込み、強く痙攣し、仰向けになって嘔吐を繰り返し、それは数十秒ほど続いた。なおも吉田たちは事態の急変に適切な対応ができていないようであり、じたじばたは続いた。やがて、兄は微動だにしなくなった。
「こっちが説明して欲しいぐらいなんだよ。なんなんだよ、これ!」
そう叫んだのは現実の世界にいる吉田だった。
「お前の兄貴がだよ、急に、急にだよ、なんか呑み込んで、ビクビクしてゲロ吐いて、死んじまったんだよ! 俺たちがやったんじゃねーよ、お前の兄貴が勝手に死んじまったんだよ」
吉田の弁明に対して、マサカズは彼の胸を押さえつけていた手の圧力を強めた。吉田は苦悶の表情を浮かべ、ベッドの上で胸部を固定されたままのたうち回った。画面の中ではトシが仰向けにさせた兄の胸を何度も両手で押し、蘇生を試みる様子が映し出されていた。
「おいおいおい、なんなんだっつーの! トシ、死んじゃってる?」
「ですね。これ、窒息してるっぽいっスね。ベロ出てるし」
「あーじゃーもーやめやめ、ケン、内藤さんに連絡して。これ、処理しねーと」
動画の中で吉田から発言された“内藤さん”という名前にマサカズは記憶を刺激された。それは歌舞伎町の事務所で登別が口にしていた、殺してしまった債務者の遺体を処理する業者のものと一致している。動画はそこで終わり、続いてハムスターがお尻を振る動画が連続して再生されたため、伊達はスマートフォンの電源を落とした。マサカズと状況の整理をする必要があるが、それより先にするべきことは、ベッドでのたうち回っているこの男をどうするかである。伊達はマサカズの目を見て、首を傾げることでそれを促した。マサカズは吉田を見下ろすと、身体を屈めた。
「吉田。兄貴は死んで、死体はおまえらが処理した、それでいいんだよな」
「はいはいはい。ちゃんと処理しましたよ」
「あのね、鍵の力って、これは僕だけが使える力なんだよ。実際、兄貴も鍵は持ってたけど、あんたらに屈して死んでしまった。僕以外使えないからなんだ。だから、あんたたちがどう足掻いてもムダだ。鍵の力を使いたければ、僕を味方にするしかないし、それはあり得ない。今度は栃木の実家を人質にする? それもムダ。だって僕はあんたらの電話にも出ず、実の兄を見殺しにしたんだから」
淡々と、マサカズは告げた。
「前にお願いしたよね。僕とあんたは出会う前に戻るって。けど、あんたは約束を破った」
「ど、どーなっちゃうんです? 殺す?」
「もう一度お願いする。今後、一切関わらないでくれ」
「もちろん、もちろん! お約束します」
「信じるわけないでしょ。なにこの状況? 繰り返すんでしょ? あんた懲りてないし」
「いやいやいや、こりごりです! 二度と絡みません!」
「嘘つけ」
マサカズは吉田から手を離すと、今度はその胸の上に座り込んだ。吉田は大きく咳き込んだ。
「嘘じゃないってことがわかるまで何度でもこうする。たぶん、あんたと僕はこれまでにないほど密接な関わり合いになるだろう……って、言ってる意味、わかんないか」
マサカズの宣言は、伊達にとっても理解し難い内容だった。今夜、伊達はいくつかの選択肢を用意していた。その中のひとつとして、マサカズが吉田に対してどのような復讐を果たそうとするかがあった。もし殺すということになったら全力で、それこそ使ったことがない鍵の力を以てして止める覚悟をしていたが、どうやらマサカズが至った結論は異なるようである。
「伊達さん、言ってましたよね。吉田みたいな輩はちょっとやそっとじゃ反省しない。刑務所でいじめられようが、リンチされようが、ほとぼりがさめればまた同じ悪さを繰り返すって」
「ああ」
「だから、これから鍵の力を使って、“ちょっとやそっと”じゃない体験をこいつにさせます。何日か会社には出られませんけど、いいですか?」
伊達はようやく、マサカズの意図を察した。吉田はこれから想像していない、“ちょっとやそっと”ではない仕置きを受ける。一歩間違えば死にいたる可能性もあったが、今はマサカズに任せるしかない。そんな結論に達した伊達は、大きく頷き返した。
朝になった。ベッドの上で糞尿を垂れ流し、すでに失神していた吉田からマサカズは腰を上げた。あと何回繰り返せば、この男から欲しい感情が得られるのだろうか。そして自分はいつまで自らの心を凍らせられるのだろうか。相談できる伊達には、いくつかのお願いをした上で先に帰ってもらったので、自問するよりほかに手立てはない。答えが出ないまま、マサカズはホテルのベランダに出て、マスクを被ると都会の喧噪に向かって跳ねた。
【無料版】第4話 ─鉄の掟を作ろう!─ Chapter9
「僕はこれから、こいつが僕たちのことを諦めてくれるまで嫌がらせをします」
土曜日の早朝、赤坂のホテルでマサカズはそう言った。ベッドにはガウンをかけられ、気を失った吉田が、そしてその胸の上にはマサカズがあぐらをかいていた。
「できるのか? そんなこと」
問うてみたものの、伊達は静かで落ち着いた様子のマサカズをすでに信頼していたので、これは単なる確認に過ぎなかった。
「鍵の力、使ってみます。あ、伊達さん、こういったタイプって、何が嫌なんですかね?」
「そうだな……格下の前で恥かかされたり……交際相手に危険が迫ったり……」
「あとでメールしてもらえます?」
「わかった」
吉田の処遇はマサカズに任せることにした。そして彼からの頼みで、井沢の配下である猫矢による吉田への尾行は継続されることになった。朝、ホテルを出た伊達は、それから今日の火曜日までの間、会社を有休日とし、自身はあらかじめ決めていた、こなすべき業務に取り組んでいた。吉田の嫌がりそうなことについては、これまでの経験に基づいていくつかのアドバイスを土曜日の昼までに送信しておいた。マサカズからは昼過ぎと深夜にメールが届いているが、その内容はあまりにも短く要領を得るのが難しかった。ただ、昨日の深夜に届いた文面には、「終わりました。吉田の件。明日の朝、出社します」と記されていたので、ともかく会って話を聞くべきだと考えた伊達は、定時十分前に事務所入りした。
「おはようございます。伊達さん」
すでに出社していたマサカズが、笑顔で挨拶をした。顔には疲労の色が滲んでいたが、精神的には穏やかさも感じられる。伊達はデスクから椅子を持ち上げると、マサカズが座っていた対面にそれを置き、腰を下ろした。
「おじいちゃんたちは?」
「俺が連絡するまで有休にしておいた」
「なら、明日から出社してもらわないといけませんね」
そう言うと、マサカズは手にしていたペットボトルのお茶を口に含んだ。
「つまり、吉田の脅威は取り除けたってことか?」
「たぶん」
「なにをしたんだ?」
伊達は懐からスマートフォンを取り出すと、メールの着信画面をマサカズに見せた。
「土曜の昼は“吉田気絶したまま。まだですね”。日曜の夜は“吉田、おもらししました。かなりキてます”。昨日の昼は“ストツー再現したんですけど、もうひと息ってところです”。そして、夜は“終わりました。吉田の件。明日の朝、出社します”だ。最後のはまぁわからなくもない。その確信の根拠は気になるところだけど……土曜から昨日まで、一体なにをどうしたんだ?」
「じゃあ、説明しますね。あ、その前に猫矢って人ですけど……」
「昨日の夜、連絡があった。山田さんから言われたんで、尾行を終了しますって」
「ああよかった。聞こえてたんだ。“吉田の尾行、終わってください!”って叫んだんですよ、山の中で。猫矢って人、凄いなぁ。あんなとこまでついてきてたんだ」
マサカズの言葉に頷くと、伊達は煙草とライターを取り出した。
「では、あらためて説明です。まず、土曜日については伊達さんがホテルを出たあと、一時間ぐらい吉田の上で座っていました。ベランダから出て、アパートに戻ってメシ食って寝ました。で、日曜日の昼、アイツが泊まっている大塚のホテルに行ったんですよ。あ、ここから吉田の居場所については、全部猫矢さんからの情報に基づいています。で、ホテルに乗り込んでアイツの頭を掴んで壁に押しつけました。で、ルームサービスでサンドウィッチを頼みまして、赤坂のと比べるとえらく安っぽいホテルだったんですけど、二時間ぐらい押しつけてたかな?」
「吉田の様子は?」
「すっごく驚いてました。なんでここがわかったんだ、とか、あと……もう二度と関わらないって泣きながら言うんですけど、僕は嘘だなって思いまして、その夜なんですけど、あいつがやってるガールズバーに行ったんですよ。そして、事務室からラウンジに引っ張り出して、四つん這いにしてその上に座って、コーラを注文しました」
伊達は吉田がどのような責めを受けているのか、その姿を想像しながら煙草に火をつけた。
「店は営業中?」
「ええ、店の女の子とかお客さんとか何事かって様子でしたけど、僕はいいから、いいからって感じでなだめすかしました。上手くいったかはわかりませんけど。で、しばらくすると吉田の部下とかも来たんですけど、いいから、いいからって感じで対応して、そしたら吉田、おもらししちゃったんですよ。そしたらみんな大爆笑で、アレは意外でした。なぜ笑うって感じで。あと、吉田はずーっと謝ってました。まぁ、嘘っぽいなって思いましたけど」
「マサカズ、お前、そういうことできるタイプだったんだ?」
「できませんよ。でも鍵の力があると思えばなんでもできちゃうんですよね。それと、あの兄貴の動画を思い出せば、まぁどこまでもひどいことができてしまえますね」
マサカズはそう言うと、右の足で床を軽く蹴った。
「そして昨日なんですけど、地下の駐車場で、吉田の目の前で、アイツのベンツをボコりました。あの、伊達さんが教えてくれたストツーのボーナス面の要領で。でもゲームと違って上手くいきませんね。アッパーとかじゃあんな綺麗な壊しっぷりってわけにはいきません。予め予告の電話入れといたんで、風呂に入ってた吉田がすっ飛んできたときには、もう完全に廃車って感じにはしちゃいましたけど。それで、猫矢さんからネタももらってたんで、次はお前のポルシェも同じようにするから、って脅しときました。吉田は、ずっと謝ってましたけど、嘘ですね」
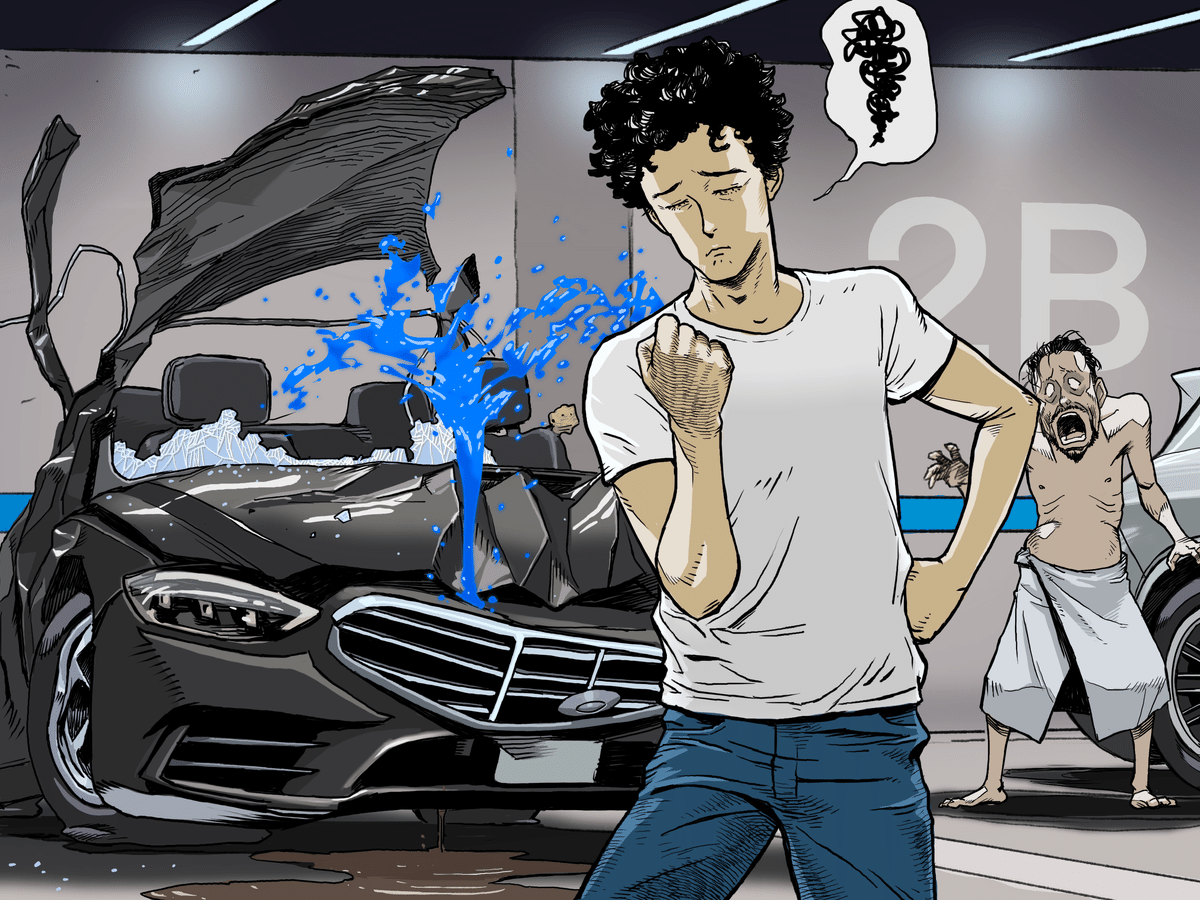
煙草をふかしながら、伊達はマサカズの話に興奮を覚えていた。吉田が嫌がることのアドバイスはメールしたものの、彼の実行内容はそれを超えて効果的だと思われる。こうなると、昨晩のとどめがなんであるのか興味は高まるばかりだった。
「そして、そして、きのうの夜です。まずはアイツの実家に行きました。大泉学園って、初めて行きましたよ。そこでちょいと拾いものをしてから、鶯谷のホテルにいた吉田を連れさらって、抱えて跳びました。吉田、ギャーギャー叫びましたよ。で、どこか適当な山奥の国道まで跳んで、なんかよくわからない橋みたいな、手すりぐらいの太さのとこに降りました。吉田と並んで座ったんです。細くてめっちゃぐらぐらとしてましたけど。で、大泉学園で拾ってきたヤツを見せたんです。小さくて可愛い老犬です。あれはパピヨンって種類だったかな? 吉田、ビックリして。僕はその犬を抱え上げて、下ではダンプとかがビュンビュン飛ばしてて、吉田は泣き出して、メリちゃんだったかな? 犬の名前を叫んで。吉田が高校生のころから一緒だった犬なんですよ。それを僕は撫でたり、高い高いしたり。そしたら吉田、あんな細いところで土下座して“もう嫌だ”って言ったんですよ」
「その言葉を以てして、お前は勝利を確信したってことか?」
「はい。嫌がられたんなら、まぁたぶん本当なんだろうなと思いました。僕はアイツに謝って欲しくなくって、嫌がって欲しかったんです。そのときわかったことなんですけど。で、メリちゃんと交通費を吉田に手渡して、猫矢さんに尾行の打ち切りを叫んで、アパートに戻りました」
マサカズの報告を受け、伊達は分析を進めてみた。しかし明確な結論は出ず、彼は険しい顔で煙草をふかし続けた。
「難しいな。お前の脅しは相当えげつないと言うか、不気味な領域に足を踏み入れてはいるけど、吉田の心にどれほどのダメージを与えたのかは……うーん、最後の老犬は確かになぁ」
「猫矢さんから電話で聞いたんですけど、吉田はお盆と正月は必ず実家に帰っているそうなんです。つまりはまぁ、メリちゃんにも愛着あるんでしょうね。親孝行ってタイプじゃありませんし」
「しかし、今後の逆襲がないとは言い切れないぞ」
「そのときは、また対応するだけです」
「わかった。しばらくは監視を続けよう。井沢さんに連絡しておく」
「煙草、一本もらえます?」
マサカズの意外とも言える申し出に、伊達は困惑した。
「吸わないんじゃなかったっけ?」
「なんとなく、どうなのかなって」
「そうか」
伊達は頷くと、マサカズに煙草を一本手渡した。
「親父や兄貴は吸うんですよね」
そう呟くとマサカズは煙草をくわえ、伊達はそれに火をつけた。マサカズは煙草を吸うと、肺に流入してきた煙の違和感に耐えられず、大きく咳き込んだ。
「ムリですね! 僕はやっぱり僕だ!!」
咳き込むマサカズの背中を、伊達はさすった。殺すことなく、怪我を負わせず、ひとまずだが敵を無力化した。このちりちり頭は、得た力を効果的に運用して目的を果たした。伊達は見込み以上の才覚に対して静かな昂ぶりを覚えていた。
【無料版】第4話 ─鉄の掟を作ろう!─ Chapter10
マサカズが自ら吸い込んだ異物に肺を刺激され、苦しく噎せた翌日の朝、Tシャツにデニム姿の彼は代々木の事務所で伊達と三人の老人、そしてひとつのモニターの前に立っていた。モニターには通院のため午前半休を取っていた草津の姿が映し出されていた。
「えっと、わたくし山田社長からみなさんに、お話があります。金曜日から今日まで会社をお休みにさせていた件とも関係があることです。僕の兄、山田雄大は金曜日付けで退職、クビにしました。従いまして、今後については彼がいない前提でお仕事を進めることになります。ここまでは、皆さんにとっても知っている話だとは思います。この機会に、もうひとつ踏み込んだ話をさせてください」
マグカップを手に取ったマサカズは、中の水をひと口含んだ。四人の老人たちへの説明は、昨日伊達と話し合った末に導き出した結論のひとつだった。それはマサカズにとって、先週末から起きてしまった事件の解決方法について、自分に対して今一度言い聞かせる意味合いも含まれていた。
「兄は、悪人でした。会社の機密を盗み、それによって深刻な被害を生じさせる可能性を生み、幸いにしてそれは防がれましたが、もう彼が僕たちの前に現れたり、メールをしてくることはありません。絶対に。永遠に」
抑揚に乏しく、淡々とした口調であり、弟が兄について語る内容としては乾ききった説明である。伊達は人差し指で眼鏡を直すと、次の言葉を待った。
「ごめんなさい。兄ということで、悪人だとわかっていたのに仲間にしてしまいました。被害は小さいものの、ここ数日、僕と伊達さんは彼のトラブルを処理するのに労力を費やすことになってしまいました。けど、もう終わりました。兄が押しかけてきた以前に戻ります。忘れてください。彼のことは。一番お勧めで簡単なことは、忘れてしまうことです」
「社長、雄大氏は今どうしているのですか?」
その質問は、伊達からだった。これも昨日、事前にすり合わせをしておいた想定問答だった。マサカズは彼の目を見ると、小さく頷いた。
「知りません。親族の僕でも連絡がつかない状態です。ただし、最後には僕への謝罪があったので、反省はしていたと思います」
言いながら、マサカズは昨日吸い込んだ流煙の違和感を思い出した。吉田のスマートフォンの中で見た兄は、確かに最後は謝っていた。そして、鍵を呑み込み呼吸を断たれ、命を落とした。小さな画面で繰り広げられた一連の断末魔がなにを意味しているのか、マサカズはそれをずっと考えていた。事務所に忍び込み、鍵を手に入れ、それを動画配信して世の中に情報として拡散しようとした。だがチンピラたちに攫われ、拷問を受け、なにも答えられず、最後に詫びた。鍵は手に入れたものの南京錠の調達は間に合わず、それでもなにか逆転の方法があると期待しながら、もしかすると兄は気づいたのだろうか。弟もこれまでに強烈な暴悪に晒され、それに立ち向かっていたことを。あの、情けない弟が。あの、頼りない弟が。手に入れた力のせいでならず者に目をつけられ、なにもかもを秘密として抱え込んでいた。だから「ごめんな」と、最後に叫んだのだろうか。そこまでの考えに至ったマサカズは、身体中が重苦しく感じ、関節が耐えきれなくなり、椅子に座り込んでしまった。
無意味だ。もう、兄はなにもない。なにもできず、なにも発することもなく、想像と記憶だけの情報でしかない。この辺りでもう止めてしまおう。自分に何かできたのではないのか。そのような可能性はいくらでもある。だから、これから先はやってはいけない掟を設けよう。それを考えることと引き換えに、あの鬱陶しく押しつけがましく、厄介で、威張り散らしていた兄のことを考えるのは止めよう。マサカズはマグカップの水を飲み干すと、軽く咳払いをした。すると、目の前には三人の年寄りが並んでいた。
寺西は個別包装された小さいチョコレートを、木村は水の入ったペットボトルをそれぞれ差し出し、浜口は口元を歪ませ、目を泳がせ、鍵盤を叩くように両手を細かく上下させていた。マサカズは笑みを浮かべ、チョコレートとペットボトルを受け取り、浜口に頷き返した。
「ありがとうございます。皆さん」
察してくれたのだろう。辛さは伝わったのだと思う。最後にモニターの中の草津に目を向けたマサカズは「それじゃ、今からいつも通りです。頑張りましょう」と、皆に告げた。
山梨での森林伐採は、細々とした辻褄を合わせることが必要であり、この日はその対応と対策が多くの時間を占めた。伐採時間、範囲といった規程について、鍵の力を秘匿とするために事実とは当てはまらないことが多く、保司の紹介してくれたいくつかの業者を通すことで、ぼんやりと、曖昧な形で当局からの追及が発生しないように誤魔化すことにした。マサカズは予定されていた通りの手順で、業者への発注書や受注書に署名と捺印をし、手違いがないように何度も確認をした。思えばあの深夜の木こりは、兄と自分が唯一同じ現場で稼いだ仕事だった。苦手な運転手を務め、虫に刺されながらも周辺の警戒をし、意識を失ってしまってからは業務の完遂までしてくれた。しかし、もうあの時点で兄の排斥は決められていた。全ては手遅れで、全ては無意味だった。おそらくだが、このロクでもない結果を防げたとすれば、三週間ほど前に事務所まで押しかけてきた兄に対して毅然とした態度で臨み、有無を言わさず転進させ、扉には固く鍵をかけ、あの野卑な笑顔を二度と目に入れないようにすることだったのだろう。マサカズは大きく上体を伸ばすと、定時を迎え事務所から出て行く木村や草津たちに「お疲れ様です」と声をかけた。
「すまない。マサカズ」
伊達はマサカズに頭を下げた。
「伊達さんが謝ることじゃないですよ。初手をミスったのは僕です」
「けどな、俺は今回の件で、いくつも判断ミスをした。雄大や吉田を見誤りすぎた」
「山田雄大は怪物です。伊達さんの手に負える相手じゃない」
マサカズの断言に、伊達は形のいい顎に手を当て、眉間に皺を寄せた。
「伊達さん、ルールを決めようと思うんです。これまで僕、ぼんやりと生きてきたって感じなんですけど、思えば鍵の力を手に入れてから、よくないことって全部ルールを決めてないから、曖昧にしてきたから起きてしまったと思うんです。だから、伊達さんにはルール作りを手伝って欲しいです」
「……また見誤りか。お前がそこまでしっかりと考えているとは思ってなかったよ」
「それこそしっかりして下さいよ伊達さん」
落ち着き払っている。デスクを挟んだマサカズがあまりにも静かだったので、伊達は踏み込むことにした。
「マサカズ、お兄さんがいなくなって、死んでしまったことに対して、お前の気持ちはどうなっているんだ? すまない、雑な聞き方をしてしまって」
伊達の問いかけにマサカズは天井を仰ぎ見て、ため息をひとつ漏らした。
「あー、なんでしょ。たぶんなんですけど、今すぐはムリって言うか、山田雄大になにも割きたくないんですよ。これ、自分でもひでーなって思ってるんですけど、アイツが死んだことを怒ったり悲しんだりするのも億劫というか、それって損だなって、ひでーな、ほんと。で、アイツのことなんかより、吉田さんの犬の方が心配で。だってもう二十歳とかですよ。可愛いし、これからも元気だといいなって。そんなこと考えてると、余計にどうでもいいって言うか……ひでーな」
マサカズはときおり何かを確かめるように、そう言った。伊達はネクタイを緩めると視線を落とした。
「すまない」
「その口癖、今日はもう聞きたくないです。それよりゲーセンでもバーでも、どっか行きません?」
マサカズは伊達を見上げ、腰を上げた。彼の感情は膨張しきっている。そしてそれを自覚もしている。破裂すれば深刻な後遺症を残すだろう。それがわかっているからこそ、今は鎮め方を模索している。伊達は相棒の心境をそう分析し、いまは彼の言いなりになるべきだと思った。
「わかった。新宿にいいゲーセンがある。メダルゲームとかキャッチャーとかもあるし、新しめのゲームばかりだから楽しめるだろう。ここからなら歩いて行ける。そのあとは呑みに行こう。歌舞伎町に気になるモツ焼き屋がオープンしたんだ。築地の老舗の支店だ」
早口でそう告げた伊達は、マサカズに背を向けた。お互い考えるのは明日からでいい。いまはひとまず、楽しいことで心を埋め尽くしてあげよう。伊達はリモコンでエアコンの電源を落とし、事務所の鍵を手にした。
メダルゲームというものを初めてやってみたが、ものの三十分で二千円もの資金が吸い込まれていった。伊達は「ただの不運だ」と言っていたが、マサカズは楽しさが微塵も感じられず、恐ろしさで震えるばかりだった。
そのあと寄ったモツ焼き屋では、ノンアルコールビールでモツの脂を流し込んだ。老舗の支店らしいが味は確かであり、カウンターで串を手にしながら、マサカズは眼鏡の後輩と呑んだ夜をふと思い出してしまった。伊達はビールの中ジョッキを四杯空け、今夜はサウナで一泊していくらしい。
マサカズは地元の小岩まで戻ってくると、家路に着きながら路地でスマートフォンを手にした。
「あ、親父、起きてた? ごめん、こんな夜遅くに。ちょっと、知らせておきたいことがあってさ。オレオレ詐欺じゃないって。携帯、新しいのに買い換えたんだよ。だけどナンバーは変わってないでしょ?」
栃木の両親には、どうしても知らせておかなければならないことがあった。だからこそ、今夜はアルコールを避けたマサカズだった。
「兄貴さ、会社から出ていったんだよ。あ、知らない? そうなんだよ。ちょっと悪さしちゃってさ、俺がクビにした。今どうしているかはわからない」
嘘を知らせる。そうするしかなかった。気がつくと、スマートフォンを持つ右手が震えていた。左手を添え、身を屈め、歯をガチガチと鳴らしたマサカズは、どうにか正気を保つことで精一杯だった。
「たぶん、たぶん、兄貴とはもう会えない。そう思っといて。なんで? なんでだろうね。俺にもよくわかんないよ」
電話を切ったマサカズは、考えるのを投げ出したかったため、路地に座り込んでしまった。「よくわかんないよ」小さな声でそう呟いた彼は、ブロック塀に背中をつけ、膝を抱え込んだ。湿気が身体を包み込み、ひどく不快ではある。ここからアパートまで五分とかからないが、それでも彼は動きたくなかった。集中して、考えることから逃げたかったからだ。すると、うなじを生暖かい雫が濡らした。アスファルトは瞬く間に雨で染め上げられ、夜空は稲光で白く転じ、雷鳴が鼓膜を乱暴にノックするように轟いた。不貞腐れてもいられない。マサカズは舌打ちをして腰を上げ、うんざりとした気持ちを抱えたまま、駆け出すしかなかった。
第4話「鉄の掟を作ろう!」おわり
【無料版】第5話 ─信じられる仲間を集めよう!─Chapter1
赤い帽子にオーバーオールのイタリアンと思しきそれが、真っ暗な画面で横向きに跳ねる。挙げられた拳は上層の床を震わせ、歩いていた亀が転倒した。すると白い帽子を被った、やはりオーバーオールが亀に接触し、それははじけ飛んでいった。
九月に入り、最初の日曜日になった。今日、株式会社ナッシングゼロは定休日だったが、二人の青年役員は仕事のため高田馬場のゲームセンター“エンペラー”を訪れていた。空調と幾重もの電子音がどよめきのように耳をくすぐる中、テーブル筐体に並んで座っていたマサカズと伊達は、二人の兄弟が亀や蟹と戦う古いビデオゲームに興じていた。
「マリオって、こんなこともしてたんですね」
マサカズの驚きに、伊達はうっすらと微笑んだ。
「ああ、これは最初に兄弟を冠にしたタイトルだ。だから兄弟で戦っていた。けどな」
伊達が赤い帽子のキャラクターを操作すると、マサカズの白い帽子は床から跳ね飛ばされ、歩いていた亀に触れると急に正面を向き、両手をバタつかせながら画面の底部へと落ちていった。それが敗北を示唆していることは明白だったため、マサカズは顎を付き出し、加害者である伊達を横目で見た。
「こうやって、足の引っ張り合いだってできちまうんだ」
「まるで、俺たち兄弟みたいですね」
マサカズの言葉を受け、伊達はゲームの選択を誤っていたと初めて気づいた。まだ一週間程度しか経っていないというのに、よりによって兄弟で殺し合いが成立してしまうゲームに誘うとは無神経にも程がある。伊達はジョイスティックレバーから手を離し、マサカズから顔を背けた。
「古っ! それって前世紀のゲームですよねっ!」
聞き覚えがあった。後ろから浴びせられた威勢のいい声に、マサカズは素早く振り返った。
声をかけてきた若い男は、Tシャツにデニムといった、マサカズと似たような出で立ちだった。腰にはスタジアムジャンパーを巻き、イエローのシックスインチブーツを履いており、痩せ型で足が長く、やや猫背である。チェックのハンチング帽を目深に被り、髪はあちこちが跳ね上がり、目は細く自然な笑顔が清涼感すら漂わせていた。マサカズは声の主が想像とあまりずれていない容姿だったので、彼が猫矢春平であると疑わなかった。
“エンペラー”を出たマサカズたち三人は、高田馬場の駅ガードを越え、神田川を見渡せる小さな公園までやってきた。時刻は正午過ぎであり、残暑の太陽は三人を容赦なく照りつけていた。確か、今日で何日か連続の真夏日だ。その記録がスタートする前日はやはり何日か続いた猛暑日だった。マサカズはその“何日か”をさっぱり記憶しておらず、そもそも興味自体がなかった。ただ、うんざりするほど“暑い”日が続いている。猫矢はリュックから茶封筒を取り出すと、それを伊達に手渡した。
「えーと、おやっさんってどーしてるんですか? その中に必要なことは全部記されちゃってますけど」
やや鼻にかかった声で、猫矢は伊達たちに尋ねた。
「“おやっさん”って、井沢さんのことか?」
「そーです、そーです」
「あの人だったら……そうだな、こういったケースの場合だと、書面の内容をざっくりと報告してくれることが多いかな?」
「でしたら……」
猫矢が話す内容を取りまとめようとしたところ、マサカズが割って入るように彼の前に乗り出した。
「キミが猫矢さんなんだよね?」
「にゃーん。その通りです」
「ほんと、こないだは助かったよ。吉田の居場所もばっちりだったし、ワンちゃんの件とか、重要情報も追加してもらえて」
「まー、仕事ですから」
内容こそ素っ気ないが笑顔のままだったので、マサカズの猫矢に対する印象は上ぶれしたままだった。
「尾行なんて、すごいよね。よくできるって思うよ。猫矢さん、井沢って人から教わったの?」
興味津々にそう尋ねるマサカズに対して、猫矢はベンチに腰を下ろし視線を向けた。
「実はですね、山田さんの尾行もしたことあるんですよ。俺」
質問に対しての返答ではなかったが、あまりにも刺激的な内容だったため、マサカズは興味を増し、猫矢の隣に座った。
「ヤバ、じゃあ僕の力のことも……」
「ローキック、こっそり見せてもらいましたよ」
マサカズと猫矢のやりとりがあまり有益ではないと感じた伊達は、二人の前に立つと仏頂面で腕を組んだ。
「猫矢、なんでキミなんだ? 井沢さんは?」
「おやっさん、このまま山田さんたちと関わったら判断が鈍って下手すりゃ地獄行きだって、だから俺が今後は窓口になれって……え!? じゃー俺はどーなってもいーのかよって」
そう言うと、猫矢はゲラゲラと笑い出し、足を上下させた。
「まー、おやっさんにゃ逆らえないから、いーんですけどね」
猫矢は手にしていたペットボトルのスポーツドリンクをごくごくと飲むと、口を拭ってマサカズとの間を空けた。
「じゃ、おやっさんみたく、概要について報告しますね。まず、吉田はフィリピンに逃げました。犬とハムスター連れで。理由は山田さんが怖いからです。それと、吉田の一連の動きについちゃ、池袋ドラゴンは噛んでません。吉田が二人の子分使って個人的にってやつです。まぁ、組織も吉田の逃亡の原因が山田さんだって把握してるっぽいですけど、いまあの界隈で山田さんに手を出そうってチャレンジャーは出てこないでしょうね。これは、俺じゃなくておやっさんの見立です」
吉田は土下座して、自分を拒絶した。しかしなおも国外へ高飛びをするということは、これ以上こちらから手出しをしないという信用がまったくないからだ。彼は稼業柄猜疑心が強いため、それも当然の判断だろう。マサカズは猫矢の報告を自分なりに分析していた。
「終戦……ってことか」
そう呟いた伊達は煙草の箱を取り出したが、マサカズの刺さるような視線を感じたため、それを再びジャケットのポケットに戻した。
「そう考えていいと思いますよ。ですんで、俺もお二人と会うのはこれで最後かもしれませんね」
猫矢はベンチから腰を上げると、左手首を軽やかに振りながら公園から路地に出て行った。伊達は入れ替わるようにマサカズの隣に座った。
「若いですよね。彼。下手すりゃハタチにもなってないかも」
「井沢さんはああいった手合いを何人か飼ってる。中でも猫矢はかなりいいスジをしてるって、井沢さんは言ってたよ」
「まぁけど確かに吉田絡みが全部終わったんなら、もう井沢さんとかのお世話になる機会も減るでしょうね」
「ああ、真っ当なビジネスを進めよう。でな、マサカズ、これは提案なんだが、そろそろスタッフを増やさないか? 正直なところ、事務職が足りていない」
「アレ? それこそ井沢さんに頼めばいいんじゃないですか? 猫矢さんみたいな人材、紹介してくれるかもですよ」
「“事務”って言っただろ? それにもう今後は非合法から距離を置くべきだ。俺たちは色々とその、やりすぎている」
「まぁ、吉田にやったこととか、普通に考えればどーかしてますよね。もちろん、どーかしてるのはあいつらが先ですけど」
「お前の力はもっとまともな使い道があるはずなんだ。モグリの解体業で終わるつもりはない。だから、それを実現するためにも、とにかく真っ当にいく必要がある」
「モグリの解体業、儲かりますけどね。保司さんもいい人だし」
「それに甘えてちゃいけないんだ。ズルズルと引きずり込まれて、取り返しが付かない沼の底まで一直線だ」
マサカズは膝の上で指を組み、背中を丸めた。沼の底には、おそらくあの大柄な兄が待っているのだろう。あの小さな後輩が足掻いているのだろう。膝まで頭を垂らしたマサカズは、「そうですね」と呻くように返した。
【無料版】第5話 ─信じられる仲間を集めよう!─Chapter2
これからは真っ当なビジネスを進めよう。怪しげな反社会的勢力とは関わりを持たず、鍵の力をもっとまともなことに役立てる。きのう伊達からそう言われたので、この月曜日から心機一転といったところで頑張っていこう。そう心に決めていたのに、いまの自分ときたらどうだ。これは真っ当と言っていいのだろうか。道場の磨かれた板の上で闘うために身構えていたマサカズは、こうなった結果について自分で決めたとはいえ、正しいかどうかまではわからなかった。
「オヤジは“空手を終わらせた達人”、と呼ばれていた。俺はいっとき絶望した。なら、俺はこれからどうすればいい? 否! 結論は我が拳のごとく神速だっ!」
目の前で、白い胴着を着た筋骨隆々とした彫像のような青年が構えている。対峙して数分が経っているが、さきほどからべらべらとよく喋る男だ。しかし、なにを言っているのかは心に染み込んでくれない。まるで雑音のようでもある。マサカズはデニムのポケットに入れた鍵を南京錠に差し込み、「アンロック」とつぶやいた。
「己の空手を始めればよいのだ! 雷轟流空手、第二章の幕開けだ! 自分は二代目館長として、己の空手道を切り拓く! 山田正一クン! キミへの勝利はその伝説の序章とさせてもらう!」
ツーブロックの髪は、いかにも今どきのスポーツマンといった印象であり、自信に満ちあふれた笑顔は彼の背後に立ち並ぶ胴着姿の青年や少年たちに、指導者としての信頼を振りまくスパイスとなっているのだろう。マサカズが左に注意を向けると、そこにはTシャツを着た入れ墨だらけの大男がいた。彼は表情に緊張を貼り付かせ、スーパー銭湯で襲撃してきた際の様子とは大きく異なる。初遭遇は自信に満ち、蹂躙する悦びが顔だけではなく細かな所作にまで顕れていた。それなのに今ここにいる彼は、ただただ事の成り行きを固唾を呑んで見守る雑魚の一匹に過ぎなかった。
「しかし……殺気の欠片も感じられん……瓜原! 本当に彼はキミを倒した男なのだよな!」
胴着の青年に促された瓜原は背筋と両手をヒンと伸ばし「間違いありません!」と、まるで従者のように即答した。
遡ること一時間ほど前、注文していた頑強な金庫が事務所に届き、伊達や老人たちと和気藹々としていたところ、インターフォンが鳴った。兄の来訪と追放をきっかけに、事務所にはモニター付きのインターフォンを設置し、扉も常に施錠を心がけていた。マサカズがモニターを確認したところ、アメリカの先住民族のような入れ墨面が飛び込んできた。反社会的勢力の暴力を代表する、それはマサカズにとって忘れようもない顔だった。真っ当ではないトラブルの発生を予期し、どう対応しようか考えあぐねたが、瓜原の態度はあくまでも腰が低く、何かを嘆願しているようでもあった。そして、その背後にいたのが、いま板の上で対峙しているこの青年だ。彼は真山稲魂と名乗り、なにやら有名な空手家らしく、伊達もその存在を知っていた。事務所のドアを開け、一応は招き入れたところ、真山はこう言った。「地下格闘技界の帝王、瓜原を一撃で倒した山田クンとお見受けしたっ! 私は雷轟流空手二代目館長、真山稲魂! ひとつ私とお手合わせ願えんかね?」と。
事情がわからず困惑するばかりのマサカズに、瓜原は「こっちの業界じゃザワついてるんスよ。ワイを返り討ちにした素人の山田ってどーなんだって? あんさんと戦って勝ったらワイより強いってことになって、それってウチの業界じゃ勲章になるんスよ」と説明したのだが、マサカズはますます迷路に入り込むばかりで、ともかく最短距離を探ってみたところ、要するに美術の時間にデッサンされるような、この屈強な青年と戦えば、いくらか疑問も解決するのだろうとの考えに至った。
しかし、この狭い事務所で試合ができるはずもない。そのような事情を説明したところ、市ヶ谷に本部道場があり、立会人も揃っているのでそこで戦おうと提案してきた。当然のことながら伊達は反対してきたが、解決方法は実に単純かつ迅速に行えると思われたので、マサカズは伊達を説き伏せ、真山の高級な国産のセダンカーに乗せられ、市ヶ谷の道場まで連れてこられ、この現状に至っていた。
伊達が反対する理由はよくわかっていた。空手家との果たし合いなど、きのう誓い合った“真っ当”な路線からは脱線している。だが、反社会的勢力との関わりと比べれば、目の前で身構えるこの青年はまだ“まとも”だと思われ、実際にこの道場にやってきた際、胴着姿の門下生が一斉に頭を下げ、「押忍!」と挨拶をしてきて、その中に小学生ほどの子供たちが交じっていたため、安心感も湧いてきた。問題は、この奇妙な状況にどのような落とし前をつけるかである。これまで、猛者と呼ばれる者との戦いは瓜原の一戦のみである。瓜原の態度から察する限り、真山という青年は瓜原より格上の格闘家だと思われる。そうなると、自分を倒して勲章を得るとすれば真山が目指すのは圧勝という結果だけだ。空手というもの自体がよくわからないが、確か打撃のみを追求しているはずなので、掴みかかってくることはないだろう。鍵の力は動体視力を向上させる付与がなかったので、彼の突きや蹴りを捉えることは不可能だ。だとすれば、当てさせてみて反応を窺い、そこから考えよう。マサカズが考えをまとめた刹那、真山のそれと思しき拳が顔面に迫ってきた。無論、反応することなどできず、マサカズは棒立ちのままだった。その正拳突きは頭部に衝撃を与えることもできず顔面を滑り、バランスを崩した真山はなんとか立て直し、再び構えた。
「あー、殴られた場合ってこうなるのか……真山さん、びっくりしたでしょ? 僕にはなんも効かないんですよ。なんか、そんな才能に目ざめ……」
説明が終わらぬうちに、真山はマサカズに蹴りと突きを次々に繰り出した。三発、四発と続き、それはやがてラッシュとなった。真山はときおり間合いを取り直して直立したままのマサカズを打ち続け、それは時間にして一分ほど続いた。必殺の打撃はことごとくがマサカズの身体を滑り、なんのダメージをも与えることができなかった。迫り来る拳や足先に晒され、これまでに聞いたこともない空気を裂く鋭い音は伝わってきたが、痛みや圧力はまったく感じることができなかった。マサカズはちりちり頭をかきたくなったのだが、かけ声を上げ攻めてくる真山の真剣な様子や彼を見守る人々の期待を込めた圧力を感じたため、それが失礼にあたると思ったので我慢するしかなかった。
永きに亘る空振りに真山は呼吸を激しく乱し、足元はぐらぐらと揺れ、額からは滝のように汗を流し、なによりその顔は青ざめ、唇をとがらせ苦悶しているようにも見えた。マサカズは、まだ頭をかけないままでいた。
「えっと、僕はここに突っ立ったままです。で、これなんですけど、真山さんがいくらオラオラやっても変わりません。どうします? サンドバックが欲しいんでしたらまだ立ってますけど? まぁ、僕としてはハッキリいって嫌なんですけど。社長業もありますんで」
「なぜだっ! どう見ても鍛練を積んだ肉体とは思えん。なぜ我が武が通じん! この突き、この蹴り、決して一朝一夕ではない! 人生の全てを懸け、無心で打ち込み精度と破壊力を向上させてきたのだ! 幾人もの強者を屠り、ついにはオヤジに“稲魂ぁ……ついにお前の武が、始まっちまったなぁ”とまで言わしめた技だ! なぜそれが、このような者に通じんのだっ!」
真山は目に涙を浮かべていた。状況の理解のしがたさを、彼は落涙で鎮めようとしているのではないだろうか。そう思ったマサカズは理不尽な体験をしている真山がいささか哀れに思えた。
「ごめんなさい! 真山さんがすっごく努力しているのって、よくわかんないけどわかります。強そうだし、なんかちゃんとしてますし、打撃も全然見えませんでしたし。僕のコレは病気みたいなものなんで、あー、あなたはいま……アレ、いい喩えが出てこないな。とにかく、これは事故みたいなものです。ここだけの話なんですけど、僕の身体は拳銃の弾も平気なんです。だから諦めましょう。僕に何をしてもあなたが得られるものはありません」
「しかし……」
そう呟いた真山は、深呼吸をして両手を胸の前で交差した。素人のマサカズではあったが、それが防御を意味する構えであることはなんとなくだがわかった。
「山田クン、来なさいっ! 瓜原を一撃で葬ったというキミの体当たり、ナナハンのバイク並と言わしめたそのタックルを、受けてみせようぞ!」
「だ、だめですよ! 怪我しちゃいます!」
「雷轟流に後退という文字はないっ! きたまえ!」
「だ、だからムリですって、吹っ飛びますよ。ねぇ、瓜原さん」
マサカズに制止の補足を求められた瓜原は、口をあんぐりと開け、困り果てた様子で首を細かく横に振るばかりだった。
「ほら、どうした! 私が怖いか? 恐ろしいのか?」
脈絡としてはなんとも不可解な焚きつけの言葉だった。しかし、語彙が混乱するほど彼は追い詰められているのだろう。それは、この奇っ怪な状況を見守る門下生たちに対して、指導者としての面子を保つためなのか、それとも彼個人が武道家として落とし所のつけ方を模索しての結果なのか。マサカズは考えてみたが、あまりにも自分とは立場が異なる真山がなにを目論んでいるのかわからなかった。とうとう茶番の様相を呈してきたこの状況に幕を下ろす必要がある。自分とて暇ではないのだ。早く事務所に戻って署名捺印といった“真っ当”な仕事をしなければならない。
「わかりました。じゃーいきますよ!」
「すまん! 全力、フルスロットルでお願いしたい!」
真山はそう要求してきたが、そもそも恨みもなく、怪我をさせる理由もない相手である。マサカズは頭をひとかきすると、できるだけ勢いがつき過ぎぬように心がけ、一気に踏み込んだ。マサカズの右肩は真山の交差した両腕に僅かに突き上げる角度で衝突し、その巨体は軽々と弾き飛ばされ、縦軸に何度か回転して壁に叩きつけられた。逆さまになり、両手をだらりと伸ばした真山は脳天から床に崩れ落ちた。威力の調整を失敗した。マサカズは慌てて真山に駆け寄った。
「ごめんなさい! ごめんなさい! 大丈夫ですか?」
目は虚ろだったが、真山は意識を失ってはいなかった。門下生や瓜原も彼を囲って見下ろし、真山は深く息を漏らしながら彼らを見渡した。
「瓜原、今のタックル、どうだ?」
「ワイのときと一緒っスよ! スーパーウルトラレアタックル!」
「そうか……これが、それか……ふふ……右も左も折れたな……アバラも何本か持っていかれた。しかし今の一撃を知ることにより、我が空手道は更なる高みを目指せるというものだ」
「ですよねー」
真山と瓜原のやりとりを見ているうちに、罪悪感は薄れていった。マサカズは何も告げず、門下生たちの注目を一身に集めたまま、道場を後にした。
その日の夜、仕事を終え小岩駅まで帰ってきたマサカズは、駅のショッピングセンターにある合鍵作製の専門店を訪れた。
空手の達人らしき人物から戦いを挑まれる。想定外の出来事だった。今後も鍵の力を巡って何が起きるか予想もつかない。ありとあらゆる事案に対して備えが必要だ。例えば、自宅のアパートに今日のような挑戦者が押しかけてくる可能性も考えられる。そう考えたマサカズは、手持ちの鍵の複製を依頼した。万が一に備え、自宅にも鍵を一本備えておくためである。帰路の電車内での思いつきだったため、伊達には電話でこの旨は伝えておいたが、彼はこのアイデアに対してあまり乗り気ではない口調だったような気がする。それでも賛同してくれたのは、今日のトラブルをすべてひとりで解決したからであろう。鍵ができるまで少しばかり時間がある。マサカズは真山の骨が粉砕される音と感触を思い出しながら、行きつけのラーメン店に向かった。
【無料版】第5話 ─信じられる仲間を集めよう!─Chapter3
七月の創業以来、マサカズは作業現場で解体業や運搬業の実務を担当し、それ以外の時間は代々木の事務所で、役所や取引先に提出する公的な書類の署名捺印に追われていた。そしてなおも余裕があると判断した場合、マサカズはビジネスパーソンとして不足していると思われる様々な知識を、ネットを駆使して精力的に学んでいた。税金にまつわる根本的な考え方や、商取引において関係してくる法律についてなど、調べるほどにマサカズは己の無知を思い知らされていたが、確実に知識を得られている、といった実感もあり、勉強は苦労より充実感から生まれる喜びの方が大きかった。
一方の伊達は主に営業を担当し、全国の企業や官庁に足を運び、マサカズの鍵の力を秘匿にしながらもその絶大な遂行能力をアピールしていた。従って伊達が代々木の事務所に滞在している時間は限られていたのだが、その出勤スケジュールとは反比例したボリュームの事務仕事を彼は背負っていた。雑務については四人の老年スタッフに任せることができたのだが、企画書や提案書の作成や、業務に対しての許可や補助の申請にはどうしても鍵の秘密に抵触する部分があり、伊達とマサカズしか担当することができない。しかしマサカズはまだ経験が足りておらず、おのずとその負担は伊達ひとりが背負うことになっていた。明らかなるオーバーワークは連日に及ぶ定時外労働を生じ、伊達はここ数日ほど日付を跨いでの退社となっていた。
事務スタッフの増強は株式会社ナッシングゼロの急務となっており、まずは自社のWebサイトで求人を募ることにした。
急募! 事務スタッフ 新宿近辺の職場 服装は自由 PCに文字を入力するだけ
世の中の役に立てる事業を展開中の発足間もない会社です。人を助けたい。世の中のために貢献したい。そんな夢を共有できる方を求めています! 夢の実現に向けて、共に歩んでいける仲間を求めています!
業務内容はカンタン! PCに文字を入力するだけ! 誰でもカンタンに収入を得られるチャンス!
ただし、会社の秘密は必ず守っていただきます。
月給20万円以上 経験者優遇
勤務時間9:00〜17:00 休憩1時間 土日祝休み
以上の内容をサイトに追加したところ、待てど暮らせど応募の連絡はまったくなかった。ネットワーク担当の草津によると、会社のWebサイトへのアクセスは一日あたり一桁台であり、そもそも求職者へリーチする母数自体が僅かなものでしかなかった。マサカズの判断で求人ページ自体はそのまま残すことにはなったのだが、次の手を打つ必要があった。マサカズと伊達は四人の老人たちにも相談を持ちかけ、その結果、できるだけ審査のハードルが低く、即時掲載ができるいくつかの求人サイトや、フリーペーパーといった媒体への露出を試みることになった。
「応募、来ると思います?」
定時を過ぎ、ひぐらしの音が漏れ伝わる事務所で、マサカズは隣のデスクの伊達に尋ねてみた。しかし煙草をくわえた彼は返事をせず、仏頂面を横に振った。
「いい条件だと思いますけどね。あ、でもアレか、今度入る人には鍵の秘密を教えるんですよね」
「そうだ。でないと新しく集める意味がない」
「となると狭き門ですよね。よっぽど人間ができてないと務まらない」
「だから焦ってるんだよ。狭き門を叩いてくるのが行列を作ってるのなら問題ない。よりどりみどりだ」
「さびれたラーメン屋みたいなのだと、ちょっとヤバいですよね。客選んでる場合じゃないって感じで」
「致命的な問題もあるんだよな」
伊達は三本目になる煙草に火をつけた。
「普通、求人の場合一番手っ取り早いのは青田買いだ。まだ学生の連中を勧誘する」
「やりましょうよ、それ」
「ムリだ」
「どーしてです?」
「青田買いってのはな、事業内容に関連した大学や高校、専門学校とパイプを作ったうえで行うものだ」
「作りましょうよ、そのパイプってのを」
「“事業内容に関連した”」
伊達は強い口調で改めていい放った。その意図をマサカズは考えてみたが、すぐには答えは出なかったため、伊達に向けて困った笑みを向けるしかなかった。
「例えばだ、自動車修理工場だったら工業高校だ。レストランなら調理師専門学校。ゲーム会社なら……なんかよくわからないけどその手の専門学校だ。じゃあ、ウチは?」
「解体業だから……工業高校?」
「ギリ正解だけどさ、そもそもモグリ業からは距離を置きたいわけだ。そうなると、ウチはなに業に該当する?」
「人助け業……世のため人のため業……」
言ってみて、マサカズの笑みは引き攣ったものに移り変わった。
「あるかよ、そんなの専科にしてる学校なんて」
「たしかに……」
それから一週間が経ち、九月も半ばに差し掛かろうとしていた。フリーペーパーの掲載結果が出るのにはまだ時間が必要であり、求人サイトについては五件の問い合わせがあったものの、そちらに応募してくる者たちは、総じてコミュニケーションスキルがあまりにも低く、伊達の判断によって、書面選考にまで辿りつけない状況となっていた。
今日、マサカズと伊達は新宿区四ッ谷にある『東京都事業支援センター』という公共機関の事務局を訪ねていた。時刻は午後三時になろうとしていた。
「この書面だと、ウチでは受理できませんね」
応接室でマサカズたちと対座したスーツ姿の太った中年の男はそう言うと、テーブルの上の書類を二人に差し戻した。それはこの事務局が主催する合同企業説明会という、企業が学生に向け求職相談を受けるイベントの申込書類であり、伊達の指導のもとマサカズが記載したものだった。Tシャツ姿のマサカズはテーブルの縁を掴み、身を乗り出した。
「どーしてです? 全部ちゃんと書き込みましたよ」
「課内で話し合った結果です。おたくは条件に適っていない」
「説明になってません。なにがどう悪いんです?」
「個別の案件について、当方では説明できません。とにかく、御社は我々が主催する今回の合同企業説明会には参加できかねます。次回、またご応募いただけましたら再度検討いたしますので、本日はお引き取り願えますか?」
「次回またって、次回も同じ書類にしかなりませんよ? まぁ、資本金は増えているかもしれませんけど」
「お引き取り、願えませんか?」
わざとらしく大きく首を傾げて男はそう告げた。伊達はマサカズの肩を掴み身体を引き戻させると、眼鏡を人差し指で直した。
「事業実績と事業内容が怪しげで問題視されたんですね。最近じゃこういったカタギの場にも反社が紛れ込んで求人勧誘をしているって話も聞いたことがあります。創業して間もないうえ社会貢献だの謳い、具体的な業務内容を提示しない弊社を、そういった連中と同様だと判断した。そんなところですか?」
淀みなく、若干の早口で伊達は指摘した。男は顎を引き、上目遣いで伊達を見つめた。この無言は同意である。伊達はそう理解し一定の満足を得ると、書類を手にして腰を上げた。
事務局のビルを出た二人は、自動販売機で冷たい飲み物を購入した。
「お茶も出さないなんて、よっぽどですよね」
コーラをひと口飲んだマサカズは、そう毒づいた。伊達はコーヒーを飲むと、表情を曇らせた。
「それこそな、ワンチャンいけるって思ってた俺が甘かった」
「要するに、ウチが怪しげでヤバめって思われてるってことですよね。世間からも国からも」
「ああ、そうだ。こうなると人材確保はいったん諦めるしかないな」
「そーゆーわけにもいかないでしょ。伊達さん、昨日も深夜コースだったんでしょ?」
「もちろんこれ以上のムリはしたくないしできない。だから人手を増やす以外に、事務負担を軽減させる手を考える必要がある」
「ごめんなさい、僕が使えないヤツなばっかりに……」
「それは最初から織り込み済みだし、吉田のことやこないだの真山の件だってそうだけど、お前は俺の想像以上に不測の事態に対処、対応をしてくれているよ。だから気にしないで長所を伸ばしてくれ」
「鍵のこと、アピールできれば違うんでしょうけど……なんか、ますます秘密結社って感じですね、僕たち」
「実際そうだからな」
「あ、やっぱりそうなります?」
「ナッシングゼロは、世のため人のための秘密結社だ。俺はそう認識している」
「でもそれ自体を人に説明できないのって」
「辛いな。まったく」
マサカズは、コーラを一気に飲み干すと炭酸の刺激に喉を詰まらせてしまい、咳払いをした。
「さーて、今夜は頑張りましょう。えっと、どこの山でしたっけ」
「神奈川の西の方だ。出発は夜十時。事務所から向かうぞ」
保司からの依頼で、今夜は倉庫の解体業務が入っていた。免許もない、人には言えないいわゆるモグリの闇仕事である。マサカズにとって秘密結社とは、日本征服を目的としてテロ活動を行う浮世離れした存在しか連想できなかったので、この身の丈に合っているにも関わらず非合法を生業としている現状は、どうしても馴染みがたく、居心地の悪さを感じていた。
【無料版】第5話 ─信じられる仲間を集めよう!─Chapter4
九月も残り十日となった。この一週間で二件の解体仕事を行い、経営自体は黒字だったのだが、マサカズは不安を募らせていた。その原因の全ては伊達にあった。目は落ちくぼみ、顔の輪郭はより鋭くなり、定時内でもうっかり煙草を吸うこともあり、電話口で怒りを顕わにすることもあるなど、彼は明らかに焦燥感を隠しきれない様子だった。“真っ当”な路線が何の成果も挙げられていないのがその原因だと思われる。伊達は公的な機関へ営業の働きかけをしていたのだが、連絡した段階で断られることが全てで、門前払い以前の段階で足踏みをさせられていた。マサカズは何度か助力を申し出てみたのだが、伊達は都度断り、食い下がってみたところで反論が正論尽くめであり、確かに自分が手を貸せる能力には達していなかった。
ならばせめてということで、マサカズは自分のできることを増やそうと励んだ。たった二日だが教習所でオートバイの操縦方法を学んでみたり、事務所用に自転車を購入し、老人たちが欠席の際の雑務をこなせるようにしたり、手段を増やして伊達の煩わしさをできるだけ軽減することに務めていた。このままだと伊達は体力だけではなく、気力も摩耗してしまう。不安はしだいに懸念、危機感に膨れあがり、マサカズは伊達の負担を少しでも減らせないものかと、懸命に試行錯誤していた。
「マサカズ、明日の夕方だけど、俺と付き合ってもらえるか?」
やつれ顔の伊達は、昼下がりの事務所で隣に座るマサカズにそう尋ねた。
「いいですけど、何です?」
「柏城法律事務所だ。俺の古巣。そこに行くのに付き合って欲しい」
「なにしに行くんですか」
「オヤジに人脈を頼ろうと思う。できれば公的な繋がりが作れればと思ってさ」
「“オヤジ”って、所長さんでしたっけ?」
「そうだ。俺の師匠だ」
「えっと、僕が同行するのって、勉強のためとか?」
「いや、まぁそれもそうなんだけど、オヤジがマサカズに会いたいって話なんだ」
マサカズは腕を組み、頭を傾けた。
「“なんで?”って顔だな」
「なんで? ですね」
「人脈紹介するのなら、お前の雇い主を値踏みさせろってところだろうな」
「いやいやいや、弁護士の大先生になんて、僕、ボロしか出ませんよ? 無知の負け組ですし。行かない方がいいんじゃないですか?」
「行かないなら、紹介自体がなくなる」
伊達がそう返すと、木村が挙手して席を立った。
「逆に言えばですよ、副社長の師匠は社長の出席を条件にしたってことは、お眼鏡にかなった場合は人脈の紹介は確実ってことになるんじゃないですか?」
「その通りだと思います。というわけで、明日は頼んだぞ、マサカズ」
久しぶりに、彼らしい不敵な笑みを向けてきた伊達に、マサカズはちりちり頭をかいた。
「服装とか、どーします?」
「今さら形から入っても仕方ない。いつものそれ」
伊達は顎をくいっと上げた。
「そのTシャツとジーンズでいいだろ。明日も暑いって予報だし」
「いいんですか?」
「若手社長っぽいと思うぞ。俺も明日はお前に合わせてラフな感じでいく」
やつれてはいるものの、伊達の様子がいくらか楽しげであると感じたため、マサカズは明日のイベントを気楽に挑むことにした。
無理だ。気楽にできるはずもない。ただ緊張して強張るだけだ。柏城法律事務所の応接室で、ソファに座っていたマサカズは震える手で湯飲みを手にした。隣にいたポロシャツ姿の伊達は、横目でその様子を見て、ため息を漏らした。
「ここに来るのは初めてじゃないだろ? リラックスしろ」
「いやだって、前に来たとき相手してくれたのは伊達さんだけだったじゃないですか? 所長さんってどんな人なんです?」
「いま聞くか? すぐに来るのに」
「そうですけど……」
マサカズが言いあぐねていると、応接室の扉が開き、クリアファイルを手にした初老の小柄な男が入ってきた。三つ揃いのスーツは伊達がいつも着用しているそれと同じく灰色で、人相は穏やかでもあり険しさもあるようで、マサカズは捉え所のない印象を抱いた。伊達が立ち上がるとマサカズもそれに倣った。
「ご無沙汰してます。所長」
「えっと、初めまして。ナッシングゼロの代表の、山田です」
伊達に続いて挨拶をしたマサカズは、名刺を差し出した。柏城はそれを受け取ると、自分の名刺をマサカズに手渡した。伊達も名刺を柏城に差し出し、便宜上の挨拶は淡々と済まされた。ソファに着いた三人の中で、真っ先に口を開いたのは柏城だった。
「ホームページ見たぞ。ナッシングゼロ。なにしてんだ?」
極めて抽象的な問いだとマサカズは感じた。伊達は少しだけ前屈みになると、膝の上で両指を組んだ。
「まだなにもしていません。どうやら自分の能力を過信していたようで、これまでの経験や人間関係を利用してみたところ、成果はまったくと言っていいほど上がっていません」
「あ、でも伊達さんは立派なんですよ。凄い量の仕事をこなしてくれてますし、なにもしてないなんてこともないです。実際黒字で利益は出てますから」
マサカズの咄嗟のフォローに、伊達は軽く驚き目を向けた。柏城は小さく微笑み、顎を引いた。
「山田さん、その黒字はどうやって稼いだんですか?」
「あ、秘密です。企業秘密です」
「なら、別段困ってることもないと?」
「いえ、困ってます。いささか説明が難しい稼ぎ方をしているものなので」
「では、誰にでも説明できるシノギが欲しいと? だから私を訪ねてきた?」
「あ、いや……誰にでも説明っていうのは、ちょっと難しいですね。ただ、秘密を共有できる対象のスケールを、もっと大きくしたい……で、合ってますよね?」
マサカズに問われ、伊達は大きく頷いた。柏城はゆっくりと身を乗り出し、マサカズを睨みつけた。
「俺の人脈を巻き込みたいってことか?」
柏城から圧力を感じたが、マサカズはここが最も大切な場面だと思ったので、身じろぎすることなく睨み返した。
「その価値はあります。根拠は秘密ですけど、自信を持って言えます。これは、人類にとって大きな利益を生む力です」
言い切りながら、マサカズはくるくると回転した真山を思い出していた。いまの彼は、並大抵の圧迫には怯まない心の強さを得ていた。柏城も気圧されることなく、抗じる態度を崩さなかった。
「その利益は、弱い連中を救えるのか?」
「わかりません、そんなこと。ただし、全体を救うことができる力を僕は持っています」
柏城は伊達に視線を移した。伊達は何度も頷くと、柏城は身体を引き戻し湯飲みを手にした。
「伊達、頑張れよ」
唐突な激励の言葉に、伊達は戸惑った。柏城は茶をひと飲みすると湯飲みを置き、テーブルの上のクリアファイルから一枚のコピー用紙を取り出し、それを二人に差し出した。
「法務官僚の庭石って男だ。昔、検察官時代に俺がいくらか世話をしてやった。いまじゃ課長だから、交渉しだいでいい案件が紹介してもらえるだろう」
名刺がコピーされた紙を手にした伊達は、興奮を抑えきれず口元を歪ませた。
「庭石には俺から予め連絡しておく」
「ありがとうございます、所長!!」
伊達の感謝に、柏城はすました顔をしてやりすごした。
法律事務所を出た二人は、駅に向かって夕暮れの路地を歩いていた。
「法務省の課長さん……なんか、よくわかりませんけど、凄い人紹介してもらえたってことはわかります。なんとなくですけど」
低いトーンでそう言ったマサカズに対して、伊達はまだ昂ぶりが醒めてはおらず、震える手を見せつけた。
「上出来すぎる成果だよ! どう考えてもお前の手柄だ。オヤジ、お前のこと気に入ってくれたんだよ。クリアファイルにはまだ何枚か紙が入ってた。おそらく、オヤジの中でもとびきりの人脈を紹介してもらえた」
「手柄って……伊達さんが謙遜しすぎだって思ったんですよ。実際、解体業は僕が実務を担当してるわけですし、その凄さとかってわかってるつもりです。あんまり控えめにしてもよくないかなって」
「そーなんだよな。やっぱり実際にやった人間にしか説得力が出せないってことだ。それがよくわかったよ。それに、弱者救済に対して“わかりません”って、普通できる返事じゃないぞ」
「だって、実際にそうじゃないですか。僕、葵さんも救えなかったし」
重い言葉だったが、伊達はマサカズへの評価を霞ませたくなかったため、前向きな気分を保つことにした。
「素直なんだよな。マサカズは。それがオヤジのお眼鏡に適ったってことだ。正直なところこれは最後の手だったんだ。本当によくやってくれたよ」
「うーん、成功した原因が僕にはよくわかりません。けどまぁ、結果オーライってことですかね」
「そう、お前はこれからもこんな感じでいてくれ。俺ももっとお前の活かし方をよく考えてみる」
評価されること自体は悪い気がしない。マサカズはようやく晴れ晴れとした気持ちになると、空腹を感じた。
「高田馬場の美味しいお店とか知ってます? ぼち夕飯どきですし」
「おう、ここは俺にとって庭みたいなもんだ! 今日はおごらせてもらうぞ」
伊達はマサカズの前に回り込むと、両手を広げて満面の笑みを向けた。
【無料版】第5話 ─信じられる仲間を集めよう!─Chapter5
“ホウム”省官僚を紹介された。文部科学省や防衛省ならどのような役割を担っているのか、ぼんやりではあるもののわかっているつもりだが、ホウム省だと想像力が届かない。そもそも“ホウム”とはなにを意味するのかがわからない。それに付け加え、役人にも“課長”という役職が存在するとは知らなかった。マサカズはこれまでの知識の外にある庭石課長について、具体的なイメージがまったく浮かばなかった。その価値は伊達の興奮から推し量るしかない。おそらくだが“カンリョウ”の課長を紹介されたのは大それたことなのだろう。とても偉く、以前の自分であれば一生関わり合いをもつことがなかった存在だろう。しかもその接触の扉を開くのに、自分の立ち回りが大きく貢献したらしい。日曜日の夕暮れ、伊達と一緒に高田馬場の神田川を望む公園までやってきたマサカズは、何がどうしたことでよい結果をもたらしたのかわからいままだった。
「にゃーん」
ハンチング帽を被り、左手を招き猫のように構えた猫矢が、陽気さを漂わせながら公園にやってきた。伊達の説明によると、これは情報を買うための接触である。数日前、井沢たちのような非合法とは今後距離を置こうと言っていたのに、なぜ再び彼と落ち合うことになったのか。マサカズはそれを伊達に問うたが、彼は接触後に説明する、とだけしか答えてくれなかった。
「猫矢さん、お疲れ様」
マサカズが軽く挨拶をすると、猫矢は人差し指を立て、眉を顰めた。
「えっとですね、“さん”づけはカンベンかなぁ? 俺、まだ十九ですし。春平でいいですよ」
「あ、じゃあ“猫矢くん”でいい?」
「折衷案ですね。いいですよ」
猫矢はたすき掛けに提げた鞄からA4大の封筒を取り出すと、それを伊達に手渡した。
「概要説明、いります?」
「いや、今回はいい。内容の度合いだけ教えてくれ」
伊達にそう言われた猫矢は、右の掌を前に出し、それをわなわなと震わせた。
「かなりのものです。特級クラスですね。おやっさんの手柄ですけど。ぶっちゃけ伊達さんたちは相当運がいいって言ってましたよ」
「そうか……わかった。ごくろうさま」
その謝礼には別れの合図も含まれていた。猫矢は伊達の意図を察したのか、「料金はいつもの通りの段取りで」と告げると、手を振りながら公園を駆け出していった。
「えっと、伊達さん。僕たちの何がラッキーなんです?」
マサカズの問いに答えず、伊達はベンチに腰を下ろし、封筒の中から書類を取りだした。
「伊達さん?」
伊達の隣に腰掛けたマサカズは、書類をのぞき見した。“調査報告書”と記されたそれには、庭石陽菜という名をした女性の覚醒剤購入についての詳細が記されていた。
「庭石って、あの庭石さん? “ホウム”省の課長さんの?」
「ひとり娘と書いてある。去年の十二月、今年の四月、八月と三回に亘って覚醒剤を購入している。つまりは使用しているってことだ」
「逮捕されたりしたんですか?」
「いいや、まだ発覚していない事案だ。現在、これを知っているのは彼女自身と売人、そして井沢さんたちと俺たちだけだ」
「じゃあ、通報しましょうよ。違法薬物は絶対にダメですし」
「いいや。しない」
「いやいやいや、そんな悪いのを見逃すなんて、伊達さん弁護士だったんだし、よくないですよ。それに僕たちの目標は社会貢献なんですよ」
「このネタは、確かにあるひとりの女の違法行為を意味している。が、同時に知りうる者の立場によっては、大きな武器になる」
説明している内容が伊達にしては珍しく、よくわからない内容だったので、マサカズは呻り、腕を組み、首を傾げた。
「すまない。わかりづらかったな。いいかマサカズ、このネタを知っている者の中に、ある人物が含まれていないことに気づかないか?」
「えっと、僕たちと、井沢さんたちと、当人と売人ですよね……」
考えを巡らせたマサカズは、すぐにひとつの解答に辿り着いた。
「お父さんですね」
「そうだ。庭石課長は娘の悪事を知り得ていない。いや、仮に知っていたとしてもだ、これから交渉を進める俺たちにとって、このネタは大きな、とてつもなく強力な武器になる」
「まさか、課長さんを脅迫するってことですか?」
「有り体に言えばそうなる」
「いやいやいや、ダメですって! それって悪い連中のすることですよ」
伊達は書類を封筒に戻すと、それを鞄に入れ、マサカズに鋭い眼光を向けた。
「ここからは俺の読みになるけど、法務官僚の課長が俺たちレベルの相手とビジネスの話をしてくれるわけがない。俺は創業前から庭石よりずっと下のランクの役人とも交渉したけど、どれもが空振りだし門前払いだってあった。今回はオヤジのツテで仕方なく会食程度なら付き合ってはくれるだろうけど、そこが天井だ」
マサカズは反論したかったが、いまは伊達の説明を最後まで聞くことにした。二人の間には秋を感じさせる涼しげな風が流れ、乾いた空気が漂っていた。
「今度俺たちは庭石と会食をする。そこでビジネスの話に発展しなかった場合、この爆弾を突きつけ交渉する。もし発展した場合は……やはりこの爆弾は庭石に手渡す形になる。娘をどうするかは彼の判断に任せる」
二人の間にしばらくの沈黙が続いた。それが説明の終了だと判断したマサカズは口を開いた。
「えっと、娘さんの犯罪を知っている僕たちに対して、庭石課長が毅然とした態度を……つまり、通報したけりゃすればいい、なんて感じだった場合はどうするんです?」
「九十九パーセントそれはあり得ない。ただし、このネタを庭石自身が通報して、なおかつ俺たちの要求を突っぱねるって可能性はある。しかしそれはそれで仕方がない。もちろん、そうさせないように俺は努力するつもりだ」
「努力って?」
「刑事弁護人としての経験から、知識から、庭石に警告できる内容は山のようにある」
伊達の師匠に官僚を紹介してもらい、あとはまともな手立てで仕事の交渉になるのだろうと考えていたマサカズは、伊達の絡め手にうんざりしてしまった。しかし、そもそもが鍵の力を秘密にしたまま国からの仕事を請け負うこと自体が真っ当な段取りになるはずもなく、仕方がないようにも思えてきた。しかも官僚という人物像も皆目見当もつかず、このような飛び道具を用意する必要があるのかどうかもわからない。少なくとも、自分より伊達は今度戦う相手のパラメーターや繰り出してくる技や防御テクニックを知っている様であり、そうなると交渉の手段は彼に任せるしかない。マサカズは少しずつ細かく納得を重ねようとしていた。
マサカズから強く確かな納得は得られない。伊達は肩を落とす彼を見ながらその確信をあらためて得ていた。自分の経験を考慮した場合、庭石への営業は徒手空拳では成立しない。たとえマサカズの力を見せたとしても理解されず、かえって関わりを持ちたくないと拒絶されるだろう。だから、もう頼るはずのなかった井沢に調査を依頼した。当然のことながら、空振りに終わる方に天秤は大きく傾いていたのだが、まさかこれほどの武器が手入るとは望外のことである。巨大な幸運への興奮をマサカズと共に分かち合いたかったが、この様子ではそれも叶わないだろう。伊達はニコチンを強く求めたが、ここではそれを堪えるしかなかった。
「マサカズ、気安めにしかならないけど、庭石がおおらかで、こちらの営業に前向きに対応してくれるか、さもなくば飛び道具をはね除ける、残り一パーセントの毅然さを示してくれる可能性だって残っている」
「ムチャクチャ後ろ向きな期待なんじゃないですか? それって。言ってる伊達さんが一番あり得ないと思ってる。だって、つまり庭石って人は僕たちが戦うにはずっとレベルの高い敵ってことなんですよね。ゲーム風に言えば」
「そうそうそう、レベル十とかで竜王と戦う様なものだ」
「たとえがよくわかりませんけど、なんとなく想像はつきます」
「だからさ、武器が必要だったんだよ。相手を確実に状態異常に持ち込める武器が。いや、俺にしたってせいぜい収賄か浮気の発覚レベルだと思ってたんだよ。それどころか空振りに終わるって覚悟もしてたし、そっちの可能性が遙かに高いと予想していた。しかしフタを開けてみりゃ、なんだよこれ。チートレベルのアイテムじゃないかって、いまそんな感じだ」
“チートレベル”がなにを意味しているのかはわからないが、早口でまくし立てる伊達はその結果に満足している様でもある。マサカズは立ち上がると、すうっと息を吸い込んだ。
「伊達さん、こないだ行ったアジフライの店、行きません? ハッキリ言って、ムチャクチャ美味かったです」
マサカズの誘いに、伊達は子供の様にニッコリと笑みを浮かべ、大きく頷いた。
【無料版】第5話 ─信じられる仲間を集めよう!─Chapter6
伊達が庭石との会食に選んだ店は、品川の割烹料理店だった。九月最後の水曜日の夜、伊達と共に店を訪れたマサカズは、いつものTシャツではなくダンガリーシャツにジャケット姿だった。
「この格好で、いいんですかね? 伊達さんみたくスーツじゃなくて?」
「ジャケットにシャツだったら問題ない。新進気鋭の社長っぽいと思うぞ」
「あー、そう言えばそうかも」
暖簾をくぐり木製の引き戸を開けると、マサカズはほのかな香りを感じた。たまに利用する居酒屋やバーとは違い、雅にもてなす気持ちが感じられる香りだ。やはり高級な店というものは、細かな気遣いというものが行き届いているのだろう。そのようなことを考えながら、マサカズは店員に案内され、伊達と共に奥の個室までやってきた。スニーカーを脱ぐように促されたそこは十畳ほどの和室であり、床の間には川のような風景が描かれた掛け軸が据えられていた。いわゆる、政治家や官僚、大企業の幹部を接待するような場所だ。マサカズは座椅子に腰掛け、店員から熱いおしぼりを受け取った。これも香りがついている。額の汗を拭いながら、マサカズは緊張を高めていった。
「マサカズ、落ち着け。ここは言うほど高級じゃない」
「嘘でしょ?」
「本当だ。オヤジと庭石が昔よく使っていたらしい。もちろん個室じゃなくってテーブル席だけど。だからここを選んだんだ」
世の中にはまだ上のランクというものがあるのか。マサカズはおしぼりで顔を拭くとため息を漏らした。
それから十分ほどが経ち、個室の襖が開いた。入ってきたのはスーツ姿のひどく痩せた男であり、白髪交じりの顔は頬もこけ、事前に知らされていた五十四歳という年齢よりひとまわりほど老けている印象をマサカズは受けた。伊達が立ち上がったので、マサカズもそれに倣った。まずは名刺を交換し、マサカズたちと庭石は挨拶を済ませ、席に着いた。
「伊達先生はかなりの手練れだと聞いてますよ、柏城先生から」
「いやはや、恐縮です」
「柏城先生はお元気ですか?」
「ええ」
「そいつはよかった。私はね、ほんと柏城先生にはお世話になったんですよ」
庭石と伊達のやりとりは、食事が運ばれてきても続いたが、その内容は主に庭石の検察官時代の昔話ばかりであり、彼はナッシングゼロについての質問をなにひとつ投げかけてはこなかった。マサカズにとって不毛とも言えるやりとりは三十分ほど続き、彼はとうとうしびれを切らしてしまった。
「あのう、ちょっといいですか?」
おそるおそる切り出してみたものの、庭石はマサカズを無視して、現在運転している自家用車の話題を続けた。
「あのですね、僕たちはナッシングゼロという会社を運営しておりましてね!」
割り込む形で、強い口調だったため、庭石はようやくマサカズに目を向けた。
「名刺にそう書いてありますね。山田さんは代表?」
「そうです。今日庭石さんをここにお招きしたのは、単刀直入に申しますと、我々の事業にお力添えをしていただけないかと、そういうことなので」
言い切ったものの、庭石は返事もせず鯛のお造りを口に運ぶばかりだった。伊達は肩をマサカズに軽くぶつけた。その仏頂面からは「つまり、そーゆーことだ」と言わんばかりの意図が感じられ、マサカズは庭石が自分たちのことをビジネスの対象にしていないのだと痛感した。
「ここはさ、柏城先生とよく来たんですよ。ランチがリーズナブルでね。特に刺身定食、いいんだよねぇ」
あくまでものらりくらりとした態度を崩さない庭石に、マサカズは腰を浮かせて身体を乗り出した。
「庭石さん、昔話よりも僕たちの話を聞いてもらえませんか?」
「ムダですよ。私はあなたがたのお役に立てそうな人間ではありません」
「いいえ、僕たちの力はあなたと結びつくことで、きっとみんなのためになるはずなんです」
マサカズの力説に、庭石は箸を乱暴な仕草で芋煮に突き立て、片眉を吊り上げた。
「ホームページを拝見させていただきましたが、実績や事業実態が……これは本当に失礼な物言いとなってしまい恐縮なのですが、あなた方の会社の本質がまったく、全然、これっぽっちも見えてこない」
「それは……」
反論をしたかったのだが、咄嗟には適当な言葉が出てくれず、マサカズは言いよどんだ。すると庭石は悪辣な笑みを浮かべた。伊達はそれが弱者につけ込む強者の態度であることを、経験上よく知っていた。
「人助けだの社会貢献だの、あれじゃまるっきり怪しい団体だ。まさか秘密結社の真似事でもしてんのかよ、なーんてね。そんなのに力なんて貸せるわけねーっつの。バカか、ほんと」
言葉を重ねる度、汚物が積まれていく。これが庭石という人物の本質なのだろう。マサカズはお猪口の日本酒をひと呑みすると、伊達を睨みつけた。相棒からのGOサインを受け取った伊達は、鞄から封筒を取り出した。庭石は芋から箸を引き抜くと、蛸の刺身をつまみ上げた。
「娘さん、陽菜さんのことですけど、いいですか?」
「“いいですか”って、なにその抽象的なクエスチョンは」
「陽菜さんについて、父親としてどの程度の把握をされていますか?」
「把握って、普通だよ。そりゃハタチの娘だから、知らんことも山ほどあるけど、それって普通だろ? まー、まだ男はできてないとは思うけど……大学生だから、いずれはって諦めてはいるよ」
「刑法に触れているって点については、いかがですか?」
伊達の言葉に、庭石は箸から蛸の刺身をこぼれ落とした。
「んなわけねーでしょ」
「私が手にしている封筒には、娘さんが三度に渡って覚醒剤を購入したという事実についての調査報告書が入っています」
「だから、んなわけねーだろっつってんだよ」
アルコールも入っていたためか、庭石の口調は顔合わせをした時からはかけ離れ、粗野なものに変わり果てていた。
「オヤジほどじゃありませんが、私もかなりの数の刑事事件を担当してきました。もちろん、覚醒剤取締法違反についてもです」
伊達はそう言い放つと、封筒から資料の束を取り出し、それを庭石に手渡した。受け取った庭石は次々と書類をめくり、顔からは血の気が引き、小さくガタガタと震えだした。
「ウソだろ……なんなんだよ、これ」
「おおかた大学のサークルとかで、ダイエットに効くとか吹き込まれて軽い気持ちで手を出したんでしょう。しかし常習性が鎌首をもたげた。放っておけば、また冬前ぐらいには四度目の購入となるでしょう」
「ウソウソウソ……ウソだって」
充血した目で資料を通読する庭石の耳には、どこまで伊達の脅しが届いているのだろうか。マサカズは観察してみたがわかるはずもなかった。
「庭石さん、これって当事者たちと僕たち、そして情報屋さん以外はまだ誰も知りません。どうします?」
「“どうします”って、どーしよーもねーだろ!?」
庭石の荒んだリアクションを想定していなかったため、マサカズは面食らってしまった。
「じゃ、じゃあお父さんとして、庭石さんが警察に通報しますか?」
そうあって欲しい、そういった願いからでたマサカズの言葉だったが、「バカか!?」との即答で打ち消されてしまった。庭石は資料を膝の上に置くと、伊達を睨みつけた。
「何が望みだ? カネか?」
「いえ、山田代表が先ほど述べた通りです。我々にお力添えをしていただきたい」
自信に満ちた力強い口調で伊達はそう告げた。庭石は犬のように激しく鼻を鳴らすと頭を何度も横に振った。見かねたマサカズが水の入ったコップを差し出すと、庭石は乱暴な所作でそれを受け取り、ごくりとひと飲みした。
「なにすりゃいいんだ?」
「公共事業を斡旋していただきたい。山田代表は、一人で重機十台以上の力を発揮します。信じてください。ですのでまずは最も小さな規模の案件をご紹介していただきたい。これに失敗した場合は、我々はあなたの前に二度と顔は出しません」
「一人で重機? はーん? なに言ってんの。どーやってそんな力だせるんだよ?」
「それは、秘密です」
「ふざけやがって」
「客観的な証拠が必要でしたら、明日にでも経理資料を送ります。いくつかの解体業務において、人件費などの諸経費を照らし合わせればその実務がたったひとりで、たった一日で遂行されたことが判明します」
庭石は目を泳がせ、明らかに困惑した様子だった。マサカズは腰に提げていたポーチから小銭入れを出すと右手で五百円玉をつまみ取った。そして、左手をデニムのポケットに突っ込むと、南京錠に鍵を差し込み、それを回した。
「庭石さん、一応、簡単な証明をさせてください」
マサカズはそう言うと、庭石の顔の前で五百円玉を親指と小指で折り曲げ、それを机の上に落とした。
「まぁ、これってプロレスラーとかでもできるかもしれないんですけど。軽くやってのけたっていう点を評価していただけますと幸いです。いや、実際もっと凄いんですよ。ジャンプ力とか腕力とか。なんか、異常体質っぽくって、僕」
ちりちり頭をひとかきし、マサカズは照れ笑いを浮かべた。
「庭石さん、案件をご紹介いただけましたら、娘さんの件についてはあなたとの共有の秘密として我々は墓場まで持っていきます。弁護士としてお約束しますし、娘さんをどうするかは、あなたにお任せします」
庭石は伊達の言葉に震えるばかりで返事をせず、折り曲げられた硬貨をじっと見つめていた。
「覚醒剤取締法違反は十年以下の実刑です。初犯ということでやり方しだいでは猶予刑になる可能性もありますが、娘さんの場合、常習性があり三度の所持ということになると、仮に私が担当したとしても五年といったところでしょうか?」
検察官経験者に対して効果がある言葉ではないと思った伊達だったが、庭石は「五年」と呻るように呟いた。もうひと押しだ、そう判断した伊達は、庭石の隣まで身を寄せた。
「庭石さんの最終的な目標は、確かご出身の静岡県知事……」
言いきらぬうちに伊達は庭石から突き飛ばされ、畳に転げた。
「わかった。わかったからもういい加減にしてくれ」
姿勢を直して腰を上げた伊達は、勝利を確信した。
一週間以内に案件を用意する。庭石はそう言い残した。彼は滅多打ちにされ敗戦したボクサーのようにフラついた足取りで店をあとにし、マサカズたちは残された料理と酒に取りかかることにした。
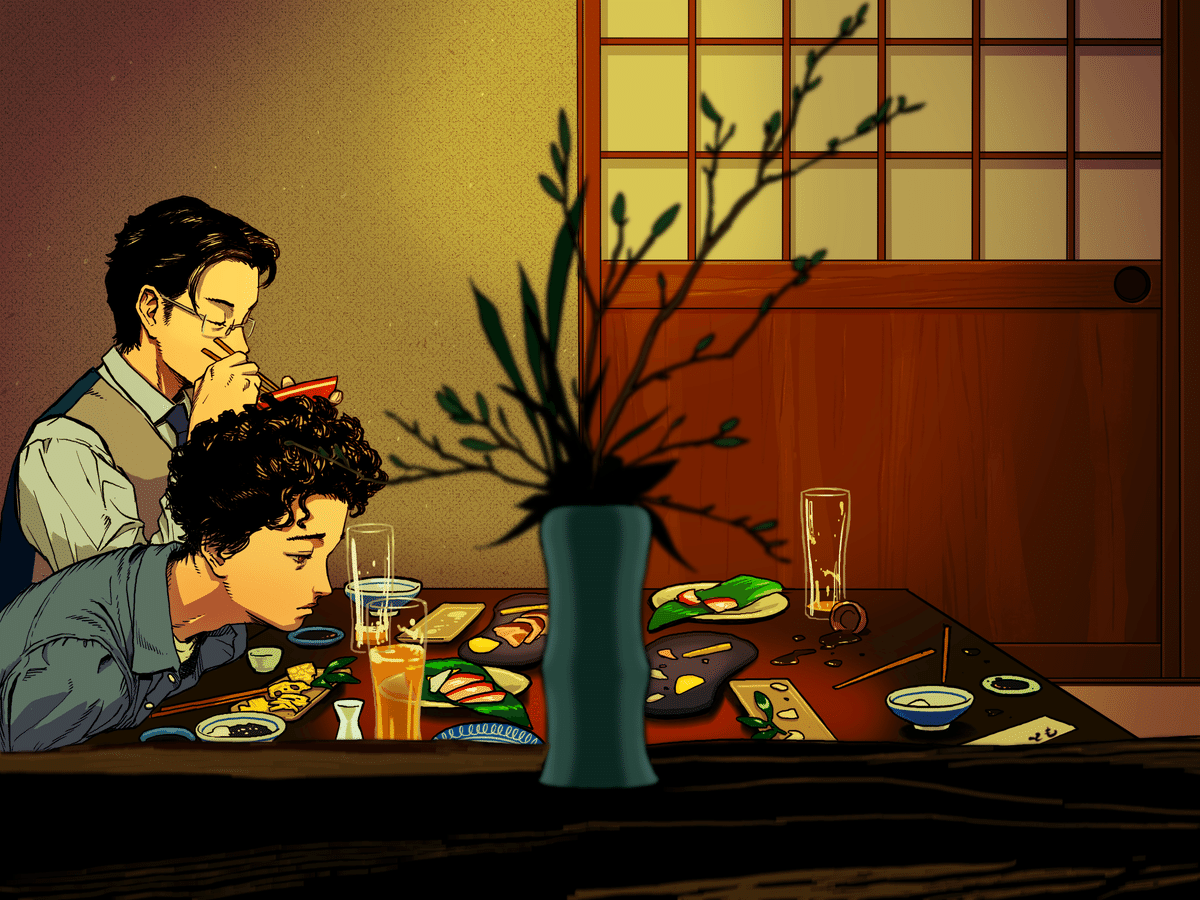
「庭石さん、娘さんのこと、どうするんでしょうね」
「四度目をどう阻止するか、だよな。報告書に売人の名前もあるから、子飼いの検察使ってしょっぴくにしても課長レベルだと購入者リストをもみ消すのは至難の業だ。今ごろ、アイツの頭の中はぐっちゃぐちゃだろうな」
「あ、いや、娘さんの件ですけど……やっばり考え直して通報しないのかなって」
頼りない口調のマサカズに対して、隣でビールグラスを手にしていた伊達は「ほぼ百パーセント、ない」と素っ気なく返した。
「それにしても伊達さん、さっきからずっと食べ続けてますけど、よく食欲がありますね。僕なんて胃が痛いぐらいなのに」
「俺も昔はそうだったよ。けど、悲しいかな慣れちまった」
伊達は苦笑いを浮かべてそう言うと、いくらの茶漬けを勢い良くかき込んだ。
【無料版】第5話 ─信じられる仲間を集めよう!─Chapter7
品川の割烹料理店で庭石から仕事の紹介を確約したあの夜から、マサカズは“法務省”についてネットで検索して知識を得ていた。その上で、彼は自分の力を有効に使える仕事が何であるのか想像を膨らませていた。
法務省とは文字通り法律に携わる行政機関であり、下部組織には検察庁や刑務所、出入国在留管理庁などがある。ひらたく言ってしまえば日本の法と治安を司る組織だ。柏城の紹介に対して伊達が喜んでいた理由を、マサカズはようやく理解できた。鍵の力を使うのに、これほどわかりやすい窓口はない。
例えばどうだろう。テロリストとの戦いを命じられる。日本の国益を損なわんとする武装組織に対して敢然と立ち向かう自分の姿はいかにも正義のヒーローだ。弾丸をものともせず、次々と悪漢どもをなぎ倒していく己の勇姿を、マサカズは深夜のアパートで想像してみた。それはやがて妄想へと変容していき、朝方には相棒の女性エージェントが殉職し、その怒りと悲しみから新たな力に覚醒するというプロットまで仕上がっていた。
例えばどうだろう。誰もが匙を投げる凶悪犯ばかりを集めた極北の刑務所に、特別刑務官として赴任する。ルール無用の最凶囚人たちに、有無を言わせず道具を使わせず、素手で便所掃除をさせる。制服姿で囚人たちを屈服させる威容を、マサカズは事務所で署名捺印しながら想像してみた。それももちろん妄想へと進み、定時が過ぎるころには毒を使う脱走犯を街中で倒し、人質になっていた女性を抱きかかえるなどといった、他人に覗かれたらため息しか生み出さないような、愚かな場面を思い浮かべていた。
だが、現実はそのようなドラマチックな妄想を打ち消すだけだった。六日が経ち、庭石から紹介された仕事は、あまりにも萎びた内容だった。
「いまメールを転送した」
事務所で隣の席の伊達からそう言われたマサカズは、メールソフトで庭石からの案件に目を通した。
依頼内容・建設資材の運搬業務
概要・十月五日、埼玉県秩父山中(所在地は地図参照)にて、拘置所の建築資材をB点よりA点まで運搬。委細は別途添付ファイルを参照。
事情・業者が資材を誤ってB点に運搬したため、これを本来のA点まで移動。
「えー」
マサカズは思わず嫌気を声に出してしまった。伊達は苦笑いを浮かべ、珍しく揃っていた四人の年寄りもそれぞれ笑いを漏らしていた。
「建築資材の運搬って、つまりは力仕事ってことですか?」
「成功したら、もっと派手な案件を紹介してもらえるさ。我慢しろ、マサカズ」
ハードなアクション映画を想像していたのだが、発注されたのはドラマ化もされそうにない“お仕事”である。言ってしまえばこれまでやってきた解体業とあまり変わりはない。拘置所という点が法務省の管轄を匂わせるものだが、あまりにも地味でつまらない業務である。
「立派な仕事ですよ」そう励ましたのは木村だった。
「社長のスーパーパワーで、パパッと済ませりゃいーのよ」浜口の軽口は相変わらずである。
「がんばれ!」語彙力のなさは寺西の個性とも言えた。
「税金の節約にもなりますし、公益に貢献できますよ」嫌気を少しは打ち消してくれる草津の言葉だった。
「やりますよ。第一歩ですし、たぶん楽勝案件でしょうから、クリアして次に進むだけです」
マサカズは前向きな気持ちを言葉にして、老人たちと伊達に返した。創業以来、木村たちには業務内容については情報を共有していた。しかしその手段については秘匿としていたのだが、マサカズは一度昼食の際、それが気にならないのか正直な気持ちを問うてみた。そしてその回答は四人が異口同音に、「興味はあるけど関心はもたない。結果としてお給料をもらえればそれでよし。なぜなら、もう先も長くないから」と説明してくれた。尋ねたのが兄、雄大の離脱後だったため、彼らは会社の秘密に触れることに何らかの危険を感じていたのかもしれない。自分たちが世話になっているこの会社には闇の部分があり、それに手を出せば職を失う危険をはらんでいる。だからこそ、保司のような怪しげな業者ではなく法務官僚からの仕事の依頼に対して、安心して朗らかな激励をしてくれるのだろう。マサカズはちりちり頭をかき、添付されている業務の詳細を記したファイルを解凍した。
その翌日の深夜、伊達は事務所でパソコンに向かっていた。残業の原因は、草津が急遽検査入院のため明後日まで不在となってしまったからである。草津は会社のネットワークやWebサイトの管理を一手に引き受けており、今日はちょうどサイトの更新業務があったため、伊達がその代役を引き受けていた。Webサイトの更新などこれまでにやってきたことはなく、夜の七時から始めて業務内容のページに二行の文面を追加するだけで四時間もかかってしまった。そのうち最初の一時間はサイトの構成の理解に費やし、次の二時間でHTMLとCSSの基礎知識を学び、最後の一時間で更新する文面の打ち込みとFTPへのアップロードを実行した。やり遂げた伊達は十本目になる煙草を灰皿に押しつけると、両手を挙げて大きく伸びをした。
人手があからさまに足りていない。安い人件費で年寄りたちを雇い、能力については申し分なく性格面でも柔軟な者ばかりで扱いやすいのだが、体調や家族のイベントなどでどうしても欠席が多く、総力を用いての運営はできていない。マサカズも事務仕事においては成長しつつあるが、力仕事の翌日は疲労のため自宅で静養するため、あてにすることはできない。せめてあともう一人、若い戦力が欲しい。あるいは明日の夜に予定されている庭石からの案件を無事成功させれば、今後健全で安定した収益が見込め、営業から解放され事務仕事に充てる時間が増やせるかもしれない。そうなれば追加の人員も不要となり、人件費の増加も防げる。
それにしても我ながら無茶な試みだ。伊達は十一本目の煙草に火をつけた。マサカズの超能力を秘密にしたまま、公益に叶う業務を遂行する。そう発想した当時、最悪を一として十レベルの段階で状況を想定していたのだが、現状ではレベル三だと言える。最高のレベル十まで、あとどれだけの行程を経ればいいのだろうか。そして自分とマサカズはその実現のため、どれだけ成長しなければならないのだろうか。
ゲームの開発に喩えてみれば、ゲーム機の仕様は把握でき、開発方法も見通しが立ったようなものだ。しかしどのような相手にいかなるソフトを提案できるのか、それについてはまだ入り口に辿り着いたばかりのようなものだ。庭石というメーカーに対して、自分たちデベロッパーがどう立ち回れるのか。考えることは山積みではあったが、公的案件の獲得という試みが現実になろうとしていたため、伊達は疲れを感じていなかった。
「電気がついてると思ったら、まだいたんですか? ぼち終電ですよ」
ドアの鍵を開け、事務所に入ってきたのはマサカズだった。
「俺はバイクだから、終電とか別にだけど、お前は定時上がりのあと、こんな時間までどこ行ってたんだ?」
「ジムです駅近くの。先週から入会したんですよ」
「知らなかった。スポーツジムか?」
「ええ、鍵の力が少しでも使いこなせればって思って。格闘技のコースもあるんで、まだまだ初心者ですけど」
「格闘技って、MMAか?」
伊達は目を輝かせ、そう尋ねた。
「いや、ボクシングのエクササイズです」
“MMA”という単語もわからぬまま、マサカズはそう返すと伊達のデスクまで進み、缶コーヒーを差し出した。
「サンキュー。ちょうど欲しかったんだ」
缶を受け取った伊達は、プルトップを引っ張った。
「もしかして、草津さんの穴埋めですか?」
「ああ、ホームページの更新が必要だったんだよ。いや、まいった。HTMLとかFTPとか全然素人でさ。なんとか更新までは辿りつけたけど、まぁ疲れたな」
「あ、それだったら僕に言ってくれればよかったのに」
「できるのか? ウソ?」
「書店のひとつ前の、自転車屋のバイトでホームページの更新やらされてたんですよ。しかも予算がないから専用のソフトとか使わずテキストエディタで、CSSとかJavaとかなんかもかじりましたし」
マサカズの言葉に、伊達はぐったりとうなだれた。
「もっとお前のこと、知る必要があったな、俺は」
「まぁでもパソコンは得意じゃないですから、できることは狭いですよ。あんまり期待……してもらえるようにもっと頑張らないと……か」
考えを巡らせながら、マサカズは言葉を選んだ。伊達の負担を減らすためにも自分がやるべきことは、途方もないほど広く大きい。ジム通いもその一環ではあったのだが、自分にはもっとデスクワークを引き受けられる力が必要である。しかもその習熟内容を伊達に聞くのは彼の実務を増やすだけであり、木村たち四人から学ぶのが最善策だと思えた。
「明日はいよいよ初の公共事業ですし、ぼちぼち僕は上がりますね」
「ああ、ほんと、明日は頼んだぞ」
「そうだ、ひとつ聞きたかったんですけど……なんで柏城さんに最初っから紹介をお願いしてもらわなかったんです? ほら、独立でよくあるでしょ? 前の職場から取引先の紹介してもらうのって」
問われた伊達は、仏頂面で煙草を灰皿に押しつけるとコーヒーをひと飲みした。
「オヤジに頼むのは、最終手段にしていたんだ。カッコつけてたんだよ、俺は」
「つまりそれほど僕たちは追い詰められていたってことですか?」
伊達は無言のまま頷くと、コーヒーを一気に飲み干した。
「あとな、オヤジに紹介を頼んだ場合、間違いなくお前に一度会わせろって言ってくると思ったんだ」
「つまり、僕だと柏城さんに認められなくって、紹介してもらえないと?」
「そうだ」
「じゃあなんで?」
「ここしばらくのお前を見て、大丈夫って期待した。そして、それは間違っていなかった」
「あー、じゃあ僕は起業以来、成長したってことなんですね?」
嬉しそうなマサカズに対して伊達は静かな口調で、「それだけじゃない、隠れていた才能が開花したってこともある」と返した。すっかり有頂天になったマサカズは伊達に敬礼すると、軽やかな足取りで事務所を後にしていった。
「そして、俺にはそんなものは、ない」
残された伊達は、寂し気にそう呟いた。
【無料版】第5話 ─信じられる仲間を集めよう!─Chapter8
マサカズが埼玉西端の秩父鉄道三峰口駅のホームに降り立ったのは、終電となる夜十時過ぎのことだった。十月に入り夜にもなると寒気を感じることもあり、マサカズもTシャツの上に青いダンガリーシャツを羽織っていた。生まれる前の昭和を想起させる古びた駅舎を出た彼は、すぐ近くのタクシー乗り場に向かった。
事務所の代々木を出たのが夜七時半で、ここまで三度の乗り換えを経て三時間近くを要していた。料金も一千四百円ほどかかり、あとで交通用の電子マネーにチャージをしておかなければならない。伊達は今日も増資の件という、マサカズにとってまだ勉強が追いついていない分野の事務処理で忙しく、今日の仕事は単独行動になっていた。
やるべきことは庭石から送られてきた資料で把握しており、念のためにスマートフォンにそのファイルも保存しておいた。簡単に言ってしまえば運搬業務であり、力仕事なので消耗は覚悟の上である。今夜中に終わらせ、どこかで宿を取り、明日は一日休養に充てる旨は伊達ともすり合わせ済みとなっている。
鈴虫の音が洪水の様に耳を刺激する中、マサカズはタクシーに乗車した。最近ではあまり見ることがない、スライド式ではなくヒンジ式の扉をしたセダンカーである。マサカズは中年の女性運転手に、ここから五キロほど離れた国道沿いの、なにもない場所を目的地として告げた。
「あのう……あまり聞くべきことではないとは思われるのですが」
運転を始めた運転手が抱く疑問を、マサカズは予め予想していた。
「あ、フクロウの観察が目的なんです。研究しているもので」
「あぁ、フクロウですかぁ。夜になるとホーホーいってますよねぇ」
「ええ」
「でも帰りはどうするんです? この辺だと配車アプリも使えませんよ」
「それはまぁ、なんとかしますんで」
まさか適当な宿まで跳躍して移動するなどとは言えない。マサカズは運転手が納得していないことを、車内に漂う雰囲気で感じていたが、これ以上の言葉を重ねるのは余計だと考え、口をつぐんだ。
荒川を越え国道に入り、山に向かって進むタクシーの中で、マサカズは昨晩の事務所での伊達とのやりとりを思い出していた。彼が言うには、自分には柏城というベテランの弁護士を信用させる力が備わっている。それはもしかすると、隠れた才能が開花したからかもしれない、とも推察していた。昨日はすっかり浮かれてしまったが、よくよく考えてみれば昔から交渉や駆け引きといったものには縁がなく、どちらかと言えば苦手だと思っていた。そうなると、鍵という新たに得た力が根拠になり、勇気や大胆さが身についたと考えるのが妥当ではある。伊達は柏城との交渉の帰り道で「お前はこれからもこんな感じでいてくれ」と言ってくれたのだが、才能をより育てるためには鍵によってより多くの結果や成果を導き出し、それを以てしてより豪胆に、よりふてぶてしい自分を目指すべきである。だからこそ、今夜の仕事もきっと何らかの自信に繋がってくれるはずだ。マサカズはそう結論付け、車窓から秩父の山々を見上げた。深夜に差し掛かろうとしていたため、それは漆黒のシルエットでしかなく、これまでなら決して一人で訪れるような地域ではない。マサカズはデニムのポケットに手を突っ込み、鍵を握ることで怖じ気を払った。
タクシーは、目的地である国道沿いにある空き地の前で停車した。
「あのう、帰りのお時間がわかるようでしたら、私、来てもいいんですが。あ、もちろん時間にもよりますけど」
料金を受け取ると、運転手はそう申し出てきた。マサカズは腰を浮かすと「あ、時間、まだわかんないんで。大丈夫です」そうやんわりと断り、タクシーを降りた。
タクシーが去り、二分ほどが経っていた。周囲には梟の鳴き声や虫の音が響き渡っていたが、人の気配は全くなく、道路灯もこの空き地を照らしきれてはおらず、闇の中にマサカズはいた。彼はリュックから電灯付きのヘルメットを取り出し、それを被った。
マサカズの眼前には、一辺が二メートル大の立方体のコンテナが鎮座していた。数にして横並びに十個。それはこの空き地にあってはならない荷物だった。中には新設する拘置所の建築資材が入っているらしく、ここから二キロほど離れた山中の建設現場まで運搬される予定だった。しかし業者が配送先を間違え、この国道沿いの空き地に届けられ、もう五日も放置されているらしい。本来であれば手違いをした業者が建設現場まで運び直すべきなのだが、そこに庭石が割り込む形で権限を発動し、ナッシングゼロへの運搬依頼となったと伊達は説明してくれた。
マサカズは南京錠に鍵を差し込み、「アンロック」と呟いた。
コンテナの角を、マサカズは両手で抱え込んだ。僅かに力を入れるとそれは軽々と持ち上がり、重さはほとんど感じられない。これならば、運搬自体は容易に行えるだろう。注意するべき点があるとすれば、コンテナの破損である。建設現場まではトラックが通れる登りの舗装路があり、この時間は誰も利用していないということなので、そのルートを使うのが最も安全である。跳躍すると、コンテナの大きさも相まって万が一目撃される恐れもあるので、走って運ぶしかない。段取りを頭の中でまとめ上げたマサカズはひとつめのコンテナを抱え、勢いよく駆け出した。
地道な仕事だ。九度目の往路を登り切ったマサカズは、九個目のコンテナを運搬先である建設現場の指定されていた資材置き場に下ろした。拘置所はまだ整地が済んだばかりで建設は始まっておらず、予定では来年の夏に完成するらしい。犯罪の結果このような山奥に閉じ込められるなど、想像してみただけでも恐ろしい。マサカズは自分が殺人の罪を犯したという自覚は常にあったので、拘置所の建設に自分が関与していることに奇妙さも感じていた。
自分の能力から推し量れば、たったの二キロ間の手軽な運搬作業ではあったのだが、ヘルメットのライトだけを頼りにコンテナへの気遣いをしながらの作業は神経をすり減らす。マサカズは空き地に腰を下ろすと、両手を後ろに着け、深呼吸した。
あと一度の往復でこの仕事も完了する。最後に証拠となる写真を撮り、伊達に報告すればいい。さて、今日はどこに泊まっていこうか。もう日付も変わってしまったので、いまからチェックインできる宿はないだろう。となるとスーパー銭湯かサウナという選択肢が考えられる。仕事のあとについてはまったくのノープランだったため、マサカズはスマートフォンを手にした。
そのころ伊達は、未視聴だったプロレスのDVDを自宅マンションのリビングで見ていた。外国人チャンピオンに日本人が挑戦するタイトルマッチであり、伊達が生まれる前、昭和の時代に行われた試合である。ついさきほどの帰宅であり、ソファでくつろぎネクタイを緩めた彼は、スマートフォンが振動しているのに気づき、それを手に取った。
「おお、マサカズ。あと一個で終わり? いい感じじゃないか? 秩父のサウナか健康ランド? いや、すまない。心当たりはないな。けど秩父駅まで行けば、なんか見つかるんじゃないのか?」
伊達からは情報を得られなかった。マサカズは淡々とした気持ちで電話を切ると、ゆっくりと立ち上がった。
最後のコンテナがある麓の空き地まで向かうため、マサカズは山道を下りていた。残りひとつで終わり。そのあとは秩父駅まで誰にも見られないように移動して、サウナのあと生ビールでも呑むか。冷たいジョッキの生ビールを想像した途端、喉の渇きを覚えたため、マサカズは背負っていたリュックからペットボトルを取り出した。それにしても奇妙な能力である。自分が受け入れるという明確な意思さえあれば、鍵の防壁を突破してペットボトルの中身は喉へと運べられる。生ぬるくなってしまったコーラをごくごくと飲みながら、マサカズはあらためてこの力が自分にとって都合良く制御できてしまえるのが可笑しく思えた。彼は飲みかけのペットボトルをリュックに戻そうとしたのだが、うっかり手を滑らせ、それは山道を外れ林の中に転がっていった。このままではポイ捨てになってしまう。それにまだ中身が入っていてもったいない。マサカズはペットボトルを求め、慌てて真っ暗な林に足を踏み入れた。
ぬめりとした感触が、スニーカーの底に伝わってきた。これは濡れた落ち葉だ。栃木の故郷にいたころ、山で遊んでいた際に何度も感じたことがある、危険のシグナルでもある。重心を著しく崩し、膝は体重を支えきれず、転倒したマサカズは落ち葉の絨毯を滑落していった。
先ほどは少々素っ気ない対応をしてしまった。伊達はパソコンで秩父周辺の公衆浴場の情報を集めると、それをスマートフォンに転送し、マサカズに電話をかけた。しかし、何度かの送信音ののち、留守番電話に切り替わってしまった。作業中で対応できないだけなのかもしれない。そう考えるのが最も自然である。だが、伊達はなにやら心の奥で言いようのないざわつきを感じていた。スマートフォンのGPS機能を使い、マサカズの現在地を確認してみたところ、彼はいまも作業現場の山中にいる。更にもう一度電話をかけてみたところ、結果は変わらなかった。電波が届き、連絡手段が確保されているにも関わらず、彼の声を聞くことは叶わない。これまでにも何度か電話にでないことはあったが、ざわつきは増すばかりであり、伊達はその正体が不安であることに気づいた。彼はテレビを消すとソファから立ち上がり、バイクのキーを手に取ると玄関へ向かった。
【無料版】第5話 ─信じられる仲間を集めよう!─Chapter9
ヘルメットのライトに照らされた、その黒く逞しい獣の胸には、三日月型の白い斑紋が入っていた。それ故、このクマ属はツキノワグマとの学名がつけられていた。雑食であり普段は木の実や果物、動物の死骸などを食糧としており、日本全国の山林に生息し、この埼玉県秩父も例外ではなかった。本来は夜行性であるのだが、最近では食糧を求めて日中に人里に出没し、人間に危害を加える事件も発生している。
身長は成人男性より低い場合が大半なのだが、マサカズが山中で対峙しているその個体は、彼よりもずっと大きく、口からは涎を垂らし、重低音で呻り、敵愾心を剥き出しにしていた。
滑落した。濡れた落ち葉に足を滑らせ、転び、転がった。そういった際、鍵の力をどう使えばわからず、ただただゴロゴロと落ち葉を纏いながら丸太のように斜面を落下していった。途中、二度ほどスマートフォンが振動したのだが、応対することはできなかった。傾斜も緩まり、ようやく転落もおさまり、立ち上がったところ、目の前に“こいつ”がいた。黒い 獣だ。様子を窺う限り、友好的な相手ではない。どうやら自分はクマの縄張りに侵入させられてしまったようだ。
こういった哺乳類との接し方など、テレビで少し聞きかじった程度の知識しか持ち合わせていない。死んだふり、大きな音を鳴らす、決して背中を見せずゆっくりと後退する。しかしマサカズにとって、対応する手段はもっと別にあった。彼はデニムのポケットに手を突っ込み、南京錠と鍵が繋がったままであることを確かめた。つまり、力の有効期限はまだ切れていない。ならば、この最も有効な対抗手段を用いるだけである。いまにも襲いかからんと身構えているそれは、地下格闘技のチャンピオンや空手の猛者と比べ、どの程度の戦力と、そして防御力を有しているのだろう。殺されも殺したくもなかったマサカズは、ジムで覚えたてだったボクシングの構えを取った。

臭いを感知しようと意識をしてみると、動物園で嗅いだことのある獣臭を感じる。こいつはいきり立っている。招かれざる客を撃退するべく、懸命に己の戦意を高めている。ならば、こちらもそうしてみよう。マサカズは顎を引き、ツキノワグマを睨みつけた。すると、対する獣は身を屈め、爪で地面を何度か掻き、慌てた様子で背中を向け、木々の中へと駆け出していった。
まさかの撤退だった。おそらく、このまま暴力で衝突した場合、命を失う危険を察したのだろう。縄張りを放棄するほどの脅威を感じ取ったということだ。マサカズは構えを解き、常に生存の値踏みをしている野生動物の方が、勘違いをした格闘家などより身の程というものを知っているのだと理解した。
「おーい、お前の狩り場を荒らすつもりはないから、あとで戻ってきな!」
言葉が通じぬことはわかってはいたが、マサカズは木々の暗闇に向かってそう叫んだ。
法を逸脱した人間たちだけではない、あのように獰猛な動物に対しても恐怖を感じなくなっていた。熊が去った林の中で一時間ほどの休憩をとったマサカズは、山道に戻り下山を始めた。山を転げ落ち、猛る熊と遭遇し、気合いだけでそれを退ける。異常だ。それでいてどこか地味だ。起きた出来事をあらためて整理していたので、下山の足取りも重かった。マサカズは自分が段々と恐怖や脅威に対して鈍感になっていると感じていた。
いま最も恐ろしいのは、悪意を持った存在が鍵を手に入れることである。現在所持しているものと、事務所の堅牢な金庫に収められた六本、そして自宅にある一本が鍵の全てである。ツキノワグマを威嚇だけで退かせるほどであり、銃弾をものともしないこの力は、何としてでも他人の手に渡してはならない。敵対した場合の危険だけではない、七浦葵や兄、雄大の様に、手に入れること自体で命を落とす恐れがあるのだ。そう思えば、確かに自分は変わり者なのかもしれない。葵のように不満を解決するために使わず、兄のように特異性を喧伝して何らかの成果を得ようといった発想には至らない。伊達などに言わせれば普通の人間は、力に応じた欲求を抱くらしいのだが、もしかすると既に三人を殺してしまったのが大きく影響している可能性もある。あれ以来ずっと、罪滅ぼしをしているような気がする。それが的外れな思い込みであることは、よくわかっている。しかし奪ってしまった命に対して弔うため、せめて世の中の役に立てないだろうか。明確にそう考えたことはなかったが、自身の特異性の原因としてはなんとなくだが腑に落ちる。
マサカズが麓の空き地までやってくると、そこにはバイクに跨がった伊達の姿があった。
「マサカズ! なにかあったのか?」
「あ、いや、伊達さん? なんで?」
言いながら、二度の電話の相手が彼であることは履歴から知っていた。だが、都会ではないため電波の状態は不安定であり、あらためて確認することもないままここに至っていた。
「電話しても出ないから、嫌な予感がしてすっ飛ばしてきた。まぁまぁ違反はしたけどな」
ヘルメットを脱ぎ、バイクから降りた伊達はスーツのポケットから煙草とライターを取り出した。
「ああ、山を滑り落ちちゃったんですよ。でもアンロックしてたんで、平気です。で、そのあとクマと遭遇して。でも平気です。気合いで追い返しました」
すらすらと述べるマサカズに、伊達は思わず煙草の箱を地面に落としてしまい、慌ててそれを拾い上げた。
「なんか、なんつーか、メチャクチャだな」
「ですね。一番おかしいのは、自分より大きいクマが目の前にいるのに、ちっとも怖くないんですよ」
「おかしくないだろ。いまのお前はおそらくこの星で、一番強い生物なんだから」
「努力もしないでそんなのなんて、ちょっと気が引けますね」
「だから世の中に役立てて、みんなに還元するんだ。コンテナはあと一個みたいだな」
「ええ、すぐに運び出すんで、伊達さん、心配かけてごめんなさい」
「謝るタイミングが独特だな」
「たぶん、軽く混乱してるんだと思います。僕」
マサカズはそう言うと、最後のひとつとなったコンテナを抱え上げた。伊達はプロレスラーでも見られないその怪力に、あらためて子供じみた興奮を覚えた。
二キロ離れた建設現場まで、マサカズは最後のコンテナを運び込んだ。
「お疲れ様」
そう声をかけてきたのは伊達だった。彼はコンビニのビニール袋からサンドウィッチとおにぎりをひとつずつ取り出し、「どっちにする?」と尋ねた。
コンテナに寄りかかるように座り込んでいたマサカズは鮭のおにぎりを、その隣で伊達はタマゴサンドを、それぞれ頬張っていた。
「腹減ってたんで助かります。これ、どーしたんです?」
「途中で買ってきた。お茶もあるぞ」
「伊達さん」
「なんだ?」
「できれば次の現場、山じゃない方がいいかも」
「検討する……けど、期待はしないでくれ」
「見られたらアウトですもんね」
苦笑いでマサカズはそう返すと、いまは何もない建設予定の更地に目を移した。
「拘置所って、犯人が入れられる施設なんですよね」
「大雑把に言えばそうだけど、正確には刑が確定される前の被告人や死刑囚が収容される施設だ」
伊達の説明に、マサカズは目を丸くして彼の顔を見た。
「あー、刑務所とは違うんですね」
「そうだ」
「あ、サンドウィッチひと口下さい。おにぎり一個とサンドウィッチ三つだとなんかワリが……」
言い終える前に、伊達はタマゴサンドをひとつマサカズに突き出した。
「そっか、死刑囚もここに入れられるんですね」
おにぎりを食べ終えたマサカズは伊達からサンドウィッチを受け取ると、再び更地に目を戻した。
「ああ、懲役刑と違って、死刑は執行時点で刑が完了するからな」
「僕なんかも本来なら死刑なんですよね」
「あれは事故だ。俺なら無罪にだってできる」
それは嘘である。二人の従業員については正当防衛を主張し減刑も望めたが、登別については状況から考えても一方的な暴行殺害であり、監禁と脅迫に抵抗するためという主張をしても実刑は免れず、検察官の技量しだいでは死刑も考えられる。
「罪の意識を持つのは構わないし、もしそれが仕事への原動力になっているのならそれもいい。ただ、自分が犯罪者だと思うのはやめろ。実際そうじゃないし、おまえにそのつもりはなかったのだから」
「すごい……伊達さん、罪悪感が原動力って、ちょうどついさっきそれについて考えてたんですよ。伊達さんってやっぱり超能力者?」
「ずば抜けて人の心を察する力があるだけだ。それに、俺はお前のことを考えるのに結構な時間を使っている」
「照れますね。なんだか」
「俺だって恥ずかしいよ。だからこんなこと、あんまり言わせるな」
マサカズは最後の仕上げとして、完了を証明するコンテナ群の写真をスマートフォンで撮った。それを見届けた伊達は、お椀型のヘルメットをマサカズに差し出した。
「スペアを持ってきた。これからどうする?」
ポケットの中の鍵を外したマサカズはヘルメットを受け取ると、ちりちり頭をひと掻きした。
「うーん、途中で休憩は入れたんですけど、鍵外したら結構な疲れですね。今日はとっとと帰って寝ようかな」
「わかった。なら送っていくよ。サウナとかはいいのか?」
「ビールかぁ……あー、やっぱりやめておきます。伊達さんだって明日は仕事でしょ?」
「俺のことは気にしなくていい。わかった、タンデム中にキツくなったら合図してくれ」
「タンデム?」
「本来なら二頭立ての馬車、いまのはバイクの二人乗りって意味だ」
「へぇ、伊達さんって色んな言葉知ってるんですね」
感心するマサカズに、ジェットタイプのヘルメットを被った伊達は人の悪い笑みを浮かべた。
「羨ましいか?」
「いえ、別に」
マサカズのリアクションがあまりにも素っ気なかったため、伊達は笑みを消し「なら、言うなよ」と呟きながらバイクに跨がった。
【無料版】第5話 ─信じられる仲間を集めよう!─Chapter10
あちらこちらの関節が軋み、全身に力が入らず、なにより意識がぼんやりとしてままならなかった。それでも伊達との“タンデム”は中断することなく、なんとか小岩の自宅アパート前まで保つことができた。伊達の運転は制動が優しく丁寧で、それ故の心地良さに意識が遠のくこともあったが、ときおり声をかけられたので、その都度はっきりと取り戻すことができた。
敷きっぱなしだった布団に大の字になって倒れ込んだマサカズはその日の午後、ようやく目を覚ました。空腹を覚えた彼は、まず何を食べるのか考えた。カップ麺やレトルトカレー、米などの蓄えはある。眠気はないものの疲れは抜けておらず、だるさと鈍さで身体を思うように動かせないため、自炊をする気にはなれなかった。もちろん外出も困難で、いつものコンディションに回復するには、このまま夜まで横になっているしかない。昨晩の仕事はそれほどの運動量ではなかったのに、なぜここまで疲労を感じているのだろうか。マサカズは考えてみたが、その原因は心因的なものしか思い当たらなかった。作業があまりにも単純だったため、少々考え事が過ぎてしまった。つまりこれはストレスというものだ。十年前、初めての仕事である学習教材のセールスをやっていたころもこの様な現象はあった。しかし当時とは違い、この消耗は休養を取れば回復し、そもそも仕事に対しての意欲は減るどころか前のめりでもあるので心配はない。だが、腹が減っている。そう言えば以前、事務所で草津がオンラインのフード注文、配達サービスを利用することもあると言っていた。身体を起こして食事を摂る程度の体力はあるので、マサカズは枕元のスマートフォンを手に取り、その手立てを検索してみようとした。すると、呼び鈴が鳴った。布団からのっそりと起き上がった彼は、玄関の覗き窓に顔を寄せた。瓜原の入れ墨面が見える。その背後にはひと月ほど前に相手をした空手家の姿もある。取るべき選択肢に居留守もあったのだが、二人の様子がなにやら穏やかだったため、マサカズは仕方なく扉を開けた。
「中国拳法から派生した独自の拳法、狸王拳という流派がある」
部屋に招き入れた空手家の真山は、そう切り出した。正座している彼は両腕をギプスで固めており、その原因が道場での立ち合いにあることを、マサカズはよく自覚していた。
「狸王拳は一子相伝。その六十七代目継承者である尾之花紅化殿は我々の世界では神と崇められている最強の実力者だ。無論、この自分などとは比べようもない。天と地だ」
真山の後ろには瓜原が正座していた。壁により掛かり、二人と向かい合っていたマサカズは、わざとらしく大きなため息をついた。
「あのですね。今日の僕はひどく疲れているんです。何か用があるんでしたら、手短にお願い出来ませんか?」
「尾之花殿がつい先日特別指導員として我が道場に訪れたのだ。そして俺のこのザマを見て問うてきた。自分はキミのことを話した。尾之花殿は強い興味を抱き、立ち合いを希望した」
「えーと、つまり六十何代目かの達人が、僕と試合をしたいってことですか?」
「いまからでもウチの道場でどうだ? 尾之花殿も待機している」
「だから、今日は無理です。後日、日をあらためてってことなら相手をしてもいいですけど」
マサカズがそう答えると、真山は爽やかな笑顔で力強く頷いた。
「わかった! いつでも連絡をしてくれ!」
「前もってひとつ聞いておきたいんですけど、その六十何代目って、おたくの業界では最強って言っていいんですか?」
「過言ではない!」
「じゃあ、その人を倒したら、もうラストってことでいいんですよね。正直な話、誰もケガさせたりしたくないんです」
真山のギプスを見つめ、マサカズはそう告げた。真山は笑みを消すと、マサカズに鋭い眼光をぶつけた。
「ケガ? するのはキミの方だと俺は見込んでいるのだがな。無論、治療が必要になった場合、当方で費用は負担するし、社長業に支障が生じるようなら、その損害額も補償する」
その言葉に、後ろにいた瓜原が何度も細かく頷いた。マサカズは反論する気力もなかったので、床に目を落とし、「はい」と呟いた。
真山は名刺を残し、瓜原と共にアパートから立ち去っていった。残されたマサカズは芋虫のように這って布団を求めると、再び空腹を覚えた。ひと休みして体力を取り戻したら、駅のショッピングセンターで弁当を買ってこよう。真山が言っていた“リオウケン”という単語から焼売弁当を連想していた彼は、静かに瞼を閉ざした。
マサカズが真山たちの来訪に疲れ果てていたころ、伊達は代々木の事務所で寺西から封筒を受け取っていた。中には株式会社変更登記申請書が入っており、これは資本金の増額のため、伊達が寺西に取り寄せさせたものだった。
「ところで昨日の仕事、上手くいったんですか?」
浜口がそう尋ねてきたので、伊達は拳を握って親指を立ててみせた。
「そりゃあよかった。お国からの仕事、増えるといいねぇ」
そう言うと、浜口は机上にあった三冊のファイルを抱え上げた。
昨晩の仕事量を推し計ってみれば、マサカズの疲労はそれほどでもないはずである。しかし、彼はひどく消耗しているようにも見えた。たったひとりで山奥での作業は、体力より気力への負担が重かったのだろうか。伊達は封筒から出した書類を確認しながら、そのようなことを考えていた。彼は椅子から立ち上がると、バイクのキーを手にした。
「じゃあ、自分はこれから法務省に行ってきます。そのあと営業もあるので、今日は直帰です」
木村たちにそう言った伊達は、壁のホワイトボードの自分の欄に、“直帰”と記されたマグネットを貼り付けた。
バイクで霞ヶ関の法務省を訪れた伊達は、警備員に庭石の名前を告げ、応接室まで案内された。ソファに座り湯飲みの茶を啜った伊達は、対座する庭石に柔らかな笑みを向けた。
「写真はご覧いただけましたか?」
「請求書を出してくれ。来月末には振り込むよう手配する」
「価格は発注の三分の二にしておきます。我々にはそれでもじゅうぶん利益が出ますので」
伊達の申し入れに、庭石は顔を顰めて手を払う仕草をした。
「やめてくれ、不自然な請求額に対して誰が辻褄合わせをすると思っているんだ? これは民間同士の業務じゃないんだぞ」
「そうですか、公益に貢献できると思っていたのですが、残念です。ああそうだ、業務の遂行中、作業担当者が熊と遭遇しました。もちろんすぐに撃退し、事なきを得たわけですが」
「伊達、言っておきたいことがある」
名前を呼びつけられた伊達だったが、怯むことなく澄ました顔で「どうぞ」と返した。
「今回の案件をお前たちに回すことについて、私がどれだけの手間をかけ、リスクを警戒したと思う? 私たち縦割りの官僚機構の中で、この便宜は破格と言ってもいい」
「ありがとうございます。娘さんはお元気ですか?」
返事をすることなく庭石は俯き、大きくため息をついた。
「今後、定期的に案件をお願いします。我々は庭石さんとこうやって、穏やかなやりとりが続くことを望んでいます。もちろん、そのためには破格とやらをこれからも続けていただくしかない。我々とあなたが共有した秘密を守るためには、そうするしかありません」
しだいに、庭石は小刻みに震え始めた。その様子を観察した伊達は、これ以上の念押しは必要ないと感じたが、最後に言っておきたいことがあったため、ソファから腰を上げ、庭石に向けて身を屈めた。
「我々はこれまで苦労を重ねてきました。問題もいくつか抱えています。しかし、そのうちのひとつがいま、ようやく解決できました。それは共に秘密を抱えた仲間です。庭石さん、ようこそ」
伊達は右手を差し出した。しかし庭石はそれを握ることなく、両手で身体を抱いたままうめき声を上げるだけだった。
「どこかで覚悟はしていただきます。我々の仲間として、それがあなたにとって最善の選択です」
弁護士として何度もこのような要求をしてきた。伊達は心を凍らせ、震える小男を冷淡に見下ろしていた。できることなら、このような自分はマサカズに見せたくない。我ながら図々しい望みだ。そう、弁護士だったころといまのこれは似たようで異なる。右手を戻した彼は、自分が行っていることが脅迫であることをしっかりと自覚していた。そして、それがいまの自分たちが先に進むため、取るべき手段であると信じていた。
望んでいない結託に絶望しているであろう庭石のもとをあとにした伊達は、バイクを停めている駐車場に向かうことにしたが、その途中、彼は法務省のほど近くの、ある建物の前で足を止めた。
ここは、かつて何度も足を運び自分が戦場としていた東京地方裁判所である。途端に伊達は、腹の中が重苦しく腫れ上がる感覚にみまわれた。それは後ろめたさというストレスから発した変調である。そう気づいた彼は、狼狽を顔からまき散らしながら四足生物に近い姿勢で、逃げるように駆け出していった。
第5話「信じられる仲間を集めよう!」おわり
【無料版】第6話 ─ジャックされた幼稚園バスを取り戻そう!─Chapter1
二十名を越える旧友たちが楽しげに言葉を交わし、アルコールを交えた飲食に興じる。マサカズにとって、それはこれまで経験したことがない規模の宴だった。
「“ヤンマサ”くんが社長になったなんて、驚いたわぁ」
“ヤンマサ”。そのあだ名で呼ばれるのは十五年ぶりで、中学校に入ってからはすっかり耳にしなくなった。小学生のいつごろ、そして誰が付けたのかはわからない。山田正一をもじったことはなんとなくわかるのだが、ここにいる全員に尋ねてみたところで、出典について明確な回答は導き出せないだろう。参加者の中で唯ひとり椅子に腰掛け、オレンジジュースの入ったグラスを手にしていた面前の老婦人に、マサカズはちりちり頭を掻きながら「まぁ、一応は」と返した。
空手家と地下格闘王者の訪問を受けた二日後、十月二週目の日曜日の夜、マサカズは故郷の栃木県芳賀町のホテルのレストランで行われている立食パーティーに出席していた。主旨としては小学校の組単位での同窓会で、同じクラスだった三十名のうち、担任教師だった老婦人を含めた二十一名が出席し、旧交を温めていた。マサカズはシャツにデニムのジーンズといったラフな服装だったが、出席者の男性のうち何名かはスーツ姿をしていて、なんとなくではあるが現在の立場が窺い知れた。
「何人ぐらいが働いてるの?」
薄い桃色のカーディガンを羽織っていた老婦人は、小学校五年生から六年生にかけての担任教師で、当時授業についていけなくなり、段々と精彩を欠きつつあった小学校生活の終盤を優しくフォローしてくれた恩師だ。彼女は卒業後すぐに定年退職をしており、現在ではボランティア活動を精力的に行っていると、そのような近況を語ってくれた。
「あ、僕ともう一人と、あとはパートさんが四人です」
「凄いのねぇ。立派になって」
「そんなことないですよ。まだまだスタートしたばかりで、もうがむしゃらで」
「ほんと、みんなよく集まったわね」
恩師がフロアを見渡した。マサカズもそれに倣うと、すっかり大人になったクラスメイトが会話を弾ませていた。ほとんどが中学校卒業まで同じ学校に通った仲で、高校で同窓だった者もいる。高校卒業後、上京してからはすっかり連絡を取ることもなくなっていて、SNSでの繋がりを交わす者もいたのだが、マサカズはアカウント登録をしたものの利用することがほとんどなかったため、彼らの近況などさっぱりわからず、わざわざ検索するほど強い興味や関心もなかった。
「お兄さん、雄大くんは、今どうしてるの?」
その問いに、マサカズはグラスを持つ力を強めてしまった。
「兄は、わかりません。どうしているのか。どこにいるのか」
絞り出すように掠れた声で、マサカズは返事をした。彼は踵を返すと、クラスメイトたちの輪に向かった。
兄についての質問は、全て今の回答で対応してしまおう。当時一緒に遊んだ者もいたので深掘りしてくる可能性もあるが、“わからない”を繰り返すしかない。
マサカズは懸念を無理矢理抑え込むと、輪の中で際立った陽気をふりまく一人の女性に注目した。あれは新実葉月だ。小学校三年生から六年生までの同窓であり、女子の中でもリーダー的な存在感をもった生徒で、気が強く好奇心旺盛で、何事にも首を突っ込んでくる明朗な人物だった。当時から凛とした佇まいをした美少女だったが、今では健やかに成長し、薄い化粧と黄色いワンピースがよく似合う美しい大人の女性になっていた。当時、他の男子たちと同じく彼女に対して淡い好意を抱いていたマサカズは、物思いに耽った。
自分の人生の全盛期は、確か小学校四年生のころだったと思う。成績もよく、足も速く、ギャグも冴え渡り、クラスの中心的な存在だった。新実とはよく周囲からカップリングされ、大統領とその夫人などと揶揄されたこともあった。こちらとしては満更でもない気分だったが、さて彼女は当時、どのような気持ちでその扱いを受け止めていたのだろうか。今の自分は当時の輝きをすっかり失い、それを取り戻そうと懸命に足掻いてはいるのだが、現在の彼女は如何なる日々を送っているのだろうか。いくつもの疑問はアルコールの廻りを加速させたため、マサカズはテーブルにあった水の入ったグラスを手に取ると、それを一気に飲み干した。
新実の隣で笑顔を見せて周りと談笑しているのは、三条哲秋だ。小学校のころは五年生と六年生を共に過ごしたが、性格にはやや陰りがあり、クラスでも孤独な存在だった記憶がある。夏休みの自由研究では、地元の産業史についてノート三冊にも及ぶ研究資料をまとめ上げるといった、少々偏執的ともいえるこだわりを発揮したこともあったため、マサカズは彼のことを変わり者だと思っていた。しかし、小柄で痩せていた彼はもういない。三十路を迎えようとしていたスーツ姿の“三条君”はすっかり肥え太り、恰幅の良さと朗らかな様子は別人の様にも感じられる。あれが“三条君”だととわかるのはごくわずかな名残と、胸につけた名札のためだった。
それにしてもだ。新実と三条の距離が、随分と近いような気がする。二人が同じ方向を向いて周囲と話しているのも違和感がある。マサカズがそう訝しんでいると、二人は談笑の輪から離れ、彼の前までやってきた。
「やあ、ヤンマサ」
確か彼からは当時、あだ名で呼ばれたことはなかったはずだ。マサカズは一応は挨拶を返したものの、なにやら愉快ならざる不信感を覚えていた。
「ヤンマサ、久しぶり!」
三条と並ぶ新実が、当時と変わらぬ陽気さを醸し出しながらビールグラスを傾けてきたので、マサカズもそれに笑顔で返して乾杯した。
「久しぶりだなぁ、新実さん」
マサカズにそう言われた新実は、笑みに恥ずかしさを加えると、隣の三条に視線を移した。決して勘がよい方ではなかったが、マサカズは彼女のあからさまな態度にある事実を察してしまった。
「え、なになに? なんなの?」
今回の同窓会では、冒頭に現在の自己紹介をすることもなく、乾杯のあとなんとなく始まってしまった。マサカズはわからないふりをしてそう言いながらも目の前の二人がどういった間柄であるのか、当にわかってしまっていた。
「結婚したんだよ。僕たち。三年前」
新実と三条が三年前に結婚した。クラスの太陽と、かつては日陰の雑草が。人生とは何がどうなるかわからない。自分も相当でたらめな力を得てしまったが、三条が得たのはそれを上回る破格の伴侶だ。マサカズは何がどうしてこうなったのか知りたくなったが、同時に生々しさが気味悪くもあり想像したくもなくなった。ただ、あらためて見ると彼女の名札には『新実(三条)』と記されていて、そこに注意が向けられなかったのは、新実があまりにも変わっていなかったからだった。
「じゃあ、しばらく二人でどうぞ。当時の大統領とその夫人だもんな。葉月、キミから色々と話しておいて。僕はちょっと疲れたから隅で座って食べてるよ」
そう言い残すと、三条はわざとらしく太鼓腹を叩きながらテーブル席に向かっていった。残された二人は目を向け合ったが、マサカズはなんとも言いがたい気まずさを感じていた。
「説明すっからね。あのね。色々あったんだけど、大学出てからこっちに戻って就職したら、同じ会社で哲秋と一緒になったの。あの通りすっかり見た目も印象も変わってたから、最初は気づかなかったんだけど、彼の方から声をかけてきたの」
「ああ、三条くん、別キャラって感じだ。太ったし、明るいし」
「ヤンマサは、あんまり変わってないね。あ、でも社長なんだよね。サイト見たよ」
「一応だよ。ま、けど法務省から仕事をもらったりしてるかな」
娘の違法行為で脅迫し、やり遂げたのは今のところ山奥での運搬業務だ。これは空虚な自慢に過ぎない。言ってしまってから、マサカズは軽い自己嫌悪に陥った。
「官からお仕事請けてるの? うわっ! ヤンマサ社長、すごいじゃない」
「あー、とは言え……その……あ、新実……さん?」
「今は三条かな?」
新実こと三条はショートヘアをひと撫ですると、マサカズから視線を外した。
「じゃあ、三条さんかな? ウチはまだまだ小さい零細だし。そんな大したものじゃないよ」
「けど、スローガンは社会貢献とか人助けなんでしょ?」
「あれは、うちの副社長のアイデアなんだ。元弁護士の凄い人なんだ」
マサカズの言葉に、三条夫人は目を輝かせた。彼女から溢れんばかりの生気を感じたマサカズは、すっかり気圧されてしまい、少しだけ退いてしまった。思い出してしまう。これは当時の輝きのそのままだ。
「なんだかさ、ヤンマサってすっかりテイスト上げちゃってるんだね! いずれは宇宙とか行っちゃいそう」
今もやりようと工夫によっては、着の身着のまま宇宙に行けないこともない。想像したものの、あまりにもくだらなく思えてしまったため、マサカズは吹き出してしまった。
「よくこんな風にバカ言い合ってたよね。ウチら」
「だよだよ。そーだった。特に四年生のころは」
「わたし、ヤンマサの家にも遊びに行ったもんね」
「あー、来た来た。三井さんとかと一緒に」
「ヤンマサは、誰かいい人とかいないの?」
「唐突な質問だと思うけど」
「だって、気になるじゃん。やっぱり。ウチら仲良しだったし。今のヤンマサが幸せなのか、すっごく」
クスクスと笑いを交えながら、彼女はそう言った。マサカズはグラスのビールを少しだけ呑むと、ため息を漏らした。
「いい人とか誰もいないよ。そしていまの僕は三条さんほど幸せじゃないかな。不幸ではないけど」
「え、わたしって幸せに見える」
「そのものって感じ。旦那といい感じなんだろ?」
「まーねー! バレたかー!」
屈託のない満面の笑みだった。彼女はあのころから迷い間違わず一直線に駆け抜け、この底抜けの幸せを手に入れたのだろう。高校卒業後の進路を誤り、顧客や従業員への倫理観が破綻した企業で身も心も摩耗し、すっかりくたびれてしまった自分は、ここから彼女が得たような充実を掴めるのだろうか。笑い返して二度目の乾杯をしつつ、マサカズは隅のテーブル席でフライドチキンを貪る同窓生を横目で窺い、その憂いの感じない様子を少しばかり羨ましく思った。
【無料版】第6話 ─ジャックされた幼稚園バスを取り戻そう!─ Chapter2
十月も中旬に入った水曜日の昼過ぎ、伊達は柏城法律事務所の応接室にいた。応対した後輩の男性弁護士に土産として手渡したのは、新宿のデパートで購入したバームクーヘンだった。地下の食品売り場ではなく、八階のレストランフロアに店舗を構える、銀座の本店が大正時代に創業した老舗の洋菓子店であり、洋菓子では唯一、宮内省御用達のお墨付きを得ている有名店である。それでいて、いちホールあたり二千円を下回るリーズナブルな価格で、柏城のお気に入りの一品だった。
三ヶ月ほど前まで、自分はこの部屋を顧客対応のため、所属弁護士として使っていた。そして今では仕事の世話を受ける業者として、客として訪れている。変転した立場は、テーブルを挟んで座る位置が反対側になったことでよくわかる。たったひとりで待つことから実感できる。
「おお、バームクーヘン、ありがとうな」
そう言いながら部屋に入ってきたのは柏城所長だった。彼は伊達の向かいに座ると、口元に笑みを浮かべた。
「どーやったんだ? 庭石から仕事を取れるなんて、ちょっと驚いたぞ」
「企業秘密です。って、オヤジが意外そうにしてるのが、ちょっと心外です」
「そりゃ、紹介した以上、俺にしてもお前たちに勝算があるって見込みもあったわけなんだが、正直なところその確率は……」
柏城は顎に手を当て、視線を宙に泳がせた。
「出てこねぇな。いい喩えが。とにかく、お前たちが庭石を御せたってのは、俺にとって驚きだったってわけだ」
娘の覚醒剤購入と使用の情報を入手し、それを以てしての脅迫によって、柏城が困難と思っていたミッションは達成された。彼はそういった絡め手の想像をしているのだろうか。伊達は緊張感を高め、湯呑みの茶を飲んだ。
「正攻法じゃないんだろ?」
やはり、そういった筋道を想定するのか。それはそうだろう。このベテラン法律家は、正解に辿り着く術を知り尽くしている。ごまかしの虚言でお茶を濁すのも無駄だと思った伊達は、柏城の目をしっかりと見据え、両指をテーブルの上で組んだ。
「当たり前です。我々程度の雑魚が、なんの武装もせず法務官僚にまともな取り引きができるはずもありません」
「だろうな。でだ、どんな手かはまぁどうだっていい。好きにすりゃいいんだからな。俺が気になっているのは、山田だ」
「と、言いますと?」
「お前の考えた手、どうせえげつないやつだと思うし、でなけりゃ庭石には勝てねぇ。しかし山田はそれに反対したんじゃねぇのかって思ってな」
「さすがはオヤジさんですね。ええ、その通りですよ。マサカズは嫌がりました。けど、最後には賛成し、一緒に立ち向かいました」
「気を付けろ。お前とあいつの相性は最悪だ。お前のやり方が過ぎると、いずれは対立する」
「それはわかっていますよ。でも走り出した以上……」
これ以上の自己正当化は暴走とも言える。そう思った伊達は言葉を止めた。柏城は笑みを強くすると、目の前にあった湯呑みを手に取り、音を立てて茶を啜った。
柏城への挨拶を終えた伊達は法律事務所を出た。恩師の助言は、伊達にとって今後の課題としなければならない内容だった。庭石を脅すのは、あくまでも一時的な手段に過ぎない。ここで実績を作れば今後、公的機関を通して社会的により大きな貢献を果たす役割を担うことができるはずである。過程にさえ目をつぶればマサカズにとっても望ましい結果が得られると見込んでいる。だからこそ、庭石への対応は見直したくなかった。だが、それが原因でマサカズとの関係が悪化するのは避けたい。そうなると、できるだけ迅速に結果を残していくだけだ。伊達は簡潔な結論に達し、歩みを速め坂道を下った。
次の用事のため、伊達は柏城法律事務所から五分ほど離れたゲームセンター『エンペラー』に向け、歩いていた。すると、ひとりの女性が坂道を上ってきた。空色のセーターを着た伊達と同年代の彼女は、彼の前で立ち止まった。ロングヘアーで細い目をしたその女性は、愛想笑いを浮かべて伊達の胸を掌で軽く突いた。
「あれれ、伊達ちゃんさん?」
伊達は自分の運のなさを感じながら、辟易としてその場を去ろうと背を向けた。
「なにしに来たの?」
女性は長い髪を撫でつけると、伊達の背中に早口をぶつけた。
「オヤジに挨拶だ」
伊達もキッパリとした口調でそう返した。
「ふーん。そうそう、笹本ちゃん、離婚したんだって。伊達ちゃん知ってた?」
伊達は素っ気なく、「知らねぇ」と答えたが、去ることはせずその場に立ち止まったままだった。
「オヤジが言ってた通りだよね。やっぱ、しくじった」
「原因はなんだよ」
「旦那の浮気。三股かけてたんだよ。よりさ、こっち向いてよ。なんかヘンな感じじゃん」
促されたため、伊達は振り向き、女性はその顔を覗き込んだ。
「あー、伊達ちゃんいい感じだ」
「相変わらず適当だな」
「言わないでよー。わたしの直感はオヤジ公認なんだよ」
「根拠がないんだよ。お前のそれは。なのに当たるから気味が悪い」
伊達と向き合うこの女性は木内という名の柏城法律事務所に所属する弁護士であり、伊達にとってはかつての同僚に該当する。幾度も同じ案件を担当した仲間で、能力としては申し分なかったのだが、無作法に踏み込んでくる態度はどうしても好ましくは思えず、プライベートでは避けてきた人物だった。
「笹本さん、いまどうしてるんだ?」
「知らないけど、熊本に帰ったっぽいよ。あっちの事務所に行くみたい」
「“知らない”わりには知ってるな」
「保険、保険。このネタ、間違ってる可能性も高いし」
「そうか。それじゃ次の用件があるから、ここで」
「えー? 笹本ちゃん情報、まだあるんだけど」
「俺に関係したことか?」
問われた木内は、人差し指を唇に当て、身体をくねらせた。
「んー、んー、ない」
「じゃあな」
伊達は片手を挙げると、この場から立ち去った。
「これ、概要説明いります? レベルとしちゃ、結構なネタですけど」
「いや、いらない」
ゲームセンター『エンペラー』にて猫矢と待ち合わせた伊達は、封筒を受け取った。
「山田社長は一緒じゃないんですね」
「ああ、マサカズは今日、家で休んでるよ」
「ってことは、あのパワー使ったんですね」
「そういうことだ」
伊達は猫矢に対して、必要以上の言葉を交わさないように心がけていた。彼に対して情報収集のプロとしては信頼していたが、信用の鍵はかけたままにしていた。猫矢はハンチング帽を目深に被り直すと、周囲のゲーム筐体に目を移した。
「ゲームかぁ。俺、スマホのぐらいしかやんないんですよね」
興味のある話題だったが、伊達は口を閉ざしたままだった。
「なんか、オススメのとかないですか? ここ、伊達さんとの待ち合わせ場所だし、これからもよく来ることになるわけですし」
人懐っこい笑顔を貼り付かせ、猫矢は手を後ろに回し、伊達の周囲をくるくると巡った。
「たぶん、君が楽しめるようなゲームはここにない。コインを入れる期待感と緊張感、そのゲームの作法を知っていく面白味、上達していくことへの満足感、できないことへの挫折感、そのいずれもが高度な感受性を要する」
「えー? それって俺がニブいってことですか」
言い過ぎてしまった。ゲームのことだったので、つい自我が鎌首をもたげてしまった。伊達は不貞腐れた猫矢に「とてもすまない」と言い残すと、シンプルな電子音の波の中、ゲームセンターを後にした。
「資本金を一千万円に増資しました」
時刻は夕方にさしかかり、日比谷公園の優しくライトアップされた噴水を前に、伊達は庭石にそう告げた。
「なんのこと?」
「資金調達をしたんです。三千万円ほど」
「どうせまともな手段じゃないんだろ」
「ええ、資金洗浄で得たものです」
「だからなんのこと?」
「仲間である庭石さんには、隠し事を極力避ける必要があると思いまして」
庭石はため息を漏らすとその場にしゃがみ込んだ。見下ろした伊達は、小さく痩せた庭石が、ゲームに登場する亜人の一種のように思えた。
「伊達くん。君のキャリアを頼って相談したいことがあるんだが」
俯いたまま、膝を抱えた庭石はそう告げた。
「いいですよ。こちらで乗れる内容でしたら」
快諾した伊達に、庭石は顔を上げた。その頬は引き攣り、口元は歪み、目は潤んでいた。
「ヤクだよ。どーすればやめさせられる? 検察官はヤク中をムショ送りで終わりだが、君ら弁護人はアフターフォローをすることだってあるだろ?」
「つまり、娘さんの件ですね」
「お前らに言われてから様子をこっそり観察してんだよ。そしたら当てはまりまくりなんだよ。あれやこれや」
「そうですか」
「どーすりゃいいんだよ。このままじゃ四度目は確実だ」
「ですね」
「どーすりゃいいんだよ」
庭石は再び俯いた。伊達は鞄から、ゲームセンターで猫矢から受け取った封筒を取り出すと、庭石の隣にしゃがみ込み、それを手渡した。
「四度目は確実じゃなくって、もう過去の出来事です」
伊達は抑揚のない口調でそう告げた。庭石は封筒から『調査報告書』と書かれた書類を抜き出すと、それを一読した。彼はその場で四つん這いになり、嗚咽を漏らした。
「娘さんの購入ペースは上がってますね。こうなると五度目は年内にも起こるでしょう。」
「売人を始末してくれぇ……」
「いやいやいや、庭石さんが一番良くご理解のほどでしょ。中毒患者はどんな手を使ってでもクスリを手に入れますよ。売り手なんて星の数ほどいる。ご存じでしょ?」
「こんなの、イヤだよ。知らせてくれるなよ」
声を震わせ、目からは大粒の涙をこぼれ落とし、庭石は子供の様に嘆願した。立ち上がった伊達は仏頂面を崩さぬまま、震える法務官僚を冷淡に見下ろした。
「えっとですね。これはアフターサービスです。知っておいて損ではないと思いまして」
それは虚言だった。井沢への調査依頼は庭石を今以上に追い詰める目的であり、決して彼に対して手助けをするつもりはなく、できることもないと考えていた。
「こちらについちゃ、娘さんの件とは真逆で間が空くのはよくありませんね。週末の浜松の様に更なる案件、期待していますよ」
庭石の背中を軽く指先で叩くと、伊達は噴水を背に歩き始めた。
公園近くの駐車場までやってきた伊達は、停めておいたバイクに跨がった。今日は三件の用事を済ませた。ひとつは恩師への挨拶、ひとつは情報屋との接触、そして最後のひとつは脅迫である。たまたまの不在ではあったが、マサカズがいたらどういった変化が生じていたのだろうか。特に庭石に対して自分でも驚くほど冷淡な態度をとれてしまったが、あのちりちり頭の彼が同席していたら、なにか違った様相を呈していたのかもしれない。そしてそれはおそらくだが、自分の気持ちにもう少し丸みを帯びさせ、朗らかなものにしていたのだろう。だが、仕方がない。今晩の結果を以てして、次に進むだけのことだ。伊達はヘルメットを被ると、バイクのキーを差し込んだ。
【無料版】第6話 ─ジャックされた幼稚園バスを取り戻そう!─Chapter3
庭石が家畜のように這いつくばった次の日、マサカズは板の上に棒立ちで佇んでいた。真山の頼みを受け、市ヶ谷駅近くの雷轟流空手道場の三階建ての本部ビルを訪れたマサカズは、その最上階にて磨かれた板張りの床上に在った。対するのは漆黒のカンフースーツに身を包んだ、身の丈二メートルを超える体格に恵まれた禿頭の青年であり、その左目は潰れていた。二人の周囲には成り行きを見届けるため、胴着を着た道場生たちや真山、そして瓜原の姿があった。真山はすうっと息を吸い込むと、広い道場の隅にまで響き渡る声量で叫んだ。
「山田クン! いまキミが対しているのは狸王拳第六十七代継承者、尾之花紅化殿だ! 狸王拳は中国拳法を源とした流派である。かつて雷轟流空手を代表して自分も挑んだが、圧倒的敗北を喫した! 以来、尾之花殿とは奇妙な友情が生まれ、今では雷轟流空手の特別師範として我々に武を導く存在となっている!」
よく通る声だ。マサカズの抱いた感想はたったそれだけで、真山の言葉はなにも頭の中に入ってくれなかった。なぜなら、聞いて、理解して、消化する意味が全くないと思っていたからだった。それよりも今は大勢の前に板の上に裸足でいることの方が気になる。
九歳の夏、あのときも裸足で、身に着けていたのは水泳用のパンツだけだった。重さを伴うと錯覚するほどの暑さの中、プールサイドで戸惑っていたのをよく覚えている。彼女は授業で見る紺の単色ではなく、カラフルなワンピースの水着を身に着けていたからだ。
「ヤンマサじゃん!」
「新実さんじゃん」
ここは地元の市民プールであり、連日の暑さから考えれば違和感もない遭遇だった。しかし、見慣れない彼女の水着で心をかき乱されていたのを思い出される。
「ヤンマサはひとり?」
「ひとり。新実さんも?」
「うん。葉月でいーよ」
「あ、いや、うん」
そう、戸惑いの連発だった。結局、その日もその先も彼女を“葉月”と呼んだことはないはずだ。
一緒に泳いだり、すっかり別々になったり、その日は微妙な距離感を保ったままだったのだが、偶然なことにプールから帰るタイミングが重なったため、彼女とは出口で数十分ぶりに言葉を交わすことになった。ひぐらしの音が降りそそぐ中、彼女は露店で買ったアイスキャンディーを手にしていた。
「ヤンマサは、ヒーローものとか見るんだ? 日曜日の朝にやってるの」
「もう見ないよ。ガキじゃねーし」
偽りである。毎週ではないが、タイミングしだいで見られれば見る。
「あ、そーなんだ」
「マンガやアニメは見るよ。深夜のとか」
「うわ、ヤンマサってエッチなんだ」
彼女は、どこか嬉しそうな様子だった。
「じゃねーよ。バトルものとかだよ」
これもまた、偽りである。バトルだけではなく、性的な興奮が得られるものも親に隠れて見ていた。
「ふーん、じゃーけっこう大人なんだね」
「当たり前じゃん。もう十歳なんだぜ」
「あ、わたしはとうに十歳だよ。ヤンマサは十一月だよね」
「年上ムーブか?」
「そんなんじゃないけど。わたし、ヤンマサよりちょっとお姉さん」
はにかんだ笑顔だった。それが、ひどく眩しかったことはよく覚えている。同窓会での再会で、記憶のどこかが鮮明化されたと思われる。裸足で人に囲まれただけで、胸騒ぎを伴う思い出が発掘される。
「俺を一瞬で屠ったあの狸王拳、臆・十三連撃も通じんのかっ! 微塵もっ!?」
左から、真山の叫びが耳に入ってきた。目の前では、身構えた隻眼禿頭の大男が呼吸を整えていた。彼の表情には明らかな驚きが貼り付いており、マサカズは市民プールでの淡い記憶を思い出しているあいだ、何が起きていたのかようやく把握した。おそらくだが、この六十何代目とやらの攻撃を受けたのだろう。アンロックしたこの身には何も感じることはなかったが、周囲のざわめきや対面する男の様子からそう察するのが自然である。
今回は、どういった落とし所をつけよう。恨みなどない相手だから、怪我はさせたくない。なんとか穏便な解決策を導き出さなければ。今日はまだ昼前なので、このあとは事務所に戻ろう。その前に昼飯はどうしよう。この市ヶ谷でいいお店はないだろうか。この道場の誰かに聞いてみるか。マサカズが周囲に目を向けると、そこには胴着を身に着けたポニーテールの少女がいた。
中学二年生のころ、新実葉月は長くなった髪をポニーテールにまとめていた。中学校の三年間で彼女とは一度も同じクラスにはならず、話す機会もなくなりすっかり疎遠になっていた。だからこそ、二学期の終わりの曇り空の中、下校した際の偶然が印象深く思い出される。紺のブレザー姿の彼女は、急に背後から声をかけてきた。
「山田クンだよね?」
振り返ると彼女がいた。息が白く、駆けてきたことがなんとなくだがわかる。
「新実さん?」
「そーだよ、久しぶりー!」
「三年の高知さんと付き合ってるんだよね?」
それはなんとなく伝え聞いた噂話だった。今にしてみると、なぜあのような唐突で失礼な確認をしてしまったのだろう。
「うわぁ、なんで山田クンが知ってるのよ〜」
あからさまに、気味の悪さを顔と声で顕していた。
「別に。なんとなく。で?」
なぜ、念押しの確認をしてしまったのか。
「うん、先月から。あっちからコクってきたんよ」
「ふーん、どんな感じ?」
「デートとかまだだよ。あ、クリスマスに映画行こうって」
「なに観に行くの」
通学路の住宅街を並んで歩いていたはずだが、詳しい場所までは思い出せない。ただ、彼女の息が白いことだけはよく覚えている。
「えっとぉ……なんだっけ?」
「俺に訊くなよ」
中学二年生のころは、本当にひどい有様だった。成績も落ち込む一方で、両親との関係もぎくしゃくし、兄とも対立し、なにより身体の変化に心がついていけず、大人になろうとしていたのに準備が間に合わず、自分が得体の知れない怪物になってしまうのではないかと怯えていた。だから、異性とまともなコミュニケーションもとれない。今ならもっとましな会話もできるはずだ。
「訊いてなんかいませーん」
「訊いたよ」
「からむなぁ」
「からんでない」
「まーいーや。ヤンマサはさ、誰かと付き合ったりしてるの?」
急に呼び方が昔に戻った。あれはなんだったのだろうか。
「どうだっていいだろ」
「ヤンマサ背も伸びたし、けっこうイケメンだもんね」
「うるせーな」
「いるんだ? 彼女」
「いねーよ」
なぜ正直に答えてしまったのだろう。そして、その返事で彼女の足が止まったのが意外だった。
「なんだよ?」
「へぇ、ヤンマサってばフリーなんだ」
「だからなんなの? 新実さんに関係ないだろ?」
「いやぁ。確かにそーなんだけど。あー、あー、あー」
奇っ怪なリアクションだった。彼女は曇天を見上げ、その表情は強ばり、学生鞄の持ち手を握る手には力が入っていたように見えた。
「へんなヤツ」
そう言い残し、彼女を置き去りにして帰ってしまった。そしてその後はあの同窓会まで話す機会は訪れなかった。
道場は、そこにいた人々の驚愕の声によって騒然となっていた。それによりマサカズが中学生時代の思い出から現実に意識を取り戻したところ、カンフースーツの六十何代目が足元に倒れていた。
「真山館長! 今のは?」
ジャージ姿の瓜原が隣の真山に尋ねた。
「知らん……が……俺も初めて見る技だが、おそらくアレは狸王拳最終奥義、金色だ。全てのエネルギーを掌に乗せ、寸勁の要領で敵の急所へと放つ。金属の扉ですら粉砕するとオヤジから聞いたことがある。凄まじき技だがその反面、放った者の消耗は著しく、最悪の場合、意識を失うらしい」
「じゃあ、あの人ガス欠っスね」
「うむ……ともかく手当をせねばならん」
何事か皆目見当もつかないマサカズは、カンフースーツに駆け寄る真山たちをただ傍観するだけだった。ともかくだが、鍵のアンロックによってこの望まぬ戦いは決着したようである。この界隈では神と崇められる最強の存在が全力を以てして勝利を得られなかったのだから、この茶番劇とも言える無駄な時間もこれで終わるのだろう。マサカズはそれだけが嬉しかった。
【無料版】第6話 ─ジャックされた幼稚園バスを取り戻そう!─Chapter4
春よりも秋の風が好きだ。春は夏を告げ、秋は冬を知らせる。秋風は暑さへの労いと、これから訪れる厳しい寒さへの気配を運んでくれる。春風は寒さを紛らわし、この先のひどい暑さを警告してくれる。あくまでも自分の好みでしかない。だが、秋の風が好きだ。労われるのがとても心地がいい。
静岡県は浜松という、初めて訪れた駅前広場で秋風に晒されたマサカズは、そのようなとりとめのないことを思っていた。背後にはライトバンが停まっており、その天面に設置されたお立ち台にはマサカズもテレビで見たことのある二人がいた。ひとりは男性の元アナウンサーであり、もうひとりはニュースによく登場する老齢の財務大臣だった。
第六十何代目かのカンフースーツが、よくもわからないまま究極奥義とやらで失神してから二日が経った土曜日のことである。マサカズは庭石の紹介でこの仕事に就いていた。その業務内容は浜松市長選挙運動期間最終日に行われる浜松駅前広場での演説会の警護で、この日の彼は、およそ十年ぶりとなるリクルートスーツにネクタイ、革靴を着用し、黒服の同業者たちとともに周囲を警戒していた。伊達からは演説の一時間、じっとその場に立っているだけでいいと言われていた。何があっても何もせず、それらしく過ごしていればいいと。
「ですけど、もしも不審者とかいたら、鍵の力でやっつけた方がいいんじゃないんですか?」
この仕事を依頼された五日前の夜、事務所でマサカズは伊達にそう尋ねた。
「やめとけ。素人判断じゃ間違いを起こすことになる」
「いや、たとえばナイフとか持ったやからが突っ込んできたりしたら、そりゃもう勘違いのしようもないでしょ」
「それはそうだけど、うっかり鍵の秘密を白日の下にさらすようなことになりかねないぞ。当日は警察関係者も多くいる。民間警備会社も精鋭が配置される。つまりだ、お前は目の利くドリームチームのただ中ってことだ」
「なんか、おかしくないですか?」
「おかいしいよ」
「やです」
「仕方ないだろ」
「そりゃ、山奥の仕事は嫌がりましたけど、重要人物の警護なのに、力を使っちゃいけないなんて、間違ってると思うんですけど」
「なら、俺が替わる」
「それは、もっと嫌です」
マイクを通して聞こえてくるのは、背後のお立ち台に立つ静岡地方局の元アナウンサーが、いかに浜松市長として相応しいかの美辞麗句だった。財務大臣の熱弁は時間が経つにつれヒートアップしていたが、言っている内容がこの浜松という都市に紐付いたものだったため、よそ者のマサカズの心には響かなかった。
納得できない仕事ではある。しかし、それでも社長として職務は全うしなければならない。伊達はこの仕事は利益こそ僅かだが、今後において大きな実績になると言っていた。何もしてはならないが、それでも不審者を発見して警備責任者に報告すれば、より大きな功績となって、会社の未来を明るくすると思える。広場に集まり財務大臣を注目していた五十名ほどの聴衆たちに、マサカズは鋭い目を向けていた。
現役の大臣のボディーガードなど、本来なら請け負えるような業務ではない。それは無知なマサカズでもなんとなくはわかっていた。庭石はこの案件を自分たちに回すため、かなりの絡め手を使ったはずとしか思えない。それについてマサカズは庭石の負担を心配したのだが、伊達の返答は「官僚はそんなにヤワじゃない。しかも庭石は検察上がりだ。あいつらは相当だ」であり、自分よりずっと官僚に近いと思しき弁護士の言葉だったので、それについてはひとまずだが納得するしかなかった。
それにしても老人が多い。全体の四割が七十代を超えているように見える。そのためか、どこか空気は緩く淀み、財務大臣の熱弁は空回りし、秋空へと吸い込まれていくような気がした。
伊達から伝えられたこの仕事についての情報は、日時、場所、職務内容だけだったので、マサカズは守るべき対象のプロフィールも検索してみた。市長候補の元アナウンサーは昨年まで午後のワイドショーの司会も務めていて、テレビで見たこともある、エネルギッシュでパワフルさを売りにした中年男性だった。かつては女子アナウンサーとの不倫疑惑で謝罪会見を開いたこともあったのだが、マサカズにとってそのスキャンダル自体、今回の検索で初めて知るほど興味の範疇の外での出来事だった。
そして、本日の主役と言ってもおかしくないほどの存在感を見せつける応援弁士の財務大臣は、民間起業だったらとうに定年を迎えた老境に達している重鎮で、これまでに失言を多発し、その都度他人事のような態度でのらりくらりと批判をかわしてきた政治家である。どちらかと言えばあまり関わり合いをもちたい類の人間ではなかったが、彼を危険から守るのが今回の仕事である。マサカズは自分の好みを隅に追いやり、警戒に徹していた。
ダメだ。いや、この場合はかえってよいのか。テロリストなどいるはずがない。いや、どうなのか。マサカズは緊張感のないこの空間に、無法の気配を察することはできなかった。プロのボディーガードなら、なにか発見できることがあるのだろうか。例えば自分のすぐ右隣で同じように後ろで手を組むこのスーツ姿の若い女性は、眼鏡越しの鋭い眼光で既に周辺の異変を察知しており、なんらかの動きがあれば即座に然るべき対応をする準備を整えているのだろうか。いや、前提自体が破綻している。そもそも異変自体が起きていないかもしれないのだから。マサカズは考えるのが面倒になったが、それでも警戒すること自体は怠らなかった。
一時間ほどして、財務大臣の応援演説は終わった。まったくなにもなかった。ただ喋り、拍手があり、聴衆はそれぞれ次の目的のため解散し、テロリストの摘発もなく、ドラマのような出来事は起きなかった。それこそこれがドラマであれば、この一時間はまるごとカットされるだろう。警戒の緊張より、退屈による疲労の方が強いと思われる。マサカズは大きくため息をもらすと、お立ち台から降りてきた二人がセダンカーに乗り込んでいくのを見届けた。
「えっと、山田さん」
そう声をかけてきたのは、右隣で警備を担当していた田宮という名の女性だった。彼女とは演説が始まる一時間前のミーティングで顔合わせをしていたが、声を聞くのは初めてのことだった。
「はい」
「お疲れ様」
「あ、はい。もう終わりなんですね」
「ええ、事務手続きを済ませれば解散です」
「いやー、何事もなくてよかったですねー」
「ええ、ちょっと何人かは、アレっていうのはありましたけど」
“アレ”とはおそらく不審者を意味しているはずだ。つまり、自分がまったく気づけなかった異変をプロの彼女は察していたということになる。己の間抜けさを、マサカズはあらためて感じた。
「後学のためってやつなんですけど、誰と誰が怪しかったです?」
「やたらと鞄に手を突っ込んでいた男とか、しょっちゅう背伸びして距離感を測ろうとしていた男とか……」
そのような怪しげな者がいたとは気づかなかった。いや、気づいていたのかもしれないが、それらを“怪しい”と認知できなかっただけのことだろうか。マサカズは何やら忸怩たる思いにかられ、ちりちり頭を掻いた。
「それよりなんですけど、山田さん、どうやって今回のお仕事受注できたんです? 今回は三社が参加しましたけど、ウチともう一社の共和さんは一応この業界では実績もありますし、社歴も長いです。正直言って、山田さんのナッシングさんは、大変申し訳ないのですが、あまり存じ上げないというか……」
なるほど、声をかけてきた理由はそこか。伊達とも事前に想定していた状況だったため、マサカズはネクタイを締め直し、落ち着いた態度で咳払いをした。
「法務省にコネがあるんですよ。まぁまだお試し期間ってところですけど」
「へぇ」
田宮は目を輝かせると、腕を組んだ。
「山田さん、このあとどうです? お茶でも行きません?」
この展開も伊達と想定済みである。マサカズは掌を田宮に向けた。
「いえ、このあとも仕事が入っているので、すみません」
同業者は“コネ”に対して興味を抱き、かなりの確率でそれを探ってくる可能性がある。無論、それには最大限での防御をしなければならない。
「あ、じゃあ後日いかがです?」
食い下がってくる。さすがは老舗の警備会社だ。鋭い目をし、スポーツ選手のように均整の取れたスタイルをした田宮は、好みの範疇に入る容姿をした異性ではあったが、秘密を守るためには下心が介入する余地もなく、マサカズは心の扉を固く閉ざした。
「あ、はい、いずれまた」
精一杯、取り繕う言葉でごまかしたマサカズは、事務手続きをするため現場の責任者を求め、その場から駆け去った。力こそ使えなかった。しかし、それがあるからこそいられるはずもない現場に居場所があり、なにかがあってもどうにでもできるという自信をもとに挑めた。マサカズはそれが確かな一歩だと思えた。
【無料版】第6話 ─ジャックされた幼稚園バスを取り戻そう!─Chapter5
財務大臣の応援演説に伴う警護という大仕事から一転し、マサカズが次に担ったのはスケールが小さく、それでいて命に関わる重大な職務だった。創業以来なにかと縁がある廃棄物処理業者の保司から回されてきたその仕事の概要説明書類の冒頭には、『幼稚園バス降車見守り』という名目が記されていた。事務所で書類を目に通したマサカズは、伊達に向かってその業務内容をあらためて確認した。
「一時間以内に五件の幼稚園を回って、送迎バスに残された子供がいないかを確認するんですよね」
「ああ、時間的には自転車でギリギリなんとか回れるはずだ」
「あれ、でも確かなんかブザーとか、安全確認装置でしたっけ、バスへの取り付けが義務づけされたんじゃないですか? 前にニュースで見ましたけど」
「現実には間に合ってない」
「うわ、やっぱりそーなっちゃってるんですね」
「児童回りの類はなにもかもがそうだよ。理想と現実の食い違いが顕著だ」
「段取りとしてはこうですね。バスの鍵を幼稚園で受け取って、バスを確認して、子供が居残ってたら園の人に報告する。居残ってなくても報告する。そして鍵を返却する」
「ああ、それでいい」
伊達の素っ気ない返事に、マサカズは下唇を突き出し、あからさまに顔を顰めた。
「なんか、外部に依頼する仕事じゃないような気がするんですけど」
疑問を口にしたマサカズに、木村が席を立った。
「安全装置の不備に対して、我々のような外部業者の手を借りることで急場の対策を取り、親御さんたちを安心させる意図があるのだと思いますよ」
「うーん、木村さんの言ってることもわかりますけど、ならとっとと安全装置付けた方がいいと思うんだけどなぁ。だって義務づけなんでしょ?」
「その場しのぎには、しょーもねぇ事情があるんですよ社長。取り付け業者や安全基準を確認する役所のスケジュールが空いてねぇとか、急な施策でそもそも物品自体が不足してるとか。けど子供の命ってこたぁ、優先順位ってもんが高い。だからこんなわけわかめなお仕事も発生しちまう」
マサカズの疑問に答えたのは浜口だった。充分すぎる内容に、マサカズは納得するしかなかった。
「伊達さん、最後に質問なんですけど」
「なんだ?」
「なんで廃棄物業者の保司さんが、このお仕事紹介してくれたんです? なんだか関係がえらく遠いって感じですけど」
「知らないよ。それに気にする必要もない。あの人は顔が広いからな」
想像もできない人間の関わり合いというものがある。これまでの人生で自分が知りうる範囲は実に狭く、単純なものだ。それは自覚していたのだが、やはり廃棄物処理業者と幼稚園では接点が思いつかない。古くなったバスの廃棄絡みだろうか、それともたまたま呑み屋で知り合った縁なのか、はたまた親類づきあいか。マサカズは考えを巡らせてみたが、どれもが正解で、どれもが正解で、どれもが不正解のような気がしたため、
十月最後の金曜日の朝、マサカズは自転車で五件目となる最後の幼稚園に辿り着くと、職員からバスの鍵を受け取った。足立区の住宅街の中にあり、外から見る施設からは幼児たちの気配は感じられなかった。最近では近隣住人の苦情も多いため、できるだけ大人しくさせているとの話も事務所の老人たちから聞いていた。自分のころなどは田舎ということもあり、幼稚園ではよく大騒ぎをしていたものだ。そう言えば、新実葉月も同じ幼稚園に通っていたはずだが、クラスが異なってたのだろうか思い出がない。そのようなことを考えながら、マサカズは幼稚園に隣接する駐車場に向かい、停めてあったバスに乗り込んだ。
取り残された園児はここにもいなかった。今日これまでに巡った四件も全てにおいてがそうだった。なにも問題がなく、平穏無事という結果だ。
それにしてもだ、遂に鍵の力がまったく関係しない仕事まで請け負うようになったのか。マサカズはそう思うと苦笑いを浮かべてしまった。財務大臣警護においては最悪の事態が発生した際には、アンロックして暴漢に立ち向かうつもりだったが、この仕事の場合、有事においては園のスタッフに報告するのが最善であり、怪力や跳躍はまったく役立てない。これからはこういった内容も増えていくのだろうか。少々物足りなくも思えるが、それはそれで秘密の漏洩といった不安もなく精神的な負担もない。浜松で知り合った田宮の鋭利な視線を思い出しながら、マサカズは幼稚園に向かった。
「問題なしです」
幼稚園の入り口でマサカズがそう報告すると、幼稚園の従業員であるエプロン姿の若い女性が笑みを浮かべた。
「助かりますぅ。来週もお願いしますね」
礼を言うと、女性は書類を貼り付けたバインダーをマサカズに手渡した。園内からは児童たちの元気な声が響き渡り、それは普段子供とは縁の遠いマサカズにとって新鮮な音色だった。外から察することができなかったのは、おそらくだが防音がしっかりと機能しているからだろう。マサカズは渡された安全確認の書類に、認め印を捺印した。
「あの、なんですけど」
どうしても聞いておきたかった質問を、マサカズは口にした。
「園児の降り残し、そちらの方でも確認してるんですよね」
その問いに、女性の笑みは苦いものへと変化した。
「はいぃ……やってます」
「いや、僕の仕事がムダとか、そういったことを言っているわけじゃないんですけど。その一応、だよなーって思ってしまいまして」
「ええ、やっぱりどうしても外部の方の確認がないと、ご家族の納得というものが得にくくって。だから、本当に助かります!」
納得と安心を作る仕事というものを、マサカズはこれまでに経験したことがなかった。物品を販売。顧客の質問やクレームへの対応。そして建築物の破壊と運搬。財務大臣の警護。最近では遂行する内容の幅こそ広がっていたが、この幼稚園バスの見守りという名のアリバイ作りのような職務はなんとも腑に落ちない。これにかかる費用を、たとえば目の前で恐縮する彼女や従業員たちの給与に充てれば、よりよい教育環境を整えられるのではないのだろうか。そこまで考えたマサカズだったが、さすがに出しゃばりが過ぎると感じため、気持ちを切り換えて幼稚園を後にした。
東京の中心地からの方角として、この足立区は現在住んでいる江戸川区と同じ東側に位置していたが、マサカズはこの西新井という土地を訪れたのは今日が初めてだった。そろそろ飲食店が開店する時刻であり、事務所に出社する前に昼食を済ませたいと思った彼は、レンタルしていた自転車を駅前で返却すると、めぼしい店舗を物色した。すると、“白いカレー”なるものを提供する飲食店があったので、マサカズは物珍しさからそこで昼食を摂ることにした。
カレーの香ばしさが漂う狭い店内はカウンターしかなく、コックスーツ姿の中年男性がひとりで接客と調理を担当していた。マサカズはカウンターに着くとカレーを注文し、スマートフォンを取り出した。そう、財務大臣の警護を行った浜松町選挙の結果をまだ確認していなかった。不倫騒動のあった元アナウンサーではあるが、どうせなら当選して欲しい。そんな願いから検索してみたところ、僅差での落選だった。ため息を漏らしたマサカズは、先ほど漏れ聞こえてきた園児たちの陽気な喧噪を思い出した。
自分も来月の十日には二十九歳になる。いわゆるアラサーというやつだ。同窓会ではあの園児たちぐらいの子供がいる同窓生もいたが、さて自分はどうなのだろう。いずれは誰かと巡り会い、結ばれ、子供が作れるのだろうか。これまでは狭い世界で生きてきたのだが、この会社を始めてからは様々な人たちと出会う機会が増えている。そのような環境で、意中の人が現れる可能性もある。だが、それは同時に鍵の秘密をどう取り扱うのかにも繋がる。まさか伊達は自分が異性と付き合うことを反対することはないだろうが、秘密については共に頭を悩ませることになるだろう。
そうか、それは伊達にしても同様だ。彼が今後誰かと愛し合うことになれば、自分と同じ心配を抱えることになる。マサカズは何度か頷くと、なにやらそわそわとした気持ちになった。
目の前に、カレーが差し出された。それは確かに白く、これまでに見たことがないカレーだった。一見するとシチューの様でもある。スプーンでひと口運んでみる。辛さはそれほどでもないのだが、なにやら味が薄く形容し難い違和感がある。食べ進めれば感想も変化してくるのだろうか。そのような期待を抱きつつ、マサカズは幾度もカレーを口にした。
料金を支払い、マサカズは小さな店舗を後にした。いつか彼女ができてデートすることになってもこの店を利用することはないだろう。そのようなことを思いながら、彼は駅に向かい歩き始めた。
【無料版】第6話 ─ジャックされた幼稚園バスを取り戻そう!─Chapter6
十月末日の夜、マサカズは上野の繁華街にあるイタリアンレストランの個室にいた。テーブルを挟み対座していたのは、クリーム色をしたチェック柄のブラウスを着た新実葉月こと三条葉月だった。
昨晩、電話があった。明日の夜、会いたいと。理由と目的を尋ねたところ、それは会ってから話すということだった。マサカズは戸惑いはしたものの、拒む理由も特になかったので応じることにした。そして今日の昼、この店のWebサイトのアドレスと“午後七時待ち合わせ”という情報がメッセージで送信され、このような状況になっていた。マサカズにとって特に意外だったのが、来店すると彼女がひとりで個室にいたことだった。夫と一緒であると思い込んでいたので、彼はどこか気まずさを感じ、それを紛らわすためレモンサワーをひと口呑んだ。
「ヤンマサ、なんだろうって思ってるでしょ」
「どうなんだろう」
「だって、おかしいでしょ。これ」
「半々ってとこかな。ギリおかしくないかも。えっと、三条さん……」
「あ、新実でいいよ。なんなら葉月でもオーケー」
抑揚に乏しい口調で、新実はそう告げた。
「なら、新実さん。これって単に飯食べたいって理由?」
「理由が気になる?」
「それは、やっぱりギリおかしいと思うし」
「だよね。やっぱりおかしいよね」
迷っている。なにについて、なにに対してかはわからないが、彼女は自分の考えを制御できていない。そう感じたマサカズは、どう対していいのか考えあぐねていた。空腹でもあったため、彼は目の前のマルゲリータを一切れ取り、それを頬張った。
「法務省とお仕事してるんだよね。どんななの?」
「簡単な運搬とか、選挙演説のボディーガードとかだよ」
「すっごいんだね。知り合いとかいるの?」
内容とは裏腹に、声が微妙に震えている。マサカズはいよいよわからなくなってしまい、ピザにタバスコをふっていなかったことに今さらながら気づいてしまった。
「いるよ。課長さん。なんの課かはよくわからないけど。小さくて痩せた人」
「ふーん。ふーん」
「あのさ、なんなの?」
「昔の友だちとイタリアンでディナー。だよ」
「ちょっとさ、イラっとはしてきたよ。新実さん、病気?」
「葉月は元気だよ」
目が虚ろだ。とてもではないが、“元気”とは言いがたい様子である。同窓会では昔と変わらない太陽のような生気をあふれ出していたというのに、今夜の彼女は固く冷たい月の様だ。
「ヤンマサの会社は、人助けをしてくれるんだよね」
「目標な。スローガンってやつ。できてるかって言うと、かなり微妙だけど」
「助けてくれるんだよね」
「なんの念押しだよ」
「だよね?」
「だから!」
苛立ったマサカズが腰を浮かすと、新実は素早く席を立ち、つかつかとした足取りでテーブルを回り込むとマサカズの隣の席に座った。その唐突とも言える行動にマサカズは戸惑い、息を呑んだ。
「わたし、わたしたち、助けてほしいの」
「え?」
「助けてほしいから、ヤンマサに連絡したの。助けてよ!」
正面を向いたまま、新実はそう告げた。
「何があったんだ? できることなら力になるよ。場合によっちゃ料金は取るけど」
だが、そこから一分ほど沈黙が続いた。新実は両手でパンツスカートを握りしめ、その横顔は青ざめていた。マサカズはその間、様々な想像を巡らせた末、あることに思い至った。
「あのさ、誰か、死んだ?」
登別たちを殺してしまったあとの自分を、マサカズは思い出していた。自分もあの当時、このように混乱し、硬直し、迷走していた。
新実はマサカズに顔を向けると、表情をひどく壊し、よろめき、彼の胸元に抱きついた。
「ヤンマサって凄い」
「凄いというか、ひどい経験をしてきてしまった」
「助けてよ」
「まさか、三条が? 死んだ?」
「違う。あいつが、殺した」
顎先から、いい香りが漂う。マサカズは新実のうなじを見つめ、殺害の告白に対してあまり動揺できない自分に呆れていた。
「順序を頼む。とんでもないことだとは思うけど、経緯と現状を正確に教えてくれ」
落ち着いた口調でそう言うと、新実はマサカズから離れて立ち上がり、丁寧な所作で椅子を彼に向けて座り直した。
「凄いんだね。ほんと。ビックリだよ。ヤンマサ、信じていいんだよね」
新実の表情は柔らかく、いつものように凛とした生気が戻っていた。
「そこは保証できないな。僕はここ最近、急に、ひどく恐ろしいことに立ち会ってきた。僕がやってしまったひどいこともある。だから、僕は善人じゃない」
「いい、勝手に信じる。善人とかどうだっていい」
「それで? なにがあったんだ?」
「哲秋が“かりん”って女子高生と浮気してたの。知ったのは同窓会のすぐあと」
想像しがたい。このように美しく瑞々しい色香に溢れた伴侶がいながら、別の女性に手を出すとは。三条哲秋という人物をマサカズはまったく理解できなかった。
「わたし、哲秋に離婚しようって言ったの。そしたらあいつ、浮気相手と別れるって約束してくれたの」
「そうか」
「そしたら何日かしてから哲秋から電話がかかってきたの。宇都宮のラブホから。で、行ってみたら女子高生が死んでたの」
「三条が殺したのか?」
「ううん、正確にはちょっと違う。別れ話切り出してシャワー浴びてたら、持ってたクスリをアホみたいにやって、死んだって」
「じゃあ、自殺ってこと?」
「そうとも言うわね」
「それからどうしたの?」
「二人で死体を運び出して、山に埋めたわ。途中、ホームセンターでスコップとか色々用意して」
「どーしてそーなる!?」
「だって、あの女が使ったクスリは、哲秋が用意したヤバいやつだったのよ。バレれば逮捕だし、なんかもうムチャクチャじゃない!!」
「ちょっと待てよ。ひどすぎないか?」
「わたしは悪くない!」
「いやいや、犯罪だ。えっと、死体遺棄って罪だ」
「なんでよ? 夫に浮気されて、ひどいとすればわたし以外の全部だ!」
「そこは同情するけど……いま、三条は?」
「普通に仕事に行ってるわ。図々しいほど普通に」
何をどうすれば最善なのか、マサカズは懸命に頭を働かせた。自分には超越した力があるものの、この事態に対してそれはまったく役に立たない。伊達ならどういった判断をするのだろうか。しかし考えてみたところでシミュレーションができるはずもなく、彼の喉はひどく渇き、それを潤すためレモンサワーを呑んだ。
「ヤンマサ、法務省にコネがあるんだよね。だから、助けて」
「嫌だ」
思わず即答してしまった。新実に目を向けると、彼女は鼻を鳴らして笑い声を漏らし、マルゲリータを手にしていた。
「だよね。そりゃそうだ」
「これは、友だちの元弁護士から聞いたことがある話なんだけど、素人が遺棄した遺体ってのは、ほぼ百パーセントの確率で発見される。それに、行方不明になったその女子高生だって捜索されれば、三条との関係もいずれは発覚する。宇都宮なら防犯カメラだっていくつもあるし、バレるのは時間の問題だ」
「じゃあ、わたしたち夫婦は逮捕?」
「確実にそうなる」
「終わりだね。それじゃ」
「終わり方を少しでもマシにする方法がある」
「自首?」
「そう」
「やっぱ、そーなるか」
つぶやくと、新実はマルゲリータにタバスコを振りかけると、思い切り勢いよく齧り付いた。
「わたし、あんなヤツとじゃなくって、ヤンマサと結婚すりゃよかった。まぁ、そもそもあのバカをたぶらかした、かりんって女がそもそもの元凶なんだけどね。アイツが一番悪い。勝手に死にやがって」
「葉月」
諫めるため、思わず強い口調で名前を呼んでしまった。マサカズは咳払いをすると、ちりちり頭をひと掻きした。
「うん。わかってる。ひどいこと言ってるって。なんだろうね。ちょっと前までは幸せだったのに。なんだろうね」
葉月は身体を屈めると、再びマサカズの胸にもたれかかってきた。マサカズは彼女の肩を抱き止めた。
「ごめんね。自分たちでなんとかする。今日は、本当にありがとう」
穏やかな声だった。切なくなったマサカズは天井を見上げ、小さく呻いた。
【無料版】第6話 ─ジャックされた幼稚園バスを取り戻そう!─Chapter7
幼なじみを胸に抱いてしまった。だが、そこまでだった。そこから先の深みはなかった。彼女は地元の栃木へと帰っていった。上野駅の改札まで見送ったマサカズだったが、ほとんど言葉を交わさず、別れも沈黙のままだった。自分たちでなんとかする。そう言っていたが。あまりにも落ち着いた様子だったため、なにをどうするつもりなのかは尋ねられなかった。
あくる日、事務所でマサカズはネットで検索をしてみた。キーワードは“かりん”“女子高生”“栃木”“行方不明”とした。すると、ひとつのSNSアカウントを見つけた。アカウント主は栃木在住の、永野かりんという高校三年生の少女の父親であり、一週間前から連絡が取れず姿をくらませてしまった娘の情報提供を訴えていた。おそらく、この彼女が三条哲秋と不倫をし、ラブホテルで別れ話を起因にオーバードーズにより死亡し、夫妻によって山中に遺体を遺棄された少女だろう。この事件は今後どのような推移を辿るのだろうか。
自分は父親や捜査機関が現時点で知り得ぬ情報を知ってしまっている。三人も殺害し、それを明らかにしないまま、人には自首を勧めるような度しがたい自分が知ってしまっている。マサカズは増えてしまった秘密にどう向き合えばいいのか、わからぬままだった。
父親がネットで公開した娘の写真を見ると、黒いボブヘアの大人しそうで可愛らしい少女だった。彼女こそが昨晩葉月の言っていた“元凶”で、冷たい土の下に埋められた被害者である。写真に添えられたテキストには、彼女がいかに心優しく親思いで、これまで家出などしたことがない、品行のよい娘であることなどが綴られている。その真偽がわかるはずもないのだが、娘の喪失を嘆く父親の訴えにマサカズは心を抉られ、抱えた秘密はその重みを増していった。
小学五年生の春、下校途中の県道で“それ”を見てしまった。車道に横たわる黒く体操着袋ほどの小さな塊は、血だまりの中にあり、ぴくりとも動かない。
「ヤンマサ、あれ、狸だよ」
共に下校していたのは葉月だった。
「車に轢かれたのかな?」
わかりきったことを、なぜ言ってしまったのか。
「だろうね。かわいそうに」
しかしこういった際、どうすればいいのかのフローチャートは持ち合わせていなかった。だから、ただ通り過ぎるしかないと思っていた。だが、彼女はそうでなかった。車を警戒しながら死骸に歩み寄り、それを抱え上げた。Tシャツとスカートは瞬く間に血まみれとなったが躊躇なく、なんの迷いもなく、彼女の様子は淡々としたものだった。
「新実、なにしてんだよ」
「埋めるの。だって、このままにしてられないでしょ」
それは確かにそうなのだが、自分にできる行為ではない。新実葉月というクラスメイトが不気味とさえ思えてしまったことを、よく思い出せる。
「ヤンマサはいいよ。あとはわたしがやるから。先に帰ってて」
言われるがまま、その場から立ち去ってしまった。亡骸を抱きかかえ、平然とした血まみれの彼女からできるだけ早く距離を置きたかったからだ。翌日、登校してきた葉月は「埋めといたよ。簡単だけど、石でお墓も作った」と言ってきた。
「あのさ、その、新実ってすごいんだな」
「なんで?」
「死んでる狸を抱えて埋めるなんて、それもあんなに普通に。僕にはムリだよ」
「なんでムリなの?」
「だって、怖いよ。血だってドバっだったし」
「わたしだって怖いよ。けど、可哀想じゃない。あのままなんて。轢かれて、ゴミみたく転がって。あんまりだよ。普通になんて言わないでよ。いっぱいいっぱいだったんだから」
今にも泣き出しそうな様子だった。夫と高校生の少女を埋めたとき、彼女はどのような面持ちだったのだろうか。わからないことばかりだ。このような場合は、信頼の置ける人物に相談するしかない。
「じき、庭石から次の仕事がくる。それまでは幼稚園バスの見守りを頼むぞ」
代々木駅前の薄暗い照明をしたバーのテーブル席で、伊達はマサカズにそう言った。
「ええ」
「しかしお前から呑みに誘うなんて珍しいな」
「まぁ、ええ」
信頼できる人物を誘い出したものの、マサカズはなにをどうやって相談したらよいのか、その中身については無策なままだった。彼はハイボールのグラスを手にすると、中の泡をぼんやりと見つめた。
「最終的にはさ、公安関係の業務を取れればなって思っている。対テロリストとか、あの力にうってつけだろ? 危険は増すけど、唯一無二の存在になれる」
「ですね。けど、庭石さんって、大丈夫なんですか?」
「どういう意味だ?」
「僕が会ったのはあの料亭だけですけど、なんて言うかあの人、潰れちゃわないかって」
「またそれか……あいつが弱い人間ってことか?」
「そうは言いませんけど、人があんなにパニックに……」
言いながら、マサカズは自分が散々脅迫し、遂には海外へ逃げ出してしまった吉田を思い出した。そして、登別に返済を迫られ、命の危険に晒された自分や伊達も。「人があんなにパニックに陥ることを見たことがない」そう言いたかったのだが、考えればむしろ見慣れた状況ではあったので、マサカズは黙り込んでしまった。
「ああ、わかったよ。今後は手は緩めていくよ。大前提として、娘の件が発覚すれば庭石は使えなくなるから、できるだけ早くヤツと同等の別ルートを開拓しなけりゃならない。庭石から得た実績を売りに、今度は脅したりせず正攻法でな」
そう言うと、伊達はビールグラスに口を付けた。
「なんか、僕はとても遠いところに来てしまった気がします」
「なんだ? 誘ったのは人生相談か? それなら残念だけど俺は適任じゃない」
「どういうことです?」
「そりゃ、弁護士だから法律についての相談に乗るのは得意だけど、生き方とかはアドバイスできない」
「えっと、どういうことです?」
「人の生き方なんて、責任が持てないからだ。だいたい正解がない」
「でしたら、極めて限られた状況について、解決策の相談はできますか?」
「なんだ?」
伊達は、マサカズの観察を始めた。彼は顎に指を当てると、対座するマサカズの所作や表情、声のトーンに注意を向けた。
「あのですね。今後のことを考えた場合、あり得る状況ってあると思うんですよ」
これは、隠し事についての相談か。伊達はそう判断すると、三杯目のビールをバーテンに注文して会話の間を開けた。
「例えばです。例えばですよ。僕の知り合いが自殺した人の遺体を、やむを得ない事情によってどこかに埋めてしまったとします」
「ああ」
「それを僕が知ってしまったとしたら、僕はいったいどうすればいいのでしょうか?」
「二つにひとつなんじゃないのか?」
「通報するか、しないか、ですか?」
「その通りだ」
「伊達さんならどうします?」
「知り合いが誰か、そして事情による」
「通報しないってのは、どんなケースです?」
「そうだな、知り合いが逮捕されたら、俺が著しく損害を被る……例えばお前とか」
登別たち三人の殺害について、確かに伊達は目撃者にも関わらず通報することはなかった。それは借金をもみ消すため、金庫の持ち出しという犯罪の示唆を自分にした、言わば共犯関係であるから理解できる。しかし葉月のケースはまったくの無関係であり、通報すること自体になんの利害も影響しない。
「あのさ、仮の話って前提だけど、どうせすぐにバレるような事案だし、放っておくって手もある。法治国家の国民としては決していい姿勢ではないけど、友人がこれ以上追い詰められるのに加担する精神的負担からは解放される」
伊達は“仮の話”という前提では話していない。全ては見抜かれている。彼の口調が優しくしっかりとしていたため、マサカズはそれがわかってしまった。
「すみません。伊達さん」
「仕事柄、俺も見て見ぬふりは数え切れないほどやってきた。お前もそうすればいい」
そう言った伊達は、生ビールを勢い良く呑んだ。
「この力、ほんと使い勝手が悪いんですよね」
「世の中の大半が、腕力で解決できないトラブルばっかりだからな」
その通りだ。マサカズはハイボールを飲み干すと、二杯目を頼んだ。
【無料版】第6話 ─ジャックされた幼稚園バスを取り戻そう!─Chapter8
伊達とグラスを傾け合った翌る日の朝、マサカズは晴天の住宅街で、レンタルした自転車を漕いでいた。ここ何日か、幼稚園バスの見守りの仕事を続けているのだが、一件としてトラブルには遭遇していない。なにもないことを確かめる仕事は退屈でもあったが、幼稚園の従業員たちは誰もが働きぶりを有り難がり、感謝の態度で接してくれるので、誰もいない真夜中の山奥で解体や運搬をするよりは、ずっと晴れがましい気分ではある。
「自分は意外と子供好きなんだって思いました。ちょっとだけしか見る機会はないんですけどね。なんか、ウキウキしてくるんですよ。あー、元気だよなぁって」
昨晩、バーで向き合っていた伊達にそう言うと、彼は眼鏡を人差し指で直して人の悪い笑みを作った。
「結婚したくなったか?」
「ちょっと短絡的すぎやしません?」
「そうだな。結婚するだけが手段じゃないしな」
その夜五杯目となるビールを飲み干した伊達は、六杯目を注文した。
「そりゃ、いずれは結婚して子供が欲しいって、そんな希望はありますね。伊達さんはどうなんです?」
「俺は……そうだな……」
しばらくの沈黙だった。マサカズはナッツを口にすると、伊達の様子を窺った。彼は運ばれてきたビールグラスを両手で掴んだまま、虚ろな目でテーブルに見つめていた。
「予定だと、三十には結婚するつもりだったんだよ」
ようやくの返答だった。マサカズは大きく頷くと、次のナッツをつまみ上げた。
「一応、相手らしき目星もつけてはいたんだ。同業者でな」
ナッツを囓りながら、マサカズは伊達の声が低く小さくなっていると感じた。
「伊達さん、それって話したい話です?」
「いや、まったく。酔ってるから口に出てしまった」
「呑みすぎなんですよ。いつも思うんですけど、伊達さんって底なしじゃないですか」
「屈折してんだよ。キャバもギャンブルも絶てたけど、こればっかりは依存が治らない」
「まぁけど、あんまり悪酔いしませんし、ほんと、ほどほどにしましょうよ」
「ありがとうな。俺、そんなこと言ってくれるヤツ、お前が初めてだよ」
「いずれは僕たち、それぞれ幸せな家庭ってのを持ちましょうよ。僕と伊達さんの子供、友だちになったりして。あ、それっていいかも」
「悪くない未来だな。夢がある」
ようやく、伊達に笑顔が戻った。二人は今夜三度目になる乾杯をして、そのあとも終電まで二時間ほどバーで他愛のない話題に花を咲かせた。
バスの安全装置の取り付けもそれぞれの幼稚園で準備が進められていくため、この地域での見守りもあと何日かすると終了することになる。特にこれから向かう、この日五件目の幼稚園については今日が最後だ。マサカズは自転車を漕ぎ、つい最近動画サイトで知った歌を、歌詞もうろ覚えのまま口ずさみながら幼稚園の隣の駐車場にやってきた。
どうやらいささか早い到着になってしまった様だ。バスは着いたばかりであり、園児たちが次々と降車している。こういった場合の段取りも幼稚園側と事前にすり合わせていたので、マサカズはそれに則り自転車から降り、エンジンがかかったままのバスに向かった。
「ども」
マサカズはアイドリング中のバスの前で園児たちの降車を促す、初老の男性スタッフに挨拶をした。
「あ、ゼロのひと? 山田さん?」
「ええ、早めに着いちゃったんで、中から子供たちに促しをやりますね」
「ぐずる子がいたら言って下さい。私がなんとかしますんで」
「バス、エンジンかけたままなんですか?」
「このあとすぐに工場入りなんですよ。安全装置付けるんで。このバス、ポンコツでエンジンがかかり辛いんで」
スタッフの言葉に頷くと、マサカズはバスに乗り込んだ。まだ五名ほどの児童が車内に残っていたため、彼は息を吸い込み、よく通る声で「はいはい、降りましょうね」と促した。すると、手の甲に暖かく柔らかい感触が伝わってきた。何事だろうかと目を下ろすと、紺色をした園服姿の小太りな女児が手を掴んでいた。後頭部で髪をまとめ上げたこの少女からは、見上げる表情から強い意志が窺い知れる。マサカズはそれに応えるため、少しだけ身を屈めた。
「えっと、なに?」
「お兄ちゃん……大好き」
脈絡など、この年齢の幼児に求められるはずもない。それはよくわかってはいるのだが、大人として子供とのコミュニケーションの経験がこれまで皆無だったマサカズは困惑するしかなかった。そうしている間にも園児たちはバスから次々と降りていった。
「じゃあ、お兄ちゃんと一緒に降りようか」
自分でも中々スムーズな促しだと思ったが、女児は手を掴んだまま身体を揺らし、あからさまに不満げな表情を浮かべていた。これが“ぐずる子”というやつなのだろう。そうなると、先ほど挨拶したバスの外で降車確認をしているスタッフを頼るしかない。
困り果てたマサカズが乗降用のドアに振り返ると、鼠色のパーカー姿の見覚えのない若い男が目に飛び込んできた。そり込みの入ったスポーツ刈りで、首にはタトゥーが入っている。どう見ても幼稚園バスの車内には似つかわしくない、関係者とは思えない青年だ。男は運転席に着くと、扉を閉ざした。急な後退のため車体は大きく揺れ、マサカズは全身のバランスを崩した。彼は傍らの女児を座席に押し込みつつ、床に倒れ込んでしまった。

非常事態が発生している。起因は運転席の闖入者だ。まずは状況を把握する必要があるのだが、それをするためにもまずはやっておくべき事がある。マサカズはデニムのポケットに手を突っ込むと、「アンロック」と呟いた。
車内に残っている児童は手を握ってきた女児だけであり、運転席ではパーカーの青年がバスを運転していた。駐車場を出たバスは法定速度を越えたスピードで都道を走り出した。マサカズは身体を起こすと、揺れる車内で女児の傍らに寄り添い、シートベルトで彼女の身体を固定した。
「僕がなんとかする。だからじっとして」
怯える女児にそう告げたマサカズだったが、重力には逆らえず再び転倒した。次に行うべきは、この場の支配者に対する接触である。床に伏したマサカズはそう決断した。先行車を追い抜く度に、車体は左右に激しく揺れるため、女児はとうとう大声で泣き出してしまった。しかし、シートベルトでの身体の保持は奏功しているように見える。マサカズは彼女に向かって拳を作り親指を上げたのだが、号泣は止まず気安めには失敗してしまった。
これはいわゆるバスジャックということだろう。あの男は何かの罪を犯し警察に追われた末、このバスに遭遇し奪った。運転することだけに集中しているようなので、計画性もなく子供を人質にとろうといった発想自体もない可能性がある。なにより、この車内でもうひとりの異質な存在となる自分のことを認知しているかどうか怪しい。
マサカズは床に這いつくばりながら、考えを巡らせた。鍵の力があったため恐怖はないが、子供の存在が不安だった。背後からあの男に攻撃を加え、無力化するのは容易だ。しかし、その途端高速で走行しているバスはコントロールを失い事故が発生する。自分はおそらく平気だが、子供は無事では済まないだろう。できるだけ穏便にこの事態を処理するべきだ。そしてその度胸の根拠は既に得ている。マサカズは運転席まで這った。
「えっとですね。いいかな?」
「うわっ! えっ? なんだお前!?」
床から声をかけられた運転席の男はひどく驚き、マサカズに一瞬だけ目を向けた。
「なにしてるんだ?」
「見りゃわかんだろ。逃げてんだよ」
「ムダだって」
「うるせぇ! ブッ殺すぞ! 俺はな、ツイてるんだよ。バスなんて普通出くわさねぇぞ。こっからは風林火山だ!」
なにを言っているのかよくわからない。子供の泣き声が響き渡る車内で、マサカズは異常事態に対してあくまでも冷静なままの自分が、少しばかり可笑しく思えた。
「あの小さい子、黙らせろよ。気が散って仕方がねぇ」
運転をしながら、男はそう命じた。“小さい子”という表現にマサカズはひどく違和感を覚えた。
「あ、でも僕は専門家じゃないからムリだって」
「幼稚園のヤツじゃねーのかよ?」
「臨時の見守りマンだ」
「はぁ? なにそれ」
車外からパトカーのサイレンが鳴り響いてきた。男は額の汗を腕で拭うと雄叫びを上げた。
「テメェらを人質にする!」
「いや、だからそういうのって成功した例ってないよ。僕の友だちの元弁護士さんも言ってたし」
そういった途端、マサカズは男のハンドル捌きによる大きな揺れのため、車体前部のステップに転げ落ち、閉ざされていたドアに背中を叩きつけられた。痛みを感じることもなく、彼はポーチからスマートフォンを取り出し、ニュースサイトを確認してみた。とにかく情報が必要だ。そして的確な判断を下し、この焦燥しきった青年からバスを奪還しなければならない。マサカズはしだいに方針を固めつつあった。
「これだね。御徒町の四人組宝石店強盗。ワンボックスカーで逃走、警察に追い詰められたあとちりぢりになった。パーカー姿の写真もあるし、これなんでしょ!?」
「うるせぇっつってんだよ! え? もうニュースとかになってんのかよ!?」
バスは突然急停車をし、マサカズは再びドアに背中を打ち付けた。すると体重を支えていたそれは自動で開き、マサカズは地面に放り出されてしまった。どうやら、バスはビルの入り口に横付けされた様である。仰向けになっていたマサカズが上体を起こすと、パーカー姿の青年がバスから降りてきた。彼は女児を抱え、肩には鞄が提げられ、右手にはオートマチック式の拳銃が握られている。女児は既に泣き止んでいたが、その表情には恐怖が貼り付いていた。
「立て! 行くぞオラ!」
どうやらこの男はバスでの逃走を早々に諦め、人質を取ったうえでの篭城に作戦を切り換えたように思える。今ならバスの事故を気にせずに男を制圧することはできるが、自分の未熟な技術では女児を無傷で解放できる自信はない。今はとにかくチャンスというものを待つしかない。マサカズは立ち上がると両手を挙げ、抵抗の意思がないことを伝えた。
【無料版】第6話 ─ジャックされた幼稚園バスを取り戻そう!─Chapter9
東京都北区赤羽の雑居ビル『レッドアーク赤羽』の二階、『串焼き大陸・テツ』のガラス戸は、パーカーの男が手にしていた拳銃の底でたたき割られた。男は扉の内側に手を回し、速やかに解錠した。彼は慣れている。これまでにこういった不法侵入を繰り返してきたのだろうだろう。一連の様子を背後から見ていたマサカズはそう思った。
「入れ!」
男にそう促されたマサカズは、従うことにした。このバスジャック犯が胸に女児を抱えている以上、逆らうことはできなかった。
侵入した店内は開店前であり、店員はまだ出勤していないようである。電灯が点けられた店内はカウンターとテーブル席が四つほどの狭さだった。男は女児を床に下ろすと、背中を軽く押してマサカズに目を向けた。
「ふん縛るから、それまでこの子の面倒を見ろ」
うめき声を上げ、ときおり身体を痙攣させる少女の肩をマサカズは掴み「大丈夫。僕がどうにかする。だから大人しくしててくれ」と耳元で囁いた。すると彼女は目を見開き、三度ほど大きく頷いた。
想定していなかった展開だ。まさか、人質を預けられるとは。反撃の条件は呆気なく揃ったように思えたのだがそれが早計であることを、向けられ続けている銃口からマサカズは察した。自分は平気だ。しかしこの女の子に当たれば致命傷となる。このような状況に対応する訓練は受けておらず、女児を庇ったままの立ち回りができる自信はない。命が懸かっている以上、失敗は絶対に許されない。店内を物色する男に注意を向け、マサカズは更なる機会を窺うことにした。
マサカズと女児は背中合わせになる形で床に座らされ、ゴムのホースでまとめて縛り上げられてしまった。店の隅に設置されたテレビではワイドショーが流されていて、幼稚園の送迎バスが横付けされたこの雑居ビルの周辺にパトカーが何台も到着し、警官の配備が進む様子が映し出されていた。
「大げさなんだよ。ったく、どーすりゃいいんだよ」
テレビで“強盗事件に詳しい”といった肩書きで専門家がこの事件ついてコメントしているのを横目に、パーカーの犯罪者は苛ついた様に裏返った声で焦燥感を言葉にした。
「大人しく自首するしかないよ」
マサカズの言葉に、男は振り向いて銃口を向けた。
「お前さ、ちょっとおかしくねーか?」
「まぁ、普通じゃないよね」
「なんなん?」
「一応、正義の味方になりたいって思っている」
「なんかやってるの?」
「いや、そう言われると……」
立てこもり犯と人質のやりとりとしては、あまりにも木訥で間が抜けていた。マサカズはこれからの成り行きが見通せなくなり、途方に暮れてしまった。
「副社長、こりゃ、ちょっとまずいかも」
代々木の事務所で、伊達は寺西からそう声をかけられた。
「どうしました?」
「株価調べるついでにニュース見てたんですけど、社長が見回ってる幼稚園のバスがジャックされたらしいんです」
「マジで!?」
伊達は席から立ち上がると、寺西の席に移動した。事務所にいた木村と草津も同じように寺西の背後に回り込み、四人はモニターに映し出されたニュースに注目した。現在わかっているのは、幼稚園の送迎バスが何者かに奪われ、赤羽の雑居ビルまで逃走し、犯人はその中の飲食店に立て籠もったとのことだった。当時、バスには降車しきれなかった女児ひとりと、アルバイトの青年が同乗し、犯人はこの二名を人質としている可能性が高い。
ニュースを読んだ伊達は、自分の座席に戻るとブラウザでテレビ局が動画配信しているライブニュースにアクセスした。空撮されたビルの前にはパトカーと警官が配備され、これから状況の確認を進めるらしい。伊達はマサカズに連絡を入れようかと思ったが、あまりにも情報が不足していて、場合によっては犯人を刺激する可能性もあるのでそれを躊躇った。昨日の打ち合わせで、見守り仕事は業務が完了した時点で、マサカズから連絡が入る段取りとなっている。時刻からしてとうに電話がかかってきてもおかしくはないため、“アルバイトの青年”と報じられている彼がマサカズである可能性は極めて高い。いま、自分にできることはなんなのか。伊達は素早く結論に達すると、テキストエディターを起ち上げ、勢い良くキーボードを叩き始めた。
拳銃を突きつけられてる。おそらくは本物なのだろう。弾丸が入っているかどうかまではわからない。マサカズはパーカーの立てこもり犯から決して目を離さなかった。男はときおり煽るように銃口を上下させたり、わざとらしく大きな挙動で引き金に人差し指をかけたりしたが、マサカズはまったく動じることもなく、心配だったのは背中合わせに縛られている少女の無事だけだった。
「もしかしてさ、サバゲーのやつだと思ってるん?」
「いや、サバゲーとかよくわかんないし」
「本物だぞ。三十万円もしたんだ」
「へぇ」
マサカズが平然と返事をすると、店の外で駆け足の音が響いてきた。男はビクリと全身を震わせ、拳銃を割れたガラス戸へ向けた。しばらくしたのち、男は再び銃口をマサカズに転ずると、急に嘔吐きだし、涙をこぼれ落とした。
「もーさー、なんでこーなっちゃうんだよ? ぜってー成功するって言われたんだよ?」
嘆きの叫びだった。マサカズは平然としたまま男を見据えていると、引きつった笑みが返ってきた。
「なぁお前、実は凄いヤツなんじゃないのか?」
「空手家の、真山って知ってる? テレビとかにも出たことあるらしいけど」
「ああ、あの虎と戦ったヤツだろ。知ってる知ってる。すげぇヤツだ」
彼はそんなことまでしたのか。マサカズは苦笑いを浮かべ、「僕はそいつを倒したことがある」と告げた。男はしばらく沈黙すると、マサカズの前までやってきた。
「なんだろ、信じられる気がする。お前、全然強くなさそうなのに、ちっともビビラねぇし」
「ビビるほどの状況じゃないからね」
「なぁ、だったら助けてくれよ。分け前やるからよ。たぶん何千万円かにはなる。オレをここから逃げ出してくれよ」
「それはムリだよ」
「何千万円だぞ」
「お金の問題じゃない。だって犯罪じゃん。嫌だよ」
「お前がいくら頑張っても稼げない額だぞ」
「矛盾が過ぎる。僕を見込んでるのに、なんで僕が稼げないヤツだって都合よく見くびる」
その言葉に、男はいきり立った様子でマサカズの胸ぐらを掴んだ。同時に、ポーチに入れたスマートフォンから振動音が漏れてきた。
「だだだ、ど、が、ぎ、ごごご!」
言語化できない感情の発露である。マサカズは機会が訪れたと判断し、両腕を強引に広げて拘束していたホースを内側から引きちぎり、男の胸元に頭突きを見舞わせた。男は嗚咽を漏らしながらその場に崩れ落ちた。マサカズは振り返ると、女児の様子を確認した。彼女は振り向くとマサカズの腰に抱きついてきた。
「警察だ!」
割られたガラス戸の向こうでそのような叫び声が聞こえてきた。マサカズは女の子の頭を軽く撫でると「大丈夫です! 終わりました!」と返事をした。
「行こうか」
マサカズは女児を促したが、彼女は額を擦りつけ、抱きついたままだった。
「えっと、怖いの終わったから」
言いながら、マサカズはポーチからスマートフォンを取り出した。どうやら先ほどの着信はメールの様だ。それは伊達からのもので、表題は『人質の被害者として取り調べを受けるにあたっての注意事項』と記されており、本文は長文のようだった。
「ほら、パパやママのところに帰らないと」
いくら説いても頑なに離れない。マサカズは少女の心持ちを計りかねていた。すると、青い制服の救急隊員と警察官が店内に入ってきた。
「山田正一さんですか?」
若い警官のひとりがそう尋ねてきた。
「ええ、ってどういった把握です? あと、奥で倒れているのが犯人です」
「あなたとその子、岩越まゆりさんが人質にとられていると把握しています」
なるほど、警察は正確に事態を掴んでいる。これから被害者として取り調べを受けることになるはずであり、それに向けて伊達からの長文メールを事前に頭に叩き込まなければならない。その時間が取れるのか、マサカズは不安になった。そして同時に、今この状況での自分というものが他人から見た場合、先ほどの立てこもり犯が感じたであろう違和感に満ちた人物だと思われてしまうかもしれず、それはあまり得策ではないと思った。
「マジで、ほんと、怖かったんですよぉ」
泣き顔を作り、女児に抱きつかれたまま、マサカズは思いきり震えた声で警官にそう訴えた。
【無料版】第6話 ─ジャックされた幼稚園バスを取り戻そう!─Chapter10
今回の事件ではまったくの無傷に終わったが、マサカズと女児は警察の指定する、篭城現場からほど近い総合病院で検査を受けることになった。そのおかげで、検査の合間に伊達からの長文メールも読むことができた。そこには、「今後の裁判のため、検察の指示で身体検査が行われる可能性が高い」と記されていて、さすがだと感心した。
検査は一時間ほどで完了し、そこから徒歩で赤羽警察署に移動することになった。それを伝令してきた警察官が、午後も遅い時刻だが昼食をどうするのかと尋ねてきた。マサカズはなにやら奇妙な自由を感じながらも空腹を覚えていたので途中で摂ると返答し、病院から警察署までの道のりで蕎麦屋に立ち寄り、きしめんを食べた。
「最後に、犯人と口論になったんです。犯人は僕に助けてくれって言ってきて、でも断って。そうしたら胸ぐらを掴んできたんです。怖くって、無我夢中ってやつで、そうしたらゴムのホースが運良く千切れて、腐ってたんでしょうね。で、犯人に体当たりしたんです。そしたら倒れちゃってって感じです」
人生二度目となる警察署の取調室で、中年の女性捜査官にマサカズは事件の顛末をそう説明した。
「体当たりで? 竹下信玄を失神させたと?」
ハスキーな声の女性だった。マサカズは初めて耳にする人名に首を傾げた。
「あ、容疑者の氏名ね」
即座の補足だった。マサカズは頷くと「だから風林火山なんて言ったのか」と、呟いた。
「あの、僕、今日は帰れるんですかね?」
「ええ、もちろん。ただ、後日証言を求めることがあるかもしれないけど」
「あぁ、検察からの要請ですね。被告人の罪を裁判所に証明させるために、裏付けがいるんですよね」
まったくの受け売りである。つい先ほど読んだばかりの、伊達からのメールに記されていた今後考えられうる可能性をマサカズは口にした。女性は面食らった様子で黙り込み、やがて笑みを浮かべた。
「詳しいのね」
「あっ、ええ、まぁ」
取り調べは二時間に亘った。伊達からのメールは、事件後の可能性をいくつかの分岐で示唆していたため長文となっていたのだが、警察署での取り調べにの対応については簡潔で明瞭であり、「鍵を除いた事実をそのままに証言する。その際、態度については臆病を貫け」だった。
警察署を出ると夜の空気は冷たく、マサカズはシャツの第一ボタンを留めた。
「お疲れさん」
スーツ姿の伊達が柔らかい笑みを浮かべ、マサカズに向かって頷いた。
「もしかして……またマスコミ対策とかしてくれました?」
「そのつもりだったんだけど、ひとりもいなかったよ。おそらくだが、幼稚園の女の子の方に集中してるんだと思う」
「そっか」
「晩メシ、どうする?」
「ちょっと前にきしめん食べたんで、腹は減ってないですけど、ストレスはありますね」
「だろうな」
「呑んできます? 赤羽って個性的な呑み屋があるんですよね」
「そうくると思って、電車で来た」
赤羽駅近くの老舗の居酒屋は仕事帰りの客で賑わい、マサカズと伊達はU字型のカウンターで背を丸めて鯉の刺身をつまみに一杯やっていた。
「たぶん、あの女の子には気づかれてないはずです」
「まだ幼稚園児だしな」
「警察署って、受付以外は静かですよね」
「場所による」
「ま、そーか」
マサカズはレモンサワーをひと口呑むと、ちりちり頭をかいた。
「なんか、最近なんですけど、女の人の登場率が増えてるって感じです」
「ほう」
「選挙の時のボディーガードの人とか、幼稚園の人とか、一緒に人質になった女の子とか、さっきの取り調べも女刑事でした」
もうひとり、幼なじみの顔も浮かんだのだが、マサカズは彼女の存在を口にしたくなかった。
「女のエンカウントバフがかかってるってことか。鍵の力か?」
からかう様な軽い口調の伊達に、マサカズは「まさか」と返し、伊達より早くグラスを空けると二杯目を店員に注文した。
「珍しくハイペースだな」
「二度目なんですよね。警察で取り調べ受けるなんて。なので、一度目のことを思い出してしまって」
「七浦葵の件だな。で、それが起因して、女のことを考えてしまった?」
「かも知れません。あ、けどそんな理路整然としたのじゃなくって、もっとモヤっとした感じです」
グラスを受け取るマサカズを、伊達は観察した。重い口調と鈍い仕草からして、あまりよい心のコンディションではないように感じられる。であれば、励ますのが自分の役目だ。
「今回のことで思ったんですけど、僕、ちょっとおかしいかなって」
「ああ」
「あ、伊達さんから見てもそう感じます?」
「いや、見てわかるものじゃないけど、お前が経験している事柄を鑑みれば、精神的にまいったり変調を来すのは極めて普通だと思える」
「どーしたらいいんですかね?」
「趣味でも持て。それでストレス発散だ」
「趣味かぁ……」
「ゲームでもいいし、スポーツとか、映画とか、音楽とか」
「漫画ぐらいなんだよなぁ。それも最近じゃ読んでないし」
「なんで?」
「あー」
マサカズは唐突にうめき声を上げるとレモンサワーを呑み、大きく頷いた。
「わかった。わかりました。興奮しなくなっちゃったんですよ」
「そりゃ、そうだろうな。あんな力だもんな」
「漫画って言うか、物語って基本的にはウソじゃないですか。けど、僕のこの力はもっとデタラメでガバガバでウソもいいところだ」
伊達はビールジョッキをテーブルに置くと、マサカズの肩を軽く叩いた。
「今日の出来事を振り返ってみろよ」
「え? どういうことです?」
「凄いことだぜ。拉致籠城事件を、お前は解決したんだ。たったひとりで。しかも強盗事件の一部解明にも貢献した」
「あー、それってちょっとヒーローっぽいですね。そーか、僕、最初はこういうことがしたかったんですよ」
「できたじゃん」
笑みを浮かべた伊達は、ジョッキを掲げた。
「あ、できたんですよね! 悪いやつ倒して、女の子助けて!」
「正義のヒーローだよ、今日のマサカズは」
どうやら、マサカズが抱えている心の曇りはいくらか晴れた様である。しかし本来の漠然とした陰りには向き合わせず、この励ましは誤魔化しと言ってもいい邪道だ。伊達は自覚していたが、正しい解決方法がこの場では思いつかなかったので、仕方なくそうするしかなかった。マサカズは嬉しそうに鯉の刺身を口に運び「鯉ってはじめて。美味い、美味い」と呟いた。
「今回の件、あとは俺に任せてくれ。俺たちの秘密が漏れないように絵図を描く」
「え? 伊達さんが?」
「竹下の弁護人を引き受けることにした。手弁当でな。当番が就く前でよかったよ」
伊達の言っている言葉の前半には疑問が生じ、後半は意味自体がよくわからない。マサカズは困惑し、顎を突き出した。
「なに言ってるんです? 伊達さん」
「だから、竹下にはお前のことをできるだけ自供させないように仕向ける。そうすることのメリットをあいつに吹き込む。どうせお前、肝が据わった態度だったんだろ?」
「そりゃ、怖くなかったんで」
「捜査関係者が万が一そこに違和感を持ったら、面倒なこともあり得る。だから、俺がその芽をあらかじめ摘んでおく。お前はあくまでもごく普通のいち青年で、特に語るべき存在ではない。むしろ女の子をできるだけ丁重に扱ったことをアピールするべきだって助言する」
「なるほど……けど、伊達さんって弁護士辞めたんでしょ?」
「おいおい、事務所は辞めたけど資格はそのままだぞ」
「あー、運転免許みたいなものなんですね。伊達さんって、今でも弁護士なんだ」
「そーゆーこと」
まだまだ自分の知らない世界というものがあるのだと思い知らされたマサカズは、頼もしい友人に尊敬の念を抱いた。
「僕、伊達さんと頑張ってたら、幸せになれそうな気がしてきました」
「なんだよいきなり」
「こないだも言いましたけど……モヤモヤしてたのって、鍵の力で解決できない問題がいっぱいあるってわかってしまったからだって。けど、そっちは伊達さんを頼りにすればいいんだって、あらためて思いました」
「ああ、できることはなんだってやるよ……例の死体遺棄についてか?」
「ええ、幼なじみの女子なんですけど、もし自首なり逮捕されたときは、伊達さんに弁護をお願いしてもいいですか?」
「ああ、無罪はムリでも全力は尽くすよ。あ、もしかしてマサカズはその子のこと……」
「人妻です」
抑揚のない即答に伊達は首を傾け、マサカズに向かってジョッキを突き出した。マサカズは正面を向いたまま、グラスを持った手を伊達に伸ばした。

グラスとジョッキが、喧噪のなか小さく鳴った。
第6話「ジャックされた幼稚園バスを取り戻そう!」おわり
【無料版】第7話 ─バッタの力を借りてみよう!─Chapter1
その日、十一月八日の朝、アパートで出勤の準備をしていたマサカズは、テレビのワイドショーに目を留めた。そこで取り上げられていたのが、五日前、自身も深く関わった串焼き店篭城事件だったからだ。鼠色のパーカーを着た容疑者は竹下信玄という名の青年で、昨年までは幼稚園バスの運転手をしていたらしい。しかしそこでのトラブルで解雇されてからは窃盗など繰り返し、今回の事件に至ったとのことである。
シャツのボタンを留めながら、マサカズは竹下が人質の女児のことをなぜ“小さい子”などと呼んだのか、なんとなくだがわかった様な気がした。おそらく彼は彼なりに、運転手をしていたころは子供たちと朗らかで柔らかな付き合いをしていたのだろう。彼が一体どこで道を間違えたのかはかはわからないが、自分にしても吉田の依頼で非合法な暴力を振るったこともあったので、まったく遠い存在だとは思えなかった。
鍵の力を使って篭城事件を解決し、一部ではあるものの、強盗によって奪われた宝石を取り戻すことができた。実際のところ、ゴムホースを引き裂いて、竹下の胸にただ頭突きをしただけで、高度な判断ができた覚えはない。しかし緊急事態に対して、絶対的に安全である、といった確信に依る心の余裕が、よい形に作用してくれたとは思う。目まぐるしく変化する状況に対して冷静に分析し、その結果、最適とも言える立ち回りができた。あの経験は、今後においてきっと大きな実績になってくれることだろう。つい先日買い換えた新品のリュックサックを背負ったマサカズは、揚々とした気持ちでアパートを出た。
伊達は竹下の弁護人となり、鍵の力の隠蔽を行うと言っていた。拳銃で脅されていたにも関わらず、不気味にまで落ち着いていた自分の存在感をできうる限り薄く、弱々しい青年として証言させるらしい。その結果、竹下自身にもメリットが生じるのだと、取り調べに対する取り組み方を誘導するとも言っていた。腕利き弁護士である伊達のことだから、きっと上手くやってくれるのだろう。その点については、マサカズに不安はまったくなかった。
総武線の小岩駅までやってきたマサカズは、上り電車に乗り込んだ。車内は全ての席が埋まり、立錐の余地もないほぼ満員であり、彼はかろうじて吊革まで辿り着くとそれを掴み、腰のポーチからスマートフォンを取り出した。
幼なじみの三条葉月から、夫の浮気相手で自殺した女子高校生の遺体を山に埋めたと告白されてから、今日でちょうど一週間が経っていた。あれから毎日、マサカズは検索で辿り着いた女子高生の父のSNSアカウントをチェックしていた。父は連日に亘り、娘の行方が知れなくなったことを嘆き、悲しみ、その情報をネットに求めている。
今のところ葉月夫妻が自首したという情報はない。父親が既に行方不明者届を出していたとしても対象が若い女性ということもあるので、警察が捜査に動く優先順位は低くなるらしい。単なる家出の可能性もあり、それよりは認知症で行方不明の老人の方が命の危険があるため、そちらを優先する傾向があるということだ。このケースだと、行方不明者届を出してから、本格的な捜査が始まるまで一ヶ月以上はかかるだろう。この件を相談した際、伊達はそう予想していた。
つまり、この事件はまだなにも動きが生じず、“凪いだ”状況である可能性が高い。そして、自分が情報提供すれば、それは一気に暴風域へと達する。だが、それはどうしてもできなかった。幼なじみが罪に問われるのを忌避しているのではない。あの太陽の様に燦然として、常に凛とした輝きを放っていた葉月にはしっかりと罪と向き合い、反省をし、自らの意思でその償いに進んで欲しかったからだ。マサカズはそんなことを考えながら、ぎゅうぎゅう詰めの電車に揺られ、車窓に流れる風景をぼんやりと眺めていた。
「マサカズ、お前の懸念な、アレ、正しい可能性が出てきた」
伊達と共有している懸念は、これまでにいくつかあったので、マサカズは目を泳がせ、下唇を突き出した。
その日の昼休み、二人は代々木駅前の中華料理店の二階で、赤いテーブルを挟んで向き合っていた。伊達の前には天津飯が、マサカズの前には中華丼が、それぞれの空腹を満たすため置かれていた。
「えっと、庭石さんのことですか?」
「そうだ」
庭石からは四日後の衆議院補選に伴う、演説会の警護業務が紹介されていた。何の懸念があるのだろうか。マサカズは甘酢に和えられた白菜とニンジンを米と共に口に運ぶと、伊達の言葉を待った。
「連絡がさ、取れないんだよ。メールにも返事がないし、電話にも出ない」
「電話って、携帯です?」
「ああ、だからついさっき、法務省にも電話した。そうしたら昨日から体調不良で欠勤しているってことだ」
「どうします?」
「とにかく、一度話をしてみないことにはどうしようもない。単なる病気なら別にいいけど、そうだな、もう一週間ぐらいは様子を見ながらって感じだな」
「そっちの方は伊達さんに任せますよ。上手くやってください」
「ああ、もちろん」
返事をすると、伊達はレンゲで天津飯を崩した。
庭石から仲介されていた四日後の仕事は、衆議院補欠選挙に付随して行われる、街頭演説の警護だった。昼食から事務所に戻ってたマサカズは、自分の席に着くと業務内容をあらためて確認した。
今年は記録に残るほど、夏の暑さが長期に亘って継続し、十月に入っても夏日が続いていたのだが、さすがに十一月に入ると季節も移り変わって秋が深まろうとしていた。この事務所もここ数日は冷房を点けず、南側の窓を開放し、秋の空気を取り入れていた。マサカズはうなじに涼しさを感じながら、この仕事は浜松でのそれとあまりかわらない、特に何事も起きないまま、ただ立っているだけの結果に終わるのだろうと予想していた。
「木村さん、こちらがこないだの出張の支出リストと領収書一式になります」
「はい、確認しておきますね」
伊達と木村が、これまで何度も耳にしたやりとりをしていた。浜口は寺西にシーズンオフとなったプロ野球の話題を持ちかけ、草津は手を頭の後ろで組み、モニターを見ながら細かく頷いていた。緩めの表情から察すれば、おそらく『マイニングクラフト』のアップデート情報でも確認しているのだろう。缶コーヒーを手にしたマサカズは、なにやら心地の良い眠気に見舞われた。ここは穏やかでひりつきのない場だ。老齢なので欠勤も多く、その穴埋めに伊達の負担が重くなることもあるが、彼が選んだスタッフたちは諍いをおこすことなく、明るく穏やかな空気をこの事務所に作り出していた。
「マサカズ、スーツは新調するのか?」
隣の席に着いた伊達が、そのようなことを尋ねてきた。マサカズはちりちり頭を掻くと首を横に振った。一昨日、選挙演説の案件を伊達から知らされた際、マサカズは青いリクルートスーツだと、ボディーガードとして見た目が今ひとつの様な気がするのでなんとかしたい、と事務所で漏らしていた。
「ジムもありますし、ちょっと時間足りないかなって」
「飛び込みでも一時間ぐらいでなんとかなるぞ」
伊達の言葉に、マサカズは「へー」と、抑揚のない調子で返した。
「ほんとはね、オーダーメイドがいいんですよ。身体に合いますから。銀座なんかで作っても十万円足らずで、品質のいいお店もありますよ」
低く穏やかな声でそう言ったのは木村だった。“オーダーメイド”という言葉がとてもではないが、自分には縁遠く感じる。しかしこれから先、政府との仕事が増えてくるのであれば、身なりにも気を遣っていかなければならないのだろうか。マサカズは少しばかり億劫に、それよりも大きく面白そうだと感じた。
「伊達さん、それに皆さんにお願いです。僕は、その、こんな感じで状況に応じた服装とかって全然なんで、なんていうか、ツッコミは大歓迎です」
腰を浮かせたマサカズがそう告げると、伊達を含めた皆は緩く優しい笑みを向けた。
電車のドア近くに寄りかかっていたマサカズは、手にしていた缶コーヒーをひと口飲んだ。帰宅のため乗り込んだ車内は満席で、出社の際と比べれば床面積にそこそこの余裕があったが、満員電車には変わりがなく、快適ならざる環境だった。
選挙演説の警護、建設資材の運搬、幼稚園バスの見守りと、十一月のスケジュールはそれなりに埋まっていた。経営は軌道に乗りつつあり、順調と言ってもいい。利益も出ていたため、登別から奪い資金洗浄した金も資本金以外では手を付ける必要もなかったので目減りもせず、五千万円もの資金が蓄えられている。事務所の雰囲気も居心地がよく、ジムに通ったり、会社経営に必要な知識を学んだりと、自分自身の成長も上手くいっていると思える。伊達も庭石からの案件が入ったことで、最近では営業に充てる時間が減少し、事務作業の負担も老人たちの尽力によって効率化が進み、残業時間も減りつつある。
なにもかもがいい方向に進んでいる。成功に向けて、あと何歩か進むだけだ。その途上で苦労することや悩みもあるだろうが、自分たちならきっと乗り越えられるはずだ。そして、偶然トラブルに巻き込まれてもこの力さえあれば、敢然と立ち向かえる。マサカズは思わず鼻を鳴らして笑い声を漏らした。そして、すぐに表情を曇らせた。
「もしもし葉月。ヤンマサだ」
アパートの自室で、マサカズは幼なじみに電話をかけた。
「報道はまだだけど、警察とかどうしてるんだ?」
スマートフォンから聞こえてくる声は、たどたどしく、言葉の中身は要領を得ず、同じ日本語を共通言語にしている相手とは思えないほど、会話そのものが成立してくれなかった。
「自首は、できるだけ早い方が減刑も見込める。腕利きの弁護士の協力も取り付けた。僕の会社の副社長をしている刑事事件専門の弁護士だ。まだ若いけど、腕は確かだ」
ダメで元々。そんな気持ちで情報をぶつけてみる。やはり、その返答は意味を理解できない解像度の低さだった。
マサカズは通話を切り、スマートフォンをカラーボックスの上に置いた。敷きっぱなしの布団に座り込んだ彼は、傍らにあったコンビニの袋からトンカツ弁当を取り出した。今ごろ、葉月は夫に手料理を振る舞っているのだろうか。いや、電話の様子だと、まともな日常を送っているかどうかも怪しい。違う、意外とそういった状態の方が、極めてまともな生活を保っているという考え方もできる。
わからない。誰かと結婚して共に暮らす。それも共に犯罪に手を染めたうえで。わからない。わかるはずもない。トンカツに齧りついたマサカズは、ソースをかけ忘れていたことに気づくと、小さく首を傾げた。
【無料版】第7話 ─バッタの力を借りてみよう!─Chapter2
「社会貢献を社是としているのが素晴らしいと思います。そして、寺西氏から山田社長の優れた人間性をお伺いいたしまして、ぜひともその下で学びたいという欲求にかられたのが動機となります!」
顔立ちは眉目秀麗にして、まるで古代の彫刻の様であり、百九十センチを超える長身は全体のバランスがよく、スーツの上からでも筋骨隆々としているのが窺い知れる。青い目をした短髪の青年は、事務所から五分ほどの表通りに面した喫茶店で、向かい合わせたマサカズと伊達に、淀みのない力強い口調で志望動機を告げた。
マサカズの手には履歴書があり、彼は今一度それに目を通した。
「ホッパー剛さんですね。現在、砦南大学、大学院生の……二十四歳ですね」
「はい、間違いありません」
張りのある声だ。伊達とは違う意味で、自分とは出身の根本が異なる人間だと思える。最近だと空手家の真山と近い印象だが、目の前で紅茶を啜る彼は米国人を母に持つらしく、武道家と言うよりはハリウッドのアクションスターの様でもある。マサカズは隣に座る伊達に目配せをしたが、彼は小さく顎を突き出した。これはつまり、自分が会社の代表として、雇用主としてこの青年を更に値踏みをしろという合図である。マサカズはそう諒解した。
「砦南って言えば、ノーベル賞とかも出してる超一流で。その大学院では生化学を研究……それにアメリカでの総合格闘技のアマチュア大会で優勝して、モトクロス国際B級ライセンスですか。なんか色々と凄いですね」
「はい、自分でもそう思います。しかし、自分にはまだ足りていないものがあります」
「なんですか?」
「社会経験です。特に労働というものについては、これまでアルバイトの経験もありません。自分は御社で、それを学び、積み重ね、社会と自分に還元したいと思っているのです! 今からでも自分は御社のお力になりたいと思っているのです!」
分厚い胸に逞しい手を当て、青年はそう熱弁した。
これはナッシングゼロとして、初めての採用面接だった。事務所には応接や会議に使える部屋がなかったので、この喫茶店を利用することになったのだが、店内にはこのハリウッドスターの様な青年に、関心を向ける客や店員がいた。
彼、ホッパー剛はWebサイトの採用フォームに求職の申し込みをしてきた。風変わりな名前なので事務所で話題になったところ、老齢スタッフのひとり、寺西が知っている人物だということがわかった。彼は寺西の孫の知人であり、孫に確認してみたところ、ナッシングゼロとマサカズのことをホッパー剛に教えた途端、彼は強い興味を抱き、人生初のアルバイト先として申し込みをする、と言っていたらしい。
「寺西さんのお孫さん、つまり君の知人は僕のことをどう語ってましたか?」
これはマサカズにとって重要な質問だった。寺西に鍵の秘密は漏れてはいないはずだが、マサカズの異能は薄々勘づいているはずだ。あくまでも暗黙の了解として、秘密を知る必要がないということが四人に共通しているわけであり、この問いはそれを証明するいい機会でもあった。
「誰もが思いもしない発想で異次元の成果を上げる天才。そして心が広く、穏やかで朗らかな人柄だと聞いています。そして、つい先日の篭城事件の報道を見ましたが、人質の子が山田社長がいたので怖くなかったと言っているのを知り、寺西くんが祖父から伝え聞いた人物評が正しいと裏付けられたと思いました!」
青年は大きな手振りを交え、興奮した口調でそう言った。人質だった小太りな少女、岩越まゆりが自分のことをそう言っていたのは、ワイドショーを見たスタッフの浜口から聞いていた。マスコミについては伊達がブロックしていたので、今のところ直接の取材はなく、すべて文章での対応となっているのだが、女児の発言を否定するようなコメントはせず、しかし終始平然としていたことについては触れず、ただ怖い思いをしていたと、そのような偽りの感想を返答した。
「副社長からは?」
「いえ、特にありません」
伊達は仏頂面で、腕を組んだままそう答えた。
「それでは本日の面接はここまでにします。結果は数日ほど待ってください」
「はい! よろしくお願いいたします!」
青年は勢い良く立ち上がると深々と礼をしたのち、肩を前後に振りながら喫茶店から出ていった。マサカズは椅子から立つと、青年が座っていた椅子に腰掛け、伊達と向き合った。
「どう思います? 伊達さん、ずっと無言でしたけど」
そう言われた伊達は、眼鏡を人差し指で直すと首を傾げた。
「うーん、ちょっと予想外だったな。寺西さんから聞いていたのの十五倍ぐらいのスペックだ」
「ビックリですよね。なんか、笑っちゃいます」
「企業、スポーツ、芸能……どこの採用も断る理由がないほど完璧な経歴だ。スーパーウルトラレア人材ってとこかな。これまでの採用がどれも空振りだったことを考えると、とんでもない当たりだな」
「うーん、欠点をムリヤリ見つけようとするなら、ウチに応募してきたってことですかね。彼ならもっと上のランクの会社に入れますよ」
「いや、竹下の件でお前の株は上がっている、寺西さんはぼんやりとした伝え方しかできていないだろうけど、お前は神秘性をもった存在だって捉えられていてもおかしくはない」
「僕が?」
「そうだな、難癖をつけるとすれば、ホッパーは思い込みが激しい傾向がある。ただ、それは俺たちで制御できうる類だと思う」
「あ、ホッパーって呼びます?」
「名字がそうだからな。“タケシ”はない」
二人は既に、採用を前提とした会話を交わしていた。
「非の打ち所のない文武両道なだけじゃない、英語力も大きいな。今後において、俺たちにとって大きな武器になる」
「伊達さんって英語は? あ、ちなみに僕はちっともなんですけど」
「俺もそんなに……いや、全然できない」
伊達の言葉をマサカズは意外だと思い、首を傾げて身を引いた。
「成績は悪くなかったけど、実際に使うってなるとてんでダメだった。以前、ペリーズって国の被告人を担当したことがあったんだけど、ロクにコミュニケーションが取れなくって、検察の言うがままになっちまったことがある」
「経験に基づいた自己評価ってやつですね」
「ああ」
「じゃあ、ホッパーくんは採用ってことでいいですかね」
「聞いておきたいのだけど、お前はアイツをどう思う? どう評する?」
「ありゃ完璧でしょ。それになによりも性格がいいですよ。明るくてビシっとしてますし。断る理由がこれっぽっちもない」
「ああ、確かに性格はいいな。前向きで目的に対しての明確性が強い。あれなら、いずれは鍵の件を共有してもいいかもしれない」
マサカズは想像してみた。あの美丈夫な青年と、共に解体作業や選挙の警護に当たる姿を。それは興奮を伴うのと同時に、自身のひ弱さを想起させるものだった。
「ははは、僕、彼の付き人みたいに見えちゃいますね」
「俺だってそうなるさ」
思いもよらぬ人材が門を叩いてきたものだ。篭城事件の解決も影響しているのなら、これは自分たちの努力の結果といってもいいのだろう。すっかり機嫌がよくなったマサカズは、伊達の隣に置きっぱなしにしていたコーラのグラスに手を伸ばした。
「じゃあ、ホッパーは採用にしよう。彼の希望通り、アルバイトということで」
「ゆくゆくは正社員にしたいですね」
「それは俺たちしだいだ。あの特級のエリートから愛想を尽かされないようにしないとな」
伊達はそう言うと、コーヒーをひと啜りした。経歴から類推する限り、ホッパーは総合的に高い能力を有しており、今後の事業展開において選択肢が急激に増加する。彼の働きぶりをしっかりと見定め、場合によっては計画の修正をする必要があるだろう。
「運が向いてきたかもな」
「ですよね。伊達さんもそうですけど、以前だったら僕なんかが関われるような人間じゃない」
「お前は相応しくなるように、もっと頑張るしかないな」
そう言われたマサカズは腑抜けた笑顔を浮かべると、ちりちり頭を掻いた。
定時を二時間ほど超えた夜、事務所でひとりになった伊達は、パソコンでネット検索をした。検索ワードは“ホッパー剛”である。煙草をふかした伊達は、頭の後ろに手を回し、椅子を背中の窓際に引いた。
彼の名前は、一介の大学院生としては異例とも言える分量の検索結果をたたき出していた。彼のSNSアカウント、大学での研究成果、総合格闘技、モトクロスレースでの活躍、多才故に露出も多く、下手な駆け出しの芸能人では足元にも及ばないほどである。弁護士としては、これまでに関わってこなかった類の人間であると言える。彼が法律に頼ることがあるとすれば、事件に巻き込まれ、被害者となった場合だろう。
SNSのアカウントを確認してみたところ、所属するテニスサークルでの活動や、彼女とのデートや旅行、本業とも言える研究についての記録など、どれもが華々しい学生生活と言っていい内容だった。彼女の露出が一年前を境にしてまったくなくなったのは、何らかの事情があったのだろう。
ひとつだけ気になったのは、政治的な発言に関する部分だった。現行政権に対しては批判が強く、その指摘は的確であると言え、対案も頷ける内容である。そうなのではあるのだが、自分とマサカズがこれから進んでいく道を、彼は共に歩むことができるのだろうか。
伊達は煙草を灰皿に押しつけると立ち上がり、ハンガーから上着を取った。道を違えるのなら、それはそれで仕方がないことだ。事業を拡大していくには国との関係は良好に保たねばならず、学生の理想主義になど付き合ってはいられないのだから。彼はそう結論づけると、夕飯はどこで何を食べようかと考えを切り換えた。
【無料版】第7話 ─バッタの力を借りてみよう!─Chapter3
彼は自分などより、ずっとこの場に相応しい。マサカズは隣に並ぶ暗灰色のスーツを着たホッパーを一瞥し、今日になって五度目となる感想を抱いた。仕事が始まってからまだ十分しか立っていなかったが、もう何度も同じ感想が繰り返されている。天井部にお立ち台が取り付けられたライトバンを背に、胸を張り後ろで手を組むこの青年は、いかにもボディーガードという風体である。
静岡県磐田駅の駅前ロータリーでは衆議院補欠選挙の演説会が行われ、ナッシングゼロはその警護の仕事を庭石の口添えで受注していた。業務の内容としては先月の浜松駅の市長選挙演説会と同じであり、終わるまで何があっても何もせず、ただ立っているだけといった前提で取り組むことになっていた。お立ち台には応援の弁士はおらず、与党が推薦する立候補者とその支援スタッフが二名いた。集まった聴衆は四十名ほどであり、その大半が老人だった。
「どうにも納得できません。何もしないというのは、職務怠慢かと思われるのですが。私にとってこれは人生において初仕事です。人に誇れぬ行いは我慢なりません。私とは思想信条を違える対象ではありますが、警護という職責を全うするためには、危害行為に対して全力を以てして対するのが当然だと思います」
今から二時間前、駅近くのプレハブ小屋で警護の事前ミーティングを終えたマサカズとホッパーは、現場に向かうため路地を歩いていた。ホッパーの不満に、マサカズはちりちり頭を掻いた。ホッパーには昨日の十一月十七日の金曜日からアルバイトとして勤務を始めさせていて、今日は初めての外勤だった。
「伊達さんからの指示なんだよ。僕たちは特権でこの仕事を得ているけど、素人だから専門性のある対応をしちゃいけない……そうだなぁ」
ただその場にいて何もしてはならないのは、鍵の力を秘匿としなければならないからである。テロリストが行動を起こした際、自分はこの力を使わずに対処することなどできないからだ。しかし、青い目をした屈強な彼はどうだろう。アマチュアではあるが、総合格闘技の王者にもなったほどの実力者である。自分などよりは優れた対応ができるかもしれない。だが、警護の素人であるマサカズには、それを許可するだけの根拠を持ち合わせてはいなかった。
「えっとさ、ゴメン。ホッパー君、ひとつ間違ってる。これは君にとって初仕事じゃない。君はきのう、みんなのお弁当を買ってきたり、名簿の整理をしたり、ホームページの英訳を始めたり、しっかりと働いてくれているじゃないか。立派に務め上げているよ」
そう言い終えると、ホッパーはマサカズの前に素早く回り込み、重々しく頭を垂れた。
「社長のおっしゃる通りです。私は仕事というものに対して、勝手に軽重をつけていました。深く反省いたします! そして、誠に感謝いたします!」
それから、ホッパーとは駅前に到着するまでのあいだ、この街を本拠地とするプロサッカーチームの話題に終始した。彼の真っ当な不満に対して答えられなかった。とにかく立場上何かを言わなければいけないといった、漠然としたプレッシャーのための指摘だったが、彼はそれに対して深く反省してしまい、自分に対しての従属心を強めてしまった。マサカズは今後、ホッパーへの理解をより深め、より慎重な対応が必要だと思った。
今回の件について、ホッパーは行動指針に対して納得できず、多少の燻りは生じるだろうが、結果としてこの演説会では何かをする機会自体が発生しないので、うやむやのままにしてしまえるだろう。そして、いずれ彼への信用が一定の値に達すれば秘密を共有し、遡った上で理解を得られるだろう。立候補者の熱弁を背に、マサカズはホッパーとのそのようなやりとりを思い出していた。
庭石とは、この十日ほど連絡が取れなくなったままになっていた。携帯電話には応答せず、法務省に登庁はしているのだが、一時的な不在を理由に電話で話もできず、メールの返答もないと伊達は言っていた。今日の仕事を割り振ってはくれたものの、娘が違法薬物の中毒に陥り、父親としてそれに向き合うことに懸命なため、自分や伊達に対して関わり合う余裕がないのではないのだろうか。マサカズは現状をひとまずそう解釈していた。
娘が薬漬けになる。夫と女子高生を山に埋める。宝石店に強盗して幼稚園バスを乗っ取る。誰もが余裕もなく、司法の処断に怯えている。それなのに三人を殺害した自分は、昨晩、歓迎会でホッパーと、うろ覚えのボーカロイド曲をカラオケでデュエットして呑気に楽しんだりしている。あの罪を打ち明けたら、隣に立つ彼はどのような反応をするのだろうか。正義感が強いのはもうわかった。おそらくはこれまでの成功経験に基づき、自身の価値観に疑いがないからだろう。受け入れ、内側に入れてしまったものの、ホッパーという存在はマサカズにとって処理しきれていないゴミ箱を、あらためて覗くきっかけとなっていた。
いわし雲の元、二度目となる警護という仕事に対して集中できず、ぼんやりとしたままだったマサカズが次の瞬間目にしたのは、隣にいた暗灰色の背中が弾丸のように突進し、聴衆の群れに突入し、中年男性に掴みかかるといった、日常ならざる光景だった。マサカズはホッパーの唐突な行動に驚き、慌てて駆け寄った。
「ホッパー君! なんだ!?」
ホッパーは白髪交じりの男の右肩を抱え込み、アスファルトに組み伏せていた。
「テロリストです!」
ホッパーの報告は明確だった。マサカズはそれに対しての検証を試みたが、関節技を極められているこげ茶色のブルゾンを着た男から、テロリストの要素を見つけ出すことができなかった。すると、黒いスーツ姿の女性が駆け付け、男の傍らにあったトートバックをまさぐり、銀色の筒を取り出した。
「ティーツーか。おそらく」
女性の言った“ティーツー”とは、事前の打ち合わせでも説明された、投擲型の爆発物の呼称である。火力しだいでは殺傷能力を有するものであり、もし本物ということなら、ホッパーに制圧されている男はテロリストということになる。
「あ、山田さん?」
筒を手に振り返った女性は、浜松の一件で知り合った警備会社の田宮だった。
演説会は急遽中止となり、聴衆の中でスマートフォンを持っている者は、その原因となったホッパーとトートバッグの男を動画に撮っていた。おそらく、午後のニュースで“視聴者提供”のテロップ付けられ、これらの映像は流されるのだろう。唐突に訪れた緊急事態に、マサカズは困惑しながらも納得に向けて考えを整理することにした。そのためには、とにかく置いてきぼりにされてしまった当事者に話を聞く必要がある。
トートバッグの男は警察に引き渡され、マサカズたち警護スタッフは事前のミーティングで利用したプレハブ小屋に戻ってきた。
「ホッパー君、お手柄だ。よくやった」
雇用主の賞賛に対して、美丈夫は分厚い胸を張り強く鼻を鳴らした。
「会社の実績に貢献できたと思います!」
「僕にはまったくわからなかった。あのトートバッグの男が危険人物だって、どうやって気づいたんだ?」
「はい、あれは悪意溢れる形相でバッグに右手を突っ込んだまま、最前線で候補者への距離を測るように細かく前後に身体を運んでいました。不審だと思ったのです。そして、遂に見えたのが銀色の筒です」
ホッパーが制したあの男は、マサカズも存在を認識はしていた。しかし、彼から悪意はまったく感じなかった。
「それだけの情報で、あの行動をとったの?」
わかりづらい問いかけだと思ったが、マサカズには適当な言葉が思いつかなかった。ホッパーはしばらく黙り込むと、両手を窓を拭くように震わせた。
「すみません社長! 何もしてはいけなかったのですよね! なのに自分はやってしまった! いま処罰の覚悟をしている最中です!」
裏返った声の謝罪に、マサカズの傍らにいた田宮が吹き出して口を手で押さえた。
「山田さん、なんです? 面白いわね」
そう言われたものの、マサカズは返す言葉が見つからなかった。プロの警備スタッフがホッパーを笑い事にしている。つまり、今回のこの“やってしまったこと”は、この業務において許容されたということになる。
「トートバッグ男、どうなったんです?」
マサカズは田宮にそう尋ねた。
「現行犯逮捕されたわ。おたくの行動はいささか早すぎでしたけど、爆発物が二発にサバイバルナイフが一本押収されたから、結果論としてあいつはテロリスト認定されたわね」
「じゃあ、ウチが叱られることはないってことですか?」
マサカズの言葉に、田宮は意外そうに細い目を見開いた。
「なんですそれ? お手柄ですよ。公安からの評価も爆上がりですよ。羨ましい。こんなこと、滅多にないんですから」
興奮気味にそう語る田宮に、マサカズはちりちり頭を掻き、ホッパーの分厚い胸板を裏拳で軽く叩いた。
「ホッパー君、君の行動は正しかった。間違っていたのはウチの方針だ。今後もこの調子で頼むよ」
「処罰はないのですか!?」
「君のおかげでひとりの政治家の命が救われた。そしてウチには今後、こういった仕事が増えるかもしれない。今日のこれは大いなる実績だ。ありがとう」
ホッパーはマサカズの賛辞を即座に理解できていないようであり、何度も大きく瞬きをし、うめき声を上げていた。二十四歳の青年だが、その内実は少年のように素直で単純で、それが許される人生を送ってきたのだろう。マサカズはそう理解すると、羨ましく思った。もし彼に鍵の力を与えたら、迷いなく正義のために活用してくれるのではないだろうか。例えば先日のバスジャックも瞬時に解決し、そもそもバスが乗っ取られること自体がなく、竹下を車外で制圧していたかもしれない。マサカズはスラックスのポケットに手を突っ込み、力の源を握った。
この演説会で、会社としては大きな実績を残した。今後は庭石の紹介に頼らず要人警護の仕事が回ってくる可能性も出てきた。これらが事実に基づき想定されうる未来である。伊達の方針に反した結果でもあるが、彼は思考が柔軟なので方向性の変更をいくらでもできるはずである。マサカズは田宮と談笑するホッパーを見上げ、この極めて優秀な人材をこれからどう起用していくべきか、伊達と相談する必要があると感じていた。
【無料版】第7話 ─バッタの力を借りてみよう!─Chapter4
演説会のあったその日の夕方、電話をかけてきたマサカズの第一声は「今日は事務所ですよね? 何でもいいので磐田駅のテロ事件のニュースを確認してください」だった。つい先日、事務所用に購入したテレビを点けてみたところ、磐田駅前のロータリーで、爆発物とサバイバルナイフを持った男が警察官に確保されている事件を報道していた。マサカズが説明するには、この検挙の初手はホッパーによるものであり、彼は自分たちが決めた取り決めを破ったが、結果として大きな手柄を立てたということになる。つい先ほども公安の責任者を名乗る人物から感謝され、名刺交換をしたとのことだった。
伊達はすぐに従来の方針を修正する必要があると思った。今後において、ある程度はホッパーの自由意志での判断を容認する必要がある。しかし、そうなるとこの会社の実態と彼の能力をどう釣り合わせるか、慎重な調整を心がけなければならない。伊達はマサカズに労いの言葉をかけ、電話を切った。ホッパーという青年は、自分が思っていたよりずっと優れているようだ。初仕事で聴衆の中から暴漢を見極め、真っ先にそれを無力化する。まるで公安のスペシャリストのようだ。マサカズの力と同じように常識が通じないスペックではあるが、マサカズとは異なり、然るべき機関で検査をすれば、それは充分証明がつけられる能力なのだろう。唯一の不安点は、暴漢と判断した途端、すぐに制圧を実行したことだ。あまりにも迷いがなさ過ぎる。自信過剰と言ってもいい。書類に目を通しながら、伊達は生じていた懸念に顔を顰めた。
それから二日後、十一月も後半に入ろうとしていたよく晴れた月曜日の朝、マサカズが事務所にやってきた。伊達が何気なく目を向けると、彼は黒い革製のダブルのライダージャケットを身に着けていた。
「わ~お社長! シュワちゃんみたいじゃない。カッコい~!」
腰を浮かせた浜口が、からかい交じりにマサカズへ声をかけた。マサカズは照れ隠しでちりちり頭を掻くと、ジャケットを脱ぎながら伊達の隣の自分の席までやってきた。
「おはようございます」
「ああ、おはよう。それ、買ったの?」
「ええ、なんか急に寒くなってきちゃったんで」
マサカズがそう言うと、ロッカー近くの奥の席にいたホッパーが右手を挙げた。
「自分がお付き合いしました!」
「ホッパーが? マサカズと?」
いくら警護の仕事を共にし、年齢がそれほど離れていないとは言え、入社して数日のアルバイトが社長と共に個人的な買い物に行く、といった状況と、そこに至る人間関係の構築方法が、伊達には少しばかり理解できなかった。
「はい! 自分、ジャケットには少々ではありますが詳しいので、昨日は有楽町で社長の服選びのお手伝いをしました!」
「剛くんはね、雑誌のモデルをやったこともあるんですよ」
寺西の補足に、ホッパーは掌で弧を描くように泳がせ「たいしたものではありません! お願いされ、一度だけやっただけのことです」と、上ずった声で言い訳をした。伊達は眼鏡を人差し指で直し、小さく咳払いをした。
この調子だと、ホッパーには履歴書では計り知れない経験や、スキルがまだまだあると思っておいた方がよいのだろう。いずれは「学生プロレスなら、頼まれていち試合だけ出場しました! なんとマスクマンで、見よう見まねでトペスイシーダという技をやってみました」だの「実はゲームソフト、ダウンロード版のみのインディですけど、ディレクターを頼まれて引き受けたんですよ。のちのち配信者のあいだで流行ったので、いっとき話題になってしまいましたね」だの「サウナですか? 本場と言われるフィンランドのなら行ったことがありますね。あ、現地の友だちから、付き合ってくれって頼まれたからなんですけど。最初の一度で“整い”ましたよ」だの「二輪免許、実は限定解除してるんですよ。あれ? 履歴書にその点も書かないといけなかったのでしょうか? いや、知人からツーリングに付き合ってくれって頼まれたもので」だの言い出してくるかも知れず、今後なにが判明したところで驚くこともなくなっていくような気もする。伊達はそれがひどくつまらないと感じていた。
隣の席にいたマサカズから見ると、頬を引き攣らせている今の伊達は困惑しているようでもあり、呆れているようにも見受けられた。いずれにしてもその対象はホッパーだろう。一昨日の仕事で最も驚かされたのが、不審だと思える程度の存在を、瞬間的にテロリストにまで認定し、なんの躊躇いもなくタックルで潰し、肩を固めたことだ。結果としては会社にとって大きな実績となったが、あの晩アパートに帰ってからもう一度よく考えてみたところ、彼は自分の判断がもし間違っていたら、勘違いだったらという可能性を考えなかったのだろうかと、そのような疑問が湧き起こった。昨日は一緒に買い物に出かけたが、普通に接する分には礼儀正しく快活で、わからないことは何でも質問してくる好青年だ。しかし今後、彼と日常ならざる事態に直面した場合、自分は制御役として注意を重ねる必要がある。この点については今夜にでも伊達と相談してみよう。この懸念は伊達ならきっとわかってくれるはずだ。そう思ったマサカズが改めて隣を振り向くと、座っていたはずの伊達は腰を浮かし、両手の先は小刻みに震え、顔色も悪く口元はわなわなと震え、眼鏡は鼻先までずれ落ち、眉間には深い皺が寄せられ、その様子は明らかにいつもの冷静な彼とはかけ離れていた。
「伊達さん? どうしました」
マサカズの言葉をきっかけに、事務所にいた四人の老人たちとホッパーの注意が伊達に向いた。
「庭石が、死んだ」
絞り出すような掠れた声で、伊達は極めて単純な内容でありながら、この小さな事務所の空気を瞬時に凍り付かせる言葉を漏らした。
法務省大司法法制部司法法制課長、庭石哲治享年五十四歳。中央区の自宅書斎にて彼は、首を吊っているところを妻に発見された。足元には遺書と思われる手紙が残されていて、自殺であることは明らかだった。庭石は都内の病院に救急搬送されたものの、既に窒息死していたとのことである。事務所のテレビで報じられるそのような内容のニュースを、皆が固唾を呑んで注目していた。しかし伊達だけは力なく、ぐったりとした様子で、視線は宙を泳ぎ定まってはいない。自殺の原因に心当たりがあるマサカズは、伊達が責任を感じ、自身を追い詰めてしまわないかと心配していた。
「この庭石という法務官僚は、我が社に案件を紹介してくれる、いわばパイプ役のような人物だったわけですよね?」
ホッパーは淀みない口調で場の者達にそう尋ねた。四人の老人は明確な意思を示すことなく、呻くような声を上げ、なんとなく頷き返すだけだった。
「そうだホッパー君。庭石さんは僕たちにとって仕事仲間のような人だった。死んでしまったのは、とても残念だし悲しい」
マサカズは責任者としての役目を果たすため、ホッパーにそう説明した。
「連絡とか、葬式とか、なにか我が社からすることはないのですか? 自分でよければなんでもお手伝いしますよ」
ホッパーがあまりにも自然に口にする“我が社”という言葉が、放心していた伊達の心を小さく、くすぐるように波立たせた。
「僕たちと庭石さんの関係は、あまり公的なものじゃないんだ。だから、然るべき人にこれからどうするべきか相談する」
マサカズはホッパーや木村たちにそう説明すると、最後に「それでいいですよね、伊達さん」と付け加えた。確認された伊達は上体をビクリと痙攣させると、隣のマサカズに振り向いた。
「あ、ああ、うん。マサカズ、連絡を頼む。お前に任せていい?」
裏返った頼りない声だった。これまで、伊達がパニックに陥ったのは見たことがあったが、想定外の事態に対して、子供の様に途方に暮れる姿は記憶になかった。こうなってしまうと、それこそ護るべき存在だと思って扱うしかない。マサカズは席を立つと、伊達の両肩をしっかりと掴んだ。
「伊達さん、今日はもう早退してください。電車で。いいですね? 今日一日ぐらいは僕がなんとかしますから。明日までにいつもの伊達さんにしてきてください」
伊達の泳いでいた目は、ようやくマサカズに向けられた。彼は何度か頷くと眼鏡を両手でかけ直したのだが、途端に激しく咳き込んでしまった。マサカズはその背中をさすり、「大丈夫です。大丈夫です」と語りかけていた。
東京都中央区月島は、都心に近く湾岸地帯に位置する、もんじゃ焼きが名物で知られる下町だが、同時にタワーマンションが林立する高級住宅地といった一面も有していた。その中のひとつ、三十七階建てのタワーマンションの二十八階に、庭石は妻と娘の親子三人で暮らしていた。遺書があったものの、病院ではなく、医師も不在での死亡だったため、遺体は慣例通り死因を調査する目的で検視に回された。伊達が言うには、これが殺人事件だった場合、検視には相当な時間がかかり、ケースによっては数ヶ月を要するらしい。しかし警察の調べですぐに事件性がないと判断されたため、僅か一週間足らずで、遺体は文京区大塚の監察医務院から遺族の元に返されることになった。妻の意向によって遺体は自宅マンションではなく、すぐ近くの葬儀場に運び込まれることになった。そして通夜と葬儀を経て、庭石の亡骸は十一月最後の日曜日となる今日、土砂降りの中、黒い霊柩車で江戸川区瑞江の火葬場に持ち込まれた。自殺から今日の火葬に至るまでの流れを猫矢から得ていたマサカズと伊達は、その駐車場に傘を差して佇んでいた。
遡ること訃報の翌日、出勤してきた伊達はいつも通りのコンディションを取り戻していた様子だった。マサカズが早速行ったのは猫矢への連絡であり、今日までの六日間で集められた情報は、庭石の死についての警察の捜査状況と遺体の検視、葬儀のスケジュールについてだった。
マサカズと伊達は傘を差し、火葬場の入り口をじっと見つめていた。
「きのう、追加の情報があったんですけど、もちろん遺書には娘さんのこととか僕たちについては、一切触れていないみたいです。自殺は、仕事への悩みが原因ってことになっていたそうです」
「すまない、マサカズ。ここしばらく、お前にほとんど任せちまって」
「まぁ、猫矢くんと話すのは、もちろん雑談の方ですけど、結構面白いですし」
庭石の葬儀に対して、当然のことながらマサカズと伊達は招待されていない。いま火葬場にいる庭石の親族たちの中に、二人を知る者は皆無となる。
「伊達さん、大丈夫ですよね?」
「ああ、もちろん。もう今後について考え始めているよ。お前が磐田で名刺交換した相手もいるし、明日からでも営業再開だ」
この火葬場に訪れるのを提案したのはマサカズだった。何ができるというわけでもなかったのだが、庭石の最後をせめて見届けよう。そのような意図であり、伊達が拒めば説明するつもりだったが、彼は素直に従った。そして、その理由をマサカズは特に確かめたくなかった。
しばらくして、火葬場から喪服姿をした一組の家族が出てきた。人数は三十名ほどで、中央には骨箱を抱えた中年女性の姿があった。あれは庭石の妻だ。猫矢からの資料で顔を知っていたマサカズは、その隣で彼女の肩を抱き支える、ひどく痩せこけた若い女性の存在に気づいた。
「庭石陽菜 ですね。あの子」
「ああ」
遺族と思しき誰かが差し出した傘のもと、母と娘は嗟嘆に暮れていた。彼女は四度、違法薬物を使用し、父の死の要因ともなった娘である。マサカズと伊達は彼女の秘密を知っていた。だが、今となってはそれはもう何の利用価値もなく、僅かにも意味を持たない。マサカズと伊達は背中を丸め、土砂降りの中を並んで歩き、火葬場を後にした。
第7話 ─バッタの力を借りてみよう!─Chapter5予告
マサカズの前に立ちはだかる超武神。その戦いの結末は…。
「無料配信版」の続きはこちら!
※最新話は以下で読むことができます(※下の「2024年間購読版」はかなりお得でオススメです)
◆一番お得な「2024年間購読版」でも最新話をお届けしていきます!
※初めての方は遠藤正二朗氏の「シルキーリップ」制作秘話も読める「Beep21無料お試し10記事パック」もあわせてご覧ください!
遠藤正二朗氏の新作小説
「秘密結社をつくろう!」では
みなさんからの応援メッセージや
感想をお待ちしています。
続きも楽しみ!と思った方は、記事の左下にあるハートマークの「スキ」も押していってくださいね。どうぞよろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?

