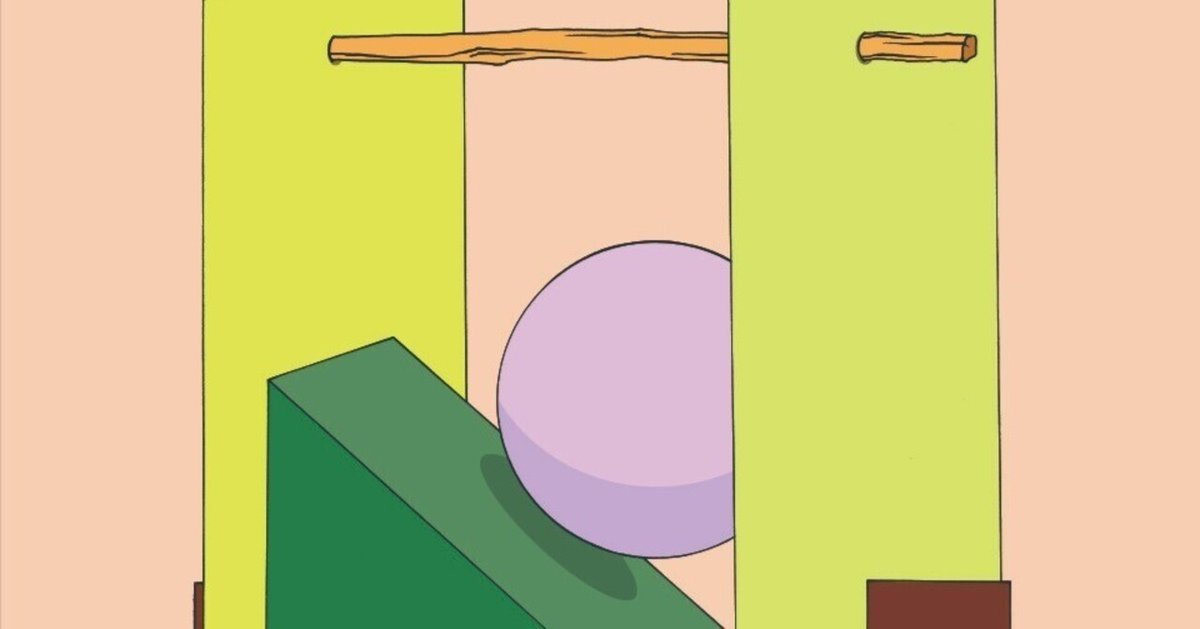
連載 第十八回:幸せ÷当たり前
最果タヒ『MANGA ÷ POEM』
Text:Tahi Saihate / Illustration:Haruna Kawai
ビームスが発行する文芸カルチャー誌 IN THE CITY でも大好評だった詩人・最果タヒの新連載が登場。好きな「漫画」を、詩人の言葉で見渡すエッセイ

帰りたい、と家にいたって思うし、幸せになりたいと、幸せがなんなのかも具体的にイメージできないのに思う。本当のところ「世間的な幸せ」に自分がどこまで引き摺られているのかもわからず、そうじゃなくてもっと人によって様々な「幸せ」があるのですよと教えてくれる作品を、そうだよね、と受け止めて頷きながら、人はいつまで「先入観」や「みんなの意見」に首を横に振る形で「私」を見つけなくてはならないのだろう、と考える。自由を思い出すために、この世界の居心地の悪さに目を向けなければならないことが、なんだかいやだな、まるで退屈な世界に生まれたみたいじゃないか、と思ってしまう。きっと実際退屈なところもたくさんあるのだ。でも、どこかで、この世界もそれなりに好きな自分がいることを知っている。
自由に生きる人たちや「当たり前」に抗う人たちに元気をもらうときは、いつも、世界の歪さと対峙しなければならない、敵対さえしなければならないこともある。その世界の不自由さに本当はずっと気づいていた自分を直視する時間でもあり、私は自分の鈍感さが嫌になるのだ。この世界を好きだと思う自分は馬鹿なんだなぁって思ってしまう。
『プリンセスメゾン』の阿久津さんが、私は好きです。彼女は彼氏と別れた後も、寂しさのあまり早く誰かを見つけて付き合いたいと考えたり、家族連れを見て自分の現状に不安を抱いたり、そうした「当たり前」や先入観にかなり囚われた人だけれど、そうした価値観を他者に押し付けることはほとんどしない。自分の同僚が好きなアーティストを追いかけすぎて音響外傷になったときも、涙を浮かべながらもそんな無茶苦茶な追いかけ方はするな、とは(言いたいのに)言わなかった。
「ほんとはほんとはライブ行くのとか止めたいですよー。私たちの将来は不安がいっぱいなのにちょっとでも健康でいたいじゃないですか。」
「でも人生って安全に健康に安定して生きてければ幸せってわけじゃないことくらい…私だって知ってるから。」
阿久津さんにとってこの世界はどんなふうに見えるのだろう、と読むたびに、思う。
世界が勝手に決めた「幸福」に体を収めようとしても絶対に無理で、それがうまくできたとしてもそれを幸せだとは思えない、とはよくわかっている。淡々とそうしたものに背を向けて生きている物語のキャラクターを見ると、勇者の物語を追いかけているようなそんな感覚になり、私もそうでありたいとただ憧れるし、憧れられるだけで自分の心はだいぶ明るくもなるんだ。幸せって多分、「幸せになろうとする」ことそのものであって、けれど自分の心でなんの力も借りずに最初からそれができる人はきっととても少なく、だから先入観に囚われず、世間的な幸せではなく「私の幸せ」を最初から追える人には(そして私は)憧れるのだろうな。私は、彼女たちほどはっきりとしていない、むしろいろんな「当たり前」に身を任せて生きていた時間が過去にたくさんある気がしていて、無頓着にぼんやりと生きてきたそんな自分をそうした物語を読むとたまに思い出し、悲しくもなった。私はこの世界を正しいとは思ってないが、好きなことがあるし、一つのことを考えるのに夢中になりすぎる時間もあるし、決して全てを見通せてはいないと思う。正しくあってほしいと願うことはできても、たぶん私にはまともに見えてなくて、悲しむはずのところでなんとも思わずにいたことがきっと何度もあったと思う。勇者たちのことを「勇者だ」と思うたび、私は私のことが嫌いになります。それは本当に、どうやっても抗えないのです。
本当は、そうした「勇者」だって、完全に世界の「当たり前」から切り離された幸せなんて見つけていないのだと、自分を嫌いになる間は忘れてしまいます。自分の方がずっと世界と同一化してるから、彼女たちが切り捨てられない「世界」の存在に気づけず、ひたすらに勝手に無自覚に、神格化してしまっているから、彼女たちも今の世界の中で今の社会の中で、いろんなものに体と心を馴染ませて生きている。その中でどの部分は己を貫くか、それこそが大切で、そして戦いなんだっていうことに私は長く気づかなかった。
きっとそれは、そうした物語の中にはもっと世界の「当たり前」に引き摺られている人が多く登場し、そしてそんな人たちが勇者たちに拒まれる場面が出てくるから。だから私はそのたびに変な汗をかき、そして、それから目を逸らすように、勇者たちに憧れてしまった。
「プリンセスメゾン」では、さまざまな女性が「家を買うか」どうかを考え、行動している。そこには「家は家族ができてから」とか「女性一人ぐらいで家を買うの?」とか「結婚以外の幸せ」とか色々出てくるのだけれど、それらも、そもそも家を買うかどうかの話も、根っこからこの社会のあり方に寄り添った話で、世界から独立はしていない「幸せ」の話だとも思う。この物語に登場する人たちはみな、そうした社会の中でどうしても生きなければならず、でも、この物語が透き通って見えるのは、みながそれらを個人の出来事として語っているから。それは、勇者のような人たちだけでなく、この物語に登場するほとんどの人がそうだからだ。社会的な幸せにかなり近いところに生きている人も「私の幸せ」としてしかそれを捉えていない。他者にそれを押し付けない。だから、社会から簡単には離れられないことや、この世界そのものに鈍感な部分があることに、自己嫌悪が湧くことはなく、全ての人が並列に見えてくる。私として生きて、私として全てを決めて生きていきたいと願うけど、その「人生」は世界の中にあり続ける。世界にある「人と人の付き合い」や、「仕事と人生のあり方」や、「他者との距離の置き方」と無縁になって、「当たり前の価値観」から解放されることはきっとない。世界という水槽の中でどう生きるか、その話をずっとしてくれるから安心するのかもしれない。
だから、私はこの作品が好きです。勇者のことを追いかける物語のふりをして、ここにいるのはみんな普通の人たちだ、と私は思う。勇者の勇気ではなくて普通の人の勇気の話だ。そして、そんな中で、水槽の水に慣れ親しみ、大してそこに違和感を抱かずにいる阿久津さんが、たまに苦しくなったりもしながら、それでも優しくて柔らかな心を他者にだけは向け続け、愛されて、そして彼女はいつまでも未熟な自分を嫌いにならず、恥じず、むしろちゃんと自分を好きでいることが嬉しかった。私にとってとても特別なキャラクターです。
・プリンセスメゾン(池辺葵・著)
https://yawaspi.com/princess/

さいはてたひ。詩人。詩やエッセイや小説を書いています。
はじめて買ってもらった漫画は『らんま1/2』。
はじめて自分で買った漫画は『トーマの心臓』。
