
連載 第四回:みんないろいろあるんだね÷愛情
最果タヒ『MANGA ÷ POEM』
Text:Tahi Saihate / Illustration:Haruna Kawai
ビームスが発行する文芸カルチャー誌 IN THE CITY でも大好評だった詩人・最果タヒの新連載が登場。好きな「漫画」を、詩人の言葉で見渡すエッセイ

そんなにもあなたは、他人なのだろうか。
学生時代、友達のことをよく知っている気がしていた。よくわかっている気がしていた。彼女の家も彼女の家族もよく知らないのに、彼女がどんな幼少期を生きたのかもわからないのに、私は彼女をよく知っている気がしていた。親しいとはそういうことだと思っていた。どんな家に帰っていっているのか、どんな夕飯を食べているのか、知らない。想像ができない。私の知らない時間の方が、ずっとあなたの1日を多く占めて、それなのに私の日々に、あなたは強く存在し続けて。あなたのことをよく知っていると、私は簡単に思ってしまう。
中学のころ。わかっているつもりだった、相手は他人だということ、話せば想像もしなかった返事をもらうということ、それらを何度も経験しているのに、私はその子たちのことを全て「わかっている」と思ってしまった。私にとって彼女たちはあまりにも大きな存在だったから。彼女たちの目に自分がどう見えているのか、私は多分一日中気にして生きていたから。私が、私として生きているのは学校の中だけで、そこでどれだけ「私」でいられるかということを、私はずっと考えていた。学校の中でだけ完結した「私」でいられるのが、多分楽しかったのだろう。それは虚構であるし、家族や近所の大人たちの目がある自分の人生の流れからは切り離されているように思えた。自我がなく、様々な人の助けで育った幼い頃の私と切り離した形で、私は自立した「私」を1からここで作ることができる、全ての選択を自分ができる気がしていた。だから、学校で作るものや、話すこと、友達との関わりが最重要で、学校の外でも生きていたはずなのに、学校の内側にいる自分がほとんどの自分だと思っていた。
そう思えることはとても恵まれていたことだったのだが。
でも、誰もがそうに違いないとどこかで思っていたのだろう。
1から自分を作ることができる、と考えられるほど、当時私は自由だったのだと思う。家庭や学校外の人間関係を引きずる必要がなかった、多少の悩みはあれど、それが学校生活を左右することはなく、頭から離れない、なんてことは多分なかった。今になってそう断言することはすこし難しい気もするが(私はもう当時の私とは別人なので)、自分自身ではどうすることもできないしがらみが少なく、学校という舞台を現実から切り離して見ることができてしまっていたのかなと思う。
自分にとって、学校の中にいる自分が全てだった。というより、そう思い込んではしゃいでいた。だから他人もきっとそうで、学校で見えるものだけが全てだとつい思ってしまって、それがあまりにも大雑把な態度であると、たびたび気づいて落ち込んでいた。わかったつもりの友達が、わからない表情をすることがある。そのたびに申し訳なくて、自分の鈍感さが嫌になり、それなのに「知り尽くした仲間」としていることが、理想的な友人関係なのではないかとつい憧れてしまいそうだった。
彼氏彼女の事情。私が中高生のころ愛読していた漫画。当時リアルタイムで漫画を追って読むなんてこの作品以外はしていなかったし、私にとって当時「少女漫画」といえばこの作品を指していた。主人公の雪野の視界から外れたところで、他の登場人物の人生や事情が開示される。学校はただの他者の人生が交差する場所でしかないのだと、作品は幾度も思わせてくれた。その作品を見て、当時の私はどんな夢物語よりドラマ性を、ロマンティックなものを、感じていたのかもしれない。あなたは他人だ、ということを、私は教室でずっと思い知りたかった。でも自分は「知らない」ままだ、わからないままだ、それぞれに何かがあるのだということがちゃんと理解できなくて、それがただもどかしかった。知らなくても、わからなくてもいいから、それを「無いもの」だとは思いたくない。わからないことの奥行きを中身がわからないまま、受け止めていたい。そう願いながらも実行するには難しくて、頭を悩ませていた。もしも、私の視界の外で描かれるあなたの物語があるなら、その気配だけでも感じていたかったし、それがあるということだけでも知る人でありたいと思っていた。でもそれは難しいことなのだ、現実は。みんないろいろあるよね。なんて言葉が、本当に何も知らない状態で、冷たいものでも、距離を感じるものでもなくて、単なる事実として、発せられる人間になれるかなあ。私は多分、「学校の中にいる自分」が自分の全てだと思えてしまう自分が、浅い気がして不安だったのだろう。自分にも奥行きがあれば、もっと他者を見つめられたはず。もしかしたら、自分の全てが学校にあるなんてただの勘違いかもしれないのに、それにまだ気づかない。私は、他者とまっすぐに向き合うことを、その時点で避けているのではないかって。
彼氏彼女の事情の主人公・雪野を見ていると、そんな不安が当時の私から消えていったのかもしれない。彼女には「事情」と呼ぶべき人生の課題や痛みがほとんどないが、彼女は他者に対して真摯だった。そして、自分自身に対しても彼女はどこまでも真摯だった。
私は学校にいるときの自分が好きではなかった。自分で1から作れる自分だと思いながら、理想的な自分ではちっともなくて、毎日帰宅してから、学校で言ったことや、したことを思い出して叫び出したいような気持ちになっていた。自分が思うことを思うままに言うのは、嘘をついているような気がしてしまう、変な話だけど、自分がするべきだと思ったことをしたら、恥ずかしくてたまらなくなるのだ。私は私のままでいようとしていただけで、でもそれが思っていた以上に困難で、まるで自分が何かを演じているような錯覚に陥っていた。自分をさらけ出しても、世界の固く結ばれた糸は自動でほどかれていくわけではない。たださらけ出した柔らかいところがどんどんその糸に触れて、躊躇っていく。自分だけが嘘をついている気がした、自分というものを作っている気がした。いつまでも自分の思うように行動するには勇気が要って、自分にとっても意図しなければできない、「不自然なこと」だった。学校にいる自分が全てだなんて勘違いのような気がして、自分を偽っている気がして、気まずかったのだ。学校が全てだと思えるほど、幸運なだけだったのに。友達のことをまっすぐに見つめる時間がたくさんあるという、それだけのことだと今はわかるのに。当時は、みんなと向き合う資格がないような気が(すこし)していたのだろう。
天性の真摯さを持つ雪野が最初とてつもない嘘つきであったこと。彼女がどこまでも意識して、正直に生きようとすること。当時、私がどんな気持ちでこの作品を読んでいたのか今の私にはわからない、読み直して、なんていい作品なんだろうと驚いたけれど、でも、当時はただ雪野が好きだったし、雪野が誰とでも友達になれることが、なぜか私に勇気をくれていた、そのことしかわからない。彼女の他者との距離感は、私にとってたぶん一番憧れる「他人」だった。その理由を「知性」だと断言できるこの作品の力強さも、特別だった。そうだね、知性だ。考えることができる、思いを馳せることができる。わからなくても。雪野は、他人に出会って、自分を思い知って、それからずっと勇気を出している。勇気を出して、考えている。彼女における「知性」は裏を返せば勇気だった。当たり前なんてなく、そして自然に出せる「自分らしさ」なんてどこにもなく、彼女はずっと勇気を出して「自然な私」でいる。今読み返すと、私はだから彼女が好きだったのだろうと思えた。誰もが自分でいることは怖いよ。いつまでも慣れやしない。でも、勇気は、作り出すことができるものだ。考えることができれば。諦めなければ。真摯であるための武器として、手を伸ばせば届く武器として、知性を描くこの作品が私にとって大切だった。
・彼氏彼女の事情(津田雅美・著)白泉社公式サイト
https://www.hakusensha.co.jp/comicslist/48182/
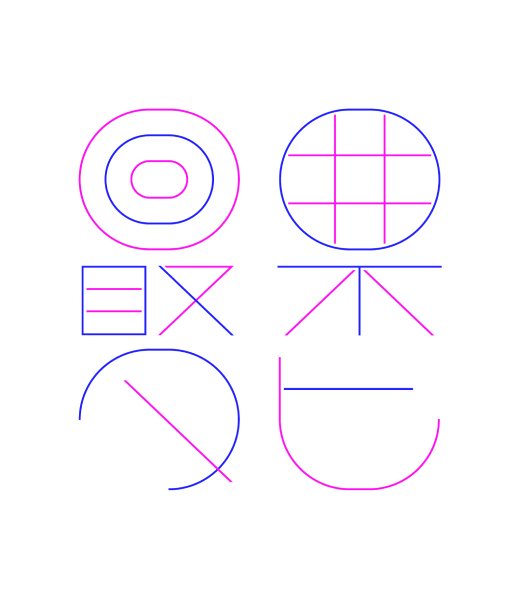
さいはてたひ。詩人。
詩やエッセイや小説を書いています。
はじめて買ってもらった漫画は『らんま1/2』。
はじめて自分で買った漫画は『トーマの心臓』。
