
【映画日記】日本映画の現代
きっかけは、石橋英子氏(音楽家)から濱口竜介氏(映画監督)への映像制作のオファーだったそうです。
「ドライブ・マイ・カー」(21)
で意気投合したふたりは、試行錯誤のやりとりをかさね、濱口氏は、
「従来の制作手法でまずはひとつの映画を完成させ、そこから依頼されたライブパフォーマンス用映像を生み出す」
ことを決断。
そうして、石橋氏のライブ用サイレント映像『GIFT』と共に誕生したのが、長編映画『悪は存在しない』。
自由に、まるで、
「セッション」
のように作られたのが、本作です。
「ドライブ・マイ・カー」で米アカデミー賞(国際長編映画賞)に輝き、カンヌ、ベルリン、ベネチアの世界三大映画祭を制覇した世界が注目する映画監督のひとりである濱口氏。
「他なる映画と」は、濱口監督がこれまでに発表してきた映画論を2冊にまとめたものであり、1巻目は、「映画講座」編、2巻目は、「映画批評」編となっています。
1巻目の「映画講座」篇には、仙台・神戸・鎌倉・ソウルなどで開かれたレクチャーをまとめる(すべて初活字化)。
映画史上の傑作・名作はいかに撮られてきたのか、その作劇と演出と演技へと迫ります。
2巻目は、「映画批評」篇として、映画をつくりながら折々に発表してきた作品レビューや映画をめぐる論考・エッセーにくわえ、日本語未発表原稿や書き下ろし2篇(7万字に及ぶブレッソン『シネマトグラフ覚書』論ほか)も収録しています。
「映画を見ながら、映画をつくってきた」
と自ら語る濱口氏は、いったいどのように映画を見てきたのかが、この2冊を通じて、それが明らかになっていて、読み応えがあると思います。
さて、濱口氏が、映画について、いろんな場所で語った講座を集めた本なのですが、いろんな場所で語った「話し言葉」がベースになっている「他なる映画と 1」と、「書き言葉」がベースになっており、より緻密で専門的な「他なる映画と 2」は、色んなところで書いた映画論をまとめた本の中では、特に、ロベール・ブレッソンの唯一の著作である
「シネマトグラフ覚書 映画監督のノ-ト」ロベール・ブレッソン(著)松浦寿輝(訳)

についての研究・解説・読み解きは、驚きべき緻密さです。
まずは、「他なる映画と 1」を読んで頂けると、映画について、基本的なことがわかる本になっているので、勉強になります。
濱口氏は、大学卒業後に、映画監督を養成する東京藝術大学大学院で黒沢清氏から多くのことを学んだそうです。
その黒沢氏は、映画監督の仕事として、根本的なことは、下記の二つだと言ったそうです。
・カメラをどこに(向けて)置くか、を決めること。
・カメラをいつ回し始め、いつ回し終わるか、を決めること。
つまり、撮影現場で、
「いったいどこから、いつからいつまで1ショットで撮るのか」
ある1ショットのありようを決定することが、映画監督における最も根本的な仕事だと、言ったそうです。
世界最初の映画のうちの一つ、リュミエール兄弟の『工場の出口』等、
世界初の映画『工場の出口』や、120年前の日本の様子も!映画『リュミエール!』予告編
いくつかの作品を引き合いに出しながら、濱口氏は、
「ショットは、まず何よりも過去に起きた出来事の記録としてある」
と語っていました。
カメラは、
「機械的無関心」
によって、記録を行うものであり、
「他性」
とは、
「機械の自動性」
に由来するのだと。
だから、時に、
「刺激情報の少ない映画」
を見ると、
「眠くなる」
のだと、そう語っていました。
濱口氏も、学生時代に、色々な映画を見始めた頃、度々、映画がわからなくて、眠くなったそうです。
ただ、一旦寝て、起きてからの時間、映画を見続けていくなかで、起きた後の冴え渡るような感覚、今までだったら、寝てしまっていた画面を、
「見続けられるようなからだ」
を手に入れた感覚を、持ったらしいと、書かれています。
「この小さな死と再生を体験するような感覚が、映画を見ながら寝て起きる時間にはありました。
その体験が少しずつ現実に、私のからだも変えていったような気がしています。
『他なる映画と』というタイトルの「と」の部分にこめたのは、この生き物と機械の間にある「非ー生き物的な」時間への愛だった、という気がしています。
結局、それはとりつくしまがなく、映画が終われば消えてしまうような時間ですが、私はつかんでは消えていくこの時間の正体を知りたくて、映画とずっとかかわりあっているように思えます。」(P28)
そして、ショットが記録しているのは、この世界における極めて
「断片的な時空」
であり、フレームの中、
「スタートとカットの間だけの記録」
としてあるということだそうです。
リュミエール兄弟が、記録できるカメラは、50秒だけ。
しかし、その50秒以外の時間、そのフレームの外には、膨大に広がる時間があり、際限のない空間が存在しています。
カメラが持つ完璧なる
「記録性」
と同時に、
「画面外にある何か」
を見たいという気持ちを喚起する
「断片性」
こそが、
「映画」
を
「フィクションへ」
と導く、絶対的な可能性なのだそうです。
グリフィスは、
「クローズアップ」
という技法の発見者として記憶されがちなのですが、
彼が、一番、上手く使いこなしたのは、
「画面外の空間」
だそうです。
カメラをクローズアップで撮れば撮るほど、空間の断片性が上がっていきます。
グリフィスは、クローズアップを撮ることによって、
・画面外の空間
・画面外を見つめる瞳
・画面外の視線
を発見したのだとか。
それぞれの
「ショット」
は、別々の時空の記録にも関わらず、その画面外を見つめる、それぞれの視線の方向を、右左で合わせて並べると、二人は、まるで、今、同じ空間に属して、見つめ合っている、という
「フィクション=物語」
が生まれます。
映画は、編集によって、多様なフィクションを生み出していくことになります。
カメラの
「記録性」
が、
「ドキュメンタリーの側に属するショットの本性」
とするなら、
「断片性」
は、明らかに
「フィクションの側に属する本性
となります。
「ある映画について「ドキュメンタリーなのか、フィクションなのか」という区分けを試みるよくある問いは、私にはほとんど無意味に感じられます。
映画制作の最小単位であるショットを撮る時点で、ドキュメンタリーとフィクションとしての性格は必ず同時に生じます。
ならば、その集積として作られる映画もまた、常にある程度ドキュメンタリーであり、ある程度フィクションである以外はありません。
映画は常にフィクションであると同時にドキュメンタリーである。
あくまでも個々の作品のアプローチによって、その度合いが違うというだけなのです。」(P38)
黒沢氏の問い、
「いったいどこから、いつからいつまで1ショットで撮るのか」
とは、撮影現場で、個々のショットの記録性と、断片性の度合いを、具体的に、どう調整するのか、ということを問うものです。
その調整を通じて、映画における
「フィクションの力」
と、
「ドキュメンタリーの力(それは、ともすれば、互いに弱め合ってしまう二つの力)」
が、いったい、どうやって、同時に、最大化されるのか、ということが、映画監督の仕事なのだそうです。
「映画はドラマを語るということに最も向かないメディアなのだ」
と黒沢氏は言ったといい、
「カメラは基本的に現実を写すものであって、現実を写すことを通じてフィクションを作るというのは、大いに破綻した行為、矛盾した行為なんだ」
と。
しかし、濱口氏は、
「カメラが機械であり、映写機が機械である。
その機械が、観客が一体何を思うおうと、観客がどのような体調であろうと関係なく、自らが構成された通りにある画面を、否応なく見せ続け、終わる。
その厳然としたありようは「運命」というものにきわめて似ている。
そんな気がしています。
映画は運命を語るのに最も適している。」
と、映画の可能性につい語っていました。
フィクションを作るということの困難さ。
カメラに顔を向けながら、セリフを言う演技というものの嘘臭さ。
そういうものに、自覚的でありながら、1回限りしか起こらないような奇跡的な瞬間、偶然をどう捉えられるかが、すぐれた映画なのかもしれませんね。
■話し言葉
「他なる映画と 1」濱口竜介(著)

「映画をこれまでほとんど見ていない」ような人でも理解できて、しかもその人をできるだけ自分の感じている「映画の面白さ」の深みへと連れて行けるように、という思いで構想した。」――「まえがき」より
「私の映画との関わり方、というのは何かと言うと、それはもちろんまず撮る人――この場合は監督として――ということです。
そして、もう一つは、もしかしたらそれ以上に映画を見る人、ただの映画好き、一ファンとして、ということですね。
映画好きが昂じてそれが職業になるところまで来たので、一応は人並み以上に好きなのだろう、とは思っています。
ただ、そんな風に人並み以上に好きであるにもかかわらず、映画というのはどこか、徹頭徹尾私にとって「他・なるもの」であるようだ、というのがほとんど二十年近く映画と関わってきて、私が強く持っている感覚なんです。」――「他なる映画と 第一回 映画の、ショットについて」より
1巻目の「他なる映画と 1」は、仙台・神戸・鎌倉・ソウルなどで開かれた映画講座を収録。
すべて初活字化となる。
本書の半分を占める「他なる映画と」と題された全3回の連続講座では、映画史上の傑作・名作を取り上げながら、映画の画面はどのようにつくられ、そこで俳優たちはどのように演技し、監督はどのように演出してきたか、という映画の核心へと迫ってる。
そのほか、濱口監督にとって重要なテーマである「映画における偶然」を考察する講演、小津安二郎監督「東京物語」とホウ・シャオシェン監督「悲情城市」をめぐって、その細部における演出を分析していくレクチャーなども収録している。
「自分が文章を書くことでしようとしていたこと、それは、その作品なり作家なりの生産原理を摑むことだった。
文章によって、その原理の核心を鷲摑みにすること。せめて尻尾だけでも摑んで離さないこと。」――「あとがき」より
■書き言葉
「他なる映画と 2」濱口竜介(著)

2巻目の「他なる映画と 2」には、この15年のあいだに執筆してきた、作品レビューや映画をめぐる論考・エッセーをまとめている。
取り上げられる映画監督は、リュミエール兄弟、ロベール・ブレッソン、小津安二郎、マノエル・ド・オリベイラ、エリック・ロメール、土本典昭、ジョン・カサベテス、クリント・イーストウッド、ジャン=リュック・ゴダール、ジョナサン・デミ、エドワード・ヤン、相米慎二、ペドロ・コスタ、レオス・カラックス、ギヨーム・ブラック、そして、瀬田なつき、三宅唱、小森はるか・・・と、映画史の始まりから、現代の最新鋭にまでわたる。
なかでも、映画を志す者にとってのバイブル、ロベール・ブレッソンの著書「シネマトグラフ覚書」を読み解く論考は、7万字に及ぶ力作であり、本書のための書き下ろし。
さらには、蓮實重彦やアンドレ・バザンといった映画批評家の仕事を論じた文章なども収録している。
■映画と、からだと、あと何か
「忘れられない日本人 民話を語る人たち」小野和子(著)

「映画を追え フィルムコレクター歴訪の旅」山根男(著)

「ゴダ-ル的方法」平倉圭(著)

「非暴力を実践するために 権力と闘う戦略」ジーン・シャープ(著)谷口真紀(訳)

「あいたくて ききたくて 旅にでる」小野和子(著)

「彼自身によるロベール・ブレッソン インタビュー 1943–1983」ロベール・ブレッソン(著)ミレーヌ・ブレッソン(編)角井誠(訳)

「宝ヶ池の沈まぬ亀 ある映画作家の日記2016‒2020」青山真治(著)

「宝ヶ池の沈まぬ亀Ⅱ ある映画作家の日記2020‒2022 ―または、いかにして私は酒をやめ、まっとうな余生を貫きつつあるか」青山真治(著)

「ゼロから始めるジャック・ラカン 疾風怒濤精神分析入門 増補改訂版」(ちくま文庫)片岡一竹(著)

「本多猪四郎の映画史」(叢書・20世紀の芸術と文学)小林淳(著)

「シネマトグラフ覚書 映画監督のノ-ト」ロベール・ブレッソン(著)松浦寿輝(訳)

「<責任>の生成ー中動態と当事者研究」國分功一郎/熊谷晋一郎(著)

「マイ修行映画」みうらじゅん(著)

「小津ごのみ」(ちくま文庫)中野翠(著)

「思いがけず利他」中島岳志(著)丹野杏香(イラスト)

「料理と利他」土井善晴/中島岳志(著)

「人はみな妄想する ージャック・ラカンと鑑別診断の思想」松本卓也(著)

「サスペンス映画史」三浦哲哉(著)
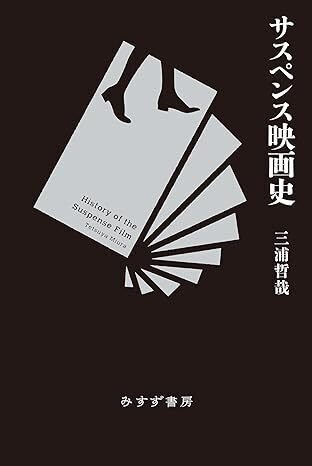
「ショットとは何か」蓮實重彦(著)

「ショットとは何か 実践編」蓮實重彦(著)

「ショットとは何か 歴史編」蓮實重彦(著)

「境を越えてPart1 このまま死ねるか!?」岡部宏生(著)

「映画技術入門」ゆめの(イラスト)高良和秀(編)

「監督 小津安二郎〔増補決定版〕」(ちくま学芸文庫)蓮實重彦(著)

「どもる体」(シリーズ ケアをひらく)伊藤亜紗(著)

「手の倫理」(講談社選書メチエ)伊藤亜紗(著)

「ラカン入門」(ちくま学芸文庫)向井雅明(著)

「家父長制と資本制 マルクス主義フェミニズムの地平」(岩波現代文庫)上野千鶴子(著)

「勉強の哲学 来たるべきバカのために 増補版」(文春文庫)千葉雅也(著)

「中動態の世界 意志と責任の考古学」(シリーズ ケアをひらく)國分功一郎(著)

「映画表現の教科書 ─名シーンに学ぶ決定的テクニック100」ジェニファー・ヴァン・シル(著)吉田俊太郎(訳)

「かたちは思考する 芸術制作の分析」平倉圭(著)

「記憶する体」伊藤亜紗(著)

「独裁体制から民主主義へ―権力に対抗するための教科書」(ちくま学芸文庫)ジーン・シャープ(著)瀧口範子(訳)

「映画を早送りで観る人たち~ファスト映画・ネタバレ――コンテンツ消費の現在形~」(光文社新書)稲田豊史(著)
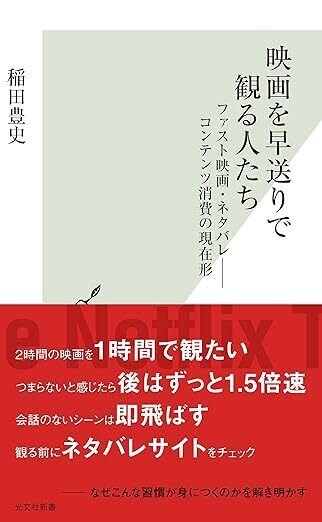
「20世紀最高の映画100作品」古澤利夫(著)
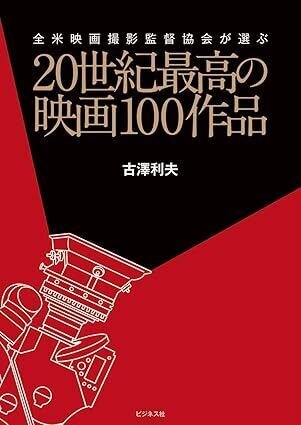
「あかんやつら 東映京都撮影所血風録」(文春文庫)春日太一(著)

「映画術 その演出はなぜ心をつかむのか」塩田明彦(著)

「笑犬楼vs.偽伯爵」筒井康隆/蓮實重彦(著)

「Film Analysis 映画分析入門」マイケル・ライアン/メリッサ・レノス(著)田畑暁生(訳)

「ことばが劈かれるとき」(ちくま文庫)竹内敏晴(著)

「センスの哲学」千葉雅也(著)

「ラインズ 線の文化史」ティム・インゴルド(著)工藤晋(訳)

ユリイカ 2022年12月号 特集=三宅唱 ―『やくたたず』から『Playback』『THE COCKPIT』『きみの鳥はうたえる』、そして『ケイコ 目を澄ませて』

「寝ても覚めても 増補新版」(河出文庫)柴崎友香(著)

「ビリー・バッド」(光文社古典新訳文庫)メルヴィル(著)飯野友幸(訳)

■濱口竜介監督が選んだ傑作映画20本
『リオ・ブラボー』ハワード・ホークス1958 アメリカ
『グロリア』ジョン・カサヴェテス 1980 アメリカ
『10話』アッバス・キアロスタミ2002フランス、イラン
『流れる』成瀬巳喜男 1956 日本
『都会のアリス』ヴィム・ヴエンダース 1974 ドイツ
『エストラパード街』ジャック・ベッケル1953 フランス
『海辺のポリーヌ』エリック・ロメール 1983 フランス
『天が許し給うすべて』ダグラス・サーク1955 アメリカ
『ハタリ!』ハワード・ホークス 1960 アメリカ
『刑事ベラミー』クロード・シャブロル2009フランス
『エル・スール』ヴィクトル・エリセ1983 スペイン、フランス
『ミュンヘン』スティーヴン・スピルバーグ2005アメリカ
『台風クラブ』相米慎二 1985 日本
『ラルジャン』ロベール・ブレッソン1983 フランス、スイス
『チャイニーズ・ブッキーを殺した男』 ジョン・カサヴェテス 1976 アメリカ
『「女の小箱」より 夫が見た』増村保造 1964 日本
『ポンヌフの恋人』レオス・カラックス 1991 フランス
『生きるべきか死ぬべきか』エルンスト・ルビッチ 1942アメリカ
『ミスティック・リバー』クリント・イーストウッド 2003 アメリカ
『CURE』黒沢清 1997 日本
■そうだ、映画を観よう!
古内東子「映画を観よう」
どんな映画にも、忘れがたいシーンとセリフが登場します。
古くても、新しくても、こんなマイナーでマニアックな映画でも観ようかな(^^)
『BAD LANDS バッド・ランズ』原田眞人
『Single8』小中和哉
『Tromprie』アルノー・デプレシャン
『アネット』レオス・カラックス
『アルマゲドン・タイム ある日々の肖像』ジェームズ・グレイ
『ある男』石川慶
『アル中女の肖像』ウルリケ・オッティンガー
『イノセント』ルイ・ガレル
『ウェンディ&ルーシー』『ミークス・カットオフ』ケリー・ライカート
『エターナルズ』クロエ・ジャオ
『エドガルド・モルターラ ある少年の数奇な運命』マルコ・ベロッキオ
『エンパイア・オブ・ライト』サム・メンデス
『オールド』M・ナイト・シャマラン
『ガールフレンド』クローディア・ウェイル
『きのう生まれたわけじゃない』福間健二
『キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン』マーティン・スコセッシ
『クライ・マッチョ』クリント・イーストウッド
『こちあらあみこ』森井勇佑
『コーダ あいのうた』シアン・ヘダー
『ショーイング・アップ』ケリー・ライカート
『ジョージア、白い橋のカフェで逢いましょう』アレクサンドレ・コベリゼ
『せかいのおきく』阪本順治
『トリとロキタ』ジャン・ピエール&リュック・ダルデンヌ
『にわのすなば GARDEN SANDBOX』黒川幸則
『パシフィクション』アルベール・セラ
『パワー・オブ・ザ・ドッグ』ジェーン・カンピオン
『バーナデット ママは行方不明』リチャード・リンクレイター
『バービー』グレタ・ガーウィグ
『ビーチ・バム まじめに不真面目』ハーモニー・コリン
『フェアリーテイル』アレクサンドル・ソクーロフ
『ベネデッタ』ポール・ヴァーホーヴェン
『ほかげ』塚本晋也
『ミュージック』アンゲラ・シャーネレク
『みんなのヴァカンス』ギヨーム・ブラック
『メモリア』アピチャポン・ウィーラセタクン
『やまぶき』山崎樹一郎
『よだかの片想い』安川有果
『愛なのに』城定秀夫
『遺灰は語る』パオロ・タヴィアーニ
『黄色い繭の殻の中』ファム・ティエン・アン
『花腐し』荒井晴彦
『渇水』高橋正弥
『月の寵児たち』オタール・イオセリアーニ
『春江水暖~しゅんこうすいだん』グー・シャオガン
『水の中で』ホン・サンス
『水を抱く女』クリスティアン・ペッツォルト
『清掃する女:亡霊』七里圭
『青いカフタンの仕立て屋』マリヤム・トゥザー
『戦争と女の顔』カンテミール・バラーゴフ
『草の響き』 斉藤久志
『天上の花』片嶋一貴
『冬薔薇(ふゆそうび)』阪本順治
『逃げた女』ホン・サンス
『二人静か』坂本礼
『熱のあとに』山本英
『彼女のいない部屋』マチュー・アマルリック
『別れる決心』パク・チャヌク
『防寒帽』ジャン=フランソワ・ステヴナン
『麻希のいる世界』塩田明彦
『夜のロケーション』マルコ・ベロッキオ
『夜明けまでバス停で』高橋伴明
『由宇子の天秤』 春本雄二郎
『夕方のおともだち』廣木隆一
■映画批評サイト「noboy」
▶2024年ベスト
▶2023年ベスト
▶2022年ベスト
▶2021年ベスト
▶2020年ベスト
▶2019年ベスト
▶2018年ベスト
▶2017年ベスト
▶2016年ベスト
▶2015年ベスト
▶2014年ベスト
▶2013年ベスト
▶2012年ベスト
▶2011年ベスト
NOBODY47号 大特集「日本映画の現代」(仮) 出版支援プロジェクト!
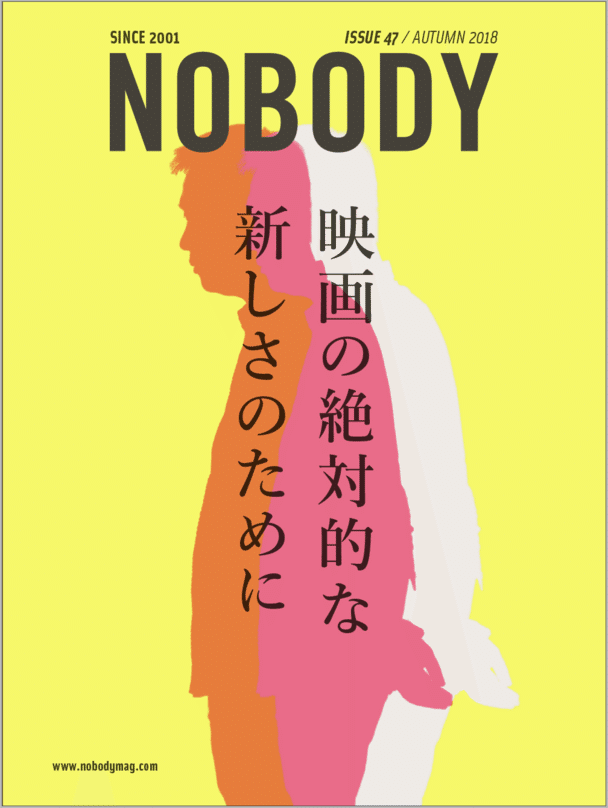
濱口竜介『寝ても覚めても』
tofubeats「RIVER」
三宅唱『きみの鳥はうたえる』
佐向大『教誨師』
鈴木卓爾『ゾンからのメッセージ』
■暗闇の中を歩く楽しさと怖さが同居する、音楽と石橋英子の関係
石橋英子「Coma」
石橋英子「時を告げて」
石橋英子「I'm old」
石橋英子「imitation of life」
石橋英子「resurrection」
■映画にまつわる雑文
「映画館と観客の文化史」(中公新書)加藤幹郎(著)

[ 内容 ]
映画はいったいどこで見るべきものなのだろうか。
ホームヴィデオの普及以降一般的になった、個人的な鑑賞は、果たして映画の本来的な姿から遠ざかってしまったものなのだろうか。
本書は、黎明期から今日までの一一〇年間の上映形態を入念にたどりながら、映画の見かたが、じつは本来、きわめて多様なものだったことを明らかにする。
作品論、監督論、俳優論からは到達し得ない映画の本質に迫る試みである。
[ 目次 ]
はじめに パノラマ館を見る―絵画、幻燈、写真、映画、ヴィデオ・ゲーム 理論的予備考察
第1部 アメリカ篇(映画を見ることの多様性 一九〇五年から三〇年代までの映画館
オルターナティヴ映画館 テーマパークの映画館 観客の再定義)
第2部 日本篇(日本映画の問題の傾向と対策 映画都市の誕生―戦後京都の場合 多種多様な観客)
[ 発見(気づき) ]
映画史ではなく、映画館と観客の歴史を語る本。
郊外のシネマコンプレックスでブロックバスター作品を観るという、現代の日米での、映画鑑賞の典型スタイルができるまでに、とてもたくさんの視聴スタイルがあったことに驚かされる。
映画が生まれたころの、覗きこみ式装置のキネトスコープの時期には、1台で1分ほどの映像が限界だった。
そこで6台並べて、1分1ラウンドずつの、ボクシング試合の映像を続けてのぞくというのが流行ったそうだ。
演劇やコントの合間に上映されていた時代もあったし、日本では長い間、男女が分かれて座っていたこともあったのである。
米国の1950年代のドライブインシアターでは、観客は自由におしゃべりし、食事をし、走り回り、ときには愛の行為に及んだりした。
席に座ってみんなで静かにロードショーを見るというのは映画史110年のなかで最近の文化なのだ。
さまざまな映画鑑賞スタイルの紹介が、細部まで描かれていて興味深い。
[ 教訓 ]
現代日本のポルノ映画館が、実質ゲイの人のハッテン場になっているというのは驚きでもあった。
米国では、第二次世界大戦で若者たちが帰国し、安価な住宅地を求めて郊外へ移り住んだ。
その結果、郊外にショッピングセンターが発達し、ドライブインシアターや映画館が併設された。
それは、やがてショッピングモールとシネマコンプレックスとなって融合して、映画製作にも大きな影響を与えた。
「そもそもブロックバスター映画という概念が超高予算を組み、それに見合った超高収益を期待するものである以上、それはできるだけ多くの潜在顧客を掘り起こすような、万人受けする内容でなければならない。
つまり、ブロックバスター映画はなにかしら目新しくて(とどまることを知らないコンピュータの技術革新とその映画的応用)、なにかしら圧倒的で、それでいて、おなじみの保守的スペクタクル(見世物)的要素をもつ映画でなければならない。
それは映画学者トマス・シャッツの言葉を借りれば、「ハイコスト=ハイテック=ハイスピード」映画ということになる。
そうした斬新かつ保守的なスペクタクルに全世界同時的に触手をそそられる多数の観客が存在しうるということは、おそるべき観客の均質化が達成されたということを意味する。」
映画館の均質化と同時に、異質なものは家の大画面液晶でDVDで観るとか、やインターネットで観る、という棲み分けも進んでいるのだろう。
時代状況に応じて映画館と観客の文化というのは、10年や20年くらいでも、大きく変わってしまうことがわかった。
[ 一言 ]
そういえば、昔は、2本立て上映が多かった気がするのだが、最近は、そういう映画館は少なくなったようだ。
国によっても、映画の見方は、大きく違うようだ。
米国で映画を見たら、画面に向かって観客が、拍手喝さいやブーイングをするので驚いたことがある。
一体感があって楽しかったが、日本の観客は、他人を気にして、静かに見るのが普通だ。
インドだとか、中国だとか、アラビアでも、きっと違うのだろうと思う。
日米以外も知りたくなった。
映画を作品ではなく、映画館と観客という視点で分析したことで、面白い展開になっている。
映画好きにおすすめ。
