
【宿題帳(自習用)】帰納と演繹と創造的推論

観察から新しい現象をみつけ、モデルを作って、それを理論的に検討しながら、演繹的に物性の予測に結びつけていく方がいい。
科学の進展には、「技術」と「発見」と「アイディア」が必要だ。
理論先行型の研究というのは、発見・ブレークスルーには、能率が悪い。
いろいろな方法論を考えた後に、“ふと”出てくるものである。
経験だけでは語れない。
物事をモデルを上手に作って解明していく必要がある。
言語学は、かつては経験科学だった。
残っているテキストを解釈していくものであったが、人間の自然言語というのは、経験論・帰納論では語ることができない。
人間は、無限の文を作ることができるし、無限の文を理解することができる。
それをソシュールのように「類推」とか、
「一般言語学講義」フェルディナン・ド・ソシュール(著)小林英夫(訳)
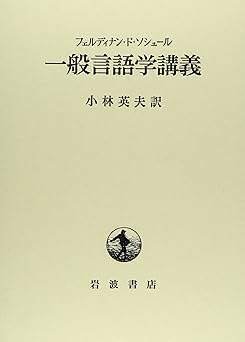
「ソシュールを読む」(講談社学術文庫)丸山圭三郎(著)

マルコフの「有限状態文法」などでは、
解けない。
そのために、チョムスキーは、「原理とパラメータのアプローチ」(Principles and Parameters Approach)というモデルを用意して、演繹的に言語を研究しようとしたのだった。
それまで文献を中心とした科学だったのを、チョムスキーは、演繹的な実験科学に変えた。
「新・自然科学としての言語学―生成文法とは何か」(ちくま学芸文庫)福井直樹(著)

帰納論的な手法で全ての文を集めてから文法を作ることはできない。
文は無限にあるからだ。
演繹論的にモデルを作って、現実と照らし合わせながらモデルを変えていく方法でなければならないとチョムスキーは考えたのだ。
「言語研究入門――生成文法を学ぶ人のために」大津由紀雄/池内正幸/今西典子/水光雅則(編)

「言語研究の世界 生成文法からのアプローチ」大津由紀雄/今西典子/池内正幸/水光雅則(監修)杉崎鉱司/稲田俊一郎/磯部美和(編)

「認知文法論I」(シリーズ認知言語学入門 (第4巻))西村義樹(編)

「認知文法論Ⅱ」(シリーズ認知言語学入門 (第5巻))中村芳久(編)

演繹を考えたのは、ルネ・デカルトだから、チョムスキーは、「デカルト派言語学」を標榜している。
デカルトは、「方法序説」の中で、真理を探究する方法として次の四つの規則を採用している。
「方法序説」(岩波文庫)デカルト(著)谷川多佳子(訳)

偏見にだまされず、自分で真と認めるものだけを受け入れること。
大きな問題は、分割して考えること。
単純な認識をつみあげて、順序よく考えること。
全体をよく見て、見落としがないかを確認すること。
ただし、「答えのない時代」に、どれだけ有効か、分からない。
橋本治の「「分からない」という方法」は、まさに20世紀の病を克服しようとした試みだが、「人の言う方法に頼るべき時代は終わった」といい、「二十世紀は理論の時代で、『自分の知らない正解がどこかにあるはず』と多くの人は思い込んだが、これは、『二十世紀病』と言われてしかるべきものだろう」としている。
「「わからない」という方法」(集英社新書)橋本治(著)

自分がぶち当たった壁や疑問は、自分オリジナルの挫折であり疑問である。
「万能の正解」という便利なものがなくなってしまった結果なのではない。
ただ、チョムスキー理論の人の論文の中には、時々、本当にこういうだろうかと、言語直観を疑うような例文が並ぶことがある。
シャーロック・ホームズはいう。
「人は理論的説明にあうように、知らず知らずのうちに事実の方を曲げるものだ」と。
ちなみに、フランシス・ベーコン(Francis Bacon)は、1620年に出した「ノヴム・オルガヌム」(Novum Organum)で、哲学を3つのタイプに分けた。
「ノヴム・オルガヌム(新機関) 」(岩波文庫)フランシス・ベーコン(著)桂寿一(訳)

クモ型とアリ型とハチ型だ。
クモ型というのは、自分の体からクモの糸を次々に出して網を作るが、同じように、自分の原理・原則を中心にして、すべての観念をひねり出し、推理の網を張り巡らせるもの、つまり、演繹的手法である。
アリ型というのは、ひたすら地上を這い回って餌を集めるアリのように、個々の事実ばかりを集め、データをたくさん集めれば、いつか判断できると考える、帰納的手法を指す。
ハチ型というのは、花から花へ移動しながら餌を集めてくるもの。
材料を集めてくるが、そのまま使わず、ハチの巣のように自分の力で形を変えるもの。
精神の生み出した原理や観念に頼ることも、観察から得た個々の事実だけに固執することもせず、変化させて、理性の中に蓄えることこそが大切だと、ベーコンは考えたようだ。
論理には、「帰納」(induction)と「演繹」(deduction)だけしかないように思われているが、チャールズ・パースによって提唱されたアブダクション(“abduction”「発見の論理」「創造的推論)」というものがある。
シャーロック・ホームズが用いるような推論である。
「アブダクション 仮説と発見の論理」米盛裕二(著)

ウォルポールが「セレンディピティ」という言葉を友人に宛てた書簡で初めて用いたときには、「幸運な偶然の発見」ではなく、むしろ、アブダクションに近いことを意味していたと伝えられている。
例えば、三人の王子が旅の途中でラクダを曵いた商人に出会ったとき、ラクダそのものを見ないで、その足跡や道端の草の食べられた跡などから、ラクダの身体的な特徴を的確に言い当てたエピソードを指して、「目指す答えに到達するための能力」を意味するものとして使ったとされる。
それが違う方向に進んでしまったのだから、世の中は面白い。
アブダクションを、有馬道子「パースの思想」によって、パースが作った例を挙げてみる。
「パースの思想―記号論と認知言語学」有馬道子(著)

私が部屋にはいって、そこにいろいろな種類の豆のはいった多くの袋をみつけたとしよう。
テーブルの上には、一握りの白い豆がある。
そして、しばらく探した後で、それらの袋の一つには、白い豆ばかり入っているのをみつけたとしよう。
すぐ私は、一つの蓋然性、言いかえれば、妥当な推理として、この一握りの豆は、その袋から取り出されたと推論する。
このような推論を仮説を立てるという。
そこで、次のようになる。
仮説:この袋から出る豆はすべて白い。
規則:ここにある豆は白い。
結果:ここにある豆はこの袋から出たものだ。
∴事例
次のようにもいう。
アブダクションは、説明のための仮説をつくる過程である。
それは、新しい考えを導き出す唯一の論理的な働きである。
というのは、帰納は価値を決めるだけであり、演繹は、単なる仮説の必然的な結果を導き出すだけである。
演繹は、そうであるに違いない(must)ことを証明し、帰納は、実際に(actually is)そのように働いていることを示し、アブダクションは、そうであるかも知れない(may be)ことを単に示唆するだけである。
それを正当化する理由としては、その示唆から帰納によって検証されうる予言を、演繹によって引き出すことができるということ、そして、いやしくも、私たちが何かを知ることになったり、現象を理解するようになったりするということがあるとすれば、そうしたことがもたされることになるのは、アブダクションによるより、他にないということだけである。
何もないところから何も生まれないから、教養とか知性とかが必要になってくる。
知識がなければ、新しい知識が生まれるはずがない。
白紙から生まれるのではない。
しかし、教養とかアカデミズムには、陥穽もある。
目の前の現実が見えなくなることもある。
上野千鶴子は、「<わたし>のメタ社会学」で次のように書いている。
「差異の政治学 新版」(岩波現代文庫)上野千鶴子(著)
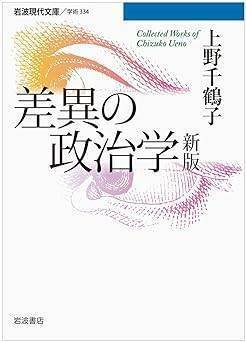
「「教養」や「オリジナリティ」に、神秘的な意味を与える必要はない。
「すでに知られていること」が何か知ること。
それと、自分の考えていることが、どう違うかを分節する能力を持つこと。
「異見」は、そのようにして創られる。
次のようにもいう。
人は、訓練によって「情報」の量を増やすことができる。
ひとつは、自明性の領域を、懐疑と自己批判によって削減することによって。
もうひとつは、異質性の領域に対して、自己の受容性を拡大することによって。
パラダイムは、当事者の経験を構成する世界観の根底をなしており、「説得」や「論破」によって取り替えることができるようなものではない。
経験を組み替えるカテゴリーの萌芽は、「臨床の知」の中に満ちみちている。
・・・・・・それは、<わたし>の「外から」しか訪れない。
<わたし>にとってエイリアンなものを「聞く力」を持つこと。
「当事者のカテゴリー」こそ、パラダイム革新の宝庫である。」

【関連記事】
【雑考】垂直思考と水平思考
https://note.com/bax36410/n/nc041319885eb
【雑考】対位法的思考
https://note.com/bax36410/n/nef8c398b72cb
【雑考】複雑系思考法
https://note.com/bax36410/n/neaab25206650
【宿題帳(自習用)】ふと目を向けた風景、しゃがんだ時に見えるもの。
https://note.com/bax36410/n/nad27a9739ea4
